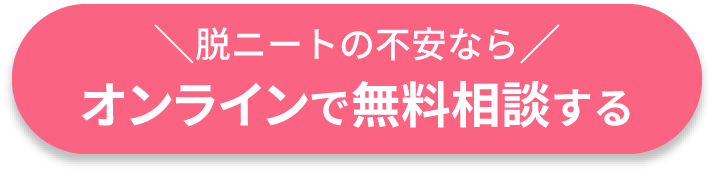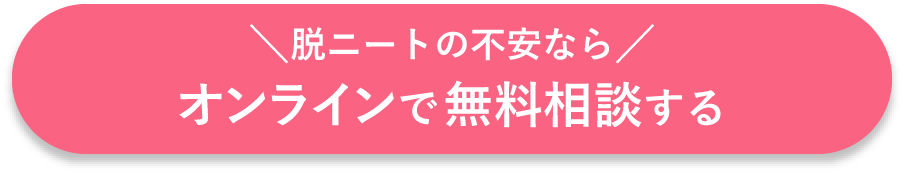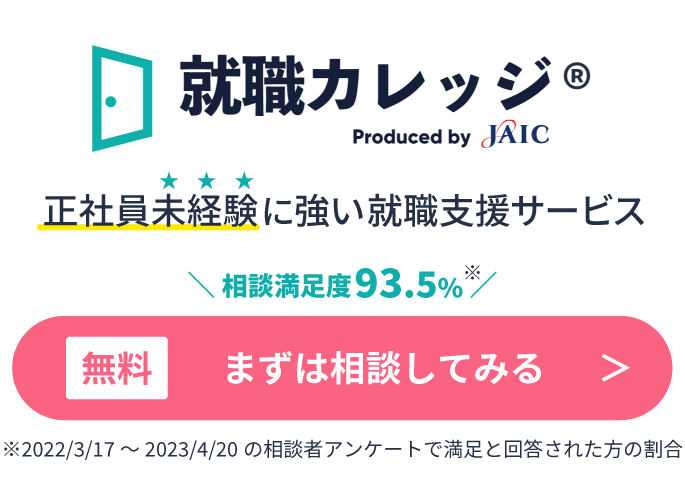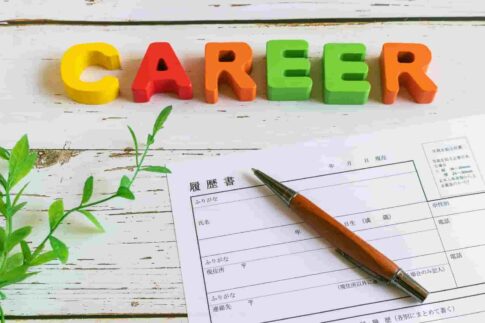「35歳以上でニートの自分なんて、就職はムリだ……」と諦めていませんか?たしかに、年齢を重ねるにつれ、就職が厳しくなるのは事実です。しかし、これは「働き先がない」といったことではありません。むしろプライドを捨て、30代後半から働くことに対してポジティブに捉え直すことができれば、就職への道は広がっていきます。
この記事では、そもそも就職が厳しい理由と共に、就職成功に向けたポイントもお伝えします。就職成功に向け、ぜひ参考にしてみてください。
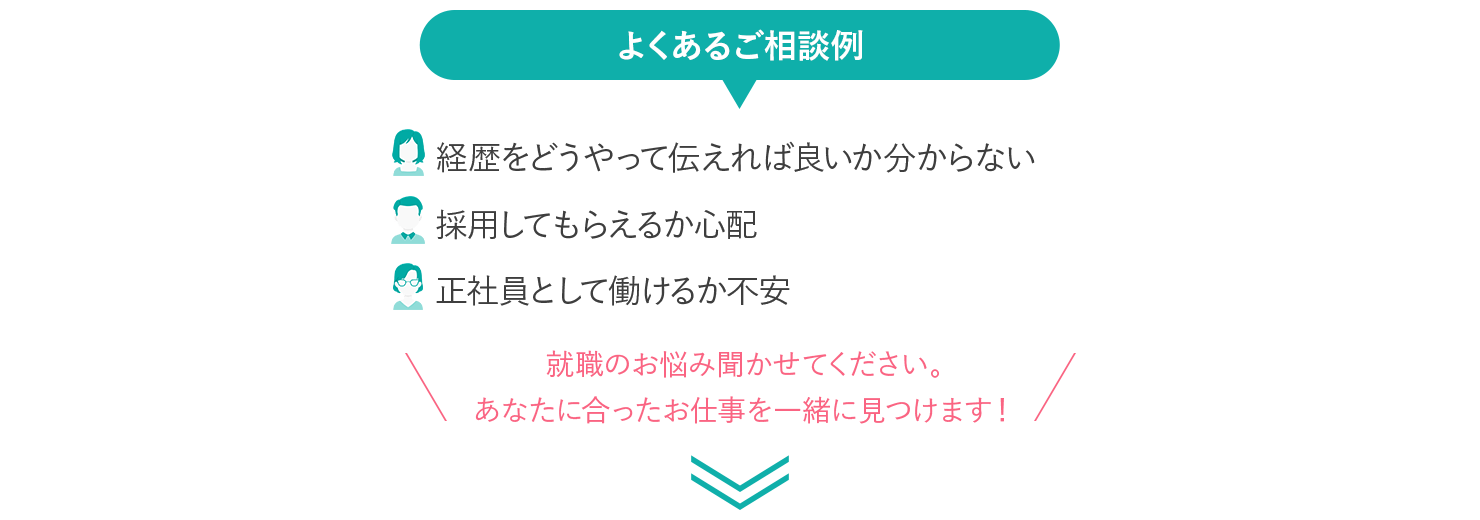



- 35歳を境に「若年無業者」いわゆるニートから、「中年無業者」と呼び方が変化
- 35歳以上のニートの就職が難しいのは、「教育のしづらさ」など会社側の理由と、「プライドの高さ」などニート側の理由にあり
- 35歳以上のニートが就職を成功させるために、未経験OKの仕事探し、エージェントの活用がおすすめ
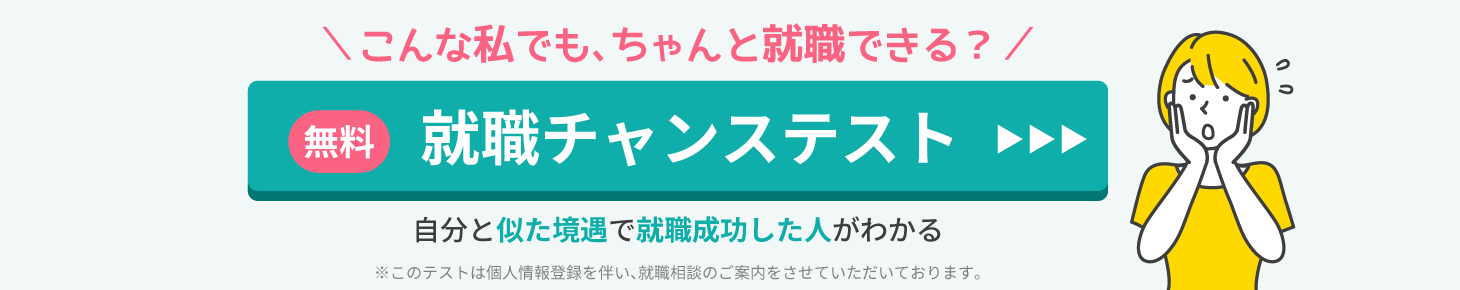
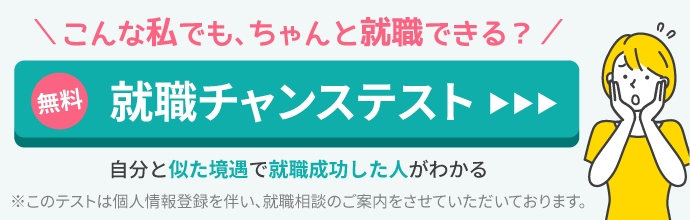
この記事の目次
ニートの定義
そもそも「ニート」には明確な定義が存在しません。しかし同様の意味として、厚生労働省では次のように表現しています。
つまり一般的にニートとは、34歳以下の若年層を表す言葉ということです。いわゆる「若年無業者」と呼ばれ、若いのに働く意思がない人を指します。
一方で、高齢で働く意思がない人の存在が徐々に社会問題化していくに従い、15~34歳という定義に収まりきらない人たちが現れ始めました。そこで同じくニート状態を指す言葉として、35歳を境に「若年無業者」、そして「中年無業者」といった区分けがなされるようになったのです。
- 若年無業者:15~34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者
- 中年無業者:35~44歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者
35歳以上のニートの呼び方

ニートについては、「働いていない人」といったざっくりとした認識が一般的です。しかしもう少し具体的にみていくと、同じニートであっても「若年無業者」と「中年無業者」の2つに区別されることが分かります。
35歳以上のニートは中年無業者
35歳以上44歳未満のニートは、中年無業者もしくは中年ニートと呼ばれます。45歳以上のニートは、高齢ニートと呼称が変化します。
ニート=働いていない人のイメージを持つ方もいるでしょう。しかし、厚生労働省はニートを15〜34歳で働く意思のない人のうち、通学や家事をしていない人と定義しています。
平成24年に発表した「貧困・格差の現状と分厚い中間層の復活に向けた課題」では、中年ニートはニートの年齢要件を35〜44歳としたものと定めました。
ニートと失業者の違い
ニートと失業者の一番の違いは、就職の意思があり、就活しているかどうかです。以下の表にまとめたので、参考にしてください。
| 名称 | 意味 |
|---|---|
| 失業者 | 就職する意思があり、就活中の人 |
| ニート | 就活をせず、家事や通学もしていない人 |
失業者の定義は、以下3つを満たす人です。
- 現在仕事はなく、調査期間中に労働しなかった人
- 仕事があればすぐに就労できる人
- 調査期間中に求職活動をしている人
失業とありますが、ニートとは異なるため注意してください。
ニートと無職の違い
ニートと無職の違いは、就職に向けた「意識の差」にあります。
まずニートは「働く意思がない人」を指す言葉です。そのためニートに該当する人は、就職に向けた行動などを基本的にはおこなっていません。
一方で無職に関しては、一般的には「働きたくても仕事が見つからない人」を指します。たとえば会社をリストラされてしまい、自分の意思に反して仕事がなくなってしまった人が無職と呼ばれますが、こうした人はニートと違い、働く意思を持っていることは多いものです。つまり働く意思のあるなしによって、両者は区別されています。
ニートと引きこもりの違い
ニートと引きこもりの大きな違いは、社会との交流があるかどうかです。
引きこもりは、さまざまな要因から社会との交流を回避し、おおむね6カ月以上家に留まる状態を指します。要因は、いじめなどの精神的ストレスやうつ病が挙げられます。
ニートは、就労する意思の有無が問われるのに対して、引きこもりは社会的つながりの有無が判断基準です。
ニートと引きこもりは別物であり、引きこもりはニートの基準を満たす場合もあります。
ニートとフリーターの違い
フリーターはアルバイトやパートなど、現在就職している状態の人を指します。
ニートは就職しておらずかつ、就職する意思のない人を指すため、ニートとフリーターは意味が大きく異なります。
また、フリーターは雇用形態がアルバイトまたはパートの人です。正社員や派遣社員の方は、フリーターに含まれないため注意してください。
フリーターでの社会経験は、正社員を目指すうえで大きなアピールポイントになります。ニートとフリーターの違いを適切に理解しておきましょう。
ニートと家事手伝いの違い
ニートと家事手伝いの違いは、家庭の炊事、掃除、介護などを日常的に行っているかどうかです。
具体的に家事手伝いは、両親の介護をしたり、両親が仕事で家事ができないため、代わりに家事をしたりする人を指します。一方、ニートは家事をしていないことも条件の1つに含まれます。
他にも、結婚前の準備として家事手伝いをする方もいるでしょう。
家事手伝いは、家族を支えるためなど目的を持って行動している人がいるのも、ニートとの違いとして挙げられます。
35歳以上のニートの人口

35歳以上のニート人口は、総務省集計局が2022年に公表した「労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均」によると約36万人です。
ピーク時である2012年、2013年、2015年は約44万人いましたが、2016年以降は減少傾向にあります。また、人口における35歳から44歳のニート人口の割合は、2012年から2022年まで2.3〜2.4%の間を推移し、ほぼ横ばいの状態です。
35歳以上のニートが就職しづらい原因

35歳以上のニートが就業しづらい理由を、次の2つの側面から解説します。
- 会社目線の就職しづらい原因
- ニート目線の就職しづらい原因
そもそも年齢を問わず、ニートの就職率は低い傾向にあります。たとえば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表した「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状 ③」を見ると、アルバイトやパートとして働いている人が一部含まれるものの、ニートと同じ意味合いで語られることの多い「フリーター」の就職率は次のようになっています。
- 15~19歳:29.9%
- 20~24歳:32.7%
- 25~29歳:25.5%
- 30~34歳:18.1%
- 35~39歳:15.5%
- 40~44歳:15.6%
このデータを見る限りでも、35歳以上の就職率が厳しい現状が見えてきます。では、その原因について具体的にみていきましょう。
会社目線の就職しづらい原因
まずは、採用する会社目線でみた、35歳以上のニートが就職しづらい原因をお伝えします。
- 長期間働いていないことへの疑問・不安が大きい
- 教育しづらい
長期間働いていないことへの疑問・不安が大きい
ひとつ目の原因として挙げられるのが、長期間働いていないことへの疑問・不安です。
35歳以上のニートのなかには、高校や大学卒業後に一切働いた経験がない、または働いたとしてもすぐに辞めてしまい、そのあとはずっとニート、といった人が少なくありません。
こうした人に対し、企業は「働く意思がないのかな」と疑問を感じたり、「ウチで働いてもすぐに辞めてしまうのでは」「人間関係がしっかり築いていける人なのかな」と懸念を覚えたりします。これは一種の偏見でもありますが、こうした理由からニートの採用に二の足を踏んでしまう企業は多いのです。
教育しづらい
教育のしづらさも、企業が35歳以上のニートの採用を見送る原因のひとつです。
たとえば20代前半の場合、まだまだ社会を知らないことが多く、こうした世代は企業の理念や仕事の手順などを柔軟に吸収してくれる傾向にあります。そのため企業としては教育がしやすく、少しくらいの空白期間があったとしても、こうした柔軟性を買って採用するケースは多いのです。
一方で30代、特に30代も後半に差し掛かった人は、すでに自分なりの価値観が確立されています。固定観念が強い人、いわゆる「頑固」な人も多く、企業から与えられる指示に対してあからさまに不服な態度をとるケースも見られます。そして35歳以上のニートを採用する場合、年下の20代が40代を指導する、といったケースも珍しくありません。
すると、企業としては35歳以上のニートを「扱いづらい人」と感じてしまうことがあり、結果として「教育がしにくい」といった理由から採用を見送る場合があるのです。
ニート目線の就職しづらい原因
次に、ニート目線でみた就職がしづらい原因をお伝えしていきます。
- 就職できないと思っている
- プライドが高い
就職できないと思っている
まずは「そもそも自分は就職できない」と思っていることが原因として挙げられます。
お伝えしてきたように、35歳以上のニートの就職が厳しいことはたしかです。しかし、これは「就職できない」というわけではなく、前述のデータを見ても35歳~44歳のおよそ15%は定職に就けています。
そのため正しい努力を積めば正社員への道も残されているわけですが、はなから「自分なんて就職はムリ」と悲観的に考えている人の場合には、自信がなく、さらには行動力もないため、結果として年齢だけを重ねていってしまいます。そのため、就職が難しい状況に自らを追い込んでいってしまうことになるのです。
プライドが高い
プライドの高さも、35歳以上のニートが就職しづらい原因の一つです。
たとえば、いざ働くことになった場合、おそらくはじめは基本的な仕事がメインになります。すると同時期に入社した新卒社員や、20代前半の同僚と机を並べ、業務にあたることも考えられるでしょう。このとき「仕事経験が少ないから仕方ない」と割り切れる人は、置かれた状況でも頑張り切れるものです。一方で「年上の自分が、こんな若い世代と一緒の仕事をするなんて」と考えてしまう人の場合には、そのプライドの高さが邪魔をして、仕事に集中できず、イライラばかりが募っていってしまうことでしょう。
特に30代の後半にもなると、一回りも離れた20代と仕事をすることに強い抵抗感を覚えてしまう人は少なくありません。そのため、プライドが傷つけられることを内心で恐れ、就業に踏み切れないニートが多いのです。
35歳以上のニートが社会復帰を目指すためのポイント7つ
35歳以上のニートが社会復帰を目指すためのポイントを7つ紹介します。
どのポイントから始めても問題ありません。自分の状況に応じて、少しずつでいいので動いてみましょう。
また、挑戦を決意した方は早期の行動が大切です。年齢を重ねるごとに就職は不利になります。
社会復帰のポイントが知りたい方は、参考にしてください。
1. 本当に働ける状態なのか知る
まずは、本当に働ける状態なのか確認しましょう。
心身が健康ではじめて労働できるからです。確かに就職は早めの行動が大切です。しかし、健康状態に問題があるままでは、納得いく就活ができません。
心身の状態に少しでも不安がある方は、病院で受診するのが先です。無理して就活を始めてしまうと、かえって悪化する恐れがあります。
心身が不調になると、就職するまでにさらに時間がかかるでしょう。少しでも早く社会復帰するためには、心身ともに健康であることが重要です。
いきなり就活を始める前に、就活できる健康状態なのか確認しておきましょう。
2. 今までの生活習慣を見直す
今までの生活習慣を見直すことは、社会復帰に必要なポイントの1つです。
フルタイムで働く場合、多くの職種で9〜18時で勤務することになります。日中に高いパフォーマンスを発揮するため、生活習慣を整えることが重要です。
ニート生活が長くなると、昼夜逆転生活になる人もいます。日中に眠いと面接に参加しにくくなるでしょう。
また、食生活も同時に見直してください。栄養バランスの乱れは、心身の乱れにつながります。
社会復帰を目指す方は、生活リズムを見直し、良い状態で就活ができるようにしましょう。
3. 散歩などで身体を動かす
社会復帰には、散歩などで身体を動かすことも効果的です。
家にいる時間が増えると運動する機会が減少します。その結果、運動不足になり生活リズムが崩れたり、体内時計が狂ったりします。
運動は、健康的な心身を支えるためにも重要です。社会復帰したい方は、運動も併せてしましょう。
最初からハードな運動は、挫折の原因にもなり継続が困難です。近所を散歩したり、近くのスーパーまで歩いたりするのがおすすめです。
慣れてきたら、ジョギングやジムに通うことも視野に入れてみてください。軽い運動から開始して、健康的な身体を手に入れ、就活を効果的に進めましょう。
4. 周囲とコミュニケーションを取る
4つ目のポイントは、周囲とのコミュニケーションを取ることです。
コミュニケーション能力は、就活で重要視される項目の1つです。ニートになり自宅で過ごす時間が増えると、社会との交流が減少します。その結果、コミュニケーションを取る必要がなくなり、面接だけでなく社会に出てからも周りとコミュニケーションを取れずに困ってしまう可能性があります。
コミュニケーションに不安を感じる方は、家族との会話から始めてください。慣れてくれば、ボランティアに参加したりアルバイトを始めたりすることで、必然的に会話が発生します。
上記の経験は、面接での話題にもなるため少しずつ取り組んでみてください。
5. 世の中で起きていることに関心を持つ
世の中で起きていることに関心を持つことは、社会復帰のために大切です。
エントリーシート(ES)や面接で時事問題が出題される可能性があります。本番で焦らないためにも、世間に興味を持つ習慣を身につけておきましょう。
テレビやSNS、新聞など情報を入手する方法は多岐にわたります。1つの媒体からの情報では偏りが生まれるため、注意してください。
複数の媒体から情報を獲得することで、さまざまな視点からの意見が学べます。そのうえで自分の意見として考えを持っておきましょう。
社会復帰したい方は、世の中の出来事に関心を持つことをおすすめします。
6. 資格取得やスキルを身につける
6つ目は、仕事に関連する資格取得やスキルを身につけることです。
資格やスキルは、就活で熱意や意欲をアピールできるので、プラスに働くことがあります。企業によっては資格手当が存在し、同じ仕事内容でも給与が増えるでしょう。
自分が志望する業界や職種が決まっており、お金と時間に余裕がある方は、資格取得をおすすめします。ただし、資格取得には時間がかかるため注意してください。
志望企業の職種がこれから目指す資格を重要視しているのか、資格手当の対象になるのか、事前に確認することでお金と時間が無駄になりません。資格やスキルの獲得より、場合によっては先に就職を目指すほうが良いこともあります。
社会復帰を視野に入れている方は、資格やスキル取得も検討してみてください。
7. 短期アルバイトや派遣から始める
最後は、短期アルバイトや派遣から始めることです。
短期間の労働から開始することで、働く環境に慣れつつ、社会経験が積めます。いきなりニートから正社員に就職しようとすると、心身に負担がかかり早期離職につながる可能性があるため無理は禁物です。
まずは、短期アルバイトや派遣から始めることで、心身に無理なく働けます。慣れてきたらシフトを増やすことも可能です。また、お金も稼げるため、就活の資金になります。
アルバイトから正社員に昇格する方法もあります。勤務態度や勤務年数などの条件はありますが、慣れた環境に就職できるため、安心して働けるでしょう。
アルバイトや派遣の経験は、社会復帰の可能性を高めるため視野に入れておいてください。
35歳以上のニートが就職を成功させるポイント5つ
ここからは、35歳以上のニートが就職を成功させるポイントをお伝えします。
- 早めに行動に移す
- 自己分析を行い自分の得意なことや苦手なことを知る
- 書類と面接対策の準備を万全に行う
- 未経験でも就職できる業界や職種を目指す
- 35歳以上でも利用できる就労支援サービスやエージェントに相談する
1. 早めに行動に移す
35歳以上のニートが就職を成功させるためには、早めに行動に移すことです。
就職は年齢を重ねるごとに不利になります。企業は若い人を採用して、少しでも長く勤続してほしいと考えているためです。
就職するために必要な行動は、以下の4つが挙げられます。
- 健康状態の確認
- 生活習慣の見直し
- 資格やスキルの取得
- アルバイトや派遣の開始
上記の4つは就職を有利に進めるために必要です。しかし、いきなり全てに取り組もうとすると挫折する可能性があります。
一度挫折すると、元に戻るのに時間が必要になり、就職が遅れるでしょう。その結果、さらに焦りが生まれ空回りするかもしれません。
まずは、自分にとって負担のないものから始めて、少しずつ行動を増やしていきましょう。
2. 自己分析を行い自分の得意なことや苦手なことを知る
自己分析を行い、自分の得意と苦手を把握しておくことも大切です。
自己分析は就活の一歩目であり、自分の将来を考えるうえで欠かせません。自己分析の方法は、以下の3つがおすすめです。
- 自分史を作成する
- 自己分析ツールを使用する
- キャリアアドバイザーに相談する
自分史は、自分の人生を振り返りながら強みや弱みを再認識する手法です。自分1人で作成できるため簡単に始められます。
自己分析ツールは、無料で公開されているものもあります。自分に合った職種や働き方を知るのに効果的です。
また、キャリアアドバイザーに相談することで、客観的なアドバイスがもらえます。就活のプロであるため、履歴書の添削や面接対策まで幅広い対策が可能です。
3. 書類と面接対策の準備を万全に行う
ポイントの3つ目は、書類と面接対策の準備を万全に行うことです。
30代以上のニートだと、書類選考で落とされる可能性が高くなります。また、面接で無職期間に何をしていたのか質問されるので、回答を準備しておく必要があります。対策が不十分だと質問に答えられなかったり、曖昧な回答になったりするでしょう。
書類や面接の対策は、本やインターネットからでも可能です。しかし、1人で対策するには限界があるでしょう。
対策が不安な方は、ハローワークや就職エージェントの利用がおすすめです。ただし、担当者との相性があるため、合わない場合は違う担当者や新しいサービスを検討してください。
書類と面接の対策は、内定を勝ち取るために準備しておきましょう。
4. 未経験でも就職できる業界や職種を目指す
まずは、未経験でも就職できる業界や職種を目指しましょう。
たとえば専門性が求められる仕事の場合、給料も高い傾向にありますが、こうした仕事は経験者が優遇されるためニートからの就職はかなり難しいのが現実です。一方で大量採用が前提の仕事、たとえば営業職や、アパレル業界の販売職などの仕事は未経験でも採用してくれるケースがあり、こうした仕事を着実に見つけ、応募していくことが、内定の確率を高めることにつながります。
5. 35歳以上でも利用できる就労支援サービスやエージェントに相談する
最後は、35歳以上でも利用できる就労支援サービスやエージェントに相談することも視野に入れてください。
専門のサービスに相談することで適切な就職サポートが受けられます。一般的な就職エージェントでは、経歴的に支援を受けるのが難しいため、35歳以上のニートの人でも受けられる専門サービスがおすすめです。
35歳以上で長期間ニートの経験がある方は、専門的なサポートが可能な就労支援サービスやエージェントに相談することで安心して就活ができます。
就労支援サービスやエージェントを検討している方は、就職成功率を比較しておきましょう。サービスによって得意不得意な業界があり、経験値も異なるので確認しておきましょう。
35歳以上でも利用できる就職支援サービス
35歳以上でも利用できる就職支援サービスを5つ紹介します。
それぞれのサービスには、得意不得意や自分に合う合わないが存在します。各サービスを表にまとめたので、利用する前に参考にしてください。
| 名称 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ハローワーク | 幅広い職種を紹介してくれる | 個人へのサポートは薄い |
| 地域若者サポートステーション(サポステ) | 49歳までの人材に特化している | 就職先の斡旋はしていない |
| 生活困窮者自立支援センター | 生活に必要なサポートも受けられる | すぐに就職できるとは限らない |
| 就労移行支援事業所 | 資格取得やスキルが身に付く | 基本的な対象は障害のある方 |
| ひきこもり地域支援センター | 他のサービスと密に連携してくれる | 対象は引きこもりの方 |
以下の章では、それぞれのサービスを詳しく解説しています。興味のあるサービスや自分に当てはまりそうなものは、読んで理解しておきましょう。
適切なサポートを受けることで、スムーズな就職が可能です。
1.ハローワーク
35歳以上のニートの人には、ハローワークがおすすめです。
厚生労働省が運営する就労支援施設で、全都道府県にあり、職業紹介や雇用保険など幅広い支援を無償で受けられます。
利用前には自己分析を丁寧に行い、応募する企業像を明確にしておきましょう。ハローワークは求職者全体を支援するため、個人へのサポートは薄くなるためです。
ハローワークは幅広い業種の求人を紹介してくれます。しかし、求人はハローワークと連携している企業になるため、全てではありません。
自分に合う企業が他にもある可能性があることを覚えておきましょう。
ハローワークで仕事を探す方法については、以下の記事で詳しく解説しています。興味のある方は参考にしてください。
ハローワークで仕事探しをするメリットは?仕事探しの方法も解説
2.地域若者サポートステーション(サポステ)
地域若者サポートステーションの利用も、35歳以上のニートの人が就職を考えるうえで効果的な方法です。
地域若者サポートステーションは、厚生労働省が委託した若者支援の実績やノウハウがある民間団体などが運営しています。全国177箇所にあり、全都道府県に設置されています。対象年齢は15〜49歳です。
具体的に受けられるサービスは、以下の4つです。
- 面接指導
- 就労相談
- 職場体験
- コミュニケーションスキルの向上
就活に必要な対策が総合的に受けられます。しかし、直接就職先を紹介してくれるわけではないため、注意してください。
「働きたいけど自信がない」
「久しぶりの就活で緊張している」
上記のような悩みを抱えている方は、手厚いサポートが受けられるでしょう。
3. 生活困窮者自立支援センター
35歳以上のニートで生活が苦しい方は、生活困窮者自立相談センターの利用を検討してみましょう。
生活困窮者自立相談センターは、生活保護を受けていない困窮者をサポートする機関です。
就労支援以外に受けられる支援は、以下の3つです。
- 家計改善
- 住まいの確保
- 社会からの孤立
就活にはお金がかかるため、良い条件の求人に応募できない人もいるでしょう。
また、仕事をしたくても、家庭の事情や心身の健康を理由にあきらめている人向けに手厚く支援しています。
仕事、家、お金など生活の基盤に不安や悩みのある方は、生活困窮者自立相談センターの利用を検討してみてください。
4. 就労移行支援事業所
障害をお持ちの方は、就労移行支援事業所も選択肢の1つです。
就労移行支援事業所は、障害のある方が一般企業への就労をサポートするサービスです。原則は18歳以上65歳未満の身体や精神、知的障害のある方が対象になります。
健康状態に問題のない方は利用できないため注意してください。ただし、医師の診断書があれば利用できる場合があるため、お持ちの方は事前に確認しておきましょう。
就労移行支援事業所で受けられる支援は、以下の5つです。
- 模擬面接
- 実務技能の習得
- 社会人に必要なマナー
- コミュニケーションスキル
- 履歴書、職務経歴書の添削
就職してからも活かせるスキルが多く学べます。イチからサポートしてほしい人にはおすすめです。
5. ひきこもり地域支援センター
最後は、ひきこもり地域支援センターをうまく活用することです。
ひきこもり地域支援センターは、引きこもりの人を専門にサポートしているサービスです。社会福祉士、精神保健福祉士などの専門知識を持ったプロが1人ひとりに合った支援を計画してくれます。
ハローワークや地域若者サポートステーション、NPO法人と連携した就労支援が可能です。他には、医療機関や行政などさまざまな機関ともつながっているため、一度の利用で包括的な支援が受けられます。
まとめ
35歳以上のニートは、若年層と比べ、社会的な風当たりの強さをダイレクトに受けることが少なくありません。世間の冷たい目に触れるなかで、「自分なんて就業はムリだ……」と諦めてしまう人もいることでしょう。
しかし、まだまだ諦めるのは早いです。長く働く意思さえ感じられれば、その意欲を買って、30代後半以上のニートであっても雇ってくれる企業は存在します。
年齢は変えられませんが、就業に向けた意識は自分次第で変えられます。そして行動しないと、未来は変わっていきません。まずは1歩ずつ、就業に向けた行動を起こしていきましょう。
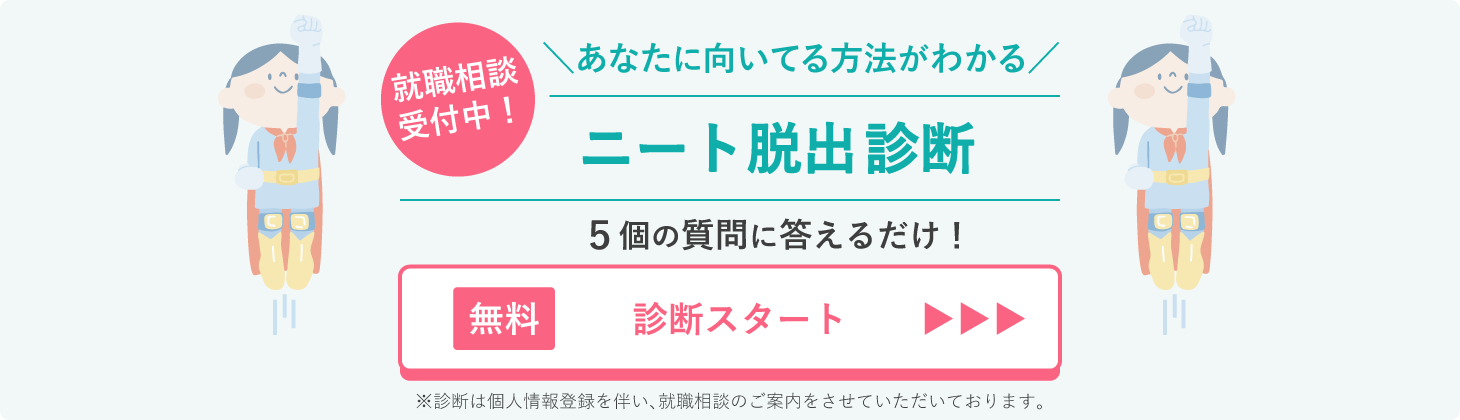
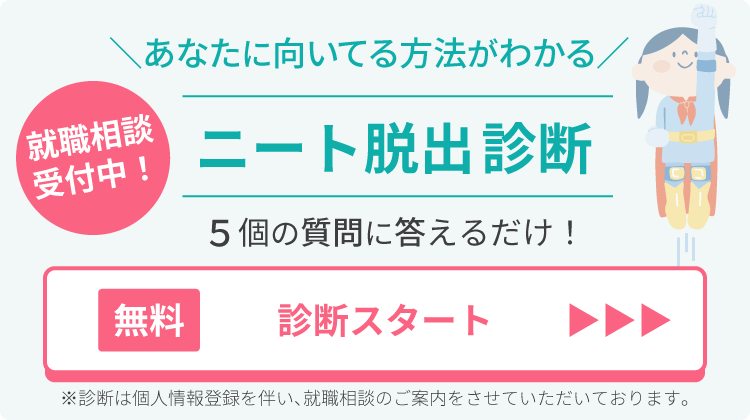

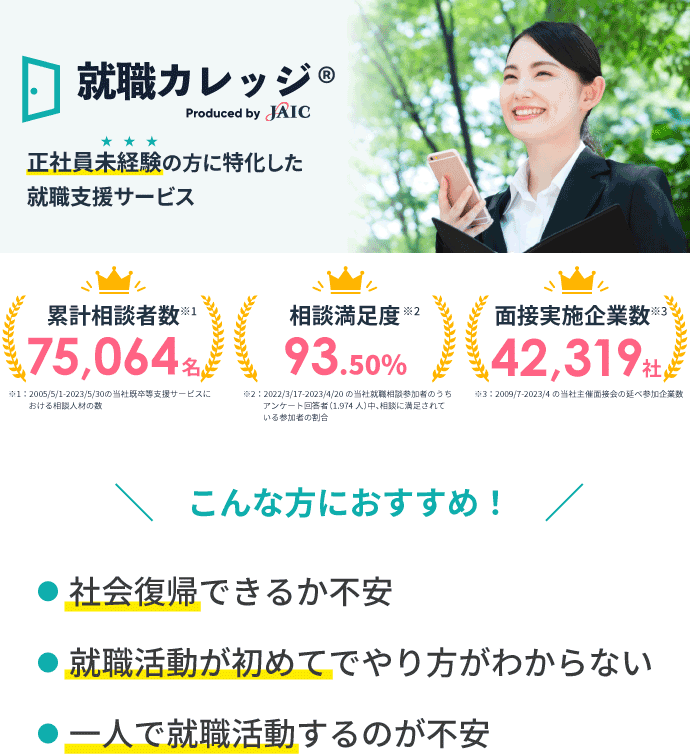

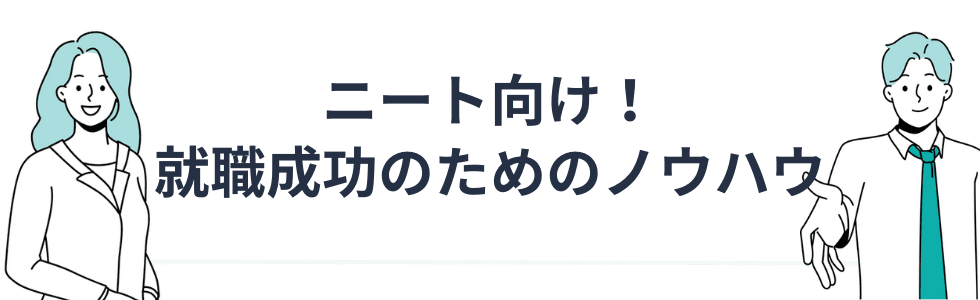
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説
- ニートの就活は何からすべき?就職活動のやり方の流れとコツを解説!
- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説
- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説
- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?
- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説
- ニートにおすすめの仕事25選【向いている仕事の特徴も解説】
- ニートOKの就職支援サービスと正社員就職のステップを解説!
- 高卒ニートは就職できる?職歴なしで正社員になる方法を解説!
- 大卒ニートの割合はどれくらい?末路や就職のコツを解説
- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介
- ニートが就職するのにおすすめのサイトは?就職サイト7選を紹介