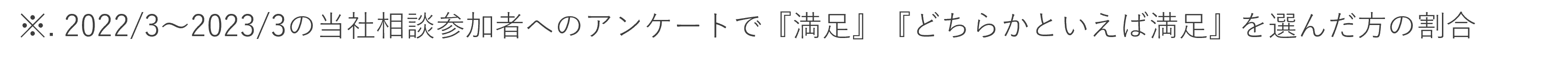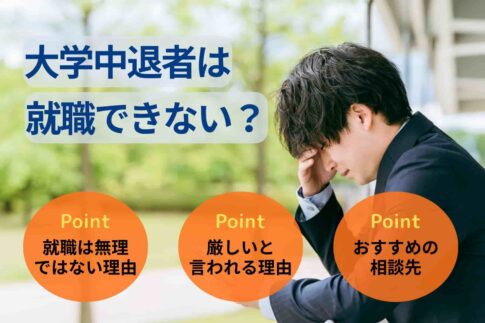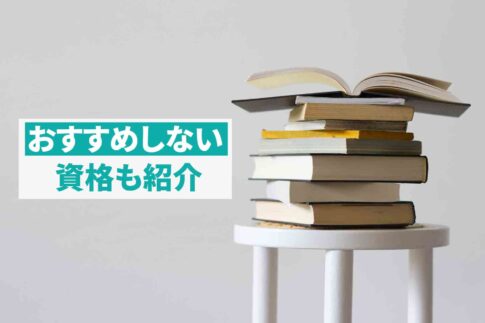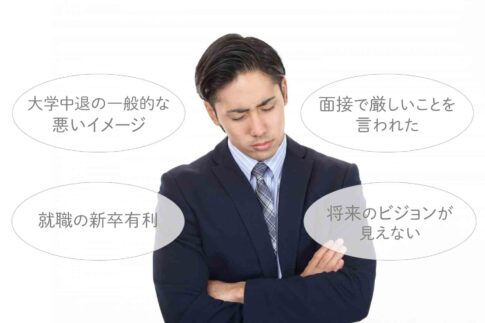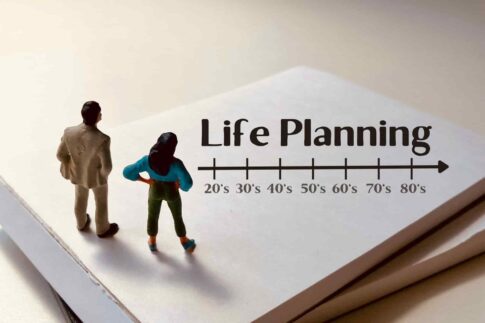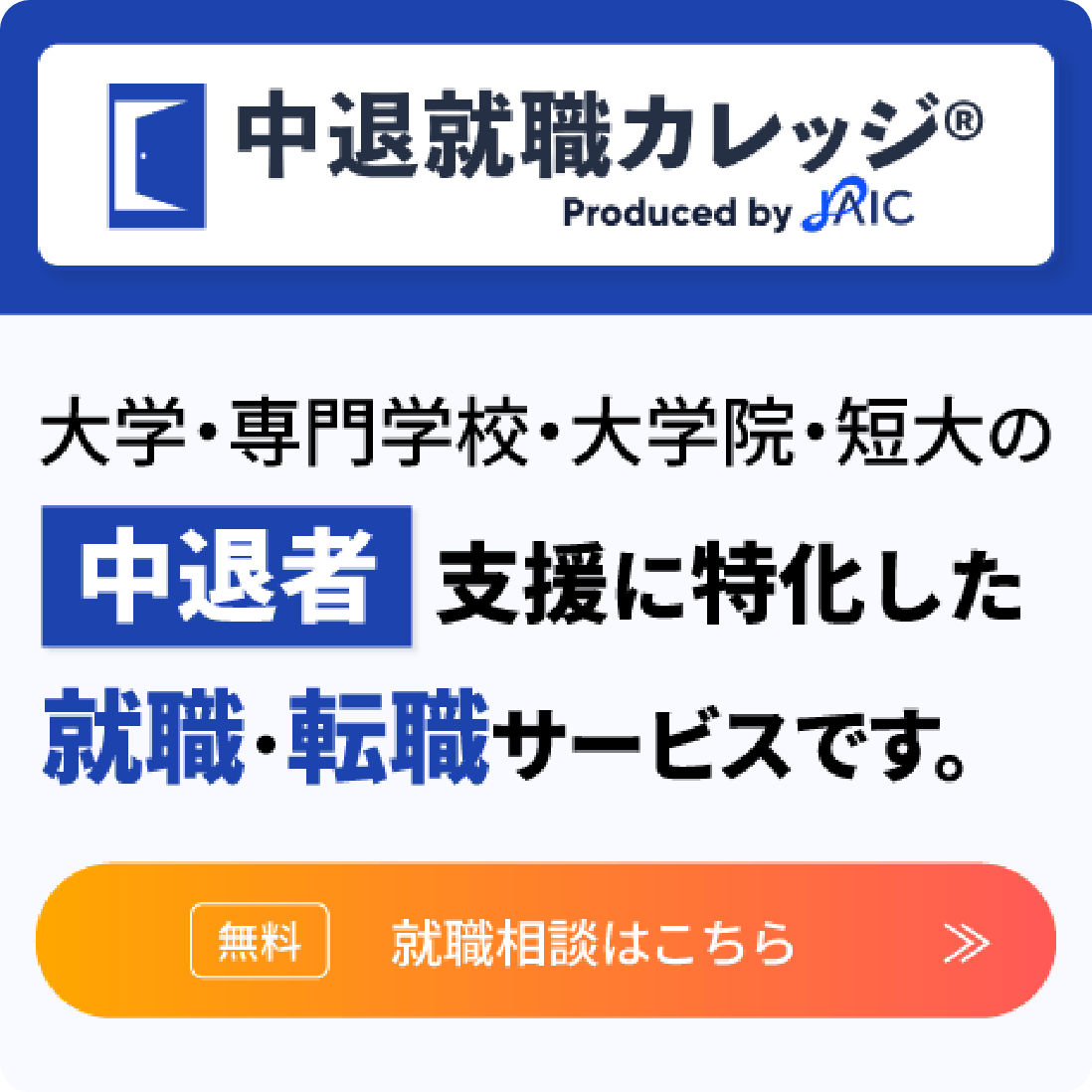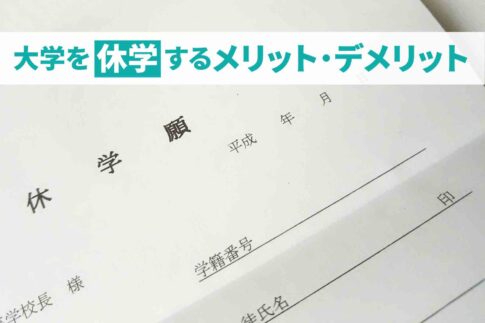大学中退の手続きの流れを解説!親に内緒でもOK?退学理由の書き方は?
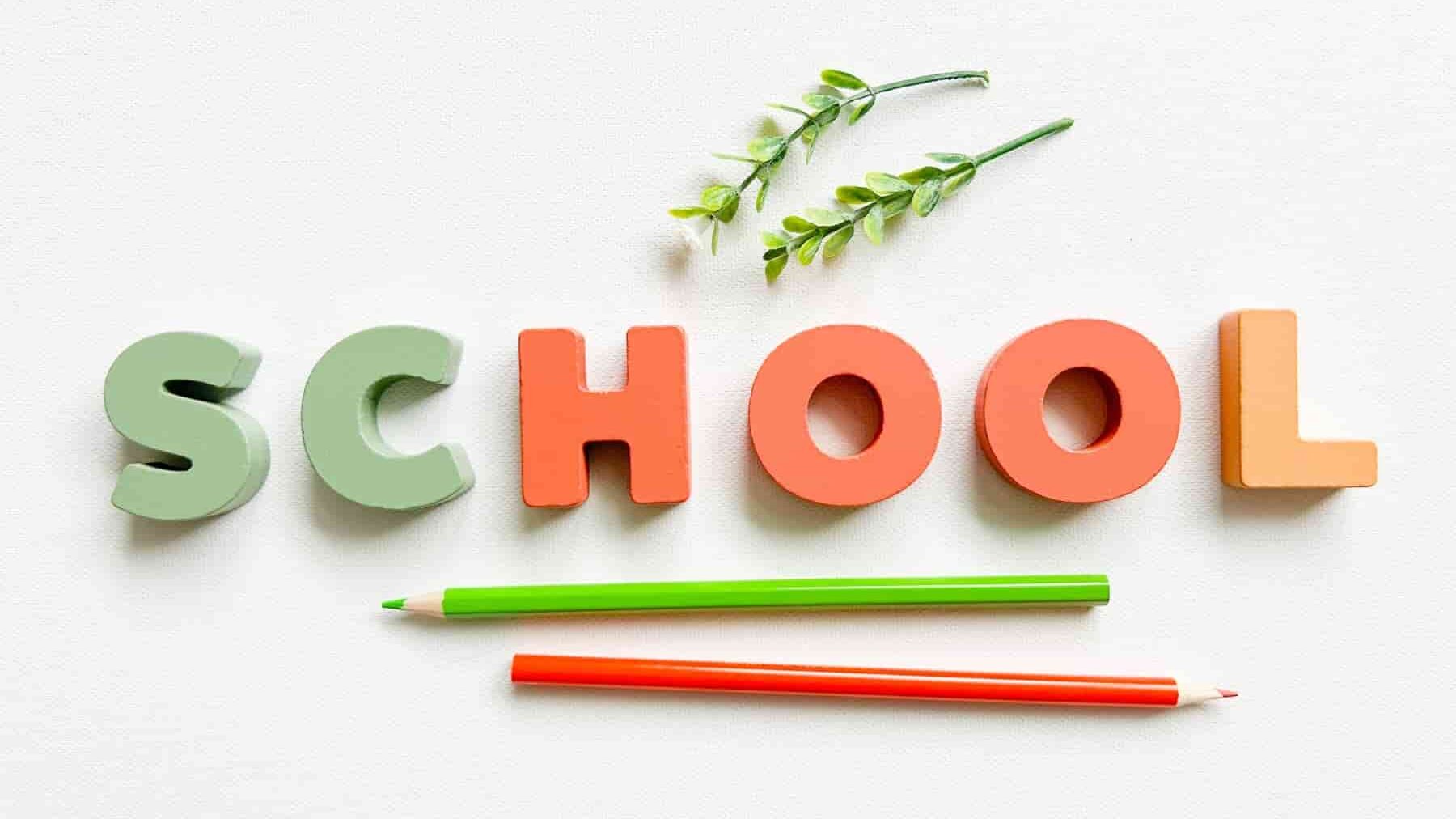
大学中退の手続きは大学によって多少異なりますが、指導教員との面談、退学届の作成・提出、保証人への確認連絡といった流れは、多くの大学で共通しています。
この記事では、大学の中退を検討している方に向けて、手続きの方法を6つのステップに分けて解説します。
「親に内緒で中退はできる?」「退学理由はどう書けばいいの?」といった9つの疑問にも回答していますので、中退するか迷っている方や、手続き方法を知りたい方は参考にしてください。
大学中退手続きの流れ
大学中退の手続きは、次の6つのステップで進むことが一般的です。
- 大学の公式サイトで流れを確認
- 指導教員と面談
- 退学届(退学願)を記入
- 退学届と必要書類を提出
- 大学から保証人に電話確認
- 退学許可通知書が保証人に届く
まずは大学の公式サイトなどで、退学手続きの流れを確認しましょう。
中退にあたっては、指導教員との面談や退学届の提出がほぼ必須です。
状況によっては、異動願(奨学金の停止手続きに必要な書類)や、病院の診断書の提出も求められます。
保証人に対し、大学から直接電話で確認が入ることも多いため、あらかじめ両親などと中退についてよく話し合い、同意を得ておくことも大切です。
中退が正式に認められると、保証人宛に「退学許可通知書」が郵送されます。
※こちらで紹介している手続きは一般的な流れです。全ての大学に当てはまるわけではないので、詳しくは各大学の公式サイトや学務課などで確認してください
1. 大学の公式サイトで流れを確認
中退の手続きのステップや提出書類は大学ごとに多少異なるため、まずは大学の公式サイトに掲載されている「中退・退学手続き」の流れを確認してください。
手続きの締め切り日も異なるため、公式サイト上でしっかり確認しておくことが大切です。
手続きの流れが掲載されていない場合は、学生課や教務課などで教えてもらいましょう。
2. 指導教員と面談
大学によっては指導教員との面談が必須のため、中退を決めたらできるだけ早く連絡を取り、面談の日程を調整しましょう。
指導教員とは、一般に「学生生活担当教員」や「所属学科のゼミ担当教員」を指します。誰に連絡すれば良いか分からない場合は、学生課や教務課に問い合わせてみてください。
面談では、主に退学の理由や今後の進路について質問されます。質問にスムーズに答えられるように、あらかじめ自分の考えを整理しておくと良いでしょう。
3. 退学届(退学願)を記入
学生の中退を認めるか大学側が判断する際の資料となるため、大学を中退する際は「退学届(退学願)」を記入し、大学側に提出する必要があります。
退学届は、学生支援課などの窓口で直接受け取れるほか、大学の公式サイトからダウンロードできる場合もあります。
大学によって異なりますが、主な記載項目は以下の通りです。
- 学部・学科、研究科、専攻
- 氏名、電話番号、学籍番号
- 奨学金受給状況
- 退学日
- 退学理由
- 保証人の記入欄(氏名、住所、電話番号)
記入漏れや誤記があると再提出を求められ、大学中退の手続き期限を過ぎてしまう恐れもあります。
退学届は、大学側に正式に中退を認めてもらうための重要な書類です。
保証人(親など)の署名も必要なため、早めに準備したり、誤りがないか何度も確認したりするなど、スピーディーかつ慎重な対応を心がけましょう。
4. 退学届と必要書類を提出
大学によっては退学届以外にも必要な書類があるため、事前に手続きの流れをよく確認し、期限までに提出できるように準備しておきましょう。
たとえば、以下のような書類が挙げられます。
- 異動願(日本学生支援機構の奨学金受給者のみ)
- 診断書(病気療養・体調不良の場合)
- 指導教員の意見書
- 中退理由書
- 学生証
日本学生支援機構の奨学金を受けている方は、中退時に奨学金の停止手続きも必要です。具体的には「異動願(届)」を学生支援課などで受け取り、必要事項を記入して大学に提出します。
また、病気療養などの理由で中退する場合は、診断書の提出が求められることもあります。
退学届と同じく、これらの書類の提出を忘れたり、記入に不備があったりすると手続きが遅れ、中退が認められないこともあります。そのため全ての書類を抜かりなく、期限内に正確に提出しましょう。
5. 大学から保証人に電話確認
学生が親に内緒で退学しようとしたり、退学届の「保証人の署名」を自分で書いたりするケースも考えられるため、大学側は保証人に対し、電話で直接確認することが一般的です。
保証人とは、学生の責任を負う立場の人のことです。一般には親が該当しますが、祖父母や叔父・叔母などが保証人になる場合もあります。
保証人への確認が取れないと大学中退の手続きが進まないため、あらかじめ両親などとよく話し合い、中退について同意を得ておくことが欠かせません。
6. 退学許可通知書が保証人に届く
学長の決裁が下り、大学側の審査が完了すると、中退を正式に許可した証として「退学許可通知書」が保証人宛に郵送されることが一般的です。
この通知書を受け取ることで、退学証明書や在籍期間証明書などの各種証明書を発行できるようになります。これらの証明書は、就職活動や他の学校への入学手続きなどで必要となる場合もあります。
「退学許可通知書」は重要な書類なので、大切に保管し、必要に応じてコピーを取っておくと安心です。
【例文あり】大学退学理由の書き方
退学届(退学願)には「退学理由」の記入欄が設けられていますが、形式的な確認に過ぎないケースも多いため、基本的には「一身上の都合です」と記載すれば問題ありません。
ただし、大学によっては具体的な理由の記載が必須の場合もあります。
退学理由は「就職することにした」「学費の支払いが難しくなった」など、本音を記載して構いません。ただし「なんとなく」といった曖昧な理由だと面談などで深掘りされ、中退の許可が下りるまでに時間がかかってしまう恐れもあるため注意が必要です。
そのため、あらかじめ具体的な退学理由を準備しておくことをおすすめします。
- アルバイト先から社員登用のお声がけをいただき、就職を決めました・父親が会社を退職し、経済的な理由から学業の継続が難しくなりました
- 精神的な不調により、安定して通学することが困難になりました
大学中退の手続きをスムーズに進めるためにも、明確な退学理由を用意しておきましょう。
大学中退手続きの9個の疑問
大学の退学手続きは、多くの大学で「退学希望月の前月末まで」または「学期末の9月30日・3月31日付」での締切が一般的です。
ただし、大学によって提出期限や必要書類、学費の取り扱いが異なるため、必ず在籍大学の教務課や公式サイトで確認しましょう。
退学届の用紙は、各大学の公式サイトからダウンロードできるほか、学生課や教務課などの窓口で直接受け取ることも可能です。
ここでは、こうした基本情報も含め、大学中退の手続きに関してよくある質問・疑問を9つに分けて解説します。中退を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 大学退学手続きはいつまで?時間は?
退学届の提出期限は大学によって異なります。「退学希望月の前月末まで」「退学希望日の1か月前まで」「前期は〇月〇日、後期は〇月〇日」など、大学により様々なので、大学のホームページをチェックしましょう。
大学中退の手続きは、学生課や教務課の窓口が開いている平日9:00〜17:00の時間帯が中心ですが、一部の大学は土曜の午前中も対応しています。
学期末試験後の成績確定時期や、授業料の納付期限が近づく時期は中退希望者が増える傾向があり、窓口が混雑します。そのため、早めの準備と申請を心がけましょう。
2. 大学退学届のもらい方は?
多くの大学では、公式サイト内の「各種手続き」や「大学生活」のページに退学に関する情報が掲載されており、そこから退学届(退学願)をダウンロードできます。
また、在学生向けのポータルサイト内で書類を入手できる場合もあるでしょう。
学生課や教務課の窓口でも退学届を受け取ることができ、その場で記載方法も教えてもらえます。大学中退の流れも詳しく教えてもらえるので、手続きに不安がある方は窓口で退学届を受け取るのがおすすめです。
3. 大学退学届は郵送もOK?
一部の大学では退学届の郵送を認めていますが、多くの大学では学生本人が学生課などの窓口に直接提出することを義務づけています。
ただし、入院中で大学に足を運べないなど、こうしたやむを得ない事情がある場合に限り、個別に郵送での提出を認めるケースもあります。
とはいえ、これはあくまで例外です。大学の公式サイト内に「退学届は郵送可」と明記されていない限り、基本的には窓口に直接提出する必要があると理解しておきましょう。
4. 大学退学手続きは親に内緒でできる?
大学中退の手続きを進めるには、原則として「保証人の同意」が必要なため、親に内緒で中退するのは難しいのが現実です。
ただし、以下のような例外もあります。
- 保証人が親以外に設定されている(祖父母、叔父・叔母など)
- 学則に「保証人の同意が必要」と明記されていない
なお、成人している場合は本人の意思が尊重される傾向があるため、たとえ学則に「保証人の同意が必要」と書かれていても、退学が認められる可能性も少なからずあります。
とはいえ多くの大学では、退学届に保証人の署名を求めたり、保証人あてに確認の電話を入れたりするなど、保証人の承認を得るプロセスを設けています。
そのため、親に黙って中退するのは、現実的にはかなり難しいでしょう。
5. 大学退学手続きは本人以外もできる?
大学側としては「学生が本当に中退を望んでいるのか」を確実に確認する必要があるため、大学の退学手続きを本人以外が行うことは非常に難しいのが実情です。
ただし以下のようなケースでは、代理人による手続きが認められることもあります。
- 学生本人が事故などで意識不明、または外出が極めて困難な場合
- 海外在住など、物理的に大学に足を運ぶことが難しい場合
こうした特別な事情を除けば、大学中退の手続きは学生本人が行う必要がある、と覚えておきましょう。
6. 大学退学届が受理されない理由は?
必要事項が全て正しく記入され、必要書類が揃ってはじめて大学側は中退手続きを進めるため、退学届が受理されない理由としては「書類上の不備」が考えられます。
たとえば、以下のようなケースが挙げられるでしょう。
- 退学届の記入漏れ、押印忘れ
- 保証人の署名がない
- 必要書類の提出漏れ(中退理由書、医師の診断書など)
- 書類の提出期限を過ぎている
退学届が受理されない場合は、上記の点に不備がないかをいま一度確認してみましょう。
7. 大学の退学が認められないのはなぜ?
退学手続きの時点で当該学期や過去の学費が支払われていない場合、退学を認めていない大学がほとんどのため、中退が認められない要因としては「学費の未納」が考えられます。
また多くの大学では、退学にあたって指導教員との面談を義務づけています。この面談では退学理由の確認などが行われますが、面談を実施していない場合、大学側が学生の意志や状況を十分に把握できないため、退学の受理が保留になることもあります。
その他、保証人に連絡が取れない、本人以外が退学申請を行っているといったケースも、退学を認めてもらえない理由といえるでしょう。
8. 大学を中退したら学費はどうなる?
納入した学費は原則として返還されないため、その学期分の学費をすでに支払っていて、すでに新学期が始まっている場合、返金されないことが多いです。
ただし、学期が始まる前に退学手続きを完了できた場合は、学費を払わずに済む、あるいは納入済みの学費の一部が返金される可能性があります。
たとえば、前期が始まる前の3月中に退学が受理されれば、前期分の学費は発生しない、といったケースです。
このように、大学を中退する場合は、「すでに支払った学費は基本的には戻らない」「納期前に退学が決まれば次年度(次学期)の学費は不要」と理解しておきましょう。
9. 大学を退学手続きしないとどうなる?
大学中退の手続きをしないと、大学側は「その学生が在籍している」とみなすため、たとえ大学に通っていなくても学費の請求が続きます。
そして、大学からの督促を無視して学費を長期間滞納すると、最終的に「除籍」となります。除籍とは、学校側がその学生の学籍を抹消する処分のことです。
除籍になると、他大学への編入や、就職活動で企業から提出を求められる「成績証明書」が発行されない場合もあるため注意が必要です。
退学手続きをしないでいると、学費の負担だけでなく、将来のキャリアにおいても悪影響が出る恐れがあることを理解しておきましょう。
大学中退手続きが完了したらすること
大学の中退手続きが完了したら、通学定期や携帯電話の学割プランの解約、大学寮の契約解除などを忘れずに行いましょう。
親の扶養から外れる場合は、多くのケースでは国民健康保険への加入が必要になります。国民年金については、「学生納付特例制度」を利用していた人は、年金事務所などで通常の納付への切り替え手続きを行う必要があります。
日本学生支援機構の奨学金を受けていた人は、中退後およそ7か月目から返済がスタートします。
中退後に就職を目指す場合は、ハローワークやサポステ、就職エージェントなどの就職支援サービスの活用もおすすめです。
1. 学割や寮費の解約
大学を中退すると学生証が無効になるため、学生証を提示して利用していたサービスがあれば、速やかに解約や変更手続きを行う必要があります。
たとえば、以下のようなものが該当します。
- 通学定期券の解約・払い戻し
- 携帯電話料金の学割プランの解約
- サブスクの学生版ライセンスの解約(Amazon Prime、YouTube Premiumなど)
大学の寮に住んでいた場合、「退寮届」を出さないと寮費を請求され続ける可能性がある点にも注意が必要です。
中退後は学割が使えなくなり、寮費の支払い義務もなくなるため、忘れずに必要な手続きを済ませておきましょう。
2. 社会保険の手続き
大学を中退すると、健康保険と国民年金の手続きが必要になる場合があります。
親の扶養から外れる場合は、自分で市区町村の役所で国民健康保険に加入する必要があります。一方、扶養のままであれば、健康保険の手続きは基本的に不要です。
国民年金は、20歳以上の全員が加入義務があります。そのため、18〜19歳で中退した人は手続きは特に必要ありません。
20歳以上の中退者で「学生納付特例制度」を利用していた場合は、適用が終了するため、自分で保険料を納めるための手続きが必要です。制度を利用していなければ、国民年金に関して特別な手続きは不要です。
国民健康保険
大学を中退したあと、親の扶養に入っていない場合は、自分で国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険とは、自営業者や無職の人などが加入する公的な医療保険制度で、病気やけがをしたときに医療費の一部を補助してもらえる仕組みです。
一般に、大学生の間は親の扶養に入り、親の勤務先を通じて健康保険に加入しているケースが多く見られます。しかし、中退後にアルバイト収入が一定額(年収130万円以上が目安)を超えるなど、いくつかの要件を満たすと扶養から外れる可能性があるのです。
この場合は、住んでいる市区町村の役所で、速やかに国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
中退後の健康保険の扱いは「扶養に入っているかどうか」で大きく変わります。そのため、まずは両親に状況を伝え、会社の担当部署に扶養の継続可否を確認してもらいましょう。
国民年金
学生納付特例制度を利用していた人は、大学中退後に通常の国民年金保険料納付への切り替え手続きなどが必要です。
国民年金とは、日本に住む20歳以上の全ての人が加入する公的年金制度です。そのため、18〜19歳で中退した人は手続きを行う必要はありません。
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生で所得が一定以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用していた場合、中退によって「学生」ではなくなるため適用対象外となります。すると自分で保険料を納める義務が発生するため、年金事務所などで手続きが必要になるのです。
一方、学生納付特例制度を利用していない人は、中退後に特別な手続きは不要です。
中退後の国民年金の扱いは「学生納付特例制度の利用有無」によって変わるため、まずは自分が制度を使っていたか確認しましょう。
3. 奨学金の返済
日本学生支援機構の奨学金を借りていた人は、大学中退後、奨学金を最後に借りた月の翌月から数えて7か月目に返済が始まります。
貸与型奨学金の場合、中退時には次のような手続きが必要です。
1、大学の学生課などに連絡し、奨学金の振込を停止してもらう
↓
2、「異動願(届)」を大学から受け取り、必要事項を記入して提出する
↓
3、「貸与奨学金返還確認票」を大学から受け取り、口座振替(リレー口座)への加入手続きを行う
返済が難しい場合には、「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」といった救済制度を利用できることがあります。
大学中退後、基本的には奨学金の返済が7ヶ月目以降に始まりますが、経済的に厳しい人はこうした制度の活用を検討しましょう。
4. 就職支援サービスに登録
大学中退者は、新卒と比べると就職活動で不利になりやすいため、内定の可能性を高めるためにも、就職支援サービスの活用をおすすめします。
中退者に特におすすめのサービスは、次の3つです。
| 支援先 | 主なサービス |
|---|---|
| ハローワーク | 求人検索・紹介、就職相談、就活セミナー、履歴書の添削、職業訓練など |
| サポステ (地域若者サポートステーション) | コミュニケーション講座、就活セミナー、就職相談、職場体験など |
| 既卒・第二新卒向け就職エージェント | 求人紹介、就職相談、面接練習、履歴書の添削、企業との面接日程の調整、給与交渉など |
どれも無料で利用でき、仕事経験がない10代後半〜20代の方も丁寧にサポートしてくれます。
大学を中退し、「ひとりで就活を進めるのが不安」「高卒になるけど内定を取れるかな…」と感じている方は、こうした支援サービスをぜひ利用してみましょう。
大学中退手続きの注意点
大学を中退する前に、まずは本当に卒業が不可能なのか、学生課や教務課で履修状況を再度確認してもらいましょう。
思い込みで退学を決めてしまう人も多く、実際には必要な単位が足りていた、というケースは珍しくありません。
また、大学中退の手続きが遅れると次の学期の学費が発生し、余計な出費につながる恐れもあります。そのため中退の意思が固まったら、退学届を早めに提出し、スピーディーに手続きを進めることも大切です。
図書館の本や、研究室の備品など、大学から借りている物品がないかも改めて確認し、中退前に忘れずに返却しておきましょう。
1. 卒業要件などを満たしていないか再度確認する
退学の手続きは一度完了すると取り消せないため、自分が本当に卒業できないのか?について、中退手続きを進める前にもう一度しっかりと確認しましょう。
中退を考える人の中には、「単位が足りない」「進級できない」といった思い込みによって、大学の継続を諦めてしまうケースも少なくありません。しかし実際には、卒業に必要な単位が足りていた、ということもあるのです。
そのため、中退という重要な決断を下す前に、まずは学生課や教務課で自分の履修状況を何度も確認してもらいましょう。自分ひとりで判断せず、客観的な意見を聞くことが何よりも大切です。
2. 退学を決めた後はなるべく早く退学届を提出する
退学届の提出が遅れると、次の学期の学費を支払わなければならない場合があるため、大学中退の意思が固まったら手続きを先延ばしにせず、早めに退学届を提出しましょう。
大学にもよりますが、学期の途中で退学しても、その学期分の授業料は返還されないケースがほとんどです。たとえば3月中に退学しようと思っていたのに、手続きを4月まで放置すると、4月から9月までの前期の授業料が発生してしまいます。
退学届の提出が遅れると、本来なら支払わなくてよかったはずの学費を請求されることがあるため、中退を決意したらできるだけ早く退学届を提出するようにしましょう。
3. 大学から借りているものを忘れずに返す
大学から借りたままの物品を返却し忘れると、中退後に費用を請求される恐れもあるため、大学からの借用品がないかも中退前に改めて確認しておきましょう。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
- 大学の図書館から借りている書籍、DVD、資料
- 研究室から借りている物品、実験器具
- 大学所有のパソコン、タブレット、Wi-Fiルーター
- パソコンにインストールしたソフトウェアのライセンス
- 大学内のロッカーの鍵
- 部活やサークルで借りていた備品
- 学生証
大学に返却が必要な物品は意外と多いので、借りているものをリストアップし、全て確実に返却できているか確かめましょう。
まとめ
この記事では、大学中退の手続き方法について解説しました。
中退の手順は大学によって異なるため、まずは大学の公式サイトや学生課で具体的な流れを確認することが大切です。
手続きが遅れると次年度の学費を支払う必要が出てくるなど、余計な負担が発生する恐れもあります。そのため早めに準備を進め、スムーズに中退手続きを完了させましょう。
当社の就職に関するコンテンツの中から、大学中退後の就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- 大学中退者が就職するには?就活のやり方のコツを徹底解説!
- 大学中退者の就職先におすすめの仕事15選!選び方のポイントも解説
- 大学中退後の就職は厳しい?中退して良かった声や就職成功法を解説
- 履歴書に中退を書かないのはNG?大学中退の書き方を見本付きで解説!
- 大学中退理由は武器になる!履歴書/面接での効果的な伝え方
- 大学中退者の就職体験談総まとめ!11人の成功談を徹底分析
- 大学中退者は就職できない?厳しい理由と行った方いい相談先を解説
- 大学中退者向け就職サイト5選!選び方や活用法を解説!
- 大学中退してよかった理由と後悔した理由を実際の声から解説
- 大学中退は人生終了?就職を成功させる方法や注意点を解説!
- 大学中退したその後の進路7選!将来どうなるか選択肢を解説