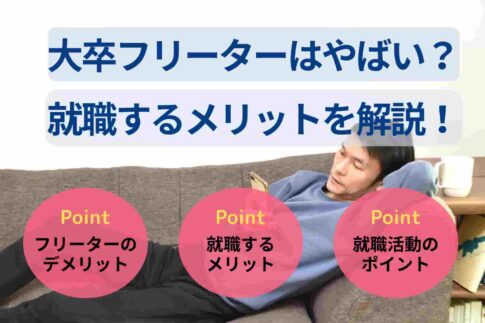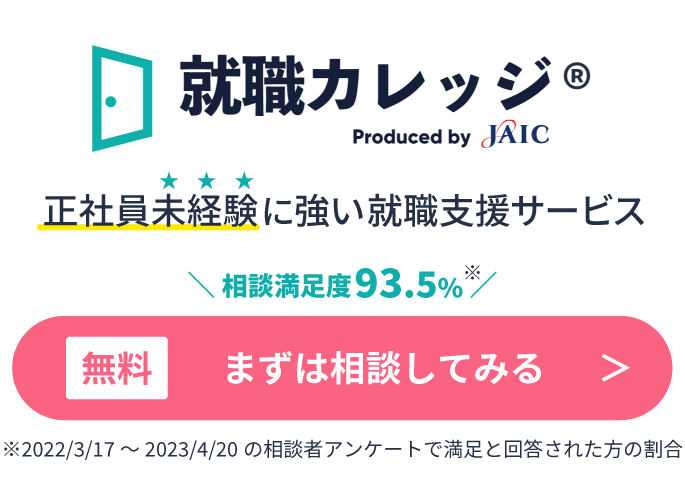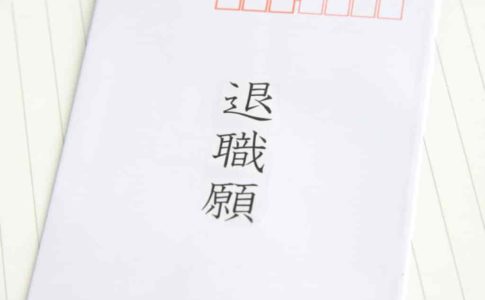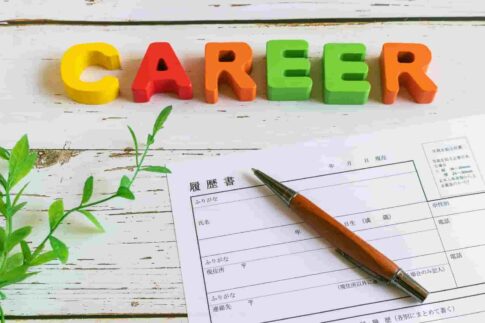公務員試験の受験資格を満たし、公務員試験に合格すればフリーターから公務員になることができます。公務員試験は学歴にかかわらず受けることができますが、年齢によっては受験資格を満たさないことがあります。
この記事では、公務員試験の受験資格や年齢制限、学歴要件などの確認しておきたいポイントや、高卒・大卒それぞれに適した試験対策を紹介します。また、国家公務員と地方公務員の違いや、一般職・特別職・専門職の種類についても詳しく解説します。
フリーターが公務員を目指す際のメリットとデメリットも客観的にお伝えするので、あなたのキャリアチェンジを成功させるために、ぜひご活用してみてください。
- 「フリーターから公務員を目指すときのポイント」を高卒・大卒別に解説
- フリーターから公務員を目指すメリットとデメリット、どちらも知った上で検討しよう
- 「自分は公務員に向いていないかも」と感じたら、民間企業への就活も同時に進めよう
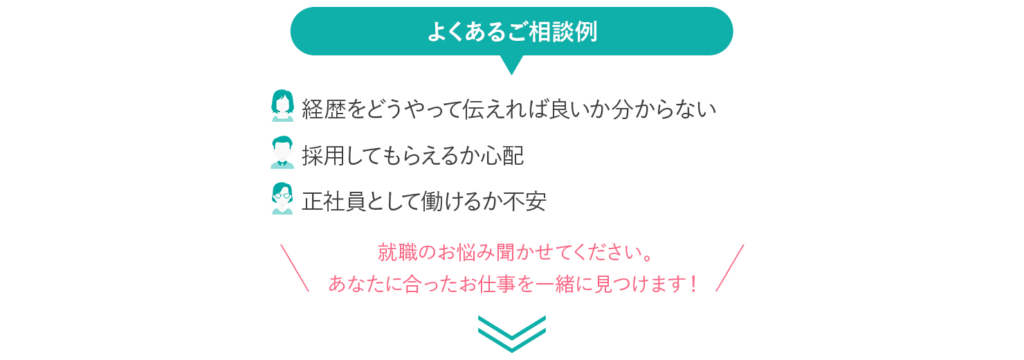



この記事の目次
フリーターから公務員になれる?
公務員試験の受験資格を満たしており、公務員試験に合格することができれば、フリーターから公務員になることが可能です。
公務員試験の受験資格
フリーターから公務員を目指す際には、まず受験資格を確認することが重要です。公務員試験の受験資格には、いくつかの重要な項目があります。それぞれを詳細に理解しておくことで、準備を着実に進めることができます。
欠格条項
公務員試験には、法律に基づく欠格条項が存在します。特定の犯罪歴がある場合や破産手続き中である場合など、 一部の法令上の条件に該当する場合には、受験資格を満たさないことがあります。したがって、自分が該当しないかどうかしっかり確認することが必要です。
一禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
引用元:e-Gov 法令検索「地方公務員法」
年齢制限
公務員試験には年齢制限が設けられており、多くの職種では採用時に29歳または39歳未満であることが求められます。フリーターから公務員を目指す際には、年齢制限に注意を払い、その制限内での受験計画を立てることが重要です。年齢制限を超えると受験資格を失うため、早めの計画が必要です。
学歴
公務員試験は、学歴にかかわらず受けられることがほとんどです。公務員試験は、「高卒程度」「短大・専門卒程度」「大卒程度」に分けられていますが、試験の難易度を表しているだけで、高卒だからと言って「大卒程度」の公務員試験に応募できないわけではありません。
ただし、公安職の一部の職種や、国家公務員総合職は大卒以上の学歴が求められることもあります。
資格
特に専門職や技術職を目指す際には、それに関連する資格が求められる場合があります。例えば、技術職では土木や情報技術に関する資格が必要とされることがあります。他にも福祉職には社会福祉士の資格が必要になることもあります。資格取得は、試験突破のための大きなアドバンテージとなるため、必要な資格が指定されているかどうかを必ずチェックしましょう。
身体的条件
公安職など一部の職種では、身体的条件が設けられている場合があります。警察官や消防士など、身体的な健康状態が業務の遂行に影響を及ぼす可能性のある職種では、身体検査が実施され、基準に達していることが求められます。したがって、応募前にその身体的条件を確認し、必要な準備を行うことが大切です。
フリーターから公務員になる方法
募集要項の確認・応募
フリーターから公務員を目指す際、まず重要なのは募集要項の確認です。公務員試験にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる受験資格や年齢制限が設けられています。特に年齢制限については注意が必要で、29歳まで〜34歳までとされていることが一般的です。また、市役所職員や地方公務員、国家公務員など自分がどの職種を目指すのか明確にし、それに基づいて必要な手続きを進めましょう。募集時期には限りがあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
一次試験(筆記試験)
公務員試験の最初の関門である一次試験は、主に筆記試験で構成されています。この試験は一般知識や専門知識、教養試験などが含まれており、試験対策が不可欠です。筆記試験に合格するには、十分な勉強時間と計画的な学習が必要です。独学での学習も可能ですが、専門的な指導が受けられる予備校へ通うことも検討すると良いでしょう。試験の内容に関しては事前に詳しく調査し、自分の苦手な分野を特定して集中的に勉強するのが効果的です。
二次試験(面接試験)
一次試験に合格した後は、二次試験である面接試験が待っています。この試験では、フリーターとしての経験や職員としての適性が見極められます。面接試験ではコミュニケーション能力や志望動機、自己PRが重要となりますので、過去の経験を生かしてしっかりと準備して臨みましょう。面接練習を繰り返し行い、自信を持って自分をアピールすることが求められます。
最終選考
面接試験を通過すると、最終選考に進むことができます。最終選考では、応募者の適性や意欲が再確認され、職員としての総合的な判断が行われます。フリーターから公務員に転職する際、過去の経験が評価されることもありますので、自分の強みをしっかりとアピールすることが重要です。これまでの道のりを振り返りながら、この段階で再確認される目的意識を持ち、安定した公務員への道を進んでいきましょう。
フリーターからなれる公務員の種類
フリーターから公務員になりたいと考える場合、選択肢は多岐にわたります。国家公務員の種類と地方公務員の種類を理解することは重要です。それぞれの職種について詳しく見ていきましょう。
国家公務員の一般職
国家公務員の一般職は、中央省庁での事務的な業務を担当します。フリーターから公務員を目指す方にも人気が高く、安定した職場環境を求める方に適しています。基本的に全国規模での異動が生じることがありますが、幅広い業務を経験することができるのが魅力です。
国家公務員の一般職の試験には、大卒程度試験、高卒者試験、社会人試験(係員級)があり、公務員試験をクリアすることで、この職への道が開けます。
中卒・高卒で卒業後2年以内の場合は「高卒者試験」を、中卒・高卒で卒業後2年以上経っている場合は「社会人試験(係員級)」で受験します。
それぞれ受験資格や試験のスケジュールが異なるので、事前に確認しましょう。
| 受験資格 | 倍率 | |
| 大卒程度試験 | 20歳~30歳3月までに大学、短期大学又は高等専門学校を卒業見込み | 2.29倍(2023年度) |
| 高卒者試験 | 高校、または中学卒業後2年以内3月までに高校、中学卒業見込み | 2.4倍(2023年度) |
| 社会人試験(係員級) | 40歳まで中学・高校卒業後2年以上経っている | 2.4倍(2023年度) |
参考:人事院「国家公務員採用試験 受験案内一覧」、「試験情報」
地方公務員
地方公務員は、地域住民と直接関わる役割を担います。市役所職員として地元に貢献したいと考えるフリーターの方にとっては理想的な選択肢です。行政職、技術職、公安職などさまざまな職種がありますので、自分に合った分野を見つけることができます。
地方公務員の受験資格は、自治体により異なるため、希望する地域の自治体の募集要項をチェックしましょう。
行政職
行政職は、市役所や県庁などでの事務的な業務を担当します。地域の生活を支える重要な役割を果たし、住民からの相談に乗ることもあります。フリーターからでも目指すことができ、安定した職場環境を提供します。
技術職
技術職は、土木、建築、情報技術など専門技術を必要とする分野を担当します。特に手に職を付けたいフリーターの方にとって、技術職は魅力的な選択肢となります。公務員試験を通じて必要な技術資格を取得し、地域のインフラ整備に貢献することができます。
公安職
公安職は、警察官や消防士など公共の安全を守る職種です。命を守るやりがいのある仕事であり、体力が必要な職種でもあります。フリーターからでも体力作りをしっかり行えば目指すことができます。公務員試験では、体力試験が課せられる場合があるため、事前の準備が重要です。
国家公務員と地方公務員の仕事内容

フリーターから公務員になろうと思った時、まず最初に考えるべきなのは国家公務員と地方公務員、どちらを目指すかということです。国家公務員と地方公務員では働き方が異なり、採用に際して受験する試験も異なります。それぞれの働き方と仕事内容についてご紹介します。
国家公務員とは
各省庁やそれに関連する出先機関などに勤務し、国に関連する業務をおこなう公務員を指します。自分たちの身近なところでは働いていないように感じる国家公務員ですが、そんなことはありません。
たとえば地方の税務署に勤める職員は地方公務員ではなく「国税局の地方支部に勤める国家公務員」です。確定申告や税金に関する問い合わせなどで実際に税務署へ行くこともあるため、国家公務員のなかでは最も身近な存在のひとつといえるでしょう。
国家公務員の働き方の種類
国家公務員にも複数の働き方があり、一般職、特別職、専門職といった種類に分かれています。
一般職
国家公務員としての代表的な働き方です。外務省、財務省、文部科学省などのような中央省庁で働く人たちのことを指します。
特別職
特別職と呼ばれるのは、大臣や副大臣などのような、いわゆる政治家として選挙などで選出された人々です。また、国会の職員や自衛隊員なども国家公務員の特別職です。
こうした特別職の官僚たちが政策を決め、一般職で各省庁に勤める人々がその政策を実施していきます。
専門職
専門職と呼ばれるのは、財務専門官や国税専門官や労働基準監督官などの専門分野を持って働く人たちです。
これらの専門職は、法律に関係した分野であることが多いようです。
地方公務員とは
地方公務員は、簡単に言うと県庁や市区町村役場などの地方自治体で働く人々のことを指します。地方公務員は国家公務員よりも、地元の生活に密着して、実際に現場で市民と接する働き方が多くなるといえるでしょう。
「地元のために働きたい」という人にとっては、地方公務員は魅力的な選択肢のひとつかもしれません。
地方公務員の働き方の種類
地方公務員も国家公務員と同じように、特別職と一般職に分けられます。
一般職
大半の地方公務員の人々は、県庁や市役所に勤める一般職の職員として働いています。そうした地方自治体の役所で働く以外にも、公立機関の病院や図書館、学校、福祉施設などで働くこともあります。薬剤師や獣医のような国家資格を持った人々が、地方公務員として働く場合もあります。
このほかに、消防士や警察官も地方公務員です。一部の警察官は国家公務員として警察庁に勤めていますが、大半の警察官は地方公務員として地域の警察署などで働きます。
特別職
特別職は知事や副知事、市町村長といった選挙などで選出された人々のことを指します。
よくイメージされる公務員試験を受験してなれる職種ではないため、公務員とは別物に考えられがちですが、実は彼らも地方公務員の一員です。
公務員試験はフリーターだと不利?
フリーターから公務員を目指す時に、不利になるという心配を持つ方も多いかもしれません。しかし、実際にはフリーターであっても、公務員試験に合格することは十分に可能です。公務員試験は学歴を主たる評価基準とはしておらず、筆記試験や面接の結果が重視されるため、努力次第で道が開けます。
フリーターの方が公務員を目指す際には、試験に向けた対策や心構えが特に重要です。年齢制限はあるものの、そのルールにさえ適合すれば、一般的な資格や学歴とは異なる、多様な経歴が許容される環境です。国家公務員や地方公務員(例えば市役所職員)の試験は、その人の持つ能力や資質を評価する場ですので、過去にどのような職業経験をしてきたとしても、その経験をどのように試験で活かせるかがポイントとなります。
もちろん、フリーターとしての経験やキャリアがどのように見られるかが不安になることもあるでしょう。一時的な職歴の空白期間や、非正規雇用であることをどう説明するかは、面接における課題となるかもしれません。しかし、それを一つの経験として前向きに捉え、フリーターとして得たスキルや知識、柔軟性を具体的にアピールすることができれば、大きな不利とはならないでしょう。公務員試験は、フリーターの方にとっても新しいキャリアのスタート地点となるため、十分な準備と工夫が求められるのです。
公務員試験について
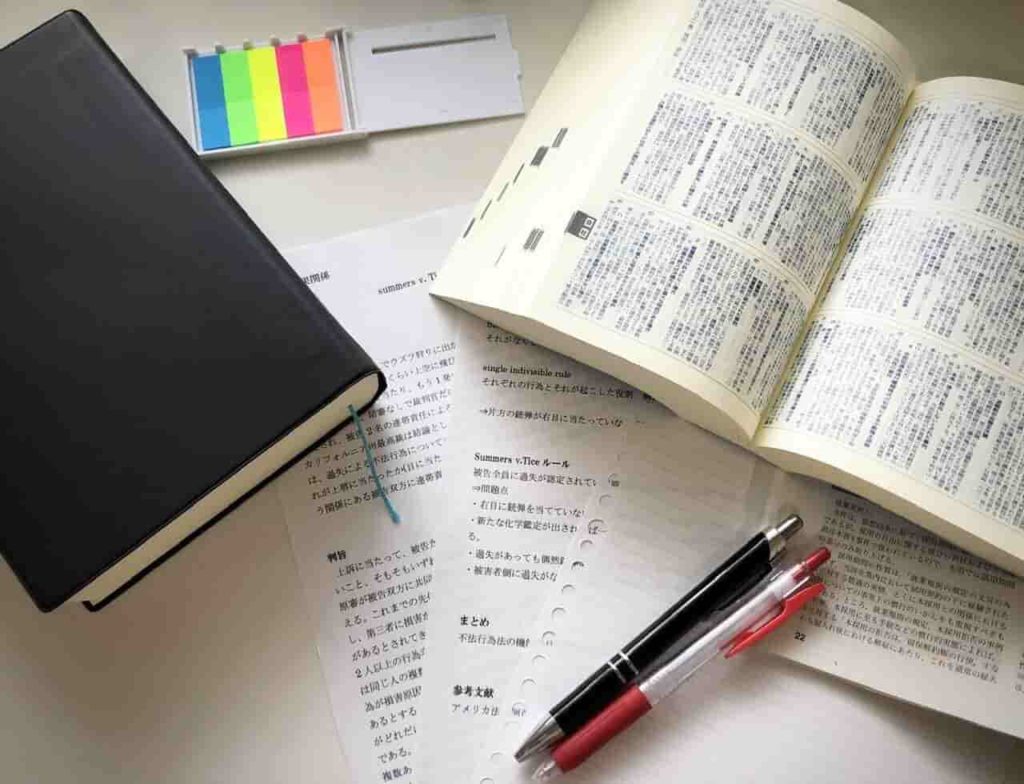
地方公務員、国家公務員のどちらを目指す場合も、公務員試験を受けて合格する必要があります。公務員試験を受ける前に、知っておくべき知識をご紹介します。
公務員試験とは
公務員試験がどのようなものなのかや、これから公務員試験を受けたいと考えているフリーターが、知っておいたほうがよいことをご紹介します。
一般枠の試験は経歴を問わない
公務員試験の一般枠の試験では、職歴や社会人経験を問われることはありません。フリーターであっても、一般枠の試験に合格することさえできれば、公務員として働くことができます。
ただし、公務員試験には国家、地方ともに年齢制限が設けられていることがほとんどです。
経験者枠は採用倍率が高い
経験者枠は、基本的には民間企業で正社員として勤務してきた人たちが受けることが多く、採用倍率も非常に高くなりがちなようです。
経験者枠については、継続的に働いていた年数や業務内容によっては、フリーターでも経験枠として応募できることもあります。
ただし正社員経験者とフリーターでは、どうしても面接などで不利な部分も出てきてしまうかもしれません。フリーターの方はしっかりと目指す職種の試験対策を行った上で、一般枠で応募する方が合格に近づけるかもしれません。
年齢制限がある
国家公務員の場合は大半が30歳まで、地方公務員の場合は各地方自治体によって異なりますが、やはり30歳前後までが上限年齢とされていることが多いようです。
また、公務員試験には一般枠の試験の他に、経験者枠の試験もあります。これは民間企業で一定の期間、働いた経験のある人が対象とされている試験です。この試験枠の場合は、一般枠での試験よりも、上限年齢が高く設定されている場合が多いようです。
求められる民間企業での職務経験年数は、職種や地方自治体によって異なるため注意が必要です。
確認すべきなのは、自分の年齢と、応募したい職種の上限年齢があっているかということです。国家公務員であれば人事院から、地方公務員であれば各地方自治体のホームページなどで、採用募集職種と受験資格年齢が記された採用計画の要項が発表されているはずです。
多くは「平成☓☓年4月2日から平成☓☓年4月1日までに生まれた方」といった形で、明確に年齢上限が定められていますので、必ず確認しましょう。年齢だけを見て判断してしまうと、応募時は上限年齢内だったので受験資格があると思ったが、採用時には上限年齢を超えてしまうため受験資格がなかった、ということもありえます。
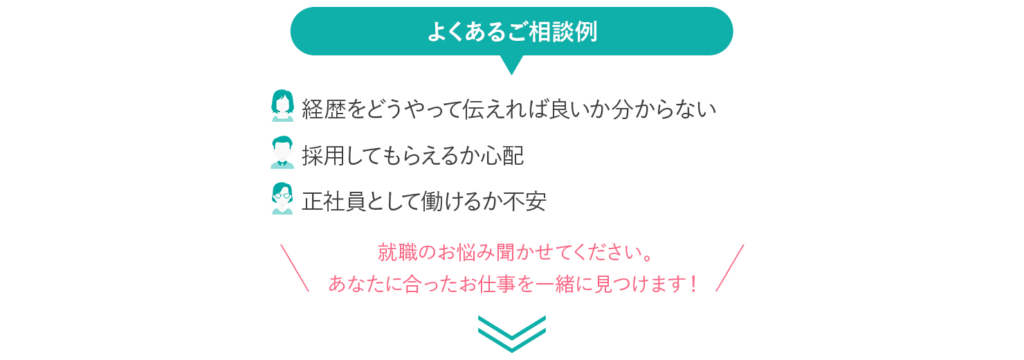



【高卒・大卒別】フリーターから公務員を目指すときのポイント

フリーターが公務員を目指す際のポイントについて、高卒、大卒のそれぞれに分けてご紹介します。
【高卒フリーター】公務員試験を目指す場合
高卒フリーターが公務員試験を目指す場合、以下のことを理解しておきましょう。
高卒フリーターでも公務員になることは可能
高卒で、その後フリーターとして生活をしてきた人であっても、公務員になることはできます。採用試験の高卒程度を要件としているものならば問題なく受験可能で、大卒程度とされているものであっても、学歴が不問であれば受験することもできます。
「高卒程度試験」がおすすめ
高卒でも大卒程度の大卒程度の試験を受けることはできます。しかし高卒程度よりも難易度が高いため、高卒であれば高卒程度の試験を受ける方が一般的でしょう。
国家公務員であれば、「国家公務員一般職高卒程度」の試験に合格すれば、一般的な事務職員として国家公務員になることができます。
専門職への応募も可能
高卒フリーターは、専門職になることも可能です。税務職員や刑務官、入国警備官、皇宮護衛官などの職種は、高卒でも受験することができます。
地方公務員の場合は、市役所職員として勤める一般事務の他、公立学校での学校事務などもあります。電気や機械、建築、土木といった技術職につくこともできます。
このほかにも、消防官や警察官、自衛官といった職種も、高卒で試験を受けることができます。
【大卒フリーター】公務員試験を目指す場合
大卒フリーターが公務員試験を目指す場合、以下のことを理解しておきましょう。
大卒程度の試験を受験するのが基本
大卒でフリーターとして生活をしてきた人は、大卒程度を要件にした試験を受験することになります。
上限年齢の問題で、高卒程度を要件とした試験は、一部の職種を除いて受けられない場合がほとんどとなるでしょう。
「キャリア組」になれる可能性も
国家公務員としては、試験に合格すればいわゆる「キャリア官僚」と呼ばれる国家公務員総合職になることができます。各省庁で将来の幹部を目指し、政策の企画・立案などを行います。総合職のみではなく、一般職の試験を受けることも可能です。
警察官の場合は、警察庁に勤める「キャリア組」と呼ばれる警察官になることができます。高卒程度などで地方公務員として警察官になった人たちはノンキャリア組と呼ばれ、代表的な働き方は交番など現場での勤務が主です。
キャリア組はデスクワーク的な業務が多く、将来的には警察組織の幹部を目指します。警視総監などの立場の人は、基本的にキャリア組の警察官が就任しているようです。
地方上級公務員や教師も目指せる
地方公務員としては、地方上級公務員になることができます。職種は一般事務など高卒程度の職種と共通していますが、上級試験で採用された場合は各自治体の将来の幹部候補として働くことになります。業務も上級の方が幅広い内容になることが多く、政策の立案などに関わることもあります。
また、高校などの公立学校の教師になることもできます。ただしこの場合は、大学や短大などで取得できる教員免許を取得している必要があります。
大卒のフリーターについて知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
フリーターから公務員への就職を成功させるポイント
フリーターから公務員を目指すのは決して不可能ではありませんが、いくつかの成功ポイントを押さえておくことが重要です。
計画を立てる
まず、フリーターから公務員になるには、確実な計画を立てることが求められます。公務員試験の年齢制限や試験日程を確認し、それに合わせたスケジュールを組み立てることが必要です。
自分に合う職種で応募する
次に、職種選びが成功のカギを握ります。国家公務員と地方公務員では仕事内容や求められるスキルが異なるため、自分に合った職種を見極めることが重要です。特に地方公務員として市役所職員や他の地域に密着した職種に関心がある場合は、自分が地域のためにどのように貢献できるかを考えるとよいでしょう。
勉強法を工夫する
また、効率的な勉強法を確立することも重要です。公務員試験は筆記試験と面接試験の二段階がありますので、それぞれの対策をバランス良く進める必要があります。予備校を利用するのも一つの方法ですし、独学であれば計画的に勉強スケジュールを組み立てることで集中力を維持することができます。
面接対策をする
そして、面接対策も欠かせません。フリーターとしての経験がどのように公務員の仕事に活かせるかを明確にすること、生活のためにフリーターをしていた理由をしっかりと説明できるよう準備することが必要です。これにより、自身の経験を強みに変換することができます。
早めに準備をする
最後に、安定した雇用や生活水準の向上といったメリットを頭に入れつつ、競争が激しい試験を突破するための覚悟を持って取り組むことが、フリーターから公務員への就職を成功させるためのポイントです。試験に向けての努力と継続が大切ですので、早め早めの準備を心がけましょう。
フリーターから公務員を目指すメリット
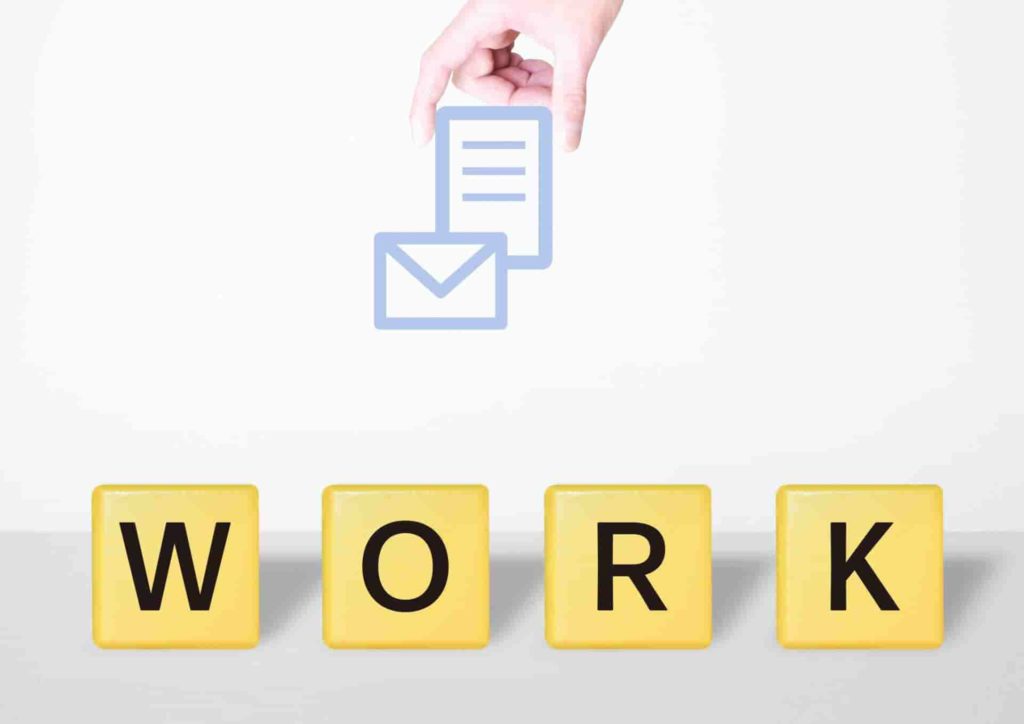
フリーターから公務員に就職すると、どんなメリットがあるのでしょうか。
- メリット1:定年までクビにならない
- メリット2:規則正しいスケジュールで働くことができる
- メリット3:福利厚生が充実している
主に上記3つのメリットが考えられます。順番に解説します。
メリット1:定年までクビにならない
民間企業は、収益が上げられなければ倒産するおそれがあります。安定を求めてフリーターから正社員として就職しても、世界情勢や時流の変化によっては失職するリスクはゼロにはなりません。これは、新型コロナウイルス感染拡大による社会的影響を目の当たりにした今、以前よりも実感できることではないでしょうか。
一方、公務員とは「国や地方公共団体などの職員として、広く国民に対し平等に働くことを活動目的とし、営利を目的とせず、人と社会のために幸せな生活の舞台をつくりだし支える仕事を担う職業」です。国や地方自治体のもとで働くので、一般企業のように倒産するというリスクはありません。「定年まで安定的に収入を得られる職に就きたい」と考える人に向いています。経済的・社会的に不安定なフリーターの立場を経験したからこそ、公務員の最大の魅力を実感できるとも言えるでしょう。
メリット2:規則正しいスケジュールで働くことができる
フリーターは、職場によってはシフト制で働く場合もあります。日中の勤務だけでなく、夜間の勤務もあるでしょう。
一方、公務員の勤務時間はある程度決まっています。一日8時間・完全週休二日制で、8時30分から17時までの7時間45分(昼休み45分)というのが一般的です。配属先や担当業務によっては残業もあり得ますが、基本的に一定の時間帯に働けるのは、心身の健康を保つ上で大切な要素ですから、人によってはそのことが大きなメリットとなる可能性があります。
メリット3:福利厚生が充実している
公務員の福利厚生は充実している傾向にあり、そこに魅力を感じて就職する人も多くいます。年間20日間の有給休暇や各種特別休暇が用意され、産前・産後の休暇はもちろん、育児休暇が確実に取得できます。育児休暇中も一定の所得が保証されます。さらに、保養所や宿泊施設などの福利厚生施設が充実しています。もちろん退職金も支給されます。福利厚生を重視したい方にとっては、メリットといえるでしょう。
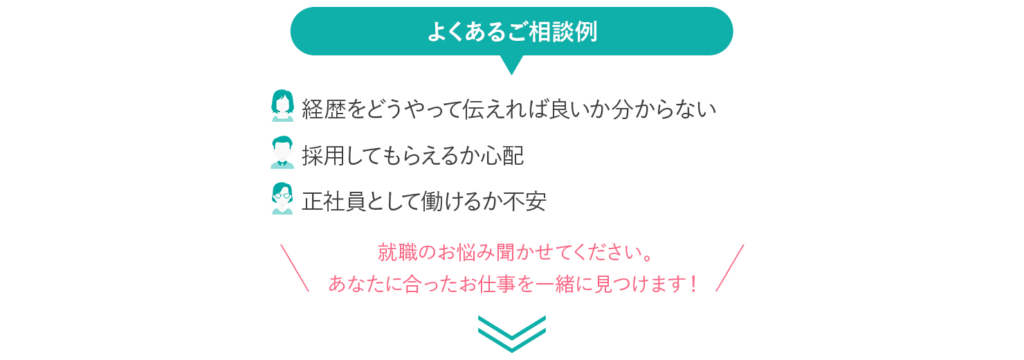



フリーターから公務員を目指すデメリット
公務員のメリットを見ると、収入の安定性や福利厚生の点に強みがあると考えられます。しかし、決して良いことばかりではありません。公務員として働く上でのデメリットを見ていきましょう。
- デメリット1:副業ができないことがある
- デメリット2:実力や業績が収入に直結しない
- デメリット3:仕事を退屈に感じる可能性もある
上記の3つが、主なデメリットにあげられます。あなたの意向と照らし合わせ、検討してみてください。
デメリット1:副業ができないことがある
原則として、公務員が副業することは法律で禁止されています。国家公務員は国家公務員法第103条と104条に、地方公務員だと地方公務員法第38条に明記されています。
一部、認められている場合(不動産賃貸業や農業など、条件を満たせば)もありますが、一般的なアルバイトや自営業は認められないケースがほとんどです。
一方、民間企業では副業を許可している会社も増えてきており、自分の趣味や特技を活かして副収入を得ることも可能な場合があります。本業と副業を両立することで、より高い収入を得たいと考えているフリーターの方には、デメリットになるおそれがあります。
デメリット2:実力や業績が収入に直結しない
公務員は年功序列制度が根強いという特徴があります。たとえば、年齢が上がるにつれて昇給していく等です。つまり、成果や業績を上げても、ダイレクトに給与に反映されることはありません。そのため「早くから成果を出して収入を上げたい」という人には向いていない可能性があります。
民間企業であれば、若いうちから成果次第で収入を増やすことも可能です。「就職したら、できるだけ早いうちに経験を積んで稼ぎたい」と考えている場合は、実績や成果が給与に反映される制度がある企業の方が向いているでしょう。
デメリット3:仕事を退屈に感じる可能性もある
公務員は、国や自治体の役に立っていることを実感できる仕事です。しかし、企画したり政策を練ったりする部署は別として、形式的な業務が多いのが特徴です。安定していることは悪くありませんが、淡々とルーチンワークをこなすだけでは物足りないと感じる人、仕事で創意工夫をしたい人には不向きかもしれません。フリーターをしている時にルーチンワークが苦痛だった人は、公務員が向いているとはいい難いでしょう。
まとめ
公務員試験に合格すれば、フリーターから公務員になることができます。安定した雇用や充実した福利厚生は、公務員になることの何よりの魅力です。好況、不況に左右されず定年まで働くことができるという安心感は、フリーターの不安定な生活とは大きく異なります。
しかし、公務員を目指す人は多く、簡単な試験ではありません。自分の目指す公務員試験の内容を確認し、しっかりと勉強を重ねた上で試験に臨んでください。
また、公務員のメリット・デメリットを参照して「自分は公務員に向いていないかも…」と感じた方は、民間企業への就職を目指してみましょう。私たちジェイックは、20代のフリーターや既卒者の方の正社員就職に強みを持つエージェントです。就職活動をどう進めていいか分からない人は、ぜひお気軽にご相談ください。
フリーターから公務員を目指す人によくある質問
可能です。公務員になるためには筆記試験と面接に合格する必要がありますが、逆に言えばその2つを合格できれば誰でも公務員になることが出来ます。もちろんそれらは簡単なことではありませんので、試験概要をしっかりと確認して対策していきましょう。
やはり、フリーターではない方が面接での印象もよいでしょう。ただし、明確な意思や理由があってフリータを続けており、それらを面接で上手に伝えることが出来れば、不利に働くことはないでしょう。もし、民間も同時並行で進めたい場合には、フリーター・未経験の就職に強いジェイックを頼ってください。
フリーターから公務員を目指す場合は、まず自分がどのレベルの試験を受ける必要があるのかをしっかり確認しましょう。この記事では学歴別の攻略ポイントを紹介していますので、参考にしてみてください。
あらかじめ浪人する期間を決めてしまいましょう。「3年以内に公務員になれなければ民間に切り替える」などの期限を決めなければフリーター期間が長引いてしまい、民間就職もできなくなってしまいます。もうすでに数年間 浪人をしているのであれば、思い切って民間就職に切り替える勇気も必要です。ジェイックは公務員志望フリーターの相談実績も多数ありますので、不安な方はお気軽にご相談ください。



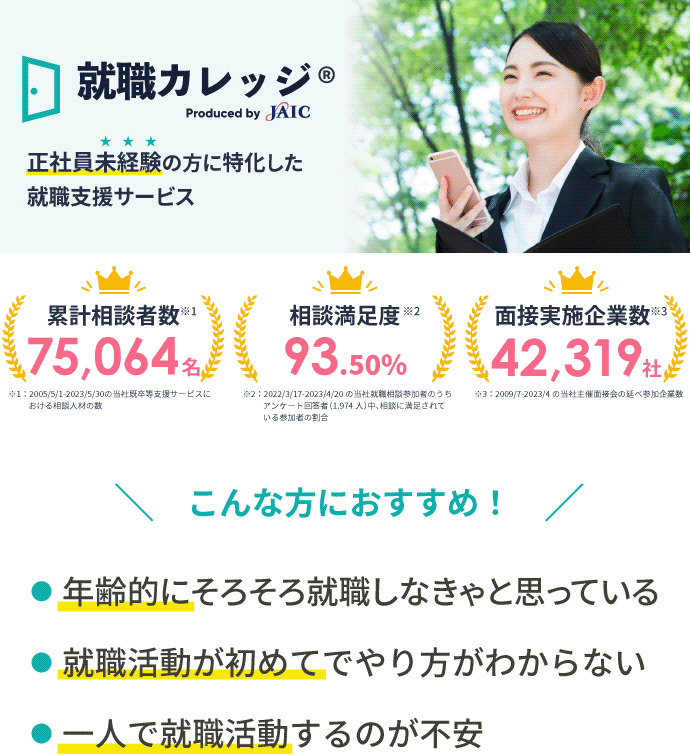

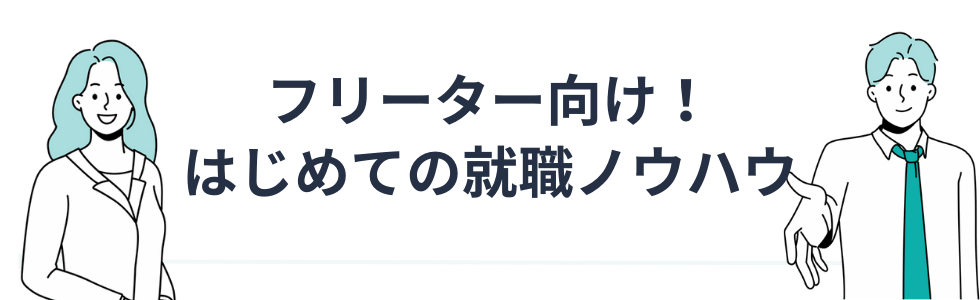
当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。