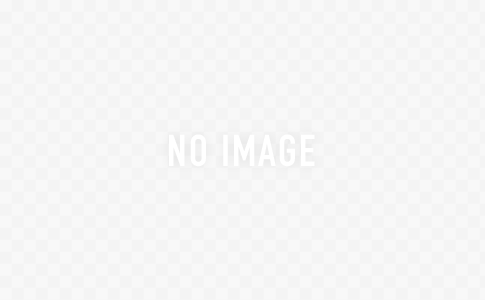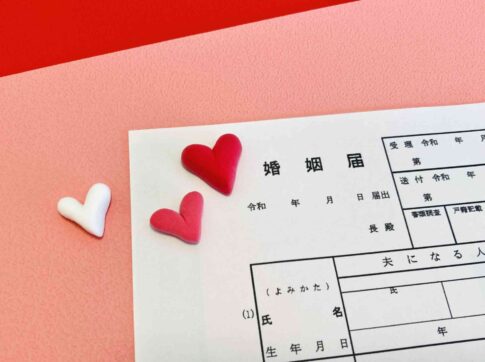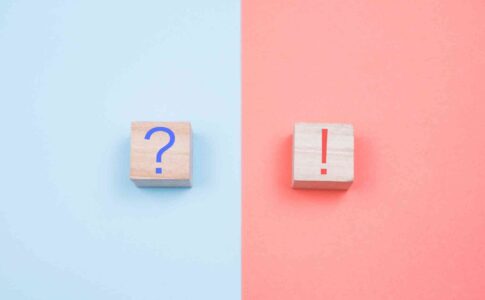就職したいと考えるフリーターやニートの方でも、正社員への就職は十分に可能です。
実際に約7割のフリーター、約2割のニートが正社員として就職を実現しています。
フリーターやニートから就職するには、自己分析や企業研究で方向性を見極め、挑戦しやすい職種から始めるのがコツです。また、ハローワークや就職エージェントなどの支援サービスを活用すれば、一人で悩まずに就職活動を進められます。
この記事では、学歴別の就職率や挑戦しやすい仕事、就活の進め方など、就職を目指すうえで役立つ情報を紹介します。
「就職したいけれど自分にできるか不安」「何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
就職したいけれどできる?
就職したいと考えるフリーターやニートの方は、正社員就職が可能です。
フリーターからの正社員就職は約7割、ニートからの就職も約2割が実現しています。高卒者の就職内定率も77.3%、大卒者は約9割と高い水準です。
学歴によって就職のしやすさは異なりますが、自己分析や企業研究をしっかり行い、適切な就職支援サービスを活用することで、誰にでもチャンスはあります。
大切なのは、一歩踏み出す勇気と、諦めずに努力を続けることです。
まずは、自分の状況を把握し、できることから始めてみましょう。
ここでは、フリーターやニート、学歴別の就職率を紹介しますので、進路選びの参考にしてください。
1. フリーターから正社員就職した割合は約7割
フリーターから正社員になった人の割合は約7割です。
以下の表は、フリーターから正社員就職を希望した人のうち、実際に正社員になれた人の割合を示しています。
| 性別 | 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2016年(25-29歳) | 2021年(25-29歳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2016年(25-29歳) | 2021年(25-29歳) |
| 男性 | 76% | 68.8% | 65.7% | 61.9% | 66.7% |
| 女性 | 51% | 63.8% | 62.4% | 40.8% | 61.2% |
参考:(独)労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No.213」
2001年以降、男女ともに数字は少し下がっていますが、約7割が正社員就職に成功しています。つまり、非正規やフリーターからでも、就職の可能性は十分にあるといえるでしょう。
2. ニートから正社員就職した割合は約2割
ニート状態から正社員として就職した人は約2割です。
以下に、1年前ニートだった方が現在どのような就業状況にあるかを表にまとめました。
| 年齢(性別) | 正社員 | パート・アルバイト | 派遣社員 | 契約・嘱託社員 |
|---|---|---|---|---|
| 15~34歳(男女) | 18.0% | 10.5% | 3.4% | 5.2% |
| 15~34歳(男性) | 18.3% | 8.5% | 2.6% | 4.4% |
| 15~34歳(女性) | 17.4% | 13.6% | 4.7% | 6.5% |
参考:(独)労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③平成29年版「就業構造基本調査」より」
このデータから、1年前にニートなど無業状態だった15~34歳の方々のうち、約18%が正社員として就職していることがわかります。
一方で、1年後に就職活動を行っているニートの方も約18%だったため、時間をかけて丁寧に就職活動を進めるのが成功への近道といえるでしょう。
3. 高卒の就職内定率は77.3%
文部科学省によると、令和7年3月に高校卒業予定の就職希望者の就職内定率は77.3%でした。
このことから、就職したいと希望する高卒の多くが内定を獲得し、就職出来ていることが分かります。
| 卒業予定者 | 940,036人 |
| 就職希望者 | 128,349人 |
| うち就職内定者 | 99,218人 |
| うち未内定者 | 29,131人 |
参考:文部科学省「令和7年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(令和6年10月末現在)に関する調査について」
4. 大学卒業後に就職した割合は約9割
大学卒業後の就職率は約9割と、非常に高い水準です。
以下の表は、大学と短期大学の就職率を一覧にしたものです。(令和5年度大学等卒業者)
| 区分 | 就職率 |
|---|---|
| 国公立大学 | 98.5% |
| 私立大学 | 97.9% |
| 短期大学 | 97.4% |
参考:文部科学省「令和5年度大学等卒業者の就職状況調査(4月1日現在)」
大学卒業者の就職率は非常に高く、4年制大学も短期大学も卒業後はほぼ全員が就職していると分かります。
就職に向けて行動している学生の割合が多いため「自分も正社員になれるよう努力しよう」と思える環境と言えるでしょう。
就職活動における7つの流れ
就職活動は、「自己分析 → 企業研究 → 求人探し → 書類準備 → 応募 → 面接対策 → 内定獲得」という流れで行います。
就職活動には基本的な流れがあるため「何から始めればいいのかわからない」と不安を感じている人も、このステップに沿って進めていけば落ち着いて取り組めるはずです。
就職活動にかかる期間は、個人差はありますが1ヶ月~3ヶ月程度かかるのが一般的です。
これらの流れでスケジュールを組んでみてください。
1. 自己分析をする
就職したいと思ったら、まず自己分析を行いましょう。
自己分析とは「自分がどんな人間か」「何を大切にしたいか」「どんな働き方が合っているか」などを整理することです。
自己分析が必要な理由は以下のとおりです。
- 自分に合った仕事や業界を選びやすくなる
- 面接や書類で自分の強みをわかりやすく伝えられる
- 就職後のミスマッチを防ぎやすくなる
具体的な自己分析の方法としては、まず過去の経験や自分の性格を振り返ってメモを取ってみましょう。
それに加えて、自己分析ツールや適職診断を活用したり、家族や友人に自分の印象を聞いてみたりするのも有効です。
2. 企業研究を進める
自己分析が終わったら、次は企業研究を進めましょう。
企業研究では気になる企業について情報を集め、自分に合いそうかを見極めていきます。
仕事内容や企業文化、福利厚生などを把握しておくと、応募時や面接時にも役立つはずです。
企業研究をする理由は以下の通りです。
- 自分に合った会社かどうかを判断しやすくなる
- 志望動機に説得力が出る
- 面接での質問に自信をもって答えられる
企業研究では企業理念や事業内容を確認し、その会社がどんな方針で事業を展開しているのかを理解しておきましょう。さらに、社風や実際に働く人の声(口コミ)もチェックして、会社の雰囲気や働きやすさをイメージするのもおすすめです。
3. 求人をチェックする
企業研究が終わったら、次は具体的な求人情報を集めてみましょう。
求人を探すには、主に以下のような方法があります。
- ハローワークに相談する
- 転職・求人サイトに登録する
- 就職エージェントに相談する
- 企業の公式サイトの採用ページを見る
ハローワークには地元企業や未経験者向けの求人が多く掲載されています。
求人サイトでは、業界・職種を問わず多種多様な求人を検索でき、自分のペースで仕事を探しやすいのが特徴です。
それぞれの方法には特徴や得意分野があるので、うまく使い分けましょう。
4. 応募書類を準備する
求人をチェックして応募する企業が決まったら、次は応募書類の準備に進みます。
応募には、一般的に以下の書類が必要です。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 履歴書 | 学歴・職歴・自己PR・志望動機などを記入 |
| 職務経歴書 | これまでの仕事内容・実績・スキルを具体的に記載 |
応募書類を作成するときは、まず誤字や脱字がないように丁寧に見直すことが基本です。
自分の強みや意欲がしっかり伝わるように内容を工夫し、志望する企業に合わせて書き方を調整すると、より好印象につながります。
なお、履歴書や職務経歴書の詳しい書き方は「フリーターの履歴書の書き方!アルバイトの職歴・志望動機を例文付きで解説」「フリーターの職務経歴書の書き方【見本・チェックリストあり】」で解説していますので、参考にしてください。
5. 求人に応募する
求人を見つけたら応募手続きを行いましょう。
Web応募・メール応募・郵送など、企業によって応募方法が異なります。
応募が完了したら、企業からの連絡を見逃さないように、メールや電話をこまめにチェックしましょう。面接日程の調整や、追加書類の提出依頼などが来る場合もあります。
連絡があった際には、できるだけ早く丁寧に対応しましょう。
スムーズなやりとりができると、ビジネスマナーや社会人としての基本姿勢が伝わり、好印象につながります。
6. 面接対策を行う
応募が終わったら、次は面接に備えましょう。
面接は自分の人柄や意欲を直接伝える大切な場です。事前の準備が合否を左右します。
面接対策でやるべきことは以下のとおりです。
- よく聞かれる質問を想定して答えを準備する
- 自己紹介や志望動機を言えるように練習しておく
- 面接マナー(服装・言葉づかい・入退室の作法など)を確認する
こうしたポイントを事前に押さえておけば、本番でも落ち着いて自分らしさを伝えやすくなります。
なお、面接で何を聞かれるか知りたい方は「面接で聞かれること-よくある質問と回答例を紹介!企業の意図は?」もご覧ください。
7. 内定を獲得する
面接を通過すると、いよいよ企業から内定の連絡が届きます。
内定通知を受けたら、まずは就職の意思をしっかりと伝えましょう。
その後は、必要書類の提出や健康診断の受診といった具体的な手続きが始まります。
企業によっては入社前にオリエンテーションや研修があるため、案内が届いたら内容を確認し、日程を調整しておきましょう。引っ越しや通勤手段の確認など、生活面の準備が必要になる場合もあります。
入社に向けた準備を早めに整えておけば、気持ちにも余裕が生まれ、安心して新しい環境へ踏み出せるはずです。
就職したい人が就活に向けてまず行う5つのこと
就職活動を始める前に、まずは生活や気持ちの準備を整えることが大切です。
就職に向けた行動は、自己分析や生活リズムの改善など、今すぐできることから始めます。
気持ちが前向きになり、スムーズに就活へ入れるようになるため、以下の5つのステップを実践してみてください。
- 就活の目的をはっきりさせる
- 生活リズムを整える
- 清潔感のある見た目に整える
- 就活の不安点をノートに書きだす
- できそうな仕事から始める
1. 就活の目的をはっきりさせる
就活を始める前に「何のために就職したいのか」をはっきりさせましょう。
目的が明確になっていれば、自分に合った仕事や応募先を選びやすくなり、就活の軸がぶれません。また、面接でも自分の気持ちをしっかり伝えられるはずです。
例えば「生活費を安定させたい」「正社員としてスキルを身につけたい」「社会とのつながりがほしい」など、人によって理由はさまざまです。
まずは紙に書き出すなどして、自分の気持ちを整理するところから始めてみましょう。
2. 生活リズムを整える
就職したい人が就職活動を始めるには、まず生活リズムを整えることが欠かせません。
夜型の生活をしていると、面接や職場見学の時間に間に合わなかったり、体調が安定せず集中力が落ちたりするからです。
生活リズムを整えるためのポイントは、以下のとおりです。
- 朝は決まった時間に起き、日光を浴びる
- 起床後1時間以内に朝食をとる
- 夜はスマホ・PCを寝る直前まで使わない
- 寝る2時間前までに入浴を済ませる
- 決まった時間に就寝する
参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」
これらを意識するだけでも、体調や気分が安定し、就活への意欲も高まりやすくなります。
逆に不規則な生活が続くと、体調不良や集中力の低下につながり、チャンスを逃しかねません。
3. 清潔感のある見た目に整える
就職したい人は就活に向けて、清潔感のある見た目に整えましょう。
就活では第一印象がとても大事です。特にフリーターやニートからの就職活動では、第一印象で「きちんとした人かどうか」を判断される場合もあります。
清潔感を保つために心がけたい行動は、以下のとおりです。
- 髪はきちんと整える(長い場合はまとめる)
- ヒゲや爪をこまめに手入れする
- 洋服はしわや汚れのないものを選ぶ
- 靴やカバンも清潔にしておく
- 香水ではなく、無臭や石けんの香りを意識する
見た目に気を配らないと「やる気がない」と思われがちです。しかし、経験が浅くても、礼儀や立ち居振る舞いで信頼を得るチャンスはあります。
4. 就活の不安点をノートに書きだす
就職したい人が就活に向けてまず取り組みたいのが、不安な気持ちをノートに書き出す作業です。
心配事を視覚化すれば「何に不安を感じているのか」「どうすれば解消できるのか」を整理しやすくなります。
就活を始めると「面接でうまく話せるかな」「職場にうまくなじめるかな」など、いろんな不安が出てきます。不安をそのままにしておくと、就職活動が進まず、せっかくのチャンスを逃しかねません。
不安が整理できれば、今の自分に必要な準備や対策が見えてくるはずです。
5. できそうな仕事から始める
就職したいと思いつつも自分に合う仕事がわからない場合は、まずは「できそう」と思える仕事から挑戦してみるのがおすすめです。
ハードルの低い仕事から始めれば一歩を踏み出しやすく、行動できないまま時間が経ってしまうリスクを減らせます。
さらに、経験を積む中で自信もつき、次のステップへ進む力が自然と身についていくでしょう。失敗を恐れずに、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。
実際に働き始めると「この業界は自分に合いそう」「次はもっと〇〇の仕事に挑戦したい」といった気づきが生まれ、進みたい方向が見えてくる場合もあります。
就職したい人が挑戦しやすい仕事5選
就職したいと思ったときは、まず「挑戦しやすい仕事」から始めるのがおすすめです。
経験や資格がなくても始めやすい職種を選ぶことで、就職への一歩がぐっと近づきます。
最初から難しい仕事を選んでしまうと、気持ちが追いつかず途中で挫折してしまう可能性もあります。
ここでは、未経験から始めやすく、正社員も目指せる仕事を5つ厳選してご紹介します。
仕事内容や向いている人の特徴なども合わせて解説するので、自分に合った選択肢を見つけるヒントにしてください。
販売職[就職したい人が挑戦しやすい仕事 1/5]
販売職は特別な経験や資格がなくても始めやすいため、就職したい人にとって挑戦しやすい仕事です。仕事内容は、店頭での接客やレジ業務、商品の陳列、在庫管理などがあります。
アパレルや雑貨、家電量販店など、幅広いジャンルで募集があり、自分の興味に合った職場を選びやすいのも魅力です。
働くうちに、あいさつや言葉遣い、商品説明のコツなどが自然と身につき、社会経験の少ない人でも一歩ずつ成長できます。
人と接する機会が多いため、接客を通じて人と関わる経験を積みたい人におすすめです。
| 平均年収 | 361万円 |
| 必要なスキル | 基本的なあいさつや言葉遣い商品を分かりやすく説明する力周囲と協力して働く姿勢丁寧な接客対応 |
| 向いている人 | 人と話すのが好きな人明るく前向きに対応できる人身だしなみに気を配れる人人と関わる仕事に興味がある人 |
| 就職するための方法 | アルバイトから始めて経験を積む求人サイトやハローワークで探す接客未経験OKの募集に応募する履歴書で「人と接するのが好き」など強みをアピールする |
飲食店の店員[就職したい人が挑戦しやすい仕事 2/5]
飲食店の店員は未経験からでも始めやすい仕事内容が多いため、就職したい人が挑戦しやすい仕事です。
主な業務は、注文の受付や料理の提供片付けなどで、特別な資格や経験がなくても働ける職場が多くあります。
接客で学べる話し方や礼儀は、就職活動や実際の仕事でも活かせるでしょう。さらに、シフト制で働き方の融通がききやすいため、短時間からのスタートも可能です。
アルバイトから正社員を目指せる職場もあり、ステップアップを目指しながら社会経験を積みたい人にぴったりの仕事です。
| 平均年収 | 327.9万円 |
| 必要なスキル | 基本的なあいさつや丁寧な言葉遣い周囲への気配りや丁寧な対応体力や立ち仕事への慣れ |
| 向いている人 | 人と接するのが好きな人明るく前向きな対応ができる人チームで協力して働ける人まずは働くことに慣れたい人 |
| 就職するための方法 | アルバイト情報サイトで近くの店舗を探すハローワークで飲食業の求人を紹介してもらう知人の紹介や店舗の張り紙をチェックする |
営業職[就職したい人が挑戦しやすい仕事 3/5]
営業職は、学歴や職歴に自信がなくても「人柄」や「やる気」で評価されやすく、就職したい人にとって挑戦しやすい仕事です。
企業や個人に商品やサービスを提案し、新規顧客の開拓や既存顧客のフォローなどを通じて会社の売上に貢献します。
営業職には外回りやオンラインツールを活用した営業などさまざまなスタイルがあり、自分に合った働き方を選びやすいのが特徴です。
研修制度が整っている企業も多く、基礎からスキルを学べます。成果が評価に直結するため、努力が収入や役職に反映されやすいのも魅力です。
人と関わる仕事を通じて成長したい方、自分の力でキャリアを切り開きたい方に向いています。
| 平均年収 | 579.5万円 |
| 必要なスキル | 元気のいいあいさつや礼儀正しい対応相手の話をよく聞く力(傾聴力)商品やサービスをわかりやすく伝える力基本的なビジネスマナー |
| 向いている人 | 人と話すのが苦ではない人前向きにチャレンジできる人成果を目に見える形で得たい人学ぶ意欲がある人 |
| 就職するための方法 | 未経験OKの営業職求人に応募就職支援サービス(ハローワーク、エージェント)を活用 |
工場作業員[就職したい人が挑戦しやすい仕事 4/5]
工場作業員は、経験や特別なスキルがなくても始められる求人が多く、就職したい人にとって挑戦しやすい仕事です。
主に製品の組み立て・加工・検品などを担当します。担当工程ごとに業務が分かれているため、マニュアルに沿って黙々と進める作業が中心です。
また、工場作業員は製造業や食品工場、自動車関連など、さまざまな分野で募集があります。
シフト勤務や夜勤、交代制など働き方を選べる職場も多く、自分の生活リズムに合わせやすいのも魅力です。
体を動かす仕事が好きな人や、決まった流れで作業することが得意な人にも向いています。
| 平均年収 | 340.1万円 |
| 必要なスキル | マニュアルに沿って作業する力集中力や丁寧さ体力時間を守る習慣 |
| 向いている人 | コツコツと作業に取り組むのが得意な人人と話すより、黙々と働きたい人体を動かすことが苦にならない人ルールや手順を守れる人 |
| 就職するための方法 | 未経験OKの工場求人に応募派遣会社や製造業専門の求人サイトを活用ハローワークで紹介してもらう面接で「真面目に働きたい意欲」を伝える |
介護スタッフ[就職したい人が挑戦しやすい仕事 5/5]
介護職は常に人手不足の業界で、未経験者歓迎の求人が多いため、就職したい人がチャレンジしやすい仕事です。
主な仕事内容は、高齢者や身体が不自由な方の日常生活のサポートで、食事や入浴、排せつの介助などを行います。
介護職はシフト制が多く、早番・遅番・夜勤などライフスタイルに合わせた働き方を実現できるのが特徴です。また、経験を積めば資格取得やキャリアアップも目指せます。体力が必要な場面もありますが、その分やりがいを感じられる仕事です。
人の役に立つ場面が多く「誰かの力になれている」と実感しながら働けるでしょう。
| 平均年収 | 371.4万円 |
| 必要なスキル | 人への思いやりや気配り相手の立場で考える力体力や継続力基本的なコミュニケーション能力 |
| 向いている人 | 人の役に立ちたいと思っている人誰かを支えることにやりがいを感じる人感謝される仕事がしたい人こつこつ真面目に取り組める人 |
| 就職するための方法 | 未経験歓迎の施設に応募するハローワークや福祉人材センターを活用する働きながら資格取得を目指せる職場を選ぶ |
就職したい人が就活で気を付ける6つのポイント
就職したい人が就活を始めるときに、気を付けておきたいポイントを6つ紹介します。
意識せずに進めてしまうと、自分に合わない職場を選んでしまい、すぐに辞める結果になるかもしれません。
ぜひ以下の内容を参考にしてください。
1. どこでもいいから就職したいと思わない
就活で気を付けるポイントの一つは、どこでもいいから就職したいと思わないことです。
焦って選んだ仕事が自分に合わず、早期離職につながるケースも少なくありません。
どこでもいいと思ってしまうと起こりやすいリスクは、以下のとおりです。
- 興味や適性のない仕事に就いたことにより、長く続けられない
- ブラック企業に入ってしまい、心身をすり減らす
- 短期間で辞めてしまい、次の就活にも影響する
まずは「なぜ働きたいのか」「どんな働き方をしたいのか」といった希望を紙に書き出して整理してみましょう。そのうえで、複数の求人を見比べながら、自分に合いそうな職場をじっくり選ぶ姿勢が大切です。
2. 求人のキャッチコピーを信じすぎない
就職したい人が就活で気を付けるポイントは、求人のキャッチコピーを信じすぎないことです。求人票のキャッチコピーには魅力的な言葉が並びますが、実際の業務内容や働き方と違うケースも多くあります。
信じすぎないほうが良いキャッチコピーの例は、以下のとおりです。
- アットホームな職場です
- 未経験大歓迎!
- 若手が活躍中!
- やりがいのある仕事です
例えば「アットホーム」と書かれていても実際には人間関係が閉鎖的だったり「未経験歓迎」と言いつつ実際は即戦力を求められたりするケースもあります。
求人のキャッチコピーだけで判断せず、仕事内容や勤務時間、離職率などの詳細にも目を向けるようにしましょう。
3. 休みや年収だけで求人を選ばない
就職したい人が就活で気を付けるポイントは、休みや年収だけで求人を選ばないことです。
条件の良さだけで応募すると、仕事内容や職場の雰囲気が合わず長く働けないケースが多く見られます。過酷な勤務環境や人間関係のトラブルが原因で、結果的に早期離職してしまうケースもあるため注意が必要です。
求人を選ぶ際には、働き方や仕事内容と条件のバランスを見ながら検討するようにしましょう。実際に働いている人の声や口コミを参考にすれば、職場の実情をより具体的にイメージできます。
4. 書類や面接マナーに気を配る
就職したい人が就活で気を付けるポイントは、書類や面接マナーに気を配ることです。
書類や面接のマナーを丁寧に守れば、社会人としての誠実さや常識が伝わります。
スキルや経験が少なくても、丁寧な対応や礼儀正しい言動によって、信頼感や前向きな印象を与えられるでしょう。
書類作成と面接時のマナーは、以下のとおりです。
| 書類のマナー | 面接のマナー |
|---|---|
| 誤字脱字をチェックする | あいさつや礼を丁寧に行う |
| 丁寧な字で読みやすく書く | 質問には落ち着いてはっきり答える |
| 内容が簡潔でわかりやすいか確認する | 目線や姿勢にも注意を払う |
| 最新の情報を書く | 面接後はお礼の言葉を忘れない |
就活では、こうした基本的なマナーが第一印象を大きく左右するため、丁寧に対応する意識を持ちましょう。
5. 過去よりも未来の取り組み方について伝える
就職したい人が就活で気を付けるポイントは、過去よりも未来の取り組み方について伝えることです。これまでの経歴よりも「これからどう働きたいか」といった前向きな姿勢が、企業側の評価に影響する可能性があるからです。
フリーターとして働いていた場合は、次のように伝えると前向きな印象を与えられる傾向にあります。
フリーターとして働いていましたが、正社員として安定した働き方を目指したいと考えるようになり、就職を希望しています。
なお、前向きに伝えるポイントは以下のとおりです。
- 過去の経験から得た学びを簡潔に整理する
- 今後の目標や意欲を具体的に伝える
- 「変わろうとしている姿勢」が伝わるよう意識する
自分のこれからの働き方や成長の方向性を、前向きな言葉で伝えましょう。
6. 一人で就活を乗り越えようと思いすぎない
就職したい人が就活で気をつけるべきポイントは、一人で就活を乗り越えようと思いすぎないことです。「誰にも頼らずに頑張らないと」と思い込むと、行き詰まりやすくなります。
一人で抱え込むと起こりやすいリスクは、以下のとおりです。
- 不安や焦りが強くなり、モチベーションが下がる
- 客観的なアドバイスが得られず、視野が狭くなる
- 書類や面接での改善点に気づきにくい
こうした状態を防ぐためにも、ハローワークや就労支援機関を活用したり、家族や友人など信頼できる人に相談したりしてみましょう。
就職したい人が利用できる4つの就職支援サービス
就職したい人には就職支援サービスの利用がおすすめです。
就活に不安を感じている方は、どんなサービスが自分に合っているのか分からず、迷うかもしれません。
ここでは、それぞれのサービスの特徴や使い方をわかりやすく解説します。
自分に合いそうなサービスがあるか、参考にしてみてください。
1. ハローワーク
ハローワークは厚生労働省が運営する公共職業安定所です。
求職者であれば誰でも無料で利用でき、求人紹介のほか、職業相談や職業訓練などが行われています。(参考:厚生労働省「ハローワークの相談支援」)
利用する主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 全国に窓口があり、利用しやすい公共機関なので安心感がある職業訓練を通じてスキルアップが図れる | 窓口や相談員によって対応に差がある労働条件の良くない求人を紹介される場合がある |
なお、職業訓練(ハロートレーニング)では、就職や転職に役立つ知識や技能を学べます。
主にハローワークを通じて紹介・申込が可能です。
また、35歳未満の若者を対象とした「わかものハローワーク」では、担当制のキャリア支援が受けられるなど、若年層に特化したサポートも充実しています。(厚生労働省:「わかものハローワーク」)
2. ジョブカフェ
ジョブカフェは就職に関するさまざまな支援を無料で提供している施設です。
2025年4月時点では46の都道府県にジョブカフェが設置されており、全国の多くの地域で利用できます。(参考:厚生労働省「ジョブカフェにおける支援」)
利用する主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 若者に特化しており相談しやすい就活初心者でも安心して利用できる職場体験やセミナーで就職にまつわる知識を増やせる | 求人紹介の機能が弱い場合がある(ハローワークとの併用が必要)地域によってサービス内容に差がある |
ジョブカフェは若者向けの支援や体験型プログラムが充実しており、求人紹介を中心とするハローワークとは異なる印象を持ちます。ただ、一部地域ではハローワークと連携・併設しているため、状況に応じて両方のサービスの活用が可能です。
3.地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーションは、15歳から49歳までの若者を対象に、就職に向けたステップを段階的に支援する厚生労働省委託の公的機関です。
仕事への不安やブランクがある人でも安心して利用でき、就職活動に必要な土台を整えるところから始められます。
主な支援内容は以下のとおりです。
- マナーやコミュニケーション講座
- 合宿形式の集中訓練プログラム
- ジョブトレ(就業体験)
参考:地域若者サポートステーション「主な支援内容」
また、主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 働く準備を整えてから就職活動に臨める就職活動の苦手・不安を減らせる | 求人紹介は行っていない支援内容や頻度は地域によって異なる |
生活リズムや人間関係に不安がある場合も、少しずつ準備を進められるので安心です。
4. 就職エージェント
就職エージェントは、民間企業が運営する無料の就職支援サービスです。
専任のキャリアアドバイザーがつき、マンツーマンで就職活動全般をサポートしてくれます。
正社員を目指す人や、自分に合った求人を効率よく探したい人に向いています。
主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| マンツーマンでの丁寧なサポートが受けられる非公開求人に出会える可能性がある入社までの手続きも代行・サポートしてくれる | 希望と合わない求人紹介を受ける場合があるアドバイザーと相性が合わない可能性がある |
なお、ハローワークが公的機関で幅広い層に対応しているのに対し、就職エージェントは主に正社員希望者向けで、より個別対応に特化しています。
就職したい時によくある質問3選
就職したい時によくある質問を、3つピックアップして紹介します。
迷ったときの参考にしてみてください。
高卒で就職するにはどうしたらいい?
高卒で就職する主な方法は以下のとおりです。
- ハローワークを利用する
- 就職エージェントを活用する
- ジョブカフェやサポステを活用する
- 職業訓練校でスキルを身につける
これらのサービスは高卒の方でも気軽に利用できるのが特徴です。
履歴書の書き方や面接対策、就職への不安や悩みの相談まで、専門スタッフが丁寧にサポートしてくれます。
自分のペースや今の状況に合わせて、まずは一歩踏み出せそうな方法から試してみましょう。
早く就職したい大学生はどうしたらいい?
「早く就職したい」と思っても、まずは大学卒業を目指すのがおすすめです。
中退すると最終学歴が高卒となり、大卒向けの求人に応募できず、選べる職種や企業の幅が狭まります。
高卒向けの求人は大卒向けの求人と比較すると待遇や初任給で不利になりやすく、就職後のキャリアにも影響が出やすくなるでしょう。
以下の表は、学歴別の求人総数をまとめたものです。(2025年3月卒業予定者が対象)
| 学歴 | 求人数 |
|---|---|
| 高卒 | 約48万2,000人 |
| 大卒 | 約79万7,000人 |
参考:厚生労働省「令和6年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る 求人・求職・就職内定状況」取りまとめ(9月末現在)」
参考:リクルートワークス研究所「第41回ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」
大卒の方が求人数は圧倒的に多く、選べる企業や職種の選択肢も豊富です。
特に正社員登用やキャリアアップを目指す場合、大卒を条件とする企業が多いため、卒業しておくメリットは大きいといえるでしょう。
ニートが就職活動を始める時のやり方は?
ニートが就職活動を始める時のやり方は、以下のとおりです。
- 生活リズムを整える
- 自己分析を行う
- ハローワークなど支援機関に相談する
- 職業訓練や就職セミナーを活用する
- アルバイトや職場体験から始める
ニートから就職を目指す時はいきなり働き始めるのではなく、生活リズムを整えたり、自分の得意なことを整理したりするなど、準備から始めるのがポイントです。
まずはアルバイトや職場体験など、無理のない方法から「働くこと」に慣れていきましょう。
まとめ
「就職したいけれど自分にできるか不安」というフリーターやニートの方でも、正社員への就職は十分可能です。実際、フリーターから正社員就職を実現した割合は約7割、ニートから正社員になった割合は約2割もいるとわかりました。
ただ、学歴によって就職のしやすさには差があるため、まずは自分の立場や状況をきちんと把握しておくことが大切です。
なお、就職活動では自己分析や企業研究など、基本の流れに沿って進めるとスムーズです。
さらに、ハローワークやジョブカフェなどの支援サービスを活用すれば、就職への不安を減らしながら前に進めるでしょう。
まずは自分の状況に合ったやり方で、できることから始めてみてください。

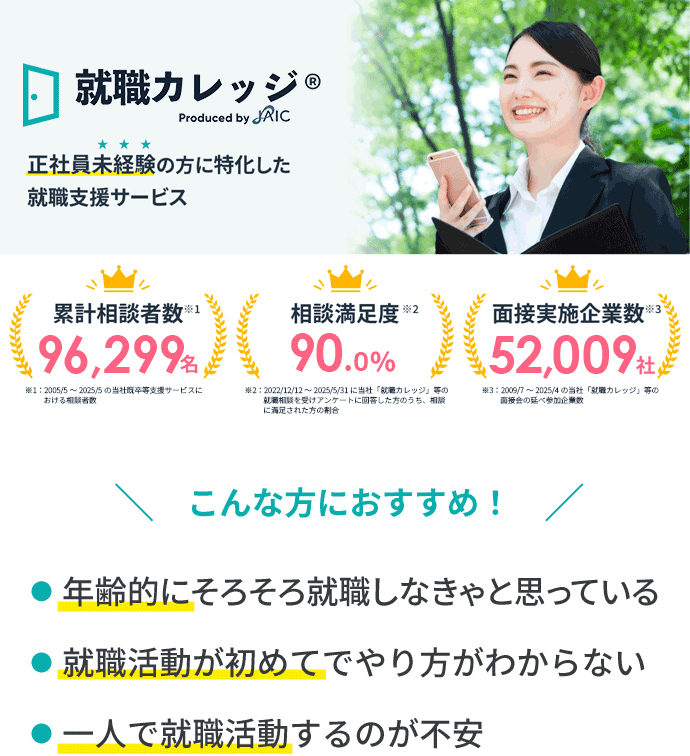

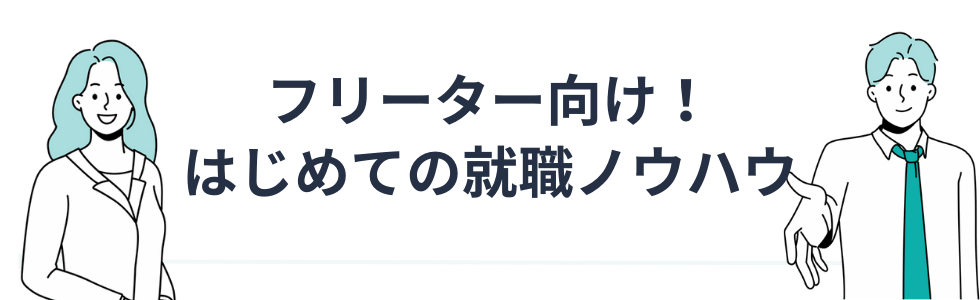
当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。