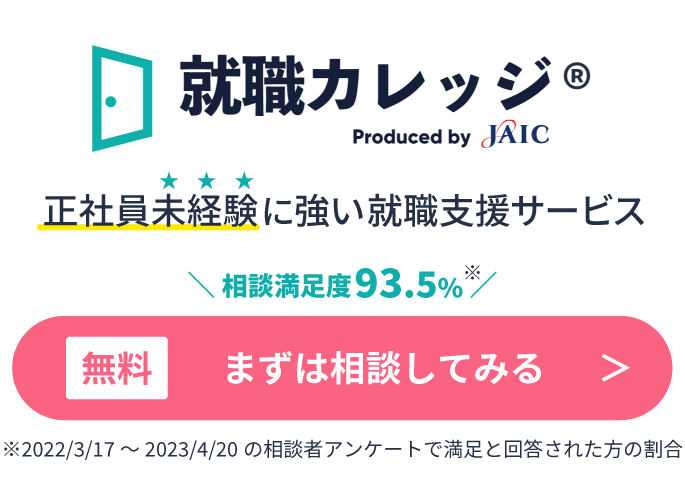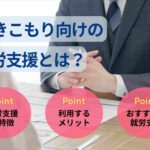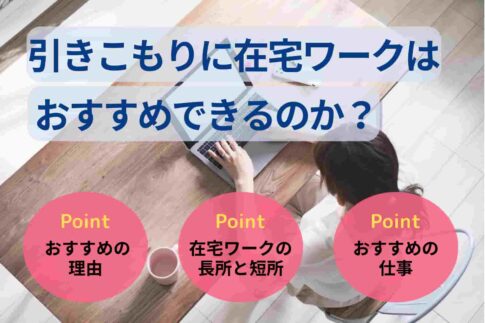引きこもりに関して相談したいのであれば、法人によって運営されている引きこもり支援団体、精神保健福祉センターなど、いくつかの相談先があります。
引きこもりのご本人やご家族にとっては、相談することで、心が軽くなったり、希望がもてるようになる可能性もありおすすめです。
この記事では、相談するメリットとデメリット、相談した方の体験談、さらに、おすすめの相談先や相談時の注意点を詳しく解説します。
ぜひ、悩んだ時にはこの記事を参考にしてみてください。
- 引きこもりについて相談すると、不安の解消、悩みの明確化、別の視点やヒントが得られるなどのメリットがある
- 心が病んだり社会から完全に孤立してしまう前に、適切な人に相談しよう!
- 引きこもりに関する相談先として、各都道府県の「引きこもり支援団体」や「精神保健福祉センター」などもおすすめ
- 東京都ひきこもりサポートネット
メール相談や訪問相談、匿名での相談など、自分のスタイルに合わせた相談方法が選べる - 東京都立精神保健福祉センター
アルコール・薬物・ギャンブルに関する引きこもりなど、幅が広く相談を受付けしてくれる - ひきこもり家族会
包括的なひきこもり脱出支援をしてくれる民間組織が数多く存在している - 就職カレッジ®
就業経験がない人や少ない人に対して、内定獲得まで手厚くをサポートしてくれる
この記事の目次
引きこもりにおすすめの相談窓口7選【無料】
引きこもりについて無料で相談できる窓口としては、「ひきこもり地域支援センター」や「精神保健福祉センター」が挙げられます。
社会復帰や就職について相談したい場合は、「自立相談支援機関(就労準備支援事業)」や「サポステ」「就職カレッジ®」の利用がおすすめです。
引きこもりの子供への接し方に悩んでいる方は、民間のNPO団体などが運営する「ひきこもり家族会」への相談も検討してみましょう。
どの相談窓口を利用すれば良いか分からない方は、現在の状況に応じて適切な相談先を案内してくれる「ひきこもりチャットナビ」を活用してみてください。
- 東京都ひきこもりサポートネット
メール相談や訪問相談、匿名での相談など、自分のスタイルに合わせた相談方法が選べる - 東京都立精神保健福祉センター
アルコール・薬物・ギャンブルに関する引きこもりなど、幅が広く相談を受付けしてくれる - ひきこもり家族会
包括的なひきこもり脱出支援をしてくれる民間組織が数多く存在している - 就職カレッジ®
就業経験がない人や少ない人に対して、内定獲得まで手厚くをサポートしてくれる
1. ひきこもり地域支援センター
ひきこもり地域支援センターとは、社会福祉士・精神保健福祉士などの資格保有者(引きこもり支援コーディネーター)が中心となり、ひきこもりの相談支援などを行っている公的機関です。
厚生労働省の指針に基づき、全ての都道府県や指定都市に設置されています(令和3年4月時点)。
>> 全国の相談窓口
年齢や、本人・家族問わず誰でも無料で相談でき、「気持ちがまとまっていない」「話を誰かに聞いてほしい」といった段階でも利用可能です。
様々な形で相談できることも特徴で、たとえば「東京都ひきこもりサポートネット」では5つの相談方法が用意されています。
- 電話相談
- メール相談
- ピアオンライン相談(ひきこもり経験者やその家族と話せる)
- 訪問相談
- 来所相談
(例)東京都ひきこもりサポートネット
| 運営者 | 東京都 |
| 電話番号 | 0120-529-528 |
| 受付時間 | 電話相談:午前10時~午後5時(月曜日~土曜日)※年末年始・祝日は休み |
| メール相談 | 可 |
| 訪問サービス | あり |
| おすすめポイント | ・有資格者がサポートしてくれる ・行政が窓口なので安心して相談できる |
| ホームページ | 東京都ひきこもりサポートネット ひきこもり地域支援センター |
※2025年9月時点
2. 精神保健福祉センター
精神保健福祉センターとは、各都道府県・政令指定都市に設置されている公的機関です。
“心の健康相談”を中心に、ひきこもりからの社会復帰に関する相談のほか、アルコールや薬物、思春期の悩みなど幅広い問題に対応しています。
子供の相談で利用する方も多いため、子供のひきこもりに悩み、精神的につらい思いをしている家族の方にもおすすめできます。
(例)東京都立精神保健福祉センター
| 運営者 | 東京都福祉保健局 |
| 電話番号 | 03-3844-2212 |
| 受付時間 | 午前9時〜午後5時(月曜日〜金曜日)※年末年始・祝日は休み |
| メール相談 | - |
| 訪問サービス | あり |
| おすすめポイント | ・“心の健康”に関わる幅広い相談に対応している ・行政が窓口なので安心して相談できる |
| ホームページ | 東京都立精神保健福祉センター 全国の精神保健福祉センター |
※2025年9月時点
3. ひきこもり家族会
ひきこもり家族会とは、ひきこもり状態にある子を持つ家族が集まり、悩みを共有したり情報交換をしたりする場です。
NPO法人などが運営していることが多く、様々な家族会が独自に活動しています。
たとえば「楽の会リーラ」では、初回の面接相談や電話相談を無料で提供しており、個別の支援計画も作成してくれます(有料の場合あり)。
(例)楽の会リーラ
| 運営者 | NPO法人楽の会リーラ |
| 電話番号 | 03-5944-5730 |
| 受付時間 | 午後1時〜午後5時(毎週水曜日・金曜日) |
| メール相談 | - |
| 訪問サービス | あり |
| おすすめポイント | ・ひきこもりに悩む親同士で交流できる ・社会復帰まで手厚く支援してくれる |
| ホームページ | 楽の会リーラ 全国家族会一覧・支部加盟案内(KHJ全国ひきこもり家族会連合会) |
※2025年9月時点

4. 自立相談支援機関(就労準備支援事業)
自立相談支援機関とは、就職や経済的な困りごとなど、生活に関わる様々な悩みに対応してくれる公的な相談窓口で、全国の自治体に設置されています。
なお、自立相談支援機関は事業内容がいくつかに分かれており、ひきこもりからの社会復帰を目指す方やその家族は「就労準備支援事業」への相談がおすすめです。
たとえば武蔵野市の就労準備支援事業では、「仕事への不安が強い」「人との関わりに苦手意識がある」といった方を対象に、原則1年を上限とした無料の支援プログラムを実施しています(収入や資産状況などの諸要件あり)。
(例)東京都 武蔵野市
| 運営者 | 武蔵野市(健康福祉部生活福祉課) |
| 電話番号 | 0422-60-1254 |
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時(月曜日~金曜日)※年末年始・祝日は休み |
| メール相談 | - |
| 訪問サービス | - |
| おすすめポイント | ・社会復帰に向けた中長期的な支援を無料で受けられる ・就職活動のサポートも用意されている(面接練習など) |
| ホームページ | 武蔵野市 就労準備支援事業 困窮者支援情報共有サイト(就労準備支援事業) 自立相談支援機関 相談窓口一覧 |
※2025年9月時点
5. サポステ(地域若者サポートステーション)
サポステ(地域若者サポートステーション)とは、働くことに悩みを抱えている15歳から49歳までを対象に、個別相談や様々なプログラムを無料で提供している支援機関です。
厚生労働省が委託した民間団体などが運営しており、全国に179か所設置されています(令和6年度時点)。
>> 全国のサポステ
たとえば「しんじゅく若者サポートステーション」では、担当の相談員が支援プランを一緒に考えてくれるほか、次のような講座や就労体験も無料で開催しています。
- コミュニケーション講座、マナー講座
- ボランティア体験、就業体験
- 就職対策講座(履歴書の書き方など)
(例)しんじゅく若者サポートステーション
| 運営者 | 労働者協同組合労協センター事業団 |
| 電話番号 | 03-6380-2288 |
| 受付時間 | 午前10時~午後6時(月曜日~金曜日)午後1時~午後5時(第1・第3土曜日) |
| メール相談 | - |
| 訪問サービス | - |
| おすすめポイント | ・若者の支援実績が豊富な相談員が担当してくれる ・社会復帰に向けた多くのプログラムに無料で参加できる |
| ホームページ | しんじゅく若者サポートステーション サポステ(地域若者サポートステーション) 全国のサポステ |
※2025年9月時点
6. 引きこもりチャットナビ
ひきこもりチャットナビとは、チャット形式の相談案内サービスです。
厚生労働省のポータルサイト「ひきこもりVOICE STATION」内にあり、ひきこもり当事者やその家族の状況ごとに最適な相談先や支援情報を教えてくれます。
たとえばチャット上で「今の気持ち(つらい/相談したいなど)」を選ぶことで、いくつかの選択肢が表示され、自分に合った情報にたどり着けるようになっています。
チャット上で直接相談できるサービスではありませんが、「どの窓口を利用したらいいか分からない」「まずは情報を集めたい」という方は利用してみましょう。
>> ひきこもりチャットナビ
就職カレッジ®
ジェイックの「就職カレッジ®」は、正社員就職の支援サービスです。20代~30代・未経験からの正社員就職の成功実績が多数あるため、現在のご状況から正社員就職を成功させたいという方にぜひご利用いただきたいサービスです。
就職カレッジ®をおすすめする理由としては、以下があります。
- 社会人としてのマナーや就職に必要なスキルを講座で学べる
- 書類選考なしの面接会に参加可能
- 就職後も長期的な活躍のため研修を実施
就業経験がない・または少ない方を、短期間で企業で通用する人材へと育成し、内定獲得を実現します。
「就職したら終わり」ではなく、就職活動~入社後の定着まで手厚いサービスを提供します。
引きこもりが相談をするメリット
引きこもりの方が誰かに相談するメリットとしては、不安な心が落ち着いたり、自分の悩みがはっきりしたりすることなどが挙げられます。
引きこもりの方にとって孤独は“天敵”とも呼べるものですが、こうした状況でも「自分の気持ちを一人でも聞いてくれる人がいる」という安心感は大きな支えになります。
また、様々な不安が頭の中をぐるぐるめぐり、何から手をつければ良いか分からなくなることも多いでしょう。こうしたとき、モヤモヤとした考えをそのまま人に伝えることで頭の中が整理され、自分が本当に不安に思っていることに気づける人も多いのです。
メリット1. 心が落ち着く
たとえ状況がすぐに変わらなくても、「不安や思いを最後まで聞いてくれる人がいる」という安心感は“心の支え”につながります。
「自分の気持ちなんてどうせ理解してくれない」と感じてしまうこともあるかもしれませんが、ひきこもり地域支援センターをはじめ、引きこもりの方を対象に専門的な支援を行っている窓口は多く存在します。
不安な気持ちを誰かに話すだけでも心が落ち着くことは多いものです。そのため、まずは少しだけ勇気を出して相談をしてみましょう。
メリット2. 自分が何に悩んでいるのかがはっきりする
言葉にすると考えが自然と整理されるので、誰かに相談することで「自分が何に悩んでいるか」がはっきりと見えてくる人も少なくありません。
たとえば「人間関係を築けるか不安」と漠然と感じていたものの、気持ちを話すうちに「面接が怖い」といった本当の悩みに気づくケースもあります。この場合、まずはハローワークの面接対策講座に参加するなど具体的な解決策が見えてくるのです。
モヤモヤとした思いが整理できることも、相談のメリットとして押さえておきましょう。
メリット3. 自分にはない考えを知れる
相談をすると視野が広がるので、自分にはない考えや新しい知識が手に入ることもメリットの一つです。
たとえば「精神保健福祉センター」に相談すると、メンタル回復につながる専門的なアドバイスを受けることができ、支援機関を紹介してもらえることもあります。
相談を通して「そんな方法もあるのか」「こういう支援を受けられるのか」と新たな発見につながることは多いため、まずは“情報収集”の一環として気軽に相談してみましょう。
メリット4. 家族や周囲の人に当たらなくなる
相談によって心に余裕が生まれると、家族や周囲に怒鳴ったり、衝動的にモノに当たったりするような行動を抑えられます。
引きこもり状態が続くとストレスのはけ口が見つからず、身近な家族やモノに当たってしまう人は少なくありません。とはいえ暴言を吐く、部屋の壁を殴って穴をあけるなど、こうした言動・行動は家族にとって大きな負担につながります。
その点、相談をすると気持ちが落ち着くため、衝動的な言動を自分自身でセーブできるようになるのです。
メリット5. 人生に希望が持てる
相談をすると気持ちが整理され、将来に希望を持てるようになる人も多くいます。
引きこもり生活が続くと、「自分の人生は終わりだ」「何をしても無駄だ」といった絶望感から抜け出せないこともあるかもしれません。
しかし、たとえば「引きこもり家族会」などへの参加を通し、引きこもり経験者の方と話をする中で「自分でもできるかもしれない」という希望が生まれることも多いのです。このように相談は、引きこもりから抜け出す勇気を与えてくれることも知っておきましょう。

引きこもりが相談するデメリット
引きこもりの方が相談するデメリットとしては、一方的に考えを押しつけられてしまう恐れがあることが挙げられます。アドバイスを“答え”だと思い込んでしまう、または求める回答が得られない可能性があることもデメリットといえるでしょう。
相談相手によっては上から目線で話してくることもあり、気持ちを十分に理解してくれないケースもあります。
「つらい状況をすぐに抜け出したい」という気持ちから、相手の助言を盲信してしまうリスクがある点にも注意が必要です。
相談を受ける側にも不得意な領域があるため、的確な答えをもらえない場合があることも理解しておきましょう。
デメリット1. 相談相手によっては逆効果になることも
勇気を出して悩みを打ち明けても、自分の状況を相手が理解してくれず、一方的に考えを押しつけられることもあります。このような場合、かえって悩みが深まったり、人間不信につながったりする可能性がある点には注意が必要です。
「相談することで傷ついてしまうかも…」と不安な方は、相談相手を一人に絞らないことが大切です。
たとえば「ひきこもり地域支援センター」だけでなく「自立相談支援機関」にも相談するなど、相談先を分散させることを意識しましょう。
デメリット2. 相談結果が全てだと思い込んでしまう
悩みが深いと、藁(わら)にもすがる思いからアドバイスを全て信じ切ってしまい、あとになって後悔してしまう人も少なくありません。
「つらい状況からすぐに抜け出したい」と焦っているときは、いわゆる“正解”を求めがちです。しかし引きこもりから抜け出す方法に正解はなく、専門家からの助言でもそれが本人とって正しい方法とは限りません。
相談はあくまでも“ヒント”を手にする機会と捉え、全てを信じるのではなく、情報を取捨選択する意識を持ちましょう。
デメリット3. 求めている回答が得られない可能性がある
相談相手にも得意・不得意があるため、相談したとしても必ずしも期待する答えが得られるとは限りません。
たとえば「引きこもりからの就職方法」について両親に具体的なアドバイスを求めても、就職に関する知識が十分でない場合、的外れな答えを返されてしまう恐れもあるでしょう。この場合は「サポステ」のように、就職支援を専門的に行っている機関に相談するのがおすすめです。
本当に必要な情報を手にするためにも、自分が聞きたい内容に適した相談窓口を選びましょう。

引きこもりが相談しない末路
引きこもりの方にとって「相談」はハードルが高いかもしれませんが、悩みや不安を誰にも打ち明けられないと精神的に参ってしまったり、社会から孤立してしまったりする末路が訪れる可能性があります。
部屋の中でゲームや動画視聴をして過ごす生活に対し、「自分は何をしているんだろう…」と虚(むな)しさを感じる方も少なくありません。
自分の知識だけで就職活動を進めた結果、ブラック企業に入社してしまう方もいます。
家族が「相談窓口」を何度も紹介してくれているのに聞く耳を持たないと、次第に愛想を尽かされ、親との関係がさらにぎくしゃくしてしまう恐れもあるでしょう。
精神を病んでしまう
引きこもりがその現状を誰かに相談することで、心を落ち着かせられたり、引きこもり解決の糸口が見つかると考えられます。
裏を返せば、誰かに相談しない限り引きこもりは解消に向かわない可能性があるとも言えるかもしれません。
引きこもり期間が長期化すると、必然的に部屋に居続ける期間が増えます。
誰とも話さずに一人だけの時間を過ごせば過ごすほど、自分の人生に対して自問自答をする回数も増えます。
引きこもりの自問自答は、自らの人生に対する焦りや諦めを始めとしたネガティブなものになりやすく、ネガティブな自問自答ばかりしていると、精神を病みやすくなってしまうでしょう。
精神を病んだ状態が続けば、うつ病や統合失調症などの精神病を発症してしまうこともあり、想像以上に長い期間引きこもりとして生きていかなくてはいけなくなるかもしれません。
社会から完全に孤立してしまう
引きこもり期間が長引くにつれ、自分の周りから人がどんどん離れていきます。
リアルの友人から始まり、両親・きょうだいと離れていき、最終的にはたった一人で起きている間の時間を過ごすことになるでしょう。
「自分はリアルじゃなくてもインターネットに友人がいるから大丈夫」と考える人もいるかもしれませんが、その認識は甘いです。
現在インターネットで繋がっている友人は、あなたと全く同じ境遇で、同じように引きこもりをしているとは限りません。
仕事が忙しくなったり、ライフステージが変わってしまえば、その友人はあなたと唯一繋がっているインターネットに見向きすらしなくなるでしょう。
インターネットでの交友を否定するつもりはありませんが、オフラインと同じく関係性に永遠というものはほぼ存在しませんので、最終的に孤立してしまうこともあり得ます。
人生を無駄にしてしまう
引きこもりの期間にやることは、「ゲーム」「漫画や小説を読む」「アニメや映画を見る」といった趣味に時間を費やすといったものがほとんどなのではないでしょうか。
もちろんこれらの趣味は想像力の向上やストレス緩和に有効ではあるものの、人生の質という観点で見ると、どうしても弱いものになってしまいます。
人生には限りがありますので、生きていれば様々な価値発揮ができるにも関わらず、新しいことに挑戦せず毎日決まったことばかりしていると、その分人生が無駄になりかねません。
相談をすれば、その分早く引きこもりから脱出でき、有意義な人生を送れる可能性が高まります。
間違った方向に突き進んでしまう
相談をしないと、自分の考えを信じて行動することしかできなくなりますので、もし自分が間違った判断や思考をしていても、そのまま突き進んでしまい、思わぬトラブルが生じることがあります。
例えば引きこもりから脱するために、自分のノウハウだけで就職活動を進めてしまうと、いきなりブラック企業に入社してしまう恐れがあります。
ブラック企業に入社すると、「メンタルをぼろぼろにされるような業績管理」、「どれだけ働いても残業が無くならずに体調を崩す」など、二度と社会復帰することができないような傷を負ってしまうかもしれません。
引きこもりを脱し、その後幸せな人生を送るためにも、順序立てたステップを踏むようにするべきですし、そのためにも相談をすることが重要となるのです。
人間関係が悪化する
相談は、必ずしも自分から行わなければいけないということではありません。
時には悩んでいる自分に、相談を促すような声をかけてくれることがありますが、この声を拒絶し相談しない選択肢を取ってしまうと、人間関係が悪化することもあります。
例えば親が「何か悩んでいることがあったら相談してみてほしい」と言ってきた時、拒絶するように突き放してしまうと、親は「信頼されていない→相談を促しても怒鳴られる→もう話しかけないようにしよう」といった思考を行い、二度と話しかけてくれなくなる可能性があります。
相談をすることは決して恥ずかしいことではありません。
時には人に弱さを見せ、誰かに頼ってもいいのです。
就活に悩んだら“就職カレッジ®”という選択肢も。
● 年間1000人以上のフリーターやニートの方が正社員に※
● 入社後のサポートも充実で安心
● ずーっと無料
▶ 詳しくは「就職カレッジ」で検索※2023年2月~2024年1月「就職カレッジ」参加者からの正社員未経験者就職決定人数
相談によって引きこもりを脱出した人の体験談
ここからは、実際に相談をすることで引きこもりニートから脱出できたという体験談をいくつか紹介します。
体験談1.「同じ境遇だった友人に相談したら引きこもりを脱せた」
「公務員になるために、2年間努力したものの見送りになりました。
精神的にもつらく引きこもりになってしまいましたが、このままではまずいと思い、就職活動を始めることにしました。
その時、自分と同じような境遇だった友人に相談したら、いいサービスがあることを教えてもらい、そのサービスを利用したら無事引きこもりを脱せました。」
この体験談から、相談内容と相談先の掛け合わせが大切であることが改めて分かります。
この人の場合、既に引きこもりを脱したいという思いは持っていましたが、これから取るべきアクションについては分かっていませんでした。
そこで、同じような境遇にあった友人に相談したことにより、脱ひきこもりに直結する有用な情報を聞けたのです。
ちなみに、この人は就職後も4年以上同じ職場でやりがいを持って働けているそうです。
体験談2.「地域の就職支援センターに相談した」
「1社目も2社目も自分とは合わない仕事であったので、長続きはしませんでした。
2社目の退職時と同時に家族も引っ越すことになり、就職先を探すために地域の若者就職支援センターのスタッフに就職活動の相談をしてみました。
そのスタッフに聞いた方法を実践してみたら見事内定獲得。今はその会社に10年程在籍していますし、妻も子どももできました。」
この体験談から、地域の就職支援センターも相談先として有効であることが分かります。
引きこもりが仕事を探すためには、ハローワークしかないと思っている人もいるかもしれませんが、実は地方自治体や民間の企業でも脱引きこもり支援を行っている組織があります。
どんな組織があるのはについては、この後の紹介をご覧ください。

引きこもりに関連した国の政策
引きこもりが相談しやすい環境づくりのために、民間団体だけでなく国も施策を設け、味方になってくれようとしています。
すぐに利用をしなくても、知識的に知っておくことで、「相談できる環境がある」という安心感を感じられるでしょう。
ひきこもり地域支援センター
ひきこもり地域支援センターは、平成21年度から実施されている取り組みで、主に引きこもりに特化した第一次相談窓口としての機能をもっています。
このセンターは、引きこもり支援をしている他の関係機関とも連携しているため、相談内容に応じて適切なサービスや組織を紹介してくれるといった特徴がありますので、「困ったらとりあえずここに相談する」という判断でも問題ないでしょう。
ちなみに、ひきこもり地域支援センターは都道府県によって設置されていないこともありますので、厚生労働省「ひきこもりVOICE STATION」から確認してみてください。
子ども・若者育成支援推進法
平成22年度から、引きこもりやニートといった悩みを抱える若者への支援や、地域ネットワークづくりを目的とした“子ども・若者育成支援推進法”といった法律も施行されています。
この法律により、悩める誰もが円滑な社会生活を目指すために必要な相談センターの設置であったり、就業支援を行う民間団体の支援が行われるようになりました。
こうした法律が整備されているということは、「国をあげて引きこもり支援のバックアップが用意されている」ということです。
引きこもりは一人で悩まずに、国でも地方自治体でも家族でも友人でもいいので相談することをおすすめします。

引きこもりが相談する時に注意したいこと
引きこもりについて相談する時は、自分の相談内容に合わせた窓口を選ぶことが大切です。相談の際は落ち着いてゆっくりと話し、自分の考えを偽(いつわ)らずに素直に伝えることも意識してみてください。
対応できる内容は相談機関ごとに異なるため、合わない窓口に相談すると満足のいく答えが得られないことがあります。
早口でまくし立てるように話すと相手に要点が伝わりにくいため、落ち着いて話すことも意識しましょう。
「守秘義務」の規定によって相談内容が外に漏れることはないので、見栄を張って嘘をつくのではなく、ありのままの思い・考えを話すことも心がけましょう。
注意点1. 欲しい回答によって相談先を選ぶ
相談機関にはそれぞれ専門分野や得意・不得意な相談内容があるため、自分が本当にほしい回答をもらえそうな相談先を選びましょう。
たとえば心の不調について相談したい場合は、メンタル面の支援を専門に行う「精神保健福祉センター」への相談がおすすめです。
▼おすすめの相談先
| 相談内容 | おすすめの相談先 |
|---|---|
| 心の不調やメンタルの悩み・解決策 | 精神保健福祉センター |
| 引きこもりの子供への接し方・家族の対応 | ひきこもり家族会 |
| 社会復帰に向けた具体的な道筋 | 自立相談支援機関 |
| 無職期間が長い場合の就職活動のコツ | サポステ(地域若者サポートステーション) |
注意点2. 落ち着いてゆっくり話す
いざ誰かに悩みを相談することになったら、緊張してしまうかもしれませんが、落ち着いてゆっくり話すようにしましょう。
ゆっくりと話すことで、相談相手は「自分が何に悩んでいるのか」「どうして今引きこもりになってしまっているのか」という現状の理解が進みやすくなりますので、より具体的なアドバイスをもらえる可能性が上がります。
つらい思いを相手に話すことは、自分の弱みをさらけ出すような気持ちがして嫌だと感じてしまうかもしれませんが、相談の場に乗ってくれているということは、相手が自分に嫌な言葉をかけるつもりはないと考えることができます。
自分に対して心を開いてくれているのですから、焦らずに自分のタイミングで話しても嫌な顔はされないでしょう。
注意点3. そのままの考えを伝えるようにする
せっかく悩みを相談するのですから、嘘をついたり見栄を張ることなく、そのままの思いを相手にぶつけるようにしましょう。
素の自分で相談することは、自分の心を落ち着かせるだけでなく、よりよいアドバイスをもらうためのきっかけにもなります。
もし友人や家族とはどうしても素直に話せそうにないという人であれば、国や地方自治体、民間団体が運営しているような専門相談窓口を利用してみてもいいでしょう。
「引きこもり相談」に関するよくある質問
子供の引きこもりだけでなく、「大人の引きこもり」についても支援窓口やサポート施設は多く存在します。
たとえば以下の相談窓口は、大人の引きこもりにも対応しています。
・ひきこもり地域支援センター
・精神保健福祉センター
・ひきこもり家族会(年齢制限がある場合あり)
・自立相談支援機関(就労準備支援事業)
・サポステ(地域若者サポートステーション)
なお、「サポステ(地域若者サポートステーション)」のみ49歳までを対象としている点に注意が必要です。
「精神保健福祉センター」や「自立相談支援機関」をはじめ、50代も含め、年齢を問わず引きこもりの方を支援している相談窓口はいくつも存在します。
生活の困窮や就職相談などについては「自立相談支援機関」、精神的な問題について相談したい場合は「精神保健福祉センター」がおすすめです。
・自立相談支援機関(生活の困窮や就職、経済的な悩みなどに無料で対応)
・精神保健福祉センター(不安感や気力の低下といった精神的な悩みに無料で対応)
誰かに相談したいけれど勇気が出ないときは、引きこもりから社会復帰した人の体験談を読んでみるのも一つの方法です。
同じように悩んできた人の歩みを知ることで、「自分も変われるかもしれない」「働けるかもしれない」といった希望や気づきを得られることも少なくありません。
相談にハードルを感じるときは無理をせず、以下のような事例に目を通すことから始めてみましょう。
>> ひきこもり経験者の社会参加の事例集(PDF)
「本当は何がしたいの?」「◯◯に比べてあなたは」といった発言は本人を追い詰めてしまうため、引きこもり当事者との会話では“禁句”とされています。
引きこもりの状態で将来のイメージを持つことは難しいにも関わらず、「本当は何がしたいの?」と問いかけられると大きなプレッシャーを感じてしまいます。
「◯◯くんは就職したらしいけど、それに比べてあなたは…」といったように、同世代と比較するような発言も自尊心が傷つく要因になるので控えましょう。
参考:茨城県「ひきこもりへの対応Q&A」
まとめ
引きこもりが相談することで、今の自分の焦りや不安を払拭できる可能性が高まりますが、相談内容によって相談先を意識しないと、思ったようなアドバイスを得られない可能性がある点には注意しましょう。
また、脱ニートを目指し、就職活動に特化した相談をしたいなら、引きこもりの就職支援に実績のある、私たちジェイックの就職エージェントへの登録がおすすめです。
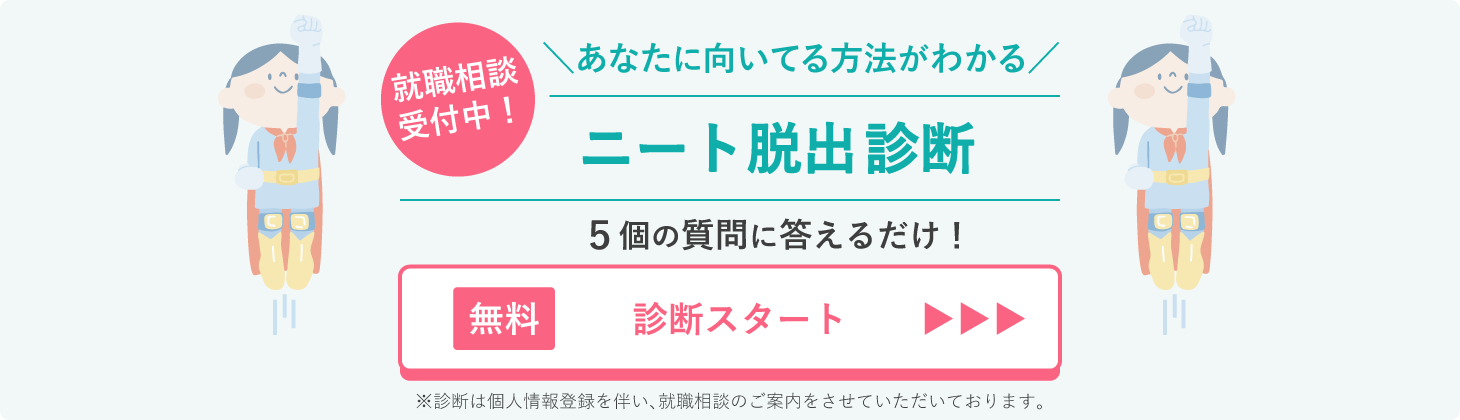
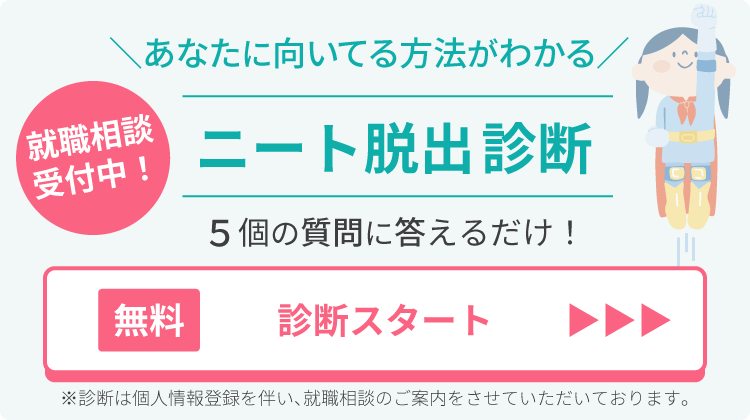
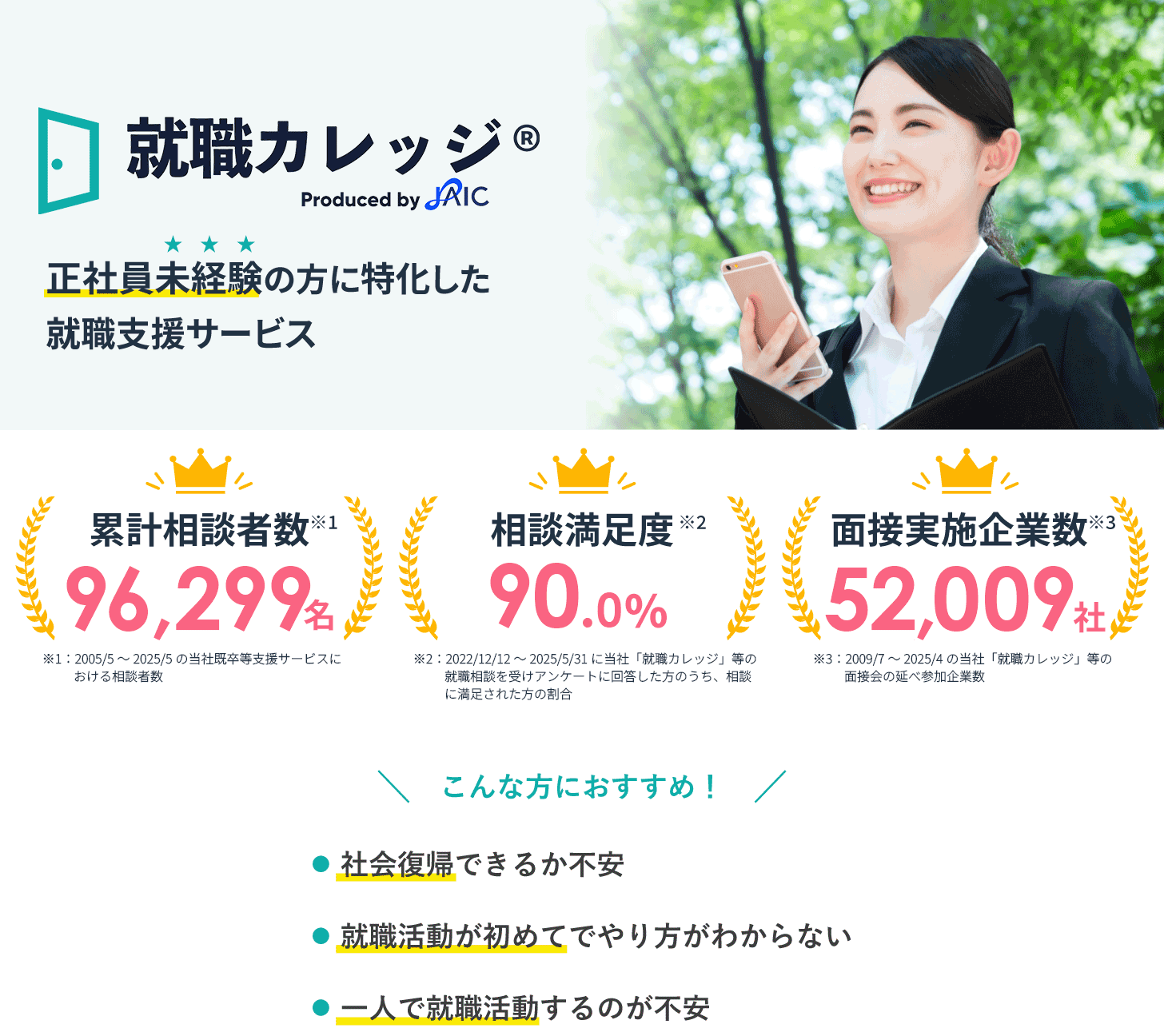
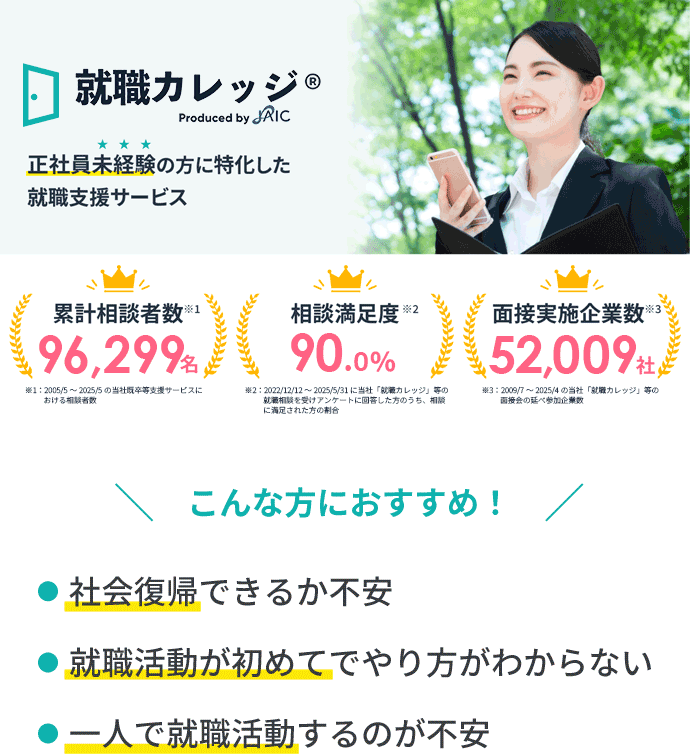

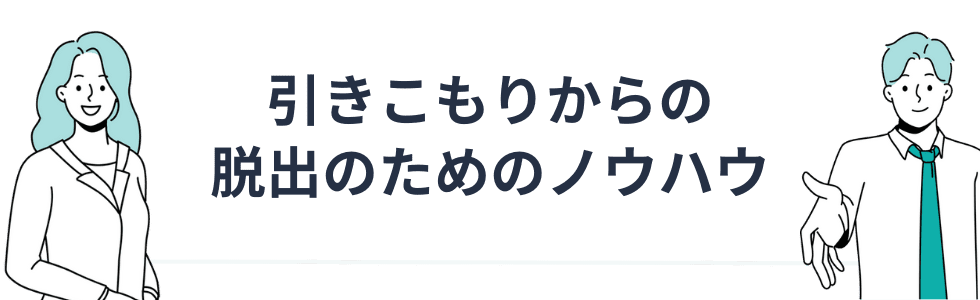
当社の就職に関するコンテンツの中から、引きこもりからの脱出や就職活動に不安を感じている方向けに、引きこもりからの脱出方法や就職活動で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- 引きこもりを脱出する方法!脱出できる人とできない人の違いも紹介
- 引きこもりでもできる仕事おすすめ20選|探し方・就職支援を解説!
- 引きこもりから社会復帰するには?支援サービスやポイントを知ろう
- 引きこもりから正社員で就職する方法!おすすめ職種を解説
- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説
- 引きこもり・ニートの末路とは?脱するための方法も紹介!
- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説
- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説
- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?
- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説
- 20代の引きこもりに関する実態について!原因や脱出方法を解説
- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介