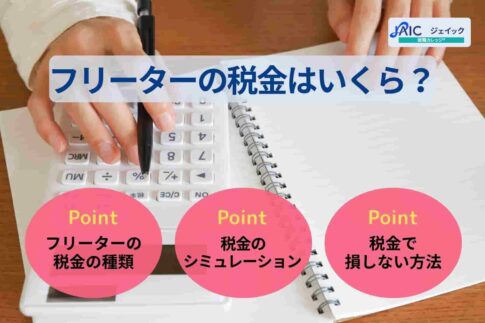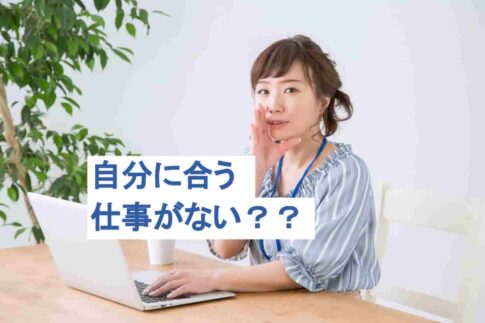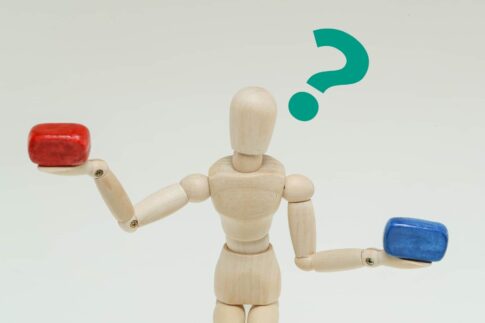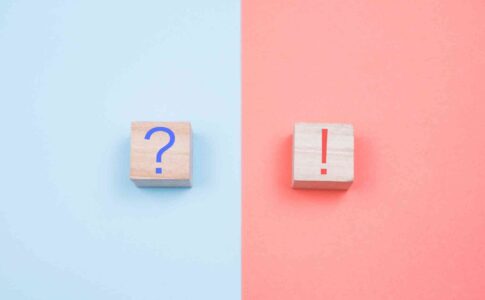転職まで無職期間が1ヶ月ある場合、健康保険や年金などの手続きが必要です。
健康保険については、任意継続保険制度や、扶養に入る方法、国民健康保険など、いくつかの選択肢があります。年金に関しては、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
この記事では、再就職までに空白期間が1ヶ月ある方に向けて、社会保険や税金の手続きを解説しています。
必要な手続きが分からずに困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
転職まで無職期間が1ヶ月ある場合の健康保険の手続き
転職まで無職期間が1ヶ月程の場合は、健康保険の手続きが必要です。
主な選択肢は3つあり、①前職の保険を最長2年間継続できる「任意継続」、②収入などの条件を満たせば「家族の扶養」に入る方法、③市区町村で加入する「国民健康保険」です。
「1ヶ月だけだから大丈夫」と思って未加入のままでいると、万が一病気やケガで治療が必要になった際、医療費が全額自己負担となり、高額な出費を強いられる可能性があります。
日本では、たとえ無職の期間であっても公的な医療保険への加入が義務づけられているので、無職期間が短くても忘れずに健康保険に加入しておきましょう。
1. 任意継続保険制度の利用
転職後に1ヶ月ほどの無職期間がある場合は、「任意継続保険制度」を活用することで、在職中と同じ健康保険を継続して利用できます。
任意継続保険制度とは、退職前と同じ健康保険に最長2年間まで加入できる制度です。
加入条件は、以下の通りです。
- 退職前に継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある
- 退職日の翌日から原則20日以内に必要書類を提出する
任意継続保険制度のメリットは、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があることです。
手続きの流れは次の通りです。
1、加入していた健康保険組合または協会けんぽの公式サイトなどで、「任意継続被保険者資格取得申出書」をダウンロードし、記入する
↓
2、退職日の翌日から20日以内までに、上記いずれかの団体に郵送する
↓
3、保険料を期日までに納付する
任意継続保険制度は1ヶ月だけの加入も可能です。
転職までの空白期間中にどの健康保険に加入すれば良いか悩んでいる方は、選択肢の一つとして検討してみましょう。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」
2. 家族の扶養に入る
家族の扶養に入ることができれば、転職までの無職期間(1ヶ月分)にかかる健康保険料を支払わずに済む可能性があります。
扶養とは、会社員などが加入している社会保険(健康保険)において、一定の条件を満たす親族を扶養に入れると、その親族の健康保険料がかからなくなる制度です。
扶養に入るための主な条件は、以下の通りです。
- 日本国内に住所(住民票)がある
- 被保険者に生計を維持されている3親等内の親族(父母、子、孫など)
- 年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)
- 同居の場合:収入が扶養者の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が扶養者からの仕送り額未満
「年収130万円未満」という基準があるため、収入が基準を超える見込みがある場合、扶養に入るのが難しいこともあります。
一方で、収入がない状態がしばらく続くと見込まれる場合は扶養に入れる可能性があるため、まずは家族の加入する健康保険組合などに相談してみることをおすすめします。
参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者とは?」
3. 国民健康保険に加入
任意継続保険制度や家族の扶養に入らない場合、たとえ転職までの無職期間が1ヶ月だけであっても「国民健康保険」に加入する必要があります。
国民健康保険とは、会社の健康保険(社会保険)に加入していない自営業者や無職の人などが加入する健康保険制度です。
加入手続きは、退職日の翌日から原則14日以内に行う必要があります。住んでいる地域を管轄する市区町村役場で手続きができますが、最近では自治体のホームページからオンラインで申請できる場合もあります。
手続きに必要な主な持ち物は、以下の通りです。
- 健康保険資格喪失証明書(退職した会社から発行される)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 預金通帳、印鑑
国民健康保険の保険料は市区町村ごとに異なるため、地域によっては、先ほど紹介した任意継続保険制度よりも保険料が高くなることがあります。
少しでも保険料を抑えたい方は、国民健康保険と任意継続保険の保険料を比較しておきましょう。
参考:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
転職まで無職期間が1ヶ月ある場合の年金の手続き
転職までに無職期間が1ヶ月ある場合、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。
手続きは、退職日の翌日から14日以内に、自治体の役所やオンライン上で行います。必要書類は、基礎年金番号通知書や、退職日を証明する書類などです。
公的年金制度の加入は国民の義務のため、無職期間が1日でもあれば、原則として国民年金への切り替え手続きが必要です。
なお配偶者の扶養に入る場合は、国民年金保険料の納付義務がなくなります。ただし、自身の年収が130万円を超えるケースなどでは対象外となる点に注意しましょう。
経済的な事情で国民年金保険料の支払いが難しい場合は、免除制度や納付猶予制度を利用できる可能性もあります。
退職の翌日から14日以内に国民年金に切り替える
次の会社に転職するまでの間に空白期間がある場合、その期間は厚生年金に加入できないため、国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。
手続きの期限は、退職日の翌日から原則14日以内です。住民票のある市区町村の役所などで手続きができるほか、オンライン申請にも対応しています。
手続きに必要な主な書類は、以下の通りです。
- 基礎年金番号通知書または国民年金手帳
- 退職日が確認できる書類(離職証明など)
なお、会社員や公務員の配偶者の扶養に入る(第3号被保険者になる)場合、保険料の納付は不要となります。ただし、自身の年収が130万円を超える場合などは対象外となり、国民年金の加入と保険料の支払いが必要です。
また、失業などで保険料の支払いが難しい人のために「保険料免除制度」や「納付猶予制度」なども設けられています。
一定の条件を満たせば負担を軽減できるため、無職期間中で経済的に厳しい方はこうした制度の利用も検討してみましょう。
参考:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き|第1号被保険者の加入の手続き」
参考:新宿区「加入・喪失の届出|会社などを退職したとき (厚生年金等の加入者でなくなったとき)」
参考:政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
無職期間が1日以上あれば手続きが必要
無職であっても国民年金保険料の支払い義務があるため、退職日から次の会社の社会保険に加入するまでの間に空白期間が1日でもあれば、国民年金への切り替え手続きが必要です。
なお、次の会社に月の途中で入社した場合でも、その月に厚生年金に加入すれば、同月の保険料は国民年金ではなく厚生年金として扱われるため、国民年金の支払いは不要です。
たとえば3月末に退職し、4月16日に次の会社へ入社した場合、4月中に厚生年金に加入するため、4月分は厚生年金が適用され、国民年金の保険料は発生しません。ちなみに、月の途中で次の会社に入社した場合、その月の国民年金保険料の支払いが不要になるケースもあります。
厚生年金の保険料は会社と折半のため、自己負担は実質半額で済みます。一方で国民年金は、全額自己負担です。
とはいえ日本では、原則として20歳以上60歳未満の全ての人に国民年金への加入が義務づけられています。未納の期間があると、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性もあるため、たとえ無職期間が短くても切り替え手続きを行いましょう。
参考:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
転職まで無職期間が1ヶ月ある場合の税金の手続き
転職まで無職期間が1ヶ月ある場合、税金面では主に「住民税」と「所得税」の手続きが関係します。
住民税については、退職時期によっては自分で納付(普通徴収)する必要があります。
たとえば、1月〜5月に退職した場合は「給与から天引きされなかった残りの住民税」を、6月〜12月に退職した場合は「退職月以降にかかる住民税」を自分で納めるケースが一般的です。
所得税については、年末(12月31日)時点で会社に在籍していないと年末調整の対象外のため、自分で確定申告を行う必要があります。
ただし、無職期間が1ヶ月あっても、年内に再就職できた場合は転職先の会社が年末調整を行ってくれるため、所得税についての手続きは基本的には不要です。
住民税
転職先が決まっていない場合、退職時期によって住民税の納付方法が変わる可能性があります。
住民税は前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月までに納める仕組みです。会社員であれば、通常は毎月の給与からの天引き(特別徴収)によって納付します。
1月1日〜5月31日に退職した場合、5月分までの残りの住民税が、最後の給与から一括で徴収されます。ただし給与から天引きしきれなかった分があれば、自治体から届く納付書に基づいて自分で支払わなければいけません。
6月1日〜12月31日に退職した場合、退職月以降(翌年5月まで)の住民税は、再転職先で特別徴収をしてもらわない限り、原則として自分で納付する必要があります。しかし退職時に会社に申し出れば、残りの住民税を最後の給与や退職金から一括で徴収してもらえる可能性もあります。
住民税に関しては、個人が自治体に直接届け出るようなものはありませんが、退職時期や金額によっては自分で納付する必要がある点には注意しましょう。
所得税
年度内に退職し、年末時点で次の会社に転職できていない場合は、所得税の精算(確定申告)を自分で行う必要があります。
会社員として働いている場合、所得税の計算や納付は、勤務先が年末調整を通じて代行してくれることが一般的です。
ただし年末調整の対象となるのは、原則としてその年の12月31日時点で会社に在籍している従業員です。そのため、年末時点で無職の場合は年末調整を受けられない可能性があり、この場合は自分で確定申告を行う必要があります。
一方、無職期間が1ヶ月あったとしても、12月31日までに次の会社に入社していれば、基本的にはその会社が年末調整を行ってくれます。この場合、前の会社から交付される「源泉徴収票」などを新しい勤務先に提出する必要がある点には注意しましょう。
所得税の取り扱いは「年末時点で無職か否か」によって異なります。勤務状況によっては自分で手続きをする必要があるので、忘れずに確定申告を行いましょう。
転職まで空白期間が1ヶ月ある場合は失業保険をもらえる?
転職までに無職期間が1ヶ月ある場合、「自己都合退職」では失業保険を受け取れない可能性が高く、「会社都合退職」であれば数日〜数十日分の給付を受け取れる場合があります。
失業保険とは、失業中の生活を支えるために支給される給付金で、正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれます。ハローワークに求職申込みを行い、“就職の意思と能力があるが、現在は職に就いていない状態”と認められることが必要です。
失業保険の支給条件や受給開始までの期間は、退職理由(自己都合か会社都合か)と雇用保険の加入期間によって大きく異なります。
| 退職理由 | 代表的なケース | 離職前の雇用保険加入期間(被保険者期間) |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | スキルアップ、キャリアチェンジ | 離職日以前の2年間に、通算12ヶ月以上 |
| 会社都合退職 | 倒産、解雇 | 離職日以前の1年間に、通算6ヶ月以上 |
自己都合退職の場合
自己都合退職によって無職期間が1ヶ月だけ生まれる人の場合、支給開始までに「待機期間」と「給付制限期間」があるため、原則として失業保険を受け取れません。
自己都合退職とは、本人の希望や都合によって会社を辞めることを指します。スキルアップや年収アップを狙っての転職など、会社側の都合によらない退職が当てはまります。
失業保険は、退職後すぐに支給されるわけではありません。まず、ハローワークに離職票を提出し、求職の申込みを行う必要があります。そのうえで7日間の「待機期間」が設けられ、さらに自己都合退職の場合、その後に原則1ヶ月の「給付制限期間」があります(※)。
つまり、支給対象期間が訪れるまで、最低でも「1ヶ月と7日間程度」かかるのです。
無職期間が1ヶ月しかない場合、失業保険の支給が始まる前に再就職してしまうケースが多く、実際に給付を受けられないこともあります。(※)。
ただし受給資格は得ているため、支給開始前に再就職した場合は「再就職手当」の対象となる可能性もあります。
※「正当な理由のある自己都合退職(父母の死亡による退職、配偶者の転勤のため通勤が困難になったなど)」の場合、給付制限期間が設けられない場合もあり
会社都合退職の場合
会社都合退職の場合、自己都合退職よりも受給条件が緩和されるため、無職期間が1ヶ月でも失業保険を受け取れる可能性があります。
会社都合退職とは、倒産や解雇など、会社側の都合による退職のことです。
ハローワークへの離職票の提出・求職申込み、7日間の「待機期間」は発生しますが、「給付制限期間」はありません。そのため、7日目の翌日(8日目)から支給対象期間のカウントが始まります。
たとえば8月1日にハローワークで申請し、9月1日に再就職した場合、8月8日〜8月31日までの24日間分の失業保険を受け取れる可能性があるのです。
なお、失業保険を一度受給すると、支給条件の一つである「雇用保険の加入期間」がリセットされます。この場合、再就職後に短期間で再び離職すると雇用保険の加入期間が不足し、再度の受給が難しくなるケースもあるため注意が必要です。
転職で空白期間の理由を質問された時の答え方
「1ヶ月の無職期間が生まれた理由」を面接で質問された場合は、ポジティブな表現に変換して説明すると好印象につながります。
ブランク期間中に自己成長のために取り組んだ勉強や活動があれば、向上心をアピールできるので積極的に伝えましょう。
さらに、その期間を通じて得た気付きや学びを交えることで、自己理解の深さも示すことができます。
また、空白期間があることに対してネガティブな印象をもつ面接官もいるかもしれません。そのため、説明の最後には就業意欲や将来の目標を伝えることで、前向きな姿勢を印象付けることも大切です。
1. ポジティブな表現に変換する
面接では無職期間の説明の仕方によって印象が変わるので、前向きな姿勢をアピールしたい方はポジティブな表現に変換して伝えてみましょう。
たとえば体調不良で前職を退職し、1ヶ月間休養を取った場合は、「体調を整え、万全の状態で再スタートするために退職しました」と伝えても良いかもしれません。
人間関係のストレスが原因で退職をした場合は、「同僚と切磋琢磨できる環境で働くことが自分にとって重要だと考え、転職を決意しました」と表現すると成長意欲が伝わるでしょう。
このように、表現を変えるだけで前向きで誠実な印象を与えられるのです。
2. 無職期間の取り組みを伝える
無職期間に「何もしていなかった」という印象を与えてしまうと、採用担当者の評価が下がる恐れがあるため、期間中に何らかの取り組みをしていた場合は積極的に伝えることが大切です。
ブランクが1ヶ月だったとしても、「専門書を読んで業界知識を深めていた」「転職後を見据えて資格の勉強に取り組んでいた」といった行動は、立派なアピール材料になります。
こうした前向きな姿勢を伝えることで、「無職期間中も自己成長に努めていた人物」として好印象を与えられます。結果として向上心を評価され、採用にプラスに働く可能性も高まるでしょう。
3. 無職期間の学び・気付きを交える
自己理解の深さをアピールできるため、空白期間で得た学びや気付きも伝えましょう。
たとえば「この1ヶ月で自分の強みを見つめ直すことができ、営業職が自分に向いていると再認識できました」といったエピソードは、自己分析がしっかりとできている印象を与えます。
転職理由についても、 「前職を辞めた理由を冷静に振り返ることで、どのような環境で貢献していきたいか明確になりました」といった形で伝えることで、職場をしっかりと選び取っている姿勢も伝えられるでしょう。
このように無職期間で得たことを伝えることで、面接官にポジティブな印象を与えられるのです。
4. 転職への前向きな姿勢を示す
無職期間に対して採用担当者が感じる不安を和らげるためにも、空白期間について説明する際は、転職に向けた前向きな気持ちを最後に伝えることが大切です。
たとえば「長期的に御社に貢献できる人材を目指します」といった意欲や、「5年後までにリーダーポジションに就いていたい」といったキャリアプランを伝えるのも効果的です。
無職期間が1ヶ月程度であれば、ブランク自体がネガティブに受け取られることは多くありません。ただし企業によっては不安を抱く場合もあるため、熱意をもって前向きな姿勢や入社への意欲を伝えることで、そうした懸念を払拭しましょう。
空白期間の回答例(リフレッシュに充てていた場合)
転職に向けた1ヶ月の無職期間を「リフレッシュに充てていた」場合の回答例を紹介します。
前職で長時間労働が続いていたため、この1ヶ月は一度立ち止まり、今後のキャリアを見つめ直す時間に充てていました。
まずは体調を整えるため、毎日ウォーキングを続けて体力の回復に努めました。御社で活かせる知識を深めるために関連書籍を読んだり、オンラインセミナーに参加したりして継続的に学習も進めております。
また、自分が本当にやりたい仕事について考え抜いた結果、御社のような成長企業で長期的に貢献したいという気持ちもより一層明確になりました。
現在は体調も万全で、新しい環境で全力を尽くす準備も整っております。
「ただ何となく過ごしていた」という印象を与えてしまうと、マイナス評価につながる恐れがあります。
そのため、上記の例のように「休養」を「キャリアを見つめ直す時間」と言い換えるなど、ポジティブな表現で説明することを意識しましょう。
空白期間の回答例(やむを得ない事情があった場合)
介護などの「やむを得ない事情」により、1ヶ月の無職期間があった場合の回答例を紹介します。
母の介護が必要になったため、一時的に仕事を離れて家族のサポートに専念していました。
退職後は介護と並行して、スキルアップのために簿記2級の勉強も続けております。
また、家族を支えた経験を通じて、責任感や協調性の大切さも改めて実感しました。御社でもこうした経験を活かし、同僚の方々としっかり協力しながら業務に取り組みたいと考えています。
現在は介護サービスを利用することで母を支える体制が整い、父からも安心して再就職に臨んで良いと言われております。
御社では経理職として経験を積み、グループ会計の分野で活躍できる人材を目指して働きたいと考えております。
介護や病気などのやむを得ない事情を伝える際は、「現在は働ける状態にあること」をしっかり伝えることが重要です。
こうすることで、企業側が抱く「この先の勤務に支障はないか?」という不安を軽減できます。
転職で空白期間が1ヶ月できる場合の注意点
無職期間中に健康保険の手続きを怠ると、その間に発生した医療費を全額自分で立て替えなければならないため注意が必要です。
たとえブランクが1ヶ月でも、任意継続や国民健康保険など、いずれかの公的な健康保険に加入する必要もあります。保険料は月単位で遡って請求されるため、未加入のまま放置しても、後からその分の保険料を支払う義務が生じる点にも注意しましょう。
また、無職期間をごまかすと「経歴詐称」と見なされる恐れもあります。内定取り消しや懲戒処分につながる可能性もあるため、無職の期間は正直に伝えることが大切です。
1. 健康保険に未加入だと全額自己負担になる
健康保険に未加入の期間が生じると、その間に医療費が発生した場合に窓口での支払いが10割(全額)となってしまうため注意が必要です。
「たった1ヶ月だし、病院に行くこともないだろう」と考えて何も手続きしないでいると、いざ体調を崩して受診が必要になった時に大きな出費を強いられる可能性があります。
そのため、任意継続被保険者制度を利用する、国民健康保険に加入する、または家族の扶養に入るなど、いずれかの方法で健康保険の手続きを済ませておきましょう。
2. 健康保険料が遡って徴収される可能性がある
健康保険については、原則として退職日の翌日から保険料の支払い義務が発生するため、手続きが遅れた場合でもその期間分の健康保険料を支払う必要があります。
たとえば3月31日に退職した場合、4月1日から国民健康保険の加入資格が発生します。つまり、手続きを忘れて5月に入ってから市区町村の窓口に行っても、4月分の保険料まで遡って請求されるのです。
この点は、任意継続被保険者制度も同様です。
「加入していない分は払う必要がない」と勘違いしていると、後から予想外の支払いが発生して慌てる可能性があります。
健康保険料は日割りではなく月単位で計算されるため、たとえ未加入でも、その月分の保険料を全額払う必要がある点には注意しましょう。
3. 空白期間をごまかすのはNG
経歴詐称と見なされる恐れがあるため、たとえ1ヶ月であっても無職期間をごまかすのは避けましょう。
すでに前職を退職して転職活動をしているのに「現在も在職中です」と偽ったり、履歴書の職歴欄に空白期間を記載しなかったりすることはNGです。
こうした虚偽の申告が発覚すると、最悪の場合、内定取り消しや入社後の懲戒処分につながる恐れもあります。企業との信頼関係を損なわないためにも、空白期間は事実に基づいて正直に伝えましょう。
まとめ
この記事では、転職によって無職期間が1ヶ月生じる場合の健康保険や国民年金、税金に関する手続きなどについて解説しました。
無職期間が短くても、必要な手続きを怠ると医療費の負担が増えたり、将来の年金受給に影響が出たりする可能性があります。
この記事で紹介した手続きに関しては、特に忘れずに行っておきましょう。
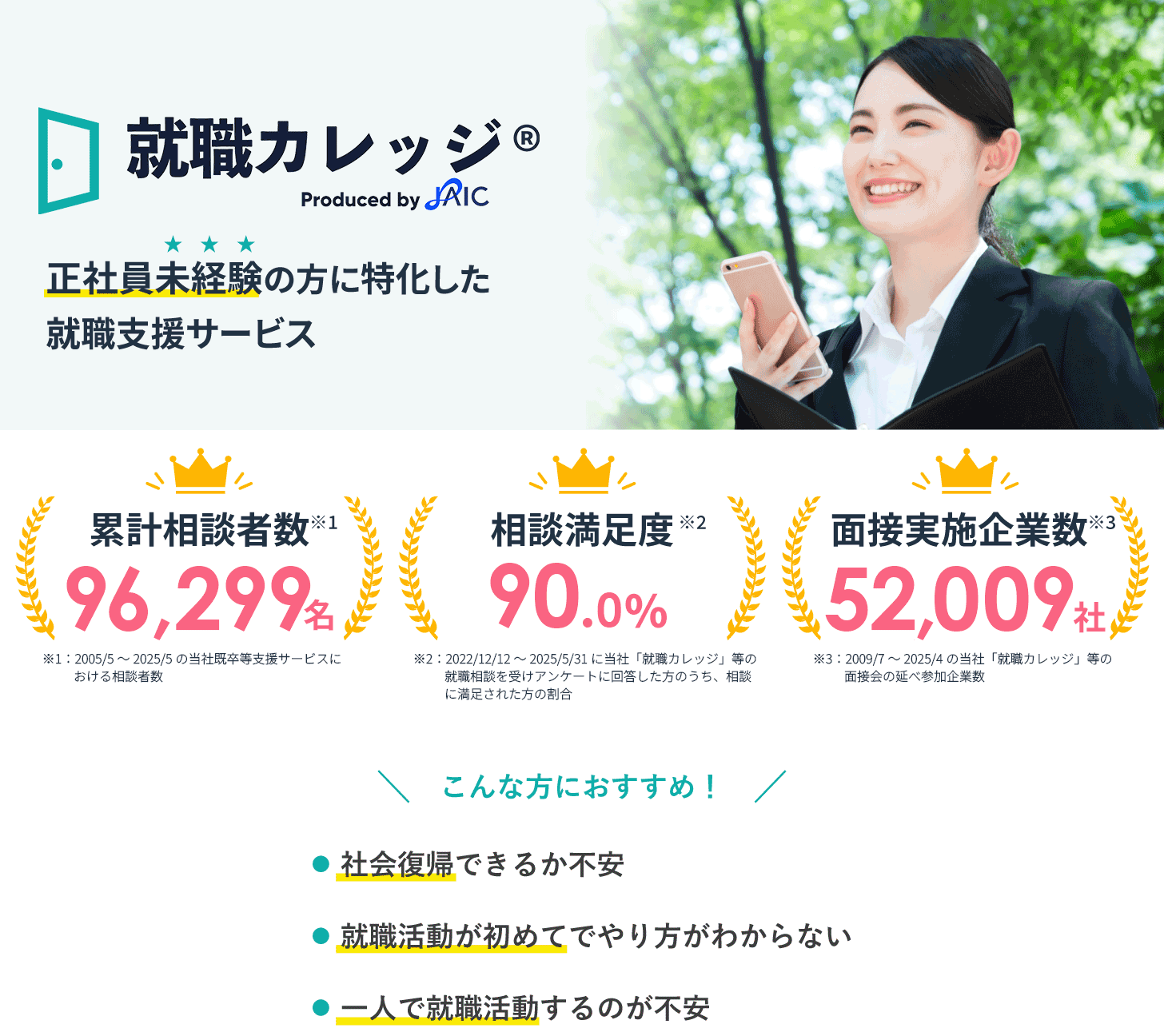
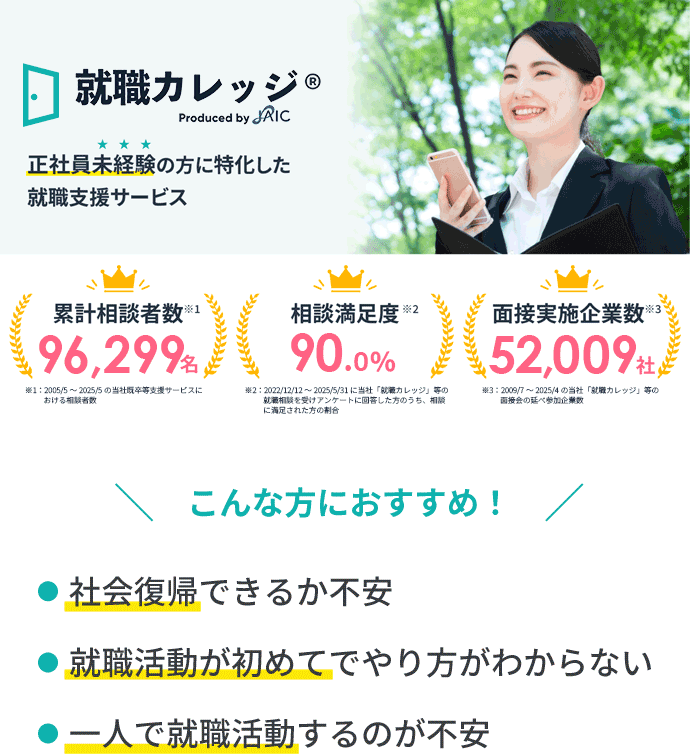

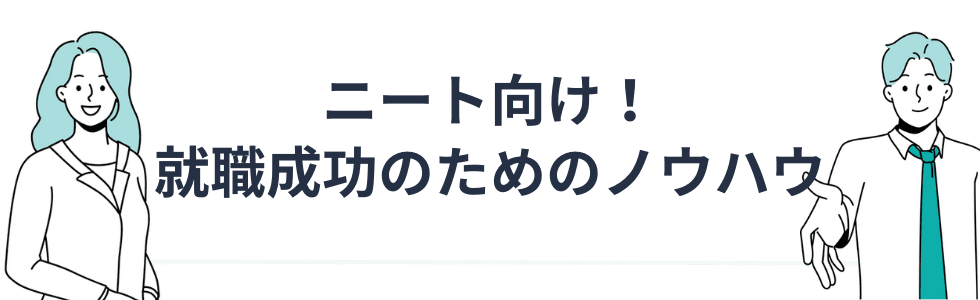
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。