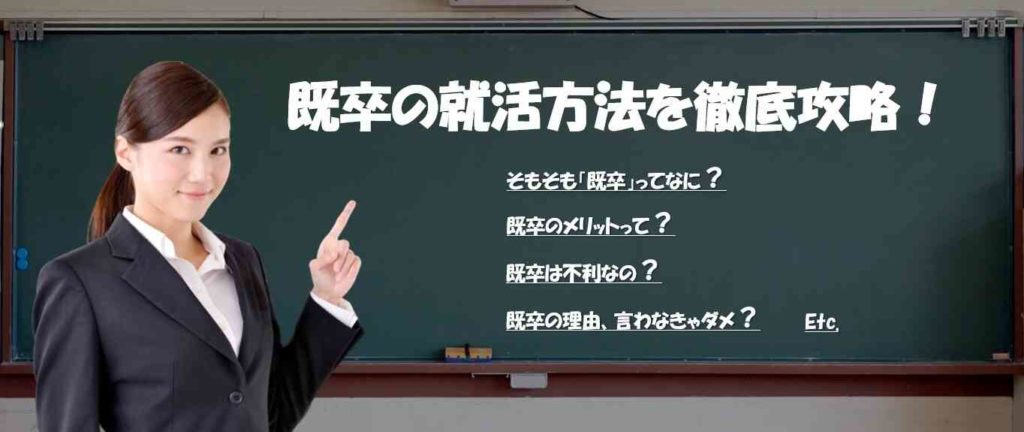
「既卒の就活は厳しいの?」「既卒就活の進め方がわからない…」新卒の場合とは異なり、既卒になると就職活動を自分ひとりで進めなければならないことが多く、戸惑う人も多いのではないでしょうか。
この記事では、既卒者の就活が厳しいといわれる理由や、既卒者におすすめする就活の進め方を紹介していきます。
既卒でも、場合によっては大手企業に就職できる可能性もあります。その方法も解説しているので、参考にして就活を進めていきましょう。
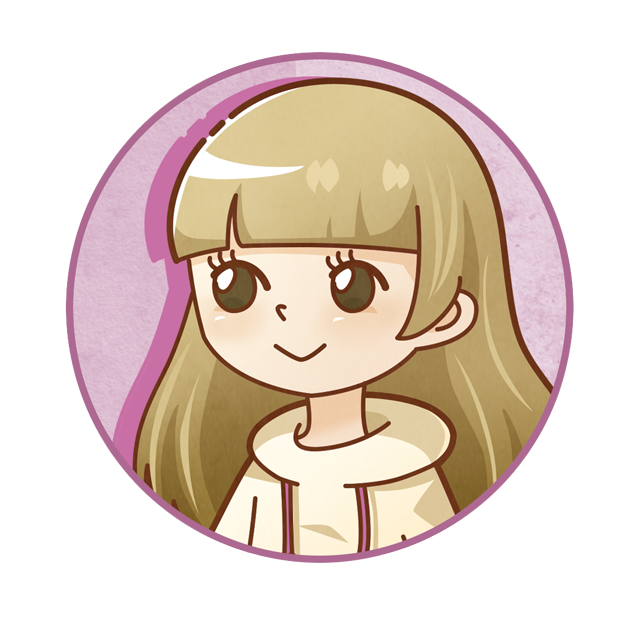
決まった就活方法がないからこそ、しっかりと進め方がを知ったうえで、就活を進めると一気に有利になるよ。紹介していくので、参考にしてみよう。
この記事の目次
既卒の就活は厳しい?
既卒の就活は、新卒と比較すると厳しいと言われています。
「2024年度 マイナビ既卒者の就職活動に関する調査」によると、2024年9月時点で、既卒者のうち、内定を「保有している」と回答したのは49.3%でした。一方、同時期の2025年卒業予定の新卒の内定率は89.8%でした。
| 内定を保有している | |
| 既卒 | 49.3% |
| 新卒 | 89.8% |
このことから、新卒と比較すると既卒の内定率は低く、就活が厳しいと言えます。
既卒の就活が厳しい理由
既卒の就活が厳しい理由には、以下のようなものがあります。
- 新卒と比べると既卒向けの求人が少ない
- 既卒になった理由が聞かれる
- 働く意欲が低いと思われやすい
- 社会人基礎力がないと思われる
- 空白期間が長いほど不利になりやすい
- 情報収集が難しい
新卒と比べると既卒向けの求人が少ない
既卒の就活が厳しい理由は、新卒と比べると応募できる求人が少ないからです。企業の多くは新卒一括採用を行っており、既卒向けの求人は限られています。特に大手企業では、新卒採用の枠が優先されるため、既卒者が応募できる機会が少ない傾向にあります。
労働経済動向調査(令和6年8月)によると、令和5年度に新卒採用を行った企業のうち、既卒者が応募可能だったのは72%でした。そのうち、既卒者の採用に至った企業は40%でした。
しかし、既卒が応募可能な企業は年々増加傾向にあります。
労働経済動向調査の令和4年と令和5年の結果を比較すると、既卒が応募可能な企業の割合や既卒の採用した企業の割合が増えていることが分かります。
| 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 既卒者は応募可能だった | 40% | 72% |
| 既卒者を採用した | 38% | 70% |
就活サイトや就職エージェントなどを活用し、既卒でも新卒枠で応募可能な求人を探してみましょう。
既卒になった理由が聞かれる
既卒の就活では、「なぜ就職しなかったのか」、「なぜ既卒になったのか」という質問がよくされます。これは、採用担当者が既卒になった理由を知ることで、応募者のキャリアに対する考え方や意欲を理解しようとするためです。
既卒になった理由を答える時は、回答内容を否定的に捉えられるリスクがあるため注意が必要です。曖昧な言い訳や消極的な理由は採用担当者にマイナスの印象を与える可能性があります。そのため、既卒になった経緯は前向きかつ合理的に説明できるように準備しておく必要があります。
就職しなかった理由に加えて、「就職しようと思った理由」「これからどうキャリアを構築したいのか」も添えると、より説得力が増します。
就活のプロに相談するのがおすすめ!
既卒になった理由の答え方が分からない、面接が不安という方は、就職支援サービスを活用し、プロに相談するのがおすすめです。
弊社ジェイックが運営する就職支援サービスは既卒の就職支援に強みを持っているため、既卒になった理由の答え方や既卒ならではの自己PRの方法についてのアドバイスが可能です。
まずは気軽に無料相談してみてください。
働く意欲が低いと思われやすい
企業側は、卒業後すぐに就職活動をしなかった理由を「働く意欲が低いのではないか」と捉えることもあるため、既卒者に対してマイナスイメージを持っています。
特に、就活が遅れた背景が明確に説明できない場合や空白期間を有効活用できていない場合に、この印象を持たれやすいです。
しかし、具体的なエピソードや行動をもって意欲をアピールすることで、働く意欲が低いという懸念を払しょくすることができます。例えば、資格の取得やスキルアップのための活動など、「その期間をどう活かしたか」を明確に伝えることで、ポジティブに評価される可能性が高まります。
社会人基礎力がないと思われる
「社会人基礎力」という言葉を聞いたことがありますか?
経済産業省が提唱したもので、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力から構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」とされています。
これは、新卒で就職した人が、入社後の数年間で身につけていくと想定されています。
引用:社会人基礎力|経済産業省
既卒者は、既卒の期間が長ければ長いほど、その力を身に着けるタイミングが遅れてしまうため、新卒者と比べて不利になると言えます。
そこで、既卒者は、応募書類の書き方や面接時のマナーなどを学び、「社会人基礎力」をスピーディーに身に着けられる「素地」がある人材だとアピールできる準備が大切になります。
空白期間が長いほど不利になりやすい
学校を卒業後、すぐに就活をせずにゆっくり過ごしてしまう人もいるでしょう。もしくは、就職活動が上手くいかず、就活が長引くこともあるでしょう。
この空白期間は「何もしていなかった時間」と見なされることが多く、採用担当者にネガティブな印象を与えることもあります。
特に、スキルアップや資格取得といった具体的な成果がない場合、その期間は「何もしていなかった時間」と解釈されるリスクがあります。
ただし、この空白期間があったからこそ気づいたことや学びを整理し、それを自己PRに繋げることは可能です。自分をよりよく知り、キャリアについて熟考する機会として捉えたことを伝えることで、むしろポジティブな評価に繋げることができます。
情報収集が難しい
既卒者の就活が厳しいと感じる理由の一つに、情報収集の難しさがあります。新卒の場合、大学や専門学校を通じた就職支援や求人情報の提供が充実していますが、既卒になると情報収集源が限られてきます。
また、既卒者向けの求人情報は中途採用枠に多く含まれている場合があるため、情報の検索や適切な企業の選定が難しくなることがあります。
そのため、就活サイト以外にも、ハローワークや民間の就職支援サービスを有効活用することが重要です。効果的な情報収集の手段を見つけ、いち早く必要な情報を確保することで、就活をよりスムーズに進められるようになります。
既卒の就活が厳しい理由と、成功させるコツについて動画で詳しく解説しているので、以下の動画もぜひご覧ください。
既卒の就活のコツ
既卒が就活を成功させるには、以下のようなコツがあります。
- 既卒になった理由をポジティブに伝える
- 自己分析をしっかりと行う
- 履歴書・職務経歴書の書き方を工夫する
- 既卒向けの就職支援サービスを活用する
既卒になった理由をポジティブに伝える
既卒就活では、面接などで「なぜ既卒になったのか」が聞かれることがよくあります。これは企業が「どのような背景があるのか」を確認し、採用の判断材料にするためです。
そのため、ネガティブな理由をそのまま伝えるのではなく、ポジティブな視点で説明することが重要です。
例えば「スキルアップのために時間を活用して資格取得を目指した」や「自分に最適な職種を見極めるためにしっかりと自己分析を行った」など、前向きな意図を盛り込むことで好印象を与えられます。前向きなアプローチが、既卒という状況を武器に変えるポイントです。
自己分析をしっかりと行う
既卒の就活では、自分の強みや価値観を明確に伝えることが成功への鍵です。まず、自分がどのような仕事や企業とマッチするのかを理解するために、徹底した自己分析が必要です。過去の経験を振り返り、目標を明確にすることで、就職活動の軸が定まります。
さらに、自己分析を行う際は、志望動機につながるエピソードや具体的な過去の成功体験を掘り下げるとよいでしょう。この工程を丁寧に行うことで、書類や面接を通じて企業に自分の魅力を的確に伝えることができます。
履歴書・職務経歴書の書き方を工夫する
既卒の就活では、履歴書や職務経歴書の内容にも工夫が求められます。例えば、空白期間がある場合でも、その期間に何を学び、どのようなスキルを身につけたかを具体的に記載することで、ポジティブな印象を与えることができます。
また、自己PRでは自分の経験や資質が応募する職種にどう活かせるかを明確に示しましょう。企業が注目しやすいよう、見やすいレイアウトや書き方にも気を配ることが大切です。これにより、書類選考の段階で既卒者への先入観を払拭し、印象アップにつながります。
既卒向けの就職支援サービスを活用する
既卒の就活は、一人で進めるよりも、就職支援サービスを活用する方がおすすめです。なぜなら、数多くの既卒者の就活を支援した中で培われたノウハウや経験からアドバイスをもらえるからです。
既卒者向けの就職支援サービスは、専任のキャリアアドバイザーが面接対策や履歴書の添削などをサポートしてくれるほか、既卒者を積極的に採用したい企業の情報を提供してくれます。
既卒者専用の求人も豊富に取り揃えているため、既卒でも応募可能な求人を効率よく見つけることができます。
既卒の就活方法

既卒者におすすめの就職活動の方法として、就職エージェント、就職サイト、ハローワークがあります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説します。
就職エージェント
就職エージェントの特徴とメリット・デメリットは、以下の通りです。
就職エージェントの特徴
民間企業が提供するサービスで、専任のキャリアアドバイザーが現状や就きたい仕事などについてヒアリングをして、希望に近い企業を紹介してくれます。
必要に応じて講座への参加や、書類添削・面接対策なども利用でき、個々に合った仕事や企業探しを、プロがサポートするサービスです。
就職エージェントのメリット・デメリット
就職エージェントを利用するメリットは、以下の内容があげられます。
- 質の高い求人の紹介が期待できる
- 専任のアドバイザーが担当するため相談しやすい
- 企業とのやり取りが不要で、就活に専念できる
一方、デメリットとしては、以下の項目が考えられます。
- エージェントや担当者と会わないこともある
- 希望に合う求人を紹介してもらえるとは限らない
- 100%就職できる保証はない
就職エージェントが扱う求人は、自社スタッフが求人企業を実際に訪問し詳細を確認しています。労働条件はもちろん、社風や社内の雰囲気などについても把握しているため安心です。
一人ひとりにプロのアドバイザーがつくため、質問や相談がしやすいのも利点です。
また、面接の日程調整や企業に聞きづらい質問などの連絡も代行してもらえるため、自分でなければできない活動に専念できます。
ただし、とにかく早く就職するよう急かしてきたり、自分の希望とまったく異なる求人ばかり紹介するエージェントや担当者には要注意。合わないと感じる場合は、担当者の変更を申し出る、他のエージェントに切り替えるなどの対応も検討しましょう。
また、エージェントを活用すると就職の成功率は上がりますが、必ず就職できると確約されているわけではない点を理解しておきましょう。
就職エージェントについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
就職サイト
就職サイトの特徴とメリット・デメリットは、以下の通りです。
就職サイトの特徴
就職サイトは、氏名や住所、年齢、学歴や職歴などを登録することで利用できます。希望職種や給料、勤務地などの条件を入力して求人検索し、気になる企業があれば、サイト上から応募できます。
大手が運営するサイトのほか、特定の業界や職種が中心、女性向け、若者向けなどの特徴を持つ就活サイトもあり、複数のサイトを併用することもできます。
就職サイトのメリット・デメリット
就職サイトを利用するメリットは、以下の内容が考えられます。
- 自分のタイミングで閲覧・応募できる
一方、デメリットとしては、以下の内容があげられます。
- 面接の日程調整などを自分でやる必要がある
- 事実と異なる/大量採用を目的とした求人もある
- 企業の詳細が分からずミスマッチも起きやすい
就職サイトはスマートフォンからでもチェックできるため、空き時間などを使って自分のペースで就活を進められます。履歴書や職務経歴書を登録すると、企業側から「応募しませんか」「面接を確約します」などの連絡が来ることもあるため、自分に合う企業が見つかる可能性もあります。
一方、すべての連絡を自分で行うため時間と手間が掛かったり、選考段階では企業に質問などがしづらいと感じることもあります。求人情報に書かれている内容は限られているため、実際に入社してから「思っていたのと違った」と感じるリスクもあります。
就職サイトについては、こちらの記事もご参照ください。
ハローワーク
ハローワークの特徴とメリット・デメリットは、以下の通りです。
ハローワークの特徴
ハローワークは国が運営を委託している、全国に設置されている職業紹介施設です。失業者しか使用できないわけではなく、求職登録をすれば誰でも利用可能です。
求人の閲覧や応募だけでなく、職員への相談やハローワーク主催のセミナー・イベント参加、条件を満たしていれば職業訓練の受講などもできます。
ハローワークのメリット・デメリット
ハローワークを利用するメリットは、以下が考えられます。
- 管轄地域の就職活動に強い
- 就職活動の一環として気軽に通うことが可能
- ハローワークならではのサービスを利用できる
一方、デメリットとしては以下の内容があげられます。
- 問題がある企業の求人も混ざっている
- 相談員の対応の質にはばらつきがある
- 正社員以外の求人も多い
ハローワークは管轄している地域の企業の求人を多く扱っているため「地元で就職したい」人にとっては便利です。
職業訓練など、就職するためのスキルを身につけられるサービスを活用するのもよいでしょう。
ただし、企業側が求人情報を出したり採用するのも無料であるため、人材採用に経費をかけられない企業や、労働環境や条件面で見劣りする企業などの求人も混ざっている点は否めません。
相談員も求人内容の詳細や社内の雰囲気までは把握していないこともあり、事前に知っておきたい情報が得られないケースもあります。また、正社員の求人に特化しているわけではなく、パートなどの求人数も多めです。
ハローワークを利用した就職方法は以下の記事でも解説していますので、こちらもご参照ください。
企業HPなどからの直接応募
企業に直接応募する場合の特徴とメリット・デメリットは以下の通りです。
直接応募の特徴
直接応募とは転職エージェントやハローワーク経由ではなく、企業に直接応募することです。
具体的には、企業のWebサイトの採用ページから応募を行う方法と、企業に書類を郵送する方法があります。
直接応募のメリット・デメリット
直接応募のメリットは以下があげられます。
- 意欲を評価されやすい
- 転職サイトにはない企業に挑戦できる
- 意欲を評価されやすい
- 転職サイトにはない企業に挑戦できる
一方で、以下のデメリットも考えられます。
- 既卒を募集していないこともある
- 企業との条件交渉はすべて自分で行う
特に企業のWebサイトでは既卒募集していないことが多いため、既卒の場合、直接応募はあまりおすすめできません。
既卒の就職活動の方法については、以下の記事も参考にしてください。

既卒就活のやり方はいくつもあるけど、自分に合った就活方法で進めていこう!
既卒就活で必要な準備

既卒就活をはじめる前に、必ずやっておきたい準備について解説します。
今すぐに、できることから取り組んでみましょう。
仕事の種類を知る
総務省「日本標準職業分類」を参照すると、日本にある職業の数は1万7209種類が想定されます。ひとことで「仕事をする」「企業に就職して働く」といっても、世の中には膨大な数の仕事があるのです。まずは職業の一覧などを参考に、どんな仕事があるのかを知るのが第一歩です。
たくさんの仕事の中から、ひとつでも自分に合ったものが見つかればよいわけですから、気軽に楽しみながら調べてみましょう。
適性検査を受けてみる
インターネットでの適性検査や適職診断などを受けてみて、自分にはどのような特性があり、どんな仕事であれば能力を発揮できそうかをチェックしてみましょう。
検査データの統計をもとにあなたの性質に適した職業が提案されるため、一定の説得力があります。ただし適性検査や適職診断は数多く存在するため、客観的に評判の良い検査・診断など、信頼性の高いものをリサーチして利用しましょう。
自己分析をしてみる
これまでの人生を振り返り、転機となったり印象深かった出来事、成功・失敗の経験などについて、当時の気持ちやそこから得たものなどを書き出してみましょう。そうすることで、自分の価値観や大切にしていること、得意なことや苦手なことが見えてきます。
人の本質は、あまり大きくは変わりません。過去を振り返ることで、自分の考え方や行動パターンなどが見えてくるため、今後のキャリアを考える上で重要な要素になります。
履歴書・職務経歴書を書いてみる
最初は見よう見まねでよいので、履歴書と職務経歴書を書いてみましょう。
いくらでも書き直しができるため、まずは自己PRや趣味・特技、アルバイトの経験がある場合は仕事内容やそこで得たことなどを書きます。書き出すことで自分の特徴・経験の「棚おろし」ができ、今後の就職活動に役立ちます。
既卒であることから自信を失っている人もいるかも知れませんが、自分の強みや個性・アピールできるところが見えてくることもあります。
以下の記事では履歴書の書き方を解説しているので、こちらも参考にしてください。
面接対策をする
既卒者が就活をするとき、既卒である理由は100%聞かれると思っておいたほうがよいでしょう。たとえば、面接では以下のようなことを聞かれる可能性があります。
- 在学ちゅに就職活動はしていたのか/していない場合、それはなぜか
- 卒業してからこれまで何をしていたのか
- 本気で就職する気はあるのか
- なぜ既卒から正社員を目指そうと思ったのか
既卒者の立場からすると、厳しく感じる質問が多いかもしれません。しかし企業は採用にコストをかけているため、ミスマッチや早期離職をできるだけ避けたいと考えています。また、一度正社員採用をするとよほどのことがない限り辞めさせることができないため、問題のありそうな人は入れたくないという面もあります。
そのため、既卒者の採用を検討する際は新卒や通常の転職者以上にシビアな目で見ていて、突っ込んだ質問をして本気度を確かめようとする傾向があります。
上記で紹介している質問の中から、回答例をご紹介します。
【例1】Q:在学中に就職活動はしたのか/していない場合、それはなぜか
A:就活サイトに会員登録して企業情報の収集や自己分析をおこないましたが、その時に「自分がやりたい仕事が何なのか?」が見えなくなり、結局、就職活動はおこないませんでした。自己分析や企業研究が不十分だったことが原因だと考えています。
自分が本当に取り組みたい仕事や大切にする価値観、強みなどを考え、その結果から自分のやりたいことが明確になりました。それを踏まえて、就職活動を再び始めることにしました。
【例2】Q:卒業してからこれまで何をしていたのか
A:両親に迷惑はかけられないと思い、生活と就職活動の費用を稼ぐためにアルバイトをしていました。
アルバイトと並行して就活サイトを利用して企業情報の収集もおこない、ようやく自分がやりたい仕事が見つかったので、御社の求人に応募いたしました。
上記のように、想定される質問に対して説得力ある回答ができるよう、自分なりに準備してみましょう。
既卒の面接について、詳しくは以下の記事をご参照ください。

まずは、自分の就活の軸を定めること。入社はゴールじゃなくてスタートだからこそ、改めて考えていきたいね。
既卒就活を成功させるポイント
既卒の就活におけるポイントと、その対処法も準備しておきましょう。
受ける企業数は一定以上は決めておこう
就職ジャーナル「内定した先輩たちに聞きました。 面接、どのくらい通過するもの?」によると、内定をもらった人のうち、面接を受けた企業数は以下の通りです。
- 1~5社:36%
- 6~10社:22%
- 10~20社:20%
マイナビ転職「【転職活動、何社応募した?】平均応募社数や、選考通過・内定の確率はどれくらい?」によると、20代の転職者が応募した企業の平均社数は、以下の通りです。
- 20~25歳:6.3社
- 26~30歳:7.1社
既卒の場合、新卒や転職者と比較すると選考が厳しくなる可能性もあるため、企業数を絞りすぎるのも危険です。しかし、やみくもに応募数を増やしても、かえって個々の連絡や準備に時間が掛かってしまい、就活の期間が長引く恐れもあります。
少なくとも5社以上、多くても20社程度を目安に考えておくとよいでしょう。
私たちジェイックの面接会では、約20社の企業と同時に面接ができます。そこに参加する企業は「良い人材であれば、既卒であっても積極的に採用したい」と考えています。効率よく、採用意欲の高い企業に出会えます。

一般的な就活事情を知っておくと、臨機応変に対応することができるようになるよ。準備して就活に挑んでいこう!
既卒の仕事選びについて、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
大手企業・有名企業ばかり受けない
応募する企業を大手有名企業に絞らず、視野を広げて就活することも大切です。
大手有名企業は倍率が高いうえに、高学歴の新卒だけでなく海外留学や起業して成果を上げた優秀な既卒がライバルになることもあるため、なかなか内定獲得に繋がらない可能性があります。大企業に就職したいのであれば、一度、同業界の会社で経験を積んでから、再度挑戦してみると良いでしょう。

既卒からいきなり大手企業への就職は難しいみたい。でも、正社員就職して、経験を積めば転職も可能だから長期的な目線で進めていきたいね。
また、大企業のみが優良企業とは限りません。全国的に有名でなくても業界ではトップクラスの企業や大企業の子会社、ベンチャー企業などにも目を向けて、自分の可能性を広げましょう。
企業選びのコツを以下の記事で紹介しているので、こちらも参考にしてください。
長期的なキャリアを描いて入社しよう
「自分には突出した経歴や実績なんて無い」という人も、それだけであきらめてしまうのは早いかも知れません。
なぜなら、既卒からすぐに大手企業に就職できなくても、いったん同業界の中小規模の企業に就職し、そこで数年間の経験を積んで実績をあげてから、あらためて大手企業の門をたたくことも可能だからです。
総務省の統計によれば、日本でも「転職をする人の数」は増加傾向にあります。2019年には351万人と、比較可能な2002年以降で過去最多となりました。また、「より良い条件の仕事を探すため」に前職を離職した転職者が2013年以降増加傾向で推移しており、2019年は127万人と過去最多になりました。
今すぐは難しくても、数回先の転職で大手企業を目指すためには、そこから逆算した長期的なキャリアの計画を立ててみましょう。
ただし、直近で就職する企業や、そこでの業務を軽んじていては、長期的な目標に到達できません。「今、自分がいる場所」で他者よりも実績をあげて評価されてこそ、さらに高い目標への道が開かれることを理解しておきましょう。
できることを増やし、スキルを磨く
就職した企業での実績や経験をもとに、いずれ大手企業を目指す方法をご紹介しましたが、それ以外にもすぐにはじめられる事はあります。
たとえば、自分が目指したい業界・企業で求められるスキルに関する資格の勉強をはじめてみるのも一案です。実際にその資格を取得しているのがベストではありますが、まだ取得していなくても「スキルアップに前向きに取り組んでいる姿勢」や「勉強を通じて多少の基礎知識をすでに持っている」ことが、書類選考や面接で企業側からプラスの評価になりえます。
実際に就職で有利になる資格を3つ紹介します。
①TOEIC
インバウンドの機会が増え、これからの時代は英語スキルが必須となります。
TOIECのスコア700点以上を採用条件としている企業などもありますので、企業によって求められているレベルを確認しておきましょう。
②日商簿記
企業の決算書や財務体質がわかるようになります。
1~3級がありますが、3級は最も初歩的な級となり、経理未経験者でも比較的取りかかりやすいと言えます。ビジネスや経済において必要な基礎的な知識を身につけることができるため、自分に自信をつけるために取得するのもおすすめです。
③MOS
Microsoft Officeの認定資格となります。
Excel、Word、Power Pointをビジネスツールとして利用している企業は多く、取得する価値は十分にあります。スマートフォンの普及によってPC離れが進んでいると言われており、基本的なPCの操作ができることの証明にもなります。
「今の自分にできること」からスタートして、できることやスキルを少しづつでも増やしていきましょう。
既卒がバイトをする場合の仕事の選び方や注意点については、以下の記事を参考にしてください。
熱い思いをアピールする
企業によっては、既卒に対して「働く意欲が低いのではないか」と懸念を持っていることもあるため、既卒は自己PRや志望動機で仕事への熱意を伝えることが重要です。
事業内容や企業理念などから「その企業で働きたい理由」「企業にどう貢献したいか」「将来の目標」を具体的に説明することで、会社への熱い思いをアピールすることができます。
併せて、前項で紹介したスキルアップへの取り組み姿勢も伝えると、より好印象です。
既卒就活におすすめの時期はある?
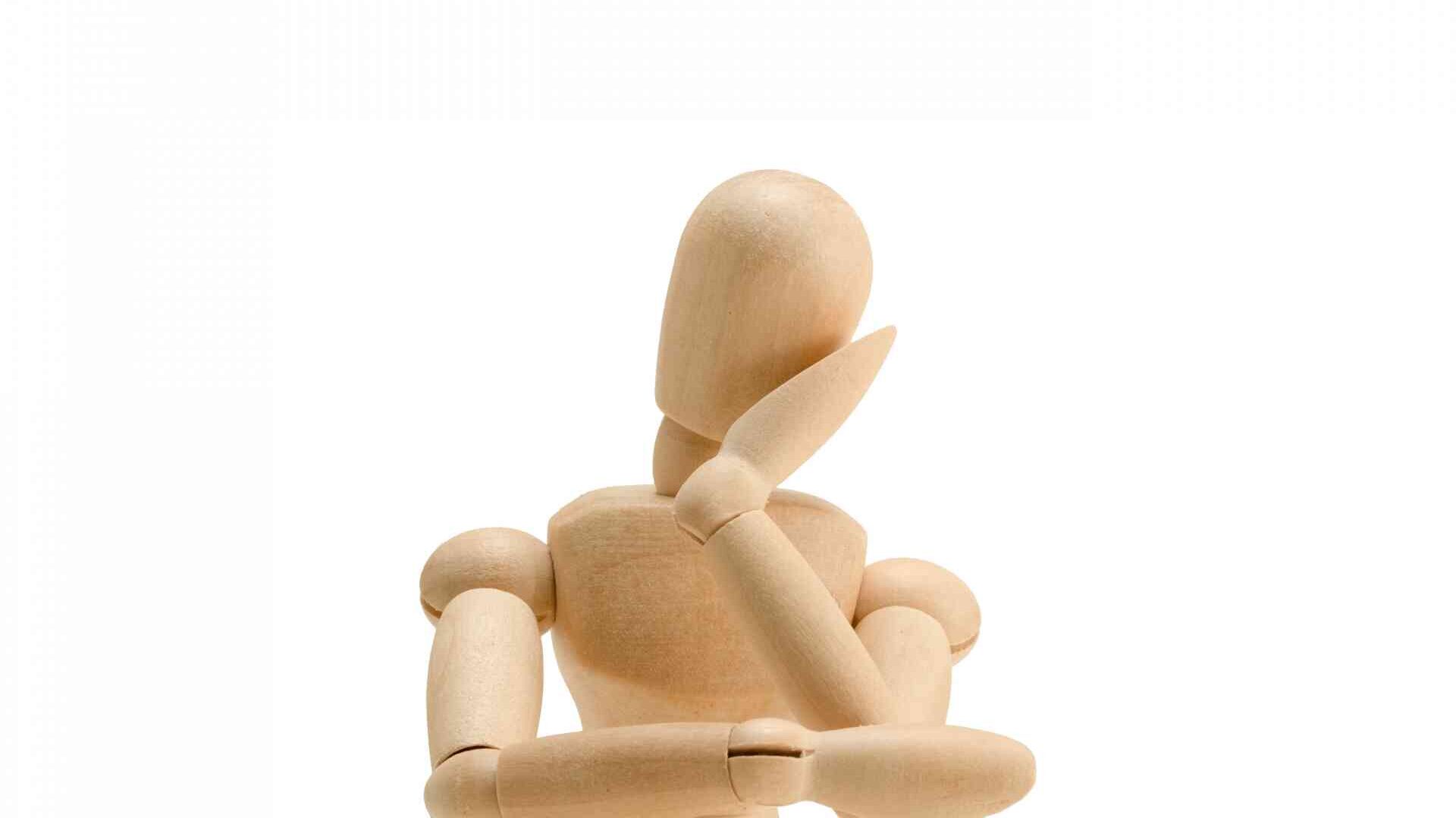
最後に、既卒者の就活のポイントについて時期別にご紹介します。結論から言うと、既卒の就活に適した時期というものはなく、いますぐに行動することで成功率が高まります。
時期によって多少状況は変化しますが、よい企業や求人は、人材を採用するとすぐに募集を終えてしまいます。タイミングを逃さず、なるべく早い段階で就活を開始しましょう。
4月~6月に就活をする場合のポイント
4月~6月の就活は、以下のような特徴があります。
- 4月に入社した新卒の教育・研修をしている企業が多い
- 新卒の早期離職などに備え、中途採用を実施する企業もある
- 在職者は仕事が忙しい時期のため、転職者(ライバル)がやや少ない
新卒のほとんどは4月入社のため、企業は新卒への教育や研修などに追われていることが多くなります。ただし入社まもない段階で離職する新卒者もいるため、中途採用を実施する企業も一定数あります。
企業で働いている人は忙しくしていることも多い時期のため、転職活動をする人はそこまで多くはないといえます。
7月~9月に就活をする場合のポイント
7月~9月の就活は、以下のような特徴があります。
- 新卒向けの研修などが落ち着き、中途採用を検討する企業が増える
- 夏季休暇やお盆休みなどで、採用選考に時間がかかることも
- 新卒者の内定辞退に備え、未経験者採用をする企業もある
夏の時期にボーナスを受け取ってから辞める人が出てくる一方で、会社自体が夏休みに入ったり、採用担当者が休暇を取得したりすることも多いため、採用選考自体は時間を要することがあります。
新卒向けに内定を出し終わっている企業も多い反面、内定辞退などを考慮して、新卒以外の採用活動を実施する企業もあります。
10月~12月に就活をする場合のポイント
10月~12月の就活は、以下のような特徴があります。
- 企業・個人ともに「年内に採用・就活を終えよう」と動く傾向がある
- 年末年始は、採用選考がストップするのが一般的
- 年末まで勤めて、その後やめる人も一定数いる
企業側・就活をする人の両者とも、きりのよい年内に採用・就活を終えたいという想いで、集中的に活動する時期でもあります。
年末年始は休みになるため、12月に入ると採用選考のスピードがやや落ちる可能性があります。在職者は、冬のボーナスをもらったタイミングで辞めるという人も出てきます。
1月~3月に就活をする場合のポイント
1月~3月の就活は、以下のような特徴があります。
- 4月入社のチャンス/あえて4月以前入社を目指すのも◎
- 2~3月は、内定をもらっていない学生のラストスパートの時期
- 春になると人事が忙しくなるため、未経験採用などの動きが鈍くなる
この時期に内定が決まると、新卒が入る前のタイミングで入社するか、4月入社かのいずれかになるでしょう。きりが良い4月入社を希望する人もいれば、新卒と比較されることを避けるため、あえて4月より前に入社してなじんでおきたいという人もいます。
2~3月になると、卒業を控えた現役の大学生がライバルになる可能性もあるため、早めの行動がおすすめです。

既卒のメリットは、新卒と違って4月入社ではないこと。既卒の強みを生かして就活を進めていこう。
既卒就活の体験談 井原さんの場合
既卒就活で第一志望の会社に就職を成功させた井原さんの体験談です。
井原さんは、大学在学中に1社から内定をもらっていましたが、大学の単位を1つ落としたことがきっかけで留年となりました。留年が決まったことで内定は辞退して、9月に卒業できました。
卒業するタイミングで就職について調べていた際にジェイックを知り、ジェイック主催の「就職カレッジ」に参加しました。就職カレッジに参加することで、同じ目標に向かって頑張る仲間を見つけることができ、前向きに就職活動に取り組むことができたそうです。当時親しくなった友人とは、今でもご飯に行く仲だそうです。
カレッジ終了後は、第一志望だった車の機械部品を取り扱う専門商社に就職が決まりました。休みがしっかりしているところと、親会社が大きく将来的に安定しているところが決め手になったそうです。
まとめ
既卒の就活は簡単ではありませんが、既卒であることをそこまでネガティブに捉えない企業も一定数存在します。既卒の方は新卒にコンプレックスを感じることもあるかもしれませんが、新卒も既卒も、社会人経験がないという点では同じです。これからの長いキャリアのスタートラインに立つべく、前向きに行動しましょう。
既卒の就活の方法は人それぞれで「これをやれば絶対に成功する」という保証はありません。しかし、何をしたらよいかわからない方は、正しい就活の方法やスキル・知識を身につけて挑むのがおすすめです。ジェイックには、既卒の方の正社員就職実績が豊富にあります。既卒でこれから就活を考えている方は、お気軽にジェイックのキャリアアドバイザーへご相談ください。
既卒の就活に関するよくある質問
既卒だからと就職をあきらめる必要はありません。既卒者を採用する企業は増加傾向にあります。既卒からの就職は可能であり、人生終了というには早計かもしれません。
既卒の就活は、就職はしたいけれど何から就職活動をスタートしたらよいのかわからないという方もいるかもしれません。ジェイックでは、5日間の研修を通して就職活動を進めることができるため、そのような方に向いています。まずは「就職相談」にお申込みいただき、ぜひお話をお聞かせください。
もっともおすすめの方法が、転職エージェントの利用です。ジェイックのサービスをご利用いただければ、研修期間から、早い方であれば約3~4週間で就職が決まっています。そのため、はじめての正社員就職を目指す既卒の方にも最適です。









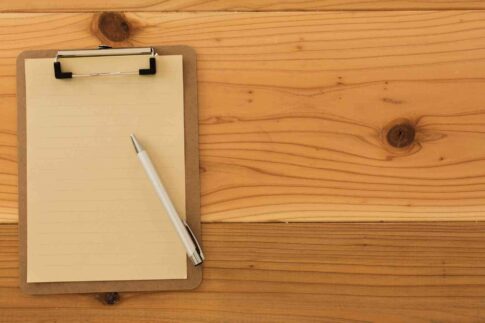




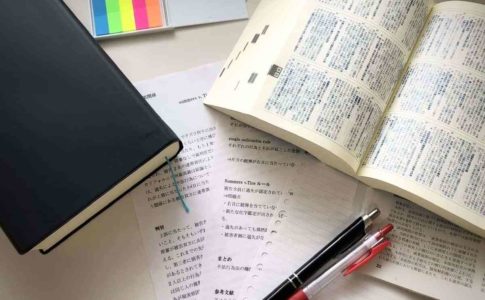






























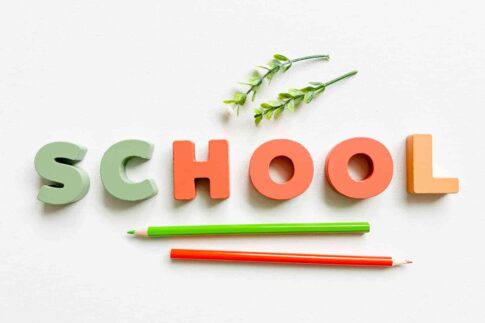
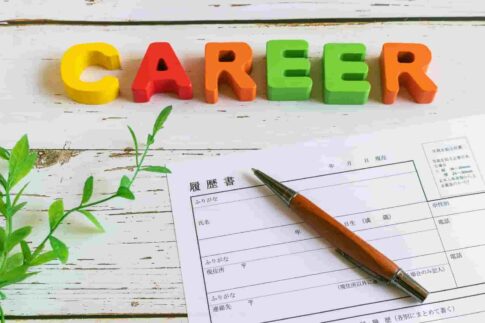








既卒になると、就活をどうやって進めればいいかわからない人が多そうだね。