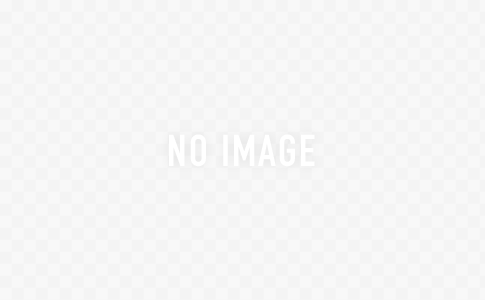フリーターとアルバイトの違いについて、疑問に思ったことはありませんか。「どちらも正社員ではない働き方だけど、具体的に何が違うの?」と考える人も多いでしょう。
本記事では、フリーターとアルバイトの定義や、それぞれの一般的なイメージ、正社員や他の非正規雇用との違いについて解説しています。
それぞれの違いを理解すると、自分に合った働き方を見つけやすくなり、将来のキャリアプランに役立ちます。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
フリーターとアルバイトの定義を解説
フリーターとアルバイトの違いは、その定義です。以下の内容について、それぞれ見ていきましょう。
- フリーターは15歳~34歳の正社員ではない若者
- アルバイトは短期的な雇用形態
- フリーターとアルバイトに法的な違いはない
フリーターは15歳~34歳の正社員ではない若者
厚生労働省では、フリーターの定義を「正社員ではない15歳から34歳の若者」としています。そのため「35歳以上で正社員ではない人」はフリーターとは呼ばず、非正規雇用者や契約社員、派遣社員などに分類されるのが一般的です。
フリーターには以下の特徴があります。
- 学生ではなく、アルバイトやパートで生計を立てている
- 自由な働き方を求める傾向がある
- 収入が安定しないため、将来に不安を感じることも多い
上記のように、フリーターは特定の年齢層に限定された働き方といえます。
アルバイトは短期的な雇用形態
アルバイトは雇用形態の一種であり、契約期間が比較的短い点が特徴です。「学生が学業と両立しながら働く」「会社員が副業として働く」などのケースが多く、自身の都合に合わせて稼げます。アルバイトの特徴は以下のとおりです。
- 短期間の雇用契約が多い(1日~数ヶ月単位が多い)
- 学生や主婦、シニア層も含まれる
- 一時的な収入源とされることが多い
また、学生や主婦、会社員など幅広い年齢層を指すため、フリーターのような年齢制限はありません。
フリーターとアルバイトに法的な違いはない
フリーターとアルバイトには、法律上の明確な違いはありません。厚生労働省の定義によると、雇用期間や労働時間、労働日数によって「常用労働者」と「パートタイム労働者」に分けられます。
常用労働者(1または2のいずれか)
- 期間を定めていない、または1ヶ月以上雇われている人
- 調査日前の2ヶ月それぞれの月に各々18日以上働いた臨時または日雇労働者
パートタイム労働者(1または2のいずれか)
- 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも少ない人
- 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じだが、1週間の所定労働日数が一般の労働者より少ない人
フリーターとアルバイトの場合、ある程度の期間や時間、日数を働くと正社員と同様に「常用労働者」と見なされるケースがあります。
フリーターに対する一般的なイメージ
フリーターは「自由な働き方を選択する若者」として肯定的に見られる一方で、不安定な収入や社会的信用の低さが問題視されることも少なくありません。ここでは、フリーターに対する一般的なイメージについて詳しく解説します。
- 自由な働き方を求める若者と思われる
- 不安定な収入が強調されがち
- 社会的信用が低いとされる
- 若年層の雇用問題として議論される場合が多い
自由な働き方を求める若者と思われる
フリーターに対する一般的な印象は「自分の時間を大切にしたい」「好きな仕事だけをしたい」「趣味の時間を多く取りたい」など、あえて正社員にならずに、自由な働き方を求める若者と思われるケースが多くあります。
クリエイティブな仕事や起業を目指している人の中には、フリーターを続けながらスキルアップを図る人もいます。そのため「個人のスキルや経験を活かしつつ、自由な生き方を実践している」という肯定的なイメージを持たれることもあるのです。
不安定な収入が強調されがち
シフト制で働くフリーターが多く、勤務時間が減ると収入が突然減少するリスクがあるため、不安定な収入が強調されがちです。また、店舗の経営状況や会社の方針によって、契約を急に打ち切られる可能性もあります。
さらに、最低賃金に近い仕事の場合は「どんなに働いても生活が厳しい」と感じる人も多くいます。そのため、フリーターは「収入が安定しない」「将来に備えるのが難しい」といったネガティブなイメージを持たれやすいのが現状です。
社会的信用が低いとされる
フリーターは毎月の収入が安定しづらく、雇用も不安定なため、社会的信用が低いと見なされる場合があります。安定した収入がある正社員と比べて、返済能力が低いと判断されやすいためです。
そのため、クレジットカードや各種ローンの審査に通りにくいケースが多くあります。また、賃貸住宅を借りる際には保証人を求められたり、契約を断られたりする場合もあります。このような理由から「フリーターは社会的信用が低い」というイメージが定着しているのです。
若年層の雇用問題として議論される場合が多い
フリーターが若年層の雇用問題として議論される理由は、正社員になれないというネガティブなイメージだけでなく、不安定な収入や社会的孤立、若者自身の意識の変化など、複合的な要因によるものです。
非正規雇用の若者が増えると消費が伸び悩むうえ、国の税収が減少するリスクがあるため、経済全体にも悪影響を及ぼす可能性があります。このような背景から、政府や企業による就職支援策が求められており、若年層の雇用問題の一環としてフリーターの存在が議論されるのです。
アルバイトに対する一般的なイメージ
アルバイトは短時間労働や補助的な業務を行う働き方として、多くの人に親しまれています。フリーターとは異なり、学業や本業と両立しながら働くことを前提としているケースが多く、比較的気軽に始められる点が特徴です。以下の点についてそれぞれ見ていきましょう。
- 学業や本業の合間に短時間で働く
- 短期的な雇用形態が多い
- 正社員に比べて責任が軽い
- 収入が安定していない
学業や本業の合間に短時間で働く
アルバイトは学生や主婦、副業を持つ社会人にとって、効率的に収入を得られる手段です。時間の融通が利きやすく、自分のライフスタイルに合わせながら稼げます。働くタイミングは以下の場合が一般的です。
- 学生:授業の前後や週末、学校の長期休み
- 主婦:子どもが幼稚園や学校に行っている間
- 副業を持つ社会人:会社帰りや週末
「学業や本業に影響が出ないように短時間で働く」「扶養内に抑えるため、働く時間を調整している」など、自分の都合に合わせてシフトを入れられるのが魅力の1つです。
短期的な雇用形態が多い
正社員とは異なり、アルバイトは長期的な雇用を前提としていないケースが多いため「短期間で働くもの」というイメージが定着しています。
例えば、年末年始の販売スタッフ、夏休みのプール監視員、イベント設営スタッフなど、一定期間のみ人手が必要な場合は、同じ職場で長期間働くことが難しい場合もあります。
一方で、短期間で多くの職種を経験できるため、コミュニケーション能力や問題解決力、適応力などのスキルを身につける機会にもなるでしょう。
正社員に比べて責任が軽い
アルバイトは補助的な役割を担うケースが多く、正社員に比べて業務の責任が軽いとされています。特に、接客業や販売業ではマニュアルに沿った業務が多く、未経験者でも比較的取り組みやすいと言われています。
また、会社の経営や売上の責任に関わることがないため、その分ストレスも少なめです。一方で、昇進の機会があまりなく、キャリアアップも限定的です。また、会社の指示どおりに働くことが求められるため、自身のスキルを活かして自発的に進められる機会は少ない傾向にあります。
収入が安定していない
アルバイトの給与は時給制が基本のため、シフトの増減によって収入が大きく変わります。閑散期や業績の影響でシフトを減らされる場合があるため、長期的に収入の安定を求めるには不向きなケースがあります。
また、正社員と違ってボーナスや昇給がほとんどないため、アルバイトのみで安定した生活を求めるのは難しいかもしれません。さらに、同じ職場で長く働いてもキャリアアップが期待できない場合が多く、収入を増やすために別の仕事を掛け持ちすることもあります。
35歳以上のフリーターは「高齢フリーター」
35歳以上のフリーターは一般的に「高齢フリーター」「中高年フリーター」と呼ばれています。日本では、フリーターの定義は「15歳から34歳までの若年層」とされているため、35歳を超えると「非正規雇用者」など、別のカテゴリーに分類されるのが一般的です。
35歳以上のフリーターの特徴は次のとおりです。
- 10代や20代の頃からフリーターを続けている
- 過去に正社員を経験したが、退職してフリーターになった
- 家庭やライフスタイルの事情でフリーターを選択した
「35歳以上のフリーターについて詳しく知りたい」「将来のリスクを回避するためにはどうしたらいいの?」と思った場合は、以下の関連サイトをご覧ください。
フリーターとアルバイト以外の非正規雇用の違い
フリーターとアルバイト以外にも、さまざまな非正規雇用の形態があります。それぞれの特徴や違いを解説します。
- フリーターとパートタイムの違い
- フリーターと契約社員の違い
- 派遣社員は派遣会社と雇用契約を締結した社員
- 嘱託社員は有期雇用で専門業務を担当する社員
- フリーランスは個人で仕事を請け負う働き方
- ニートは働いていない状態
フリーターとパートタイムの違い
フリーターとパートタイムの間には法律上の明確な違いはなく、いずれも「非正規雇用」に該当します。
フリーターは「正社員としての雇用契約を結ばず、主にアルバイトやパートタイムの仕事で生計を立てる15歳〜34歳の若者」を指します。働く時間や曜日に柔軟性があるため、さまざまな仕事を経験できるのがメリットです。
一方で、パートタイムは「平日の昼間など、特定の時間帯に働く主婦や主夫」を指すのが一般的です。子どもが幼稚園や学校に行っている間に働くケースが多く、時間が限られているため、フリーターよりも働き方の自由度が低い場合があります。
フリーターと契約社員の違い
契約社員は、一定期間の雇用契約を企業と締結し、その期間が終了すると契約更新または終了が決まる雇用形態です。特定の業務やプロジェクトに従事する場合が多く、契約期間が明確に定められているのが特徴です。
契約社員は契約期間が定められているものの、給与は月給制が多く、社会保険や雇用保険に加入する義務があるため、フリーターよりも収入が安定しているメリットがあります。契約更新を続けると同じ職場で長期間働けますが、更新が保証されていない点がデメリットです。
派遣社員は派遣会社と雇用契約を締結した社員
派遣社員は派遣会社と雇用契約を締結しつつ、派遣先の企業で働く雇用形態です。派遣会社が派遣社員に給与を支払い、福利厚生の管理も行います。
フリーターやアルバイトと異なり、派遣会社が求職者と企業をマッチングするため、就業サポートが充実しています。また、時給が高めに設定されるケースが多いため、効率的に収入を得られるのがメリットです。
ただし、契約期間が決められているため、同じ職場で長期間働けない点がデメリットです。さらに、職場によっては業務内容が正社員とほとんど変わらないにもかかわらず、昇進や昇給の機会が少ない場合もあります。
嘱託社員は有期雇用で専門業務を担当する社員
嘱託社員は企業と有期雇用契約を結び、特定の専門業務を担当する働き方です。定年退職後の再雇用や、特定のスキルを持つ専門職として採用される傾向にあります。フリーターやアルバイトと比べて収入が安定しているケースが多く、社会的信用も高いのが特徴です。
しかし、雇用期間が決められているため、契約終了時は次の仕事を探さなければならない点がデメリットです。また、企業側が求める専門知識や経験が重要視されるため、未経験者が就くのは難しい場合もあります。
フリーランスは個人で仕事を請け負う働き方
フリーランスは企業に雇用されず、個人で仕事を請け負う働き方です。自由度が高く自分のペースで働ける一方で、収入が不安定になりやすく、福利厚生の保障がない点がデメリットです。また、働く環境によっては孤独を感じやすい場合もあります。
人間関係のストレスが少ないメリットはありますが、仕事の管理から契約交渉、確定申告までを自身で行う必要があります。成功すれば高収入を得られる可能性がありますが、仕事が途切れるリスクを考え、複数の収入源を確保することが大切です。
ニートは働いていない状態
ニート(NEET)は「Not in Education, Employment or Training」の略で、教育を受けておらず、就業や職業訓練も行なっていない若者(主に15歳から34歳)を指しています。
ニートの状態が長引くと就職が難しくなるため、家族や支援機関のサポートを受けながら、働くきっかけを見つけることが大切です。まずは職業訓練やアルバイトを通じて経験を積み、社会との接点を少しずつ増やしていくことが重要です。
フリーターやアルバイトと正社員の違いを解説
フリーターやアルバイトと正社員では、雇用形態や待遇に大きな違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説します。
- 正社員は長期的な雇用契約を結んだ労働者
- 正社員は月給制が一般的
- 福利厚生や各種手当が充実している
- 昇進やキャリアアップが期待できる
- 社会的信用が高い
正社員は長期的な雇用契約を結んだ労働者
正社員は、企業と長期的な雇用契約を結んでいる労働者を指しています。契約期間の制約がなく、安定した給与や雇用が保証されているため、生活設計がしやすいのが特徴です。また、将来的なキャリアアップのチャンスも広がります。
さらに、多くの企業では正社員向けの研修や教育制度が充実しており、長期的なスキルアップも可能です。一方で、フリーターやアルバイトは短期契約が多く、収入や雇用が不安定になりやすいため、将来の計画を立てづらいデメリットがあります。
正社員は月給制が一般的
正社員の給与は月給制が一般的で、一定額が毎月支給されるため、安定した収入を確保しやすいのがメリットです。
また、ボーナスや昇給の機会があり、長期的な収入アップが期待できるのも特徴です。業績に応じたインセンティブ制度を導入している企業では、成果を上げることでさらに高収入を得るチャンスもあります。
一方、フリーターやアルバイトは時給制が多く、勤務時間によって収入が変動するため、場合によっては収入が大きく減る可能性があります。
福利厚生や各種手当が充実している
正社員は、企業から福利厚生や各種手当を受けられるのが特徴です。社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険など)に加入できるため、病気や老後の生活に備えやすいほか、退職金制度や住宅手当、交通費補助など、生活を支える制度も充実しています。
さらに、企業によっては資格取得支援や研修制度が整っており、働きながらスキルアップできるのもメリットです。一方、フリーターやアルバイトは、こうした福利厚生を受けられないケースが多く、将来の生活に不安を感じることもあります。
昇進やキャリアアップが期待できる
正社員は勤続年数や業績に応じて昇進や昇給の機会があるため、長期的なキャリアアップが可能です。また、企業によっては社内公募制度を導入しており、希望する部署への異動や新たな職務に挑戦するチャンスもあります。
一方で、フリーターやアルバイトは短期契約が多く、業務範囲が限定されているため、キャリアアップの機会が限られます。時給が多少上がることはあっても、企業内で責任のあるポジションに昇進するケースは少ないのが現状です。
社会的信用が高い
正社員は安定した雇用と収入が保証されているため、社会的信用が高いとされています。企業と長期的な雇用契約を結び、毎月一定の給与が支払われるため、クレジットカードの審査や住宅ローンの契約が通りやすく、賃貸契約の手続きもスムーズに進みやすいのが特徴です。
一方、フリーターやアルバイトは、雇用や収入が不安定と見なされやすく、金融機関の審査で不利になる場合が多いとされています。また、収入が毎月変動するため、ローンの審査に通りにくくなる可能性があります。
正社員のデメリットについて解説
正社員は安定した雇用や充実した福利厚生を受けられる一方で、デメリットも存在します。本章では、正社員として働く際の主なデメリット2点について詳しく解説します。
- 異動や転勤の可能性がある
- 勤務時間や休日の自由度が低い
異動や転勤の可能性がある
正社員は企業の人事方針に従う必要があり、自身が希望しない場合でも異動や転勤を命じられる場合があります。特に全国展開している企業では、キャリアアップの一環として転勤を求められるケースもあるのです。
転勤の場合は新しい生活環境に適応しなければならず、家族にも影響を与える可能性があります。家庭の事情によっては単身赴任を強いられ、家族と離れて暮らさなければならない場合もあるでしょう。
転勤を避けたい場合は「勤務地限定制度」を利用するか、転勤のない企業を選ぶとよいでしょう。
勤務時間や休日の自由度が低い
正社員は勤務時間が固定されている場合が多く、フリーターやアルバイトに比べて自由に休みを取るのが難しいとされています。
特に、繁忙期やプロジェクトの締め切りが近い場合は、残業や休日出勤を求められる可能性があり、プライベートの時間が制限されるかもしれません。
近年では、フレックスタイム制度やリモートワークを導入する企業が増えていますが、すべての企業で実施されているわけではありません。そのため、職場選びの際には労働環境をしっかり確認することが大切です。
まとめ
フリーターとアルバイトの違いや定義、それぞれの一般的なイメージ、正社員や他の非正規雇用との違いについて解説しました。
フリーターとアルバイトには法律上の明確な違いはありませんが、定義や社会的なイメージに違いがあります。フリーターは15歳から34歳の正社員ではない若者を指し、アルバイトは短期間の雇用形態全般を表しています。
近年は多様な働き方が広がっており、自分のライフスタイルや将来の目標に合った働き方を選ぶことが重要です。それぞれの特徴を理解し、自分にとって最適な選択をしていきましょう。

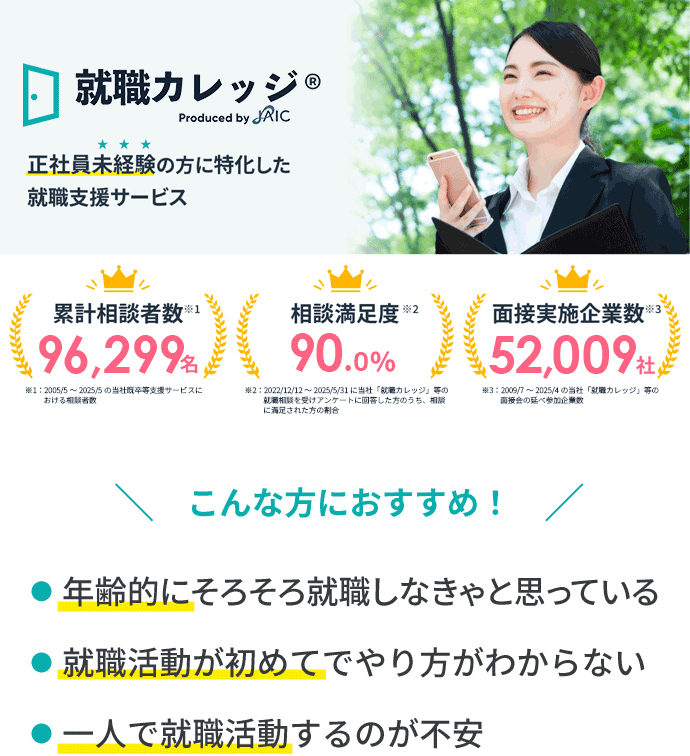

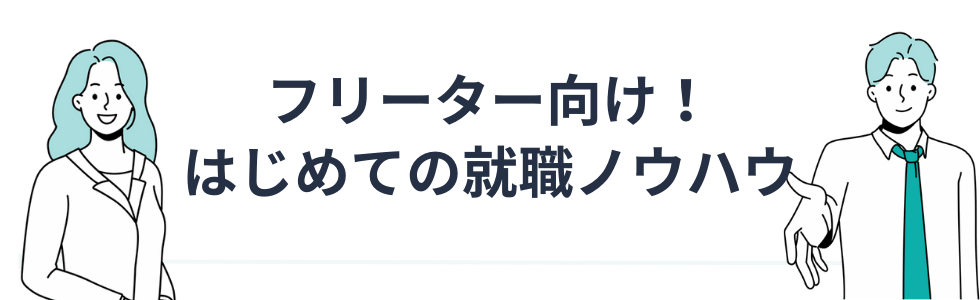
当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。