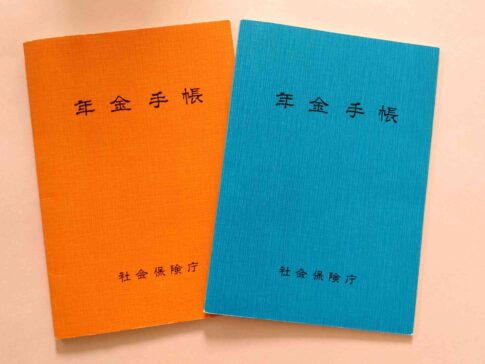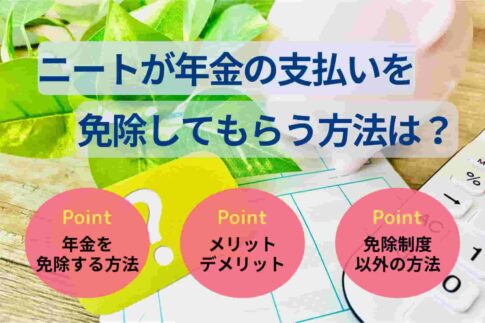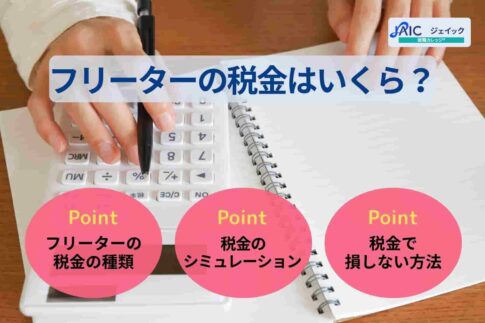無職の人であっても、国民年金の保険料を支払う義務があり、支払うべき保険料は一律で決まっています。支払いが困難な人には免除・減額・猶予といった制度も存在します。
この記事では、国民年金の加入方法、家族の扶養となる方法、支払い困難な人がとれる免除制度などを解説。さらに、将来の年金受給額を増やす方法も紹介しています。
無職でも安心して将来に備えるために、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
無職期間でも国民年金は払わなくてはいけない?いくら?
無職期間でも、国民年金は原則加入対象となります。収入がない中で国民年金の月額保険料の支払いが必要になるものの、収入がなかったり少ないと認められた場合は、全額免除や一部免除、納付猶予等の制度があるため、うまく活用していくことがポイントです。
なお、国民年金の免除や猶予を受ける際は、市区町村の年金事務所窓口などで手続きができるため、早めに行動するように意識しましょう。
まずは、無職期間の人が国民年金について理解を深めておくべきポイントを詳しく解説します。
無職期間でも国民年金への加入は必要
日本国内に住所のある20歳以上〜60歳未満で、厚生年金や共済年金に加入していない人は、原則として国民年金の第1号被保険者になります。無職で収入がない期間だったとしても、未加入で良いことはなく、国が有している最低限の社会保障を支える制度として、加入が義務付けられています。
なお、国民年金の加入や納付の記録は、将来自分が年金を受給することになる際の受給資格の土台となりますので、非加入、あるいは未納期間ができないよう注意しましょう。なお、国民年金の制度の根拠や最新の状況については、日本年金機構のホームページで確認できます。
参考:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
国民年金の金額目安
日本年金機構のホームページによれば、令和7年度の国民年金保険料は月額17,510円です。
また、まとめて前払いをすると約2%の割引が適用されます。他にも付加保険料として月額400円プラスして支払うことで、将来の老齢基礎年金の額を増額できるといった制度も設けられています。
保険料の納付方法は自治体から送られてくる納付書を持って、コンビニなどで支払う納付書払いと、クレジットカード払い、口座払いの3つの方法が選べます。
毎月納付の場合は、いずれの手段でも保険料が変わりませんが、前払いする場合は口座振替にしたほうが1,000円程度得します。
なお、国民年金として支払う金額は毎年計算されるため、最新の金額を知りたい場合は、日本年金機構のホームページを確認することをおすすめします。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の前納」
日本年金機構「国民年金保険料」
国民年金の免除制度について
収入や失業など、諸々の事情で保険料の納付が難しい場合は、保険料の全額免除や一部(4分の3、半額、4分の1)免除、納付猶予、学生納付特例といった制度が利用できることがあります。申請できる期間は保険料の納付期間から2年を経過していない期間ですので、早めに申請することが重要です。
なお、保険料の免除や猶予を受けた際には、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるほか、障害・遺族年金の受給要件にも基本的に算入されるため、保険料が支払えないから納付を無視して未納状態になる事は避けておくべきでしょう。
ただし、当然ながら保険料の免除を受けた際、将来に貰える年金額は全額納付した時と比べて低い金額になります。無職の場合は一時的に国民年金の免除制度を活用しつつ、社会復帰した後に免除期間の保険料を追納することも検討すべきです。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
免除制度の申請方法
国民年金の免除や納付猶予の申請は、自分の住所がある市区町村の国民年金窓口か年金事務所で行います。窓口に足を運ぶほか、郵送提出やオンラインでのマイナポータルからの電子申請が可能なため、自分がやりやすい方法を選ぶと良いでしょう。
なお、免許制度の申請は、7月から次の年の6月までの12ヶ月間が審査・承認期間となるため、もし数年間にわたって申請をする場合は、年度ごとの免除・納付猶予申請を行う必要があります。
記載する申請書の書き方は、日本年金機構のホームページでも確認できます。
無職の国民年金はいくら?【保険料と受給額】
こちらでは、無職の人向けの国民年金について解説します。
- 支払う保険料
- 受け取れる金額
を知りたい人は、参考にしてください。
無職が支払う国民年金保険料はいくら?
現在の国民年金保険料は、月額16,610円です。この保険料は一律で決まっており、物価や賃金に応じて毎年変動します。
後に紹介しますが、無職で国民年金保険料の支払いが困難な人は、免除・減額・猶予といった制度があり、申請をして承認されると適用となります。これらの承認がされない人は全員、無職であっても毎月16,610円を支払わなければなりません。
無職が受給できる年金額はいくら?
無職の人が65歳以降に受給できる年金は、満額で78万900円(月換算で65,075円)です。受給額も保険料と同様、毎年の物価や賃金に応じて変動します。
満額というのは「20〜60歳の期間、毎月きちんと国民年金保険料を払い続けた場合」の金額を指します。途中で年金支払いの未納・免除・減額がされていた場合は、一部減額がされるので注意しましょう。この金額だけで生活することはまず困難であるため、老後を迎えるまでにある程度の貯蓄をしておくことが必要です。
年金受給額を増やす方法
もしこれまでに年金支払いを免除・減額・納付猶予している期間があり、なおかつ将来の年金受取額を増やしたい場合は、追納制度を利用しましょう。追納は、承認された月から10年以内であれば可能です。未納の場合でも、直近2年以内の分は遡って支払うことができます。
この追納制度を利用すれば、65歳以降は満額の年金受給が可能です。国民年金保険料を支払う余裕のある人は、追納しておくことをおすすめします。手続きは、管轄の年金事務所で行えます。
無職が国民年金に加入するための手続き方法
ここでは、無職が国民年金に加入するための手続き方法を解説します。これまで働いていて厚生年金に加入していたが、退職して無職になった人は参考にしてください。
一般的な国民年金の加入方法
こちらは、会社を退職して無職になった場合に該当する、第1号被保険者の手続きです。この加入手続きは、退職日から14日以内に行う必要があります。
手続きは、住所地の役所にある年金窓口で行います。必要なものは、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書です。
家族の扶養に入る場合
- 収入が103万円以下である
- 家族が第2号被保険者である
上記に該当する人は、家族の扶養となる「第3号被保険者」に入れます。扶養に入ることによって、以下のメリットがあります。
- 国民年金保険料の支払いが免除される
- 扶養に入れた家族の税金(所得税・住民税)が減額される
家族の扶養に入る場合は、扶養に入れる人の勤務している事業所を通じて申請をします。
無職が国民年金の支払いを免除にする方法
無職であっても原則、国民年金保険料の支払い義務は発生します。しかし収入がなくて支払いが厳しい場合には、免除申請をすることができます。
もし免除申請をせずに未納のままにしておくと、将来もしくは障害発生時に年金を全く受け取れない可能性があります。なぜなら、現在の年金制度は「20〜60歳の40年間のうち、国民年年金の支払いを10年以上していないと、年金の受給ができない」と決まっているからです。そうならないために、支払いが困難な場合は必ず免除申請をしておきましょう。
免除・納付猶予手続きの窓口
国民年金の免除や納付猶予の手続きを進める際、最初の相談先となるのは市区町村の国民年金担当課や最寄りの年金事務所となります。
申請書は窓口だけでなく郵送で提出でき、提出後は受付印の押された控えを保管することになります。また、マイナポータルを使えば電子申請を24時間いつでも手続きできます。
年度ごとに手続きをすることが必要なため、無職期間が長引きそうな場合は、申請した内容を保管しておき、次年度以降の申請で活用できるようにしておくと良いでしょう。なお、手続きについて迷った場合は、窓口やねんきんダイヤルで確認することがおすすめです。
無職が利用できる免除制度
無職が利用できる免除制度について解説します。具体的に活用できる制度は、以下の3つです。
- 学生納付特例制度
- 保険料免除・納付猶予制度
- 新型コロナウイルスの影響による特例制度
それぞれの対象者と免除期間を紹介しているので、免除申請をしたい人は参考にしてください。
学生納付特例制度
学生納付特例制度は、申請により在学中、国民年金保険料の支払いが猶予される制度です。
- 大学
- 大学院
- 短期大学
- 専門学校
- 高等学校
- 高等専門学校
- 特別支援学校
- 海外大学の日本分校
ここに夜間・定時制・通信課程に通う人も含まれるため、ほぼすべての学生が当てはまります。ただし他にも条件があり、それは本人の収入が「128万円+扶養親族者×38万円」未満であることです。4月から翌年3月までの期間を対象として審査されます。該当する人は、住民登録をしている役所の国民年金担当窓口に行けば申請ができます。
保険料免除・納付猶予制度
保険料免除・納付猶予制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が少なく、国民年金保険料の納付が困難である場合に利用できる制度です。免除・猶予は以下の区分に分けられます。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 納付猶予
どれに該当するかは保険料免除・納付猶予申請をして、役所から判定されて決まります。該当すれば、国民年金保険料の支払いが1年間免除もしくは猶予されます。
収入が少なく、国民年金保険料の納付が困難な人は、申請するのも1つの手です。申請は、年金手帳または基礎年金番号通知書を持って、住民登録をしている役所の国民年金担当窓口で行えます。
新型コロナウイルスの影響による特例制度
新型コロナウイルスの影響による特例制度は、以下2つの条件すべてに当てはまる人が対象です。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
2.当年中の所得が、現行の国民年金保険料の免除に該当すると見込まれる
該当する人は、最大1年間納税の支払いが免除・減額されます。金額は「保険料免除・納付猶予制度」と同様、以下の4種類です。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
無職中に国民年金を免除・猶予するメリット
無職期間中は収入がなくなるため、免除や猶予制度を使えば、当面の生活費に余裕が生まれるといったメリットがあります。また、保険料が支払えなくても申請が承認されることで、老齢年金の受給資格期間に算入されるため、未納が避けられる点も大きなメリットと言えます。
将来的に社会復帰をして追納すれば、老後にもらえる年金額を増やすこともできますので、無職期間中に一時的に保険料の免除・猶予をしてもらう事は様々なメリットがあります。
ここからは、無職期間中に国民年金を免除・猶予するメリットを3つのポイントで解説します。
生活費に余裕ができる
国民年金の免除・猶予制度を活用することで、毎月17,000円程度の支出が抑えられます。無職は収入がないため、その分の金額を家賃や食費、公共料金の支払いなど必須の支出に回すことができれば、生活費に余裕ができるといったメリットが受けられます。
特に短期的な資金繰りに悩んでいる場合は、すぐにでも国民年金の免除か猶予を受けることをおすすめします。
一方で、国民年金を満額支払わないと将来もらえる年金額に影響してきますので、免除や猶予はあくまでも生活を再建する上での臨時的な対応として、制度を賢く使う意識を持っておきましょう。
保険料を払えなくても受給資格期間に算入される
国民年金の免除・猶予の承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。もし申請しないまま未納してしまうとその期間に算入されないため、将来年金がもらえる権利を取得するといった観点からも、免除・猶予申請をする事は大きなメリットがあると言えます。
無職は国民年金に対してまず未納期間を作らないことを意識しましょう。また、自身が保険料の免除や納付猶予の対象要件を満たす場合は、早めに年金事務所や自治体に申請をすることがポイントです。
具体的な手続きや必要書類は、自治体の窓口や年金事務所で確認してください。
将来的に追納して年金額を増やせる
国民年金の免除・猶予が承認された場合、原則10年以内であれば後から納付する「追納」が利用できます。例えば、全額免除の1年分を将来追納することで、老齢基礎年金が年間で約10,000円、納付猶予であれば年約20,000円増える目安とされています。
追納した金額は、社会保険料控除の対象にもなるため、ただ年金を受け取る金額を増やすだけでなく、短期的な税金の負担を軽減する効果も期待できます。現在無職の人は、将来正社員として就職した後に保険料の追納をすることも検討すると良いでしょう。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
無職で国民年金を払わないとどうなるか
無職で国民年金を払わないまま未納を続けると、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない上、将来の年金額が減るといった様々なデメリットに繋がります。また、督促段階を超えてしまうと延滞金が発生したり、最終的には差し押さえなどの強制徴収に至る可能性があります。
無職で収入がないから未納にしてしまうのではなく、早めに自治体に相談して免除や猶予の申請をする意識を持っておきましょう。ここからは、無職で国民年金を払わずに無視した際にどうなるのかについて詳しく解説します。
将来もらえる年金額が減る
国民年金を「未納」にしてしまうと、受給資格期間に算入されないため、将来の老齢基礎年金額にも反映されません。免除や猶予であれば資格期間に算入されますので、追納することにより、年金額を満額に近づけることができます。しかし、未納の場合は原則年金額を満額にすることはできません。
したがって、短期的に厳しい無職の現状が、将来の自分の首を絞めることに繋がると言えます。無職で収入がなく、かつ国民年金が払えない場合は、必ず免除や猶予に切り替え未納を作らない意識が老後の資金を守る上で重要になってきます。
延滞金がかかることがある
国民年金の納付期限を見ると、納付日の前日までの日数に応じた延滞金がかかります。延滞金は日割で換算されるか、延滞金の金額が50円未満の場合は徴収しないなどの規定もありますが、いずれにせよ延滞金は余計な支払いとなりますので、早めに年金事務所に相談することがおすすめです。
ちなみに、延滞金を支払ったからといって、将来もらえる年金額が上がるなどのメリットは1つもありません。特に生活費が厳しい無職は、延滞による余計な支払いを発生させないよう心がけてください。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」
滞納を続けると差し押さえのリスクがある
国民年金を支払わずにいると、自治体や年金事務所から督促状が送られてきます。何度も納付を促す督促状を受けても無視を続けてしまうことで、国民年金保険料の強制徴収の対象になってしまい、貯金や給与、不動産等の差し押さえに至ることがあります。
もし差し押さえになった場合は、世帯主や配偶者にも手続きが及ぶ場合もありますので、放置は厳禁です。繰り返しになりますが、無職が国民年金の支払いができない場合は、免除や猶予・分割納付等の相談をできる限り早く行いましょう。
参考:日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」
無職で国民年金を払えない時の短期的な対処法
無職になったばかりで生活費が厳しい場合は、未納で放置するのではなく、短期的にできることに取り組むべきです。例えば、アルバイトや短期派遣に取り組んだり、家族に立て替えてもらうことで、一時的に国民年金の保険料を支払うことをおすすめします。
また、どうしてもお金の工面ができない場合は、求職者支援制度や公的融資など国が用意している公的支援制度を活用することも検討すべきです。
ここからは、無職で国民年金を払えないときの短期的な対処法を3つご紹介します。
アルバイトや短期派遣に取り組む
なんらかの理由で突然無職になってしまった場合は、アルバイトや短期派遣などで働いて保険料分の収入を得ることが有効です。無職の国民年金保険料は令和7年度で月額17,510円となりますので、日雇いバイトを2 3日程度行えばお金の工面は可能です。
アルバイトや短期派遣を長期間続けてしまうと空白期間が長引き、次の正社員就職の難易度を上げることに繋がってしまいますので、免除や猶予の申請と並行して、家計を成り立たせられるだけの最低限の期間取り組むことを意識しましょう。
あらかじめ家計の見直しをした上で、優先度の高い支出から資金配分することにより、短期的な資金繰りを改善することができるはずです。
家族に立て替えてもらう
国民年金保険料は本人だけでなく、連帯納付義務者となる世帯主や配偶者も納付できます。どうしても働けない状況にある場合は、一時的に家族に立て替えてもらって未納を防ぐのも有効です。合わせて、親や親戚など信頼できる人に相談してみるのも良いでしょう。
家族に立て替えてもらう場合は、あらかじめいつまでに返済するのか明確にしておくことがポイントです。いくら親族であっても、お金がきっかけでトラブルに発展してしまうケースは少なくありませんので、誠実な対応を心がけることをおすすめします。
なお、いつまでも家族に立て替えてもらうと家族の生活もままならなくなるため、あくまでも短期的な処置として認識しておいてください。
公的支援制度を活用する
失業したものの雇用保険を受給できない場合は、公的支援制度を活用することもおすすめです。例えば求職者支援制度を使えば、月100,000円の給付を受けながら無料で職業訓練が受講できます。また、低所得者世帯に分類される場合は、生活福祉資金貸付制度などの公的融資が利用できることもあります。
お金の工面は国の制度を活用できるケースが多いため、無職が国民年金の保険料を支払うために、消費者金融などでお金を借りる事は避けておいた方が良いでしょう。短期的に保険料が支払えるかもしれませんが、利息分の支払いが必要になりますので、余計にお金がかかるリスクに繋がります。
公的支援制度はハローワークで申し込みができるものも多く、就職先を探すことと同時に、どんな支援制度が利用できるのかスタッフに聞いてみることもおすすめです。
無職が就職した時の国民年金の取り扱い
無職が会社に就職することで、基本的に厚生年金に加入することになります。厚生年金に加入すると第二号被保険者となり、国民年金を個別に納付する必要がなくなります。また、保険料は給与から天引きされるため、納付忘れがなくなるといったメリットがあります。
加えて、厚生年金の場合は、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金分が将来上乗せして支給されることになりますので、一般的に老後の年金額が増えることにも繋がります。
ここからは、無職が就職したときの国民年金の取り扱いがどうなるのかについて詳しく解説します。
就職することで厚生年金に切り替わる
厚生年金を適用している会社に就職すると、国民年金の第二号被保険者に切り替わるため、自分で国民年金保険料を収める必要がなくなります。就職後に厚生年金に切り替える手続きを会社側が行ってくれますので、会社から言われる必要書類を忘れずに提出することを心がけてください。
厚生年金に切り替えた後に自分の年金納付状況や将来いくら年金がもらえるかは、ねんきん定期便やねんきんネットで状況を確認できます。特に就職直後はうまく会社側で切り替え処理をしてくれているか確認するためにも、それらのサイトにアクセスすることをおすすめします。
国民年金と厚生年金の違い
国民年金とは全国民共通の基礎年金であり、いわゆる年金の一階部分と表現され、全国民が必ず加入するといった特徴があります。一方、厚生年金は会社員等が加入する二階部分に相当し、報酬比例部分が基礎年金に上乗せされるといった特徴があります。
保険料の支払い方法についても両者には違いが見られます。国民年金は自分1人が負担することになりますが、厚生年金は被保険者である従業員と事業主で折半をする形で納付をします。また、納付は事業主が給与から天引きして行いますので、従業員側が支払い忘れするような事はありません。
給与から天引きで納付する
厚生年金の保険料は、毎月の給与と賞与に保険料率を乗じた額を事業主と被保険者が半分ずつ負担し、会社が本人負担分を給与から天引きして納付するといった特徴があります。一般的に、当月支給される給与から前月分の保険料を控除するため覚えておくと良いでしょう。
また、毎月の給与だけでなく、賞与に対しても厚生年金の納付が必要になる点には注意が必要です。賞与がない会社の場合は、その分厚生年金の支払いが不要になります。会社員である以上、厚生年金の保険料は天引き以外の納付が原則不可能となる点も合わせて認識しておいてください。
参考:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
将来もらえる年金額が増えることが多い
厚生年金に加入すると、国民年金の一階部分である基礎年金に加え、報酬比例の年金が上乗せされるため、国民年金のみの場合と比べて老後の年金額が増える傾向にあります。
制度の仕組み上、収入と加入期間の積み上げが年金額に直結しますので、会社員として長く働けば、その分老後の生活が安泰になりやすいことが言えます。
裏を返せば、会社員としての収入が増えれば増えるほど、厚生年金の支払い額は多くなっていきます。これから無職が就職活動をする際は、額面でもらえるお金と、手取りとしてもらえるお金の違いをしっかりと理解した上で、求人の比較検討を進めることが大切です。
よくある質問
無職であっても国民年金の支払い義務は発生します。国民年金の第一号被保険者であれば、令和7年度の月額保険料は17,510円です。納付が難しい場合は、免除や猶予の申請を早めにしておくことをおすすめします。
無職だからといって国民年金の納付義務がなくなるというわけではありません。未納期間ができると、将来年金がもらえなくなったり、財産の差し押さえをされてしまうリスクが高まるため、すぐに自治体の年金窓口や年金事務所に相談することが重要です。
無職になっても、国民年金の支払いが自動的に免除になる事はありません。本人や配偶者、世帯主の所得等に基づく審査によって、全額・一部免除や納付猶予の可否が決まりますが、申請自体は自分から行う必要があります。
なお、生活保護受給者や一定以上の障害年金受給者の場合は、国民年金の支払いが免除の対象になりますので個別の申請は不要になります。
無職になった後の年金の手続き方法については、前職がアナウンスしてくれる事はありません。国民年金の保険料の支払いがどうしても難しい場合は、自治体の窓口や年金事務所に相談することをおすすめします。
無職での国民年金保険の支払いにつきましては「無職でも国民年金保険料の支払い義務はある」で記載しておりますが、無職であっても国民年金保険料は国が定めている制度であるため支払いは発生いたします。
無職が国民年金に加入する方法は、一般的な国民年金の加入方法と家族の扶養に入る場合で少し異なるためどうしても知りたい方は、「無職が国民年金に加入するための手続き方法」を参考にしてみてください。
まとめ
以上、無職の人向けに国民年金の制度を解説しました。毎月の国民年金保険料16,610円は大きな負担ですが、きちんと支払うことによって、以下の状況でも生活を支えられる貴重な制度です。
- 65歳以降の老後生活
- 障害発生時
- 亡くなった後、家族の生活
現在国民年金保険料の支払いが困難な人は、免除・猶予申請をすることも1つの手です。ただし後から追納しなければ、将来受け取れる年金額が減ることは理解しておきましょう。
前提として年金は支払いが義務化されているものなので、国民年金を支払っても生活に支障のない状態が理想です。しっかり保険料を支払い、将来国民年金を満額受け取れる状態にしておきましょう。
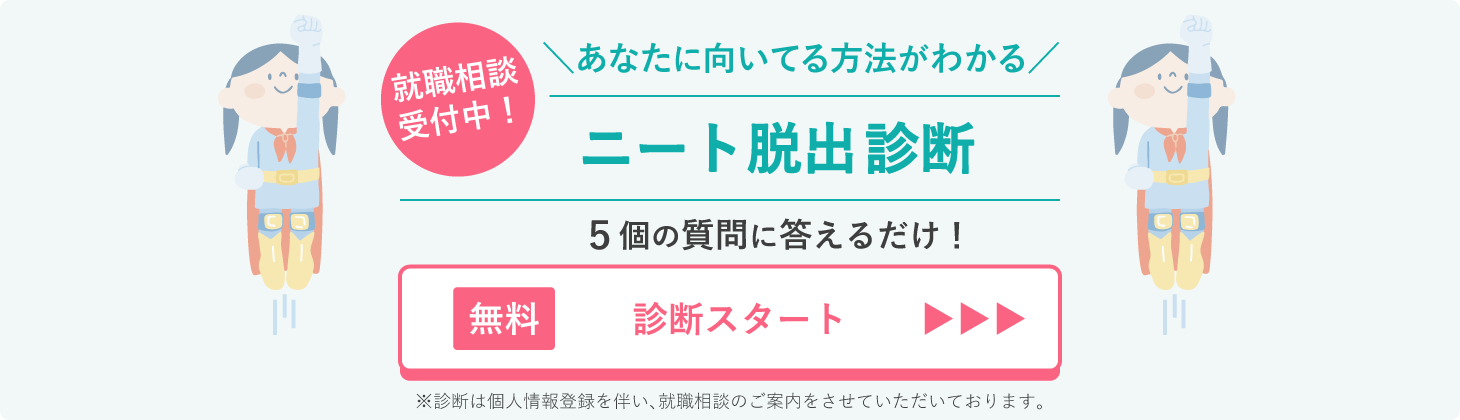
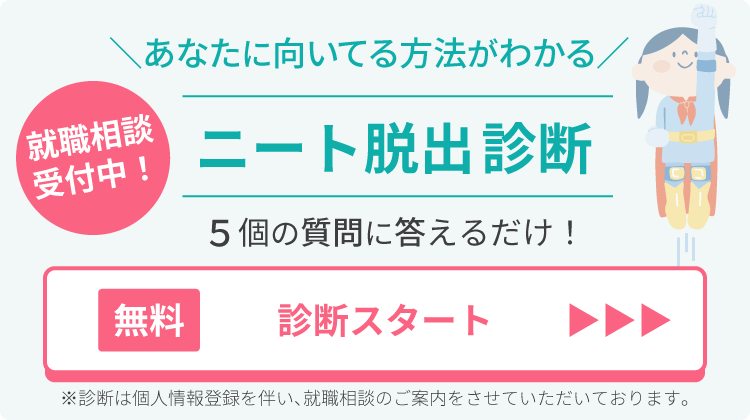
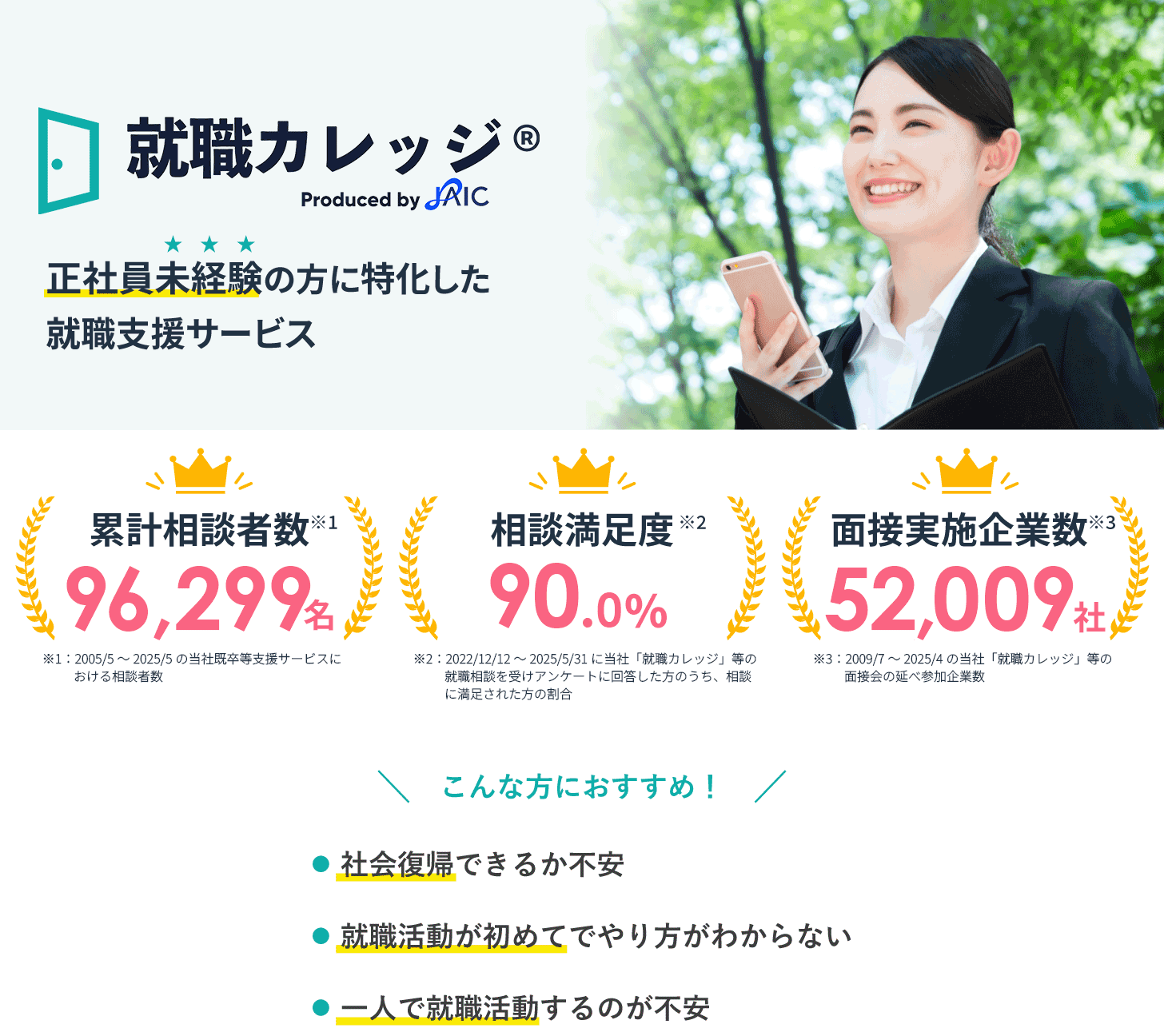
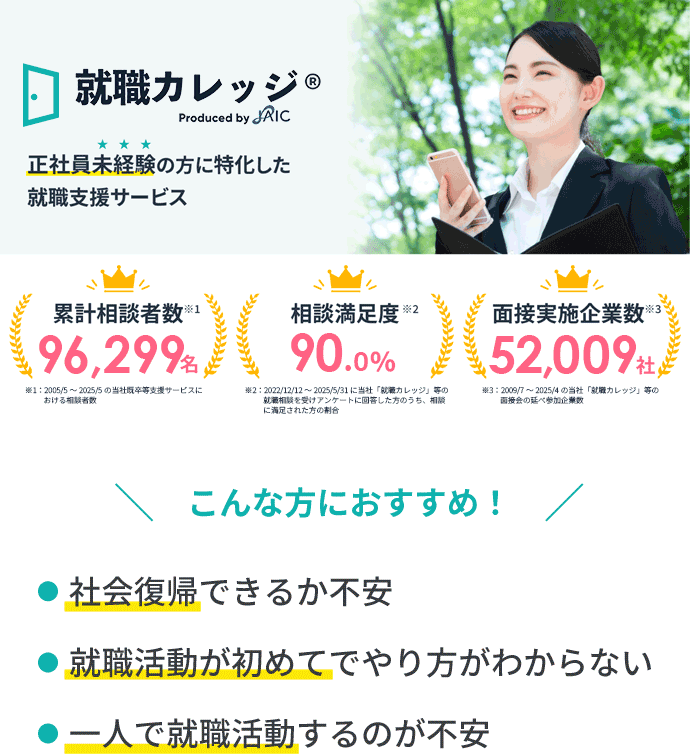

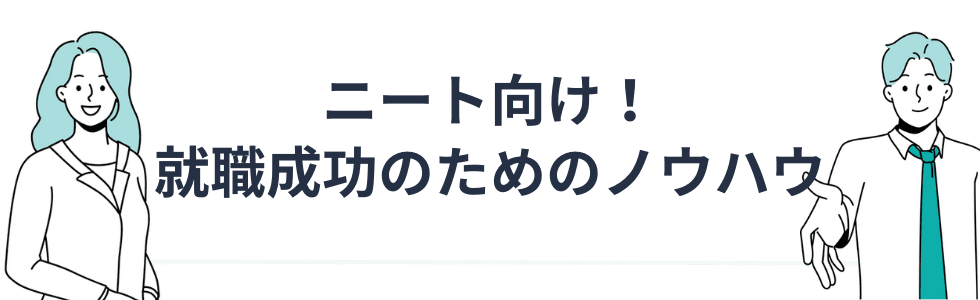
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。