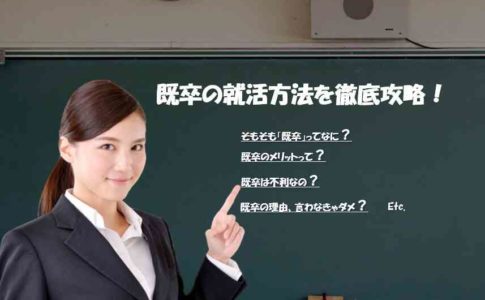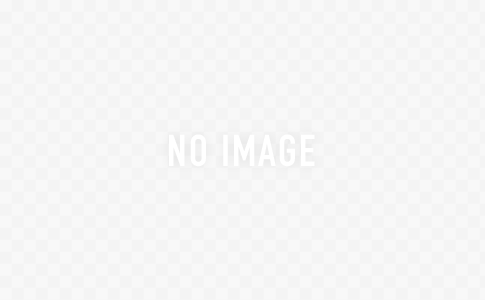ずっと無職で収入がない場合、前年の所得に基づいて課税される住民税の支払い対象とならず、支払い請求も来ないことが一般的です。
ただし、ずっと無職であっても不動産収入や株式の売買益がある場合は、住民税がかかることがありますので注意してください。
この記事では、ずっと無職の人がどういった場合に住民税がかかるのかについて詳しく解説します。併せて、万が一住民税が払えない時はどういった対処法があるのかについても解説しますので、住民税の支払いに不安を感じる無職の人は記事の内容を参考にしてみてください。
この記事の目次
ずっと無職だと住民税はかからない
ずっと無職で収入がないような場合は住民税はかかりません。
住民税は、その年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算されます。
したがって、継続的に無職で収入がない場合は、課税対象となる所得がないため、住民税はかからないということになります。
ただし、ずっと無職であっても不動産の賃料や売買収益、株式の配当金や売買益、転売やせどりによる利益等は収入とみなされることが基本のため、それらの所得が一定の非課税限度額(おおよそ35〜45万円程度)を超えると、住民税がかかる可能性があります。
具体的な基準は自治体により異なるため、住んでいる市区町村のホームページなどで確認することをおすすめします
無職でも住民税がかかるケース
無職であっても、住民税がかかることがあります。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、正社員として働いていなくても、アルバイトやパートの給与に加え、不動産や株式などからの所得が一定額を超えると課税対象となります。
ここからは、無職でも住民税がかかるケースを詳しく解説しますので、ずっと無職だから絶対に住民税を払うことはないといった勘違いをしないように心がけてみてください。
前年に収入がある場合
住民税は現時点での収入ではなく、前年の所得に基づいて課税されますので、今が無職であっても、前年に何らかの給与や報酬を受けていた場合は住民税がかかる可能性があります。
例えば自分では無職だと思っていても、業務委託として案件を受けて報酬を得た場合は、所得額に応じた住民税の課税が発生します。
住民税がかかるかどうかを判断する1つの基準としては、ずっと無職でかつ無収入であるかどうかを基準に考えていくことが良いでしょう。
アルバイトやパートで年間100万円以上の収入がある場合
ずっと無職であったとしても、アルバイトやパートなどで働いた場合は、稼いだ金額によって住民税がかかるケースがあります。自治体によって細かな金額水準は変わってきますが、年間100万円以上の収入を稼ぐと住民税の支払い義務が発生することが一般的です。
例えば、1年の間で数ヶ月間だけ働いて収入を得た場合も、トータルで年収100万円を超えることがあれば、住民税がかかるようになります。あくまでも住民税は1月1日から12月31日までの合計収入で課税されることを覚えておいてください。
不動産売却など一時的な所得があった場合
アルバイトやパートなどで働いていない無職であっても、不動産や株式の売買益など一時的な所得があった場合は、住民税が課される可能性があります。つまり、無職でも何らかの方法でお金を稼いでいる場合は、基本的に住民税がかかってくると思っておいた方が良いでしょう。
特に不動産については売買による収益が大きくなりやすいだけでなく、売買の手続きに気を取られてしまい、後に発生する住民税に目が向きにくくなることもあります。
一時的な所得が発生した際は確定申告が必要になることもありますので、住民税に限らず税金について少しでも不安を感じたら、近くの税務署や役所に相談することがおすすめです。
無職で住民税がかからないケース
無職をしていて住民税がかからないケースとしては、ずっと無職かつ無収入で所得がない人や、前年の収入がおよそ100万円以下のケースが挙げられます。
また、住民税の非課税制度の条件に当てはまるような生活保護受給者や、障害者手帳を持っている人の場合も住民税が免除される自治体が多くなっています。
ここからは、無職で住民税がかからないケースを2つご紹介します。
1年以上ずっと無職で前年収入が100万円以下の場合
1年以上ずっと無職で、かつ前年のすべての収入の合算金額が100万円以下の場合は、多くの自治体において住民税がかからないと考えられます。
収入がなかった期間が1年以上あれば、前年の所得が住民税の非課税限度額を基本的に下回りますので、住民税の納付書も手元に届かないでしょう。
ただ、住民税の非課税限度額は扶養や障害の有無、世帯状況などの細かな条件に基づいて自治体ごとに制度が設けられているため、100万円という金額はあくまでも目安になります。細かな収入基準額は自治体のホームページを見て確認することをおすすめします。
非課税制度の条件に当てはまる場合
自治体によっては、住民税に非課税制度が設けられていることがあります。
例えばその年の1月1日時点で生活保護を受給している場合は、多くの自治体で住民税がかからない傾向にあります。また、ひとり親や障害者などで一定の所得を下回る場合も、住民税がかからないケースが一般的です。
住民税は地方税の1つであり、自治体によって様々な取り決めがされているため、詳細を知りたい場合は、自身の住民票の住所がある自治体のホームページを見たり、役所に直接問い合わせてみてください。
無職がずっと住民税を払わないとどうなる?
ずっと無職であっても、住民税の請求が来た場合は基本的に全額を払う必要があります。収入がないからといって、住民税を払わず滞納し続けてしまうと、自宅に督促状が届いたり、役所の職員が自宅に訪問してくるため、同居人に住民税の滞納を知られてしまうといったリスクがあります。
それだけでなく、滞納を続けていると預金口座や家財を強制的に差し押さえられ、住民税の支払いに当てられるといったことにも繋がりかねません。様々なトラブルに繋がりますので、無職だからといって住民税の請求を無視することは避けてください。
ここからは、無職がずっと住民税を払わなかったときに、どういったリスクがあるのかについて3つの観点から解説していきます。
自宅に督促状が届く
住民税を滞納すると、法律に基づいて督促状が送付されます。督促状は住民票に登録されている住所に送られますので、もし家族や親などの同居人がいた場合は、住民税の滞納がばれることに繋がります。
加えて、延滞した時点で通常の住民税に加えた延滞金が加算されますので、支払う総額がどんどん増えていくことになります。
もし督促状が来て支払う意思があった場合でも、自治体に連絡することなく支払いが遅れれば、支払い猶予や分割支払いの交渉は難しくなります。ずっと無職で収入的にも厳しい場合は、督促状を受け取る前に自治体に相談することが大切です。
役所の職員が自宅に来る
督促状を無視し続けていると、役所の徴税担当者が自宅に訪問してくることもあります。役所職員が自宅に来ると、自宅の財産の有無や支払い計画の話し合いをすることになったり、場合によっては玄関先で住民税の支払いをするようなケースも見られます。
役所の職員は突然自宅を訪問してきますので、精神的なプレッシャーがかかるだけでなく、同居人がいた場合は大きな家庭内トラブルに発展することもあるでしょう。
訪問される前にあらかじめ市役所と相談しておけばこのような事態を避けられますので、ずっと無職の人は、住民税の支払いにおいて誠実な対応を心がけるように意識してみてください。
預金などの財産を差し押さえられる
役所の督促を全て無視し続けている状態が続けば、最終的に預貯金や自宅の家財などの財産を差し押さえられてしまうリスクもあります。
差し押さえは本人の同意なく実施される強制執行になりますので、今までの生活が一気に様変わりしてしまうようなこともあるため注意してください。
差し押さえの対象になるのは、銀行口座の残高や車やブランド品などの資産、不動産に加えて、場合によっては生命保険の解約返戻金が含まれることもあります。
一度差し押さえを受けると、将来の生活に大きな影響を与えうるため、滞納を放置することなく向き合う意識が大切です。
ずっと無職で住民税が払えない時の対処法
住民税を払いたくても、ずっと無職で収入も貯金もないような場合は、諦めて滞納をし続けてしまうのではなく、どうにかしてお金を工面して納付をし続ける意識が重要です。
具体的に住民税が払えないときの対処方法としては、以下の3点が挙げられます。
- 納付期限までに役所に相談する
- 家族や親族に相談する
- 就職活動を始める
住民税の滞納を続けていると、最終的に家財や預金を始め、あらゆる資産性のあるものが自由に使えなくなるなど大きなリスクに繋がりますので、それぞれの対処法をあらかじめ認識しておきましょう。
1. 納付期限までに役所に相談する
どうしても住民税の納付が難しい場合は、まず納付期限までに役所の窓口まで相談に行くことがポイントです。相談に行くことで、住民税をさらに分割払いできるようになったり、状況に応じて使える減免制度の案内を受けられる可能性があります。
ただし、あらかじめ定められている住民税の納付期限を超えてからの相談になると、たとえ減免制度が利用できる状態であっても、対応をしてもらえなくなる可能性が出てきます。
延滞金もかかってしまい、請求通りに住民税を納付するしかできなくなりますので、注意してください。
無職の場合は、住民税の納付書が毎年6月上旬から中旬までの間に送られますが、最初の納付期限は6月末と設定されているため、納付書が送られてきた段階で相談をするといったスピード感を意識することをおすすめします。
2. 家族や親族に相談する
無職で収入がない場合、仮に役所が住民税の分割払いを認めてくれたとしても、そもそも支払いをできる家計状況にないかもしれません。そうした時は1人で悩むのではなく、家族や親族に相談することも有効な対処法となります。
もしお金がないからといって、消費者金融で借金をして住民税の支払いを行ってしまうと、その分の金利を上乗せして洗わなければならなくなるため、長期的に見たときの支払い額が大きくなってしまい家計を圧迫しかねません。
両親や兄弟など近しい親族が経済的に余裕がある場合は、金銭的な支援を得られないか誠実に相談してみることがおすすめです。
無事に支援をしてもらえる場合は、感謝の言葉を伝えるだけでなく、いつまでに返済をするのかあらかじめ約束をしておき、金銭的なトラブルに発展することを避けましょう。
3. 就職活動を始める
住民税の支払いが難しい状況を根本的に解消するためには、正社員として就職活動を進めることが最も有効です。
「ずっと無職でいきなり正社員になる事は難しいのではないか」と感じてしまうかもしれませんが、昨今では人手不足の会社が増えているということもあり、未経験者歓迎の求人が多くなっているといった傾向が見られます。
どうしても正社員になることに精神的なハードルの高さを感じている場合は、アルバイトやパートから始めてみるのも良いでしょう。アルバイトやパートの場合、年収が100万円を超えないようにシフトを調整すれば、住民税が引き続きかからない状況を継続することも可能です。
大切なのは、ずっと無職である状況から一歩踏み出し、自分で収入を得て住民税を支払い始めるといった行為です。経済的に自立をするためにも、就職活動を始めたい人は無職の正社員就職支援に強いジェイックまでご相談ください。
よくある質問
ずっと無職だと、住民税に関する疑問がたくさん出てきがちです。最後に、ずっと無職で税金に関心のあるような人によくある質問を3つ取り上げて解説します。
ずっと無職だと住民税はいくらになりますか?
ずっと無職で、かつ収入が一切ない場合は、基本的に住民税は0円となります。住民税は前年の所得に基づいて課税されますが、各種所得控除を加味すると、アルバイト等の給与収入があるケースで年収100万円を超えない限り住民税はかからない計算になります。
ただし、住民税の計算に使われる収入とは、アルバイトやパートの収入だけでなく、不動産や株式の売買益や転売などで得た収益も合算されますので、何らかの方法でお金を稼いでいる無職は、住民税の支払い対象になることもある点には注意が必要です。
また、住民税の細かな取り決めについては自治体によって大きく違いが出てくるため、少しでも住民税に不安を感じている無職の人は、自分が住んでいる自治体のホームページを確認してみてください。
住民税は無職になった場合どうなる?
無職になった場合は、前年に所得があればその翌年に住民税の支払いが発生します。
住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に基づき、翌年の6月から課税される仕組みとなっていますので、例えば2024年に退職した場合、所得が一定水準以上あれば2025年6月から住民税の請求が届くことになります。
ただし、無職になった年の収入が目安として100万円を下回っている場合は、翌年の住民税が非課税になる可能性もあります。住民税がかかるかどうかを判断する上では、無職になった年とその前の年の収入をしっかりと認識しておくことが大切です。
なお、自分が住民税のかかる状況か知るためには、住民票のある自治体の役所に問い合わせてみることがおすすめです。
ずっと無職でも毎月払い続ける税金は?
住民税以外に固定的に支払わなければならない税金や社会保険として、国民健康保険と国民年金保険が挙げられます。国民健康保険と国民年金保険は、日本に住民票がある人に対して原則として加入義務があります。無職であっても請求されることが一般的です
ただし、ずっと無職で収入そのものがない場合は、それぞれ減免や免除の申請の制度が設けられていることもあります。
それぞれの制度を理解しておけば、実質的な負担を減らすこともできますので、無職の間はそれらの制度をうまく活用し、経済的負担を回避する意識を持っておくと良いでしょう。
まとめ
ずっと無職であっても、前年に一定の所得があれば住民税が課税される可能性があります。
この時、所得はアルバイトやパートの給与所得だけでなく、不動産や株式の売却を始め、短期間の収入でも課税対象になりますので注意が必要です。
一方で、ずっと無職でかつ無収入の場合は、自治体にもよりますが住民税が免除されるケースが多くなります。
もし住民税の請求が来て家計的に納付が難しい場合は、納付期限が来るまでに早めに役所に相談することがポイントになります。
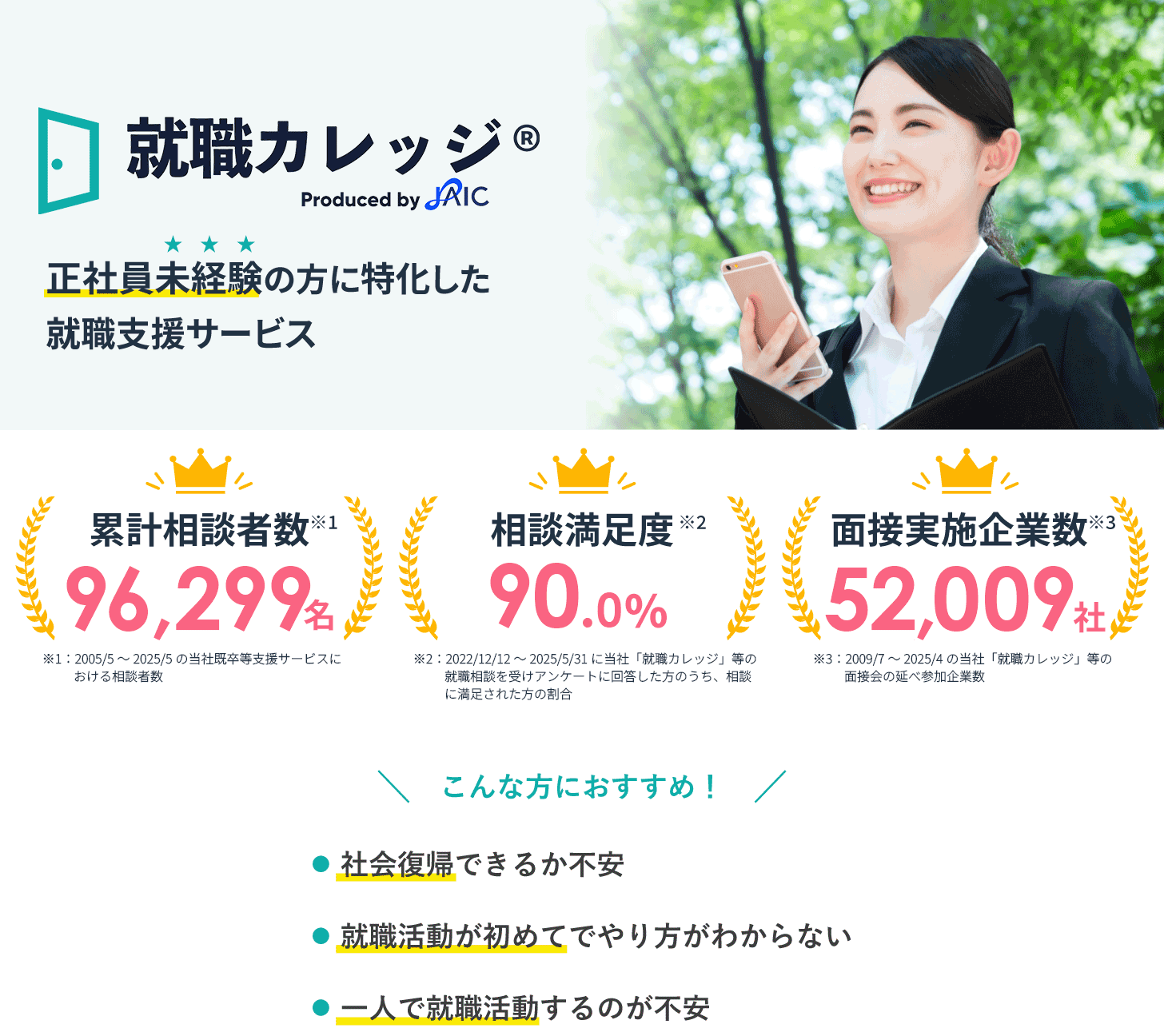
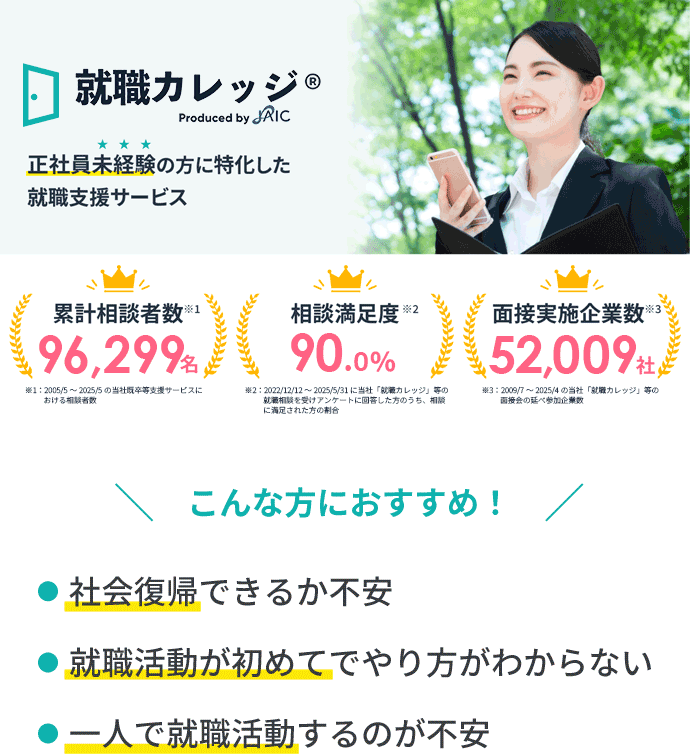

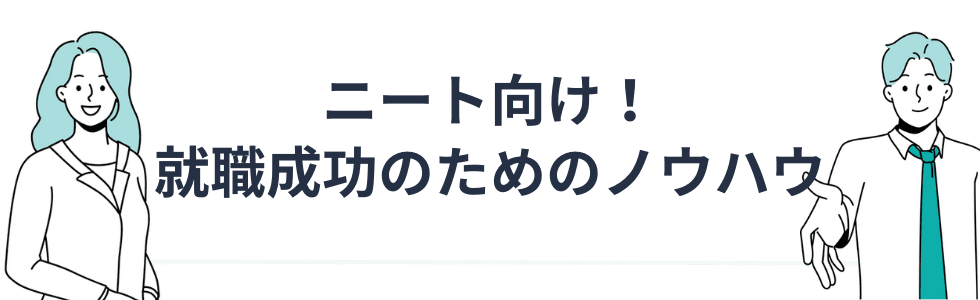
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。