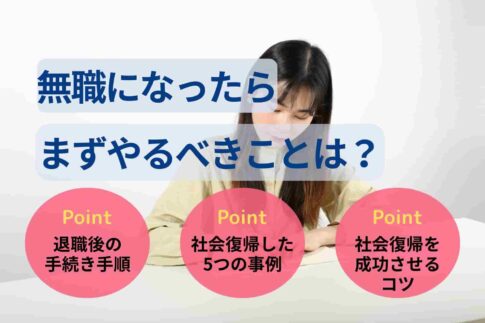無職でも失業保険や求職者支援制度、教育訓練給付金など、複数の制度を組み合わせると100万円の給付金を受け取ることは可能です。
さらに、生活支援だけでなくスキルアップとの両立も実現できる場合があります。
「仕事がなかなか見つからなくて不安…」「無職になったら、どうやって生活すればいいの?」と思う方にこそ知ってほしい制度活用のポイントや注意点を解説しています。
さまざまな給付金の情報を知ると「無職でも当面の生活費が確保できる」という安心感が生まれるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
無職でも給付金100万円は可能?制度を解説
無職でも一定の条件を満たしている場合、複数の公的制度を組み合わせると総額100万円以上の給付を受けられる場合があります。
例えば、雇用保険に加入していた方は失業保険(基本手当)を申請でき、最大で360日分の支給を受けられます。
雇用保険に未加入の方や受給が終了した方は、求職者支援制度を活用して月10万円の職業訓練受講給付金を受けながら、無料でスキルアップの訓練を受けることも可能です。
そのほか、生活が困難な方には住居確保給付金による家賃補助、教育訓練給付金による受講費の一部支給、傷病手当金の支給などの支援策もあります。
それぞれの制度には条件があるため、ハローワークや自立相談支援機関などで相談すると安心です。以下の制度について、それぞれ解説します。
- 失業保険(基本手当)
- 求職者支援制度・職業訓練受講給付金
- 住居確保給付金
- 教育訓練給付金
- 傷病手当金
失業保険(基本手当)
失業保険(基本手当)は、雇用保険の被保険者が離職した後、生活を支えながら再就職を目指すための給付金です。
自己都合退職や会社都合退職など、離職理由に応じて支給され、所定給付日数は90日〜360日です。
以下2点の条件を満たした際に、失業保険(基本手当)が受給できます。
- 求職活動中で、すぐに就業できる状態であること
(病気や育児中などで就労不能な場合は対象外) - 離職前の2年間で雇用保険に通算12ヶ月以上加入していること
会社都合退職や特定理由離職(病気などのやむを得ない事情)の場合は、離職前の1年間に通算6ヶ月以上雇用保険に加入していること
雇用保険で受給できる1日あたりの金額(基本手当日額)は以下のとおりです。
離職した日の直前に毎月支払われた賃金(賞与等を除く)の合計を180で割った金額の約50%~80%
基本手当日額(令和6年8月1日現在)
| 年齢 | 基本手当日額(上限額) |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,065円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
退職後、会社から離職票が届いたら早めにハローワークで手続きしましょう。
参考:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について
求職者支援制度・職業訓練受講給付金
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない離職者や低収入の在職者が、月10万円の生活支援給付金(職業訓練受講給付金)を受けながら無料の職業訓練を受講できる国の制度です。
再就職や転職、スキルアップを目指す方に向けて、ハローワークが訓練前から終了後まで一貫した就職サポートを提供します。
求職者支援制度の対象者は次のとおりです。
- 雇用保険に未加入の方や自営業を廃業した方、失業保険の受給が終了した方など、失業保険(基本手当)が受給できない離職者で、労働の意思と能力がある方
- ハローワークに求職申し込みをしている方
- 月収が一定額以外のパートタイマーなど、正社員への転職を目指す方
求職者支援制度の支給要件は以下のとおりです。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯収入が月30万円以下
- 世帯の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいる所以外に土地や建物を所有していないこと
- 職業訓練の実施日すべてに出席すること(やむを得ない場合は80%以上)
- 世帯の中で求職者支援制度の給付金を受給している方がいないこと
- 過去3年以内に不正などで特定の給付金を受給していないこと
- 過去6年間に職業訓練受給給付金を受給していないこと
求職者支援制度の対象で支給金を希望する場合は、ハローワークで相談しましょう。
求職者支援制度で受給できる職業訓練受給給付金には、職業訓練受講手当と通所手当、寄宿手当の3つが含まれます。詳細については次章で解説します。
参考:厚生労働省 求職者支援制度のご案内
厚生労働省 就職支援・給付金などについて知る
職業訓練受講手当
職業訓練受講給付金は、失業保険(基本手当)を受給できない求職者が無料の職業訓練を受けながら月10万円の生活支援を受けられる制度です。
厚生労働省が運営する「求職者支援制度」の一環で、再就職やスキルアップを目指す方に向けた支援策です。
求職者支援制度の対象者が利用できますが、要件が細かく決められているため、申請する際は事前に確認しましょう。
訓練コースでは事務やIT、デザイン、医療事務、介護・福祉など、さまざまな分野が学べ、学習期間は2ヶ月〜6ヶ月が一般的ですが、1年や2年の長期訓練もあります。
学科試験や面接などの選考があり、合格した場合のみ受講が可能です。また、託児所サービスを利用できるコースも用意されています。
訓練コースについては、求職者支援制度の要件を満たさない場合でも、無料の職業訓練を受けられるのが特徴です。
参考:厚生労働省 求職者支援制度のご案内
厚生労働省 就職支援・給付金などについて知る
通所手当
職業訓練受講給付金の一部である「通所手当」は、訓練施設への交通費を支援する制度です。
月額の上限は42,500円で、定期乗車券などの実費をカバーします。
支給には本人の収入が月8万円以下、世帯収入が30万円以下など、求職者支援制度と同様の要件を満たす必要があります。
収入の基本要件を満たさない場合でも、本人の収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下の場合で、他の要件を満たす場合は、通諸手当のみを受給するのも可能です。
必要な場合や支給要件に該当するか不明な場合は、ハローワークに相談しましょう。
参考:厚生労働省 求職者支援制度のご案内
厚生労働省 就職支援・給付金などについて知る
寄宿手当
求職者支援制度における寄宿手当は、職業訓練受講給付金の一部として支給されます。
月額10,700円が支給され、訓練施設へ通うために配偶者や子、父母と別居して寄宿する場合に適用されます。
住所変更がハローワークに認められた場合で、アパートや訓練施設に付属する宿泊施設に入居する場合に支給されるのが特徴です。
支給には本人の収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下など、求職者支援制度と同様の要件の場合に支給されます。
寄宿手当は通所手当と併せて申請でき、職業訓練受講手当(月10万円)とは別枠でもらえます。
参考:厚生労働省 求職者支援制度のご案内
厚生労働省 就職支援・給付金などについて知る
住居確保給付金
住居確保給付金は、離職や解雇、休業などで生活に困窮する世帯を支援する制度で、家賃を自治体から不動産会社等へ直接支払うルールです。対象要件は次のとおりです。
- 主たる生計維持者が離職や廃業後2年以内の場合
- 給与が離職や廃業と同程度に減少した場合
- 世帯収入が市町村民税非課税基準の1/12以下(基準額)かつ家賃額を超えないこと
- 預貯金が市区町村の定める額(基準額の6ヶ月分、上限100万円)を超えないこと
住居確保給付金を利用する際はハローワークで求職申し込みをしつつ、月2回以上の職業相談と週1回以上の求職活動を行う必要があります。
自営業者の場合は、事業の再生活動で代替可能です。
対象要件に合う場合は、住居確保給付金が原則3ヶ月間支給されます。
延長は2回以内に限られ、最大9ヶ月まで受給が可能です。
支給額は市区町村ごとの上限(生活保護の住宅扶助額)を適用します。
東京都特別区の場合、支給の上限額は次のとおりです。
| 世帯の人数 | 支給上限額(月額) |
|---|---|
| 1人 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3人 | 69,800円 |
必要な場合は、最寄りの自立相談支援機関で相談しましょう。
教育訓練給付金
教育訓練給付制度は、厚生労働省が提供する雇用支援制度です。
労働者の能力開発やキャリア形成を促進し、雇用の安定と就職を図ることを目的としています。
離職してから1年以内、今までに教育訓練給付金を受けたことがないなど、一定の受給要件を満たす方が指定講座を修了すると、教育訓練経費の一部が給付金として支払われるのが特徴です。
教育訓練給付金には専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金、一般教育訓練給付金の3種類があり、それぞれ支給の割合などが異なります。
対象講座は「教育訓練講座検索システム」で検索でき、約17,000講座が用意されています。
夜間や土日、オンラインで受講できる講座もあるため、平日は仕事で忙しい方でも利用できるでしょう。
支給を申請する際は管轄のハローワークで手続きができます。
教育訓練給付金を申請すると、自己投資の負担を軽減しながらキャリアアップが可能なため、ぜひ活用しましょう。
専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金、一般教育訓練給付金については、次章でそれぞれ解説します。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練は、労働者の中長期的なキャリア形成を支援する制度です。
業務独占資格やデジタル関係、大学院・大学・短期大学・高校専門学校・専門学校の課程も含まれるのが特徴です。
対象となる教育訓練を修了すると、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練中6ヶ月ごとに支給されます。
資格取得後かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合、支給率が70%(上限56万円)にアップします。
さらに、令和6年10月以降に講座を受講して賃金が受講前よりも5%以上上昇した場合、支給率が80%(上限64万円)に増額される点も大きなメリットです。
専門実践教育訓練給付金と同様、講座を開始する前にキャリアコンサルティングや受給資格の確認があるため、受講前にハローワークで必ず確認しましょう。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練は早期の再就職やキャリアアップを支援する制度で、業務独占資格やデジタル関連、大学や専門学校の課程が対象です。
受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。さらに、資格取得後かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合は給付額が50%(上限25万円)に引き上げられます。
制度を利用するためには、講座を受講する前にキャリアコンサルティングや受給資格の確認を行う必要があります。
条件を満たしていないと給付が受けられないため、手続きや対象講座についてハローワークで事前に相談しましょう。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練は、資格の取得を目的とする講座が主な対象です。
支給額は受講費用の20%(上限10万円)で、修了後にハローワークへ申請すると給付金が受け取れます。
専門実践教育訓練や特定一般教育訓練と異なり、受講前のキャリアコンサルティングや受給資格の確認が不要なため、気軽に受講できるでしょう。
専門実践教育訓練や特定一般教育訓練に比べて対象講座が多く、語学や事務スキルだけでなく医療や福祉、営業や技術など、さらに幅広く選べるのが大きな魅力です。
受講要件は雇用保険の被保険者歴など、一定の条件を満たす必要があります。
対象の口座は教育訓練講座検索システムで確認でき、手軽な自己投資として活用できるのがメリットです。
傷病手当金
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与を受け取れない場合に健康保険から支給される給付金です。
支給には連続3日以上の休暇(待期期間)が必要で、4日目以降が対象です。
支給は開始日から最長で1年6ヶ月で、以下の場合は給付金が調整されます。
- 給与が一部支払われる場合:傷病手当金との差額を支給
- 障害厚生年金や労災補償を受ける場合:原則非支給(差額あり)
- 出産手当金と重複している場合:高い方の給付を優先
退職後も傷病手当金を受給する場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 退職の前日までに1年以上の被保険者期間があること
(任意継続被保険者と国民健康保険は除く) - 資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、受給条件を満たしていること
- 退職日に出勤していないこと
1日当たりの額は「支給開始日前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」で算出します。
支給開始日以前の期間が12ヶ月未満の場合は、以下いずれかの金額が低い方の基準額で計算します。
- 支給開始日前12ヶ月の標準報酬月額の平均
- 標準報酬月額の平均額が30万円(支給開始日が令和7年3月31日以前の方)または32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)
自分が傷病手当金の対象になるか不明な場合は、退職前に健康保険の担当者へ確認しましょう。
参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金
全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金について(退職後の申請)
給付金が100万円になる主な組み合わせ
複数の給付金を組み合わせると、総額100万円程度の経済的な支援を受けられる場合があります。
主な組み合わせとして、失業保険と教育訓練給付金、求職者支援制度と教育訓練給付金、傷病手当金と住居確保給付金の3パターンが挙げられます。
それぞれの制度には支給要件が設けられており、すべての人が必ず利用できるわけではありません。
ただし、それぞれの条件を満たせれば、収入の不安を和らげながら次のステップへ進むための後押しとなります。以下の内容について、詳しく見ていきましょう。
- 失業保険+教育訓練給付金
- 求職者支援制度+教育訓練給付金
- 傷病手当金+住居確保給付金
- 組み合わせのポイント
失業保険+教育訓練給付金
雇用保険の基本手当(失業保険)と教育訓練給付金を併用すると、100万円超の支援が受け取れる場合があります。
失業保険は離職前の賃金の50〜80%が支給され、条件によって最長360日まで受給可能です。
失業保険に加えて専門実践教育訓練を受講する場合、教育訓練給付金で年間最大64万円(教育訓練講座の80%)が受け取れます。
資格を取得した後、1年以内に就職して賃金が5%以上増加した場合、上限64万円の給付が適用される点が特徴です。
申請のポイントは、失業保険の受給中に教育訓練を開始することです。
例えば、7,065円(30歳未満の基本手当日額)の失業保険を90日受給しつつ、教育訓練給付金を64万円受給した場合は次のとおりです。
失業保険(90日):7,065円 × 90日 = 635,850円
教育訓練給付金:講座費用80万円の80% = 640,000円
合計:1,275,850円
このように、失業保険と教育訓練給付金を上手に活用すると、無職で給付金を確保しながらスキルアップを目指すことが可能になります。
参考:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 教育訓練給付制度
求職者支援制度+教育訓練給付金
雇用保険の対象外となった方向けの求職者支援制度では、月額10万円の職業訓練受講手当が支給されます。
求職者支援制度に教育訓練給付金を組み合わせると、6ヶ月で100万円超の支援が可能です。
例えば専門実践訓練(最大64万円)を並行して受講する場合、自己負担分の70〜80%が給付金でカバーされ、実質的な負担軽減が図れます。
例えば、専門実践教育訓練を6ヶ月受講したうえで教育訓練給付金を56万円受給した場合は以下のとおりです。
職業訓練受講手当:100,000円 × 6ヶ月 = 600,000円
教育訓練給付金(70%):講座費用80万円の70% = 560,000円
合計:1,160,000円
求職者支援制度と教育訓練給付金を併用すると、経済的な不安を和らげながら再就職に向けた学び直しを効果的に進められます。
参考:厚生労働省 求職者支援制度のご案内
厚生労働省 就職支援・給付金などについて知る
厚生労働省 教育訓練給付制度
傷病手当金+住居確保給付金
傷病手当金と住居確保給付金は、療養中で働けない場合でも活用できる組み合わせです。
傷病手当金は標準報酬月額の2/3が最長で1年半支給され、これに住居確保給付金を加えることで家賃の負担を軽減できます。
住居確保給付金は東京都特別区の単身世帯の場合、月額で最大53,700円の家賃補助を提供し、原則3ヶ月(延長で最大9ヶ月)受給可能です。
例えば、傷病手当金が150日、住居確保給付金(東京都特別区単身・3ヶ月)の場合は次のとおりです。
傷病手当金(150日):6,000円 × 150日 = 900,000円
住居確保給付金(東京都特別区単身・3ヶ月):53,700円 × 3ヶ月 = 161,100円
合計:1,061,100円
申請時は、離職後2年以内や預貯金100万円以下などの条件がある点に注意が必要です。
参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金
全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金について(退職後の申請)
厚生労働省 住居確保給付金
組み合わせのポイント
給付金を組み合わせる際は、各制度の特性や条件を理解してからアプローチしましょう。
例えば、傷病手当金は病気やケガなどで働けない方が受給できるため、すぐに就業が可能な方が受け取れる職業訓練や教育訓練給付金との併用は原則不可です。
教育訓練給付金は最大64万円のため、単体で100万円の給付金を受給するのは難しいでしょう。そのため、失業保険(基本手当)や求職者支援制度の併用がおすすめです。
また、教育訓練給付金と失業保険(基本手当)や求職者支援制度を組み合わせると、訓練期間中の生活費と学費を同時にサポートできるのが大きなメリットです。
上記のように、給付金の仕組みを正しく理解しながら適切に組み合わせると、無職で100万円の給付金が受け取れます。
無職で給付金を100万もらうための注意点
無職で給付金を確実に受け取るためには、制度ごとの注意点を正しく理解しておく必要があります。
まず、傷病手当金と失業保険は併用できません。療養中で働けない場合は失業保険の対象外となるため、体調が回復してから失業保険を受け取る手続きを進めましょう。
また、アルバイトをしていると「就職している」と判断され、給付金が支給されない場合があります。勤務時間や契約内容によって扱いが異なるため、事前にハローワークへ確認しましょう。
職業訓練を受講する際は出席率が80%を下回ると給付金が支給停止となる場合があるため、継続して参加する必要があります。
さらに、住居確保給付金の審査や手続きに1~2ヶ月かかるケースがあり、早めの相談が必要です。
加えて、虚偽の申請は給付金の全額返還や場合によっては法的措置が取られる可能性もあります。制度を理解し、正しく申請しましょう。
無職で100万円の給付金をもらうために注意すべきことを5点、以下でそれぞれ解説します。
- 傷病手当金と失業保険は併用できない
- アルバイトをすると給付金がもらえない可能性がある
- 職業訓練に欠席すると給付金がもらえない場合がある
- 住居確保給付金は審査に1~2ヶ月かかる場合がある
- 虚偽報告の場合は全額返還や追加納付の可能性がある
傷病手当金と失業保険は併用できない
傷病手当金と失業保険が併用できないのは、傷病手当金が「健康保険制度に基づき、病気やけがで働けない期間の生活保障」を目的とする一方、失業保険は「離職後すぐに働ける状態で積極的に求職活動する人」を対象とする制度だからです。
病気療養中はすぐに働ける状態ではないため、失業保険の受給資格を満たせません。
逆に、傷病手当金は就労不能な状態が給付の条件であるため、求職活動が行える方は傷病手当金を受給できません。
失業保険の受給期間は最大3年まで延長申請が可能なため、傷病手当金で療養期間をカバーし、回復したら失業保険を受給するという方法があります。
参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金
全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金について(退職後の申請)
厚生労働省Q&A 雇用保険(基本手当)の受給要件
厚生労働省Q&A すぐに働けない場合
アルバイトをすると給付金がもらえない可能性がある
アルバイトをしていると「職業に就いている」と見なされるため、給付金を受け取れない場合があります。
以下のいずれかに該当する場合は「就職している期間」とされるため、給付金は受給できません。
- 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがある場合(原則)
- 契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上かつ1週間で4日以上働いている場合
上記の要件に当てはまらない場合、雇用保険の手続きが可能なケースがありますが、働いた日は支給の対象とならなかったり、収入によって減額されたりする場合があります。
就職しているかの確認や判断はハローワークにて行っています。不定期で短時間のアルバイトをしている場合など、判断が難しい場合はハローワークに問い合わせましょう。
参考:厚生労働省Q&A アルバイトをしている場合の雇用保険(基本手当)
職業訓練に欠席すると給付金がもらえない場合がある
職業訓練中に欠席すると給付金が支給されない場合があるのは、給付金の目的が「真剣な訓練の受講と就職支援」にあるためです。
職業訓練給付金は就職に向けて真剣な取り組みを支援するためのもので、単なる生活保障ではありません。
職業訓練への参加は就職活動の一環と位置づけられており、欠席が続くと「就労意欲の欠如」と見なされる場合があります。
給付金を受給するためには、原則として訓練実施日すべてに出席する必要があり、やむを得ない理由で証明書の提出ができる場合でも、80%以上の出席が必要です。(育児や介護、求職者支援訓練の基礎コースの場合は証明できない場合を含める)
職業訓練の継続が難しい場合や、出席率が80%を維持できないと思われる場合は、事前にハローワークへ相談しましょう。
住居確保給付金は審査に1~2ヶ月かかる場合がある
住居確保給付金は、離職や収入の減少で住居を失う可能性のある方に家賃を補助する制度です。
条件や手続きが複雑なため、自治体によっては申請から支給決定まで1〜2ヶ月かかる場合があります。住居確保給付金にかかる手続きの主な流れは次のとおりです。
- 最寄りの自立相談支援機関(市区町村の福祉課など)に相談する
- 支給要件に該当するかを自立相談支援機関にて判断する
- 申請の対象となった場合、申請者が必要書類を準備する
(本人確認書類、収入が確認できる書類、預貯金額が確認できる書類、離職や休業状況の証明書類など) - 作成した書類を申請者が自立相談支援機関に提出する
- 提出書類に不備がなければ、自治体が審査する
- 支給決定または不支給の通知が郵送される
- 給付金が不動産会社などの口座へ直接振り込まれる
住居確保給付金を支給されている間は、以下の活動が必要です。
- ハローワークへの求職申込みと職業相談(月2回以上)
- 企業等への応募(週1回以上)
- 自営業者の場合は事業再生のための活動も可能
住居確保給付金の支給には時間がかかるため、支援が必要な方は早めに自立相談支援機関へ相談しましょう。
虚偽報告の場合は全額返還や追加納付の可能性がある
虚偽報告によって給付金を不正に受け取ると、以下のように厳しい処分が科される場合があります。
- 支給停止:不正行為後の給付は一切受けられない
- 返還命令:不正受給額と延滞金を返還
(例:100万円を不正受給した場合、100万円+延滞金を返還) - 納付命令:不正額の最大2倍額を追加納付
(例:100万円を不正受給した場合、200万円を納付) - 強制処分:返還や納付を怠ると財産を差押えされる
- 刑事告発:悪質な場合は詐欺罪で告発される(刑法の適用)
不正受給の主な行為は次のとおりです。
- 就労の未申告:パートやアルバイト、試用期間中の未報告(収入がなくても申告が必要)
- 虚偽申請:就職日や求職活動の実績に関する虚偽報告
- 収入の隠蔽:パートやアルバイト、内職や手伝いで得た収入や自営開始の未報告(準備段階でも申告が必要)
- 重複給付:健康保険の傷病手当金や労災保険を隠して受給(雇用保険との重複不可)
- その他:離職や書類の偽造など
虚偽の申告による不正受給は重いペナルティの対象となるため、正しい情報で申請しましょう。
無職でも給付金100万円は可能?に関するよくある質問
「無職でも給付金100万円は可能?」に関するよくある質問をまとめました。
制度の組み合わせや申請条件を理解しておくと、無職で利用できる支援策を最大限に活用できます。給付金の申請や生活の再建を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
無職になったばかりでも給付金はすぐに申請できる?
無職になった直後でも給付金の申請は可能です。離職後は速やかにハローワークで手続きをしましょう。
ただし、給付金を受け取れるタイミングは制度や状況などによって異なります。
- 契約期間満了や解雇、令和7年4月以降に教育訓練等を受けた場合:ハローワークに離職票を提出→7日間の待機期間が経過した後に支給開始
- 自己都合の場合:ハローワークに離職票を提出→7日間の待機期間が経過した1ヶ月後に支給開始
求職者支援制度:訓練を受講している期間について、要件を満たすと1ヶ月ごとに支給
早めに手続きをすると、安定した生活と再出発への一歩につながります。
参考:厚生労働省 離職されたみなさまへ
厚生労働省 求職者支援制度のご案内
失業保険(基本手当)の受給資格がない場合は?
失業保険(基本手当)の受給資格がない場合は、求職者支援制度を利用できるケースがあります。
求職者支援制度は、失業保険(基本手当)の受給資格がない方に向けた国の支援策です。
雇用保険の適用がなかった方と、自営業やフリーランスを廃業した方、失業保険(基本手当)の受給が終了した方などが該当します。
月額で最大10万円の給付金を受けながら、無料の職業訓練を受講できるのが特徴です。
ITや医療事務、介護福祉、事務やデザインなど、さまざまな訓練コースが用意されており、2ヶ月から6ヶ月で終了するのが一般的です。
訓練コースはハローワークインターネットサービスより検索できます。
参考:厚生労働省 求職者支援制度のご案内
厚生労働省 就職支援・給付金などについて知る
病気やうつで働けない場合でも給付金はもらえる?
病気やうつで働けない場合は、傷病手当金や障害年金が利用できる場合があります。条件を満たせば、収入源を補いつつ治療に専念できる仕組みです。
傷病手当金は最大で1年6ヶ月受給でき、利用できる条件は次のとおりです。
- 健康保険の加入者が業務外の病気(私傷病)で連続4日以上働けず、給与がもらえない場合
- 前職で傷病手当金を受給しており、退職後も引き続き申請する場合
障害年金は病気などで働けない場合に、現役世代も受け取れる年金です。受給できる主な条件は以下のとおりです。
- 初診日が年金加入期間中(20歳~65歳)であること
- 直近1年間において年金の滞納がないなど、納付の要件を満たしていること
申請の際は診断書や初診時の証明書が必要です。不明な点は年金事務所に確認しましょう。
参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金
全国健康保険協会 協会けんぽ 傷病手当金について(退職後の申請)
日本年金機構 障害年金
家族と同居していても住居確保給付金は受け取れる?
家族と同居していても、住居確保給付金は受け取れる場合があります。
住居確保給付金は個人ではなく世帯単位で適用されるため、同居の家族がいる場合でも世帯全体の収入などが要件を満たせば支給対象になるからです。
世帯の収入額が基準額以下の場合、家賃額(支給額の上限まで)が支給されます。
一方で、世帯の収入額が基準額を超える場合、基準額+家賃額-世帯収入額(支給額の上限まで)が受け取れます。
東京都特別区の場合、支給の上限額は2人世帯で最大64,000円、3人世帯で最大69,800円です。
支給上限額は自治体によって異なるため、最寄りの自立相談支援機関へ相談しましょう。
参考:厚生労働省 住居確保給付金
厚生労働省 住居確保給付金 申請・相談窓口
給付金を100万円もらったら確定申告は必要?
給付金は非課税所得とされているため、原則として確定申告は不要です。それぞれの給付金について解説します。
失業保険(基本手当):
失業保険(基本手当)は原則として確定申告は不要です。雇用保険法第12条で非課税所得と定義されており、所得税や住民税の課税対象にならないためです。
参考:法令リード 雇用保険法
求職者支援制度:
求職者支援制度は所得税や住民税の課税対象外とされており、確定申告が不要です。
非課税である点は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」第10条に明記されています。
参考:法令リード 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
住居確保給付金:
住居確保給付金は非課税収入として扱われるため、確定申告での申告は不要です。公課の禁止である旨「生活困窮者自立支援法」第20条に記載されています。
参考:法令リード 生活困窮者自立支援法
教育訓練給付金:
教育訓練給付金は非課税のため、確定申告は不要です。雇用保険法第10条に記載されており、非課税である点は「第12条公課の禁止」に明記されています。
参考:法令リード 雇用保険法
傷病手当金:
傷病手当金は健康保険から支給されるもので、非課税所得に該当します。そのため、確定申告は原則不要です。
参考:国税庁 給与所得(傷病手当金、育児休業手当金を受け取った場合)
求職者支援制度の職業訓練を途中で辞めたら、給付金はどうなる?
求職者支援制度の職業訓練を途中で辞めた場合、給付金が支給されないだけでなく、すでに受給した分の返還を求められる可能性があります。
職業訓練は就職を目指す方のための制度です。そのため、訓練に80%以上出席する必要があります。
途中で辞めると就職支援を拒否したと見なされ、その期間の給付金は不支給となります。
場合によっては、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の全額返還を請求されるかもしれません。
病気などのやむを得ない理由がある場合は、証明書を提出すれば例外として扱われる可能性がありますが、自己判断での辞退は避け、ハローワークに相談しましょう。
制度を組み合わせるには、どこに相談すればいい?
失業保険(基本手当)や求職者支援制度、教育訓練給付金、傷病手当金、住居確保給付金などを組み合わせて総額100万円程度の給付を受けたいと考えている方は、ハローワークや市区町村の自立相談支援機関などへ早めに相談することをおすすめします。
制度によって相談先が異なるため、それぞれの窓口で最新情報を確認しながら進めましょう。以下は主な制度と相談先の一覧です。
複数の制度を組み合わせる場合は、条件の重複や時期の調整が必要になる場合があります。
早めに各窓口へ相談し、自分に合った支援の活用方法を確認しておくと安心できるでしょう。
まとめ
無職で受給できる給付金の制度や、給付金が100万円になる主な組み合わせと注意点について解説しました。
無職の方でも給付金を100万円受け取ることは可能です。
失業保険や求職者支援制度、教育訓練給付金、傷病手当金、住居確保給付金など、複数の制度を組み合わせると、100万円以上の経済的な支援を受けられる場合があります。
失業保険+教育訓練給付金や、求職者支援制度+教育訓練給付金、傷病手当金+住居確保給付金の組み合わせが代表的な例です。
それぞれの制度には要件や注意点があり、アルバイトや虚偽申請、職業訓練の欠席によって給付金が停止または返還対象となることもあるため、制度を正しく理解しつつ正確な申請が求められます。
給付金は原則非課税で確定申告の必要はありませんが、制度の詳細はハローワークや自治体などに確認すると安心できます。
無理のないペースで情報を集めながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
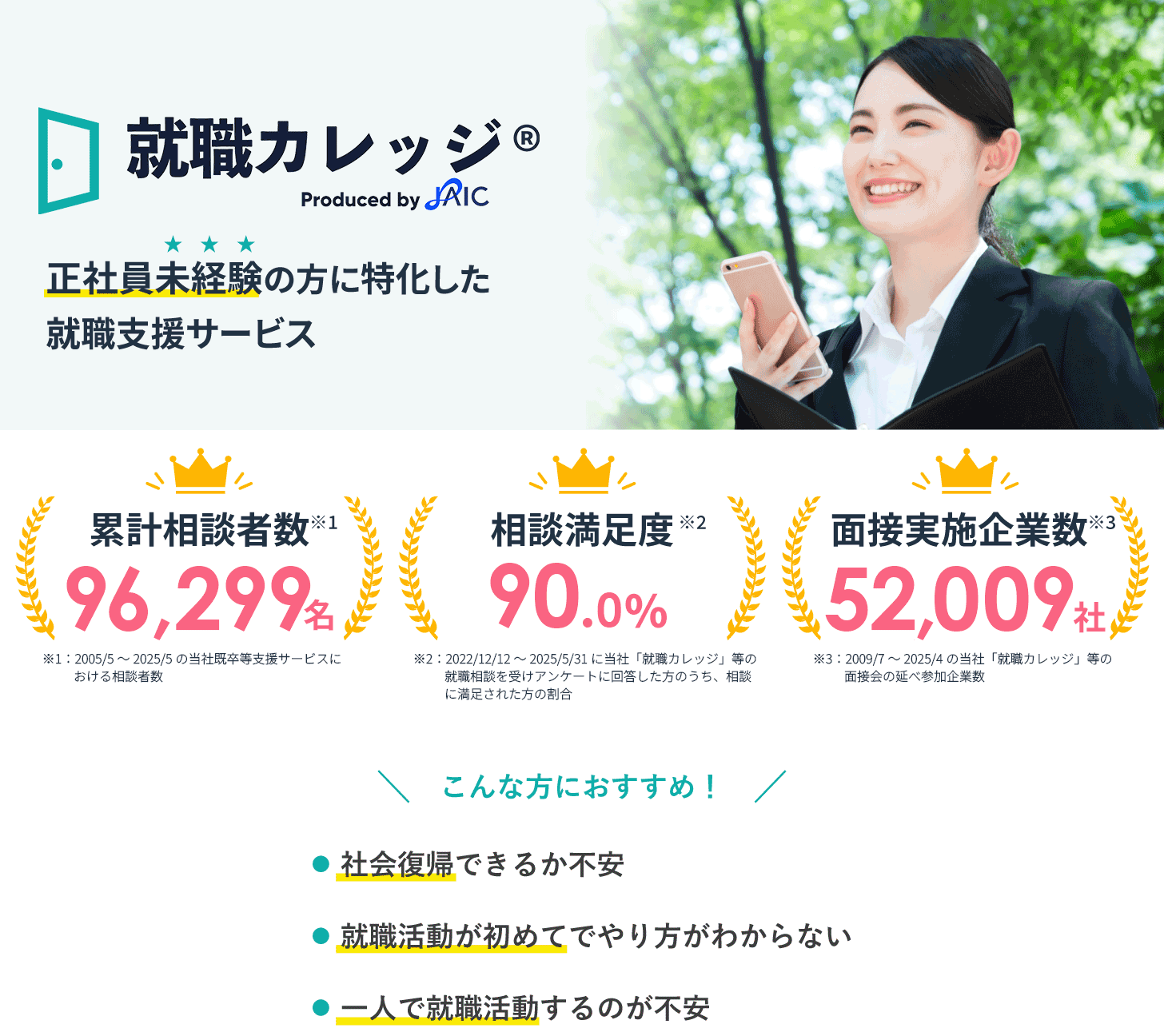
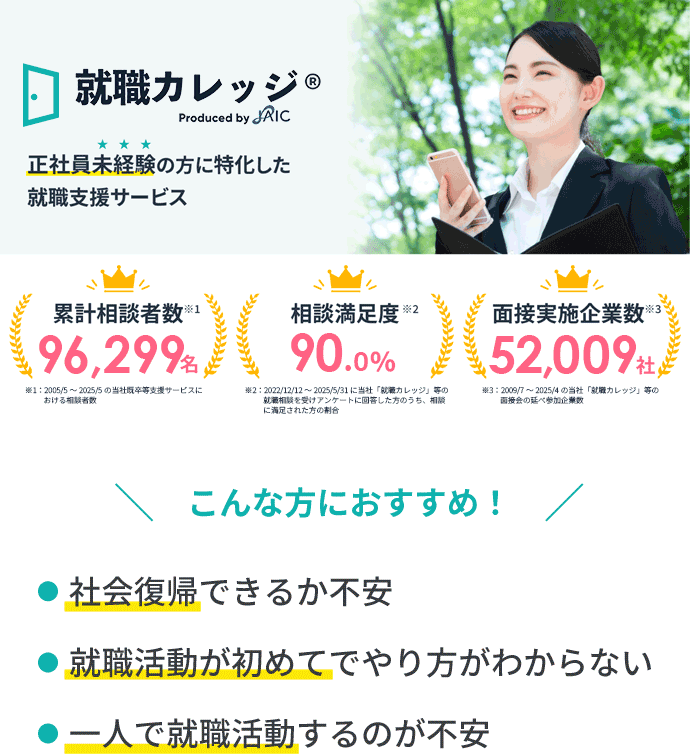

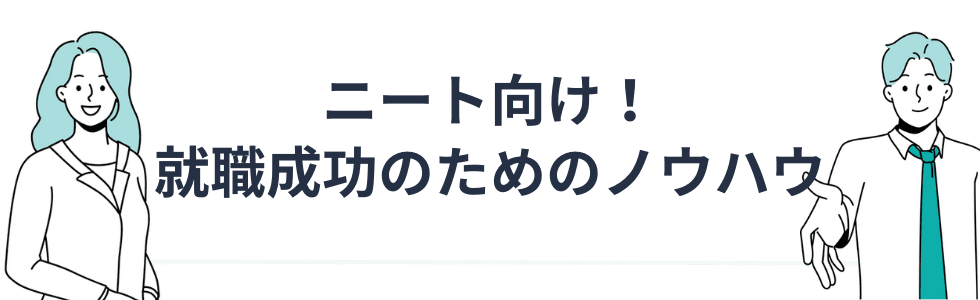
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。