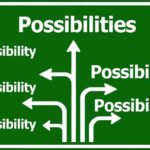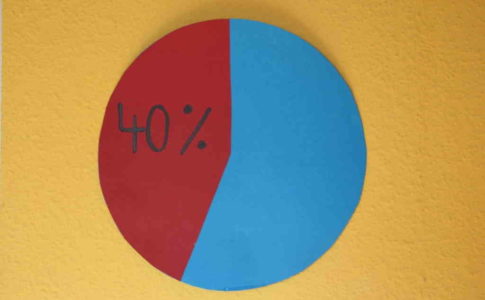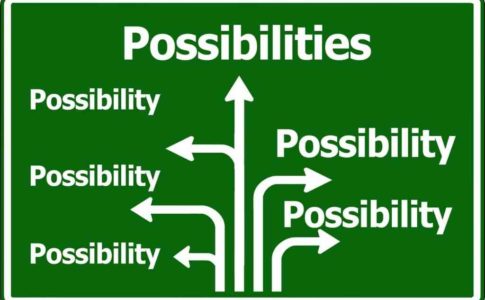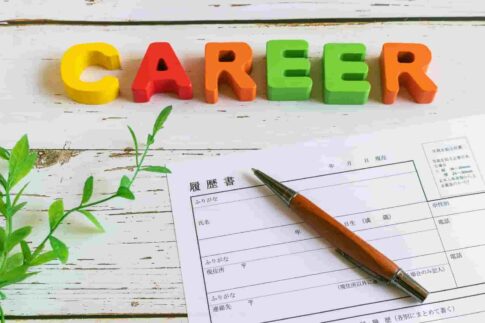高卒で公務員へ就職すると、将来的に安定すると言われてきました。一方で、高卒で公務員になったものの、後悔している人が一定数いるのも事実です。
この記事では、高卒で公務員になる前に知っておいてほしい6つの事実についてご紹介します。
また、高卒で公務員以外に民間企業への就職を視野に入れている方もいるでしょう。公務員と民間企業でどのように違うのか、公務員のメリット・デメリットなどを解説していますので、自分に合った仕事を見つけるための参考にしてみてください。
この記事の目次
高卒で目指せる公務員の2つの選択肢

高卒者は、地方公務員と国家公務員のいずれも目指すことが可能です。高卒で公務員になることを検討している方はまず、それぞれの違いについて知りましょう。
地方公務員
地方公務員の特徴は、以下の通りです。
- 仕事内容:地方自治体などに勤務し、その地域で行政サービスなどを主に担当
- 職種:役所職員、消防士、警察官、学校事務、議会議員など
- 初任給:一般行政職の場合…高卒15万2039円、大卒18万5939円
- 異動や転勤の有無…地方自治体内の異動あり。全国転勤などは少ない
地方や地域に根差して働く仕事が、地方公務員だと覚えておきましょう。
国家公務員
国家公務員の特徴は、以下の通りです。
- 仕事内容:地方自治体などに勤務し、その地域で行政サービスなどを主に担当
- 職種:官公庁職員(総務省、財務省、宮内庁など)、検察官、裁判所職員、国会議員など
- 初任給:一般職の場合…高卒15万600円、大卒:18万2200円
- 異動や転勤の有無…異動・転勤ともにあり。ただし転勤はエリア内のケースもある
立法、司法、行政という「国」のために仕事をするのが、国家公務員だと把握しておきましょう。

高卒で目指せる公務員の職種
公務員は、私たちの地域を安全に保ち、良くするために大切な仕事をします。ここでは、高卒で目指せる公務員の職種について、その仕事内容や勤務場所などを解説します。自分が望む職種なのかを検討し、今後の参考にしてみてください。
役所職員
役所職員は、市や町、都道府県の役所で働く公務員です。彼らは、住んでいる地域のさまざまな仕事を担当します。
たとえば、市や町の役所では、戸籍や住民票の管理・審査等の窓口業務から市民の相談・アドバイスなどのサービスを提供するのが主な仕事です。都道府県の役所では、地域の計画を立てたり、地元の産業を盛り上げるなどが主な仕事内容になります。
役所職員は、地域のためにいろいろな企画を考えたり、住民のために必要な事務作業を行ったりして、その地域の運営に貢献します。この仕事を通じて、多くの経験を積むことができ、地域社会の成長に直接関わることができます。
消防士
消防士は、火事や災害が起きたときに活躍する公務員です。消防士の仕事は、火災の際に消火活動を行なったり、急な病気やけがの応急処置をしたり、災害があったときに救助活動をするなど、多岐に渡ります。消防士は市や町の消防署で働き、いつでも出動できるように24時間体制で待機しています。
消防士になるには、体力や精神力、チームで働く力が必要です。そのため、訓練をして専門的な知識や技術を学びます。消防士になると、地域の安全を守る大切な責任があり、多くの人の命を救うことで大きな達成感を得られます。
警察官
警察官は、みんなの安全と秩序を守る大切な仕事をする公務員です。彼らは、警察署や交番で働き、犯罪を防いだり捜査したり、交通を安全にしたりすることで、私たちの住む地域を守るために日々頑張っています。警察官にはいろいろな種類があり、特殊部隊や警察学校で働くこともできます。
警察官になるには、法律の知識や犯罪に対する理解、そして人と話す力が必要です。この仕事は、地域社会に貢献するとともに、自分自身も成長しスキルを上げるチャンスがあります。警察官は日々の仕事を通じて、私たちが安全に暮らせる社会を作るために努力をしています。
学校事務
学校事務は、学校での事務作業や管理の仕事をする公務員です。彼らは、小学校、中学校、高校、大学などで、生徒や先生のサポートを行います。たとえば、新しい生徒が入学する手続き、成績の管理、新しい先生を採用する手続き、学校の行事を企画したり運営したりすることなどがあります。
学校事務は、学校がうまく運営されるのを助ける大事な役割を持っています。また、学校の教育環境をよくするのにも役立ちます。この仕事では、人と話す力や細かい事務作業の能力が必要です。これらのスキルを使って、仕事で成長しキャリアを築くことができます。
議会議員
議会議員は、私たちの住む地域の議会で、住民の代表として活動する公務員です。彼らは、市や町、都道府県の議会に所属し、地域に住む人たちの意見や要望を聞いて、それを議会で伝える大事な役割を持っています。議会議員は、地域のルールを作ることやお金の使い方を決めること、政府の仕事をチェックします。
議会議員になると、地域社会を良くするために直接働くことができます。また、政策を考える力や、公共の問題に対する理解が必要です。これらのスキルを使って、自分のキャリアを築くこともできます。
官公庁職員
官公庁職員は、日本の国や地方でいろいろな行政の仕事をする公務員です。国民の生活を支える政策やサービスを考えたり、実際に行ったりしています。働く場所は、国の省庁や地方の役所、特別な機関などさまざまです。
官公庁職員には、税金のこと、社会保障、環境のこと、国と国との関係など、いろいろな専門知識や幅広い知識が必要です。この仕事をすると、日本や地域社会をよくするために直接貢献できるだけでなく、みんなの幸せを高めることにも役立ちます。
検察官
検察官は、犯罪を調べたり、裁判を行ったりする公務員です。法務省に属する検察庁で働き、法律に従って犯罪を捜査し、その人を裁判にかけるかどうかを決めます。検察官は、公平で正確な捜査をする責任があり、裁判所で訴えを起こし、公正な判断を求めます。
検察官の仕事は、社会の正義を守るためにとても重要で、法律の知識や論理的に考える力が必要です。検察官になると、法律に基づいた平等と公正を実現するために貢献することができます。
裁判所職員
裁判所職員は、裁判をスムーズに進めるために働く公務員です。裁判所で働き、裁判の準備や書類の整理、裁判の進行を手伝う仕事をします。裁判所職員は、裁判官や検察官、弁護士と一緒に働いて、公平な裁判が行われるようにサポートする重要な役割を持っています。
この仕事では、法律の知識や細かい事務作業ができる能力が必要です。裁判所職員として働くことで、法律のもとでの正義と公正を実現するのに貢献することができます。
国会議員
国会議員は、日本の国の政治を担う公務員です。彼らは国会で働き、新しい法律を作ったり、古い法律を改正したり、政策を議論したりします。国会議員は、国民の意見や要望を反映させる大切な役割を持ち、政府の活動を見守る責任もあります。
国会議員は、選挙で国民に選ばれた代表として、日本の方向や社会の未来を決めるのに直接関わります。また、国の政策を考えたり、国民の幸せを向上させたりすることで貢献します。国会議員として働くことは、国がどう進むべきかを決める大きな責任を伴います。
高卒の公務員になる前に知っておくべき6つの事実

地方公務員と国家公務員の基本的な違いを理解できたでしょうか。次に、高卒で公務員になることを決める前に、知っておきたい6つの事実をご紹介します。
1.「高卒程度」と「大卒程度」の違い
公務員試験における「高卒程度」と「大卒程度」の違いは、主に年齢要件に基づいています。
つまり、試験が学歴に基づいて区別されているのではなく、高卒者でも年齢要件を満たせば、大卒程度の試験を受けることが可能となります。
ただし、大卒程度の試験は高卒程度に比べて難易度が高く設定されていて、専門科目が含まれることもあります。よって、試験の難易度は「高卒程度」と「大卒程度」とでは異なりますので、その点は注意が必要です。
2.高卒で公務員になれる確率
日本資格取得支援の国家公務員一般職(高卒者)と、地方公務員によれば、2019年度の公務員の合格率は以下の通りです。
- 国家公務員:19.8%(高卒程度試験)
- 地方公務員:17.9%(全体)
いずれも狭き門ですが、特に地方公務員は「自分の生まれ育った地域に貢献したい」「なじみのある地元で働きたい」と考える人が多く、より競争が激しくなっていることが考えられます。
3.高卒公務員と大卒公務員は年収の差がある
人事院勧告「国家公務員の初任給の変遷(行政職俸給表(一)」によれば、国家公務員の高卒と大卒のそれぞれの初任給は、以下の通りです。
- 高卒公務員:15万600円
- 大卒公務員:18万2,200円
つまり、初任給だけでも約3万円以上の差があることがわかります。仮に高卒が18歳~60歳、大卒が22歳~60歳まで働いたとして、高卒が月に3万円収入が少ない、大卒は月に3万円収入が多いことを考えて計算すると、高卒と大卒の総収入の差は以下となります。
- 高卒公務員:もらえるお金が大卒より1512万円少ない
- 大卒公務員:もらえるお金が高卒より1368万円多い
手当や昇給、職種の違いなどもあるため実際の金額は上記とは異なりますが、単純計算でも、年齢を重ねたときに計1000万円以上は、もらえるお金に差が出ることになります。
4.公務員は学歴社会の傾向がまだ根強い
人事院「一般職の国家公務員の任用状況調査」によると、平成26年度に公務員に試験を受けて採用された人の学歴別の占有率は、以下の通りです。
- 高卒:7.5%
- 大卒:21.5%
高卒の割合は、大卒の約3分の1程度という結果です。どちらかというと国家公務員のほうが大卒の割合が高く、高卒で国家公務員になることができたとしても、大卒とくらべると一定以上のキャリアアップがむずかしいことも考えられます。
5.公務員から民間に転職できる確率は低い
人事院「一般職の国家公務員の任用状況調査」によると、平成26年度の国家公務員全職員の離職率は、以下の通りです。
- 男性:6.3%
- 女性:7.5%
- 合計:6.6%
公務員は、比較的離職率が低い職業です。給料や雇用が安定しているため、自分から辞めない限りは仕事を失う心配がないということもあるかもしれません。
一方で、公務員の仕事は個人のスキルや市場価値を高めることがむずかしい傾向にあります。結果として、ほかの仕事をしたくても転職がしづらいともいえるでしょう。
6.公務員はリモートワークがあまり進んでいない
産経新聞「公務員のテレワーク進まず 住民との窓口多く対応に苦慮」によれば、テレワークを実施している人の割合が公務員はわずか14.5%と、平均以下の結果となっています。
コロナ禍における対応策として、リモートワークを導入した企業は大きく増えました。一方で、公務員の仕事でもリモートワークを取り入れているところもありますが、まだまだ少ない状況です。
役所などでの窓口業務などリモートがむずかしい仕事があるほか「紙の稟議書を回す」などの文化が残っていることも原因のひとつです。公務員の仕事や組織はまだ旧態依然としているところも多く、変化や新しいことに対応するのに時間がかかる傾向も強いといえます。

高卒公務員のメリット・デメリット

高卒で公務員になる前に、理解しておくべき点をご紹介しました。次に、高卒で公務員になるメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
高卒公務員のメリット
高卒公務員のメリットは、以下の通りです。
メリット1.進学のための学費がかからない
高卒で公務員になれば、大学や短大、専門学校への進学費用はかかりません。高校以降は学費を支払う必要がなくなるため、たとえ奨学金を借りても学費を払えないほど経済的に厳しい、勉強を続けるよりも早く安定した仕事がしたいという場合には、高卒公務員として働くほうがよいでしょう。
メリット2.いち早く社会人としての経験を積むことができる
安定した環境で社会人としての経験を積みたい人には、高卒公務員はおすすめです。給料や福利厚生などのことを考えても、高卒であまり待遇がよくない民間企業に就職するよりも、公務員になったほうがそれらのメリットは大きくなります。
高卒公務員のデメリット
高卒公務員のデメリットとしては、以下が考えられます。
デメリット1.目指している役職につけない可能性もある
高卒公務員は、大卒で公務員になった人とくらべると、キャリアアップに限界があるケースがあります。優秀な人材であっても、高卒であるということがハンデになってしまうこともあるのです。民間企業でも学歴が影響する仕事はあるものの、高卒の経歴で活躍できる環境も少なくありません。
デメリット2.同じ環境で仕事を続けるしかない可能性がある
公務員として長く働いた場合「公務員の仕事でしか使えないスキル」ばかり磨かれていくということにもなり得ます。民間企業では、そのスキルが役に立たないこともめずらしくありません。結果として転職の選択肢がなくなり、公務員としてしか働けないというケースもあるのです。

公務員と民間企業の違い

高卒で公務員になる以外の選択肢についてもイメージできたでしょうか。次に、公務員と民間企業の違いについて、3つの観点からそれぞれご紹介します。
違い1.キャリアビジョン
公務員の場合、そこで得たスキルは「公務員の仕事」以外であまり役に立たない可能性があります。もちろんレベルの高い人たちもいますが、公務員特有の仕事のやり方やルールなどは、民間企業でのやり方とはズレていることも少なくないのです。
定年までずっと公務員として働きたい人は問題ありませんが、途中で方向転換をして「民間企業で働きたい」という希望を持ったときに、そこからのキャリアビジョンが描きづらい可能性はあります。
民間企業の場合、ひとつの会社でスキルや知識をつけ、実績を積んでいくことで、転職の際に有利になることがあります。他職種や他業界の転職でも前職の経験を活かせることがあるなど、選択肢が広いことも特徴です。
違い2.昇給・昇格
公務員の給料は、ある意味平等です。基本的には年功序列の傾向があり、職務の級や号給といった、勤続年数や仕事の難易度などが定められていて、それに応じて給料が支払われます。
一方民間企業では、評価制度がしっかりしていれば、本人の実績やスキルなどに応じて昇給・昇格するところも多い傾向です。大手企業などではまだ年功序列が残るところもありますが、なかには廃止する企業も出てきています。
民間企業の場合、自分のがんばりが収入や役職に影響することでモチベーション高く仕事ができる、という特徴があります。公務員の場合、非常に優秀な人もやる気がない人も、長く働いてさえいれば給料が上がっていくため「がんばってもがんばらなくても給料は同じ」と惰性で働くようになる人もやはりいます。
違い3.待遇・福利厚生
公務員は給料のほか、諸手当や退職金なども充実しています。たとえば社宅や休暇制度、各種優待などに関しても、民間企業とくらべて手厚くなっているケースも少なくありません。福利厚生を最大限活用したい人にとっては、公務員は魅力的だといえます。
民間企業の待遇や福利厚生は企業によりばらつきがあるため「働く企業次第」といえます。収入面だけで見ると、公務員よりも多いことはあり得ます。また、企業独自の福利厚生が豊富な民間企業を選べば、恩恵を受けられます。
ただし企業によっては最低限の福利厚生のみだったり、制度はあるけれど使いにくいというところもあります。勤務先にかかわらずある程度のレベルの待遇や福利厚生を受けられるのは、公務員のほうだといえるでしょう。

高卒で公務員を目指すために

公務員の向き不向きについてご紹介しました。比較・検討したうえで「やっぱり自分は高卒で公務員を目指したい」という方もいると思います。高卒で公務員を目指すためにやるべきことについて、基本を押さえておきましょう。
地方公務員へ就職するために
高卒で地方公務員になるための方法は、以下の通りです。
- 試験方法:各都道府県や市町村が行う「地方公務員試験」を受ける
- 試験内容:教養試験、作文、個別面接(自治体により異なる。二次試験で集団討論や適性試験を課すところもある)
- ポイント:面接のウエイトも比較的高いため、各自治体が求める人材像を押さえておくことが必要。申込期間に間に合うよう、自治体のHPや広報誌などで、定期的に採用試験情報をチェックすべし
地方公務員は、各自治体によって対応が異なります。定期的に情報を調べておきましょう。
国家公務員へ就職するために
- 試験方法:人事院が実施する「国家公務員試験」を受ける
- 試験内容:基礎能力試験、適性試験、専門試験、作文試験、個別面接(人物試験)
- ポイント:試験情報に関することは人事院のホームページに記載。採用試験のスケジュールはもちろん、各種セミナーや説明会の情報もあるため、こまめに見て情報収集すべし
国家公務員の試験情報を得るために、人事院のホームページは定期的にチェックしておきましょう。
高卒で公務員を目指すときの注意点
高卒で公務員を目指す場合には、以下のことに注意しましょう。
高卒程度試験には年齢制限がある
公務員試験の場合、試験の種類に応じてそれぞれ年齢制限があります。高卒程度の試験に関しては、高校を卒業見込み、または卒業後2年以内という条件があるケースが多くなっています。
高卒程度試験を受けられる年齢制限を超えても公務員になりたい場合、大卒資格などを取得して大卒程度の公務員試験を受けるなど、別の対応が必要になってきます。
「高卒で公務員になりたい」という強い希望がある人は、早めの対策スタートが必須です。
過去問対策は必須
公務員試験の勉強のなかで、過去問対策は必須です。出題される問題に一定のパターンがあり、初めて解く場合には戸惑うことがあるかもしれませんが、問題自体はさほどむずかしいものではありません。受験を考えている時には過去に出題された問題や解答例などを参考にして、パターンを掴んでおきたいところです。
数的処理や図形処理などの問題も出るため、理数系の教科が苦手な方は、抵抗を感じることもあるでしょう。
このような問題も、一度パターンを掴んでしまえば、似たような問題が出題された時にすぐに解けるようになります。苦手意識を持たずに、解答パターンを覚えるといった対策を立てておきましょう。
作文試験では社会問題などがテーマになるケースが多く、日頃から時事問題などには関心を持っておきましょう。
難易度が高い試験もある
公務員試験には高卒で受けられる試験も複数ありますが、なかには難易度が高く、合格するのがかなりむずかしいものもあります。
せっかく高卒で公務員を目指すべくがんばって勉強しても、採用されなければ仕方ありません。合格率や難易度、自分の学力などを見ながら、どの公務員になりたいのか冷静に考えて決断することをおすすめします。
「高卒公務員」に関するよくある質問
結論、一定数の人が後悔しているのは事実です。後悔している理由は、「大学進学している友人」や「大卒公務員」と比較してしまうことが一般的には多いようです。進路について後悔したくない人は、自分に合っている仕事が何か考えてみましょう。ジェイックでは、無料の「就職相談」も実施しているので、一人で就職活動が不安な人は相談してみてください。
高卒公務員の初任給は、約15万程度と言われています。大卒と比べると約3万以上も初任給に差があることがわかります。高卒で公務員になる前に「高卒の公務員になる前に知っておくべき5大事実」を参考にして高卒公務員の実情を把握しておきましょう。
公務員・民間企業それぞれに特徴があります。なので、自分がどちらの働き方が合っているのかを考える必要があるでしょう。「公務員と民間企業の違い」でそれぞれの違いについて紹介をしているので一度検討してみましょう。
高卒で公務員になるために、「公務員になりたい理由」を明確にしておくことが必要になります。周りから言われたため、なんとなく公務員が安定していそう、などの理由で就職すると後悔の元になります。ジェイックでは、一人一人に向いてる仕事を紹介するために、自己分析や履歴書・面接対策を行う研修を無料で実施しているので、就職相談を予約するのもいいでしょう。
【まとめ】高卒で公務員になりたい理由を明確にする
高卒で公務員になると、周囲からは「すごい」「よかったね」と喜んでもらえたり、親や先生からも安心してもらえたりするでしょう。しかし、公務員の仕事が不向きでストレスを感じることが多ければ「公務員にならなければよかった」「辞めたいけど、辞めた後をどうしよう」などと考えてしまうリスクがあります。
高卒で公務員になりたいと考えている方は、そもそもなぜ公務員がいいのか、改めて考えてみましょう。「高卒で公務員になることも考えているが、自分が将来どうしたいかわからない」とお悩みの方は、ジェイックのキャリアアドバイザーへお気軽にご相談ください。

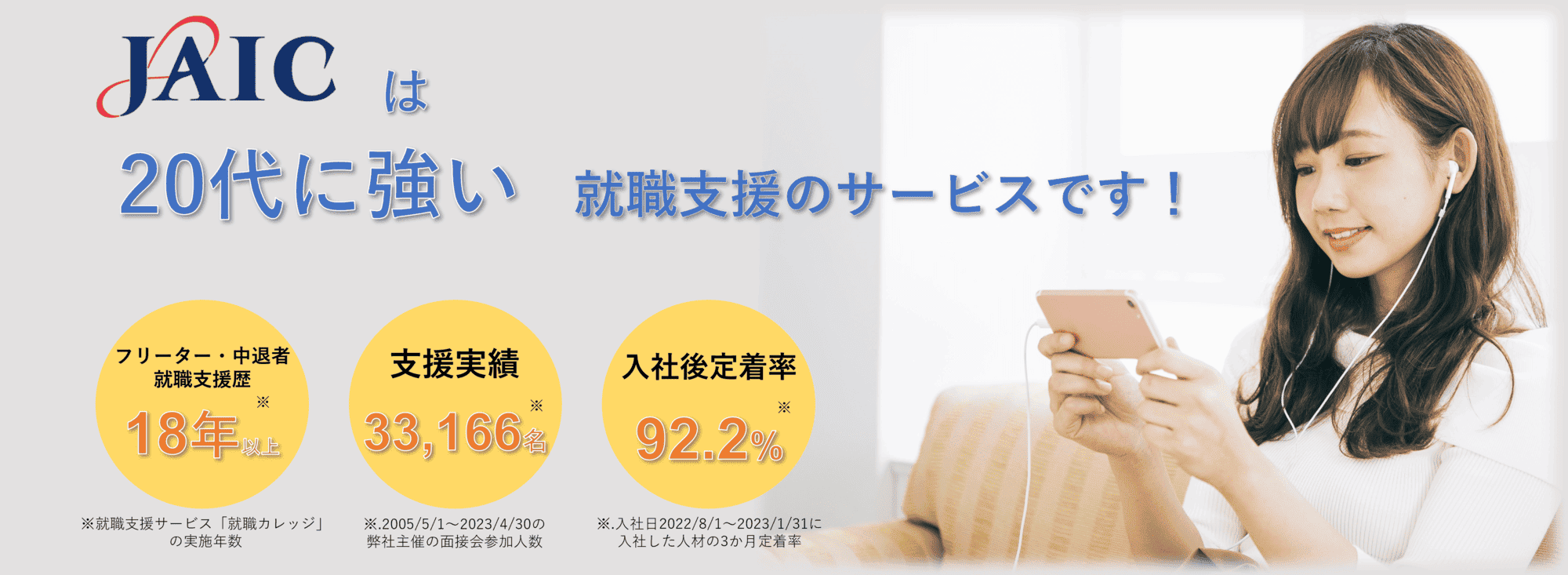
こんな人におすすめ!
- 自分に合った仕事や場所を見つけたい
- ワークライフバランスを重視したい
- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい