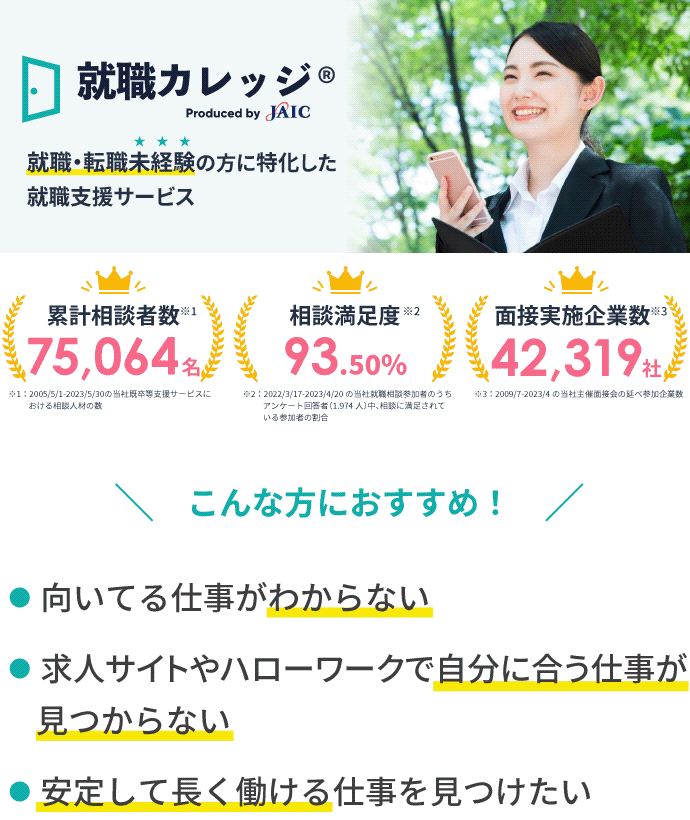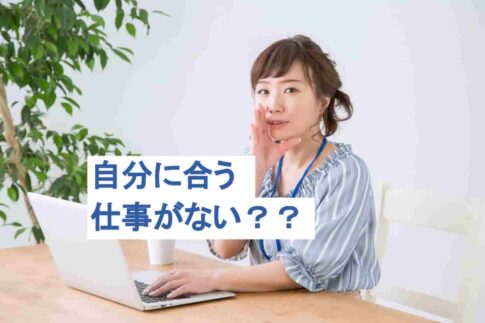飽き性な自分に向いてる仕事なんてあるのだろうか、と思う人もいるかもしれません。
仕事に飽きてしまうとやる気が持てなくなり、仕事が続かなるのではと恐れる人もいるでしょう。
ただ、実際には飽き性である特性を活かした向いてる仕事があることを知れば、特性を生かした仕事に就くことができます。
この記事では飽き性の人に向いてる仕事や、飽きっぽい人の強みや弱みについて解説しています。飽きっぽくてなかなか仕事を続けることができなくて悩んでいる方は、この記事を参考にして、今後の就職活動に役立ててください。
- 飽き性に向いてる仕事は、営業職、企画、クリエイターなど
- 飽き性の人の強みには、変化に対応する柔軟さ、知識やスキル習得力、集中力などがある
- 飽き性を活かして社会で活躍するためには、自己分析、企業研究、将来性がある仕事を選びが大切!
この記事の目次
そもそも飽き性とは
飽き性とは、新しい刺激や変化を好む性格のことを指します。
このタイプの人は、長期間同じことに注力するのが難しく、常に新しい活動や環境を求める傾向にあります。
飽き性の人は、ルーティンや単調な作業に対して早く飽きを感じることが多いですが、一方で新しいアイデアや刺激に対する好奇心は非常に高く、創造性や柔軟性を活かした分野で大きな強みを発揮することができます。
そのため、常に変化を求め、新しい環境やチャレンジに対して積極的に取り組むことができるのです。
この性格は、特に新しいプロジェクトや異なるタスクに取り組むことで、モチベーションを維持しやすく、飽きることなく仕事を続けることができます。
飽き性な人に向いてる仕事20選

飽き性な人に向いているおすすめな仕事20選をご紹介します。
なぜ向いているのかについて、詳細を以下で解説していきます。
営業職 [飽き性に向いてる仕事 1/20]
営業職は、法人や個人のお客様に対して自社の製品・サービスを提案し、契約してもらう仕事です。仕事では常にお客様とのコミュニケーションをするため、単純に飽きにくいのが特徴です。
また、仕事上出張や訪問など外に出歩く機会も多く、毎日違うお店でランチをすることに生きがいを感じているような営業職の人もいます。
それだけでなく、自身で新たな取引先を開拓することもできるため、会話をすることが苦手でない人であれば、毎日新鮮な気持ちで仕事に向き合えるはずです。
営業職は求人数も多く、未経験から挑戦できる求人も目立ちます。加えて今までの経歴や学歴も不問という募集が多いので、飽きにくい仕事でしっかり稼いでいきたいという人に特におすすめです。
| 向いてるポイント | ・多くの顧客と出会いコミュニケーションできる ・出張、訪問と外に出向く機会が多い |
| 平均年収 | 439万円 |
企画職[飽き性に向いてる仕事 2/20]
企画職は、会社の課題を見つけてそれを解決する企画を検討〜実行することにより、事業を成長させる仕事です。細かく分けると、営業企画や商品企画、プロモーション企画など幅広い職種に分かれます。
基本的に企画職はどのような職種であっても、求められる素養やスキルは共通していますので、会社によっては企画職内で横スライドのように異動する仕組みが設けられています。
飽きっぽい人であっても、異動を繰り返せば新たな施策検討と向き合うことができるため、仕事に飽きを感じにくいでしょう。
| 向いてるポイント | ・数ある選択肢から施策を検討できる ・社内異動がしやすく様々な企画業務ができる |
| 平均年収 | 527万円 |
クリエイター[飽き性に向いてる仕事 3/20]
クリエイターは、顧客の要望に応じた具体的な制作物を提供する専門職で、デザイン、イラスト、プログラミング、映像制作、ゲーム開発、VRなど幅広い分野にわたります。
プロジェクトごとに異なるテーマや要件に取り組むことが多く、これにより常に新鮮な刺激を受け、モチベーションを維持しやすいのが特徴です。
また、クリエイティブな分野は常に進化し、新しい技術が伴うことで、飽き性の人々にとっては刺激的であり続けることができます。
さらに、クリエイターは独立して働く機会が多く、自分のスキルやアイデアを活かしてキャリアを築くことができます。
| 向いてるポイント | ・多様なテーマや要件に対応する ・新しい技術を学ぶ機会が多い |
| 平均年収 | 479万円 |
戦略コンサルタント[飽き性に向いてる仕事 4/20]
戦略コンサルタントは、いわゆる「コンサル」の花形的な仕事です。事業や経営に対して課題を感じている法人をクライアントとして担当に付き、あらゆる側面から本質的な課題を特定し、その課題の解決施策まで提言するのが業務となります。
求められるスキルは仮説思考やデータ分析、施策構想力など多岐に渡って高いものが求められますが、その反面課題を解決した時のインパクトが大きく、達成感も感じられるので飽きることはないでしょう。
平均年収が高いのも特徴で、会社によっては年収1,000万円以上を稼げるケースも少なくありません。考えることが好きな人におすすめできる仕事です。
| 向いてるポイント | ・頭をフル回転して働ける ・プロジェクトの達成感がある |
| 平均年収 | 675万円 |
ITエンジニア全般[飽き性に向いてる仕事 5/20]
ITエンジニアは、プログラミング言語を用いてシステムの開発や運用保守を行う仕事です。システムの設計や要件定義を担うシステムエンジニアを始め、要件書に沿ってプログラミングを行うプログラマなど、様々なエンジニアの職種があります。
様々なものがIT化している現代において、ITエンジニアの需要は非常に高まっています。未経験からでも就職できる求人は多くありますので、スキルを身につけたい人にはぴったりです。
プログラミングやシステム開発の手法も日々進化を遂げているため、同じように働き続けるようなことはありません。
加えてリモートワークも活発に行われている仕事なので、スキルを身につけつつ様々な場所で働くというのも飽きっぽい人には嬉しいポイントでしょう。
| 向いてるポイント | ・成長実感を強く感じられる ・技術そのものが日々進化している |
| 平均年収 | 442万円 |
webライター[飽き性に向いてる仕事 6/20]
webライターは、web上に掲載される記事の企画構成や執筆を行う仕事です。ネット記事は様々な種類がありますが、正社員として働く場合は取材ありきで記事執筆を行うケースが多いです。
そのため、取材の度に色々な場所へ行けますし、今まで会ったことのないような人と会話ができるといった新鮮さが特徴です。
加えて、パソコン一台さえあればどこででも働けますので、リモートワークやワーケーションがしやすいという点もあります。
文字さえ適切に書ければ未経験からでも挑戦できる仕事です。また、やる気がある人であれば、副業から始めてみて向き不向きを確かめてみるのもおすすめです。
| 向いてるポイント | ・取材で色々な場所にいける ・毎回違う記事の執筆ができる |
| 平均年収 | 358万円 |
上流工程の機械エンジニア[飽き性に向いてる仕事 7/20]
上流工程の機械エンジニアは、機械製品を製造する上で設計や大量生産計画を策定する仕事です。製品を作る上で上流工程を担うため、幅広い知識が求められますが、自分が設計した製品をユーザーに使ってもらえるといったやりがいを感じられます。
どんな機械製品であっても、新しいものを作る際は設計書を作る必要があります。簡単に設計書を作成すると言っても、今回製造する製品のコンセプトやターゲット、絶対に守らなければいけない要件から製造コストまで、幅広い観点で検討する必要があります。
考えることが常に変わるため、仕事そのものに飽きを感じることは少ないでしょう。携わる製品の大きさや開発頻度によっても仕事の進め方が変わりますので、求人に応募する際は製造する機械をしっかりチェックしてください。
| 向いてるポイント | ・製品を作り出すといった達成感 ・アイデアや構想を形にして販売できる |
| 平均年収 | 521万円 |
研究開発職[飽き性に向いてる仕事 8/20]
研究開発職は、食品メーカーや医薬品メーカーに勤め、新たな製品のきっかけとなるような実験や研究をする仕事です。
仕事の大半は研究室にこもって研究を行うため、高い理系的な知識が求められます。
研究対象はプロジェクトによって異なりますが、基本的には成果が出るまでトライアンドエラーをすることになります。研究に失敗したら、失敗した原因を考えて改善するといったPDCAサイクルの繰り返しを行いますので、常に新しいことに向き合うことが可能です。
また、研究成果として今まで世に出ていないものを製品に組み入れることも可能なため、強いやりがいも感じられるでしょう。
| 飽きっぽい人に向いてるポイント | ・今までにないものを見つけるのが仕事 ・性質上同じ仕事というものが存在しない |
| 平均年収 | 467万円 |
建築設計士[飽き性に向いてる仕事 9/20]
建築設計士は、家や大型施設などを建築するに当たって、設計図を作る仕事です。最近では設計図をソフトウェアで作ることがほとんどですので、意外とデスクワークが多いのが特徴です。
ただ、デスクワークだけでなく実際に建築する現場の土地や環境を視察することも少なくないため、案件によって様々な場所に行けるといった特徴があります。
加えて、同じ形・環境の土地は一つも存在しませんので、一つ一つの設計で新鮮さを感じられ、飽きることも少ないと考えられます。
建築業界は人材不足が嘆かれている業界でもありますので、未経験からでも挑戦できる求人が多く募集されています。新たなキャリアを歩み、手に職をつけられるのも建築設計士のポイントです。
| 向いてるポイント | ・自分の設計が大きな建物になる達成感 ・実地調査なども頻繁に行う |
| 平均年収 | 456万円 |
トラック運転手[飽き性に向いてる仕事 10/20]
トラック運転手は、トラックを運転して貨物を運ぶ仕事です。どれくらいの距離を運搬するかは会社によって異なりますが、総じて事故を起こさない集中力とドライビングスキルが求められます。
一見すると荷物の運搬という単純作業をする仕事と思われがちですが、職場をしっかり吟味すれば毎日様々な場所に向かえるドライバーにもなれるため、日本各地を転々とすることが可能です。
また、仕事中は常に車内に一人きりのため、運転をしながらという制限はあるものの自由な時間を過ごすことが可能です。
ラジオを聞くだけでなく、好きな音楽を流したり一人で歌を口ずさんでみたりなど、飽きのこない仕事時間を過ごせるでしょう。
| 向いてるポイント | ・仕事で色々な場所にいける ・自分一人の車内で楽しみを見出せる |
| 平均年収 | 400万円 |
ウエディングプランナー[飽き性に向いてる仕事 11/20]
ウエディングプランナーは、結婚式を挙げたいと思っているカップルを担当し、挙式の企画から実施までをトータルサポートする仕事です。
結婚式という人生に一度しかない舞台の企画や準備を行うため責任感が重要となりますが、その分やりがいを感じられるのがポイントです。
結婚式はカップル一組一組で様々な思いがありますので、臨機応変な対応も求められます。基本的に全く同じ結婚式を担当することはないため、飽きにくい仕事でもあります。
非日常を常に味わうことができる特別な仕事であることからも、飽きっぽい人が飽きずに向き合える仕事と言えるでしょう。
| 向いてるポイント | ・人生に関わる仕事なので達成感がある ・仕事で非日常感を味わえる |
| 平均年収 | 310万円 |
マーケター[飽き性に向いてる仕事 12/20]
マーケターは、企業の製品やサービスの販売促進を担当する専門職です。
市場調査を行い、顧客のニーズや市場トレンドを把握してターゲット顧客を分析し、その結果を基に効果的なマーケティング戦略を立案・実行します。
具体的な業務内容には、広告キャンペーンの企画・運営、デジタルマーケティング(SNS、メール、SEO/SEMなど)の活用、ブランドの認知度向上やイメージ管理などがあります。
したがって、マーケターはデータ分析やクリエイティブなアイデアの発信、プロジェクト管理など多岐にわたるスキルを駆使して企業の成功に貢献する仕事といえるでしょう。
| 平均年収 | 630万円 |
| 必要なスキル | ・データ分析スキル ・デジタルマーケティングの知識 ・クリエイティブスキル ・プロジェクトマネジメントスキル |
| 関連する資格 | ・Google Analytics個人認定資格(GAIQ) ・Google Ads認定資格 ・社会調査士 |
| 向いてる人 | ・分析的かつ論理的な思考ができる人 ・トレンドや消費者動向に敏感な人 ・コミュニケーション能力が高く、協調性のある人 ・クリエイティブなアイデアを出せる人 |
| 仕事に就くためには | ・表計算や統計処理のソフトウェアが使いこなせる ・調査対象者からの信頼を得るためのヒアリング能力が重要 |
デザイナー[飽き性に向いてる仕事 13/20]
デザイナーは、広告、ウェブサイト、製品、パッケージなどのビジュアルコミュニケーションを担当する仕事です。
クライアントのニーズに基づき、視覚的に魅力的で効果的なデザインを作成します。
創造力と技術力を駆使し、色彩、レイアウト、タイポグラフィ、画像を組み合わせてブランドのメッセージを伝えます。
また、市場のトレンドやターゲットオーディエンスの嗜好を反映し、多様なデザインツールを使用してクライアントの期待を超える成果を提供し、ブランド価値を向上させる役割を担います。
| 平均年収 | 480万円 |
| 必要なスキル | ・グラフィックデザインソフトウェア (Adobe Photoshop、Illustratorなど)の操作スキル ・色彩理論やタイポグラフィの知識 ・創造力とアイデアを具体化する能力 ・プロジェクト管理スキル |
| 関連する資格 | ・グラフィックデザイン検定 (日本グラフィックデザイナー協会) ・色彩検定 |
| 向いてる人 | ・創造的で美的センスがある人 ・細部にまで注意を払うことができる人 ・クライアントの要望を理解できる人 ・トレンドに敏感な人 |
| 仕事に就くためには | ・デザイン関連の専門学校や大学への通学 ・自分のポートフォリオを作成しておく ・インターンシップや実習で実務経験を積む |
広報[飽き性に向いてる仕事 14/20]
広報担当者は、企業や団体のイメージやブランドを良くするための仕事です。
主な仕事には、メディア(新聞、テレビ、ラジオなど)との関係を管理、プレスリリース(公式発表文)を作成、記者会見を開く、SNSで情報を発信するなどがあります。
広報担当者は、組織のメッセージを効果的に伝えるための戦略を考え実行します。
また、トラブルが起きたときの対応や、社内外の関係者とのコミュニケーションも重要な仕事です。優れたコミュニケーション能力と戦略的な考え方が求められる役割です。
| 平均年収 | 490万円 |
| 必要なスキル | ・ライティング能力 ・コミュニケーション能力 ・メディアリレーションスキル ・プロジェクト管理スキル ・危機管理能力 |
| 関連する資格 | ・広告・宣伝検定 ・ビジネス実務法務検定 |
| 向いてる人 | ・人と接するのが好きな人 ・文章を書くのが得意な人 ・協調性があり、チームで働くのが得意な人 ・新しい情報を集めるのが得意な人 ・冷静に対応し、問題解決能力がある人 |
| 仕事に就くためには | ・広報関連の専門学校や大学への通学 ・コミュニケーションスキルを高めるための訓練 ・就職エージェントの利用 |
CADオペレーター[飽き性に向いてる仕事 15/20]
CADオペレーターは、コンピュータ支援設計(CAD)ソフトを使用して、建築、機械、電気、土木などの分野で設計図面を作成する専門職です。
設計者やエンジニアの指示に基づき、詳細で正確な図面を作成・修正し、デザインの実現をサポートします。
CADオペレーターは、細部にわたる正確さと効率的な作業が求められます。
また、技術図面の読み書き能力や業界の最新トレンドに関する知識も重要です。
よって、チームと協力しながらプロジェクトを進めるためのコミュニケーション能力も不可欠です。
| 平均年収 | 449万円 |
| 必要なスキル | ・CADソフトウェアの操作スキル (AutoCAD、SolidWorksなど) ・図面の読み書き能力 ・技術的な知識(建築、機械、電気などの分野に応じて) ・ディテールに対する注意力 ・コミュニケーション能力 |
| 関連する資格 | ・CAD利用技術者試験 ・建築CAD検定試験 ・機械設計技術者試験 |
| 向いてる人 | ・細かい作業が得意で、集中力が高い人 ・技術的な知識を持ち、正確な図面を描くことができる人 ・設計者の意図を理解しやすい人 ・コンピュータを使った作業が好きな人 |
| 仕事に就くためには | ・基本的な設計図の読み書き方法を習得する ・CADソフトの操作方法を学ぶ ・設計会社への直接応募 |
CADオペレーターの仕事内容について以下の記事で詳しく解説しています。
ホールスタッフ(レストラン)[飽き性に向いてる仕事 16/20]
ホールスタッフは、レストランでお客様にサービスを提供する仕事です。
主な業務には、席への案内、注文の受付、料理や飲み物の提供、テーブルの片付け、お会計の処理などがあります。
また、お客様が快適に食事を楽しめるよう、迅速で丁寧なサービスを提供することが求められます。
さらに、ホールスタッフには明るく親切な対応やコミュニケーション能力、チームワークが必要です。
業務が忙しい時間帯でも落ち着いて対応できるストレス耐性や、細やかな気配りも必要でしょう。
| 平均年収 | 330万円 |
| 必要なスキル | ・接客マナー ・チームワークスキル ・迅速で正確な対応能力 |
| 関連する資格 | ・サービス接遇検定 ・ホスピタリティ関連資格 |
| 向いてる人 | ・人と接するのが好きで、明るい性格の人 ・気配りができる人 ・チームで働くのが得意な人 ・迅速かつ正確に作業ができる人 ・忍耐力と体力がある人 |
| 仕事に就くためには | ・飲食業界の求人サイトの利用 ・飲食店でのアルバイト経験を積む ・一般の求人応募 |
プログラマー[飽き性に向いてる仕事 17/20]
プログラマーは、コンピュータソフトウェアやアプリケーションを設計・開発・テスト・保守する専門職です。
主な業務には、プログラムコードの記述、デバッグ、機能の実装、システムの最適化などがあります。
プログラマーは、さまざまなプログラミング言語(例:Python、Java、C++)を使い、ユーザーの要求や仕様に基づいてソフトウェアを作り上げます。
また、他の開発者やデザイナー、プロジェクトマネージャーと協力して作業を進めるため、コミュニケーション能力とチームワークも不可欠です。
| 平均年収 | 550万円 |
| 必要なスキル | ・プログラミング言語の知識 (例:Java、Python、C++、JavaScriptなど) ・データベース管理(SQLなど) ・ソフトウェア開発の基本知識 ・問題解決能力 ・論理的思考能力 |
| 関連する資格 | ・基本情報技術者試験 ・応用情報技術者試験 |
| 向いてる人 | ・論理的で分析力がある人 ・問題解決に興味があり、挑戦する意欲がある人 ・最新の技術やトレンドに興味がある人 ・コミュニケーション能力があり、チームで協力できる人 ・自主的に学び続ける意欲がある人 |
| 仕事に就くためには | ・専門学校でプログラミングを学ぶ ・基本情報処理技術者などの資格があると有利 ・SE専門の就職エージェントの利用 |
キャリアカウンセラー[飽き性に向いてる仕事 18/20]
キャリアカウンセラーは、個人の職業選択やキャリア形成を支援する専門職です。
求職者や学生に対し、自己分析や職業適性診断、履歴書・職務経歴書の作成指導、面接対策、キャリアプランの相談を行います。
労働市場や業界のトレンドに関する最新情報を提供し、的確なアドバイスを通じてクライアントの目標達成をサポートします。
継続的な支援や高い倫理観が求められ、信頼関係を築くことが重要です。
したがって、キャリアカウンセラーには高いコミュニケーション能力や共感力が必要とされます。
| 平均年収 | 579万円 |
| 必要なスキル | ・コーチングスキル ・カウンセリング技術 ・問題解決能力 ・経済や労働市場に関する知識 |
| 関連する資格 | ・キャリアコンサルタント資格(国家資格) ・産業カウンセラー資格 ・キャリアカウンセリング技能検定 ・メンタルヘルス・マネジメント検定 |
| 向いてる人 | ・人の話をじっくりと聞ける人 ・共感力が高く、他者の気持ちを理解できる人 ・他者の成長をサポートする意欲がある人 ・労働市場や経済の動向に興味がある人 |
| 仕事に就くためには | ・コーチングやカウンセリングの技術を習得する ・資格取得のための勉強と試験対策を行う ・キャリアカウンセラーを求める企業や団体に直接応募 |
カメラマン[飽き性に向いてる仕事 19/20]
カメラマンは、写真やビデオを撮影する専門職です。
主な業務には、ポートレート、風景、イベント、商品、ファッションなど、さまざまなテーマの撮影が含まれます。
カメラマンは、被写体の魅力を最大限に引き出すために、構図や照明、カメラ設定などを工夫します。
また、撮影後には画像やビデオの編集作業も行い、最終的な作品を完成させます。創造力と技術力が求められ、クライアントのニーズに応じた柔軟な対応が必要です。
よって、コミュニケーション能力やプロジェクト管理能力も重要でしょう。
| 平均年収 | 466万円 |
| 必要なスキル | ・撮影技術(カメラ操作、構図、照明など) ・画像編集ソフトの操作スキル(Adobe Photoshop、など) ・機材の知識と管理能力 |
| 関連する資格 | ・フォトマスター検定 ・Photoshopクリエイター能力認定試験 ・日本写真芸術専門学校の認定資格 |
| 向いてる人 | ・写真撮影が好きで、情熱を持っている人 ・創造力が高く、美的センスがある人 ・新しい技術を学ぶ意欲がある人 ・長時間の撮影に耐えられる人 |
| 仕事に就くためには | ・フォトスタジオや広告代理店に応募 ・テレビ局や局の仕事を請け負う外部プロダクションに応募 ・フリーランスとして独立 |
スポーツインストラクター[飽き性に向いてる仕事 20/20]
スポーツインストラクターは、スポーツやフィットネス活動の指導を行う専門職です。
個人やグループに対して運動プログラムを作成し、技術指導やトレーニング方法の提案を行います。
クライアントの体力や目標に合わせたエクササイズ計画を立て、適切なフォームやテクニックを教えます。
また、進捗を評価し、必要に応じてプログラムを調整します。
体力とコミュニケーション能力が重要で、クライアントのモチベーションを高めることが求められるでしょう。
| 平均年収 | 383万円 |
| 必要なスキル | ・専門的なスポーツやフィットネスの知識 ・トレーニングプログラムの作成能力 ・コーチングスキル ・クライアントのモチベーションを高める能力 |
| 関連する資格 | ・健康運動指導士 ・健康運動実践指導者 ・CPR(心肺蘇生法)等のライセンス |
| 向いてる人 | ・スポーツやフィットネスが好きで、情熱を持っている人 ・人を指導するのが好きで、協力的な態度がある人 ・体力があり、元気を与えられる人 |
| 仕事に就くためには | ・CPR(心肺蘇生法)などのライセンスを取得する ・フィットネスクラブやスポーツジムに応募 ・フリーランスのパーソナルトレーナーとして活動 |
飽き性の3つの強み
飽き性の人は、大きく以下3つの強みがあります。
- 変化に対応できる
- 最新の知識を得て、スキルアップしている
- 物事に集中して取り組める
これらの強みは、先ほど紹介した3つの仕事(営業・企画・クリエイター)にも活かせる点が多いです。
強み1. 常に変化をおこす
飽き性の人は、どんどん新しいことに挑戦して、豊富な経験を持っています。「飽き性=同じ状態でいるのが好きではない」といえるので、柔軟に変化できる点が強みです。
特に企画やクリエイターにおいて、求められるものや流行は常に変わっているので、変化についていけることが重要です。やはり、飽き性の人には向いている仕事といえるでしょう。
強み2. 最新の知識の取得やスキルアップをする
飽き性な人は「最新のもの」が好きで、新しい知識やスキルを早く身につけられる傾向があります。あなたはこれまで、以下のような経験はありませんか?
- 好奇心旺盛で、いろんなことに挑戦したくなる
- 趣味が多い
- やりたいことが多くて時間がない
- 転職回数が多い
- よく引っ越す
上記に当てはまる人は、飽き性である可能性が高いですが、同時に「多くの新しいことに挑戦している人」ともいえます。人の脳には元々「恒常性」という、変化を避ける性質が備わっていますが、飽き性の人は、新しいことに挑戦するストレスが少ないのです。先ほど紹介した営業・企画・クリエイターのどれもが、常に最新の情報収集が求められるので、向いていると考えられます。
強み3. 集中して取り組むことができる
飽き性の人はワーキングメモリ能力が高く、集中力のある人が多いです。ワーキングメモリとは「短期記憶を保管する能力」で、集中力はワーキングメモリの量と比例関係にあります。特に営業職では、顧客の話をヒアリングすることが必要なので、集中力が活かせるでしょう。また、集中力のある人は、物事の上達スピードも早いといわれています。
このように、飽き性の人は大きな強みがあるといえるでしょう。
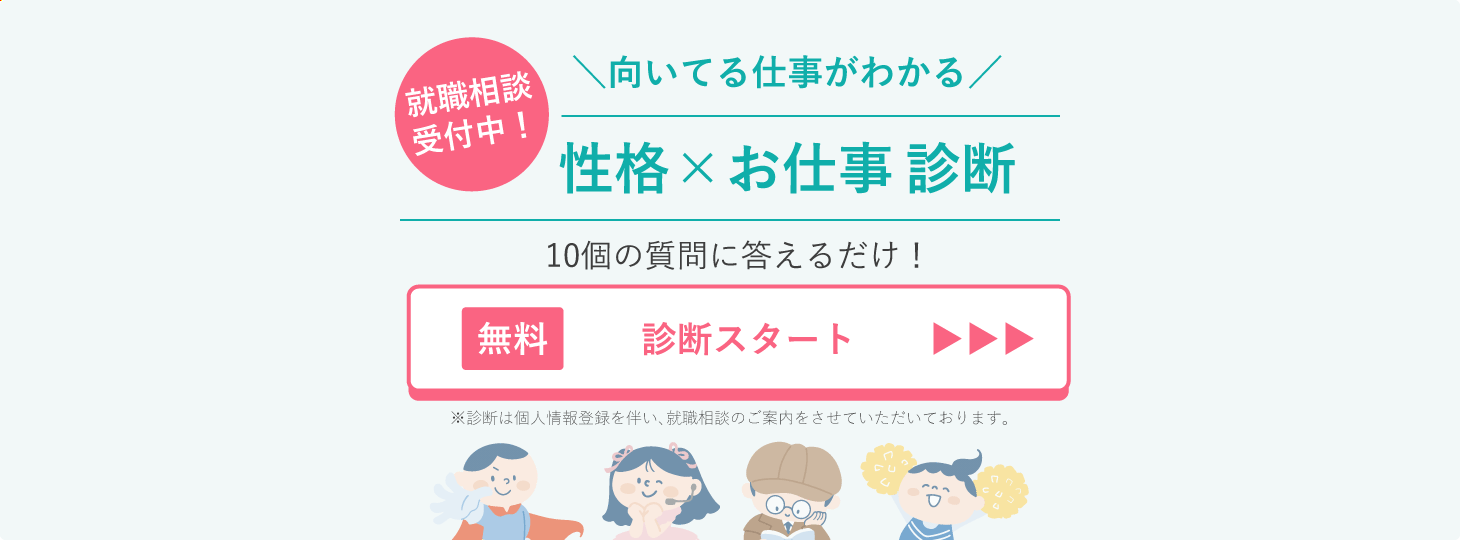

飽き性の3つの弱み
反対に、飽き性の人は、以下3つの弱みを持っています。
- 同じことを続けられない
- 変化が少ない
- 忍耐力がない
それぞれ、詳しく解説していきます。
弱み1. 同じことを続けることができない
同じことを続けられないのは、最もイメージしやすい飽き性の短所でしょう。この短所がマイナスに働くと、物事を継続できずに「中途半端なスキルが複数ある」という状態に陥りがちです。
仕事でいうと、以下のような同じような作業が続く仕事は、飽き性の人には向いていないかもしれません。
- 工場の作業員
- 経理
弱み2. 変化が少ない
意外にも「変化が少ない」飽き性の人もいます。実際「仕事が長続きしない」という人が転職を繰り返し、これといったスキルが身につかないまま歳を重ねる人は多いです。長期的にみると、飽き性の人より1つのことをコツコツ続けていた人の方が、成長していたケースはよくあります。
そのため、まずは飽きが来ないと思える、自分が続けられそうな仕事を見つけましょう。特にルーティン化しやすい、以下の仕事は避けたほうが無難と考えられます。
- 事務職
- 運送ドライバー
- 警備員
弱み3. 忍耐力がない
飽き性な人は、忍耐力がないことも多いです。これがマイナスに働くと、物事を途中で投げ出す「責任感のない人」と思われてしまいます。そのため、研究職のような、長期で成果を出すような仕事は向いていないことが多いでしょう。
また、「自分はなんて忍耐力がない人間なんだ…」と自覚することで、落ち込んでしまう人もいます。では次に、飽き性の弱みを強みに変えていく方法を解説していきます。
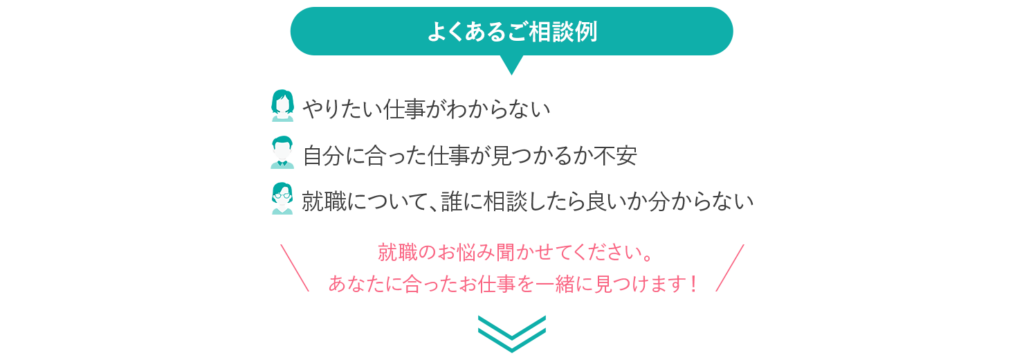

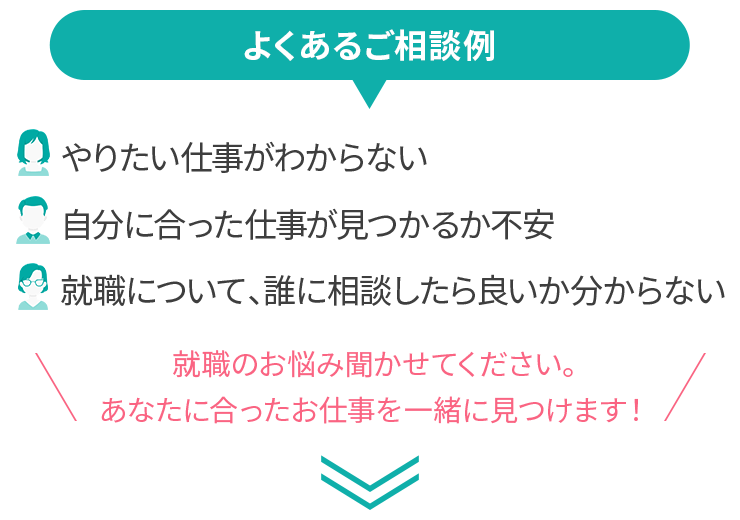
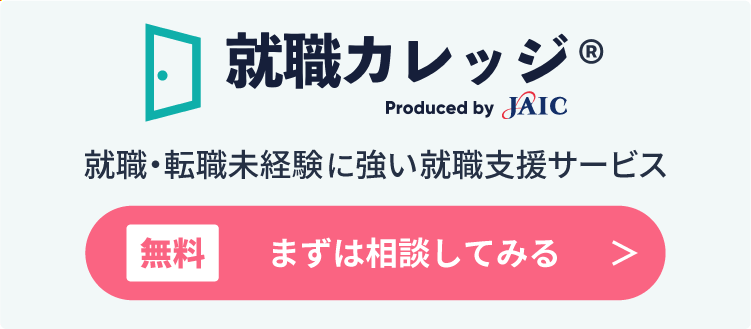
飽きっぽい人が避けるべき仕事や職場の特徴
飽きっぽい人に向いてる仕事の特徴があれば、当然その逆も存在します。
飽きっぽい人が避けるべき仕事や職場の特徴を満たした勤務先に就職してしまうと、入社してすぐに退職してしまうといった短期離職に繋がる恐れがあります。
短期離職は一度やってしまうと2回3回と繰り返しやすく、短期離職を繰り返すとやがて働ける先に大きな制限がかかることも考えられます。
そうならないためにも、次に紹介する仕事や職場の特徴を持つ会社は、なるべく避けることをおすすめします。
1. 毎日同じ作業をする仕事
飽きっぽい性格と一言で言っても様々なタイプの人がいますが、多くの場合は同じことを繰り返すことにストレスを感じるはずです。
仕事においても、毎日同じ作業をするような業務であれば、高い確率で飽きてしまい別の仕事を探すことが考えられます。
仕事は大きく分けて「新しいものを作り出す仕事」「今あるものをより良いものに改善していく仕事」「今あるものを維持し続ける仕事」の3つに分けられますが、この3つ目に該当する仕事は世の中にたくさんあります。
もちろんどの仕事もビジネスを成立させる上で非常に重要なものであることには変わりありませんが、働く人の心情としてはあまり心地いいものではないでしょう。
ただ、「あくまでも仕事はお金を稼ぐためだけの手段であり、同じことだけやってればお金がもらえるというならそっちの方が楽」と考える人であれば、もしかしたら同じ作業をする仕事が向いているかもしれません。
自分が本当に向いてる仕事を見つけたいのであれば、記事の後半で解説する自己分析に取り組んでみることをおすすめします。
2. 求められる仕事のレベルが極端に高い職場
定期的に違う業務に取り組めて、働く場所が自由で合ったとしても飽きっぽい人に向かない場合があります。それは、求められる仕事のレベルが自分にとって極端に高い職場で働くことです。
仕事のアウトプットを高く求められる場合、どれだけ頑張って自分の精一杯の成果物を提出したとしても、高い可能性でダメ出しをくらうことになります。
ダメ出しを受け続けていくと、やがて「自分にはこの仕事は向いてないんだ」「この仕事を長続きさせていても意味がない」などと考えるようになり、人よりも早く退職してしまうことが考えられます。
飽きっぽい人は興味や関心がすぐに別のものに向きやすいという特徴がありますので、仕事で壁に当たる機会が増えれば増えるほど、逃げてしまうように別の職場を探す傾向が見られます。
そのため、今自分の持っているスキルを正しく理解し、自分のスキルを適切に発揮できる職場でないと、ストレスを感じながら働き続けることになるでしょう。
3. デスクワーク全般
ここまでの内容を踏まえると、デスクワーク全般は飽きっぽい人に向いてない仕事と言えます。
同じ机に座り続け、ほぼほぼ同じ業務を毎日行い、決められた時間に退社するという日々は、飽きっぽい人からしたら苦痛に感じるかもしれません。
退社後に打ち込める趣味がある人であればいいかもしれませんが、そういった趣味も続かないような飽きっぽい人であれば、やがて自分は何のために生きているのかとすら考えてしまいます。
デスクワークの働き方を選ぶのであれば、プロジェクトが定期的に変わったり、自分のアイデアを形にできたりする仕事を選択するようにしてください。
飽きっぽい人が就くべきでない仕事3選
飽きっぽい人は、その性格に向いてない仕事に就いてしまうと、自分にとっても会社にとっても悪い影響を与えてしまいます。
特に、次の3つのような仕事に就くと、飽きてしまう可能性が高いと考えられますので、仕事選びの際はできるだけ避けた方がいいかもしれません。
1. 事務職
事務職は会社の事務作業を担う仕事で、その職域によって経理・総務・労務などに細分化されます。
仕事は基本的にパソコンで行い、業務としても日々同じような事務作業を淡々とこなしていくことが主となります。それだけでなく、業務内容もマニュアルが完備されているケースが大半で、仕事を早く覚えてしまうことも少なくありません。
従って、業務に新鮮味を感じにくくなるスピードが早くなり、飽きっぽい人にとっては変わらない業務がストレスに感じることも考えられます。
会社のビジネスにおいて事務職は非常に重要な役割を担っていることは間違いありませんが、飽きっぽい人には向かないでしょう。
事務職の仕事内容について以下の記事で詳しく解説しています。
2. サービス職
サービス職は店舗での販売員やサービス業でサービス提供をする仕事です。細かな仕事は多岐に渡りますが、基本的にはお客様に同じ対応を同じ品質で提供することが求められるため、業務に新鮮味を感じにくいのが特徴です。
また、店舗での接客を行う仕事であれば、毎日変わらない仕事場の風景を目の当たりにすることになるため、働くことそのものに飽きを感じやすいでしょう。
3. 公務員
公務員は地方自治体の役所などで働く仕事です。配属される課によって向き合う仕事は変わりますが、マニュアル通りの業務以外のことは基本できず、定型的な業務がほとんどです。
また、業務上市民の方からのクレームをもらうことが多かったり、年功序列の社会のため上司から叱責を受ける機会が多かったりと、精神的な負担も多く感じやすい仕事となっています。
飽きっぽい人が面接でアピールする時のポイント
飽きっぽい性格は仕事をする上で基本的にネガティブなマイナスイメージを与えてしまいます。そのため、就職活動の面接で飽きっぽさをアピールすることは避けてください。
ここでは、飽きっぽい人が面接でどのように自分をアピールすれば良いのかについて解説します。
1. 飽きっぽいということは長所として言い換える
飽きっぽいということはアピールポイントになり得ませんので、長所として言い換えることを検討してみてください。
具体的には、以下のような形で言い換えて面接官に伝えるのがポイントです。
「私は様々な物事に興味を持てる強みがあります。御社の仕事においても、与えられた業務をすぐに覚えるだけでなく、自ら課題を率先して見つけて問題提起できるような人材に成長していきたいと思っています。」
飽きっぽいという性格を、様々なことに興味を持てるといった強みに言い換えることで、仕事に対して前向きという印象を面接官に与えることができるはずです。
2. 様々なキャリアを積みたいことをアピールする
飽きっぽいことは、裏返せば興味が幅広いといった強みになります。そのことをより具体的に面接官に伝えるためにも、入社後様々な経験・キャリアを積みたいということをアピールしましょう。
その際は、できるだけ具体的にどんな部署で、どんな仕事に取り組んでみたいかをセットで伝えるのがポイントです。
面接準備として、企業ホームページでどのような部署があるのかを調べておくのがおすすめです。
飽き性がやった方が良い行動3選
ここでは、飽き性な人が自分の特性を活かし、社会で活躍できるコツを紹介します。具体的にやったほうが良いことは、以下の3つです。
- 自己分析を行う
- 企業について調べる
- 将来を考えた転職を行う
ポイントは「飽き性をなんとか改善しよう」と思わず「飽き性をどう活かすか」を考えることです。以下、詳しく解説していきます。
1. 自己分析を行う
まずは、過去のできごとを振り返り、自分の傾向を分析してみましょう。基本的には飽き性であっても「これだけは続いている」というものがありませんか?
- 1年以上続いたものは、なぜ続いたのか
- すぐにやめてしまったことは、なぜ続かなかったのか
を考えてみてください。飽き性の人は「どんな要因があると続けられるのか」を理解することで、長続きするコツが見つかります。
- 何時間でも本を読める
- DIYをしていたら、あっという間に1日が終わっている
など、自然と続けられるものは何かを考えてみてください。
また、「すぐに辞めてしまったこと」もリストアップしてみましょう。あなたがすぐ辞めてしまうことの共通点を見つけられれば、次に活かすことができます。
例えば、下記のようなイメージです。
- 高校時代の部活動をすぐ辞めてしまった
- 学生時代のアルバイトをすぐ辞めてしまった
- 以前に勤めていた会社をすぐ辞めてしまった
これらの共通点が「一緒にいた人が苦手だった」であれば、すぐ辞めてしまうのは「人が原因」という仮説が立ちます。そのため、次の転職先を調べるときは「どんな人たちが働いているか」を重点的に調べると良いでしょう。
「自己分析は苦手」という人は、後述する「就職エージェント」を活用することで、きちんと自己分析できるので安心してください。
2. 企業について調べる
自己分析の次は「飽きずに続けられそうか」という視点で、企業分析をしてみましょう。「飽き性」と一言でいっても、人によって続けられるもの・飽きてしまうものは異なります。先ほどの自己分析と合わせて、ストレスなく続けられそうな仕事・企業を探してみてください。
また、向いている仕事を選びと同時に、自分で変化を作れる「自由度」がどのくらいあるのかも調べましょう。飽き性の人にとって自由度の小さい仕事は、退屈に感じることが多いです。
企業の情報は、下記などで調べることができます。
- 企業のホームページ
- 求人情報
- SNS
- 口コミサイト
どうしても調べるのが苦手な人は、後述する「就職エージェント」を活用することで、キャリアアドバイザーが企業情報を提供してくれます。
3. 将来を考えた転職を行う
今の仕事がつまらないと思う人は、将来を考えて転職するのも1つの方法です。飽き性な人は、将来性のある仕事に就くことをおすすめします。「1年後には、今よりレベルアップできている」などのイメージが持てれば、仕事を頑張るモチベーションになりやすいからです。人はゴールが見えていないと頑張れないことが多いですが、特に飽き性な人はモチベーションを切らさないためにも、段階的に成長できる環境に身を置きましょう。
「将来性のある仕事がわからない」「モチベーションを保てる仕事がわからない」という人も、次で紹介する就職エージェントのキャリアカウンセリングを受けてみてください。
まとめ
以上、飽き性で仕事が長く続かない人に向けて、飽きっぽい人に向いている仕事の紹介、強みや弱み、やった方がいいことを解説しました。飽き性の人でも、長く働いてスキルアップすることは可能です。
そのためには自分に合った仕事・企業選びをしていきましょう。ジェイックの就職支援サービスを活用すれば転職活動に必要なスキルがすべて学べるので、よければ検討してみてしてください。
近い性格の人向けの記事はこちら
興味がある方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。