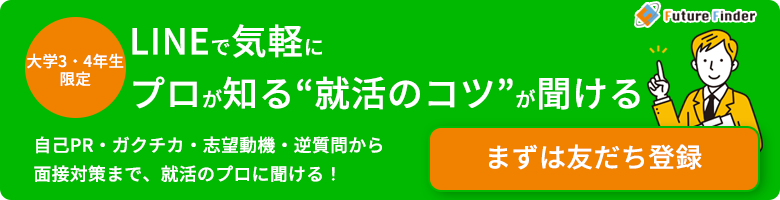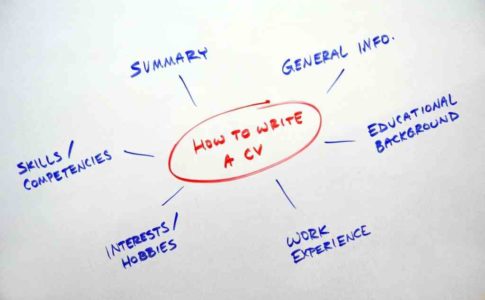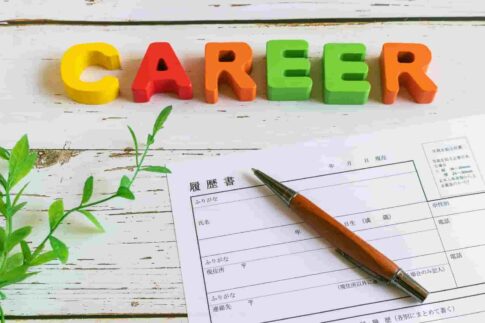※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
エネルギー業界は、石油・ガス・電気などのエネルギーインフラを供給していて、私たちの生活に欠かせない存在といえます。その仕事の公共性の高さや需要の安定性から就活生からの人気が非常に高い業界です。 人気が高い業界だからこそ、業界の動向や求められる人物像の解像度を上げることが必要です。 この記事ではエネルギー業界への就職を考える就活生に向けてエネルギー業界の基礎知識や最新の動向を詳しく解説していきます。
この記事の目次
エネルギー業界とは~石油・ガス・電気の3分野の概要~

エネルギー業界は、現代社会の生活基盤として多くの消費者になくてはならない存在です。業界をカテゴリ別に分けると、石油・ガス・電気の3つであり、これらに関わる業界の総称をエネルギー業界と呼びます。エネルギー業界はそれぞれが扱うエネルギーを安定的に供給することで収益を得ています。
エネルギー業界:石油
経済産業省・資源エネルギー庁が発表した「エネルギー白書2018」によると、2016年の世界のエネルギー消費量(一次エネルギー)の約3分の1が石油となっています。日本国内では一次エネルギーの約4割が石油となっており、石油会社は社会・経済において重要な役割を果たしているのです。一方で「エネルギー白書2018」によると日本国内における一次エネルギーの石油の割合は1970年代をピークに減少しているのです。原因としては人口減少に伴う石油消費量の低下、地球温暖化対策として化石燃料から再生可能エネルギーへの燃料転換などが挙げられます。このように人口減少や燃料転換の流れによって石油製品の需要は減少しており、その傾向は続いていくとみられています。
石油は後述する他の二つとは異なり、加工が可能な資源となっているため石油会社では石油を調達して加工するといった事業が必要不可欠です。それらの一連の流れを川の流れに例えて開発・生産を上流、輸送までを中流、国内での精製と製品販売までを下流と呼びます。具体的には原油の採掘と調達を行う資源開発、外交輸送を行う原油調達、燃料用石油や石油化学製品の製造などをする石油精製、内航輸送や陸上輸送を行う陸・海上物流、石油販売の5つの過程に分かれているのです。5つの過程の中でも日本企業は石油精製技術の高さに定評があり、需要が伸びている新興国に対しての石油精製ビジネスを展開しています。また国内の遊休資産を利用して発電ビジネスを行う取り組みなどもあります。
エネルギー業界:ガス
ガス業界は液化天然ガス(LNG)や液化石油ガス(LPG)などの原料調達を行い管理することで、家庭や施設に対してガスを届けるサービスを行っています。これによって収益を得ており構造としては各地域のガス会社が管轄地域にガスを供給する都市ガスと、導管の通っていない地域にガスを供給するLPの2系統に分かれます。都市ガスは液化天然ガスが主原料で空気より軽い性質があるため、ガス探知器も高い場所にあるのが特徴です。また都市ガスは、地面の下に通された導管を通じてそれぞれ担当の地域にガスを供給しているので、導管のインフラ整備も必要です。東京ガス・大阪ガス・東邦ガスの3社は多数のLNG基地と大規模な導管網を持っており周辺のガス事業者への卸売りによってでも稼いでいます。
LPガスは液化石油ガスが主原料で、都市ガスよりも火力が高いのが特徴です。LPガス事業については原油や精油精製過程で算出される液化石油ガスを輸入する元売業、卸売業、小売業に分かれておりそれぞれが組み合わさって収益を出しています。
ガス事業を行うためには海外での原料調達、ガス生産、国内のガス供給網の建設・維持など様々な分野が必要です。具体的には原料調達、生産事業、供給事業、営業事業、技術開発、海外事業など幅広い分野が用意されており、これにより効率的な経営をしています。
エネルギー業界:電気
電気会社は基本的に発電所を保有し、そこで出力した電気を必要な人々に送り届けるサービスを展開しています。電気は基本的に備蓄ができないエネルギーなので30分単位で需要を予測してその予測量によって発電・送電しています。このように電気会社は電力を作ってそれを需要者に届け、販売することで収益を出しており、発電までを上流、発電から需要者への送電までを中流、小売りを下流と川の流れに例えて呼ぶことが多いです。発電事業・送電事業・小売り事業を総合して「電気事業」と呼び、コスト構造も、上流・中流・下流のプロセスごとにかかるものだという認識で問題ありません。
電気事業は発電・送電・小売という3つの部門に大きく分けられ、部門ごとに業務内容も異なるため様々な職種が存在します。特に電気事業の中でも発電・送電事業では発電所や通信設備を管理するためのエンジニア職が活躍する場が多く設けられています。加えて海外での発電所の建設・運営事業や海外でIPP(発電した電気を電力会社に卸す事業)など海外展開が主流になっているため、海外で働くチャンスも多いでしょう。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
エネルギー業界のビジネスモデルについて
私たちに身近なエネルギー業界も、多くの就活生はどんなビジネスモデルになっているのか理解できている人は多くないと思います。ここでは、エネルギー業界のビジネスモデルについて解説します。
石油業界
石油業界のビジネスモデルは、原油の生産から輸送、そして販売までと一気貫通とした範囲を担っています。石油の需要は世界中で高く、交通機関や産業のエネルギー源として広く使用されているため、需要に応じて、石油企業は探査、採掘、精製、そして流通までの全方面で収益を上げています。そのため、需要が常にある高い付加価値が、このビジネスモデルの持続性を支えています。
石油企業の代表的なビジネスモデルとして、石油メジャー(世界中の大手石油企業)があります。これらの大手企業は、世界中で多くの事業を展開し、莫大な収益を確立しています。例えば、シェルやエクソンモービルは、探鉱、開発、販売までの全ての段階において業界の中でも大きな権威性を有しています。
ガス業界
ガス業界のビジネスモデルは大きく分けて2種類があります。それぞれ解説していきます。
LPガス
LPガスのビジネスモデルは、大きく分けて元売業、卸売業、小売業の3つがあります。
元売業は、LPガスを生産または仕入れ、大規模な量を卸売業者や小売業者に供給する事業のことです。
卸売業は、元売業者からLPガスを仕入れ、小売業者に大量で供給する業態です。効率的な物流や価格交渉を通じて、小売業者に安定的な供給を提供しているものになっています。
小売業は、一般の消費者や事業所にLPガスを提供する最終段階の販売業者です。個々の消費者の需要に合わせて小口でLPガスを提供し、安全性やサービス品質に焦点を当てて
都市ガス
都市ガスのビジネスモデルは、地域ごとに存在するガス会社が特定の管轄エリアに対してガスを供給する仕組みです。代表的な都市ガス事業者として「大阪ガス・東京ガス・東邦ガス」などがあり、これらの企業が市場の約7割を占めています。
これらの大手都市ガス事業者は、各地域に大きな導管網を保有しており、ガスを効率的に供給するために地域のガス事業者に対して配給を行っています。
電気業界
電気エネルギー業界のビジネスモデルは、発電、送電、小売といったプロセスを組み合わせた複雑な構造を持っています。それぞれの業態について説明していきます。
発電
電気エネルギーの最初の段階である発電は、さまざまな方法で行われます。これには化石燃料や再生可能エネルギー源を利用した発電所が含まれます。発電事業者はエネルギーを生産し、発電所から送られてくる電気を所有または購入します。
送電
送電は、発電所で生産された電気を高圧の送電網を通じて遠くの地域に輸送する業態です。送電事業者は、電力網の構築・維持・管理を行い、電気を安定して供給しています。
小売
小売事業者は、最終的な消費者に電気を供給します。彼らは電気料金の設定や請求、エネルギーサービスの提供を行います。また、一部の小売事業者は再生可能エネルギーの契約やエネルギー効率向上の提案など、顧客(消費者)に対してに付加価値を提供することが求められています。
エネルギー業界の最新トピック&動向

公共性が高く安定している半面変化に乏しいと思われがちなエネルギー業界ですが、実はそんなことは全くありません。
石油業界の最新トピック
石油業界は人口減少や輸送機器の燃料性能向上などもあり石油の販売量が減少、中小企業などは廃業に追い込まれており需要は長期的に減少傾向にあります。石油会社も石油の需要減を見越して、太陽光発電やバイオマスなど再生可能エネルギーを利用した事業を進めています。また、電気業界へ参入する石油会社もあり、事業を多角化し総合エネルギー企業として生き残る道を模索しているようです。
ガス業界の最新トピック
ガス業界も電力と同様に2017年4月からガス小売全面自由化が進み、各社の差別化が進んでいます。業界全体としては福島原発事故を機に火力発電の需要が高まり、合わせてガス需要も高まったので業界としては好調です。
電気業界の最新トピック
かつて電気業界は公益事業として特定の企業が地域の配電権利を独占し、利益を得る地域独占型を取っていました。しかし2016年4月の電力自由化を受けて様々な会社が新電力として参入し、競争が激化しました。また温室効果ガス排出削減の流れもあり、再生可能エネルギーの活用が増えていますが、自然状況に左右されたりコストが高いことから収益が期待できず電力会社にとっては収益を出しづらい状況です。
電力自由化に伴い電気業界への新規参入企業が増えると、消費者の選択肢が増えます。そのため電力会社には消費者に選んで貰うために料金の値下げをする、再生可能エネルギーに特化するなどの差別化を図る必要が出てきました。各社がより差別化をしようとして同時に業界再編が行われる可能性もあるのです。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
エネルギー業界の主な職種

エネルギー業界の主な職種を紹介します。
エネルギー業界の職種:営業
営業に対して、自社の商品やサービスを売り込む仕事というイメージを持っている方も多いかもしれません。もちろん「売る」という行為は営業に含まれますが、営業行為の1つであり本質ではありません。営業とはお客様のニーズを理解し、そのニーズを満たす商品やサービスを提供した上で正当な対価をいただく仕事となります。
エネルギー業界の営業職は一般家庭や企業に対して電力やガス、石油などエネルギーに関わる様々な商品を提案・営業するのが仕事です。エネルギーは各家庭と契約しなければ、供給できません。更にエネルギー業界の自由化が進んでいる中で競争も激しくなっているため、個人向けの営業は欠かすことができない業務のうちの一つです。
また、事業を行う上でエネルギーが欠かせないのは企業とて同じことなので、法人向けの営業も行いながら工業用や産業用のエネルギーを届けています。他にも契約手続きや問い合わせの対応など使用に関するアドバイスも積極的に行います。こうした顧客へのサポートも営業の仕事なので、顧客一人一人と向き合うことができる職種です。
エネルギー業界の職種:技術開発
エネルギー業界の技術開発は、世界各地の地下深くにある天然ガスや石油を開発しながら原料を調達するのが仕事です。資源を保有する国や所有者との交渉を経て探鉱活動の権利を取得して開発と研究を行います。供給を行うためのエネルギーの生産はもちろんですが、効率的にエネルギー生産を行うための技術開発も行っています。例えば日本の火力発電は長年に渡り技術開発が続けられ、発電効率が大きく改善しました。一般的な火力発電の発電効率は35~43%と言われていますが、2018年には西名古屋火力発電所で発電効率63%を記録しています。
発電効率が向上すれば、少量の燃料でより多くの電力を生産できます。使用する燃料が少なくなれば、排出される温室効果ガスも減るため環境対策にも繋がるのです。またエネルギー業界は化石燃料によるエネルギー生産の効率化だけでなく、次世代エネルギーの研究・開発にも力を入れています。次世代エネルギーとは水力発電や太陽光発電、地熱発電など温室効果ガスの排出量が少ない、あるいは排出しないエネルギーのことです。新しい技術によって次世代のエネルギー事情に貢献できるので理系の就活生からの人気が高い傾向にあります。
エネルギー業界の職種:各種管理
エネルギー業界には様々な事業が存在します。複数の事業を効率的に動かすためには、各種事業の工程を把握し管理する職種が必要です。そんな各種管理には計画に基づいて十分な品質のエネルギーを出力できるように体制を管理する生産管理・品質管理や、エネルギーが行きわたるような供給ルートや残量を管理する物流・在庫管理、エネルギー開発などの施工管理などがあります。どの管理業務も重要ですが、特に生産管理や製造管理に関しては管理職の小さなミスが全体の大事故につながる可能性がある職種なので、安全への高い意識と責任感が求められます。
各種管理は開発や営業と異なり、一からものを作り出したり、人と接する職種ではないので一見すると見えづらい職種かもしれません。一方、エネルギー業界がエネルギーを生産し、安定して供給するためには、施設の施工とエネルギー量を把握しながら各家庭や企業などに供給する管理が必要不可欠です。縁の下からエネルギー業界を支えているため、やりがいは十分な職種だと言えるでしょう。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
エネルギー業界の志望動機・自己PRで押さえておくべき用語
エネルギー業界に志望する就活生は、志望動機・自己PRをエントリーシートの作成や面接での受け答えの際に、以下の用語を押さえておきましょう。
1. 再生可能エネルギー
再生可能エネルギーとは「風力、太陽光、水力」などの自然の力で生み出されるエネルギーのことです。環境への負荷が少ないため、エネルギー業界では持続可能性を重視する動きが加速しています。
2. グリーンエネルギー
グリーンエネルギーは、環境に配慮した再生可能エネルギーの一形態です。具体的には、化石燃料・バイオマス発電、風力発電などのことです。SDGsなどの環境配慮への流れが、活発化し活用企業や個人が増えてきています。グリーンエネルギーの増加は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となります。
3. エネルギー効率化
エネルギー効率化は、同じ効果を得るために消費されるエネルギー量を減らすことを意味しています。省エネ技術の進化により、企業や個人はエネルギーコストを削減し、環境負荷を軽減することが実現できるようになっています。
4. グリーンテクノロジー
グリーンテクノロジーは、環境に優しい製品やサービスを生み出したり、社会的な課題解決に貢献したりするなど、持続可能な世界を作るために活用されるテクノロジーとその取り組みの総称です。サステナテック(サステナブル・テクノロジー)とも呼ばれています。
エネルギー業界に向いている人・求められる人物像

エネルギー業界に向いている人として、まず最新の技術知識やニュースを常に収集できるような勉強家が挙げられます。日本のエネルギー業界は原料の多くを輸入に頼っているため、原料輸出国で情勢が変わると日本にも多大な影響があります。こうした社会情勢の変化に対応するためにも、ニュースを常にチェックする必要があるのです。またエネルギー業界はエネルギーを安定して供給するため、環境に配慮した新エネルギーの開発のためなど、常に新しい技術知識を収集する必要があります。最新の技術知識を収集するだけでなく、取り込んだ自分の中の知識を新しいことに活かそうとする意欲の高い人、チャレンジ精神が旺盛な人も求められています。
そしてグローバルな視野を持っている人も必要です。海外の国々と取引する機会が多いエネルギー業界は、海外出張や赴任も多くなります。そのため海外に行くことをポジティブに捉えられるか、グローバルな視点を持っているかという点はエネルギー業界で働く上で重要な要素となります。また、災害や事故が起こった際は柔軟で素早い対応が求められますし、営業職などの事務系の仕事ではコミュニケーション力も求められるので、柔軟性やコミュニケーション力がある人も必要です。最後に重要なのが縁の下の力持ちとして人々の生活を支えたいという想いがある人です。エネルギーは人々の生活にとって当たり前の存在になっているため、改めてエネルギーの存在に目を向けたり、感謝したりする人は少ないかもしれません。だからこそ、縁の下から人々の生活を支えることに価値を見いだせるかどうかが重要となるのです。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
エネルギー業界に関するよくある質問
エネルギー業界を志望している就活生が業界に対して抱いている疑問を3つピックアップしてみました。それでは解説していきます。
Q.仕事で海外に行くことはありますか?
エネルギー業界では、海外勤務をしている方もいますが、人数はあまり多くはありません。資源を確保するために海外と連携を取っている企業が多いですが、ITの発展により、海外と日本を繋ぐための業務は、減りつつあります。
そのため、総合商社や投資銀行などに比べれば、海外勤務をしている方は多くありません。
Q.エネルギー業界の今後の展望はどんなものになりそうですか?
業界の今後の動きとしては、再生可能エネルギー普及し、拡大を目的とした事業の増加が考えられます。
企業によっては、すでに地域づくりのなかで、風力発電といった再生可能エネルギーの導入や環境に配慮した生活スタイルの推進を提唱している企業も年々増加しています。
今後、エネルギー業界では大手企業・新規企業を問わず、新たなエネルギーの開発やその普及に力を入れていくでしょう。また、海外に依存している一次エネルギーの自給に関しても、海外進出による事業の拡大を通して打開案を打ち出していきそうです。
エネルギー業界に向いていない人はどんな人ですか?
自分のキャリアアップを前提として就活をしている人には向いていない場合が多いです。
エネルギー業界は他の業界と比較すると、大きな仕事をチームとして進めていく傾向が強く、個人の力はあまり重視されていない傾向があります。
「自分のキャリアのことを考えて複数の企業を経験してスキルアップしたい」と考えている人は働くモチベーションが低くなってしまう可能性が高いです。なぜなら、エネルギー業界では転職をする人が少ない傾向にあるためです。
キャリアアップのために就職を考えているのであれば他業界の志望も合わせて検討しておくとよいでしょう。
エネルギー業界の理解を深めて就活を有利に進めよう

エネルギー業界について基礎知識やビジネスモデルなどについて理解できたでしょうか。エネルギー業界は安定しており変化に乏しいというようなイメージがありますが、その反対で変革を繰り返している業界です。エネルギー業界に就職を考えるのであれば最新のトレンドチェックは欠かさないようにしましょう。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
⇓⇓26卒・27卒の方はコチラ⇓⇓