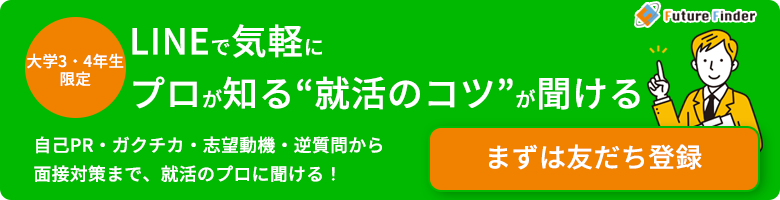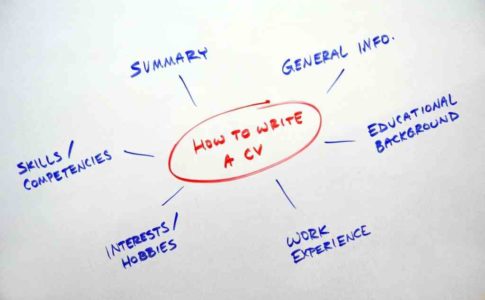自動車業界は今後100年に一度の変革期を迎えているといわれています。自動車業界を志望する就活生は、AIによる自動運転の実用化、国内需要の減少といった業界の現状や今後の動向について知っておかなければ面接を突破するのは難しくなるでしょう。そこで今回は、自動車業界の仕組み、業界が今後どうなっていくのかについて解説します。この記事を読んで、業界の基礎知識をおさらいしながら課題や将来性を知り、自分なりの意見を持った状態で面接に挑めれるようにしておきましょう。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
この記事の目次
自動車業界とは?

自動車業界、と聞くと自動車やバイク、バスなどの設計・製造・販売を行う自動車メーカーを思い浮かべる人も多いでしょう。自動車産業は日本の基幹産業の一つであり、日本製の車は世界中に大量に輸出されていて、日本の有名メーカーの車が外国の街を走っている様子を映像で見たことがあるという人も多いかもしれません。
華やかな自動車業界ですが、業界を構成するのはそうした自動車メーカーだけではありません。自動車を製造するためには何万点もの部品が必要です。また部品を作るためには素材が必要です。部品や素材の製造に関わるメーカーも、自動車業界の一角を担う重要な存在です。
さらに、ディーラーと呼ばれる自動車販売店の存在も重要になっています。幹線道路沿いに大きな看板を掲げ、新車を展示するなどして車の販売活動を行っている販売店を見たことがある人も多いかもしれませんが、自動車の販売店はブランドごとに存在し、独自の販売網を全国各地に広く展開しています。自動車がお客様の元へ届くまでには数多くのステークホルダーが関わっているのです。
その他に、自動車のメンテナンスを行う会社やレンタカー会社など、関連する様々なサービスまで含めて自動車業界と呼ぶこともあります。先述した企業群も、自動車メーカーと並んで就活生の人気を集めています。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
自動車業界の主な業種
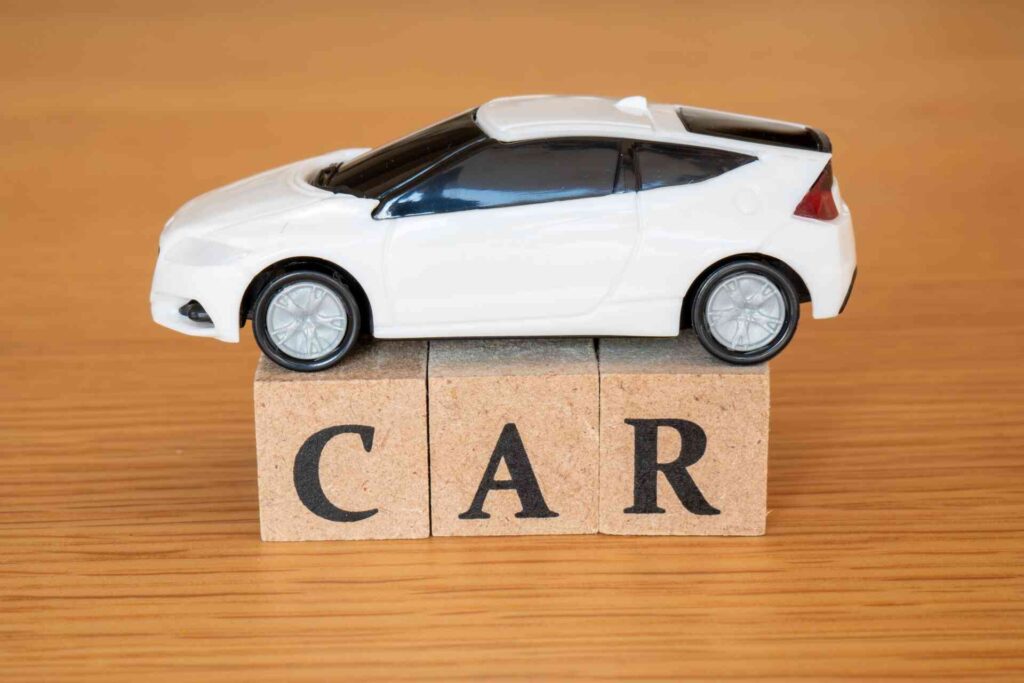
自動車メーカーをはじめ、自動車メーカーをとりまく様々な業種の概要を解説します。
自動車メーカー
トヨタや日産に代表される自動車メーカーは新車の開発・設計を行い、その車を製造するために必要なパーツを素材メーカーや部品メーカーに発注します。そのパーツを使って自社工場もしくは系列の組み立て会社で車を組み立て、完成した車を販売会社に卸売りして自動車メーカーは収益を上げています。
素材メーカー
自動車には非常に多種類の素材が使われています。最も多く使われているのは普通鋼、いわゆる鉄鋼で、ドアやボンネットといった車体はもちろん、様々な部品にも使用されている重要な素材です。他にも、エンジンを冷却するために必要なラジエーターには銅、タイヤのホイールにはアルミニウム、窓にはガラスが使われています。車体を塗装する塗料も必要です。こうした素材は、それぞれの専門メーカーが取り扱っています。
また、既存の素材を製造する一方、車体の軽量化や強度の向上を目指し、カーボンやガラス繊維を使った樹脂素材の開発を行うなど、各メーカーではより高品質な素材を目指した新素材の開発にも余念がありません。
部品メーカー
自動車1台には2~3万点という膨大な数の部品が使用されています。膨大な部品の製造を手掛けるのが自動車部品メーカーです。自動車部品の代表的なものには、エンジンが生み出すエネルギーを各所に伝える駆動系部品、カーナビやオーディオ、エンジンコントロールユニットなどの電装部品、バッテリーやブレーキ、タイヤや内装部品といったものがあり、多くの専門メーカーが存在します。
部品メーカーは階層構造になっているのが特徴です。自動車会社と直接取引をしている第1階層がティア1、ティア1に部品を供給するメーカーがティア2と呼ばれており、さらにティア2に部品を供給するティア3が存在することもあります。元々部品メーカーは特定の自動車メーカーにのみ製品を卸すことが多かったのですが、複数の自動車メーカーと取引をする部品メーカーも徐々に増えてきています。
上記の素材・部品メーカーから部品を仕入れ、完成車に組み立てるのが自動車メーカーです。なお、素材メーカー・部品メーカーを総称してサプライヤーと呼ぶこともあります。
自動車販売会社
完成した車を販売し、アフターサービスまで手掛けるのが自動車販売会社(ディーラー)です。多くのディーラーは自動車メーカーの直営となっていて、そのメーカーの車だけを取り扱っています。仕入台数や売上目標がメーカーから指示されていることもあるなど、メーカーとの結びつきは非常に強いものです。それに対して独立系のディーラーでは複数メーカーの車を扱い、地域密着のサービスを展開しています。
また、中古車の世界ではインターネットでの販売が早くから行われていましたが、新車もネット販売が徐々に主流になってきています。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
自動車業界の業界の現状
自動車業界は今、近年稀に見る100年に1度の変革期と言われています。変革期と言われている理由は大きく分けて2つあります。
1つ目は、テクノロジーの進歩です。最新のテクノロジーが自動車産業を大きく変えています。電気自動車(EV)や自動運転技術などの革新的な進歩が業界に新たな風を吹き込んでいます。特に、Tesla(テスラ)などの新しい企業が電気自動車市場に変革をもたらしています。彼らの新しいアプローチは、伝統的な自動車メーカーにも影響を与え、業界全体の競争を激化させているのです。
2つ目は、環境への意識です。環境問題への関心が高まり、自動車メーカーはエコフレンドリーな車両の開発に力を入れています。規制の厳格化や持続可能なエネルギー源への探求が業界の動向を大きく左右しています。多くの自動車メーカーが環境に配慮した新しい技術や車両の開発に取り組んでいます。ハイブリッド車や電気自動車の製造に注力し、環境負荷を低減する取り組みが業界全体に広がっています。
そのため、自動車業界は過去にない勢いで急激に変化しており、テクノロジーの進化や環境意識の高まりが大きな影響を与えています。一企業として、業界全体の変革に取り残されない競争戦略を立てるためには、革新的な技術開発や環境に配慮した製品の提供が非常に重要な鍵になっています。
自動車業界の今後の展望

次は、自動車業界の今後がどう変化してくのかについて解説していきます。自動車業界の今後を考えるうえで必ずと言っていいほど、注目が集まる2つのキーワード「CASE」と「MaaS」に着目しながら、業界の今後を考えてみましょう。
自動車の進化の方向性を表す「CASE」
CASEとは「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared & Services(シェアリング&サービス)」「Electric(電気自動車)」の4つの頭文字を合わせたものです。一つ一つの意味は以下の通りです。
- コネクテッド…インターネットに常時接続している車やサービス
- 自動運転…人が操作しなくても車が自動で走行できる技術
- シェアリング&サービス…車の貸し借りや相乗りなど所有せずに車を使うこと
- 電気自動車…ガソリンではなく電気を使って動く自動車
車のあり方・使い方ともに従来の概念を大きく覆すものであり「CASE」はまさにこれから自動車が進化していく方向性を表した言葉といえます。同時に必要となる技術領域も広がっていくため、様々な業種との技術・事業提携が増えていくことが予想されます。
自動車の新しい使い方を示す「MaaS」
MaaSは「Mobility as a Service」の略で、ICTによって様々な交通手段を統合するサービスのことです。交通手段には電車やバス、タクシーなどいろいろなものがありますが、例えば現在地からある場所に行きたいときに何をどう組み合わせて利用したら一番効率的かを提案し、かつ実現してくれるのがMaaSです。ここにカーシェアリングサービスなども統合すれば、公共交通機関の届かない過疎地で高齢者の移動手段を確保するといったことも可能になります。
これまで、公共交通機関と自動車とは別々のもの、時には対立するものとして考えられていましたが、MaaSは両者をシームレスに結びつけるものであり、自動車の新たな使い方を示すものです。この考え方は、自動車業界を大きく変革させるきっかけとして注目されています。
企業競争を超え企業協働が主流に
自動車業界は今後、企業同士の協力が重要視される時代に向かうとされています。過去の競争から協働への転換が起きており、技術革新や課題解決のための新たな手段として注目されつつあります。
まずは、技術の共有と発展が重視されています。 自動車業界では、従来のライバル関係から脱却し、相互の技術や知識を共有することが大切だと認識されています。EVや自動運転技術などの革新的な分野で、企業間の協力体制を取り推進している企業が現れているのです。連携を深めることで、業界全体の発展に繋がりより良い、車社会への実現に取り組んでいます。
また、企業間で共通の課題に対する取り組みも増えています。先述した通り自動車産業が直面する課題に対処するためには、企業間の協力が必要不可欠です。環境負荷の低減や新技術の開発など、業界全体が抱える共通の問題に対処するために企業同士が手を取り業界の課題解決に取り組んでいるのです。
電気を超え水素がメインのサスティナビリティへ
自動車業界では、持続可能性を重視して、電気車両から水素車両への関心が高まっています。これは、環境への配慮やエネルギー効率の向上を目指す取り組みの一環です。
実は、水素をエネルギー源とする車両の技術は急速に開発が進んでいます。水素燃料電池車は、電気自動車に比べて長距離走行や充電時間の問題を解決するかもしれないとされているのです。また、水素は高いエネルギー密度を持ち、車両により多くのエネルギーを効率的に供給できるため、移動距離や充電の利便性で電気自動車よりも優位性があるとされています。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
自動車業界の課題

ここからは自動車業界が直面している課題を見ていきましょう。業界全体の課題を知り、自分なりの業界に対する考えを持っておくと業界研究に大いに役立ちます。
AIによる自動運転の実用化
将来に向けて各自動車メーカーが最も注力しているのが、AIを利用した自動運転技術です。実現すれば交通事故の減少に寄与するのはもちろん、長距離トラックなどのドライバー不足にも対応できるとして、日本だけでなく欧米や中国など世界各国のメーカーが取り組んでいます。アメリカのSAE Internationalは、自動運転を以下の5段階に定義しています。
- レベル1ステアリング操作か加減速のいずれかをシステムがサポート
- レベル2ステアリング操作と加減速の両方をシステムがサポート
- レベル3特定の場所ではシステムがすべてを操作(緊急時のみドライバーが操作)
- レベル4特定の場所ではシステムがすべてを操作(ドライバーの関与なし)
- レベル5あらゆる場所でシステムがすべてを操作
このうちレベル1・2は「運転支援」と呼ばれており、レベル3以上が「自動運転」、レベル5が「完全自動運転」です。日本では2019年までにレベル2まで実用化されており、2030年までに高速道路上ではレベル5に達することを目標としていますが、それにはまだまだ大きな課題があります。
課題の一つは、AIの力不足です。自動車を運転していると様々な不測の事態に遭遇することがありますが、AIによる自動運転ではこうしたとっさの事態への対応が難しいのです。そして、システムエラーの可能性もゼロではありません。自動運転を行う際には、自車の情報だけではなく信号などの周辺情報や他車情報も正確に認識・判断しなくてはなりません。このあたりの技術向上が今後の大きなカギとなってくるでしょう。
また、自動運転普及のためには法律の改正も必要になります。事故が起きたとき、レベル2まではドライバーの責任になりますが、レベル3以上はドライバーの操作によるものではないためシステム側の責任になるといわれています。そのため、事故の責任を誰がどういう形で取るのかといったことに関する法整備が必要不可欠です。
人手不足
自動車業界では次代を担う技術者・作業者の不足も深刻です。熟練の作業者が年齢を重ねて定年に近づく一方、若い世代の絶対数が少なく、代替となる人材の確保ができていません。若年層が不足している原因として考えられるのは、少子高齢化と若者の車離れです。少子化のためそもそも若者人口が少ないことに加え、長引く不景気で若者の消費意欲が減退し、特に都市部では比較的優先順位の低い車に対する関心が薄れています。こうしたことから、市場規模は縮小する一方で将来性がないと思われていることも一因といえるでしょう。
車の開発・製造に必要なエンジニアは守備範囲が広いうえ、育成に時間がかかるため慢性的に不足しています。女性の活用推進や車への興味を喚起する活動などの施策はあるものの、人手不足をすぐに解消することは困難な状況です。そのため各社ともビジネスの管理・運営方法や製品戦略の変更を迫られています。
新興国への販路拡大
国内市場が飽和状態になりつつある一方、今後の需要拡大が期待されているのが新興国です。東南アジアや中東の新興国では、経済の発展により人々の生活水準が上がり、かつては移動手段の主流だったオートバイが自動車に取って代わられつつあります。まさにこれから自動車市場が伸びていくことが期待できるとあって、日本の自動車メーカーの多くがこうした新興国にターゲットを定め、積極的に動いています。
新興国には経済格差が存在しており、高価ではあるものの精密で性能の良い日本車を主に受け入れているのは富裕層です。富裕層の多いUAEやトルコでは日本車が強く、所得水準があまり高くないエジプトやトルコでは比較的安価な韓国車が売れているという現状があり、今後はボリュームの拡大が見込まれる中間層に対してどのように訴求していくかというのが課題となっています。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
自動車業界に向いている人
クルマが好き
自動車メーカーでは、新車モデルの企画職、研究開発職、生産管理職など、さまざまな仕事が用意されています。
自動車業界にある職種は、異なる業務を担当しますが、どの業務も「クルマ」中心になってきます。どの部署も優れたクルマ作りに向けて取り組んでいます。この業界で働き続けられる人には、商品であるクルマに対する「興味」が重要です。クルマに興味を持つだけでなく、クルマとビジネスを関連付けて考えられる人材が求められます。
自動車業界で働いている人たちは、ほとんどがクルマ好きな社員が多く、共通の趣味や価値観を持つ仲間と働ける環境も魅力的です。
チームプレイの得意な人
自動車製造は多くの社員が協力して行う仕事で成り立っています。
業務を進めるには、他の人や他の部署との連携や協力が欠かせません。特に研究開発などの技術職では、大規模なプロジェクトを何年にもわたってチームで進めることが一般的です。そのため、協調性や良好な人間関係を築くことが求められます。大規模なプロジェクトは一人だけでは完結できず、多くの人々が関わって動かしていきます。その中で、組織全体の視点で考え、行動することが求められます。
また、経験を積むと組織やチームを率いるリーダーに昇進することもあります。そのため、チームプレイ能力だけでなく、チームやプロジェクトを管理し、指導する力も求められます。
自動車業界の職種

自動車業界には様々な職種があります。
自動車業界の職種1:研究・開発
では、自動車業界にはどんな職種があるのか見ていきましょう。まず、研究開発ではモーターやエンジン、トランスミッションなど自動車を構成する様々な分野の専門家が集まって、部品ごとの開発や新しい自動車の研究・開発などを行います。燃費の向上に関する研究や、電気自動車・ハイブリッド自動車といった新世代の自動車の開発を行うほか、生産技術の開発も手掛けています。研究開発は幅広い分野に及ぶため、求められる知識やスキルが大きく異なっており、多彩な人材が必要です。
様々な専門家が集まった自動車メーカーの研究開発部門では、自動車開発で培った技術を生かして航空機のエンジンを開発したり、発電機や除雪機など人の暮らしを助ける製品を開発するといったことも行われています。
自動車業界の職種2:商品企画・販促
商品企画・販促は事務系の職種です。売れる車を作るためには、消費者がどんな車を求めているのかを知ることが大切です。そのために消費者動向調査やマーケティングを行って消費者のニーズを把握し、新しい車のアイディアを練り上げたうえで新車の企画やコンセプトの立案を行います。そしてユーザーがどのような場面で使用するのかを想定し、それに合わせた商品のアピールポイントを自社のブランドイメージと合わせて作り上げていきます。
新車発売イベントやキャンペーンの企画、ノベルティの制作のほか資材や部品の調達、海外事業支援なども重要な仕事です。どの自動車メーカーにも当然のごとく存在する部門ですが、世界トップクラスの新車発売台数を誇るトヨタ自動車では特にこの企画・販促に力を入れています。
自動車業界の職種3:生産管理
実際に現場で自動車を組み立てるのが生産管理部門の仕事です。ここでは部品・資材の手配や品質管理、生産ラインの管理などを行っています。生産量は多すぎても少なすぎてもいけないので、需要を見ながら過不足なく部品の手配と生産管理を行うことが重要です。部品の発注計画は、市場での売れ行きに合わせて綿密に立てる必要があります。もちろん納期は厳守で、たとえ数台であっても求められた納品期日にきちんと間に合わせるように生産することが目標です。
新車を作る際には企画・開発から生産・販売に至るまでの全体日程を立案し、進捗を管理する「新車進行管理業務」を行います。関係各所とコミュニケーションを取りながらプロジェクトを予定通りに進めていく重要な仕事です。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
自動車業界の今後は激動!?業界についての知見を深めてからいざ選考へ!

技術革新や国内ニーズの変化、新たな海外戦略など自動車業界は激しい変化の波にさらされています。自動車業界を志望する人は業界研究を怠らず、常に最新情報をチェックすることで状況を把握し、理解を深めていきたいものです。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
⇓⇓25卒・26卒の方はコチラ⇓⇓