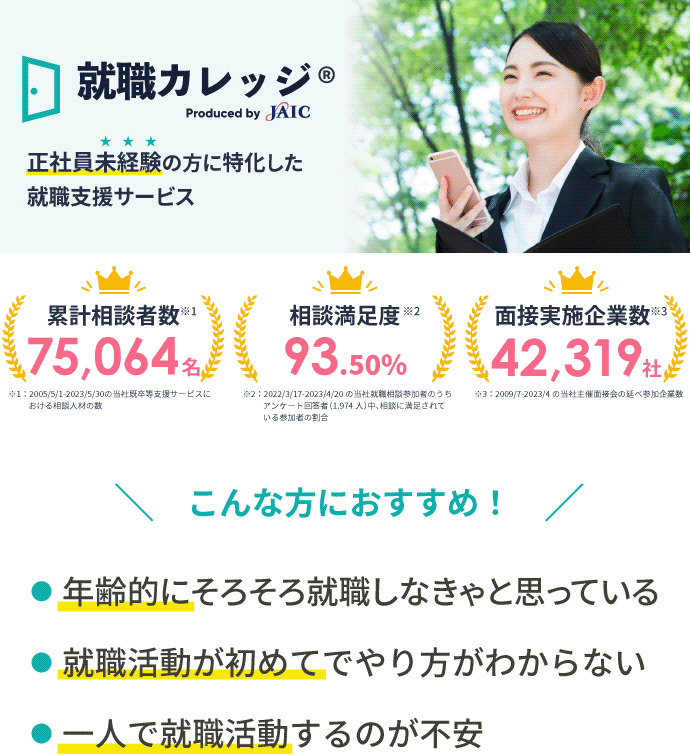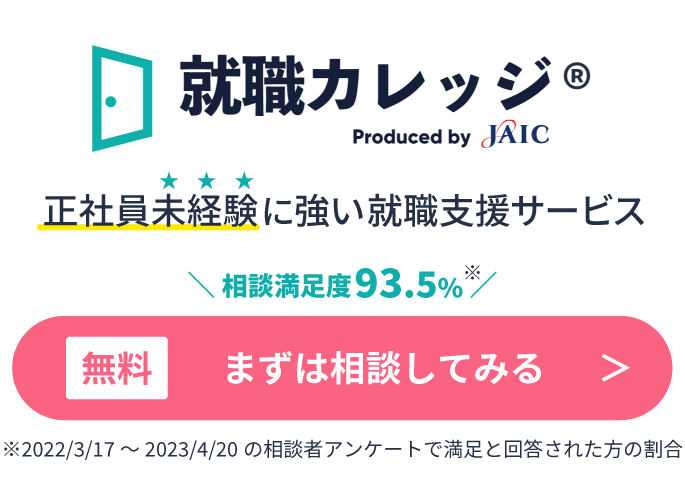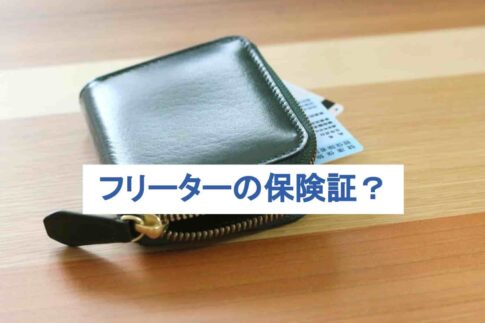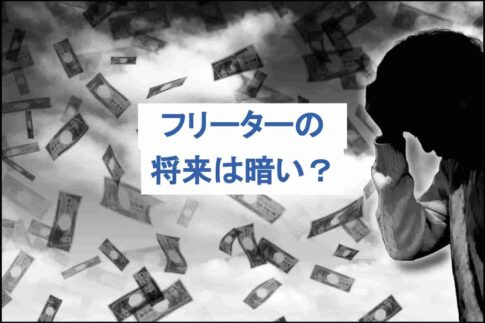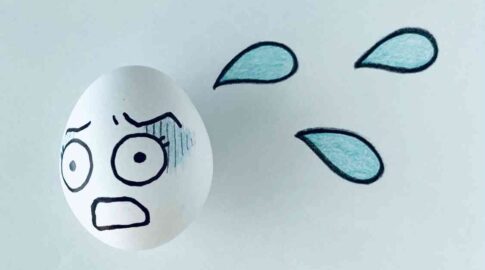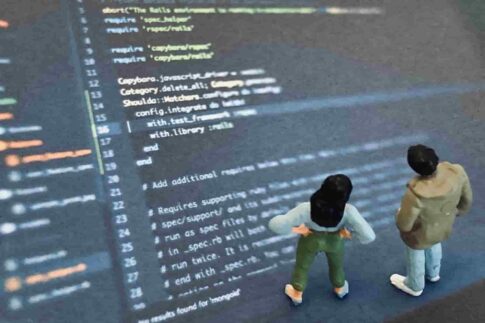フリーターの割合は日本全体でどれほどなのでしょうか?
フリーターという働き方を選択している人には様々な理由があります。一般的に考えられる理由としては、「明確な目標がない」「夢を追及している」「家庭の事情やトラブル」などです。
いずれにしても、周囲の人からはフリーターとしての生き方を理解されていないと感じる人が少なくありません。では、実際にフリーターとして働く人の割合はどうなのでしょうか。
また、フリーターから正社員になることのメリットとはどういったことがあるのでしょうか。フリーターとしての働き方について詳しく解説していきます。
こちらの動画では、フリーターと正社員の違いをお金の観点から解説しています。記事を読むのが面倒という方は是非ご覧ください。
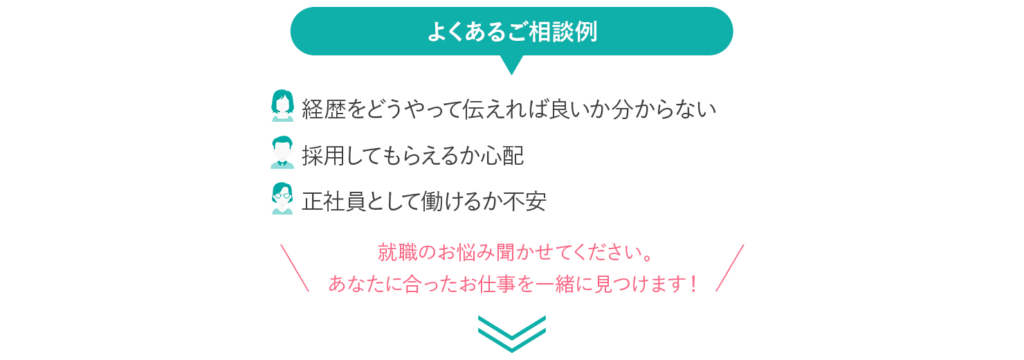



この記事の目次
フリーターとは若年層の人たちを指す言葉

フリーターとは、「フリーランスアルバイター」の略称であり、「フリーアルバイター」とも言われています。
フリーターは一般的に、パートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用で生計を立てている人やその希望者を指しますが、その中には主婦や学生は含まれません。
また、フリーターと呼ばれる人には、年齢も限定されており、学校卒業後の15歳から34歳までに該当する若者を指します。
では、フリーターとして実際に働いている人の割合はどのくらいなのでしょうか。
また、フリーターとして働くことを選択する人は増加しているのでしょうか、それとも減少しているのでしょうか。まずは、日本におけるフリーターの割合とその背景について解説します。
フリーターについて知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
実は減っている?フリーターの割合は?

1980年代から1990年代のバブル世代と呼ばれる時代に、自由な時間を確保しながら生活を維持するフリーターが注目を集めていました。
バブル時代と今のフリーター
当時は景気が良いということもあり、高給を稼ぐことも可能でありながら自由な時間を持つことができるフリーターが持てはやされていたという社会的な背景が見られます。
しかし、昨今におけるフリーターは、バブル時代のフリーターの立場とは大きく違って、定職につかないことによる生活の不安定や世間が持つイメージなどによって、避けるべき状況として認識されてきているという背景があるようです。
フリーターは152万人へ
その結果、2017年の労働調査においてのフリーターの割合は、昨年に比べておよそ2万人の減少傾向にあり、約152万人となっています。減少の理由として、若年層そのものの人口減少もありますが、派遣やフリーターなどの非正規雇用に対してのネガティブな印象が顕著となり、フリーターの存在そのものが社会問題となっているという背景があります。
このようなことから、実際にフリーターとして働き続ける人の数は減ってきているということが言えます。
フリーターになった理由は何?

フリーターという働き方を選択する人の主な理由は人によって様々ですが、厚生労働省の調査結果において比較的多いと考えられる3つの理由についてご紹介します。
就きたい仕事の下積み
ひとつ目の理由としては、「就きたい仕事のための勉強や準備、修業期間として」です。例えば、芸能関係や職人、フリーランスなどの職業に就きたいという明確な目標を持っている人が考えられます。
このような理由の人は、フリーターを選択する人の中でも、仕事への興味、やりたい仕事を優先するという考えがある人が多いようです。
生活の為に働かなければいけない
ふたつ目の理由としては、「学費稼ぎなど生活のために一時的に働く必要があったから」です。
この場合におけるフリーターとしての働きは、本人の意欲とは別の問題があるといえます。例えば、大学受験の浪人中や資格取得のための勉強のための学費や生活費の確保などが考えられます。
したがって、一時的なアルバイトであるため、仕事選びにこだわりがなく、割り切っているということが特徴です。
なんとなくフリーター
最後は「なんとなく」です。なんとなくフリーターをしているという人の傾向として、学校を卒業後、とくに明確な職業展望を持っていない「モラトリアム型」であることが考えられます。
また、学校を卒業して一度は就職をしたものの、人間関係による悩みや心身の不調により離職し、再就職の見通しがはっきりしないという人などです。
このような理由によってフリーターを続けている場合は、多くの場合そのまま長引く傾向にありますので、安定した職業に就くために抜け出したいという場合は、本人のやる気や強い意志が必要かもしれません。
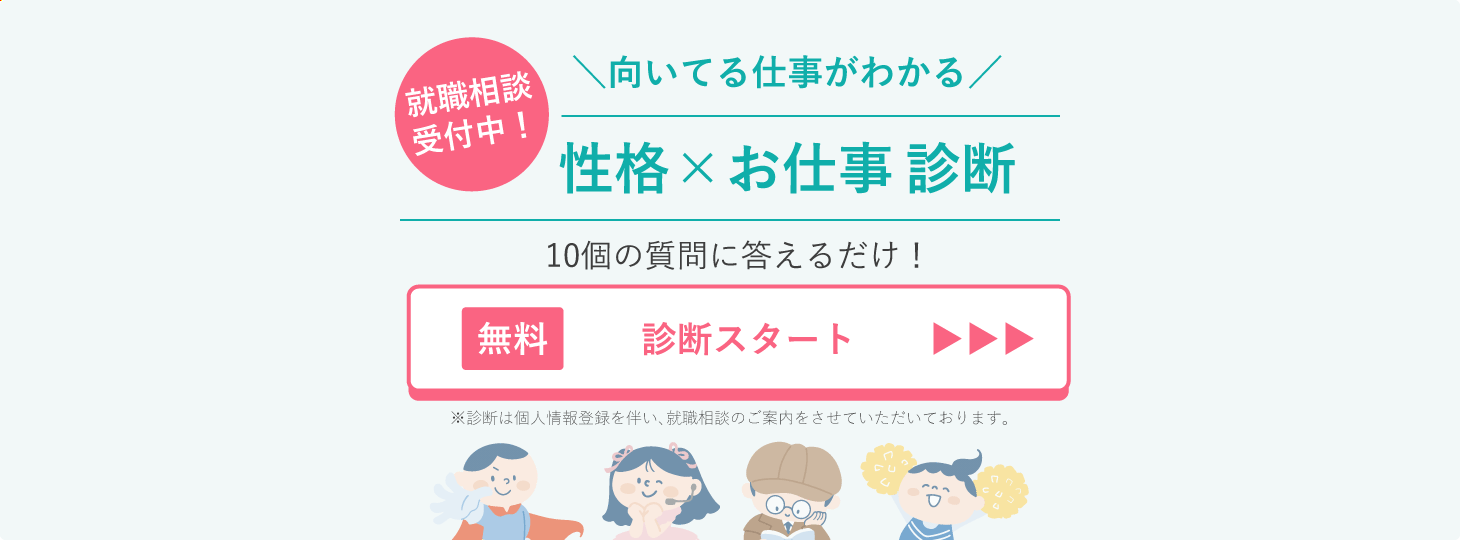

フリーターと正社員の年収の違いとは?

フリーターとして働くことについては、様々な理由があることが分かりましたが、いずれにしてもフリーターと正社員の生涯年収には大きな差があるようです。
その理由として、正社員は年齢の上昇とともに、年収、時間当たりの収入も高くなっていく傾向ですが、パートやアルバイトなどにおいては、10代であろうと40代であろうと年収や時間当たり収入にほとんど変化がなく、長く勤めても収入が上がっていくことが期待できないということがあります。
したがって、フリーターとして働き続けるということは、収入面でのリスクが大きく、正社員との賃金格差を永遠に埋めることができないということが考えられます。
したがって、フリーターとして働き続けながら、安心して生活ができるほどの収入を得るためには、人よりもたくさん働く、または時給が高い仕事を選ぶ、時給を上げるということが必要となります。
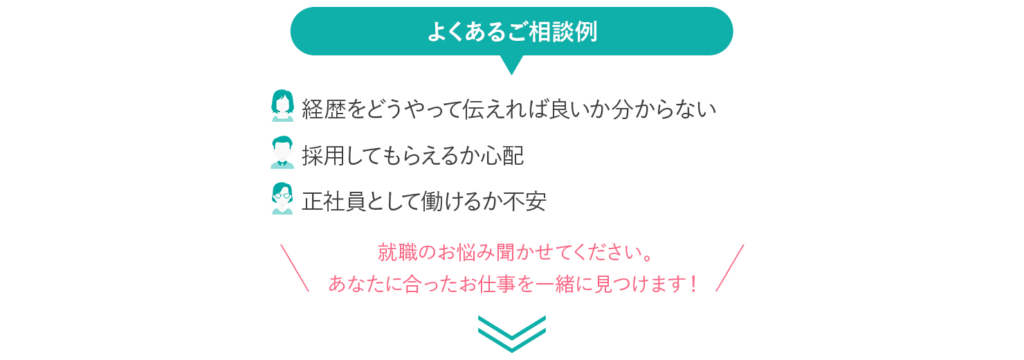



若い頃は良いけど?高齢化にともないフリーターの生活は苦しくなる

20代や30代の若いころは体力もあるため、フリーターとして働いていても場合によっては、収入を増やすために長時間労働をしたり、掛け持ちをしたりすることも可能です。
しかし、一般的に40代以上になると20代や30代の頃に比べて、体力的にも無理が効かなくなる可能性が高くなります。
高齢のフリーターは年収が下がる?
したがって、長時間労働や掛持ち労働などをすることが困難になり、結果的に若いころよりも収入が下がるケースも少なくありません。
また、アルバイトを探す際にも、若い時は様々なアルバイトの募集があり採用されていたのに、年齢を重ねるごとにアルバイトの採用率が下がり、なかなか仕事が見つからなくなったというケースも見られます。
正社員採用される確率も下がる?
さらに、フリーター経験を評価しないという企業もありますので、年齢が高くなったことに加えて職歴や経験不足などが理由となり、若いころに比べて正社員になれる可能性も格段に低くなっていく傾向があります。
このように、定職につかないまま高齢になると生活が苦しくなる一方であるため、現在フリーターの人は若いうちからしっかりとした将来設計をしておくなどの対処が必要です。
フリーターと正社員の社会保険の差とは?

正社員と比べて、フリーターなどの非正規雇用労働者の社会保険はどのように違うのか見ていきましょう。
退職金や財形制度が適用されにくい
退職後の生活設計に備えることが出来る「退職金制度」や「財形制度」などが適用されにくいという傾向にあります。
さらに、病気やけがなどに備える「健康保険」や老後の生活を支える「厚生年金」などの社会保険適用率も低いという特徴があります。
平成26年における厚生労働省の統計を例に挙げると、正社員の健康保険適用率は99.3%、厚生年金適用率は99.1%であることに対して、非正規雇用労働者の健康保険適用率は54.7%、厚生年金適用率は52.0%にとどまる結果となっています。
フリーターと正社員は収入以外にも差が生まれる
このようなことから、非正規雇用労働者であるフリーターと正社員を比較すると収入面の違いだけではなく、社会保険面や福利厚生面などに関しても大きな違いがあるということが分かります。
したがって、フリーターとして生涯働き続けるならば、少しでも収入を上げて老後の資金などを補うほどの蓄えが必要です。しかし、今の時代において、実現することは現実的に非常に困難な状況であるといえます。
自由なイメージだったバブル時代のフリーター

一般的に「フリーター」という言葉が使われ始めたのは、1987年頃であるといわれています。
当時はバブル景気ということもあり、アルバイトの収入だけでも十分に生活をしていくことが可能だった時代です。
また、掛け持ちなどをしてたくさんの収入を得ているフリーターも存在し、会社員よりも多くの収入を得ていた人も少なくなかったと言われています。
このように、バブル時代のフリーターは、収入面での心配がないこともあり、「自由に働きたい」と思った若者たちが自らフリーターとなり、会社に縛られずに自由に生きていくというライフスタイルが持てはやされていたとさえいわれています。
また、自由を求めながらも、目的や夢に向かって活気に満ち溢れていた若者も多く見られ、世間のフリーターに対する評価もそれほど悪くはなかったようです。
したがって、バブル時代のフリーターは、就職氷河期以降のフリーターと違って、自由で明るいというイメージがあったといえます。
社会問題化しているのは就職氷河期時代のフリーター

バブルが崩壊して以降の1990年代半ばから、就職氷河期に突入しフリーターに対するイメージが大きく変化することになります。
就職氷河期からフリーターのイメージがネガティブに
就職氷河期になると、たとえ大学を卒業しても就職が出来ないという状況もめずらしくなかったようです。
これをきっかけに、バブル時代は「夢を目指してフリーター」というイメージや、「自由を求めてフリーター」という明るいイメージとして世間の認識があったフリーターも、「就職が出来ない人の最終的な働き方」というネガティブな世間の認識に変わっていきました。
安定した収入を得られる正社員や公務員が評価され始めた
さらに、以前のようにフリーターとして、生計を立てていくということが徐々に困難となっていく一方で、安定した収入を得ることが出来る正社員や公務員の評価が高まり、フリーターに対する世間のイメージがまずます低下していったようです。
また、初期の就職氷河期を経験しているフリーターは2018年現在、40代半ばの年齢に差し掛かるため、企業においても40代の正社員が空洞化している状況です。このように、就職氷河期時代以降のフリーターはいつの間にか大きな社会問題となっています。
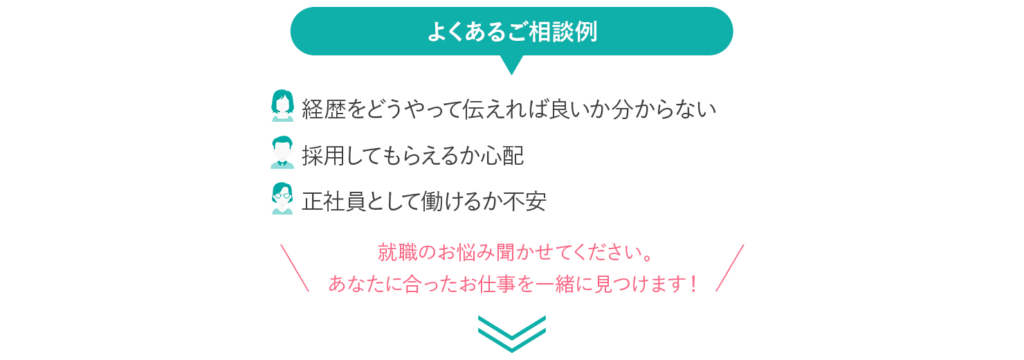



フリーターから正社員になるなら早いほうがいい!

フリーターとして生活をしている人の中には、将来の生活のことなどを考え、いずれは正社員になることを考えているという人も多いようです。
しかし、フリーターから正社員になれたという割合は、フリーター期間が短いほど確率が高くなります。
フリーターを長く続けると就職しにくくなる
厚生労働省の統計によると、フリーター期間が半年以内では、男性で約7割、女性で約6割の人が正社員になっているということに対して、フリーター期間が3年を超える場合では、男性で約6割、女性で約4割となっています。
したがって、フリーター期間が半年以内と3年を超える場合とでは、全体でおよそ15%の差が見られるということになります。
正社員経験の少なさが採用されにくくする原因の1つ
このような結果になる理由にはそれぞれの企業の考えがあると考えられますが、正社員とそれ以外の労働者では、勤務先による訓練の実施状況が異なるということも関係しているようです。
つまり、正社員時代にした経験や受けた教育が重視されているのです。
訓練の実施率が高い正社員はおよそ44.2%であることに対して、契約社員や嘱託社員は29.9%、パートやアルバイトは14.4%という結果がでているため、正社員に比べてフリーターの経験は、職業能力形成においても不利であるということがいえます。
したがって、フリーターから正社員になるなら、出来るだけ早いほうが有利です。
将来設計と一緒に働き方も考えよう

バブル時代や就職氷河期などにおいて、人々を取り巻く経済情勢や社会情勢の変化があったように、現在も世の中の状況は日々変化しているといえます。
そのような変化によって、あたり前のようにいつでも仕事が見つかったり、勤務している会社が定年まで存続したりという前提が、必ずしも期待することができないという可能性もあります。
したがって、早いうちから将来設計を立てながら、時代の変化にも対処していく必要があるといえます。
将来設計とは
一般的に将来設計とは、自分がどのような人生を望んで、結婚や出産、老後の人生の送り方などを決めていくことです。
多くの場合、将来設計を立て、実現していくためには、安定した収入を得て生計を立てていくことが大前提となります。
そのためには、フリーターから抜け出して安定した職業に就くことが一般的です。
しかし、フリーターとして働く理由は人によって違いますので、働き方のひとつとしてフリーターが必ずしも良くないこととは言えません。
正社員によって収入と安定を得られる
正社員として働くということは、フリーターとして働き続けることに比べて、収入面をはじめ、社会保険や福利厚生面においても大きな安心を手にすることができるといえます。
また、正社員としての経験を積むことによって、リストラや転職などの不測の事態が起こった際にも再就職がしやすいという可能性があります。
今の時代は、バブル時代のように、「高齢者は裕福である」という状況が必ずしもあるとは言えない時代になっています。
したがって、若い時に安定した職業に就いていなかったことによる、老後の資金不足や年金の問題などによって、「高齢者の貧困」が社会問題となっています。
若い頃から安定した職業に就いていなかったことによって、将来貧困に陥ることを防ぐためにも、若いうちから将来設計と一緒に、働き方についても考えることが大切です。
「フリーターの割合」によくある質問
フリーターと呼ばれる人は、学校卒業後の15歳から34歳までに該当する若者を指します。「フリーターとは若年層の人たちを指す言葉」で詳しく解説しておりますので気になった方はチェックしてみてください。
実際にフリーターとして働き続ける人の数は減ってきているというデータがあります。詳しくは「実は減っている?フリーターの割合は?」の章をチェックしてください。