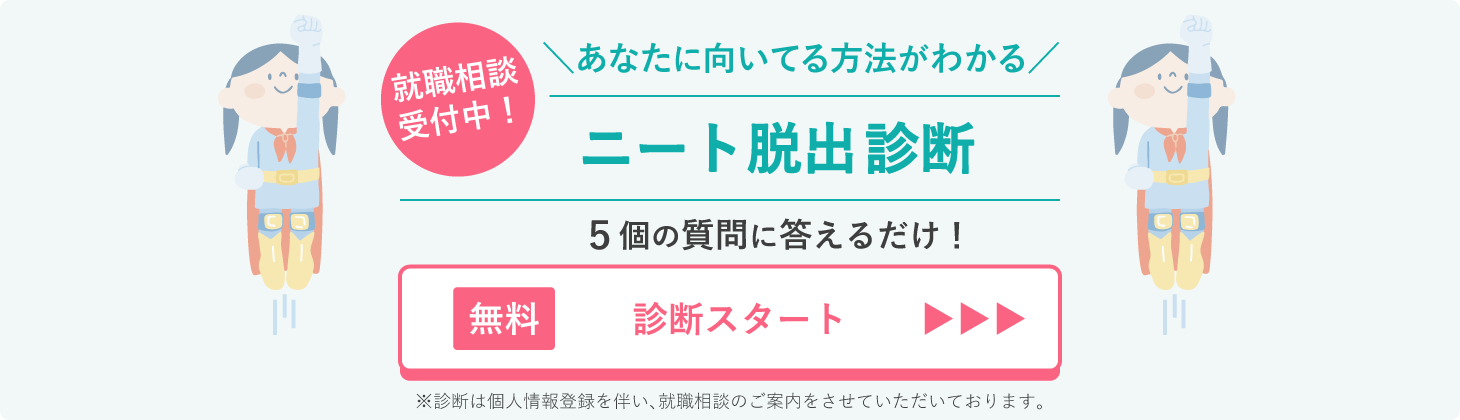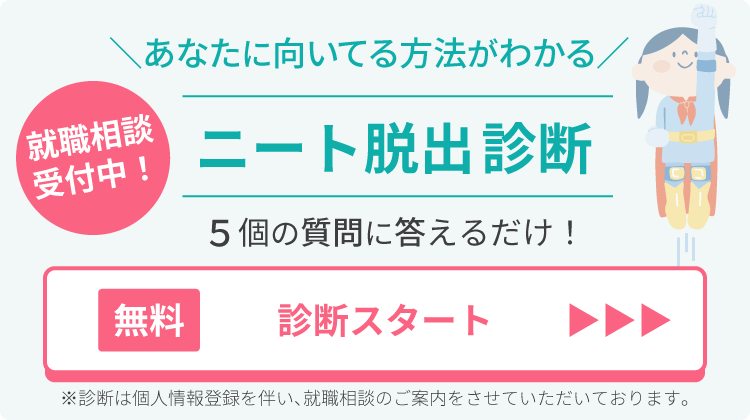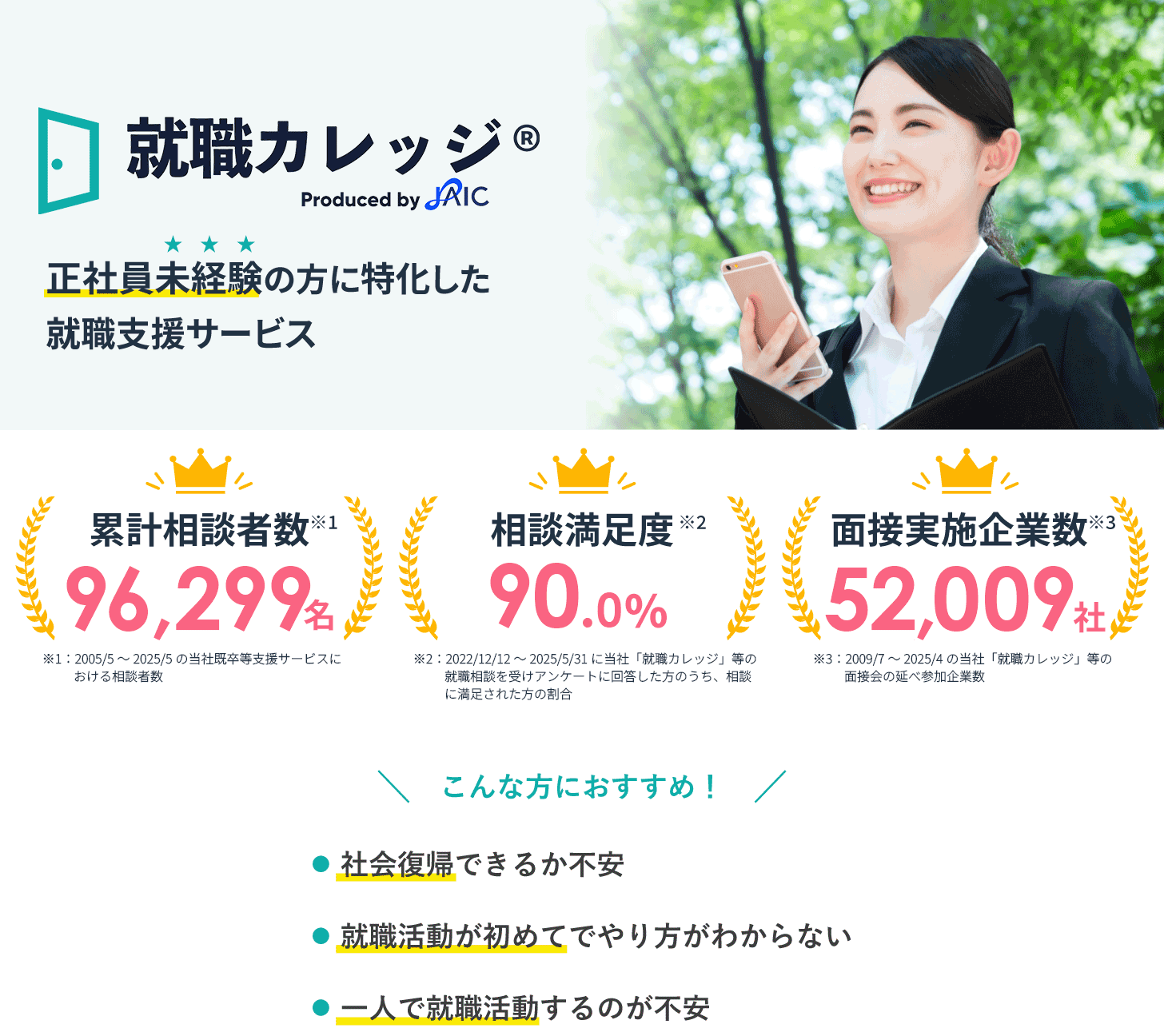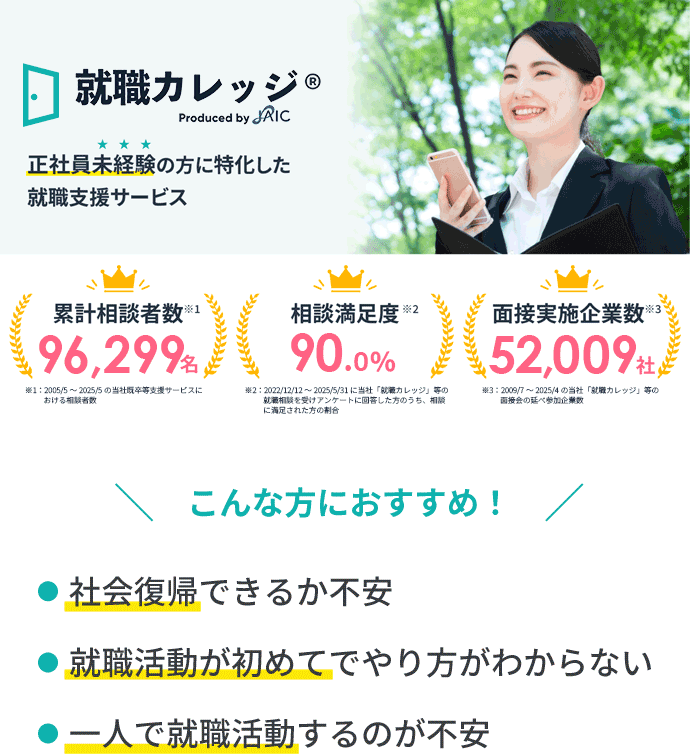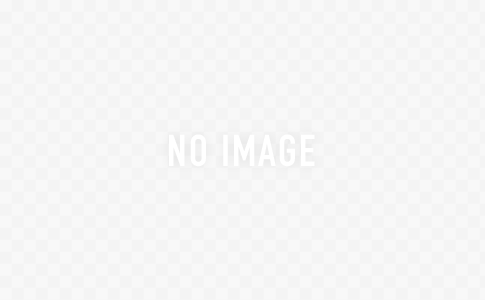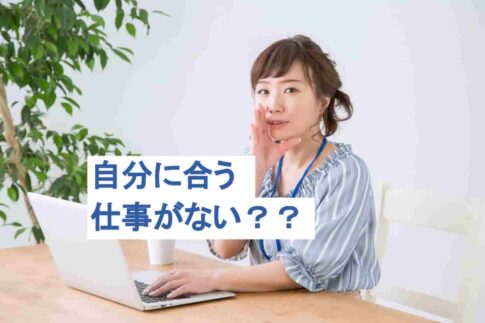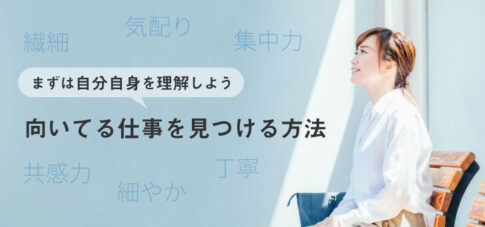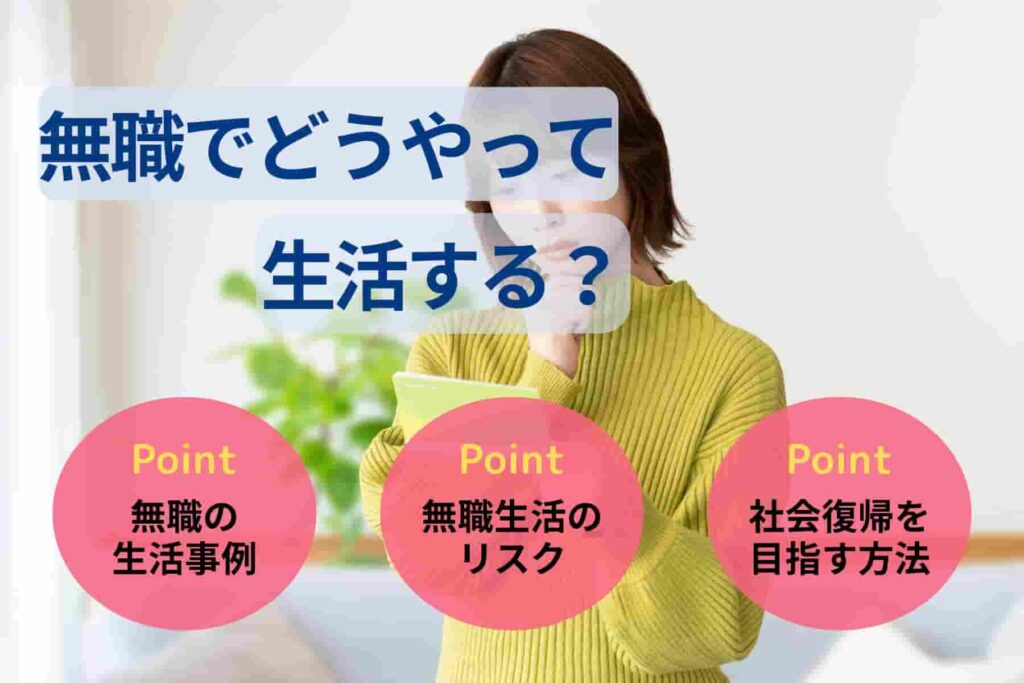
無職で生活をするためには、実家で家族に支えてもらうなど、生活をしていくための事例を把握しておくことが重要です。
なぜなら、無職で生活をするための方法は複数あるため、選択肢を把握しておくことで自分の状況に合った方法を選べるからです。
この記事では、無職で生活をする人が知っておくべき方法や、無職生活を継続するリスク、無職から社会復帰を目指す方法について解説しています。
無職で生活をしていかなければいけない人は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
無職の定義とは
無職とは、働く意欲の有無に関係なく働いていない人のことです。
具体的には、職についていなかったり家業に専念していたり、学生であったりするなど、収入を得るための仕事に従事していない状態を指します。
国内の無職は完全失業者が約180万人、非労働人口が約230万人であり、全体の約6%に上ります。
完全失業者は就職活動をしているものの職に就けていない人を指し、非労働人口は就労可能な年齢でありながら就業者と完全失業者に当てはまらない人です。
無職はフリーター・ニートとよく似ていると思われがちですが「実際に働いているか」「今どのような行動を取っているか」で意味が異なります。
1. 無職の定義
無職とは、厚生労働省の定義によると「家事(専業)」「無職」「学生」をあわせたものと定義されています。
具体的には、一般的に収入を得るための仕事に従事していない状態を指します。
参考:厚生労働省「用語の定義」
一方で、無職はフリーターやニートと混同されがちですが、違いは明確にあります。フリーターやニートとの違いは以下の表のとおりです。
| 用語 | 概要 | 概要 |
|---|---|---|
| 無職 | 収入を伴う仕事をしていない人 | 就業意思の有無を問わず広く含まれる |
| フリーター | パートやアルバイトなど非正規で働く人 | 正社員ではないが働いていて収入がある |
| ニート | 就学・就労・職業訓練のいずれも行っていない15〜34歳の人 | 「学んでいない」「働いていない」が条件で就業意思があまりない状態と言える |
無職は就業意思を問わず、仕事をしていない人全般にかかる用語に対し、ニートは学んだり働いていない15〜34歳の人に当てはまる言葉です。
また、フリーターは正社員以外の非正規で働く人を表す言葉です。
2. 国内における無職の割合
厚生労働省の調査によると、国内における無職の割合は約6%です。
労働者は約6,740万人であり、求職活動をしている完全失業者は約180万人、求職活動をしていない非労働人口が約230万人となっています。
また、女性の非労働人口は男性よりも1,050万人も多い状況です。
女性の非労働人口のうち約160万人は、働く意欲があるにもかかわらず、仕事を探せない状況にあります。「無職だと仕事をする気がないのではないか」と思う人もいますが、定義を理解していれば、無職の方に対して「働けない事情があるのかもしれない」と思えるようになるでしょう。
参考:厚生労働省「第2章 雇用情勢の動向」
無職でどうやって生活する?6つの事例を紹介
実家で家族に支えてもらうと、無職でも生活していけます。
実家に住むことで家族が生活にかかる固定費を払ってくれるため、必要な出費を減らせるからです。
また、パートナーの支援を受けながら家業に専念したり、不労所得を得たりすることも、無職で生活していく方法だと言えます。
貯金を切り崩しながら生活したり、野菜や家具を自作して生活に備えたりすることも可能ではありますが、どの方法も実現が難しい場合は公的支援に頼りましょう。
無職で生活していく方法を把握し、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
1. 実家で家族に支えてもらいながら生活する
無職で生活するためには、実家で家族に支えてもらう方法があります。
たとえば一人暮らしの場合には、どんなに食費を節約したり、移動を控えたりしても、家賃や光熱費といった固定費の支払いは毎月かかってきます。これは無職期間中にはかなり痛い出費となりますが、実家の場合、親などが固定費を支払ってくれれば貯金を減らさずに済むのは大きなメリットです。
また、仮にお金を借りるような場面になったとしても、親族であれば無利子で貸してくれることもあるかもしれません。もちろん仕事に早く就くことに越したことはありませんが、やむを得ず借金をする場合であっても、家族からの借り入れは消費者金融などからお金を借りるよりかは安心できるはずです。
2. 家業に専念する
無職で生活をするためには、パートナーや配偶者の収入をもとに、家業に専念する方法もあります。
収入面でのサポートではなく、家事や育児を担当して家庭に貢献する役割を果たせます。
一方で、家業に専念すると社会との関わりが少なくなるため、家族以外の人と接する機会が減るでしょう。
3. 不労所得を得ながら生活する
無職で生活するためには、不労所得を得る方法が挙げられます。
不労所得とは、自分が働かなくても得られる収入全般を指す言葉です。
不労所得を得る方法は、以下のとおりです。
- 株式投資で配当金を得る
- 不動産投資で家賃収入を得る
- 動画やブログの広告収入で稼ぐ
ただし、常に同じ利益を得られるかわからなかったり、収益化までに時間と労力がかかったりする点を考慮すると、リスクは大きいといえます。
たとえば、株式投資で運用すると最初に投資した金額より資産額が下回る「元本割れ」のリスクが発生しやすいと言われています。また、不動産投資の空室リスクや、動画・ブログの広告を見てもらえずに収入が減るリスクもあるため、注意が必要です。
4. 貯金で生活する
十分な貯金があれば、無職でも生活を維持することが可能です。
特に投資で生活費をまかなえる仕組みが整えば、FIREもあり得るでしょう。
FIREは経済的自立と早期退職を意味しており、働かなくても生活できることを指します。
一般的に、FIREに必要な貯金額は、年間支出の25倍が目安と言われています。
例えば、年間支出が300万円の場合だと、7,500万円が必要という計算になるでしょう。(300万円×25倍)
ただし、家族構成やライフステージ、インフレによる物価上昇などによって必要な貯金額が変わるため、あくまでも目安と認識しておくことが重要です。
5. 自給自足の生活を送る
自給自足の生活を送ることで、無職でも生活を成り立たせることは可能です。
自給自足とは、畑で野菜などを育てて自分で食べたり、家具を自作したりして、生活に必要なものを自分の手で手に入れる方法を指します。
一方で、食物の収穫までに時間がかかるうえ、農作業や家具の自作には専門知識が求められます。人付き合いが減りやすく、社会との接点が薄れてしまう点もデメリットと言えるでしょう。
また、自給自足生活でも税金は現金で払う必要があるため、どこかで現金を確保しなければなりません。
6. 公的支援を受けながら生活する
公的支援を受けると、無職でも生活をしていけます。なぜなら、公的支援は国民の命や生活を守るためのセーフティーネットの役割を果たしているからです。
無職が生活をするための公的支援として、以下の3つが挙げられます。
- 失業手当
- 生活困窮者自立支援制度
- 生活保護
それぞれの公的支援の特徴を抑えておくと、どの支援を受けられるかを判断できるでしょう。
無職生活に役立つ公的支援:失業手当
失業手当とは、雇用保険に加入していた労働者が離職した際、失業中の生活を心配せず再就職活動へ専念できるように支給される手当です。
条件は再就職の意思があることと、離職日以前の2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上あることです。
ただし、受給期間が「離職日翌日から1年間」と定められていたり、働いていた時と同額の失業手当がもらえたりするわけではないため、注意が必要です。
また、失業手当を受けるには、以下の手順に従う必要があります。
- ハローワークで求職申込みをする
- 雇用保険説明会に参加する
- 定期的に失業の認定を受け、再就職活動の報告をする
- 基本手当の支払いを受ける
失業手当の制度を理解しておくことで、スムーズな受給が可能です。
参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」
無職生活に役立つ公的支援:生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度とは、失業や収入源で生活が不安定になった人を対象に、自立を支援するための制度です。
支援内容は状況に応じて多岐にわたるため、生活再建の大きな助けになります。
生活困窮者自立支援制度の代表例は、以下のとおりです。
(参考:社会・援護局地域福祉課「生活困窮者自立支援法について」)
- 住居確保給付金
- 一時生活支援事業
- 就労準備支援事業
- 家計相談支援事業
- 学習等支援
特に住居確保給付金と一時生活支援事業は無職の生活サポートに直結する支援です。
ただし、住居確保給付金と一時生活支援事業は原則3ヶ月間だけしか受けられません。また、住居確保給付金は以下の要件を満たさないと受けられないため、注意が必要です。
(参考:厚生労働省「住居確保給付金」)
- 生計維持者が離職・廃業後2年以内である
- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていない
- 世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額を超えていない
- ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている
公的支援制度を受けるには、まずは各自治体の自立相談支援機関に連絡をし、相談することが重要です。
参考:一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク「自立相談支援機関 相談窓口一覧」
無職生活に役立つ公的支援:生活保護
無職の場合には、生活保護を受けることも視野に入ってくるかもしれません。
生活保護とは、収入を得る手段がほぼなく、さらにはお金を借りることすらできない、といった人を保障する制度です。
受給条件は高く設定されているため、誰でも受給できるわけではありません。ただし、もしもの時に使えれば無職の時期をなんとかやりくりできる可能性があるため、ピンチなときは受給条件に該当するかをまずは確かめてみましょう。
具体的には、次の4つの条件を満たすこと、さらには「世帯収入が最低生活費よりも少ない」といった条件をクリアすることで受給資格を得られます。
- 家や車、財産といった利用可能な資産を保持していないこと
- なんらかの理由で働けない環境であること
- 国からの公的融資や公的制度を利用していないこと
- 親や兄弟など、家族から援助を受けられない状況であること
参考:生活保護制度|厚生労働省
ただし、生活保護を申請すると、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。また、生活に必要なもの以外の所有は制限される点にも注意が必要です。
実際に生活保護を受ける場合、以下の手順に沿う必要があります。
- 地域の福祉事務所に事前相談をする
- 生活状況や資産、扶養の可否などの調査を受け、生活保護の申請をする
- 生活保護費が支給される
受給中は毎月の収入申告が必要となります。生活保護は誰でも受給できるわけではありませんが、無職で生活していくために、受給条件に該当するかを確認しておきましょう。
就活に悩んだら“就職カレッジ®”という選択肢も。
● 年間1000人以上のフリーターやニートの方が正社員に※
● 入社後のサポートも充実で安心
● ずーっと無料
▶ 詳しくは「就職カレッジ」で検索※2023年2月~2024年1月「就職カレッジ」参加者からの正社員未経験者就職決定人数
無職で生活するための3つの方法
無職で生活するための方法として、支出を抑えて節約する方法があります。
スマホを格安SIMに乗り換えたり、保険を見直したりすれば、生活に必要な資金を確保できるでしょう。
また、自分で稼ぐ力を身につけたり、誰かに生活を支えてもらったりする方法もおすすめです。無職で時間のあるうちにスキルを身につけて、仕事できる状態にしておくと心の安定につながるでしょう。
無職で生活していくための方法を理解し、自分の状況にあった方法を選択することが重要です。
1. 支出を抑える(節約する)
無職の時期を切り抜けるために真っ先に考えたいのが、節約です。
特に「大きな支出を削れないか」を先に考えてみてください。
節約と聞くと、多くの人は「少しでも安い野菜を買う」「電気はこまめに消す」といったことを考えますが、これらが家計に与える影響は微々たるものです。
一方で、たとえば次のような節約は家計に与えるプラスの効果が大きく、1日あれば完結できる方法もあるので、まずは優先して取り組んでみましょう。
- スマホを格安SIMに乗り換える
- 保険を見直す
- 引っ越しを考える
2. 自分で稼ぐ力を身に付ける
自分で稼ぐ力を身に付けることも、無職の期間を安心して過ごすために意識したいポイントの一つです。
たとえば「動画編集」の場合には、スキルアップのための多くの情報が無料で公開されています。初心者向けの情報も多いので、時間がある無職期間中にこうしたスキルを身につけ、仕事を請け負える状態にしておくと心の安定にもつながります。
また、ハローワークの「職業訓練」を受けることも検討してみましょう。
受講する場所によって異なりますが、たとえば「電気設備管理」「介護サービス」といった仕事の基礎スキルを実質無料で身に付けられるため、転職先を探すうえでもプラスに働くはずです。
3. 誰かに支えてもらう
無職期間中は、誰かに支えてもらうことも考えたいところです。
お伝えのとおり、実家で暮らせれば貯金を大きく減らさずに過ごせるでしょうし、場合によっては結婚をして専業主婦(夫)になる手も考えられます。
人によっては、誰かのサポートを受けることに心苦しさを感じてしまうかもしれませんが、一方で貯金が減っていく現実を前にして、そうも言っていられないことも多いはずです。
困窮している姿を見るほうが周りとしては心配になるかもしれないので、「困った時はお互い様」とある意味開き直り、誰かの支えを受けることも視野に入れてみると良いでしょう。
無職は不安という方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
無職生活を続けると起こりやすい4つのリスク
無職生活を続けていると、就職が難しくなるリスクが生じます。
実際に、ニート歴が1年未満の方より5年を超えている場合の方が、就業できない割合が高くなるというデータがあるからです。
また、やりたいことが制限されるリスクもあります。
無職だと収入がないため、自由に使えるお金が制限されてしまうからです。
社会的なつながりが薄くなったり、住む場所に困りやすくなったりするリスクもあります。
無職生活を続けるリスクを把握し、今自分に何ができるかを考えて行動していきましょう。
1. 就職が難しくなる
無職生活を続けると、就職が難しくなるリスクが高まります。
実際に、以下の表のようにニート歴が長くなると就業できなかった割合が増えるデータもあります。
| 1年以下 | 1年超〜3年以下 | 3年超〜5年以下 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 就業した | 44.2% | 45.1% | 50.7% | 42.3% |
| 就業できなかった | 30.2% | 35.2% | 31.9% | 42.3% |
参考:財団法人 社会経済生産性本部「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究報告書」
働いていない期間が長くなればなるほど、就職は難しくなりやすいので、できるだけ早めに仕事に就くようにしましょう。
また、20代のうちは将来性を重視するポテンシャル採用を実施してくれる企業も多くありますが、30代になると即戦力重視になりやすい点も押さえておく必要があります。
「30代からでは遅いかも」と落ち込むのではなく、1日でも早く正社員を目指して就職活動などの行動をすることが大切です。
2. やりたいことが制限される
無職生活を続けていると、やりたいことが制限されるリスクが生じます。
なぜなら、収入がないため自由に使えるお金が限られてしまうからです。
たとえば、旅行や趣味、習い事といった日常的な楽しみも、経済的な理由で我慢せざるを得なくなります。
また、資格取得やスキルアップのための学習にも費用がかかりやすいため、将来に向けた自己投資すら難しくなるケースもあります。
やりたいことを実現するためにも、早めに収入源を確保する行動を取ることが大切です。
3. 社会的なつながりが薄くなる
無職生活を続けると、社会的なつながりが薄くなるリスクが生じます。
仕事などで関わる人がいなくなり、家族やオンライン上での知り合いなど、限られた人としか関わる機会がなくなるためです。
よく遊んでいた友人と連絡を取り合うこともできますが、友人が働いていれば仕事やキャリアの話などについていけなくなり、疎外感を覚えてしまう可能性もあります。
結果的に孤独感が強くなり、精神的に不安定になってしまう可能性もあるため、無職生活の継続には注意が必要です。
4. 住む場所に困りやすくなる
無職生活が長引くと、将来的に住む場所に困りやすくなるリスクが生じます。
親が亡くなった後も実家に住み続けるには、実家の相続が必要です。
しかし、相続した後にも相続税や固定資産税、水道光熱費などを支払わなければなりません。
仮に親の遺産があったとしても、税金の支払いでお金がなくなってしまう可能性もあります。
また、実家を相続しない場合、賃貸物件を借りようとしても、収入がない無職の状態では入居審査が厳しくなってしまうこともあります。
住む場所に困らないためにも、早めに就職するなど対策を打つ必要があります。
無職から社会復帰を目指す4つの方法
無職から社会復帰を目指すには、まずは規則正しい生活に戻すことが重要です。
無職だと生活習慣が乱れて夜型の生活リズムになりがちなので、まずは昼型の生活リズムに戻しましょう。
また、働くために必要なスキルの習得も社会復帰にはおすすめです。
基本的なPCスキルやコミュニケーション力など、職業訓練校などで習得しましょう。
実際に行動をすると、以下の表のように、1年前に無業者だった方が1年後に正社員になることも可能です。
| 15〜34歳の男性計 | 15〜34歳の女性計 | 15〜34歳の男女計 | |
|---|---|---|---|
| 正社員になった割合 | 18.3% | 17.4% | 18.0% |
男女ともに、2割弱の人が正社員になって社会復帰を果たしています。
社会復帰を目指すためにできることを考え、行動していきましょう。
参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状 ③」
1. 規則正しい生活に戻す
無職から社会復帰を目指すには、規則正しい生活に戻すことが重要です。
まずは生活習慣や心身の状態を整えることから始めましょう。
規則正しい生活を送るためには、睡眠の質を上げることが重要です。
睡眠の質向上に向けて具体的に実施できることは、以下のとおりです。
- 日中にできるだけ日光を浴びる
- 寝室にはスマホなどを持ち込まない
- 寝室の温度を整える
- 就寝1〜2時間前に入浴して身体を温める
- できるだけ静かな環境を作る
- リラックスできる着衣や寝具で眠る
環境を整えると睡眠の質を向上できるため、規則正しい生活を送りやすくなるでしょう。
参考:健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会「健康づくりのための睡眠ガイド 2023(案)」
2. 働くために必要なスキルを習得する
無職から社会復帰を目指すには、働くために必要なスキルの習得が重要になります。
新しい知識や技術を身につけることで就業に対して前向きであると伝えられたり、働いていない期間は勉強していたと伝えられたりするためです。
無職の人が働くために身につけるスキルとしては、以下の3つがおすすめです。
- 基本的なPCスキル
- 英語力
- コミュニケーション力
スキルの習得には、お金があればどこかのスクールに通いましょう。
一方で、金銭的に余裕がない場合は、職業訓練校に通うことをおすすめします。
職業訓練校とは、スキルを身につけられるだけでなく、要件を満たしていれば月10万円の給付金をもらえる場合があります。
職業訓練校はハローワークを通じて申し込みができるため、習得したいスキルが学べるかを確認したうえで受講を検討しましょう。
参考:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
ニートがとった方がいい資格は?
ニートから就職を目指す際は、基礎的で取得しやすい資格を選びましょう。
特に、ITパスポートやMOS、介護職員初任者研修は未経験でも挑戦しやすく、就職活動でもアピールできます。
それぞれの資格の特徴は、以下の表のとおりです。
| 資格名 | 特徴 | 活かせる分野 |
|---|---|---|
| ITパスポート | ITの基礎知識を証明できる国家資格 | 事務、IT業界 |
| MOS | Word・ExcelなどPCスキルを証明可能 | 事務、営業サポート |
| 介護職員初任者研修 | 介護職の入門資格 | 福祉・介護業界 |
まずは目的に合いつつ習得しやすい資格から挑戦し、就職活動でアピールできる材料を増やしていきましょう。
3 .短期・単発バイトで働いてみる
無職から社会復帰を目指すには、短期・単発バイトで働くことが有効です。
なぜなら、無職からいきなり正社員を目指すのはハードルが高いため、まずは働くことに慣れることが重要だからです。
短期間の勤務であれば体力的・精神的な負担も少なく、労働に慣れていくことができます。
また、さまざまな職種を経験することで、自分に合った仕事を見つけるきっかけにもなるでしょう。
無職から正社員就職を目指す前のステップとして、まずは短期・単発バイトから働き始めましょう。
4. 無職に理解のある就職支援サービスを使う
無職から社会復帰を目指すには、就職支援サービスの利用がおすすめです。
無職に理解のある就職支援サービスであれば相談しても怒られる心配がないため、悩みを打ち明けやすい特徴があります。
おすすめの就職支援サービスとして、ハローワークや地域若者サポートステーション、就職エージェントの3つが挙げられます。
それぞれの特徴は、以下の表のとおりです。
| サービス | 特徴 | おすすめの理由 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 公的機関であり、全国に窓口があるため対面で相談可能 | ・地元に特化した求人を多数保有している ・公的機関なので、失業手当などの手続きも行える |
| 地域若者サポートステーション | 若者に特化した就労支援機関 | ・無職やニート経験者に特化した相談やセミナーが充実している |
| 就職エージェント | 民間が行う就労支援サービス | ・専任のアドバイザーが個別に求人紹介や面接対策など、就職活動の一連の工程をサポートしてくれる |
それぞれの就職支援サービスの特徴を抑え、自分に合ったサービスを利用しましょう。
無職に向いている仕事は?
無職に向いている仕事として、介護職と工場作業員が挙げられます。
介護職は、介護が必要な人に対して身体介護や生活援助など、身の回りをサポートする仕事です。介護職は人手不足の影響で需要の高い職種であるため、未経験であっても挑戦しやすい特徴があります。
工場作業員は、工場内で製品の製造に携わる仕事です。マニュアルが整備されていることが多く、特別なスキルや経験がない状態からでも仕事に就きやすい特徴があります。
また、正社員だけでなく期間工や派遣社員、パートなど働き方が豊富であるため、働くことに慣れる目的でも適しているでしょう。
その他の無職に向いている仕事については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
無職で生活する際によくある質問2選
無職で生活をする際によくある質問について、以下で2つ解説します。疑問点の解消に役立ててください。
総務省が公表しているデータによると、無職で生活するためには、1ヶ月で16万3,417円が必要とされています。このデータは、無職の世帯における1ヶ月の消費支出(14万2,540円)と非消費支出(2万877円)の合計です。
消費支出は日常生活を送るために必要なものやサービスに使う費用を指し、非消費支出は税金や年金など、支払う義務のある費用を指します。
ただし、あくまで平均値であるため、自分の生活スタイルに合わせて必要な金額を試算することが重要です。
参考:総務省「家計調査報告(家計収支編)2025年(令和7年)6月分及び4~6月期平均」
無職で一人暮らしをすると、家賃や生活費の支払いが困難になるため、やばいといえます。貯金が尽きてしまえば住まいを失うリスクもあります。また、新規に住居を借りようとしても、収入がなければ賃貸契約の審査も厳しくなるでしょう。
やばい状態を避けるためには、アルバイトや正社員就職で収入を得たり、公的支援を活用するといった早めの対策が重要です。
まとめ
「無職でもなんとかなる」という理由、そして方法をお伝えしてきました。
無職になってしまうと、どうしてもお金の不安などが頭に浮かんでしまいますが、その不安にだけ引きずられ、肝心の「再就職」に対する意欲がそがれてしまうようでは本末転倒です。
一方でいったん冷静になり、周りを見渡してみると、実は手に入るサポートなどに気づくはずです。
もちろんサポートに頼り切ってしまうと、それはそれで再就職へのモチベーションが下がってしまう可能性はありますが、ある程度「なんとかなる」と割り切り、使えるものは使っていく、と考えたほうが心の安定を図れることは多いものです。
お伝えした内容を踏まえ、無職の期間をなんとか乗り越えていきましょう。