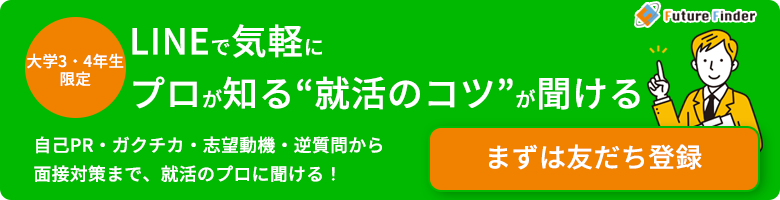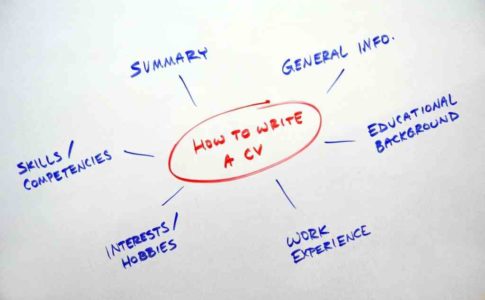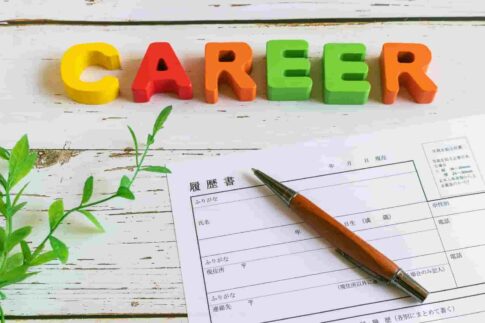「社風ってそもそもなに?」「社風の良い企業で働きたい」と企業選びのときに考える就活生は多くいます。社風とは企業における独特の雰囲気のことで、同じ業界や職種であっても、企業によって大きく異なっています。この記事では、そもそもなぜ社風を知ることが大切なのか、どんな社風があるのかの具体的な事例、企業の規模ごとの社風の傾向、志望動機を社風で伝えるときの注意点などを解説しています。 「自分に合っている社風の企業で働きたい!」と考えている就活生は、この記事を最後まで読んで自分に合う社風の企業を見つけられるようにしていきましょう。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
この記事の目次
なぜ社風を知ることが大切なのか?
会社の雰囲気や働く環境(社風)を知ることは、自分が就職する企業で働く上で大切な要素になります。
就職する企業の社風を知ることで、自分にとって合った働き方や環境かどうか見極められます。また、社風によって自分のやる気や仕事への取り組み方に影響を与えることもあります。自分に合わない職場の雰囲気だと、モチベーションの低下に繋がりやすく仕事の成果にも影響が出てしまうことも起きてしまうのです。
自分自身が楽しく働けて、自分の力を発揮しやすい環境かどうかを判断するためにも、志望する企業の社風は調べておくと就職活動がうまくいきやすくなります。さらに、働き始めてからも充実した社会人生活が送りやすくなります。
社風とは

社風とは何を指すのか、企業によくある社風の例、企業規模による社風の傾向などについて知りましょう。
社風の概要
社風とは、そこで働いている従業員が感じる雰囲気の特徴のことをいいます。各企業が持っている独自の雰囲気や価値観、と言い換えてもよいでしょう。
会社を人間に例えると、社風は人柄と考えることができます。例えば「真面目である」「積極的に何にでも取り組む」というような性格と「仕事よりプライベート優先」「広く浅くよりも、自分の強みをとことん追求する」などの価値観が絡み合うことで人柄が生まれます。
社風は、企業の雰囲気のことです。そのため、企業を構成する社員や企業理念から大きな影響を受けます。空気感と言い換えることもできることから分かるように、感覚的な要素がとても大きく、人によって感じ方に違いが現れるのも大きな特徴です。
曖昧で明確に定義することが難しい要素ですが、社風は、企業選びをしたり採用選考を受けたりして社員になろうとしている就活生にとって、その企業が働きやすいかどうかを判断する大きな判断基準となります。
企業の社風の例
具体的な社風としては、以下のようなものが挙げられます。
- 風通しがよく意見が言いやすい
- チームが団結してプロジェクトに取り組む
- 個々が独立して仕事を行う
- 個人の能力や実績を重視する
- 結果だけではなく、努力や過程なども評価する
- 伝統を重視する
- 新しいことに積極的にチャレンジする
- アットホームな雰囲気
- 上下関係が厳しく年功序列
もちろんこれらの社風は独立しているものではなく、企業ごとに組み合わさったり、程度に差があったりします。
例えば「伝統を重視する」社風と「新しいことに積極的にチャレンジする」社風は一見すると反発していて両立することはないように見えます。
しかし、実際には「伝統を重んじつつ、新しいチャレンジも大切にしている」というように、中間的な社風の会社もたくさん存在するのです。また「新しいチャレンジも重視するが、あくまで会社の重視する伝統を逸脱しない範囲で」というように条件がついていることもあります。
「上下関係が厳しい」と聞くと、縦の関係がガッチリできあがっていて、下の人間は上の人間に逆らえないような会社をイメージするかもしれません。しかし例えば、上下関係はある程度きっちりしているが風通しはよく意見も言いやすい、などの企業も存在します。
単純な言葉で言い表すことができないというのが社風の特徴であり、読み解くのが難しいポイントでもあるといえるでしょう。
企業規模による社風の傾向
社風は企業によって異なりますが、ある程度の傾向は存在します。企業規模ごとの社風の違いについてご紹介します。
大企業の社風
大企業は多種多様の大勢の人達が働いていることから、ある程度会社全体の価値観やルールが決められていることが多いです。そうしないと、大勢の人がひとつの目標に向かって働くことが難しくなってしまうからです。
企業に資産があり社会的信頼が厚いので、それを崩すまいとする意識も働きます。そのため、個人の考えや自由なルールは通りにくくなるので、チャレンジ精神の強い人や新しい発想をどんどん取り入れたいという人は、窮屈で働きづらいと感じてしまうかもしれません。
個人の実績も見えづらく、人数が多いために人間関係がシビアで、競争相手も多くなります。当然働く人数に応じて部署も増えるので、コミュニケーションにいろいろな壁を感じるという人も少なくありません。
中小企業の社風
中小企業は、良くも悪くもトップの考え方や価値観が社風に強く影響するという特徴があります。これにより、トップと同じ考え方や価値観を持っている人、方針に共感できる人は働きやすくなります。
逆に、トップと真逆の考えを持っていたりすると、仕事がやりにくい可能性が高いです。
人数が少ないことからアットホームでコミュニケーションが取りやすく、チームワークを重視する環境になることが少なくありません。大手企業に比べると人数が少なく規模も小さいため、競争相手が少なく出世しやすい環境であるといえます。。
ベンチャー企業の社風
ベンチャー企業の企業規模は小規模から中規模であることが多く、新規に起業しているので企業や事業の歴史が浅いというのも特徴のひとつで、社員数が少ないため意思決定が早いという特徴があります。
少人数であるが故に経営者との距離が近くなりがちで、トップの人柄や価値観が自分に合うかどうかも大きなポイントになるでしょう。個人の仕事の範囲が大きく、個人の裁量で自由度の高い進め方ができるのも大きな特徴です。ただし、決まったルール内で働きたい人にとっては、何をしたらいいのかわからなくなる可能性が高くなります。
変化が多く、突然事業体制や組織体制が変わってしまうことも珍しくないため、安定志向が強く変化が苦手な人はスピード感についていけなくなる可能性も出てきます。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
社風が良い企業を見つける方法
OB訪問をする
OB訪問は、その企業で働いている社会人に会い、その会社の雰囲気や働き方を知る方法です。志望企業で働いている方の話を聞くことで、実際の職場の様子などの社風を具体的に把握できます。インターネットで検索した情報とは異なり、リアルな情報を得られるため、先輩の率直な意見や実際の体験談から、その会社の社風を具体的にイメージしやすくなります。最近では、OB訪問専用のアプリも普及しているので、気になる方は検索してOB訪問をおこなってみることをおすすめします。
面接官に質問する
面接では、自分がその会社に合っているかを知るために、積極的に社風に関する質問をすることが重要です。チームワークや会社の価値観について質問することで、会社の雰囲気や特徴を知る手がかりを得ることができます。例えば、自分がチームで協力することを重視している場合「チームワークを重視している風土はどのように育まれていますか?」と質問することで、会社のチームワークの取り組み方を知ることができます。そのため、自分の大切にしている価値観を基にした質問をして、志望企業の社風を把握してみてください。
自己分析をする
自分に合った社風を見つけるためには、自己分析も非常に重要です。自己分析を怠ると、何となく興味を持った社風の企業を選ぶことになり、後で「本当に自分に合う企業なのか?」と疑問を抱くことになります。まずは、過去に所属していた部活動やアルバイト先を振り返ってみましょう。自分が居心地が良かった点や環境の共通点を見つけ、なぜそう感じたのかを考えてみてください。自分らしくいられる就職先や自分が力を発揮しやすい環境に合った社風を見つけることから始めてみるのがおすすめです。
企業選びや面接の前に知るべき社風のポイント

次は、社風のいい企業とはどのような企業なのかについて解説します。社風が良い企業の特徴を知り企業選びの参考にしてみてください。
社風のいい企業とは
「社風がいい働きやすい企業に入りたい」というのは、誰しもが思うことではないでしょうか。しかし、社風に良し悪しは存在しません。というのも「いい社風」というのは人によって異なるからです。
たとえば「アットホームな雰囲気」というのは一見すると万人に向いた社風のように感じますが「オンオフをしっかりと分けたい」「プライベートなことを職場に持ち込みたくない」という人にとっては、逆に働きにくい環境になってしまう可能性があるのです。
つまり、社風のいい会社は、自分がどんな企業で働きたいのか、自分にとって働きやすい環境はどんなものかをしっかり理解してからでないと見つけることができません。まず社風を調べる前に、自己分析にしっかり取り組み、仕事における自分の軸を見つけることが大切になります。
社風を志望動機として伝えるときの注意点
社風を志望動機に盛り込む就活生も少なくありませんが、伝える際は以下のような点について注意が必要です。
オリジナリティある内容を意識する
まず「社風に惹かれた」というだけでは他の応募者と被ってしまい印象に残らない可能性も高いことを覚えておきましょう。
具体的でオリジナリティがある志望動機を語るには、社風のどの点に共感したのか、自分の価値観や考えとの関連性はどこか、といったことと絡めるようにするのがおすすめです。社風だけを志望動機にするのではなく、企業理念や事業内容なども盛り込み、そこと関連付けて離せるようにすると説得力が増します。
社内の部署によっても雰囲気は変わる
面接で社風を志望動機として挙げるなら、他にも気をつけるべきポイントがあります。まず社風はひとつではなく、社内のチームや部署ごとにも存在します。
例えば、開発部の社風と営業部の社風は、行っている業務や目的、働く人の特性や仕事の進め方なども大きく違うからこそ、同じ会社でも同じ雰囲気というわけではないでしょう。
そのため社風を志望動機として盛り込むのであれば、自分が志望する部署の社風を知らなければなりません。
社風は不変ではない
社風は、企業の目指す方向やそこで働く人材によっても大きく変わります。企業の方向性が変化した、新しい人が入ったまたはそこで働いている人が離れたなどの理由から、職場の空気が大きく変わることも珍しくありません。
そうしたことからも、社風だけを志望動機として挙げるのは避けた方がよいでしょう。もしかしたら、自分自身が社風を大きく変化させる人材になる可能性すらあるのです。
社風に正解はない
「こういう社風が正しい」というような正解は存在しません。そのため、企業の面接で社風について語るときは社風の良し悪しではなく「自分に合う・合わない」という観点で語る必要があります。ここを間違えてしまうと、社風について勘違いしていると見られて評価が下がってしまう可能性が出てきます。
また、社風には合う合わないが存在することを理解していないと、入社後にコミュニケーションロスを起こすリスクが高くなり、ミスマッチから早期離職に繋がってしまう可能性も大きくなるので注意が必要です。
【番外編】企業が社風をアピールする理由
企業が自社の社風のアピールを積極的にすることには、以下のような理由が存在します。
早期離職を防ぐため
早期離職は、企業にとって頭の痛い問題です。せっかくお金と時間をかけて獲得した新入社員なのに、早々に退職されてしまっては企業にとって大きなロスになってしまいます。早期退職の原因は様々ですが「入社後に自分にこの企業は合わないと気付いた」というのもひとつの理由です。
社風に良し悪しはなく、問題は「その人に合うか合わないか」ということだけです。企業側から「自社はこんな雰囲気の会社です」と積極的にアピールすることで、応募者に判断基準を提供し、早期離職を防ごうとしているのです。
ブランディングのため
優秀な応募者を獲得するためには、競合他社との違いを明確に打ち出さなければなりません。とはいえ、他社にはない唯一無二の特徴を持っている企業というのは少ないものです。
そんなとき、社風は他社との差別化を行うひとつの材料になります。同じ業種、似たような業務内容や企業理念であっても、社風まで全く同じという企業はそうありません。社風をアピールすることで、自社のブランディングを行うことができるのです。
これは、応募者にとっても役立ちます。同じ業種内で就職活動を行う際「社風に魅力を感じて」と伝えることができれば、深く企業研究を行ったことやその会社を志望する熱意を強く面接官に伝えることができるのです。
コミュニケーションロス減少や生産性向上のため
コミュニケーションロスとは、意思疎通がしっかりと行えないことから生じる損失や無駄のことです。特に新入社員が陥りやすく「先輩に声をかけるタイミングがわからない」「もっと詳しく聞きたいのに迷惑かもしれないと思い聞くことができない」など、コミュニケーションが上手く取れないが故に、仕事が上手く回らなくなってしまうのです。
コミュニケーションロスが発生する原因は様々ですが、職場の雰囲気に馴染めず、他の従業員と親密性が保てていないというのはそのひとつです。応募の段階で社風をアピールし、応募者に働きやすい環境か判断してもらうことは、企業側にとって労働生産性を向上させる大切な要素なのです。
社風を理解してミスマッチをなくそう!
社風は言葉にするのが難しい概念で正解が存在しないため、就活生にとっては理解しにくく感じることも多いかもしれません。しかし、社風はその職場で働く上で無視できないものでもあります。社風をしっかりと理解することは、企業と就活生がお互いにミスマッチをなくすことにもつながります。自己分析を徹底したうえで企業の社風を研究することで、自分に合った環境の企業を見つけることができるでしょう。
※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
⇓⇓26卒・27卒の方はコチラ⇓⇓