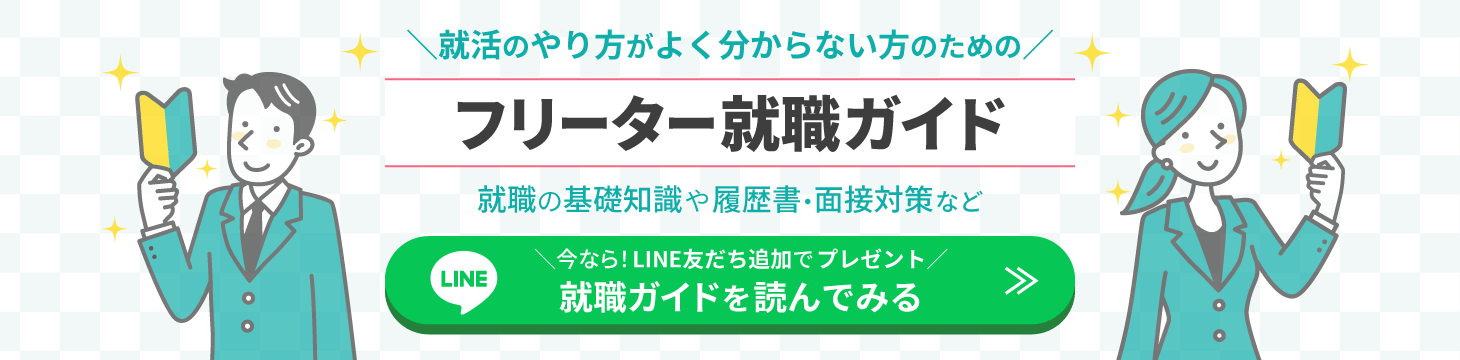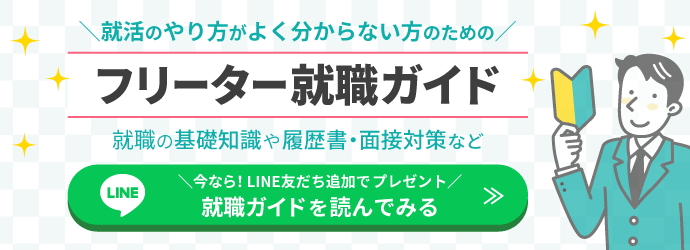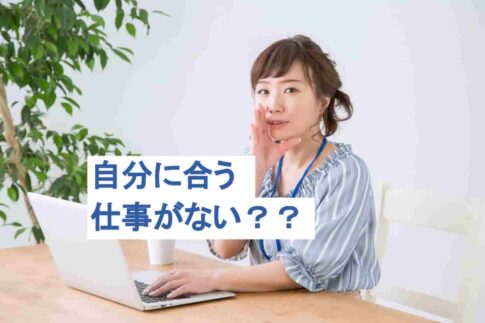社会福祉士になるには高卒でも問題ありません。なぜなら、実務経験や福祉系の専門学校・短大・大学の卒業などを通じて、受験資格を得るルートが複数用意されているからです。
社会福祉士になるには、国家試験である「社会福祉士国家試験」に合格する必要があります。その上、試験を受ける受験資格も必要です。
受験資格を得るには、さまざまなルートがあるので、自分に合った方法を選んで経験や学習を積む必要があるでしょう。
この記事では、高卒から社会福祉士になるための最短ルートや最新の受験資格情報などを紹介します。
社会福祉士として働きたいけれど、学歴や経験に不安がある方はぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
社会福祉士になるには高卒でも大丈夫!
社会福祉士になるには高卒の学歴でも問題ありません。
身体的・精神的・経済的なハンディキャップを抱えた人の悩み事を支援する社会福祉士は、近年福祉的な問題が注目される中で活躍が期待されています。
ここでは、高卒が社会福祉士になるための概要について解説します。
社会福祉士に合格する必要がある
社会福祉士を名乗って働くためには、国家試験である「社会福祉士国家試験」に合格する必要があります。
社会福祉士は「名称独占」の国家資格になりますので、医者や看護師といった「業務独占(資格保有者しかその業務に従事できない)」とは異なり、資格を保有していなくても社会福祉士の仕事は可能です。
しかし、社会福祉士と名乗って働き、キャリアを歩んでいくためには、社会福祉士の資格を保有しなければいけません。
受験資格が存在する
社会福祉士国家試験には12パターンの受験資格が存在します。
それぞれの組み合わせで年数は異なりますが、大きく分けると以下の5パターンに分かれます。
- 福祉系の4年制大学で指定科目を履修して卒業する
- 福祉系の短大で指定科目を履修して卒業後、1〜2年の相談補助実務に携わる
- 非福祉系4年制大学を卒業後、一般養成施設で1年以上学習を行う
- 非福祉系短大卒業後、1〜2年の相談補助実務に携わった後に、一般養成施設で1年以上学習を行う
- 相談補助実務に4年間携わった後に一般養成施設で1年以上学習を行う
上記のうち、高卒の場合は最後の条件を満たすことで受験資格を満たすことができます。
また、全ての条件を見てみて分かる通り、社会福祉士を目指すのであれば指定された教育機関での学習が必要となりますので、専門的な知識を求められる資格であると言えるでしょう。
受験資格について詳しく知りたい人は「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター:社会福祉国家試験」のページをご覧ください。
社会福祉士国家試験の試験概要
社会福祉士国家試験について、受験資格だけでなく試験そのものの概要を、令和6年度試験の情報を元にまとめました。
| 試験頻度 | 年一回 |
| 試験科目 | 医学概論 心理学と心理的支援 社会学と社会システム 社会福祉の原理と政策 社会保障 権利擁護を支える法制度 地域福祉と包括的支援体制 障害者福祉 刑事司法と福祉 ソーシャルワークの基礎と専門職 ソーシャルワークの理論と方法 社会福祉調査の基礎 高齢者福祉 児童・家庭福祉 貧困に対する支援 保健医療と福祉 ソーシャルワークの基礎と専門職(専門) ソーシャルワークの理論と方法(専門) 福祉サービスの組織と経営 |
| 合格基準 | ①:総得点の60%を基準に補正後の点数以上の得点を獲得した人 ②:①を満たしている人の内、試験科目の全てで得点があった人上記①②をどちらも満たした場合に合格となる |
| 受験資格 | 記事内の「試験概要」を参照 |
| 受験手数料 | 19,370円 |
| 合格率 | 受験者総数9,588名 合格率60.1%(令和6年実施実績) |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験 過去の試験問題」
試験科目や合格基準からも分かる通り、社会福祉士になるには19もの幅広い分野の勉強をする必要があります。
また、合格率は6割前後で、出題範囲が広いですが半数以上の合格者がいるとわかります。計画的に勉強すれば、十分に合格できる国家資格と言えるでしょう。
なお、社会福祉士の試験科目は法改正が頻繁に行われるため、古い参考書を使っていると情報が誤っている可能性があります。
勉強する際は、常に最新の参考書を活用しましょう。
社会福祉士になるための流れ
社会福祉士国家試験に合格するだけでは、社会福祉士を名乗って業務を行うことはできません。
試験に合格した後に「社会福祉士登録申請」を行うことで、正式に社会福祉士として登録され、仕事に取り組めるようになります。
ちなみに、社会福祉士として登録されている人数は、厚生労働省の公表によると250,346人(令和2年9月末時点)となっています。
高卒で社会福祉士の受験資格を得るルート5選
高卒で社会福祉士の受験資格を得るルートは以下のとおりです。
| ルート | 受験資格を得るまでの年数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1.4年制の福祉系大学を卒業 【最短ルート】 | 4年 | 実務試験不要で受験資格が得られる。 |
| 2.福祉系の短大・専門学校を卒業 | ・3年通学+1年相談援助実務 ・2年通学+2年相談援助実務 | 卒業後に相談援助業務の実務経験が必要。 |
| 3.社会福祉主事養成機関を卒業 | ・通学+2年相談援助実務+6ヶ月以上短期養成施設で学習 | 社会福祉主事の資格が取得でき、就職の幅が広がりやすい。 |
| 4.特定の実務経験を積んでから短期養成施設で学習 | ・4年間特定業務に従事+6ヶ月以上短期養成施設で学習 | 福祉に関する幅広い就業スキルが身につく。 |
| 5.相談援助の実務経験を積んでから養成施設で学習 | ・4年相談実務+1年以上一般養成施設で学習 | 相談援助の実務経験を積みながら資格取得を目指せる。 |
自分の学歴・実務経験を整理して、どのルートが現実的に目指しやすいかを考えてみてください。
1. 4年制の福祉系大学を卒業【最短ルート】
実務経験のある高卒の方は、4年制の福祉系大学を卒業すると最短で受験資格を得られます。
ただし、指定科目を履修できる大学を卒業する必要があります。
指定科目とは「社会福祉士国家試験の受験資格」を得るために履修が求められる科目のことで、具体的には以下のような科目があります。
- 医学概論
- 社会福祉の原理と制作
- 高齢者福祉
参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験 試験科目」
もし指定科目を履修しないまま卒業した場合は、大学卒業後に短期養成施設で6か月以上学ばなければならないので注意しましょう。
また、高卒が大学を卒業すると、実務経験不要で社会福祉士の受験資格が手に入るメリットがあります。
一方で、大学へ通うとなると学費がかかってしまうのがデメリットです。具体例として、関西福祉大学の学費を以下の表にまとめました。
| 学部 | 社会福祉学科 | 社会福祉学科 |
|---|---|---|
| 年次 | 1年次 | 2~4年次 |
| 年額 | 121万円 | 115万円 |
大学へ通う費用を用意できる、最短で社会福祉士の受験資格を得たい人は、福祉系大学への進学が向いているでしょう。
なお、通信制の大学を選べば働きながら学べます。ただし、27日間の実習に参加する必要があり、まとめて休みを取る必要がある点に注意してください。
2. 福祉系の短大・専門学校を卒業
高卒で社会福祉士の受験資格を得るには、福祉系の短大・専門学校で指定科目を履修して卒業するルートがあります。
この場合は、卒業後に以下のように相談援助業務の実務経験を積まなければならず、トータルで4年くらいの期間になるでしょう。
- 2年制の学校なら相談実務が2年
- 3年制の学校なら相談援助実務が1年
参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験 受験資格(資格取得ルート図)」
なお、指定科目を履修しないまま卒業した場合は、相談援助実務に加えて短期養成施設で6ヶ月間以上学ばなければなりません。この場合は、トータルで4年半以上の期間がかかります。
また、高卒が福祉系の短大・専門学校を卒業すると大学よりもお金がかからないというメリットがあります。
一方で、卒業後に実務経験を積まないといけないので受験資格を得るまでに時間がかかるのがデメリットです。
通信制だと働きながら学べますが、実務未経験であれば実習が必要になるため、まとまった休みを取らなければいけません。
時間をかけても計画的に学べる人が向いているルートと言えるでしょう。
3. 社会福祉主事養成機関を卒業
高卒が社会福祉士の受験資格を得るルートとして、社会福祉主事養成機関を卒業する方法があります。
社会福祉主事養成機関とは、社会福祉に関する資格の中で最も古い資格である社会福祉主事を養成するための施設です。
全国に76校あり、具体的には以下のような施設があります。
- 札幌社会福祉専門学校 教育社会福祉専門課程保育福祉科
- 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
- 九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
社会福祉主事養成機関を卒業したあとは、相談援助実務2年、短期養成施設で6ヶ月以上の学びが必要です。
養成機関での学習期間も合わせると、トータルで4年半〜5年半ほどかかるでしょう。
このルートは、社会福祉主事の資格が取得でき、就職の幅が広がりやすいのがメリットです。一方で、社会福祉士の受験資格を得るまでに時間がかかるのがデメリットと言えます。
時間がかかっても社会福祉についてしっかり学びたい人に向いているでしょう。
4. 特定の実務経験を積んでから短期養成施設で学習
高卒が社会福祉士の受験資格を得るには、特定の実務経験を積んでから短期養成施設で学習するルートがあります。
たとえば、以下のような職種が実務経験の対象となります。
| 職種 | 仕事内容 |
|---|---|
| 児童福祉司 | 虐待や貧困などの課題を抱える子どもと家庭を支援する。 |
| 身体障害者福祉司 | 身体障害者の福祉に関する相談対応や自立支援医療の要否判定を行う。 |
| 査察指導員 | ケースワーカーの指導監督を行う。 |
| 知的障害者福祉司 | 知的障害者の福祉に関する相談対応を行う。 |
| 老人福祉指導主事 | 高齢者福祉に関する情報提供や相談対応などを行う。 |
高卒が上記のような実務経験を積むと、福祉に関する幅広い就業スキルを身につけられるのがメリットです。
一方で、上記の実務経験を積むには社会福祉主事の資格が必要な場合が多く、社会福祉士になるには遠回りになってしまうのがデメリットです。
実際に現場で実務を経験しながら学んでいきたい人に向いているルートと言えるでしょう。
5. 相談援助の実務経験を積んでから養成施設で学習
高卒で社会福祉士の受験資格を得るルートの一つに、相談援助の実務経験を積んでから養成施設で学習する方法があります。
この方法では、相談援助の実務を4年積んでから、一般の養成施設で1年以上学ぶ必要があるのでトータル5年以上かかります。
時間はかかりますが、社会福祉士を取得する前に、実際の現場で相談援助の就業経験を積みたい人などに向いているルートです。
実務経験として認められる相談援助の内容は以下のとおりです。
児童分野
| 児童分野の施設種類 | 職種 |
|---|---|
| 児童相談所 | ・児童福祉司 ・受付相談員 ・相談員 ・電話相談員 ・児童心理司、心理判定員 ・児童指導員 ・保育士 |
| 児童養護施設 | ・児童指導員 ・保育士 ・個別対応職員 ・家庭支援専門相談員 ・職業指導員 ・里親支援専門相談員 |
| 母子生活支援施設 | ・母子支援員、母子指導員 ・少年指導員(少年を指導する職員) ・個別対応職員 |
| 児童心理治療施設 | ・児童指導員 ・保育士 ・個別対応職員 ・家庭支援専門相談員 |
| 児童自立支援施設 | ・児童自立支援専門相談員 ・児童生活支援員 ・個別対応職員 ・家庭支援専門相談員 ・職業指導員 |
高齢者分野
| 高齢者分野の施設種類 | 職種 |
|---|---|
| 指定介護老人福祉施設 | ・生活相談員 ・介護支援専門員 |
| 介護老人保健施設 | ・支援相談員 ・相談指導員 ・介護支援専門員 |
| 指定特定施設入居者生活介護を行う施設 | ・生活相談員 ・計画作成担当者 |
| 指定複合型サービスを行う施設 | ・介護支援専門員 |
| 居宅介護支援事業を行っている事業所 | ・介護支援専門員 |
障害者分野
| 障害者分野の施設種類 | 職種 |
|---|---|
| 身体障害者更生相談所 | ・身体障害者福祉司 ・心理判定員 ・機能判定員 ・ケースワーカー |
| 精神保健福祉センター | ・精神保健福祉相談員 ・精神保健福祉士 ・精神科ソーシャルワーカー ・心理判定員 |
| 知的障害者更生相談所 | ・身体障害者福祉司 ・心理判定員 ・機能判定員 ・ケースワーカー |
| 精神障害者生活訓練施設 | ・精神保健福祉士 ・精神障害者社会復帰指導員 |
| 自立生活援助を行う施設 | ・地域生活支援員 ・サービス管理責任者 |
その他の分野
| その他の分野の施設種類 | 職種 |
|---|---|
| 保健所 | ・精神保健福祉相談員 ・精神保健福祉士 ・精神科ソーシャルワーカー ・心理判定員 |
| 病院・診療所 | ・相談員(医療ソーシャルワーカー 等) ・退院後生活環境相談員 |
| 更生施設 | ・生活指導員 |
| 福祉事務所 | ・査察指導員 ・身体障害者福祉司 ・知的障害者福祉司 ・老人福祉指導主事 ・現業員/ケースワーカー ・家庭児童福祉主事 ・家庭相談員 ・面接相談員 ・婦人相談員 ・母子/父子自立支援員、母子相談員 |
| 母子・父子福祉センター | ・母子および父子の相談を行う職員、母子相談員 |
上記は抜粋になり、実務経験として認められる施設・職種はまだまだありますので、自分の職務経験が実務経験としてカウントされるのかについては、引用元のページをご覧ください。
実務経験として認められないケース
自分では実務経験に該当していると思っていても、以下のケースは実務経験として認められないこともありますので注意が必要です。
【実務経験として認められないもの】
- 指導員
- 児童指導員
- 保育士
- 障害福祉サービス経験者 など
自分の職務経験が実務経験として認められるかについては、試験センターに前もって確認しておくことをおすすめします。
社会福祉士の仕事内容は?
高卒が社会福祉士になるには、資格取得のことだけでなく仕事内容もしっかりと理解しておくことが重要です。
ここでは、社会福祉士の主な仕事内容について解説します。
主な仕事は相談業務
社会福祉士は、社会福祉サービスを利用する全ての人の相談を受けることが仕事になります。
もちろん話を聞くだけでなく、利用者の家庭環境や背景をしっかりと傾聴した上で、適切な解決策を提案する必要があります。
また、解決策の提案では自分の所属している組織の力だけではなく、適切な他の福祉サービスなどと連携する必要もありますので、やり取りをするのは利用者だけではありません。
相談内容も様々であり、補助金制度の利用や保険制度に関するもの、福祉サービスを受けるための確認や利用方法など、あらゆる相談を受けることになるため、社会福祉士になってからも勉強の日々は続きます。
相談業務の流れ
社会福祉士の主業務である相談業務の主な流れについても理解しておきましょう。
まずは福祉サービスの利用をしようとしている人やその家族の相談を受けるところからスタートします。
初回相談では、「どんな福祉サービスを、何故受けたいと考えているのか」「相談内容に最も適切な福祉サービスは何か」「どのような福祉サービスと連携させれば相談者の課題は解決するか」などといった疑問点を明らかにしていくため、丁寧にヒアリングを進めていきます。
初回相談が終わった後は、相談者の感じている課題を解決できるような提案を行います。
相談者は福祉サービスについての知識が全くないことも珍しくありませんので、そもそもの前提知識からすり合わせておかないと、認識に齟齬が出てしまいかねません。
ヒアリングをした時以上に丁寧な説明をする必要があるでしょう。
提案を行い、相談者が納得をすれば適切な福祉サービスと連携して案件は終了になります。
もし提案に納得してもらえなかった場合は、再提案をしたり、再びヒアリングをし直すなどを経て、相談者が最も望む形の福祉サービスを一緒に模索していくことになります。
このように、社会福祉士の抱える案件一つ一つは非常に個別性が高いものとなっていますので、画一的な知識を持っているだけでは適切な提案はできません。
より多くの相談を受け、悩みを解決した経験こそが、社会福祉士として活躍していく上で大切なノウハウとなっていくのです。
活躍できる現場は幅広い
社会福祉士が活躍できる現場は以下のように幅広いのが特徴です。
- 介護
- 医療
- 福祉
相談業務を行うと言う意味では、どの現場でも仕事内容は変わらないと考えることができますが、現場が変わることで相談者の抱えている悩みに違いが出たり、求められる知識が異なることに気を付けないといけません。
例えば介護の現場であれば相談者は高齢者や障害者ですが、医療の現場であれば病気療養中の方や入院中の患者となりますので、コミュニケーションのアプローチも変わりますし、話し方も変えていく必要があるでしょう。
社会福祉士としてより専門的な人材へと成長していきたいのであれば、様々な種類の現場で相談業務を行うことを目標にしていくといいかもしれません。
高卒から社会福祉士になった際のキャリアパス4選
高卒から社会福祉士になった際は、医療ソーシャルワーカーとして活躍するキャリアパスがあります。
国家資格である社会福祉士を持つことで職域が広がり、現場の相談員から指導的な立場へとキャリアアップも目指せるでしょう。
具体的には、福祉施設で施設長を任されたり、行政機関における福祉部門の管理職として活躍したりといったケースがあります。
社会福祉士の資格は、医療・福祉の専門家としての選択肢を広げてくれます。
自分が将来どんな働き方をしたいのかを考えたうえで、どのキャリアパスが合っているかイメージしてみてください。
1. 医療ソーシャルワーカー
社会福祉士資格、または精神保健福祉士資格という国家資格取得者で、医療機関で働いている人たちのことを医療ソーシャルワーカーと呼びます。
主な仕事は、保険医療機関において患者さんやご家族が抱える悩みの相談に乗り、問題の解決を図るために医療機関や関係機関との調整や連係を行うことです。
ここからさらにキャリアを積むと、地域連携室の管理職や病院全体の医療福祉部門の責任者としてかかわることも可能です。
地域連携室の管理職になれば、地域の他の医療機関や他施設と連携して患者さんがスムーズにサービスを受けられるようサポートしていきます。
また、医療ソーシャルワーカーの中でも高度な専門知識と能力が認められた上位資格である認定医療ソーシャルワーカーも目指せます。
医療・福祉のスペシャリストとして、専門性を高めていけるやりがいのあるキャリアパスと言えるでしょう。
2. 施設長
高卒から社会福祉士になった際のキャリアパスとして、施設長を目指す道があります。たとえば、高齢者施設や障害者施設、児童施設などの福祉施設で働けます。
福祉施設で働く社会福祉士は、入所者の生活支援から地域との連携まで、総合的な支援が主な仕事です。
他にも、ケアプラン作成や職員指導を担当し、介護職員を兼任する場合もあります。
施設長になると、組織全体のサービス向上を担う重要な立場となり、経営戦略や人材マネジメントなどの業務も行うことになるでしょう。
さらに、地域連携強化や新規事業開発などの幅広い業務を担当します。現場だけでなく、福祉施設全体を運営していく、経営者的な立場となるでしょう。
3. 行政機関における福祉部門の管理職
高卒から社会福祉士になった際のキャリアパスの一つに、行政機関における福祉部門の管理職があります。
行政機関で働く社会福祉士は、主に福祉事務所や地域包括支援センター、児童相談所などで活躍します。
主な仕事内容は、地域住民の相談援助や施策の企画立案など、地域全体の福祉向上に貢献する幅広い業務です。
福祉部門の管理職になると、部門全体の統括や政策決定への参画といったより大きな仕事を担うことになります。
地域の福祉の課題を分析し、新たな施策を企画する能力が必要です。民間事業者との連携や地域ネットワークの構築といったコーディネート業務も行います。
地域福祉の専門家として、経営的な仕事をしていくことになるでしょう。
4. 社会福祉士の講師
社会福祉士の講師は、養成施設などで社会福祉士を目指す学生や現職者に対し、指導・育成を行います。
主な業務は、授業の実施や講習資料・テストの作成などです。また、学生の進路相談や学校行事の運営などの事務業務も担います。
社会福祉士の講師になるには、まず社会福祉士資格と、相談援助業務に3年以上の従事経験が必要です。その後、社会福祉士実習指導者講習会を修了することで指導者になれます。
講習会は全国各地で行われており、2日間のプログラムで「実習指導概論」などの4科目を学びます。修了試験はなく、全科目の修了が認定条件です。
高卒が社会福祉士になるメリット5選
高卒が社会福祉士になる最も大きなメリットは、国家資格取得で社会的な信用を得やすくなる点です。専門的な知識と能力を持つ証明となり、就職や転職などでキャリアアップにつながります。
また、現場でさまざまな人と関わる中でコミュニケーション力も向上します。さらに、試験で共通科目がある他の資格に挑戦しやすくなるのもメリットの一つです。
高卒で学歴やスキルに自信がないと感じる方でも、資格を通じて堂々と自分をアピールできるようになるでしょう。
メリットを理解したうえで、社会福祉士を目指すかどうか考えてみてください。
メリット1. 様々な人とコミュニケーションが取れるようになる
社会福祉士になると業務上様々な人と関わる必要が出てきますので、どんな人ともコミュニケーションが取れるようになるといったメリットがあります。
社会福祉士が相談・援助をする人は次のような人たちです。
- 重度の精神障害を患っており、一般的なコミュニケーションが取れない人
- 経済的に厳しい状態にあり、基本的な生活すら送れていない人
- 自分一人では生活ができないような障害を患っている人
このように、社会福祉士は様々な面で弱さを抱えている人を相手にコミュニケーションしていく必要があります。
慣れないうちは相手の考えていることや感じていることを読み取れずに、ミスコミュニケーションによるトラブルを引き起こしてしまうかもしれませんが、徐々に経験を積んでいくことで、どんな人とも分け隔てなくコミュニケーションを取ることができるスキルが身につくでしょう。
コミュニケーション能力は社会福祉士にとって必須スキルですが、他の仕事においても同様に重要であるとされています。
つまり、社会福祉士として活躍できるコミュニケーションスキルを身につけることで、他の仕事に転職したとしても活躍できる可能性があることもメリットだと言えます。
メリット2. 福祉業界において信頼度が増す
社会福祉士としての仕事は資格がなくても携わることができますが、資格を持っていることで福祉業界内での信頼度を上げることが可能です。
社会福祉士の資格を保有していれば、重要な案件を任せてもらえる可能性もありますし、その分活躍できる機会が増えることになりますので、昇進・昇格のスピードも早まるといった期待が持てます。
また、即戦力人材を求める福祉系の求人では、社会福祉士の資格保有者であることが条件になっていることもあり、就職先の幅を広げる意味でも重宝することでしょう。
メリット3. キャリアアップに繋がる
会社によっては、社会福祉士の資格を持っていることを昇格の要件にしていたり、資格手当が支給されたりするケースもあることから、キャリアアップに繋がるとも考えられます。
厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護職員の平均給与額について、保有資格の有無による違いは以下の表のとおりでした。
| 勤務場所例 | 平均給与額(社会福祉士資格あり) | 平均給与額(社会福祉士資格なし) |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 400,490円 | 303,410円 |
| 介護老人保健施設 | 386,950円 | 305,230円 |
| 通所介護事業所 | 388,880円 | 280,090円 |
上記のとおり、社会福祉士の資格の有無によって、約10万円前後の差があることがわかります。
資格を持つことで、信頼だけでなく、給与やキャリアアップに繋がるでしょう。
福祉のプロとして認められることで、業務の幅も増えていくといったメリットがあるでしょう。
また、社会福祉士は福祉施設だけでなく、市役所や病院、保健所など様々なフィールドで働くことが可能です。
社会福祉士の資格を持っていることで、その分活躍の場の選択肢が増えますので、まさに手に職を付けられると言えます。
メリット4. 国家資格取得で社会的な信用を得やすい
社会福祉士は国家資格のため、社会的な信頼を得やすい点がメリットです。医療・福祉業界でのキャリアアップに役立ちます。
国家資格だからこそ以下のようなメリットがあります。
- 就職で有利になりやすい
- 発言への信頼性が高まりやすい
- 公的機関や医療機関での採用も目指しやすい
社会福祉士を採用条件として求められることも多く、資格を持っているだけで応募できる求人が増えるでしょう。
高卒で誇れるようなスキルや資格がないと感じ、自信が持てない方もいるかもしれません。社会福祉士を取得することで、積極的に自分をアピールできるようになるでしょう。
メリット5. 他の資格にもチャレンジしやすくなる
高卒が社会福祉士になるメリットとして、他の資格にもチャレンジしやすくなる点があります。資格試験において、共通科目が免除される場合があるからです。
たとえば、精神疾患を抱えた人やその家族の相談支援をする精神保健福祉士という資格があります。この資格は、社会福祉士の資格があれば、資格試験時に共通科目が10科目ほど免除になるので相性がいいです。
他にも以下のような資格があります。
| 資格 | 相性がいい理由 |
|---|---|
| ケアマネージャー | 社会福祉士としての実務経験が受験資格に定められているため。 |
| 保育士 | 一部の試験科目が免除となるため。 |
| ファイナンシャルプランナー | 社会福祉士ではお金に関する相談を受けることも多いため。 |
社会福祉士だけでなく、他の資格も取得することで、将来の仕事の幅が広がりやすくなるでしょう。
高卒が社会福祉士になるデメリット4選
高卒で社会福祉士になる最大のデメリットは、資格を取っても収入が平均よりも低い点です。
やりがいのある仕事であったとしても、収入が低ければなかなか生活水準を上げられないでしょう。
また、無資格でも相談業務ができるため、資格の価値が評価されにくい傾向があります。さらに、アドバイスには成功・失敗がないからこそ、ストレスがかかりやすい場面もあるでしょう。
何事にもメリットとデメリットがあるものです。上記のような現実を理解したうえで、自分の目指す働き方と照らし合わせてみてください。
デメリット1. ストレス負荷のかかりやすい仕事
社会福祉士は様々な人とコミュニケーションが取れることから、対話能力が身に付く反面、精神的なストレス負荷がかかりやすい仕事です。
基本的な業務は相談となりますが、常に何らかのストレスを抱えている人を相手にすることが多いので、必要以上の心ない言葉や暴言を浴びせられることも無くはありません。
また、相談内容そのそもが重いということも多々あり、仕事をしていると自分の精神も病んでしまうという人は少なくないそうです。
「社会福祉士としてどんな人にも笑顔になってもらいたい」「嫌なことがあっても気持ちの切り替えはできる」という強い気持ちを持っている人であれば問題ないかもしれませんが、そうでない人にとっては精神的に厳しい仕事になるかもしれないでしょう。
デメリット2. 自信を無くすことも少なくない
社会福祉士としての仕事を通じて、自己嫌悪感から自信を無くしかねないこともデメリットとして挙げられます。
相談によるアドバイスや、支援には正解がありませんので、自分の中で正しいと思っていたことも、時にマイナスに働いてしまうことがあります。
特に経験の浅い間は自分の仕事に満足できないことも多々あるかもしれません。
自分にとって失敗だと感じるようなことが何回も起きてしまうと、「自分が相談者になっても問題を解決することはできないのではないか」「社会福祉士として働く資格は自分にはないのかもしれない」といった自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。
デメリット3. 無資格でも相談業務ができる
社会福祉士は国家資格がないと名乗れませんが、相談業務は無資格でもできる場合があります。
生活相談員の資格要件は自治体によって異なり、必ずしも社会福祉士が必要というわけではないからです。
たとえば、島根県では「社会福祉施設等で3年以上かつ540日以上の介護業務または相談援助業務の経験」があれば要件を満たすとされています。(参考:島根県健康福祉部「生活相談員の資格要件について(通知)」)
そのため、相談業務をしたいだけであれば、社会福祉士の資格を取らなくても働ける職場があるのも事実です。
社会福祉士は取得までにお金も時間もかかるため、相談業務だけをやりたいなら別の仕事を目指すことも可能です。
デメリット4. 収入が平均よりも低い
高卒で社会福祉士を目指すデメリットの一つは、収入が平均より低い点です。
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」によると「その他の社会福祉専門職従事者」の平均賃金は440万9,600円に対し、全体の平均賃金は526万9,900円でした。
上記の賃金は「きまって支給する現金給与額×12か月+年間賞与その他特別給与額」で算出されています。
収入が低いと、結婚や子育て、住宅購入などの将来設計の選択肢が狭まる可能性があります。
お金と時間をかけて資格を取得しても、収入につながらない点は大きなデメリットと言えるでしょう。
高卒で社会福祉士に向いている人3選
ここからは、高卒で社会福祉士になるのに向いている人について解説します。
自分に向いていない仕事に就いてしまうと、自分だけでなくサービスを利用する人にとっても悪影響となりかねませんので、しっかりと確認しておくことをおすすめします。
1. 人を支えるのが好きな人
社会福祉士の主なミッションは、相談業務を通じて困っている人の問題を取り除くことになります。そのため、人を支えたり、助けたりするのが好きな人にとってはやりがいを感じられる仕事だと言えるでしょう。
社会福祉士に相談をする人は、全員何かしら悩んでいることがありますので、その悩みを一緒に解決する姿勢を見せることができれば、心身共に健康な生活を送れるようになるかもしれません。
たかが相談業務と思うかもしれませんが、その業務は相談者の今後の人生も左右しかねないほど、大切な仕事ということは認識しておいてください。
2. コミュニケーション能力が高い人
社会福祉士には非常に高いレベルのコミュニケーション能力が求められますので、既にコミュニケーション能力に一定の自信がある人には向いている仕事です。とはいえ、社会福祉士で求められるコミュニケーション能力というのは「面白い話をして場を盛り上げる」「自分の意見をどんな状況でも発言できる」といった次元のものではありません。
社会福祉士で求められるコミュニケーションは、「相手の立場になって物事を考える力」「話を傾聴し、適切な返答ができる力」です。
相談内容によっては、時に厳しい言葉を使わなければいけないこともありますが、基本的に相手の話を聞くことを起点としたコミュニケーションをしていく必要があることに注意しましょう。
3. 幅広い知識を習得できる人
社会福祉士国家試験の試験科目を見ても分かる通り、社会福祉士の仕事では非常に多くの知識を求められますので、幅広い知識を習得できる人に向いていると言えます。
基本的な福祉サービスの概要はもちろん、行政知識や法律知識、メンタルケアなど、習得すべき知識のジャンルや難易度も様々です。
社会福祉士となった後も、日々勉強をしていくことになりますので、勉強嫌いの人には向かない仕事かもしれません。
高卒が社会福祉士になる時にすべき準備3選
最後に、高卒が社会福祉士になる時にすべき準備について解説します。
これらの準備をしないで社会福祉士になろうとしてしまうと、思ったよりも時間がかかってしまうなどの不利益に繋がるかもしれませんので、ぜひ参考にしてください。
1. どういった方法で社会福祉士になるのかを決める
社会福祉士を目指したいと考えたら、まずはどのような方法で社会福祉士になるのかを検討しましょう。
社会福祉士の資格を高卒が取得するのであれば、大学・短大に進学するのか、それとも実務経験を積むのかによって、取るべき行動だけでなく、必要な費用・期間が大きく異なります。
また、社会福祉士の資格を取らずに就職をするのであれば、どういった福祉サービスに携われば自分がしたいことに繋がるかなどの志望動機を明らかにしておく必要もあるでしょう。
いずれにしても、社会福祉士としての将来的なビジョンを明らかにしておくことで、自ずと今選択するべき方法が見えてくるはずです。
2. 社会福祉士になりたいと思った理由を明らかにする
社会福祉士を目指したいと思ったきっかけを言語化しておくことも大切です。
社会福祉士国家試験の合格率は30%前後であることから、難易度が高い試験であると言えますし、もし社会福祉士になれたとしても、年収の面で大きなメリットがあるわけでもありません。
「何故社会福祉士になりたいと思ったのか」といった動機がはっきりしていなければ、試験勉強の意欲も湧きませんし、仮に社会福祉士になれたとしても長く働くことは難しいでしょう。
また、自分の動機を明らかにした結果、社会福祉士ではなく民間企業で普通に働くことが向いていると分かることもありますので、自分のキャリアの幅を狭めないという意味でもぜひ試してみてください。
3. 民間企業への就職も検討する
高卒が社会福祉士の資格を取ろうとすると、最短でも4年以上は必要になりますので、民間企業に就職した方がいいと考える人は少なくありません。
民間企業への就職を検討している高卒の方におすすめなのが、私たちジェイックの就職支援サービスです。高卒やフリーター、第二新卒向けに正社員の就職支援サービスを提供していて、就職率は非常に高いのが特徴です。
この高い就職率を実現しているのは、登録後に受けられる以下の3つの仕組みが用意されているためです。
| 種類 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| 面談 | 専任のアドバイザーによる面談 | 就職活動を何から始めたらいいか分からない人でも、今後の方針を決められる |
| 無料のビジネス研修 | 以下の研修が受講できる ・ビジネスマナー ・自己分析 ・企業研究 ・選考の対策 | 社会人経験が少ない人でも、就職活動を成功させられる可能性が上がる |
| 集団面接会 | 1度に数十社が集まる面接会 | ・書類選考なしで面談ができるため就職活動のスピードが上がる ・数十社と一度に話せるので企業の比較がしやすい ・社会人未経験者を採用したいと思っているので内定確率が最初から高い |
気になる人は以下のリンクから登録してみてください。(登録無料)
社会福祉士を目指す際のよくある質問4選
ここからは社会福祉士を目指す際のよくある質問について紹介します。疑問を解消して、社会福祉士を目指すか考えてみてください。
高卒は通信教育だけでは社会福祉士の受験資格を得られません。高卒で受験資格を得るには、以下のような方法があります。
・4年制の福祉系大学を卒業
・福祉系の短大・専門学校を卒業
・社会福祉主事養成機関を卒業
・特定の実務経験を積んでから短期養成施設で学習
・相談援助の実務経験を積んでから養成施設で学習
最短ルートは、4年制の福祉系大学を卒業する方法です。夜間コースや通信制を活用すれば、働きながらの資格取得も目指せます。
上記の中から、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。
高卒で介護福祉士から社会福祉士になるためには、社会福祉士国家資格の合格が必要です。
ただし介護福祉士の実務経験があっても社会福祉士の実務経験として認められていません。実際、社会福祉士の受験資格にも以下のように記載されています。
「指導員・訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行なう指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
引用:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験」
また、介護福祉士は実務経験として認められませんが、介護福祉士の資格を取得していれば実習が免除される可能性があります。(参考:厚生労働省「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」)
ただ介護福祉士を受験した際に実習を受けているかどうかで免除できるかどうかが異なるため、くわしくは通う予定の養成機関に確認しておきましょう。
福祉の資格は高卒でも取得可能です。特定の実務経験を積んだうえで、養成施設で学べば社会福祉士や精神保健福祉士といった受験資格を得られます。
実際、福祉の現場で働きながら資格取得を目指す人も多く、通信課程など柔軟な学習スタイルも整っています。
高卒でも十分に可能性があるので、今できることから挑戦してみましょう。
高卒で働きながら社会福祉士を目指すことは可能です。福祉系の大学や短大・専門学校の通信制や夜間コースなどを活用すれば、働きながらでも受験資格を得られるでしょう。
ただし、実習で仕事を長期間休む必要があったり、疲れが溜まりやすくなったりする場合があります。1日働いたあとに勉強するのは、相当な体力と気力が必要です。
相談援助の実務経験を4年以上積み、養成施設に1年以上通うルートであれば、無理なく働きながら受験資格を得やすいのでおすすめです。
まとめ
社会福祉士になるには高卒でも問題ありませんが、資格を取得するのであれば4年以上かかってしまうこともあることには注意してください。
また、自分が何故社会福祉士になりたいと思ったのかを理解しておかないと、理想とは異なるキャリアを歩む可能性がありますので、必ず行っておきましょう。
もし社会福祉士ではなく民間企業の正社員として働きたいと思ったら、就職エージェントを活用して就職活動を進めてみることをおすすめします。