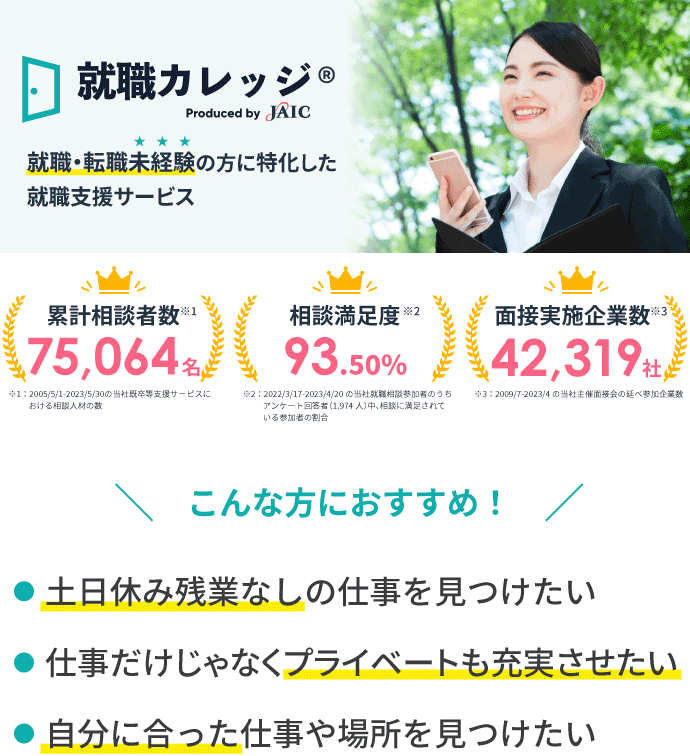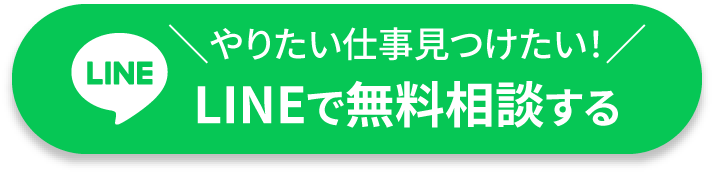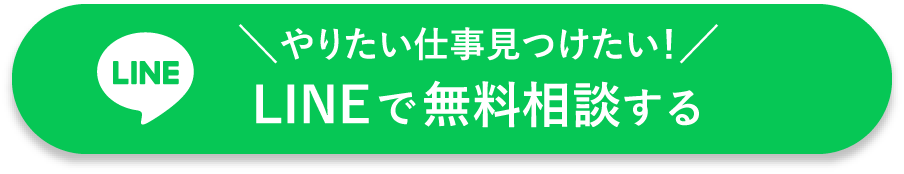家でできる仕事が最近、増えています。通勤せずに自宅で働きたいなら、まずはどんな仕事が自宅でできるかを知り、やってみたい仕事をイメージするところから始めましょう。また、在宅できる仕事でどのくらい稼げるのか知っておくことも大切です。
この記事では、家でできる代表的な仕事37選と、在宅でできる仕事の働き方について3つの形態をご紹介します。さらに、家でできる仕事の平均月収と、自宅でできる仕事で稼ぐポイントまで解説します。在宅で働きたいと考えている人や、在宅できる仕事にはどんなものがあるか具体的に知りたいという人は、ぜひ参考にしてください。
- 家でできる仕事23選の「おすすめポイント」「注意点」「平均年収」を解説
- 家でできる働き方の形態は「正社員」「個人事業主」「起業」の3種類
- 自宅でできる仕事で稼ぐポイントは「専門スキル」「正社員のコネ」「独立」
この記事の目次
家でできる仕事の種類
家でできる仕事の具体例を紹介する前に、まずは自宅でできる仕事の種類について解説します。代表的な種類と内容は次の通りです。
家でできる仕事にはさまざまな働き方があることを理解しましょう。
- 内職:あくまでも企業から雇用されている被雇用者として業務を行う働き方
- 在宅ワーク:個人事業主として企業と契約し、企業から仕事を請け負う働き方
- テレワーク:本社や本拠地から離れた場所で、ICTを活用して勤務する働き方
- 在宅勤務:本社や本拠地から離れた場所で、ICTを活用して「自宅」で勤務する働き方
家でできる仕事37選

家でできる代表的な仕事を、次の7つのテーマに分けてご紹介します。
- 資格や経験がなくても気軽に始められる仕事
- IT系の仕事
- クリエイティブ系の仕事
- コンサル・講師の仕事
- 店舗・教室系の仕事
- その他の仕事
- 家でできる正社員の仕事
それぞれの仕事の特徴とおすすめポイント、注意点、平均月収についても触れていきますので、興味のある仕事、挑戦してみたい仕事を探してみてください。
資格や経験がなくても気軽に始められる仕事5選
まずは、資格や経験がない人でも在宅でできる仕事を紹介します。スタート時の報酬は高くありませんが、努力次第で報酬アップが狙えるものもあります。まずは副業から在宅ワークを始めたい人にもおすすめです。
1. ライティング
「ライティング」は、文章を書く仕事です。家でできる仕事で多いのは、インターネット上に掲載されるWeb記事のSEOライティングです。「SEO」とは、簡単にいうとGoogleなどの検索結果で上位に表示されるためにおこなう対策のことで、ライティングの仕事をするならSEOの基本的なルールを知っておくと有利です。
| おすすめポイント | ・さまざまなジャンルの仕事があるため、自分の趣味や経験を活かせる ・未経験者可の案件も多い ・隙間時間にもできるため、副業にも向いている ・募集が多い ・実績を積めば文字単価を上げられる |
| 注意点 | ・未経験者可の案件は報酬が低いものが多い ・SEOの知識が求められる ・高報酬を狙うには、専門的な資格(弁護士・看護師・栄養士など)が必要 |
| 平均年収 | 200万~400万円 |
2. データ入力・文字起こし
「データ入力」は名刺データやアンケート結果などのアナログデータを、エクセルなどの指定されたフォーマットに入力していく仕事です。手書きの資料を扱ったり、ネットで簡単なリサーチをおこなって検索結果を入力したりする場合もあります。
「テープ起こし」はICレコーダーに録音された講義や座談会などの音声データを聴き取ってテキストに起こす仕事です。
どちらも気軽に始められる在宅ワークとして人気の仕事です。
| おすすめポイント | ・未経験者でも始められる ・パソコンさえあれば、専門知識やスキルがなくてもできる ・隙間時間にもできるため、副業にも向いている ・タイピング技術が身につく |
| 注意点 | ・報酬が安い ・タイピングのスピードと正確さが求められる ・正しい日本語を使えること、読解力が求められる ・集中力が必要 ・社外秘データを扱う場合もある |
| 平均年収 | 150万~300万円 |
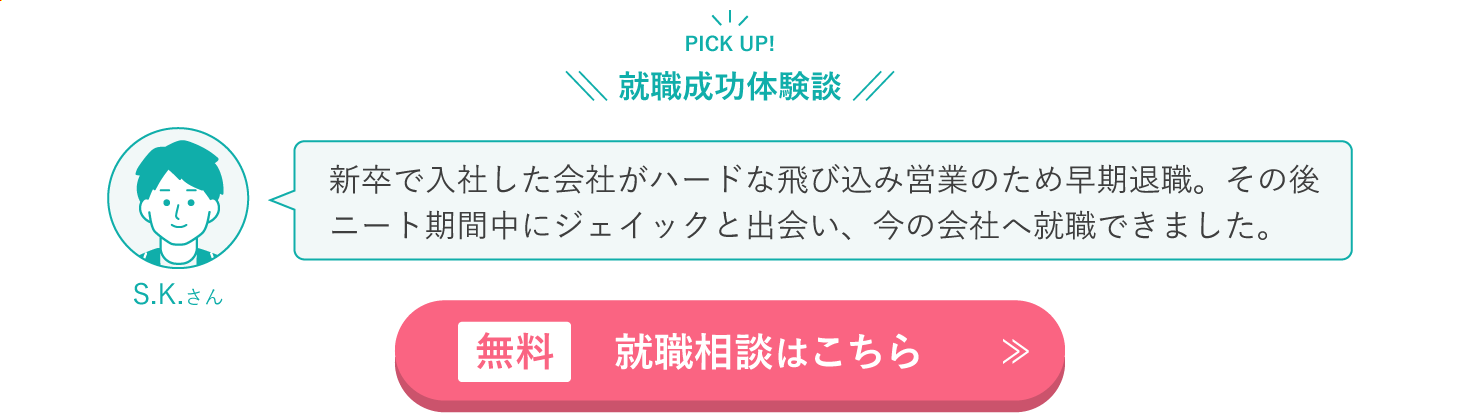
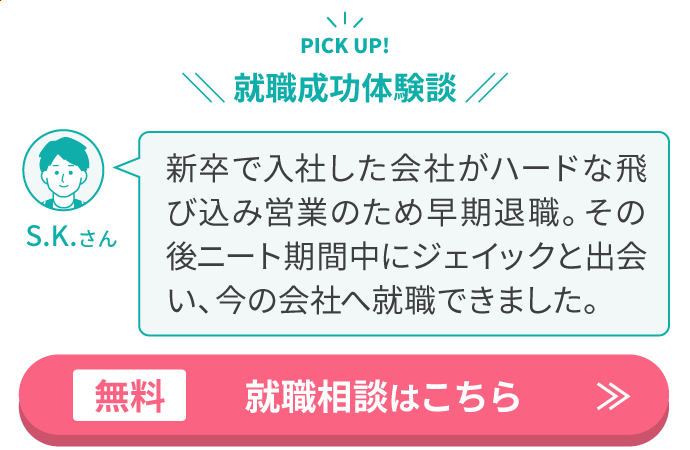
3. 内職系<パソコンがなくてもOK>
内職系の仕事には、商品や封筒にシールを貼っていく「シール貼り」、カプセルにおもちゃや説明書を詰めていく「カプセル詰め」、「ポケットティッシュの広告入れ」などの仕事があります。
単価が安く、まとまった報酬を得るには数をこなす必要があります。パソコンがなくてもできる点では人気があります。
| おすすめポイント | ・パソコンがなくてもできる ・知識や経験が必要ない ・隙間時間にできる ・黙々とおこなうことができる |
| 注意点 | ・報酬が安い ・副業として割り切っておこなうのが無難 ・単純作業のため、スキルアップにつながらない ・作業スペース、保管スペースが必要 ・材料や商品を車で取りに行かなければならない場合もある |
| 平均年収 | 50万~100万円 |
4. テレマーケティング/テレフォンオペレーター/コールセンター
「テレマーケティング/テレフォンオペレーター/コールセンター」は、いずれも電話を用いて顧客とやり取りを行う仕事です。それぞれの主な業務内容は次の通りです。
テレマーケティング:顧客に電話をかけて商品やサービスを紹介する
テレフォンオペレーター:顧客からの質問やクレームに対応する
コールセンター:電話を使って顧客とさまざまなやり取りを行う
これらの仕事はいずれも、電話とPCがあれば在宅での業務が可能です。
| おすすめポイント | ・マニュアルが整備されているため未経験でもチャレンジしやすい ・コミュニケーション能力の向上につながる ・仕事を始めるための特別な準備が不要 |
| 注意点 | ・言葉のやり取りだけでわかりやすく説明する必要がある ・クレーム対応でストレスをためるリスクがある ・マニュアルにない状況でも臨機応変に対応しなければならない |
| 平均時給 | 1,000~1,500円 |
5. メール・チャットオペレーター
「メール・チャットオペレーター」は、メールやチャットで受けた問い合わせに対して返答する仕事です。オンラインの問い合わせ窓口を設置している企業から、多くの求人が出ています。
メールオペレーターは、企業が扱う製品やサービスに関する詳細な質問に関する対応など、比較的フォーマルな問い合わせ対応を行うことが多いです。チャットオペレーターは、都度発生する細やかな質問などにリアルタイムで対応する必要があります。
メール・チャットオペレーターは電話オペレーターと違い、お客様と電話で話す必要がありません。電話が苦手な人に向いている仕事だと言えます。
| おすすめポイント | ・特別なツールは不要、パソコンが1台あれば仕事ができる ・クレームを直接電話口で聞かずに済む |
| 注意点 | ・素早く返信する必要があるため、ブラインドタッチの習得は必須 ・ある程度の文章力が必要 |
| 平均時給 | 1,300円~ |
IT系の仕事6選
在宅できる仕事の一つに、IT系の仕事があります。
在宅ワーカーを積極的に採用する企業も多く、フリーランスとして仕事を請け負うことも可能です。IT系の中でも需要の多い仕事を6種類ピックアップしてご紹介します。
6. Webデザイナー
「Webデザイナー」の仕事には、チラシや雑誌などの紙媒体、ファッション関連などさまざまなものがありますが、自宅でできる仕事で代表的なのは、Webサイトやアプリを作成するWebデザインです。
Webデザインは、デザインだけでなく、Webサイトの設計やコーディング(プログラミングの一種)までできると報酬が高くなります。クライアントやチームと一緒にサイトを作り上げるケースも多い仕事です。
| おすすめポイント | ・将来性がある ・成果物がたくさんの人の目に触れる ・Webデザインの場合、運営や保守も任されれば、継続的に報酬を得られる ・教材やオンラインセミナーなどスキルを習得する方法が多い ・独学で始める人もいる |
| 注意点 | ・デザインに必要なソフトウェア(「Adobe Dreamweaver」「Adobe Illustrator」「Adobe Photoshop」など)を使いこなすスキルが必要 ・技術やデザインのトレンドを常に勉強し続ける必要がある ・実務経験があったほうが有利 ・総合的なサイト作成ができるほうが報酬は高くなる ・クライアントの要望を引き出す力やコミュニケーション能力も必要 |
| 平均年収 | 300万~400万円 |
7. プログラミング
「プログラミング」は、コンピューター用の言語を使い、コンピューターに指示を出す「プログラム」を書く仕事です。プログラミングをおこなう人は、Webサイトなどユーザーの目に見えるものを扱う「フロントエンジニア」、サーバー環境などシステムを扱う「バックエンドエンジニア」の2つに大きく分けられます。比較すると、フロントエンジニアの方が学習しやすいと言われています。
どちらも専門スキルが必須ですが、その分報酬が高く、実力次第で大きく稼げる可能性があります。
| おすすめポイント | ・専門性が高い分平均報酬が高く、伸びしろもある ・人材不足のため仕事が豊富 |
| 注意点 | ・プログラミング言語やデータベース、開発プラットフォームなどに関する専門知識が必須 ・常に新しい情報を勉強し続ける必要がある ・仕事内容によっては緊急時の対応が求められる ・周辺領域(マーケティング、Webデザインなど)の知識があると役立つ |
| 平均年収 | 400万~800万円 |
8. システムエンジニア(SE)
「システムエンジニア(SE)」は、ITシステムやソフトウェアを設計・開発する仕事です。開発プロセスにおける上流工程の領域を担当し、一般的にプログラマーとは担当領域が異なります。
システムエンジニアが担当する具体的な工程は、要件定義・基本設計・詳細設計・テスト・運用・保守などです。案件によっては、システムエンジニア自身がプログラミングを行うこともあります。
| おすすめポイント | ・ひとつの案件に企画から運用まで長く携われる ・専門性が高いため報酬も高め ・人材が不足しており在宅案件も多い ・キャリアパスが豊富で将来の選択肢が広がる |
| 注意点 | ・プログラミングやプロジェクトマネジメントの能力が必須 ・重要な書類を扱うことが多くセキュリティへの配慮が必要 |
| 平均年収 | 450万~550万円 |


9. CADオペレーション
「CADオペレーション」は、CADと呼ばれるソフトで製図をおこなう仕事です。CADオペレーションを必要とする業界は幅広く、なかでも建築業界やインテリア業界、製造業界が代表的です。
2次元CADと3次元CADの2種類があり、両方を習得することで仕事の幅を広げられます。単に製図をおこなうだけでなく、ものづくりそのものに関われる仕事も多いため、クリエイティブな仕事に興味がある人なら特に魅力を感じられます。
| おすすめポイント | ・仕事が豊富 ・さまざまな業界でスキルを活かせる |
| 注意点 | ・CADのスキルは必須 ・集中力や根気が求められる ・業界に関する知識が求められる ・CADオペレーションだけでなく、事務と兼務の求人も多い ・必須ではないが、資格(「CAD利用技術者試験」、「建築CAD検定試験」など)があると有利 |
| 平均年収 | 300万~500万円 |
10. Webエンジニア
WebエンジニアとはWeb系のシステムを専門に扱う仕事です。大きく「フロントエンドエンジニア」と「バックエンドエンジニア」に分けられます。フロントエンドエンジニアはユーザーの目に入る部分、バックエンドエンジニアはユーザーから見えない部分を担当するという違いがあります。
Web制作はチームで行うことが多く、Webエンジニアだけで仕事が完結することはまれです。そのため、チームのメンバーと円滑に仕事を進めるためのコミュニケーション能力も求められます。
| おすすめポイント | ・Webサービスの拡大により売り手市場 ・将来性が高い |
| 注意点 | ・常に情報をアップデートし続ける必要がある ・仕事内容に幅があり、デザインなどに関わることもある ・WebディレクターやWebデザイナーと連携することが多い |
| 平均年収 | 500万~700万円 |
11. Webディレクター
「Webディレクター」はWebサイトを作る際に全体の指揮やスケジュール管理を担当し、プロジェクト全体をまとめる仕事です。WebエンジニアやWebデザイナー、さらにフォトグラファーやイラストレーターといった人たちをまとめ、Webサイトを完成させる役割を担います。
納期までに仕上げるには、チームメンバーの一人ひとりの状況を把握し、スケジュールの管理や調整をしなくてはなりません。そのため、コミュニケーション能力などの人間的なスキルが重視されます。
| おすすめポイント | ・将来性が高い ・すべての行程に関わるためやりがいを感じられる ・自分の手腕でチームを育てられる |
| 注意点 | ・マネジメント能力やコミュニケーション能力が重要 ・デザイン、プログラミング、コーディングといったWeb全般に関する知識が求められる |
| 平均年収 | 400万~700万 |
クリエイティブ系の仕事8選
12. 企画・編集
「企画・編集」は、記事の企画や構成をおこなったり、ライターからあがってきた記事の編集、校正をおこなう仕事です。在宅でできる仕事の場合、多くはインターネット上のWebサイトに掲載される記事を対象としています。
仕事の依頼主であるクライアントともライターとも関わるため、SEOの知識やライティングの経験だけでなく、折衝力や調整能力なども求められる仕事です。
| おすすめポイント | ・ライティングの経験を活かせる ・得意なジャンルの知識を活かせる ・プロジェクト単位で案件を受注できればまとまった収入が見込める ・実績を積めば案件単価を上げられる |
| 注意点 | ・ライティングの経験が必要 ・正確な日本語力が必要 ・SEOの知識が求められる ・高報酬を狙うには、得意なジャンルを持っておくと有利 ・ライターやクライアントの調整能力が求められる |
| 平均年収 | 300万~400万円 |
13. 動画編集
「動画編集」は、在宅でできる仕事のなかでも最近需要が高まっている仕事のひとつです。YouTubeなどのWebサイトに掲載する動画やウェディングムービー、企業のPRや広告に使う動画を編集します。
動画編集をするにはソフトやそれなりのスペックのパソコンを用意する必要がありますが、スキルは独学でも学べます。ただし、ツールやパターンを使うものから完全にフリーで制作するものまで難易度がまちまちで、簡単なものの報酬はそれほど高くありません。
| おすすめポイント | ・仕事が多い ・オンラインスクールや独学でスキルが学べる ・自分で仕事の量を調整しながら取り組めるため、副業にも向いている ・視聴率を稼げる動画編集ができれば報酬アップが狙える |
| 注意点 | ・簡単な案件は単価が低い ・動画編集ソフト(「Adobe Premiere Pro」など)がスムーズに使える程度のスペックのパソコンが必要 ・扱うデータが重いため、大容量のストレージが必要 ・マーケティングに関する知識があると有利 |
| 平均年収 | 200万~350万円 |
14. DTPデザイナー
「DTPデザイナー」とは、チラシやポスター、書籍など印刷物のレイアウトを制作する仕事です。DTPソフトを使って作業します。
紙媒体のデジタル化が進んでいるとはいえ、印刷物には一定の需要があり、制作したチラシなどがpdfファイルや画像ファイルの形でWeb上に掲載されることもあります。
| おすすめポイント | ・1度スキルを身につけてしまえば長く続けやすい |
| 注意点 | ・「Quark XPress」「Adobe InDesign」「Adobe Illustrator」 などのソフトウェアを習得する必要がある ・入稿・色校正・文字組みなど印刷に関する知識も大切 ・Web系のデザインやライティングなどの知識があると、仕事の幅が広がる |
| 平均年収 | 250万~400万円 |
15. イラストレーター
「イラストレーター」は挿絵やイラストを描く仕事です。雑誌や本、Webメディアなどに掲載するイラストをはじめ、商品のパッケージやキャラクターデザインを手がけることもあります。
企業や個人から直接依頼を受けて希望のイラストを描く仕事のほか、ストックイラストを扱うWebサイトに作品を掲載し、必要とする人に広く販売することもできます。
| おすすめポイント | ・資格が必要ない ・好きなことを仕事にできる |
| 注意点 | ・「Adobe Illustrator」「Adobe Photoshop」などの ソフトウェアを使いこなす必要がある ・解像度やファイル形式といった画像に関する基礎知識が必要 ・ファンがつけば報酬が上がりやすい |
| 平均年収 | 300万~400万円 |
16. 作曲家
「作曲家」は名前の通り曲を作る仕事です。ゲームや動画で使われる音楽を作ったり、ステージ用のBGMを作曲したりします。また、ストックミュージックを扱うWebサイトに登録し、音楽素材を販売するという方法もあります。
| おすすめポイント | ・自分のセンスを生かして仕事ができる ・印税収入を得られる可能性がある |
| 注意点 | ・楽器やソフトウェアなど、作曲のための機材が必要 ・スランプを乗り越える精神力も重要 ・場所を選ばずアイデア出しができる |
| 平均年収 | 300万~450万円 |
17. ハンドメイド販売
ハンドメイド販売とは、自分で作った商品をネットショップやマーケットプレイスなどで販売する仕事です。
- アクセサリー
- バッグ
- ベビー用品
- ファッション
など、扱えるカテゴリーは多岐に渡ります。
副業としてスキマ時間を使って行うこともできるため、非常に人気のある仕事です。
始めるにあたって必要な資格はありませんが、中には認定講師資格を取得して、本格的なハンドメイド販売を行っているケースも少なくありません。
| おすすめポイント | ・自分の好きなことを仕事にできる ・自分のペースで仕事ができる ・スキルアップしやすい |
| 注意点 | ・個人情報の取り扱いが煩雑 ・著作権に注意が必要 ・在庫の管理は必須 |
| 平均年収 | 6万~20万円前後 |
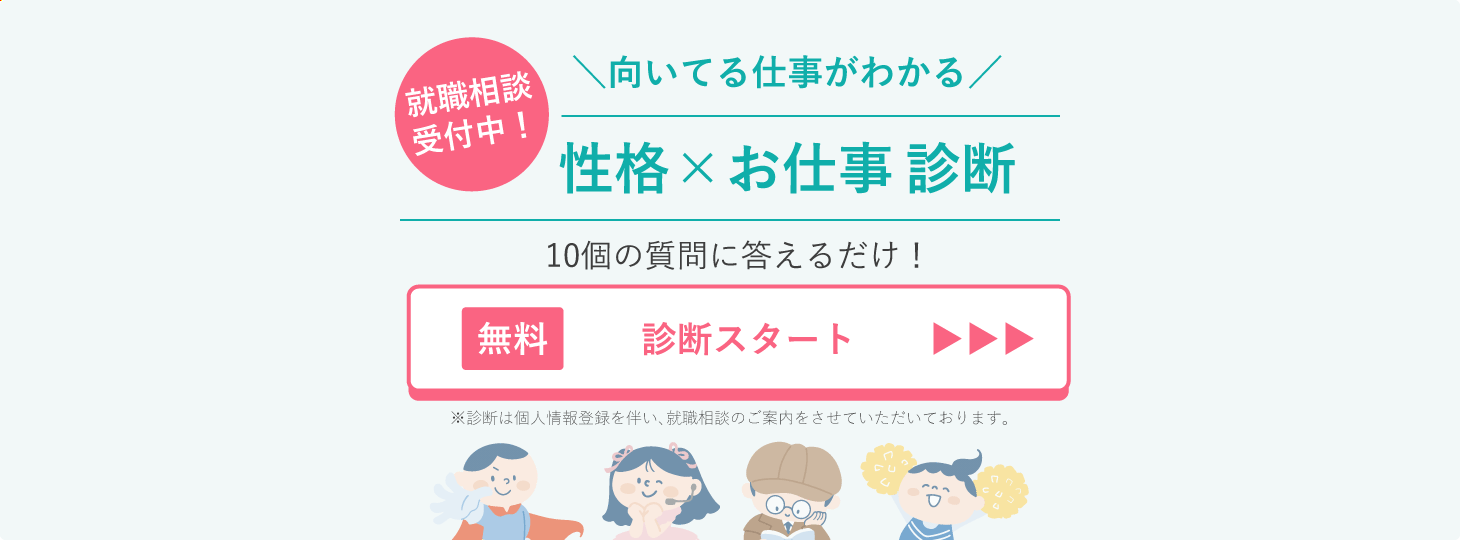
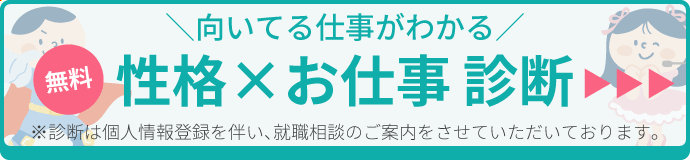
18. ブログ運営
自分自身でブログを立ち上げて、収益化するという仕事もあります。
著名人の場合は、ブログの収益だけで月間数百万円という例もありますが、一般人の方がブロガーとして安定した収入を得られるようになるまでは、非常に時間がかかるでしょう。
ブログ運営の収益は、成果報酬型広告とクリック型広告に分けられるため、とにかく多くの人に読んでもらうことが成功へのポイントといえます。
| おすすめポイント | ・美容、家電、ダイエットなど自分の得意なテーマを扱える ・時間や場所を選ばない ・さまざまなスキルが身につく |
| 注意点 | ・安定した収入を得るまでに時間がかかる ・読者のニーズに応え続けなくてはいけない ・競合が多い |
| 平均年収 | 30万~50万円(※一般人の平均) |
19. SNS運用代行
SNSの運用代行とは、個人や企業に代わってSNSを運用する仕事です
- SNSで成果が欲しい
- SNSで炎上しないように配慮したい
- SNS運用を任せられる担当者がいない
などの課題を抱えている企業や個人は多く、コンテンツの制作・投稿内容の検討・コンサルティングなどの業務を行います。
SNS運用代行は、スマートフォンの普及により拡大したSNS市場を担う仕事です。案件数が多く、本業としても副業としても働くことができるメリットがあります。
| おすすめポイント | ・時間や場所を選ばずに働くことができる ・案件数が多い ・未経験でも挑戦できる |
| 注意点 | ・ライバルが多い ・常にスキルアップをする必要がある ・収入が安定するまでに時間がかかる |
| 平均年収 | 300万~800万円 |
コンサル・講師の仕事3選
在宅でできる仕事の中には、コンサルや講師の仕事もあります。専門性が求められる仕事ですが、これから勉強したいという人にもおすすめです。
スキルや経験を活かして、独立も可能な仕事を3種類ご紹介しましょう。
20. 講師
オンライン講座を開講することで、家にいながら「講師」の仕事をすることができます。コロナ禍では、自宅でレッスンを受けたいという生徒側の要望も多く、需要が高まっています。パソコンとWebカメラ、Web会議システムがあれば、資格は特に必要ありません。
英会話、塾講師(家庭教師)、料理教室など、さまざまな講座がオンラインで開講されています。
| おすすめポイント | ・得意なことや趣味を活かして稼げる ・質が高い授業を提供すればリピーターも獲得できる ・都合のいい時間帯にレッスンを組める |
| 注意点 | ・パソコン、WebカメラとWeb会議システムが必要 ・オンラインで生徒と接する際は身だしなみも重要 ・集客にはある程度のコストや知識が必要 ・SNSを活用できると集客に有利 |
| 平均年収 | 250万~400万円 |
21. コンサルティング
「コンサルティング」は、個人や組織の抱える問題をヒアリングして、アドバイスや解決策を提示する仕事です。以前は対面で行うのが多い仕事でしたが、さまざまな分野でオンライン化が進んだことで、家でもできる仕事になりました。
ひとくくりにコンサルティングと言っても、キャリアコンサルタント、経営コンサルタント、恋愛コンサルタントなど、活躍できる分野は多岐にわたります。資格がなくても自分でコンサルタントと名乗れば活動できますが、企業の経営に関わるコンサルタントとして活動するには豊富な経験や実績が求められるため、未経験で始めるのは困難です。
| おすすめポイント | ・働き方次第ではかなり高収入を狙える ・専門知識を活かして働ける ・問題を解決する喜びややりがいがある |
| 注意点 | ・常に結果が求められる ・資格は必要ないが、未経験からの参入が難しい分野もある ・営業力が必要 |
| 平均年収 | 400万~1,000万円 |
22. カウンセリング
「カウンセリング」は、相談者の悩みに耳を傾け、解決のサポートをおこなう仕事です。個人の悩みや苦しみ全般に寄り添う「心理カウンセリング」、主にキャリア形成などを扱う「キャリアカウンセリング」などがあります。悩みを聞くという広い意味では、「占い師」として活動する選択肢もあります。
心理学などの知識があれば役立ちますが、ただ愚痴を聞いてもらえればいいという需要もあります。
| おすすめポイント | ・自身の経験を活かせる ・悩みを持つ人の力になれる ・パソコンがなくてもスマートフォンだけで仕事ができる ・資格がなくても活動できる・相談者が増えれば高収入も見込める |
| 注意点 | ・実績がないうちは集客が難しい ・感情移入しすぎると、自身のメンタルケアが必要になる可能性もある ・「公認心理師」や「臨床心理士」などの資格があると有利 ・精神力、忍耐力、洞察力が求められる |
| 平均年収 | 200万~400万円 |
店舗・教室系の仕事3選
自宅の一部を利用することでできる仕事もあります。
資格が必須なケースもありますが、自営業として独立可能な仕事です。
新しいことにチャレンジしてみたいという人に、おすすめしたい3種類の仕事をご紹介します。
23. 飲食店
自宅の一部を改修して、飲食店を開業するという選択肢もあります。
個人経営はもちろん、大手フランチャイズの飲食店に参入するというケースも可能です。
個人経営の場合は、事業計画・資金繰り・設備投資なども担う必要があるため、準備期間は必須といえます。
飲食店の業務は、大きく分けるとキッチン・ホール・店舗の運営(管理)がありますが、小規模な飲食店では、少人数で業務を担当することが特徴です。
| おすすめポイント | ・店舗経営のノウハウを学べる ・業界的に参入がしやすい ・売上が伸びることで発展性がある |
| 注意点 | ・ライバルが多い ・初期費用がかかるケースもある ・長時間労働になる可能性がある |
| 平均年収 | 257.4万円 |
24. サロン
エステサロンやネイルサロンを店舗を借りて営業するのではなく、自宅の一室を利用して開業するという方法があります。
エステティシャンやネイリストは正式な資格や免許がないため、誰でも開業することはできますが、最低でも2年以上の経験がないと難しいのが現実です。
業務内容は施術の他にもカウンセリングや機器のメンテナンスなどが必要で、経営者であれば店舗管理や売上の管理なども含まれます。
| おすすめポイント | ・開業資金を抑えることができる ・自分の都合を優先できる ・家賃の心配がない |
| 注意点 | ・生活感を出さないようにしなければいけない ・家族の協力が必要 ・セキュリティ対策をしっかり行う必要がある |
| 平均年収 | 200万~300万円 |
25. 教室
自宅で自分の得意なことを活かし、教室を開設するという仕事もあります。
- ピアノ
- 料理
- 手芸
- 学習塾
- ヨガ
など、さまざまなカテゴリーから選択することができるのがメリットです。
「先生」という指導者としての役割はもちろん、経営者としての心構えも必要になります。
自宅教室は初期費用を抑えることが可能で、家族の理解があれば誰でも行うことができますが、安定した生徒数を獲得できるまでは時間がかかるケースが多いでしょう。
| おすすめポイント | ・費用を抑えて開業できる ・レッスンの時間を自由に設定できる ・家事や育児と両立しやすい |
| 注意点 | ・生徒数が軌道に乗るまでに時間がかかる ・家族の理解が必要 ・月謝未払いなどのトラブルが想定される |
| 平均年収 | ジャンルにより異なる |
その他の仕事6選
パソコンやスマホなどのツールや通信環境が整っていれば、在宅でできるという仕事は他にもあります。
特別なスキルや経験がなくても始められる仕事も多いので、これから在宅ワークを始めてみたいという人にはおすすめです。
6種類の仕事をピックアップしてご紹介しましょう。
26. 翻訳
「翻訳」は、語学力が必要な仕事です。外国語を日本語に訳したり、日本語を外国語に訳したりするほか、すでに翻訳された文章をチェックする仕事もあります。また、翻訳の対象もメール、書籍、字幕、Webサイト、商品マニュアルやカタログなどさまざまです。
メール翻訳など簡単なものからスタートし、ゆくゆくはある分野を極めて専門書の翻訳をおこなうなど、スキルアップものぞめます。もっとも求人が多いのは英語の翻訳ですが、ニッチな言語を扱えると強みになります。
| おすすめポイント | ・語学力を生かせる ・専門性が高くスキルアップが狙える |
| 注意点 | ・翻訳する対象によっては専門知識が必要 ・扱う言語のバックグラウンド(文化や慣習など)を勉強する姿勢が必要 ・扱う言語によって報酬や案件数がまちまち |
| 平均年収 | 300万~500万円 |
27. 校正・校閲
「校正・校閲」とは、ライターが執筆した文章のチェックを行う仕事です。誤字脱字や変換ミス、表記ゆれなどがないかを、目視やツールで確認します。
クライアントのルール通りに書かれているかを確かめることも、校正・校閲の重要な作業です。ライターの仕事をしたことがある方や、Webライティング・SEOの知識がある方は、校正・校閲の仕事を比較的スムーズに始められるでしょう。
| おすすめポイント | ・ライティングの案件増加に伴い、校正・校閲の案件も豊富 ・自分の好きな時間に作業を行いやすい ・さまざまな文章に触れられるため勉強になる ・編集者に比べ案件獲得のハードルが低い |
| 注意点 | ・ライティング案件に比べ報酬単価が安めに設定されている ・案件によりチェックにかかる時間が大きく異なる |
| 平均単価 | 1記事当たり1,000~3,000円程度 |
28. アンケートモニター
「アンケートモニター」は、企業のアンケートに回答することで報酬を得る仕事です。一般的には、設問の選択肢を選んで回答していくパターンが多くなっています。
スマホが1台あればできるため、誰でも簡単にできることがメリットです。自分の好きなタイミングで取り組めることから、隙間時間を有効活用できます。
ただし、1案件当たりの報酬が安いため、数をこなさなければまとまった収入にはなりません。他の仕事と並行して取り組むのがおすすめです。
| おすすめポイント | ・特別なスキルは不要、スマホがあれば取り組める ・自分が知らなかった商品やサービスに詳しくなれる |
| 注意点 | ・報酬が現金ではなくポイントでもらえる場合、現金化が面倒 ・単発案件が多いため、小まめに案件を探さなければならない |
| 平均月収 | 100~200円程度 |
29. 商品モニター
「商品モニター」は、商品を実際に利用し、感想や意見を企業に提供することで報酬を得る仕事です。アンケートモニターと似ていますが、実際に商品を利用する点が異なります。
例えば、化粧品の商品モニターに取り組む場合、最初に化粧品が自宅に送られてきます。一定期間使用した後、感想を記入して企業に送信するという流れです。
使用する商品の代金に関しては、最初から無料で提供されるケースと、一旦購入して後から商品代金以上の報酬を受け取るケースの2パターンがあります。
| おすすめポイント | ・スマホ1つで誰でも簡単に取り組める ・美容や健康に関する商品を無料で試せる |
| 注意点 | ・報酬が比較的安く、稼ぐためには継続的な案件獲得が必要 ・1つの案件が終わるまで、数ヶ月程度の時間がかかる |
| 平均単価 | 500~5,000円程度 |
30. せどり
「せどり」とは、仕入れた商品を仕入れ額以上の値段で販売し、差額を利益とする仕事です。一般的に、実店舗やネットショップなどで仕入れを行い、販売はネットで行います。
せどりで稼ぐためには、売れる商品を見極める力が必要です。最初はなかなか売れずに苦労するケースもありますが、慣れてくれば大きな収入も期待できます。
仕入れや販売の作業を外注化すれば、自分で手間をかけずに稼げるシステムを構築することも可能です。上級者になると、せどりだけで年収1,000万円を超えることもあります。
| おすすめポイント | ・コツをつかめば大きく稼げる可能性がある ・ショップを立ち上げるのに比べ、費用を抑えられる |
| 注意点 | ・中古品を売る場合は古物商許可が必要 ・商品が売れなければ在庫を抱えるリスクがある |
| 平均時給 | 1,000円〜 |
31. 写真販売
「写真販売」は自分で撮影した写真を販売する仕事です。一般的には、PIXTAや写真ACなどのストックフォトサービスで写真を販売します。
一度登録した写真は何度も購入される可能性があるため、人気の写真を撮影できれば不労所得も期待できます。好きな時間に撮影できる点もメリットです。
ただし、写真販売で稼ぐためには、ある程度の撮影量が必要となります。ニーズを押さえた写真を撮れるよう、需要を理解したりスキルを高めることも求められます。
| おすすめポイント | ・写真が好きな人なら楽しみながら稼げる ・人気の写真は半永久的に売れ続ける可能性がある |
| 注意点 | ・本格的に取り組むなら機材の用意が必要 ・稼ぐためには写真撮影に関するスキルの向上も不可欠 |
| 平均単価 | 写真1枚当たり数十~数百円 |
家でできる正社員の仕事6選
完全に自宅で仕事をするのは難しいものの、業界や企業によっては、一部在宅勤務が可能な正社員の仕事も多くあります。そのなかから、代表的な職種を5つ紹介します。
32. 営業、CS
「営業」や顧客の困りごとを解決する「CS」(カスタマーサポート)は、以前は対面でおこなうことが多い職種でした。しかし、オンライン化が進んだことで、最近は在宅勤務可能な求人も増えています。
営業の場合、販売する商材によっては基本出社が必要な会社もあります。一方で、オンラインで商談から契約まで交わす営業スタイルを取り入れている会社も出てきています。
| おすすめポイント | ・未経験可の求人が多い ・歩合給がある場合、成果次第で高収入を目指せる ・困っている人の助けになる |
| 注意点 | ・コミュニケーション能力が必須 ・相手の要望をくみ取る洞察力が必要 ・顧客との電話対応がある場合、静かに仕事ができるスペースが必要 ・商品知識が必要 |
| 平均年収 | 営業:300万~600万円 CS:250万~350万円 |
33. マーケティング
「マーケティング」は、ユーザーのニーズを分析し、商品やサービスを販売するための企画や戦略を練る仕事です。メーカーや販売店に就職するケースと、マーケティング支援をおこなう会社に就職するケースがあります。
特にWebマーケティングは、需要が増えている分野です。SNSやインフルエンサーを起用する手法もあり、普段から利用している人にとっては馴染みやすい仕事でしょう。若い女性をターゲットにしたマーケティングの需要が高いことから、女性が活躍しやすいという特徴もあります。
| おすすめポイント | ・年収の水準が高い ・女性が活躍しやすい職種 ・関わった商品のリリースやイベントが成功した際には達成感を味わえる |
| 注意点 | ・企業規模や扱う商品によって年収に幅がある ・一通りの業務を覚えるまでは年収は標準的 ・トレンドや最新情報の収集が求められる ・分析力、洞察力が必要 |
| 平均年収 | 500万~600万円 |
34. 制作、ディレクター
「制作、ディレクター」職は、広い意味でいうと制作現場の指揮をとる仕事です。たとえばWebディレクターなら、デザイナーやプログラマーなどWebサイト制作に関わるさまざまな人をとりまとめ、プロジェクト全体の進行管理をおこないます。
そのほか、広告ディレクター、テレビディレクター、映像ディレクター、出版ディレクター、空間ディレクター、イベントディレクターなど、さまざまな業界に、さまざまなディレクター職が存在します。
制作、ディレクター職の場合、外部折衝で外に出ることもありますが、企画の立案に必要な取材や作業はオンラインでできるため、在宅ワークが可能です。
| おすすめポイント | ・クリエイティブ職のなかで年収が高い ・美術やデザインの知識を活かせる ・プロジェクトが成功した際は達成感を味わえる |
| 注意点 | ・コミュニケーション能力や折衝力が求められる ・発想力が必要 ・リーダーシップが求められる |
| 平均年収 | 300万~600万円 |
35. 人事
「人事」は、企業の人材管理に関する業務をおこないます。具体的には、社員の採用、教育、配置、評価や、社員が能力を発揮するための仕組みづくりなどに携わります。
機密情報を多く取り扱う部署のため、完全に在宅で仕事ができる会社は多くありません。しかし、最近は会社説明会や面接などもオンライン化が進んでいることから、一部在宅勤務可能な人事の求人も増えています。
| おすすめポイント | ・経営陣のパートナー的存在として、企業運営の一端を担える ・会社の顔として採用活動に携われる |
| 注意点 | ・人への関心が高く、人と関わり合うのが好きな資質が求められる ・コミュニケーション能力が必要 ・機密情報を守る必要がある |
| 平均年収 | 450万~550万円 |
36. バックオフィス、コーポレート系
「バックオフィス、コーポレート系」とは、営業などと違って直接は利益を生まない部署、企業経営の管理業務をおこなう部署全般を指します。総務、経理、法務、財務、広報、事務など、さまざまな職種が含まれます。「直接利益を生まない」というとネガティブに聞こえるかもしれませんが、企業活動には欠かせない業務です。
企業の規模、業態、職種によって仕事内容は異なりますが、社内の人とのやりとりが主な仕事です。このため自宅でできる業務も多いですが、管理部門として機密情報を扱うケースも多く、場合によって出社も必要になります。
| おすすめポイント | ・専門知識を磨ける職種もある ・会社を全体的な視点で見られる職種が多い |
| 注意点 | ・職種によって業務の内容や対応範囲が異なる ・ルーティンワークが多い職種もある |
| 平均年収 | 300万~500万円 |
37. 広報
「広報」は自社PRのために情報を発信する仕事です。プレスリリースを作成して発表したり、取材に対応したり、イベントを企画したりと、企業の顔をもいえる業務を担当します。
メディアへの対応や資料のやり取りなどは電話回線とインターネット回線があれば完結できることが多く、在宅勤務のハードルは低いといえるでしょう。ただし社内や店舗での取材対応やイベントへの出演といった、現場でしかできない仕事を任せられることもあります。
| おすすめポイント | ・会社の顔として多方面で活躍できる ・仕事の反響を肌で感じられる |
| 注意点 | ・自分自身の言動がそのまま企業イメージにつながることも ・不祥事が起こったときに顔を出して対応しなければならないことがある |
| 平均年収 | 450万円前後 |
家でできる仕事ランキングTOP5【ジェイックおすすめ】
在宅でできる仕事のうち、ジェイックがおすすめする仕事をランキング形式で紹介します。いずれの仕事も正社員になれる可能性があるため、安定した収入を得たい方は、自分に向いた仕事があるかチェックしてみましょう。
1位 バックオフィス、コーポレート系
バックオフィス、コーポレート系とは、企業活動の根幹を担う部署の総称です。総務・経理・法務・人事・広報などが該当し、社員が働きやすい環境を整える役割があります。
正社員でも在宅勤務ができるケースが多く、企業の数だけ必要な仕事であるため、求人も豊富に出ています。過去に希望職種の経験があれば、採用されやすくなるでしょう。
2位 IT系(プログラミング、SE)
プログラミングやSEといったIT系の仕事は、PCがあれば仕事ができるため、正社員採用でも在宅でできるケースが多くなっています。年収が高い傾向にあることも魅力です。
高収入を目指したい人や、経験を積んで将来的にフリーランスとして独立したいと考える人は、IT系の仕事にチャレンジしてみましょう。ライバルと差別化するためのスキルや資格があれば、採用担当者に好印象を与えられます。
3位 テレマーケティング
テレマーケティングは電話を使って営業を行う仕事です。商品・サービスの説明や販促、営業のフォローなどを行います。見込み客のニーズを把握するのもテレマーケティングの仕事です。
電話とPCがあれば仕事ができるため、特別な準備は基本的に不要です。正社員として募集している求人も多く、安定した収入を得たい方にもおすすめできます。
4位 人事
人事とは社員の採用・教育・配置や評価制度の構築などを行う仕事です。近年は人事の仕事を在宅で行う企業が増えています。正社員募集の求人が多い点もうれしいポイントです。
人事が在宅で円滑に業務を進めるためには、コミュニケーションツールやWeb会議ツールの準備が必須です。また、社員の勤怠管理も行う必要があるため、勤怠管理ツールの使い方を覚える必要もあるでしょう。
5位 Webデザイナー
Webデザイナーは主にWebサイトのデザインを行う仕事です。PCがあれば業務を行えるため、作業環境を整えれば家でも仕事ができます。企業によっては正社員として募集しているケースもあります。
Web関連の人材不足が深刻化する中、Webデザイナーの需要は増えており、今後もこの状況は続くでしょう。スキルを磨いて経験を積めば、将来的な独立を目指すことも可能です。
家でできる仕事をする3つの方法
家でできる仕事をする方法は、働き方の形態によって「正社員」「個人事業主」「起業」の3つの種類に分けられます。それぞれの方法について、くわしく解説します。
1. 正社員として自宅でできる仕事をする
在宅勤務可能な会社に就職すれば、正社員として家で仕事ができます。ワークライフバランスを重視する風潮や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などによって、多くの企業がリモートワークを取り入れるようになりました。その結果、最近では在宅勤務を前提とした社員募集の求人も多くなっています。
就職して正社員として在宅勤務する場合、細かい条件は会社によって異なります。在宅勤務可能な求人に応募する場合、次のような点を確認しましょう。
- フルで在宅勤務可能なのか、週に何日かは出社しなければいけないのか
- 初日から在宅勤務可能なのか、一定期間出社してから在宅勤務可能になるのか
- 自宅で仕事をするのに必要な経費の負担は?
募集要項に在宅勤務可能とあっても、日数が限定されていたり、研修期間は出社が必要な場合もあります。また、自宅での仕事に必要な通信費などは持ち出しの費用でも、パソコンなどのツールは、セキュリティの観点からも支給されることが多くなっています。
2. 個人事業主として家でできる仕事をする
個人事業主になって在宅でできる仕事をする方法もあります。個人事業主とは、株式会社などの法人を設立せずに、個人で独立して事業をおこなう人のことで、フリーランスと呼ばれることもあります。主に業務委託として仕事を受注します。
業務委託は、正社員やアルバイトなど企業に雇用される働き方と違って、案件ごとの契約になります。スポットで働くこともできるので、副業にもおすすめです。ただし収入は、案件によって単価や報酬が異なるため、月給制の正社員と比較すると安定しません。未経験可の案件も多いですが、単価が低いものや単純作業が多くなります。
個人事業主として家で仕事をする場合、次のような業務を、すべて自分でおこなう必要があります。
- 仕事の受注・営業
- 契約
- スケジュール管理
- 請求書の発行
- 帳簿付け・確定申告
- 仕事に必要なツールの用意・管理
仕事を受注して業務委託契約を取り交わすときには、契約書を用意し、しっかり内容を確認することが大切です。特に報酬や納期は重要なポイントです。業務委託契約は基本的に成果報酬となるため、期日までに成果物を納品しなければ報酬が得られません。請求書発行や帳簿付けなども、大切な業務です。また、パソコンなど業務に必要なツールは、基本的に自分で用意する必要があります。
3. 起業して家でできる仕事をする
起業して自宅でできる仕事をするのもひとつの方法です。ただし、独立して自分で会社を立ち上げるにはある程度資金が必要で、立ち上げるビジネスによっては大きなリスクを負わなくてはならない場合もあります。
独立するには、主に3つのパターンがあります。1つ目は、個人事業主としてある程度稼げるようになったら法人化するパターンです。この場合、ある程度ビジネスが軌道に乗ってから起業するため堅実ですが、個人事業主としてビジネスを成功させることが前提になります。
2つ目は、セルフプロデュースで自分を売り出すパターンです。たとえば、次のようなビジネスがあります。
- ブロガー
- YouTuber(ユーチューバー)
- インスタグラマー
- オンラインサロン・講師
少ない資金で始められるものもありますが、成功するにはセンスが問われる分野です。
3つ目は、自宅兼店舗を構えて営業する方法です。
- カフェ
- ピアノ教室
- 英会話教室
- 料理教室
- ネイルサロン
自宅に店舗を構えることで、開業資金をおさえられます。活かせる趣味や特技があれば挑戦しやすいでしょう。
家でできる仕事の平均月収
在宅でできる仕事にはたくさんの種類がありますが、実は生活ができるほど稼ぐことは簡単ではありません。自宅でできる仕事の平均月収と、安定収入を得るための方法を紹介します。
在宅ワークをする約半数は月収9万円以下
厚生労働省が発行する『在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン』によると、在宅ワークをおこなっている人の「過去1年間における在宅ワークの仕事による平均的な月収」は、全体の45.7%を占める人が9万円以下と回答しました。
在宅ワークでも、高度な専門スキルを持っている人ならもっと稼ぐことが可能です。実際に、30万円以上と回答した人は22.3%にのぼり、そのうち8.7%は50万円以上と回答しています。
しかし、多くの人は1ヶ月あたりの手取りが9万円以下で、副業やパート、アルバイトならまだしも、生活するには厳しい金額です。高度な専門スキルを持っていない人が在宅ワークで生計を立てるには、働き方を工夫する必要があることがわかります。
出典:厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」
安定収入を得たいなら正社員がおすすめ
これから在宅ワークを始める人や、専門的なスキルや経験がない人が家でできる仕事をするなら、在宅勤務可能な会社に就職するのがおすすめです。正社員として家で働くことには、次のようなメリットがあります。
- 給与として安定した月収を得られる
- 働きながら専門的な知識やスキルを磨ける
- 副業で別のスキルや経験を積むこともできる
- スキルや経験を活かして将来的に独立を目指せる
正社員として働けば、在宅ワークでも給与として安定した収入を得られます。また、収入を得ながら知識やスキルを習得し、独立や収入アップを目指せます。
個人事業主や起業する場合に比べて、正社員なら在宅ワークでも働くスケジュールが決まっていて、やるべき仕事も限定的です。自己管理に自信がない人やひとつの仕事に集中したい人にもおすすめです。
自宅で仕事をする3つのメリット
自宅で仕事をすることには、時間的にも金銭的にもたくさんのメリットがあります。
1. 通勤をしなくてよい
最大のメリットは何といっても「通勤する必要がない」ということです。首都圏では通勤に片道1時間以上かけている人も多く、旅行サイトの調査によると、働いている人のうち6割以上の人が通勤をストレスに感じています。通勤しないことによりストレスから開放されるだけでなく、次のようなメリットがあります。
- 満員電車に乗らなくていい
- 職場への移動時間がゼロになる
- 交通費(電車代・バス代・駐車代など)がかからない
- 通勤用の服や靴を揃えなくてもいい
- 体力を温存できる
- 女性の場合はメイクを省略できる
さらに、通勤中につい寄り道をして買い物や外食をしてしまう人なら、外出しないことで余計な出費を減らし、外食をやめることで健康にもプラスになるでしょう。
2. 家庭・他の仕事と両立しやすい
「育児」や「介護」など家庭内でやることがある人には、家庭内の用事や家事と仕事を両立しやすいというメリットがあります。また、別の仕事とのかけもちをしたり、副業として収入を得たりすることも可能です。両立の例をみてみましょう。
- 子供が幼稚園に行っている時間を利用して仕事をする
- 農業や観光業など時期によって波がある仕事のオフシーズンに在宅で働く
- 稼業を手伝いながらスキマ時間を活用する
- 劇団やバンド活動と両立しながら空いた時間に働く
自宅での仕事は時間の自由がききやすいため、歌手や声優などの夢を追いかけながら働きたい人や、本業の忙しくない時期だけ別の仕事をしたい人にも向いています。
3. 集中しやすい
自宅での仕事は自分で好きなように環境を整えられるうえ、電話を取ったり来客の応対をしたりすることもありません。同僚に話しかけられることもないので、目の前の作業に集中できます。
- 室温や湿度、BGMなどを自分好みに合わせてコントロールできる
- 好きなタイミングで休憩できるので集中力を維持しやすい
- コピー用紙の補充や備品の発注など、雑用全般をしなくていい
- 早朝や夜間など自分が集中できる時間帯に働ける
仕事内容にもよりますが、自宅で仕事をするなら、働くペースを自由に決められます。集中できる環境や時間帯は人それぞれ。自宅で仕事をすれば、「周囲が静かな深夜のほうが仕事がはかどる」「さわやかな早朝に働きたい」など、自分のタイプに合わせた働き方もでき、集中しやすいのです。
自宅で仕事をする3つのデメリット
自宅で仕事をすることはメリットばかりというわけではなく、デメリットもついて回ります。よくあるデメリットをチェックしておきましょう。
1. 同居人が気になる
自宅に家族や同居人がいて、その人のお世話が必要だったり、ひんぱんに話しかけられたりする場合は、仕事の効率が落ちてしまいがちです。在宅なら子どもの世話をしながら働けますが、「まだ小さくて一人で遊べない」「歩き始めたばかりでずっと見ていないといけない」という状況だと、実際に自宅で育児と仕事を両立させるのはかなり大変。結果的に仕事も育児も中途半端になってしまう、なんていうこともあるでしょう。
- 子供から目が離せない
- 家にいる人に話しかけられて集中力が途切れてしまう
- 来客が多く応対しなくてはならない
- 同居人がテレビやラジオをつけていて音声が気になる
こういったことがデメリットとして考えられます。
また、同居人に問題がなくても、「自宅が繁華街にあり、周囲がにぎやかで集中できない」「外で長期間にわたって工事をしていてうるさい」など、環境がマイナスになることもあります。
2. 誘惑に負けやすい
自宅には上司や同僚がおらず、他人の目がないので、仕事をサボっても誰にも怒られません。そのため誘惑に負けやすく、結果として仕事がおろそかになってしまいがちです。
- 寝坊してしまい予定通りの時間に仕事を始められない
- 何時間も昼寝をしてしまう
- ゲームがなかなかやめられない
- 動画をずっと見てしまう
- SNSに入り浸ってしまう
こんなふうにダラダラと過ごしてしまうと、いつまで経っても仕事が終わりません。誘惑に弱い自覚があるのなら、負けないための工夫も必要です。
- 仕事専用の部屋を作る
- スマホやパソコンをプライベート用と仕事用に分ける
- 誰かに監視を頼む(オンライン会議をつなぎながら作業する)
こういった方法である程度は対策できますが、そのぶんお金や手間もかかるので、ある程度は強い意思を持って誘惑を跳ね返すことも大切です。
3. ツールを揃える必要がある
会社員なら仕事に必要なツールは会社が用意してくれますが、自宅で仕事をするとなると、自分で手配をしなければならない場合があります。
- パソコン
- プリンター
- インターネット回線
- 電話回線(スマートフォン)
- セキュリティ対策のためのソフト
- 椅子や机
- 文房具
どんな仕事をするにしても、このくらいは揃っていないと自宅で仕事をするのは難しいでしょう。ただし、会社で準備してくれる場合もあるので、仕事を始める前に「仕事をするのにどんなツールが必要なのか」「会社はどこまで支給してくれるのか」をしっかりと確認しておいてください。
自宅で仕事をするのに向いている人3選
人によって得意なことや好きなことが違うように、在宅での仕事にも向き不向きがあります。自宅で仕事をするのに向いている人の特徴について解説します。
向いてる人1.自己管理ができる人
自宅で仕事をするのに向いている人は、自分でスケジュールを管理でき、仕事とプライベートの区別をきっちりとつけられる人です。自宅には何かと誘惑が多いので、いかにセルフマネジメントできるかがカギとなります。
- 自主的に毎日規則正しい生活が送れる
- 無理のないスケジュールを立てられる
- 自分が立てたスケジュール通りに仕事を進められる
- イレギュラーなできごとがあっても対応できるような余裕を持てる
こんな人なら自宅で仕事をしても誘惑に負けることなく、きっちりと職務をこなせるでしょう。
また、仕事上のマネジメントだけでなく、健康管理も欠かせません。自宅で仕事をすると出歩く機会が減り、どうしても運動不足になってしまいます。ストレッチや筋トレ、ジョギングなどを取り入れ、食事にも気をつけて過ごすことが大切です。
向いてる人2.専門スキル・知識がある人
自宅での仕事は専門知識が求められるジョブ型のものが多いので、何らかの専門スキルを持っているほうが有利です。デジタルコンテンツに関わるクリエイティブ系やエンジニア系、もしくはコンサルタント系の専門スキルや知識を持っている人なら、明日からでも自宅で仕事を始められるでしょう。
裏を返せば、これといった専門スキルがない人は初心者や未経験者でも可能な仕事からスタートしなくてはならず、最初は報酬が安かったり仕事がなかなか見つからなかったりするかもしれません。とはいえ、その分野で実績を積んでいけば少しずつ仕事の幅は広がっていきます。専門スキルがないうちは、専門性を身につけるためにコツコツとがんばることも大切です。
向いてる人3.主婦・主夫
自宅にいる時間が長い主婦や主夫は、自宅で仕事をするのに向いています。
こんな人は、外で働くよりも、時間の自由がきく自宅での仕事だと都合がいいですよね。実際、在宅可案件を多く取り扱っている主婦専門の求人サイトやサービスは少しずつ増えています。自分の持っているスキルでこなせる仕事や、条件に合った仕事、チャレンジしてみたい仕事を探してみましょう。
- 配偶者が外に働きに出ているので家事全般を担当している
- 子育てや介護があり外で働くのが難しい
- 近くにパート・アルバイトとして働けるようなお店や施設がない
- 配偶者に転勤が多く、勤めに出てもすぐに辞めなければいけない
- 妊活中なので体に負担をかけずに働きたい
自宅で仕事をするのに向いていない人3選
自宅で仕事をするのに向いている人の特徴を把握できたところで、反対に向いていない人の特徴もご紹介します。
向いていない人1.家では休みたい
家はのんびりくつろぐ場所と決めているような、環境によってオンとオフが切り替わる人は、自宅で仕事をするのには向いていません。こういう人は、自宅ではなかなか「仕事モード」に切り替えられないからです。
この場合の解決策として有効なのは、自宅の中で「休む場所」と「仕事をする場所」を決めておくことです。「仕事部屋には仕事に必要なものしか置かない」「リビングには仕事を持ち込まない」など、ルールを明確にしておきましょう。家族や同居人がいる場合は、仕事部屋にいるときは話しかけないように頼むなど、仕事モードを維持できる環境づくりが重要です。
向いていない人2.総合的に色々な仕事をしたい
在宅でできる仕事は専門性が高いものが多く、基本的には毎日同じ業務を続けることになるので、「いろいろな仕事を経験してみたい」と考えている人にはあまり向いていません。「営業もしてみたいし、クリエイティブ部門にも関わってみたい」といった希望があるなら、企業の総合職がおすすめです。
「やりたいことが決まっていない」「自分に合った仕事が何なのか分からない」という場合も、まずは就職してさまざまな業務を経験したほうが自分の可能性が広がります。
向いていない人3.人と会って話すのが好き
自宅での仕事は、基本的にリモートワーク(テレワーク)で、朝から晩まで一人です。とくにジョブ型の仕事では黙々と作業に没頭することになるので、常に周囲とコミュニケーションを取りながら仕事を進めたい人には不向きでしょう。「同僚とのランチが楽しみ」「人と話していたほうがアイデアがひらめく」という人は、作業効率が落ちたり、知らず知らずのうちにストレスを溜めてしまったりすることもあります。
ただ、リモートワークをしているスタッフ同士のコミュニケーションを重視している会社も少なくありません。「一人で作業をするのが苦手だけれど、事情があって自宅で仕事をしたい」という人は、求人を探すときにその点もチェックしてみてください。
家でできる仕事で稼ぐ3つのポイント
自宅でできる仕事で稼ぐためには、スキルを得ること、人脈を築くこと、独立することを意識しましょう。3つのポイントについてくわしく解説します。
1. 専門スキルを身につける
在宅でできる仕事で高収入を得るなら、専門スキルや資格があることは大きな強みになります。専門スキルがないとできない仕事、特定の資格がある人でないとできない仕事は、そのほかの仕事と比較して収入が高いことが特徴です。
例えばライターでも、「金融関係に強い」「法律関係に強い」など、専門分野があると単価が高くなります。さらに、金融関係ならファイナンシャルプランナー、法律関係なら行政書士など、資格や肩書きがあることでより高い報酬をのぞめます。
ただし、仕事によっては、資格や経歴だけでなく、業務での実績が重視される場合もあります。たとえば、プログラミングやデザインの仕事をする場合、学校に行ってスキルを学ぶこともできますが、在宅で仕事を始めるなら、実務経験がある程度必要です。
2. 正社員になってコネをつくる
家でできる仕事の種類や働き方が増え、ネットでもさまざまな仕事を探せるようになりました。しかし、ネットで案件を探す場合、仕事を依頼する側との関係性が構築できていないため、まずはスポットでの依頼になったり、経験者でも比較的安価な報酬でスタートしたりすることが少なくありません。
一方、知人から直接仕事を依頼される場合や紹介案件の場合、あらかじめ仕事を依頼する側との間に信頼関係が築かれているため、安定した仕事の受注や報酬が見込めます。
在宅での仕事に有利になる人脈を獲得するなら、まずは就職するのが近道です。正社員として勤務しながらお得意様を見つけておくことで、退職して個人事業主になった際や自分の会社を立ち上げた際、お得意様からパートナーとして仕事を受けることができます。
3. 独立する
経験やスキルを習得し、仕事につながる人脈を築けても、受託案件では報酬の相場はある程度決まっているため、それ以上報酬を引き上げることは難しくなります。また、仕事の単価が上がっても、一人でできる仕事量には限界があるため、大きく稼ぐには限度があります。
しかし、独立して法人化することで人に業務を依頼する立場になれば、請け負う仕事量を増やせます。起業には資金がいるなどリスクも伴いますが、結果として大きく稼げる可能性があります。
会社を立ち上げなくても、ブロガーやYouTuber(ユーチューバー)などであれば個人で始めることができ、頑張り次第では収入が青天井になる可能性もあります。ただし、安定して稼ぎ続けるのは大変です。
まとめ
家でできる仕事は数多くあります。以前はWebデザイナーなどのクリエイティブ系やプログラマーなど、在宅でできる職種は限定されていました。しかし、IT技術の発達で自宅にいてもスムーズに仕事ができるようになったことや、多様な働き手を活用しようという時流から、営業や人事、講師など、さまざまな仕事が自宅でできるようになりました。
なかには、未経験で気軽に始められるものもあります。しかし、報酬が低い、単純作業でスキルが身につかないなどのデメリットもあるため注意が必要です。
家でできる仕事で安定収入を得たいなら、在宅勤務が可能な会社に就職するのがおすすめです。正社員として在宅で働けば、安定した収入が得られるだけでなく、働きながら専門的なスキルや知識を習得することができます。将来的に、培った人脈を活かして個人事業主になったり、専門性の高い仕事で独立したり、収入アップのチャンスを見込めます。
ジェイックでは、自宅でできる仕事で安定した収入を得たい人に向けて、在宅勤務可能な求人も数多く扱っています。自分に向いている家での仕事を探したい人は、ぜひ相談してください。
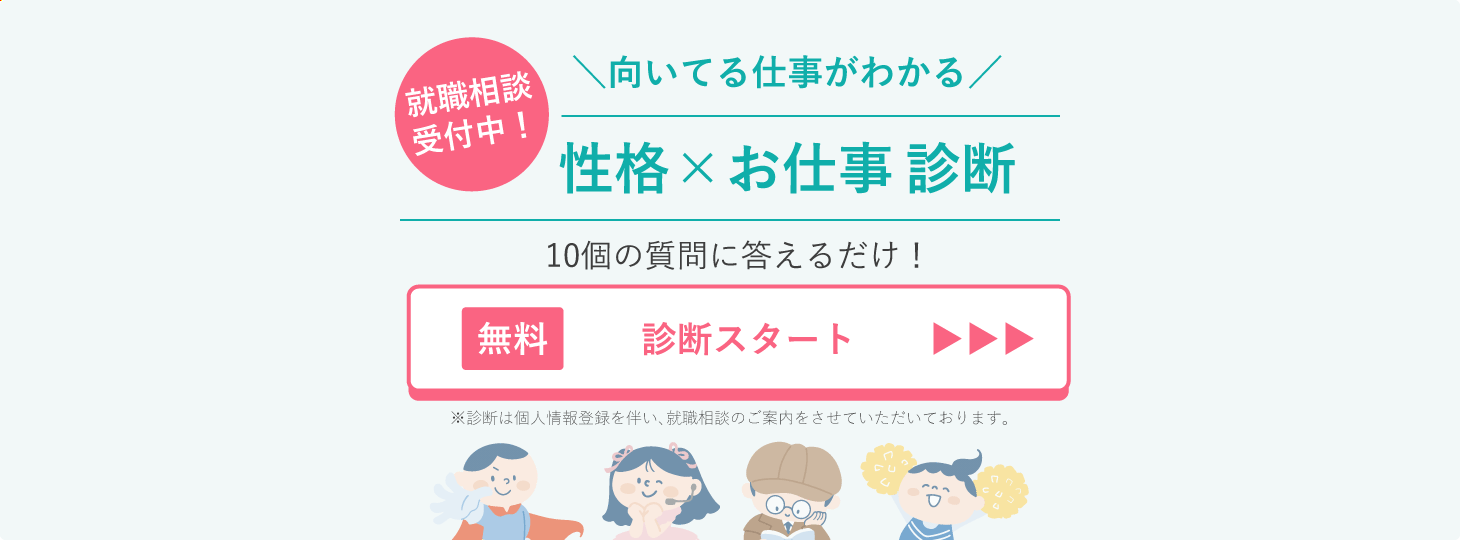

「家でできる仕事」に関するよくある質問
「資格や経験がなくても始められる仕事(ライター、データ入力など)」、「経験やスキルを活かせる仕事(企画・編集、デザイン、プログラミングなど)」、「人と接することが多い仕事(講師、コンサルティングなど)」、「自宅でできる正社員の仕事(営業、人事、マーケティングなど)」があげられます。
3つのポイントを意識しましょう。「専門スキルを身につけること」、「正社員になってコネ(人脈)をつくること」、「独立すること」です。
ジェイックの『就職相談』では、「あなたに適した仕事、働き方」を見つけるため「自己分析」のサポートも行っています。あなたの将来的な目標・意向・適性をふまえて、ご一緒に考えてみましょう。