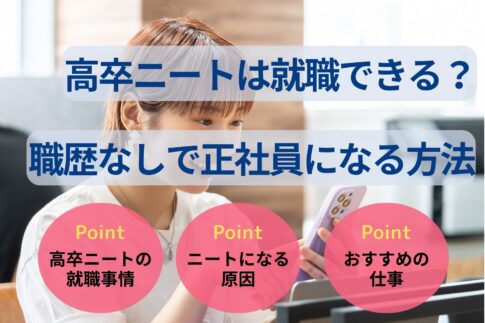退職勧奨を受けても、必ずしも転職に不利になるとは限りません。退職勧奨の理由や経緯によって転職活動での評価は異なり、もし就業先の企業に問題があった場合は、転職に不利になる事は基本的にないでしょう。
この記事では、退職勧奨が転職活動にどのように影響するのかや、不利になるケースはどういったものがあるのかについて詳しく解説します。
また、退職勧奨を受けた際の適切な対応についても解説しますので、冷静に今の状況を分析し、次のキャリアに進むための参考にしてみてください。
この記事の目次
退職勧奨されたら転職は不利になる?
退職勧奨を受けてから辞めた場合、転職活動で企業から「問題のある人材なのではないか」と疑われやすく、結果的に転職活動で不利になりやすいことがあります。ただし、退職勧奨の理由にかかわらず、丁寧な書類作成や前向きな姿勢を示すことで信頼を得る努力が不可欠です。
まずは、退職勧奨されたら転職に不利になるのかどうかについて、不利になるケースと不利にならないケースに分けて解説します。
不利になるケース
退職勧奨が転職で不利に働くのは、業務能力や勤務態度に問題があったとみなされるケースです。例えば業績が著しく低下していたり、何度指摘されても遅刻をしていた場合は、企業側が今後の勤務継続が難しいと判断して退職勧奨を受けることがあります。
また、架空の売り上げ計上や取引先に対する不利益を被らせたなど、懲戒に近い理由で退職勧奨を受けた場合は、転職活動においても「再びトラブルを起こしてしまうのではないか」と懸念を持たれ不利になるでしょう。
合わせて、転職活動の面接で前職の退職理由をうまく説明できないと、不利になりやすい点も理解しておいてください。
不利にならないケース
会社の経営悪化や戦略的な人員整理など、個人の能力や態度と関係のない理由で退職勧奨が行われた場合は、転職活動で不利にならないことが多いです。このようなケースでは、むしろ「自分にとって不利な状況に対しても柔軟に対応できる人」としてプラスに評価されることもあります。
面接においては「前向きに転職を決意した」「良い機会なので新しい環境でスキルを活かしたい」といった姿勢を伝えると、面接官からの印象も良くなります。このようなケースでは退職勧奨の事実を隠す必要はなく、正直に説明した上で今後の成長意欲をアピールしましょう。
そもそも退職勧奨とは?
そもそも退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を勧める行為のことであり、俗に「肩叩き」と呼ばれることもあります。解雇のように会社が一方的に退職を決定するのではなく、最終的な判断は従業員自身に委ねられている点が特徴です。
ここからは、似ているようで異なる会社都合退職と解雇の違い、合わせて希望退職や早期優遇退職との違いを整理して解説します。自分が受けている退職勧奨は何に該当するのか理解を深めておくことが大切です。
会社都合退職・解雇との違い
退職勧奨と会社都合退職・解雇は混同されやすいですが、法的な位置づけが大きく異なります。退職勧奨はあくまでも会社が自主的に辞めてほしいことを従業員に働きかけるものであり、本人の合意が必要な提案です。
一方、会社都合退職は、経営悪化や業務縮小など企業側の都合で退職せざるを得ない場合に用いられ、労働者の責任は問われません。さらに、解雇は従業員の合意なく、企業が一方的に雇用契約を打ち切るものであり、解雇するためには法律上の厳格な要件が定められています。
つまり、退職勧奨と会社都合退職・解雇との違いは、「退職するかどうかの最終的な判断が従業員に委ねられているかどうか」といった違いがあると言えます。
希望退職や早期優遇退職との違い
希望退職や早期優遇退職は、退職勧奨と目的や手続きの面で違いが見られます。希望退職は企業が一定の条件を提示し、応募した人だけが退職できる仕組みで、通常は退職金の上乗せなど優遇措置が設けられます。
早期優遇退職も同じく、一定年齢以上の社員を対象とした制度的な退職募集であり、従業員個人個人に退職勧奨を促すものとは異なります。言い換えれば、希望退職や早期優遇退職は、従業員の自主的な退職応募を募る企業のリストラ策の一種です。
退職勧奨は、企業の経営判断や人員整理の一環として行われることもありますが、個人の業務適正や勤務態度が影響するケースも少なくありません。希望退職や早期優遇退職と同じく、断る自由が保証されている一方で、拒否をすると会社との関係性が悪化するリスクがあるといった違いがあります。
退職勧奨となるケース
退職勧奨は企業が適当に行っているものではなく、一定の理由や背景があります。具体的には、社員の適性や勤務状況、会社の業績悪化などが背景であることが理由として考えられます。
ここからは、退職勧奨となる代表的なケースを2つ解説します。退職勧奨を実施する企業側の背景と意図を理解しておきましょう。
1.社風や業務内容などが社員に合っていない場合
社員の能力や性格が社風や業務内容に合っていない場合、会社は退職勧奨を行うことがあります。例えばチームワークを重視する社風の中で、個人主義的な働き方を執拗に続けている場合や、何度注意されているにもかかわらず、業績が一向に改善しない場合などが挙げられます。
この場合は、企業として本人が能力を発揮できる環境に移った方が良いと判断して、退職勧奨をしている意図が隠れています。表面上は穏やかに退職勧奨を受けていたとしても、実質的には活躍が難しいと判断されていることが多いため、冷静に受け止め次のステップを考えると良いでしょう。
なお、労働契約法では「客観的に合理的で、社会的に相当と認められる理由」がなければ解雇できないと定められているため、強制解雇とはなりづらいことを覚えておきましょう。
2.業績の悪化など
会社の業績悪化などを理由に人員整理が必要になった場合でも、退職勧奨を行うことがあります。この時、企業は一部の社員に対して退職を勧めることで、経営の立て直しを図るという意図があります。特定の年齢層や職種を対象に行われることが多く、特に業績やスキルに問題がある社員に声がかかることが一般的です。
本来であれば、整理解雇によって人員削減を行う事は可能ではあるものの、整理解雇には厳格な法的要件があるほか、解雇予告や解雇予告手当の支給が必要になるため、コストを避けるために退職勧奨をしていることも考えられます。
業績悪化による退職勧奨の場合、転職活動で「企業の経営方針によるもので、自身の成果や姿勢とは無関係」といった説明をすれば、不利な印象を避けられるでしょう。
違法な退職勧奨の例
本来、退職勧奨は本人の自由意思に基づく退職を前提としていますが、企業が不当な圧力や威圧、嫌がらせを加えるような場合は、違法な退職勧奨に該当する場合があります。
具体的には、退職を拒否した従業員に対し執拗に面談を繰り返したり、「このままでは評価が下がる」「居場所がなくなる」といった発言で、心理的に追い込む行為が挙げられます。
また、脅迫的な言動によって退職届の提出を迫ったり、退職を条件に有利な待遇をちらつかせるといったやり方も違法とみなされる場合があります。これらの行為で退職をせざるを得なくなったとしても、自由な意思に基づかない退職とされ無効となる可能性があります。
もし過度な圧力を受けていると感じたら、すぐに録音や記録を残し、労働組合や労働基準監督署に相談することがおすすめです。
退職勧奨に応じる場合・応じない場合の選択肢は?
退職勧奨を受けた場合は、すぐにその場で判断するのではなく、まず自分の状況や会社の意図を整理することが大切です。また、中長期的なライフプランを考える際にも、退職勧奨に応じる場合と応じない場合では、その後のキャリアや生活に大きな違いが生じます。
ここからは、退職勧奨に応じる場合と応じない場合の選択肢を詳しく解説しますので、それぞれのメリットやリスクを理解した上で最適な対応を選びましょう。
応じる場合
退職勧奨に応じる場合は、まず条件を確認することが重要です。会社が提示する退職金の上乗せや再就職支援等の優遇措置がある場合は、合意の前に必ず書面で内容を残しましょう。
退職勧奨に応じる場合は、会社を辞めて転職活動をすることになります。基本的には会社との関係性を保ちながら退職できる可能性が高いため、円満退職が実現できます。ただし、自己都合退職として処理されると、失業保険の受給開始が遅れることがありますので、会社都合扱いになるかどうかを事前に確認しましょう。
合わせて、空白期間をなるべく短くするためにも、転職に向けて計画的に動くことが大切です。
応じない場合
退職勧奨に応じないことで、解雇されるリスクを避けられる可能性があるものの、会社に居続ける居心地が良いとは言えません。まずはなぜ退職を勧められたのか、その理由を明確に聞くことが大切です。その上で業務改善の余地がある場合は、具体的な行動計画を考えておきましょう。
もし退職勧奨を拒否したことで、不当な配置転換や著しく低い評価を受けた場合は、弁護士や労働基準監督署への相談も検討しましょう。重要なのはその場の感情に踊らされることなく、すべてのやりとりを記録して残しておくことです。
冷静に対応すれば、退職を勧められたとしても、自分の意思を尊重してもらいつつ働きたい場所で働ける状況を守ることが可能です。
退職勧奨による退職は自己都合退職と会社都合退職のどっち?
退職勧奨によって退職した場合、最終的に従業員が退職を選んだとしても、基本的には会社都合退職として扱われます。ただし、会社が手続き上自己都合退職に分類して処理してしまうケースがあるため、退職勧奨を受けた際はあらかじめ会社都合退職になるかどうか確実に確認しておきましょう。
会社都合退職か自己都合退職かによって、ハローワークで失業保険を申請する際に、給付の開始時期や支給日数が大きく変わってきます。会社都合退職であれば、待機期間後すぐに給付を受けられる一方、自己都合退職になると数ヶ月間の待機期間が発生するため、金銭的に負担が大きくなります。
万が一、会社側が誤って自己都合退職に処理した場合でも、退職勧奨を受けた証拠があれば、ハローワークで訂正できることも覚えておいてください。
退職勧奨を受けたときの適切な対処法
退職勧奨を受けた際は、焦ってすぐに回答するのではなく、まずは冷静に状況や退職勧奨の背景を確認することが大切です。会社側から納得のいく回答がもらえた時点で、最終的には自分の指で判断する姿勢を持ちましょう。
ここからは、退職勧奨を受けた際にとるべき基本的な対処法を4つ解説します。
1.必ずしも退職勧奨に応じる必要はない
退職勧奨は解雇とは異なり、あくまでも企業側の退職の提案に過ぎないため、従業員が同意しない限り退職にはなりません。会社の説明を鵜呑みにすることなく、まずは冷静な姿勢を保つことで、不当な圧力や強制を防ぎやすくなります。
また、退職を勧められた際は、会話内容を録音したりメモを取ることで、後々の法的なトラブルを防げる点を意識しておきましょう。ただし、退職を拒否して会社に残ったとしても、職場で居心地の悪さを感じたり、努力が正当に評価されない環境に置かれるリスクがある点は注意が必要です。
2.会社に退職勧奨を行った理由を確認する
退職勧奨を受けた場合は、その事実を受け止めつつも、なぜ退職勧奨に至ったのかの理由を確認することが重要です。企業の意図が業績悪化なのか、それとも自分の適性の問題なのかによって適切な対応の仕方は大きく変わります。
退職勧奨の面談においては「どのような点が問題とされたのか」「自身の努力での改善の余地はあるか」などを具体的に確認しましょう。曖昧な回答しか得られない場合は、文書での説明を求めるのも有効です。
万が一退職勧奨の指摘が解雇や懲戒解雇にあたるような場合は、退職勧奨に応じるメリットも考えられます。理由を正確に把握し、事実に基づいた判断を意識しましょう。
3.会社の退職条件に正当性があるかどうか確認する
退職勧奨を受けた際は、退職時期や退職金等の条件が提示されることが一般的なため、その内容が妥当かどうかを慎重に確認することも重要です。これらの条件は、後々のトラブルを避けるためにも、口頭だけでなく文書で明示してもらうように心がけましょう。
退職条件が不透明なまま退職勧奨に合意してしまうと、金銭的な負担を被ることもあります。また、退職金制度がない場合でも、話し合いによって退職金や再就職支援といったサポートが受けられることもありますので、会社側から説明されていない事については積極的に質問することがポイントです。
4.辞めるなら転職先を探し始める
退職勧奨を受けて辞める判断をした場合は、スムーズに次の職場に移るため、在職中から早めに転職活動を進めることが望ましいでしょう。まずは就職エージェントやハローワークを利用して情報収集を行い、自分の経験やスキルを整理します。
また、退職理由を面接で聞かれた際は、「会社の方針変更をきっかけに、新しい環境で挑戦したいと考えた」など、前向きな表現を用いることがポイントです。なお、転職活動に時間がかかりそうな場合は、あらかじめ企業と退職時期の交渉をしておくと良いでしょう。
退職勧奨に応じて会社都合退職をするメリット
退職勧奨を受け入れて会社都合退職として扱われる場合、経済的にも手続きの面でもメリットがあります。特に失業保険の受給条件や退職条件の交渉面においては、自己都合退職よりも有利に進められることが多いです。
ここからは、退職勧奨に応じて会社都合退職をするメリットについて2つ解説します。
1.失業保険をより有利に受給できる
会社都合退職の場合、失業保険の給付が自己都合退職よりも早く開始され、かつ給付日数も長くなるといった大きなメリットがあります。具体的には、会社都合退職では7日間の待機期間後すぐに給付が開始されるのに対し、自己都合退職では原則3ヶ月の給付制限があります。
受給できる日数は勤続年数によって異なるものの、会社都合退職の方が最長で180日長く設定されています。例えば35歳で勤続5年の場合は、自己都合退職であれば90日ですが、会社都合退職なら180日と、1ヵ月半も失業保険の受給期間が長引きます。
退職勧奨を受け入れることで、次の職場を見つけるための余裕が時間的にも経済的にも生まれやすくなる点を覚えておきましょう。
2.退職条件を調整しやすい
退職勧奨はあくまでも会社からのお願いであり、従業員側にも交渉の余地があります。例えば特別退職金の上乗せや解決金の支給、有給休暇の買取から再就職支援サービスの提供まで、退職条件を交渉しやすいといったメリットがあります。
また、退職日を調整することで転職活動のスケジュールを合わせやすくなるため、交渉を行う際は冷静に事実を整理しつつ、生活への影響や再就職準備のための時間など、合理的な理由を伝えると良いでしょう。条件面を適切に調整し、納得のいく退職を意識してください。
退職勧奨を受けたときの退職理由の伝え方
退職勧奨を受けた場合は、どんな理由であっても履歴書や面接での伝え方次第で印象は大きく変わります。事実を正確に伝えつつも前向きな姿勢を示すことで、退職勧奨が不利にならずに済みます。
ここからは、退職勧奨を受けたときの退職理由の伝え方について、書類作成と面接での伝え方に分けてそれぞれ詳しく解説します。
履歴書・職務経歴書への書き方
退職勧奨を受けた場合でも、履歴書や職務経歴書には事実に沿った上でポジティブに記載することが大切です。例えば、履歴書の退職理由欄には「会社の方針変更により退職」や「事業再編のため退職」といった客観的な表現を用いると良いでしょう。
職務経歴書においては、通常の転職活動と同様に、これまでの実績やスキル、強みを具体的に記載しつつ、前職でどのような評価を上げたのか明確に示すことがポイントです。
ネガティブな事情よりも、自分の経験をどのように活かせるのかを重視した内容にすれば、採用担当者に前向きな印象を与えられます。
面接での回答例
面接では、退職勧奨を受けたことをどのように受け止めたのかや、どうやって次に活かしていきたいと考えているのかを回答することがポイントです。伝え方によって採用担当者に与える印象が大きく変わるため、良い伝え方をできるよう面接対策しておきましょう。
良い伝え方
退職勧奨を受けた場合でも、「そのまま会社に勧められて退職した」と伝えると、ネガティブに聞こえることがあります。
面接ではどんなことでもポジティブに表現することが効果的なため、例えば「前職では組織再編により環境が変化しましたが、自分のスキルがより活かせる場を求めて転職を決意しました」といった表現がおすすめです。
また「これまで培った営業経験をより幅広い業界で発揮したいと考えました」といったように、転職理由と成長意欲を結びつけることも効果的です。
悪い伝え方
面接では感情的になって会社の悪口を言ったり、不必要に詳細な経緯まで話す事は避けましょう。例えば「上司がひどくて働けなかった」「会社の方針が理解できなかった」といった表現は、責任転嫁に聞こえてしまうような悪い伝え方です。
また、「自分だけが退職を勧められた」などと具体的な状況を強調しすぎると、面接官にネガティブな印象を与えかねません。退職理由を説明する際は、前向きな転職を決意したという結論を置いた上で、自身の成長やキャリアの方向性を中心に話す意識を持っておいてください。
退職勧奨の転職でよくある質問
退職勧奨を受けた際の転職活動では、退職理由の扱いや転職先への影響など様々な疑問が生じます。ここからは、退職勧奨を受けてからの転職でよくある質問を4つ取り上げて解説します。
退職勧奨は自己都合退職になる?
退職勧奨による退職は、原則として会社都合退職として扱われます。会社の意向で退職を促された場合は、従業員が退職届を提出したとしても、実質的に自己都合退職ではなく会社都合退職と認められるケースが多いです。
会社退職であれば、失業保険の受給条件も有利になりますので、ハローワークでの申請時には必ず理由部分を確認することがポイントです。
会社都合の退職は転職先にバレる?
会社都合の退職は、基本的に転職先でバレないと思っておいて良いでしょう。ただし、雇用保険被保険者証や離職票を求められた場合など、一部の手続きで判明する可能性はゼロではありません。
面接時には、経営上の都合や組織変更など客観的な理由を伝え、前向きな転職理由に言い換えることを意識しておいてください。
退職勧奨を断るとどうなる?
退職勧奨はあくまでも会社のお願いであり、退職勧奨を受けたからといって、労働者に退職の義務はありません。したがって、退職勧奨を断った場合でも、基本的にはこれまで通り働き続けることが可能です。
ただし、退職勧奨を受けたという事は、少なからず自分の仕事にネガティブな面が見られるとも考えられますので、そのまま働き続けていると、居心地の悪さを感じることがある点はリスクとして認識しておきましょう。
退職勧奨されたときの答え方は?
退職勧奨を受けたときの答え方は状況によって異なりますが、基本的には即答を避け、検討の時間を設けてもらうのが無難です。例えば「突然のことで整理がつかないため、少し考える時間をください」といった答え方が良いでしょう。
また、退職勧奨を受けた際は感情的に反応せず、冷静に状況を分析することが大切です。自分一人で判断がつかない場合は、家族や友人、就職エージェントなどに相談することがおすすめです。
退職勧奨を受けて会社を辞めるかは慎重に
退職勧奨は理由次第で転職に不利にも有利にもなります。企業からの違法な強要には応じる必要はなく、理由や条件を文書で確認し、自分で納得できる場合に退職勧奨を受け入れるといったスタンスを持っておくと良いでしょう。
また、退職勧奨を受け入れたいと考えたものの、転職活動で不利になるのではないかと不安を感じる場合は、書類添削や面接対策までサポートしているジェイックの就職支援サービスの利用を検討してみてください。