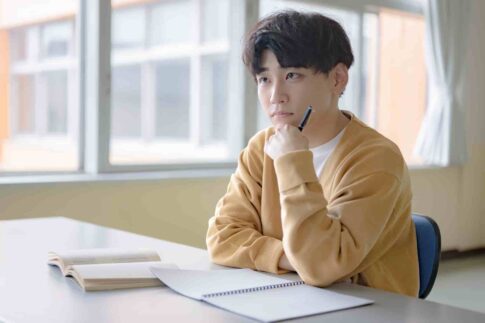施工管理は、学歴や経験に関係なく採用が活発な仕事なため、高卒の方でも多くの人が働いています。
施工管理に関連する資格は7種類あり、いずれも高卒で受験が可能です。資格を取得すれば、「資格手当」が支給される可能性もあります。
この記事では、高卒・未経験でも施工管理として働ける理由や、取得できる資格、年収事情について解説します。
施工管理の仕事内容も紹介しますので、仕事への理解を深めたい方もぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
高卒・未経験でも施工管理として働ける
施工管理は専門的な仕事ではありますが、多くの建設会社で未経験でも「見習い」として働き始めることができ、現場で実践的に学べる研修制度も整っています。
資格取得の支援体制を用意している会社も多く、働きながらスキルを身につけられる点も魅力です。
また、建設業界では人手不足と高齢化が深刻化しており、若手の採用が急務となっています。実際、国土交通省の調査を見ても、建設業就業者の約36%が55歳以上で、29歳以下はわずか11.7%しかいません(※)。
このように、未経験者を受け入れる体制が整っていること、そして若手人材の需要が高まっていることから、高卒・未経験でも施工管理として活躍できるチャンスが広がっているのです。
※出典:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」p.2,3
「見習い」から始められる求人が多いから
施工管理は専門性の高い仕事ですが、多くの建設会社では「見習い」として未経験から働き始めることができます。
実際、入社後は先輩社員とともに現場を回りながら、図面の読み方や安全管理の方法などを学べる研修制度を整えている企業が多くあります。
「1級建築施工管理技士」などの資格取得に向けたサポート体制がある会社も多く、働きながら必要な知識とスキルを身につけていけることも魅力の一つです。
このように学歴や経験がなくても成長しやすい環境が整っているため、施工管理は高卒・未経験でもチャレンジしやすい仕事といえるのです。
人手不足が深刻だから
建設業界は深刻な人手不足に直面しているため、高卒・未経験の人材でも積極的に採用している企業が多くあります。
国土交通省のデータによると、建設業の就業者数(令和4年平均)は約479万人で、ピークだった平成9年からおよそ30%も減少しました。
建設業就業者のうち55歳以上が35.9%を占める一方、29歳以下はわずか11.7%にとどまり、建設業界は高齢化も深刻化しています。
こうした背景から、若手人材の採用は業界全体の急務となっていることもあり、高卒・未経験でも施工管理として働きやすい環境が整いつつあるのです。
出典:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」p.2,3
施工管理の平均年収
施工管理の平均年収は「建築施工管理」が641.6万円(※1)、「土木施工管理」が596.5万円(※2)です。
建築施工管理のほうが年収が高いのは、都市部において高層ビルや大規模商業施設の建設プロジェクトなどが頻繁にあり、案件の単価が高いことなどが要因と考えられます。
上記の平均年収には大卒・大学院卒も含まれており、一般に高卒はこれらに比べると年収が低くなる傾向があります。そのため高卒の施工管理従事者の年収は、450〜550万円ほどを見込んでおくのが妥当でしょう。
とはいえ、高卒全体の平均年収は約460万円(※3)で、施工管理はそれを上回る水準のため、他の仕事以上に“稼げる仕事”と言われることも多いのです。
※1 出典:job tag「建築施工管理技術者」
※2 出典:job tag「土木施工管理技術者」
※3 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
平均年収=「きまって支給する現金給与額×12」+年間賞与その他特別給与額(従業員数10人以上/年齢計)
高卒が施工管理で高年収を手にする方法
高卒者が施工管理で高年収を目指すには、「1級建築施工管理技士」などの資格取得を目指すことが現実的な方法です。
資格手当によって月1〜3万円ほどの収入増が見込めるほか、専門知識を武器に現場責任者として活躍できるようになれば基本給アップも実現できます。
インフラ系や大手ゼネコンの現場に携わるのも一つの手です。規模の大きな工事を通じて貴重な経験が得られるため、市場価値の高い人材に成長できるでしょう。
中小建設会社では早くからリーダー経験を積める可能性もあり、昇給も期待できるため、高年収を手にしたい方はこうした会社を目指すのもおすすめです。
1. 資格取得を目指す
施工管理の資格を取得すると資格手当によって給料アップが期待できるため、高卒で高年収を目指す方は資格の取得がおすすめです。
実際、多くの建設会社では有資格者に対して資格手当を支給しており、月に1〜3万円程度の手当が支給されるケースも珍しくありません。
なかでも「1級建築施工管理技士」は2級と比べて給与が高くなる傾向にあり、高卒でも第一次検定の受検が可能です(※)。
1級を取得すれば現場責任者として活躍する機会も増え、基本給が大幅に上がる可能性もあります。施工管理で高収入を目指している方は、資格取得にチャレンジしてみましょう。
※試験実施年度に満19歳以上の場合、第一次検定を受検可能。第二次検定は実務経験などの要件あり
2. インフラや大手ゼネコンの現場に関わる
インフラ系の建設会社や大手ゼネコンが手掛ける現場は成長機会に溢れているため、高年収を目指す高卒の方はぜひ働きたい職場といえます。
インフラ工事や高層ビル建設などは規模が大きく、そこで得られる経験は非常に貴重です。建設業界において「市場価値」が高い人材へと成長できる可能性もあり、転職時にも高く評価されやすくなります。
インフラ系や大手ゼネコンは下請け企業(中小・中堅の建設会社や専門工事業者など)に多くの業務を発注しており、こうした会社では高卒・未経験の採用も活発です。そのため、まずは下請け企業への就職を目指すのも手といえるでしょう。
3. 若いうちからリーダー経験を積める職場で働く
リーダー経験を早く積めば積むほど昇進・昇給の可能性が高まるため、施工管理として高収入を目指す高卒の方は、若いうちから現場を任せてもらえる会社で働くことも検討しましょう。
たとえば中小建設会社の多くは人手不足に悩んでおり、学歴に関係なく、やる気のある若手に積極的に現場を任せる傾向があります。
実際、入社後2〜3年で小規模な現場の責任者になるケースも珍しくありません。
リーダー経験を積んでおくと社内での評価が高まり、出世にも有利に働くため、将来的に高年収を目指す方はリーダー経験を早く積める環境に飛び込んでみるのも手といえるでしょう。
高卒でも受験できる施工管理の資格7選
施工管理の資格は「施工管理技術検定」という枠組みの中に7つの資格があり、それぞれ高卒者にも受検資格があります。
- 建築施工管理技士
- 土木施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 電気通信施工管理技士
- 造園施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 建設機械施工管理技士
資格は全て1級と2級に分かれており、1級は大規模工事を管理でき、2級は中小規模の工事を管理できます。
また、1級・2級ともに「一次検定」と「二次検定」に分かれており、一次は年2回程度、二次は年1回実施されることも特徴です。
合格率は資格ごとに異なりますが、一次・二次ともに3〜5割ほどです。高卒者の合格率が5割を超えている資格もあるため、高卒でも十分に合格を目指せるでしょう。
▼施工管理技術検定 受検資格(2025年6月時点)
| 1級(一次検定) | 19歳以上(受検年度末時点) |
| 2級(一次検定) | 17歳以上(受検年度末時点) |
| 1級(二次検定)2級(二次検定) | 一次検定に合格し、一定の実務経験を積むことが条件(令和10年度までは旧受検資格も選択可) |
出典:国土交通省「令和6年度より施工管理技術 検定の受検資格が変わります」
※2025年6月時点の情報をもとに解説します。資格試験に関する情報は、各試験実施機関が提供する最新情報をご確認ください
1. 建築施工管理技士
建築施工管理技士は、建築物の新築、増改築、改修工事などの専門知識を持っていることを証明する国家資格です。
1級は管理できる工事の規模や職務領域に制限がなく、超高層マンションや公共施設など、大規模な工事を担当できます。
2級は中小規模の工事や、特定の分野に特化した現場管理に携わることができます。
令和6年度試験の合格率は、1級は一次検定・二次検定ともに3〜4割です。2級の合格率は、一次検定が約5割、二次検定は約4割となっています。
▼建築施工管理技術検定 合格率(令和6年度)
| 一次検定 | 二次検定 | |
|---|---|---|
| 1級 | 36.1%(29.5%) | 40.7%(22.6%) |
| 2級(前期) | 48.2%(43.4%) | - |
| 2級(後期) | 50.4%(42.2%) | 40.7%(38.1%) |
出典:一般社団法人 建築業振興基金「施工管理技術検定|過去の受検状況・検定問題・合格基準」
※カッコ内は、合格者全体に占める高卒者の割合
2. 土木施工管理技士
土木施工管理技士とは、道路、橋、ダムなどの土木構造物に関する専門知識を持っていることを証明する国家資格です。
1級は土木工事全般において、監理技術者・主任技術者として管理できます。
2級は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3分野に分かれており、資格を取得した分野において主任技術者として管理できます。
令和6年度試験の合格率は、1級は一次検定・二次検定ともに4割を超えています。2級の合格率は、一次検定が約4割、二次検定は約3割となっています。
▼土木施工管理技術検定 合格率(令和6年度)
| 一次検定 | 二次検定 | |
|---|---|---|
| 1級 | 44.4%(35.9%) | 41.2%(31.1%) |
| 2級(前期) | 43.0%(45.2%) | - |
| 2級(後期) | 44.6%(53.6%) | 35.3%(41.4%) |
出典:一般社団法人 全国建設研修センター「技術検定試験 合格発表公表資料」
※カッコ内は、合格者全体に占める高卒者の割合
3. 電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、電気設備工事に関する専門知識を持っていることを証明する国家資格です。
1級は、大規模な建設現場(総額4,500万円以上の工事など)に主任技術者・監理技術者として携わることができます。
2級は、主に小〜中規模の現場責任者として建設現場に携わることが可能です。
令和6年度試験の合格率は、1級の一次検定は約3割、二次検定は約5割です。2級の合格率は、一次検定・二次検定ともに約5割となっています。
▼電気工事施工管理技術検定 合格率(令和6年度)
| 一次検定 | 二次検定 | |
|---|---|---|
| 1級 | 36.7%(39.2%) | 49.6%(42.9%) |
| 2級(前期) | 49.7%(52.6%) | - |
| 2級(後期) | 47.4%(45.7%) | 51.4%(42.7%) |
出典:一般社団法人 建築業振興基金「施工管理技術検定|過去の受検状況・検定問題・合格基準」
※カッコ内は、合格者全体に占める高卒者の割合
4. 電気通信施工管理技士
電気通信施工管理技士は、電気通信設備工事に関する専門知識を持っていることを証明する国家資格です。
1級は、大規模な電気通信工事を管理でき、総額4,500万円以上の工事を請け負う「特定建設業」の管理業務が可能です。
2級は、中小規模の電気通信工事を請け負う「一般建設業」の現場で働けます。
令和6年度試験の合格率は、1級は一次・二次検定ともに約4割です。2級の合格率は、一次検定が6〜7割、二次検定が5割強となっています。
▼電気通信工事施工管理技術検定 合格率(令和6年度)
| 一次検定 | 二次検定 | |
|---|---|---|
| 1級 | 40.5%(29.5%) | 40.9%(32.6%) |
| 2級(前期) | 59.5%(29.2%) | - |
| 2級(後期) | 68.6%(39.2%) | 53.2%(37.8%) |
出典:一般社団法人 全国建設研修センター「技術検定試験 合格発表公表資料」
※カッコ内は、合格者全体に占める高卒者の割合
5. 造園施工管理技士
造園施工管理技士は、公園、庭園などの造園工事に関する専門知識を持っていることを証明する国家資格です。
1級は、商業施設の広大な緑地や、ゴルフ場など、大規模な造園の管理業務を担当できます。
2級は、1級造園施工管理技士の指示のもとで働く一方、中小規模の造園施工管理を担当することも可能です。
令和6年度試験の合格率は、1級は一次検定・二次検定ともに4割を超えています。2級の合格率は、一次検定・二次検定ともに約5割です。
▼造園施工管理技術検定 合格率(令和6年度)
| 一次検定 | 二次検定 | |
|---|---|---|
| 1級 | 45.4%(30.8%) | 40.0%(27.3%) |
| 2級(前期) | 51.1%(42.6%) | - |
| 2級(後期) | 50.6%(39.8%) | 49.3%(41.6%) |
出典:一般社団法人 全国建設研修センター「技術検定試験 合格発表公表資料」
※カッコ内は、合格者全体に占める高卒者の割合
6. 管工事施工管理技士
管工事施工管理技士とは、給排水、空調、衛生設備などの管工事に関する専門知識を持っていることを証明する国家資格です。
1級は、商業施設やオフィスビル、工場、病院など、大規模かつ複雑な建築物の管工事に携わることができます。
2級は、小規模な建築物などの管工事における「主任技術者」として現場管理を担当します。
令和6年度試験の合格率は、1級は一次検定が5割強、二次検定が8割弱です。2級の合格率は、一次検定・二次検定ともに6割を超えています。
▼管工事施工管理技術検定 合格率(令和6年度)
| 一次検定 | 二次検定 | |
|---|---|---|
| 1級 | 52.3%(29.6%) | 76.2%(32.0%) |
| 2級(前期) | 66.4%(38.8%) | - |
| 2級(後期) | 65.1%(40.1%) | 62.4%(39.9%) |
出典:一般社団法人 全国建設研修センター「技術検定試験 合格発表公表資料」
※カッコ内は、合格者全体に占める高卒者の割合
7. 建設機械施工管理技士
建設機械施工管理技士は、建設機械の操作・配置・管理に関する専門知識を持っていることを証明する国家資格です。
1級は、ダム建設やトンネル掘削など、大規模な土木工事現場において主任技術者・監理技術者として働けます。
2級は、比較的小規模な土木工事現場や、大規模工事現場の一部工程において、建設機械の管理や操作、作業員の指揮・監督を行えます。
令和6年度試験の合格率は、1級の一次検定が3割弱、二次検定が5割弱です。2級の合格率は、一次検定が約4割、二次検定が約5割となっています。
▼建設機械施工管理技術検定 合格率(令和6年度)
| 一次検定(6/16) | 二次検定 | |
|---|---|---|
| 1級 | 27.8%(58.7%) | 48.4%(60.2%) |
| 2級 | 41.2%(60.7%) | 51.3%(53.8%) |
出典:一般社団法人 日本建設機械施工協会「建設機械施工管理技術検定(1級・2級 第一次検定・第二次検定|合格発表(掲載期間1年)」
※カッコ内は、一次検定は「受験者全体に占める高卒者の割合」、二次検定は「高等学校・専門学校」出身者の合格割合
※2級は「種別計」の合格率
施工管理の仕事内容
施工管理の仕事は、「工程管理・品質管理・安全管理・原価管理」の4つに大別できます。
工程管理は、工事をスケジュール通りに進めるために、作業の順番や進捗状況などを管理する仕事です。
品質管理は、建物の仕上がりが設計図や基準に合っているかを確認・管理する仕事で、安全性や耐久性を確保するための重要な役割を担います。
安全管理は、作業員が安全に働けるよう現場環境を整え、事故やケガを未然に防ぐ仕事です。
原価管理では、資材費や人件費などのコストを計画・把握・調整し、予算内で工事を完了させるための管理業務を担います。
1. 工程管理
工程管理は、建設工事を予定通りに完成させるために、作業の順番やスケジュールを管理する仕事です。
基礎工事から内装工事まで、各工程がいつ始まり、いつ終わるかを計画し、工事全体の流れを把握します。
天候不良などで作業が遅れた際は、他の工程との調整を行い、全体の工期に影響が出ないように対応することも大切な業務の一つです。
担当する工事がスムーズに進むように、「全体を見て行動する力」が求められる仕事といえるでしょう。
2. 品質管理
品質管理は、建設物が設計図書や仕様書、関連法規(建築基準法など)に基づいて正しく施工されているかを確認・管理する仕事です。
コンクリートの強度が設計通りになっているか測定したり、壁の仕上がりに傷や汚れがないかを目視で確認したりします。
品質に問題がある場合は、職人さんに修正を依頼し、不具合が出ないように対処することも求められます。
建物の安全性に関わるため、施工管理の中でも特に責任が重い仕事といえるでしょう。
3. 安全管理
安全管理は、現場で働く作業員の安全を確保し、事故や災害を防ぐ仕事です。
現場内の危険箇所を特定し、足場の設置や、保護具の着用指示、立ち入り禁止区域の設定などの安全対策を講じることが主な業務です。
KY(危険予知)活動や、安全教育など、作業員に対する啓蒙(けいもう)活動も重要な業務の一つです。
事故が起きれば工事がストップしてしまうだけでなく、人命に関わる重大な事態にもなるため、工事現場において欠かせない仕事といえるでしょう。
4. 原価管理
原価管理は、工事全体の予算を管理し、計画された予算内で工事を完了させる仕事です。
資材費、人件費、重機レンタル費など、工事にかかるあらゆる費用を把握し、予算と比較します。そのうえで無駄なコストが発生していないか監視し、削減できる部分を探すことが主な仕事です。
また、工事が終わったときに「赤字になっていないか」を確認する役目も求められます。
会社の利益に直結するため、施工管理の中でも「経営的視点」が必要な業務といえるでしょう。
施工管理が「やめとけ」と言われる理由
施工管理は、工期や予算を守る責任が重く、残業や休日出勤が多くなりがちなため「やめとけ」と言われることがあります。
急なトラブル対応や事務作業も多く、体力的・精神的にハードな一面もあります。職人・発注者・近隣住民など、多くの関係者との間で調整を行うため、人間関係のストレスを感じやすい高卒の方は注意が必要です。
利害がぶつかる場面も多く、常に強いプレッシャーにさらされる仕事といえるでしょう。
施工管理が「やめとけ」と言われる理由については、次の記事でも解説しています。
1. 残業や休日出勤が多い傾向にある
施工管理は工期が厳しく設定されることが多く、そのスケジュールに間に合わせるために残業や休日出勤を余儀なくされる場面もあるため、「やめとけ」と言われることがあります。
その背景には、現場での急なトラブル対応や、書類作成・原価計算といった膨大な事務作業の存在があります。
施工管理の仕事は忙しくなりやすいため、体力的・精神的にハードに感じる高卒の方も多いでしょう。
しかし、建築業界では月45時間までの残業を原則とする“働き方改革”が進められており、会社にもよりますが状況は変わりつつあります。残業や休日出勤の頻度については、転職エージェントの担当者に聞いたり、内定後に企業に直接聞いてみると良いでしょう。
2. 納期やコストのプレッシャーが大きい
施工管理は期限内に予算を守って工事を完成させる責任があるため、常に大きなプレッシャーにさらされています。
たとえば「来年3月までに必ず完成させろ」と期限を厳しく指定されたり、材料費が予算を超えそうになると「何とかして削れ」と上司から詰められたりすることもあるかもしれません。
資材価格の高騰や人手不足などで工事が予定通り進まない場合でも、最終的な責任を負うのは現場の施工管理者です。そのため、何とかして工期と予算を守ろうと奔走する必要があります。
このように工事の成功や失敗を左右する立場にあるため、プレッシャーを強く感じやすいのです。
3. 人間関係のストレスが大きい
施工管理は、職人や業者、発注者、近隣住民など様々な立場の人と関わるため、人間関係によるストレスを抱えやすい仕事です。
たとえば職人からは「無茶な工期を押し付けるな」と不満を言われる一方で、発注者からは「なぜ工事が遅れているんだ」と責められることもあります。
近隣住民から騒音の苦情があれば、自ら謝罪に出向く必要もあるでしょう。
このように施工管理は、多くの関係者の意見を調整しながら工事を進める役割を担っています。しかし、実際には利害がぶつかり合う場面も多いため、人間関係の面でストレスを感じる状況が続く可能性があるのです。
高卒が施工管理として働くメリット
施工管理は現場経験が重視されるため、高卒で早くから働き始めれば若いうちにスキルを磨くことができ、昇進や転職の場面で大卒者より有利になることもあります。
実力次第で高収入を目指すことも可能で、資格手当などによって年収がさらに上がるケースも少なくありません。高卒の平均年収を大きく上回ることも十分に期待できます。
建築業界は慢性的な人手不足が続いており、施工管理の経験者は常に求められる存在です。将来も安定した需要が見込まれるため、長く安定して働きたい高卒の方にとっては非常に魅力的な職種といえるでしょう。
1. 大卒と比べて現場経験を早く積める
施工管理は現場経験が重視される世界のため、若いうちから経験を積んでおくと昇進や昇給に有利です。
高卒で施工管理の仕事に就けば、大卒よりも約4年早く現場経験を積めます。大学生が教室で学んでいる間に、現場での職人との接し方や、工程管理・品質管理のノウハウなどを実践的なスキルとして身につけられるでしょう。
実力主義の建設業界において、「早くから経験を積めること」は大きなアドバンテージです。経験やスキルを武器に、高年収の建設会社へ転職したり、将来的に独立して会社を立ち上げたりするなど、キャリアの選択肢も広げられるでしょう。
2. 高年収が手に入る可能性がある
施工管理は専門性の高い仕事である一方、人手不足が深刻なため、学歴に関係なく高待遇で採用する建設会社も少なくありません。
高卒者全体の平均年収は約460万円(※)ですが、施工管理として経験を積めば年収500万円以上を目指すことも十分可能です。
さらに「1級施工管理技士」などの資格を取得すれば、月1〜3万円程度の資格手当が支給されるケースも多く、年間で十数万円以上収入がアップすることもあります。
このように、学歴に関係なく、努力と実績次第で高収入を実現できる点は、高卒者が施工管理として働く大きなメリットといえるでしょう。
※ 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
平均年収=「きまって支給する現金給与額×12」+年間賞与その他特別給与額(従業員数10人以上/年齢計)
3. この先の仕事に困る心配が少ない
建築業界は慢性的な人手不足が続いているため、施工管理の経験者は仕事に困る心配がほとんどありません。
特に若手の施工管理者は引く手あまたの存在で、求人も豊富です。
新築ラッシュは落ち着きつつありますが、老朽化したビルやインフラ設備の建て替え工事は今後も大幅に増加する見込みです。
AIや機械化による工事現場の変革も進んでいますが、現場経験や人間の目によるチェックが重要なため、施工管理の仕事がなくなる可能性は非常に低いとされています。
このように建設業界は安定した需要が見込まれるため、長く安定して働き続けたい高卒の方にぴったりの仕事といえるのです。
まとめ
この記事では、高卒・未経験でも施工管理として働ける理由について解説しました。
施工管理は、体力的・精神的なタフさが求められる仕事です。一方で、高卒でも高収入を目指すことができ、安定した建築需要も見込まれるため、長く安心して働き続けられる可能性もあります。
少しでも興味を持った方は、施工管理への就職をぜひ目指してみてください。