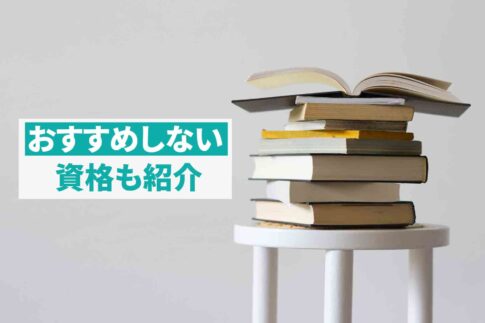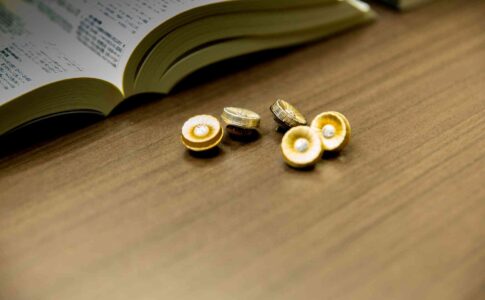建築士試験は基本的に学歴の制限がないため、高卒でも建築士になれます。
一級建築士や二級建築士として働くことも可能ですが、出身高校などによって免許取得までのルートが異なる点には注意が必要です。
この記事では、高卒の方が一級建築士・二級建築士の免許を取得する方法や、それぞれの試験内容についてわかりやすく解説します。
建築士の平均年収も紹介しますので、建築士について理解を深めたい方はぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
高卒も一級建築士・二級建築士になることは可能
高卒でも受験資格や免許登録要件を満たせば、一級建築士や二級建築士として働けます。
たとえば建築系の高校を卒業した人の場合、基本的には卒業と同時に二級建築士試験を受験できます。そして2年以上の実務経験を積むことで、二級建築士免許を取得可能です。
その後、一級建築士試験の合格、そして二級建築士として4年以上の実務経験を積むことで、一級建築士の免許も取得できます。
普通科高校を卒業した人に関しては、7年以上の建築実務経験を積むことで二級建築士試験を受験できます。
この場合、合格後に二級建築士免許を取得でき、その後の一級建築士免許取得までの流れは建築系高校卒業者と同じです。
このように、専攻課程によって取得年数までに違いはあるものの、高卒であっても二級建築士・一級建築士の免許を取得できるのです(木造建築士免許も取得可能)。
※2025年6月時点の建築士試験制度に基づいて解説します。
最新情報は、公益財団法人建築技術教育普及センターの公式サイトなどでご確認ください
※「平成21年度以降に学校へ入学した方」を対象に解説します。
高卒が二級建築士を目指す流れ
高卒者が二級建築士を目指す流れは、「建築系(建築科・土木科など)の高校卒業者」と「それ以外(普通科卒など)」に大きく分けられます。
たとえば建築系の工業高校で所定の20単位を修得した場合、卒業と同時に二級建築士試験の受験が可能です。この場合、2年以上の実務経験を積むことで免許を取得できます。
一方、建築に関する学歴がない人は、試験を受けるために7年以上の建築実務経験が必要です。
ただし、高校卒業後に建築系の専修学校や職業訓練校に進学し、所定の単位を修得・課程を修了すれば、実務経験なしで試験を受けられる場合もあります。
参考:国土交通省 住宅局建築指導課「令和2年から建築士試験の受験要件が変わり、新しい建築士制度がスタートします!」
土木科・建築科卒
土木科・建築科などの高校を卒業した方は、所定の建築系科目を20単位以上履修していれば、卒業と同時に二級建築士試験を受験できます。
ただし、試験に合格しただけでは建築士として働けません。この場合、2年以上の建築実務経験を積んで初めて免許登録が可能になります。
一方、履修単位が15単位の場合、卒業後に1年以上の実務経験を積んでから受験が可能となります。この場合、免許登録には3年以上の実務経験が必要です。
| 分類 | 必要単位(高等学校) | |
| ① 建築設計製図 | 3単位 | |
| ② 建築計画 | 2単位 | |
| ③ 建築環境工学 | ||
| ④ 建築設備 | ||
| ⑤ 構造力学 | 3単位 | |
| ⑥ 建築一般構造 | ||
| ⑦ 建築材料 | ||
| ⑧ 建築生産 | 1単位 | |
| ⑨ 建築法規 | 1単位 | |
| ①~⑨の計(a) | 10単位 | |
| ⑩ 複合・関連科目(b) | 適宜 | |
| (a)+(b) | 20単位 | 15単位 |
| 受験資格(必要となる建築実務の経験年数) | 卒業後0年 | 卒業後1年 |
| 免許登録資格(必要となる建築実務の経験年数) | 卒業後2年 | 卒業後3年 |
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「二級建築士・木造建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)」
実務経験はかなり細かく規定されているため説明は割愛しますが、気になる方は「実務経験要件(令和2年3月1日以降の建築実務)」を確認してみてください。
普通科卒
普通科の高校を卒業した場合、二級建築士の試験を受けるには7年以上の実務経験が必要です。
7年の実務経験は免許登録要件も満たすため、試験に合格すればすぐに免許を取得できます。
とはいえ実務経験を7年積む必要があることを考えると、普通科卒の場合、免許が手に入るのは最短でも25歳前後になるでしょう。
できるだけ早く資格を取得したい方は、建築系の専修学校や職業訓練校に進学するのも手です。
たとえば高校を卒業して建築系の専修学校に進学し、規定の40単位を修得すれば、卒業と同時に二級建築士試験の受験資格が手に入ります。指定の職業訓練課程を修了した場合も、実務経験なしで受験可能です。
これらのルートだと早くて20歳前後で受験できるため、二級建築士として早く働きたい高卒の方は入学(入校)を検討してみましょう。
試験に合格した後は、0〜2年の実務経験を経て免許を取得できます。必要な実務経験年数は修業年数や取得単位数などによって異なるため、気になる方は以下のページをご確認ください。
二級建築士・木造建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)
高卒が一級建築士を目指す流れ
土木科・建築科の高校卒業者、普通科高校の卒業者ともに、二級建築士免許の取得後すぐに一級建築士試験を受験できます。そして「一級建築士試験合格」と「二級建築士として4年の実務経験」の要件を満たすことで、一級建築士の免許を取得できます。
順調に進めば、土木科・建築科卒の場合は最短で24〜25歳ごろ、普通科卒の場合は29〜30歳ごろに一級建築士として働けるでしょう(※)。
※高校卒業後、大学や専修学校、職業訓練校などに入校しなかった場合
参考:国土交通省 住宅局建築指導課「令和2年から建築士試験の受験要件が変わり、新しい建築士制度がスタートします!」
土木科・建築科卒
土木科・建築科の高校を卒業した場合、基本的には卒業と同時に二級建築士試験を受験できます(15単位履修の場合は卒業後1年の実務経験が必要)。
そして試験合格と合わせて2年以上の実務経験を積めば、二級建築士免許を取得可能です。
二級建築士免許を取ると一級建築士試験を受験でき、試験合格とともに、二級建築士として4年以上の実務経験を重ねることで一級建築士の免許が手に入ります。
このルートで進めば、最短で24〜25歳ごろに一級建築士として働けるでしょう。
普通科卒
普通科の高校を卒業した場合も、二級建築士の免許を取得すれば一級建築士試験をすぐに受験できます。
その後、二級建築士として4年以上の実務経験を積み、試験にも合格すれば一級建築士の免許を取得できます。
ただし普通科卒の方は、二級建築士試験を受けるまでに7年以上の実務経験が必要です。
そのため二級建築士試験・一級建築士試験にそれぞれ一発で合格したとしても、一級建築士として働けるのは最短でも29〜30歳ごろになるでしょう。
建築士試験の概要
二級建築士試験・一級建築士試験ともに、「学科試験」と「設計製図試験」が年1回実施されます。
設計製図試験とは、事前にテーマや課題が公表され、手描きで建築図面を作成する試験です。
二級建築士試験は例年7月に学科試験が行われ、合格者を対象に9月に設計製図試験が実施されます。
一級建築士試験も学科試験は7月に行われますが、設計製図試験は10月に実施される点に違いがあります。
二級・一級どちらの試験も総合の合格率は30%未満で推移しており、いずれも難関試験といえるでしょう。製図試験に比べ、学科試験の合格率が低い点も特徴です。
※2025年6月時点の建築士試験制度に基づいて解説します。最新情報は、公益財団法人建築技術教育普及センターの公式サイトなどでご確認ください
二級建築士試験
高卒の方が二級建築士試験を受けるには、建築系の指定科目を修めて高校を卒業するか、7年以上の実務経験を積む必要があります。
試験は「学科」と「製図」に分かれており、令和6年時点の合格率はそれぞれ39.1%、47.0%です(※)。
例年、学科試験は7月上旬、設計製図試験は9月中旬に実施されます。
二級建築士試験の勉強時間は「700時間」と言われているため、特に初学者の場合は1年ほどの勉強時間を確保する必要があるでしょう。
※参考:公益財団法人 建築技術教育普及センター「試験結果|1.過去5年間の二級建築士試験結果データ」
受験資格
高卒者のうち、建築系の指定科目を修めて卒業した人は、卒業後最短0年で二級建築士試験を受験できます。
普通科高校を卒業した人は、受験にあたって7年以上の実務経験が必要です。
建築設備士の免許がある人や、外国の大学を卒業した人などには、別の受験資格も設けられています。
| 建築に関する学歴又は資格等 | 実務経験年数(試験時) |
|---|---|
| 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者 | 最短0年 |
| 建築設備士 | 0年 |
| その他都道府県知事が特に認める者(外国大学を卒業した者等) | 所定の年数以上 |
| 建築に関する学歴なし | 7年以上 |
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「二級建築士試験 受験資格」
試験内容
二級建築士試験は「学科試験」と「設計製図試験」の2つに分かれています。
設計製図の試験は、学科試験に合格しないと受験できません。
学科試験は4科目(建築計画/建築法規/建築構造/建築施工)で、それぞれ25問、計100問が出題されます。出題形式は、五肢択一のマークシート方式です。
試験時間は「建築計画」「建築法規」が合わせて3時間、「建築構造」「建築施工」が合わせて3時間の、計6時間です。
設計製図試験は事前に課題などが発表され、試験当日にその課題に基づいた問題(設計図書の作成)が出題されます。ちなみに、令和6年度の試験課題は「観光客向けのゲストハウス(簡易宿所)」でした。
設計製図の試験時間は5時間で、休憩時間はありません
勉強時間
二級建築士試験の勉強時間は、一般に「700時間」と言われています。
1日2時間の勉強時間を確保できる場合でも、およそ1年かかります。平日は1日1時間、土日にそれぞれ5時間勉強できる場合でも、700時間を達成するには10か月以上かかるでしょう。
なお、学科試験に合格した人を対象に、およそ2ヶ月後に設計製図試験が実施されます。とはいえ2か月で製図の対策をするのは時間的に厳しいため、学科の勉強と並行して製図を練習しておくのがおすすめです。
合格率
二級建築士試験の合格率(総合)は、令和6年度で21.8%です。学科試験は39.1%、製図試験の合格率は47.0%です。
学科・製図を合わせた総合の合格率は、例年20%台前半で推移しています。
それぞれの試験の合格率がほぼ50%を下回っていることを踏まえると、決して簡単な試験ではないことが分かります。
▼二級建築士試験(合格率)
| 年 | 学科試験 | 製図試験 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 41.4% | 53.1% | 26.4% |
| 令和3年 | 41.9% | 48.6% | 23.6% |
| 令和4年 | 42.8% | 52.5% | 25.0% |
| 令和5年 | 35.0% | 49.9% | 22.3% |
| 令和6年 | 39.1% | 47.0% | 21.8% |
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「試験結果|1.過去5年間の二級建築士試験結果データ」(一部加工あり)
一級建築士試験
高卒の方が一級建築士試験を受けるには、二級建築士免許を取得しておく必要があります。
試験は「学科」と「製図」に分かれており、令和6年時点の合格率はそれぞれ23.3%、26.6%です(※)。
例年、学科試験は7月下旬、設計製図試験は10月中旬に実施されます。
一級建築士試験の勉強時間は「1,000〜1,500時間」と言われており、国家資格の中でも難関とされています。そのため、合格に向けては十分な学習時間を確保することが重要です。
※出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「試験結果|1.過去5年間の二級建築士試験結果データ」
受験資格
高卒者が一級建築士試験を受験するには、二級建築士免許の取得が必要です。
二級建築士免許を取得すれば、実務経験の要件などを挟まず、すぐに一級建築士試験を受験できます。
なお、大学や専修学校などで指定科目を修めた人に関しては、卒業後すぐに一級建築士試験の受験が可能です。その他、建築設備士、外国の大学を卒業した人などを対象とした受験資格も定められています。
| 建築に関する学歴又は資格等 |
|---|
| 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校などにおいて指定科目を修めて卒業した者 |
| 二級建築士 |
| 建築設備士 |
| その他都道府県知事が特に認める者(外国大学を卒業した者等) |
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 受験資格」
試験内容
一級建築士試験は「学科試験」と「設計製図試験」の2つに分かれています。設計製図の試験は、学科試験に合格しないと受験できません。
学科試験は5科目(計画/環境・設備/法規/構造/施工)で、それぞれ20〜30問、計125問が出題されます。出題形式は、四肢択一のマークシート方式です。
試験時間は「計画」「環境・設備」が合わせて2時間、「法規」が1時間45分、「構造」「施工」が合わせて2時間45分の、計6時間30分です。
設計製図試験は事前に課題が発表され、試験当日にその課題に基づいた問題(設計図書の作成)が出題されます。ちなみに、令和6年度の試験課題は「大学の建築学科棟」でした。
設計製図の試験時間は6時間30分で、休憩時間はありません。
勉強時間
一級建築士試験の勉強時間は、一般に「1,000~1,500時間」と言われます。
実務経験がある人でも700時間以上は必要とされるため、最低でも1~2年ほどの勉強時間は見込んでおきましょう。
学科試験は二級よりも1科目増え、難易度も上がります。また、総得点が合格基準を満たしていても、いずれか1科目でも基準に達していなければ不合格となってしまいます。
製図試験も6時間30分と長丁場のため、合格に向けた入念な対策が欠かせません。
合格率
一級建築士試験の合格率(総合)は、令和6年度で8.8%です。学科試験は23.3%、製図試験の合格率は26.6%です。
学科・製図を合わせた総合の合格率は、例年8~10%台前半で推移しています。
このように一級建築士試験の合格率はかなり低いこともあり、建築系の資格の中では“最難関”とも言われています。
▼一級建築士試験(合格率)
| 年 | 学科試験 | 製図試験 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 20.7% | 34.4% | 10.6% |
| 令和3年 | 15.2% | 35.9% | 9.9% |
| 令和4年 | 21.0% | 33.0% | 9.9% |
| 令和5年 | 16.2% | 33.2% | 9.9% |
| 令和6年 | 23.3% | 26.6% | 8.8% |
参考:公益財団法人 建築技術教育普及センター「試験結果|1.直近5年間の試験結果」(一部加工あり)
高卒の建築士の給料事情
一級建築士の平均年収は702万円(※1)ですが、高卒の場合は650万円前後が現実的な水準と考えられます。
二級建築士の平均年収は500万円前後と言われており、高卒者は450万円前後が目安といえるでしょう。これは、日本人全体の平均年収(約460万円 ※2)と比べても遜色のない水準です。
建築士の世界では、学歴よりも設計力や実務経験、担当したプロジェクトの規模などが給与に大きく反映されます。
そのため、大規模なマンションや商業施設を設計したり、建設現場で豊富な実績を積んだりすれば、高卒でも大卒以上の年収を目指せるでしょう。
※1 出典:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査|職種別第1表 職種別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)※従業員数10人以上/年齢計/独立は含まない」
平均年収=「きまって支給する現金給与額×12」+年間賞与その他特別給与額
※2 出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
一級建築士の平均年収
一級建築士の平均年収は、702万円です(※)。
高卒に限定した年収データは公表されていませんが、上記の年収には大卒や大学院卒も含まれており、一般に高卒のほうが年収が低い傾向もあります。そのため高卒の場合、まずは650万円前後を目安に考えておくと良いでしょう。
ただし一級建築士ともなれば、評価の基準は学歴ではなく、設計力や実務経験、担当したプロジェクトの規模などが重視されます。
たとえば大規模なマンションや商業施設の設計を任されたり、建設会社で現場監督として実績を重ねたりすれば、学歴に関係なく高い評価を得られるでしょう。
独立して設計事務所を開業することで、年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
そのため高卒であっても、実力と経験によっては、一級建築士として600〜700万円を大幅に上回る収入が手に入る可能性もあるのです。
出典:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査|職種別第1表 職種別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)※従業員数10人以上/年齢計/独立は含まない」
平均年収=「きまって支給する現金給与額×12」+年間賞与その他特別給与額
二級建築士の平均年収
二級建築士の平均年収は、一般に500万円前後と言われます。
こちらの年収には大卒以上も含まれるため、高卒の場合は450万円前後を目安に考えておくと良いでしょう。
日本人全体の平均年収が460万円(※)であることを踏まえると、高卒の二級建築士の年収は全国平均並みといえそうです。
一級建築士(平均年収702万円)のほうが年収が高い理由は、設計できる建物の規模に制限がなく、大型プロジェクトを手がけられるためです。
二級建築士の場合、基本的には高さ16m以下の建物などしか設計できませんが、一級建築士は病院や学校、高層マンションなど規模の大きな建物も担当できます。
二級建築士として年収を高めたい場合は、施工管理技士や宅地建物取引士などの関連資格を取得して専門性を広げたり、大手のハウスメーカーや設計事務所への転職を目指したりすることが有効です。
※出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
建築士になりたい人が高校でやるべきこと
もしあなたが高校生で、将来的に建築士として働きたいと考えているのであれば、まずは建築士試験の勉強を始めましょう。
たとえば、建築系の高校を卒業予定で進学しない場合(高卒となる場合)、卒業した年の7月と9月に二級建築士試験を受験できます。
また、意匠設計や構造設計など、自分が将来関わりたい専門分野を考えておくことも大切です。目標が明確になれば、進むべき進路や、高校生のうちにやっておくべき学習も見えてくるでしょう。
授業だけでは得られない感性を養えるので、実際に様々な建築物に触れてみることも意識してみてください。
1. 建築士試験の勉強を始める
建築系の高校に通っている場合、卒業した年の7月と9月に実施される二級建築士試験を受験できるため、在学中から勉強を始めておくことをおすすめします。
二級建築士試験は700時間ほどの学習が必要とされており、1日2時間勉強しても約1年かかります。そのため早い段階から計画的に勉強を進めることで、余裕をもって試験に臨みましょう。
建築系以外の工業高校や普通科に通っている場合、卒業後すぐに二級建築士試験を受けることができず、7年以上の実務経験が必要になります。
とはいえ建築士試験の勉強は、基礎知識や法令についての理解が身につくという点で実務にも大いに役立ちます。そのため建築業界で働きたい人は、高校生のうちから勉強を始めておいて損はないでしょう。
2. 建築士として働きたい領域を考える
建築士の仕事は多岐にわたるため、高校生のうちから「将来どんな分野で働きたいか」を考えておくと、この先の進路をスムーズに決めやすくなります。
一口に「建築士」といっても、次のようにいくつかの専門分野に分かれています。
- 住宅やマンションなどをデザインする「意匠設計」
- 建物の安全性を支える「構造設計」
- 空調や電気などの設備を設計する「設備設計」
設計事務所で図面を描く、役所で建築確認の審査を行うなど、建築士免許を活かせる仕事は様々です。
目指す道が明確になると、そこから逆算して今何をすべきか見えてくるので、まずは自分がどの領域に関わりたいか考えてみましょう。
3. 様々な建築に触れて感性を磨く
空間の使い方や、光の取り入れ方、素材の組み合わせ方など、教科書では学べない感覚が身につくため、高校生のうちから様々な建築物に触れておくのもおすすめです。
たとえば、歴史ある神社仏閣を訪れて日本建築の美しさを味わったり、リニューアルされた美術館や商業施設で現代的な設計手法を観察したりするのも一つの手です。
短期留学や家族旅行などで海外を訪れる機会があれば、現地の伝統的な建物や、最先端の都市デザインにも注目してみてください。
設計の“アイデアの引き出し”が増えることも期待できるので、できるだけ多くの建築物に触れておきましょう。
高卒で建築士を目指す人からのよくある質問
1. 一級建築士の高卒の割合は?
令和6年度の試験結果から推定すると、一級建築士に占める高卒者の割合は「20%以下」といえそうです。
▼令和6年度一級建築士試験 合格者の割合(学科試験・設計製図試験)
| 学歴区分 | 学科試験 | 設計製図試験 |
|---|---|---|
| 大学 | 67.4% | 74.6% |
| 二級建築士 | 20.7% | 15.8% |
| 専修学校 | 6.6% | 5.0% |
| 建築設備士 | 1.3% | 1.1% |
| その他(短大、高専など) | 4.0% | 3.5% |
参考:公益財団法人 建築技術教育普及センター「試験結果|1.直近5年間の試験結果」(一部加工あり)
仮に「二級建築士」「建築設備士」を高卒と見なした場合、学科試験で21.4%、製図試験で16.9%が高卒者といえます。
とはいえ実際には大卒者などが含まれているため、高卒の割合は「20%以下」と考えるのが現実的でしょう。
2. 高卒で建築関係の仕事に就いている人の年収は?
厚生労働省の令和6年度の調査によると、建築関係の仕事に就いている高卒者の平均年収は「481万円(※1)」で、日本人全体の平均年収460万円(※2)を上回っています。
一方、建築関係の大卒者の平均年収は557万円(※1)のため、学歴による差はおよそ76万円と開きがあります。
ただし、建築業界では学歴よりも技術力や経験が重視される傾向があり、建築士などの国家資格を取得すれば資格手当がつくケースも珍しくありません。
建築業界は人手不足が深刻なため、学歴関係なく採用も活発です。高い給与を提示することで人材を確保する建築会社も多いので、高収入を手にしたい高卒者にとって、建築関係の仕事は有力な選択肢といえるでしょう。
※出典1:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|職種(大分類)、性、学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)建設・採掘従事者/従業員数10人以上/年齢計」
平均年収=「きまって支給する現金給与額×12」+年間賞与その他特別給与額
※2 出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
3. 高校生が建築士になるには何から始めればいい?
建築士の仕事は、設計図を描いたり構造を計算したりと、理系の知識や空間認識力が求められるため、高校生のうちに数学・物理・美術の基礎を固めておきましょう。
たとえば、三角関数や微積分は「構造計算」に必要ですし、力学の知識は「建物の安全性」を確認するうえで欠かせません。
建物のデザインを考えるには、空間を立体的にイメージする力が求められますが、こうした力は美術の授業やスケッチ、模型制作などによって鍛えられます。
建築士に必要な力を早めに身につけるためにも、まずはこれらの基礎を固めることから始めてみてください。
4. 高卒の建築士で有名な人は誰?
世界的に有名な建築家である安藤忠雄氏が、高卒の建築士として知られています。
安藤さんは大阪府立城東工科高校(※)を卒業後、独学で建築を学び、「光の教会」や「ベネッセアートサイト直島」など、世界的に評価される作品を次々と手がけました。
1979年には「住吉の長屋」で日本建築学会賞を受賞し、2021年にはフランスのレジオン・ドヌール勲章コマンドゥールも授与されるなど、国内外で数々の賞を受賞しています。
高卒であっても、学び続ける姿勢を忘れずに実績を重ねれば、世界で活躍できることを証明した存在といえるでしょう。
※大阪府立城東工科高校は、令和7年4月に「大阪府立東大阪みらい工科高等学校」として統合
まとめ
建築士試験は高卒でも受験できるため、建築士として働くことは可能です。
ただし出身校の学科や専攻内容によって、受験資格に必要な単位数や実務経験の年数が異なります。二級建築士と一級建築士では受験資格に違いもあるため、受験要項をしっかりと確認しておくことも大切です。
試験の難易度も高いので、早いうちから受験対策を始めましょう。