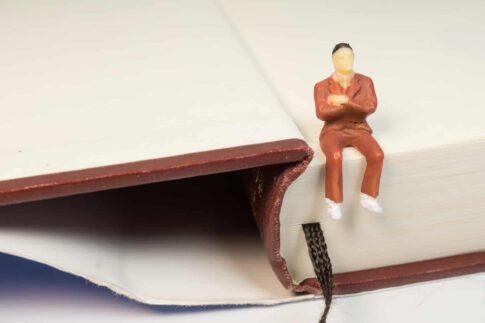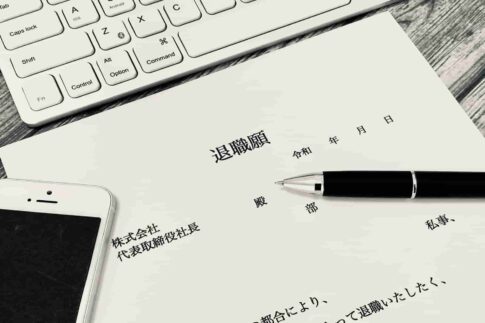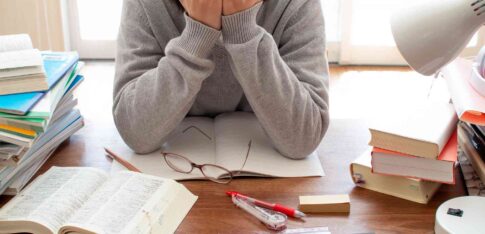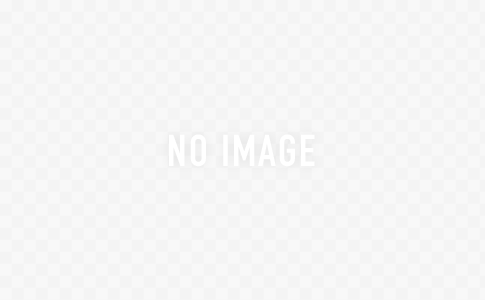高卒の就活は、在学中なら高校3年生の7月1日から本格的に始まるのが一般的です。
一方で、すでに卒業した人は自分のペースで就活をいつでも進められます。
「いつから就活を始めればいいの?」「もう卒業しちゃったけど、遅いのかな…」と不安に感じていませんか。
この記事では、高校在学中と卒業後でそれぞれの就活をスタートする時期や進め方を分かりやすく解説します。
納得のいく就職を目指すためのヒントが見つかるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
高卒の就活はいつから始めればいい?
高校生の就活は、基本的に高校3年生の7月から本格的に始まります。
効率的に就活を進めるため、できれば4月頃から準備を始め、7月1日の求人情報解禁までに自身の希望する業種や仕事をまとめておくとよいでしょう。
4月から6月までの準備内容は以下のとおりです。
4月~6月:
- 自分の強みや弱み、希望する業種や仕事を整理しておく
- 進路について先生や保護者に相談する
5月と6月には、高校生向けの就活イベントが開催されるため、気軽に参加してみましょう。自分に合いそうな仕事が見つかるかもしれません。
参考:厚生労働省 令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめました
すでに高校を卒業した方が就活する場合は、高校生とは異なる方法で進めます。
ハローワークや求人サイト、転職エージェントなどを活用して自分で求人を探しましょう。
既卒者の場合、高校生のような「1人一社制」のルールはないため、同時に複数社への応募が可能です。
在学中の就活スケジュール
高校在学中の就活スケジュールは、以下のように決められているのが一般的です。
採用活動の解禁から内定までの流れをそれぞれ解説します。
- 7月1日:採用活動解禁
- 7月~8月:企業説明会や職場見学
- 9月5日頃:応募書類提出
- 9月16日頃以降:企業による選考や内定
- 10月以降:二次募集開始
7月1日:採用活動解禁
7月1日は、高校卒業予定者にとって就職活動の本格スタートとなる重要な節目の日です。
この日から、企業による高校への求人申し込みや、学校訪問などの採用活動が正式に解禁されます。
求人票はハローワークの確認印を受けたうえで各高校に送付され、生徒は学校内で閲覧できます。興味のある業界や職種の情報を集めながら、求人票を見て自分に合いそうな企業を早めに見つけましょう。
求人票の見方や企業選びに迷う場合は、進路指導の先生や保護者へ積極的に相談するのがおすすめです。
自分の将来に関わる大切な選択だからこそ、焦らず丁寧に情報を集めることが大切です。
7月~8月:企業説明会や職場見学
7月から8月は、主に以下のスケジュールで進むのが一般的です。
- 合同企業説明会への参加
- 職場見学
- 三者面談
- 企業選定
「高校生向け合同企業説明会が全国各地で開催されます。費用は無料のため、積極的に参加しましょう。
合同企業説明会では、実際の仕事内容を体験できるコーナーもあります。
職場見学では気になる企業を実際に訪問し、雰囲気や仕事内容を確認します。
就職後のミスマッチを防ぐため、職場見学にはできるだけ参加しましょう。
その後は先生と保護者、本人との三者面談を行い、応募する企業を原則1社に絞っていきます。
9月5日頃:応募書類提出
9月5日頃になると(沖縄県では8月30日から)高校から企業へ応募書類を提出します。
高校生の就活では「学校統一応募用紙」と呼ばれる専用の履歴書と調査書が使用され、これらの書類をもとに企業が選考を進めます。
この時期は「1人一社制」が原則で、応募できるのは1社のみです。
高校生の就活では、複数の企業へ同時に応募できないため、どの企業に応募するかを慎重に決める必要があります。
また、応募書類はすべて学校の進路指導部を通して企業に送られるため、個人で企業へ直接提出することはありません。
書類作成の準備や提出スケジュールについては、進路指導の先生と相談しながら早めに進めましょう。
9月16日頃以降:企業による選考や内定
9月16日以降になると、企業の選考が正式に始まります。
選考方法は企業ごとに異なりますが、筆記試験や面接などが行われ、応募者の適性や意欲が総合的に評価されるのが一般的です。
選考開始と同時に、早い段階で内定を出す企業も多く、9月中旬から10月にかけて内定を得る生徒が増えていく傾向があります。
この時期は就職活動と学校生活を両立させる必要があるため、時間の使い方や体調管理に注意しましょう。
面接の練習や筆記試験対策などの準備を丁寧に行うと、自信を持って選考に臨めます。
焦らず着実に一歩ずつ進めていくことが大切です。
10月以降:二次募集開始
一次募集で内定を得られなかった生徒に向けて、10月以降に二次募集が始まります。
二次募集では、一次募集とは異なり複数の企業に応募できるケースが多く、選択肢が広がるのが特徴です。
応募のタイミングは地域や学校によって若干異なりますが、一般的には9月下旬から10月中旬頃にかけて開始され、11月中旬頃まで続きます。
一次募集で内定が得られなかった場合でも、二次募集で自分に合った企業と出会える可能性は十分あります。焦らず、もう一度自分の適性や希望を見直してみましょう。
高校生の就職活動は短期間で展開するため、早めに準備を始めつつ計画的に行動することが大切です。
進路指導の先生と連携を取りながら、自分の将来につながる一歩を確実に踏み出しましょう。
高校生が就活準備として行うべきこと
高校生が就活を成功させるためには、準備が必要です。
以下の内容について、それぞれ見ていきましょう。
- 自己分析を行う
- 希望する職種や業界を理解しておく
- 資格やスキルを取得しておく
- 学校で応募書類を作成する
- 学校で模擬面接を実施する
自己分析を行う
自己分析は、就活を成功させるための土台となる大切なステップです。
自分の得意なことや苦手なこと、性格の傾向、これまでに力を入れて取り組んだことなどを振り返りながら「自分はどんな人間か」「どのような仕事に向いているのか」を整理していきましょう。
自己分析が適切にできていると、履歴書に書く自己PRや志望動機に一貫性と説得力が生まれ、面接でも自信を持って話せるようになります。
また、自分にとって働きやすい環境や、やりがいを感じられる職場を見極める際の判断基準にもつながるでしょう。ノートに考えをまとめたり、先生や家族、友人に相談したりすると、自分では気づかなかった長所や特性が見えてくる場合もあります。
客観的な視点を取り入れると、自分のことをより深く理解できるようになります。
希望する職種や業界を理解しておく
就活を進める際は、自分が希望する職種や業界について十分に理解しておきましょう。
例えば、製造業を志望する場合「どのような作業があるのか」「勤務時間やシフトはどうなっているのか」「体力はどれほど求められるのか」などの実務面を具体的に把握しておくと、志望動機や面接での回答に深みが出て、信頼感につながります。
また、仕事内容をあらかじめ理解すると、自分に合うかどうかを見極めやすくなり、入社後のミスマッチや早期離職のリスクを下げることにも役立ちます。
学校の就職関連資料や企業のホームページ、動画の説明会、インターンシップの機会などを積極的に活用し、実際の働き方や職場環境について理解を深めていきましょう。
資格やスキルを取得しておく
高校生のうちに取得できる資格やスキルは、就職活動で自分をアピールするうえで強みになります。
パソコンのスキルや日商簿記、英検、危険物取扱者などは実務に直結しやすいため、多くの企業で評価されやすい分野です。これらの資格を持っていると、即戦力として期待される可能性も高まります。
また、資格の取得に向けてコツコツと努力してきた経験により「向上心がある人」「責任を持って取り組める人」として企業の人事担当が好印象を持つでしょう。
自分が目指す職種や業界で、どのような資格が役立つのかを事前に調べ、早めに計画を立てて準備することが大切です。
学校で実施される検定や講座なども積極的に活用して、着実にスキルを身につけていきましょう。
学校で応募書類を作成する
就職活動で提出する応募書類は、企業が応募者の第一印象を決める重要な資料です。
学校では、進路指導の先生のアドバイスを受けながら作成しますが、誤字脱字を防ぐだけでなく、読みやすく丁寧に仕上げる意識が求められます。
自己PRや志望動機の欄では、形式的な表現にとどまらず、自分の経験や考えを具体的に書くと、採用担当者の印象に残りやすくなるでしょう。
また、丁寧な字で書くことも評価につながるため、何度も練習を重ねて完成度を高めておくと安心です。
自分の良さを企業へ伝えるためには、書類に気持ちを込めて書く必要があります。
進路指導の先生のアドバイスを受けながら自信を持って提出できる内容に仕上げていきましょう。
学校で模擬面接を実施する
模擬面接は、本番の面接に備えて実践的な練習を行うための大切な準備の1つです。
面接では志望動機や自己PRだけでなく、話すときの姿勢や表情、声の大きさや話し方なども評価の対象になります。
学校で実施される模擬面接では先生が面接官役となり、受け答えの内容や態度について具体的なフィードバックを受けられるのがメリットです。
緊張してうまく話せなかった箇所や、自分では気づきにくい癖を事前に修正できるため、本番の面接では自信を持って受け答えできるようになります。
高校生が就活で注意すべきポイント
高校生の就活は、大卒や転職活動とは異なるルールがあります。
以下のポイントについて、それぞれ解説します。
- 在学中の就活は「一人一社制」が一般的
- 内定後「辞退は原則不可」が一般的
- 企業とのやり取りは学校を通すのが主なルール
- 面接当日は余裕を持って行動する
- 身だしなみとマナーに気をつける
在学中の就活は「一人一社制」が一般的
高校生の就活では、多くの地域や学校で「一人一社制」が基本ルールとして定められているのが一般的です。これは、古くから続く独自のシステムで、高校生が学業に専念できるようにするためです。
応募できる企業が1人につき1社に限られるため、複数の企業へ同時にエントリーできません。
自分が選んだ1社が自身の就職先となる可能性が高いため、応募先は慎重に選ぶ必要があります。
業種や仕事内容だけでなく、勤務地や勤務時間、休日、福利厚生など、企業の情報を事前によく確認し、自分の希望や適性に合った企業を選ぶことが大切です。
一度応募すると、原則として変更ができないため、担任や進路指導の先生、保護者とも相談を重ねて、後悔のない決断を心がけましょう。
内定後「辞退は原則不可」が一般的
高校生の就活では、企業から内定を受けた後に辞退するのは、原則として認められていません。
法的な決まりではありませんが、学校推薦を通じて企業へ応募しているためです。
生徒一人ひとりの行動が高校全体の信頼に直結することから、軽はずみな辞退は避けるべきとされています。
やむを得ない事情があったとしても、無断で辞退したり、個人的に企業へ連絡して対応したりするのは適切ではありません。担任や進路指導の先生に必ず相談し、学校の指示に従って対応しましょう。
「内定の辞退は原則不可」というルールは、高校生ならではの就活の特徴であり、大学生や社会人の転職活動とは異なる点です。
企業とのやり取りは学校を通すのが主なルール
高校生の就職活動では、企業との連絡や手続きはすべて学校を通じて行うのが一般的なルールです。このルールは高校生の学業を優先しつつ、未成年者を保護するためと言われています。
応募書類の提出や面接日時の調整、内定通知の受け取りなど、すべてのやり取りは担任や進路指導の先生が窓口となります。
そのため、生徒が企業へ直接連絡したり、個人的に訪問したりすることはマナー違反とされ、場合によっては企業からの信頼を損なう恐れもあるのです。
このルールを破ると、学校の信用を損なうだけでなく、自分の選考や進路にも悪影響を及ぼしかねません。
高校生の就活は学校の信頼が関わっていることを忘れずに、ルールを守って取り組みましょう。
面接当日は余裕を持って行動する
面接当日は予期せぬトラブルにも対応できるよう、早めに家を出ましょう。
電車の遅延や道に迷う可能性を考えて、集合時間の30分前には現地に着くのが理想です。
また、遅刻しそうになった場合は、すぐに学校へ連絡を入れるなど、社会人としての対応が求められます。
会場に到着したら、受付の方にも丁寧なあいさつを心がけましょう。
落ち着いた態度と時間管理の意識は、面接の評価にもつながります。第一印象を良くするためにも、心構えと余裕を持った行動が大切です。
身だしなみとマナーに気をつける
就活では、第一印象が非常に大切です。
制服がある場合は正しく着用し、しわや汚れがないよう気を配りましょう。
ない場合はスーツまたは落ち着いた服装を選ぶのが一般的です。
髪型は整え、爪や靴も清潔に保ちます。
言葉遣いやあいさつ、ドアの開け方やお辞儀の角度などもチェックしましょう。
社会人としてふさわしい態度ができているかどうかは、面接で特に見られる部分です。事前にマナーを学んだり、先生に見てもらったりすると、自信を持って面接へ臨めます。
高校卒業後の高卒の就活は3ヶ月が一般的
高校をすでに卒業した高卒の就活は、3ヶ月程度かかるのが一般的です。
企業選びや面接がスムーズに進むと1ヶ月程度で終わる場合もありますが、多くの場合は3ヶ月程度の期間を見込んでおくことが推奨されています。
厚生労働省が運営するハローワークや地域若者サポートステーションでは、求職支援プログラムの多くが「約3ヶ月の就職支援スパン」を想定しており、職業訓練や就活セミナーも、数週間から3ヶ月のスケジュールで構成されていることが多いためです。
一方で、在職中に転職する場合、現職の仕事と調整しながら活動するため、3ヶ月から6ヶ月ほどかかる場合もあります。
高校卒業後の高卒の就活ステップ
高校を卒業した高卒が就活する際のステップは、以下のとおり進むのが一般的です。
それぞれの流れを具体的に解説します。
- 自己分析と方向性を整理する
- 求人情報を確認する
- 履歴書と職務経歴書を作成する
- 応募先へエントリーする
- 面接の準備や練習をする
- 応募先企業の面接を受ける
- 内定が決まる
1. 自己分析と方向性を整理する
高校卒業後の高卒が就職活動を始める際は、自分の強みや価値観、今後の方向性を明確にしましょう。
過去の経験を振り返り「どのような仕事にやりがいを感じたか」「何が得意だったか」「働くうえで何が大切だと感じたか」などを整理すると、自分に合った働き方や職場環境が見えてきます。
また、転職を希望する理由や次の職場に求める条件を言語化すると、志望動機や面接での受け答えにも一貫性が生まれ、説得力が増します。
頭の中で考えるだけでなく、紙に書き出したり、キャリアカウンセリングなどの専門サービスを活用したりすれば、客観的な視点を取り入れながら深掘りすることが可能です。
2. 求人情報を確認する
自己分析を終えて方向性が定まったら、求人情報を確認しましょう。
ハローワークや地域若者サポートステーション、求人情報サイトを活用するのが一般的です。
また、気になる企業がある場合は、会社の公式ホームページの採用情報ページから直接応募する方法もあります。
求人を探す際は、給与や休日などの条件だけでなく、業務内容、職場の雰囲気、企業の将来性などの情報にも注目しましょう。
「未経験歓迎」「若手活躍中」「第二新卒OK」などのキーワードがある求人は、高卒や社会人経験が浅い方でも挑戦しやすいため、積極的にチェックするのがおすすめです。
複数の求人を比較検討すると、自分の希望により近い働き方を見つけやすくなります。
焦らず丁寧に情報を見極めると、後悔のない転職が可能です。
3. 履歴書と職務経歴書を作成する
履歴書と職務経歴書は、自分の人柄やスキル、仕事への姿勢を企業に伝える大切な書類です。
履歴書には氏名や連絡先、学歴、職歴などの基本情報を正確に記入し、志望動機や自己PRの欄では、実体験に基づいた具体的なエピソードを交えて書くと、説得力が増します。
職務経歴書では、前職での仕事内容や担当業務、工夫したこと、成果などを時系列で整理し、自分がどのように貢献してきたかを分かりやすく記載しましょう。
未経験の業界や職種に応募する場合でも、これまでに身につけた責任感や協調性、仕事に取り組む姿勢は十分なアピール材料となります。
完成後は信頼できる人やキャリアアドバイザーに添削してもらうと安心です。
4. 応募先へエントリーする
履歴書と職務経歴書が整ったら、応募先企業へエントリーしましょう。
応募方法は企業ごとに異なり、求人サイト経由、メール送付、郵送などの形式が指定されているため、案内に従って提出します。
メールでの応募では、件名・本文ともにビジネスマナーを意識し、分かりやすく丁寧な表現を使うことが大切です。
ファイル名や添付形式にも配慮し、相手に負担をかけないように整えると好印象につながります。
書類提出後に企業から連絡があった際には、スピーディかつ誠実な対応を心がけると信頼獲得のポイントになるでしょう。
また、複数の企業へ同時に応募する場合は、応募日・連絡先・選考状況・面接日時などを一覧で管理するシートを作成しておくと、情報整理に役立ちます。
5. 面接の準備や練習をする
応募後は面接に向けて入念に準備しましょう。
企業研究をしっかり行うと志望動機に具体性が生まれ、企業への関心や熱意が伝わりやすくなります。
併せて自己紹介や転職理由、前職で学んだことや高校卒業後の過ごし方など、よく聞かれる質問に対する回答をあらかじめ言語化しておくと、本番での受け答えに自信が持てるでしょう。
鏡の前で話す練習をしたり、キャリアカウンセラーや信頼できる友人に模擬面接を依頼するのも有効です。
第三者からフィードバックをもらうと、自分では気づかないクセや改善点に気づけます。
また、面接では第一印象も重要な評価ポイントです。
清潔感のある服装、整った髪型、明るい表情、丁寧な話し方を意識し、自然な笑顔で落ち着いて臨めるよう準備を進めておきましょう。
6. 応募先企業の面接を受ける
面接当日は時間に余裕を持って行動し、遅刻しないように注意しましょう。
受付を済ませる際からすでに選考は始まっていると意識し、明るい表情と丁寧な言葉づかいを心がけます。
面接では志望動機や退職理由、これまでの経験から学んだこと、仕事への意欲などを重点的に確認されるのが一般的です。
緊張していても、落ち着いて受け答えすることが大切です。
一問一答にとどまらず、会話のキャッチボールを意識すると、より良い印象を与えられるでしょう。
応募先企業の事業内容や応募職種について事前に調べ、自分なりに感じた疑問や興味をもとに質問を用意しておくと、入社への意欲が伝わりやすくなります。
最後まで誠実な態度で対応し、感謝の気持ちを忘れずに伝えることが、好印象を残すポイントです。
7. 内定が決まる
面接や試験を通過すると、企業から内定の連絡が届きます。
連絡方法は電話やメールなどさまざまですが、面接後1週間程度で合否の通知が届くのが一般的です。連絡が届いたら、落ち着いて感謝の気持ちを伝えましょう。
内定後は労働条件通知書などの書類を受け取り、給与、勤務時間、休日、福利厚生などを確認します。
不明な点があれば遠慮せず質問し、不安を残さないようにしましょう。
入社日が決まったら必要な書類や服装、持ち物を事前に準備し、初出勤に向けて心と環境を整えておくと安心できます。
高校卒業後の高卒が就活で注意すべきポイント
同じ高卒でも、高校生と高校卒業後では就活の方法が異なります。
高校卒業後の高卒が注意すべきポイントを5点、それぞれ解説します。
- 学校の推薦枠はもらえない
- 応募や企業との連絡は自分で対応する
- 卒業後の空白期間を説明できるようにしておく
- 職務経歴書の提出を求められる場合もある
- 求人によっては学歴や年齢の制限がある
学校の推薦枠はもらえない
高校を卒業した後に就活を始める場合、高校生のように学校を通じた「推薦応募枠」は利用できません。
高校在学中の就活は、学校と企業の信頼関係の上で成り立っており、学校推薦が応募の条件となるケースが多く見られます。しかし、既卒者はこの推薦枠の対象外となるため、一般の求人を自分で探して応募する必要があります。
推薦枠ではないため、ライバルも多くなる可能性があり、自己PRや応募書類の質、面接での受け答えなどが合否を左右します。
また、学校の先生による進路指導も利用できません。
自分で積極的に情報収集しつつ、就職支援機関やハローワーク、転職エージェントのサポートを活用するとよいでしょう。
応募や企業との連絡は自分で対応する
高校卒業後の就職活動では、応募手続きや企業とのやりとりをすべて自分で行う必要があります。
高校在学中の場合は、学校が企業と連絡を取り合い、面接日程の調整や書類の提出などを代行してくれますが、卒業後はそのサポートを受けられません。
求人情報の確認や履歴書・職務経歴書の送付、結果の確認など、すべて自分で責任を持って対応しましょう。そのため、ビジネスマナーに沿ったメールの書き方や電話応対の基本を理解しておくことが大切です。
また、応募先企業の対応スピードに合わせて迅速に行動できるよう、スケジュールを管理する力も問われます。
これらのやりとりを適切に行うと、信頼できる人物だと企業に感じてもらえるでしょう。
卒業後の空白期間を説明できるようにしておく
高校卒業から就職活動を始めるまでの空白期間がある場合、その間に何をしていたのかを説明できるようにしておきましょう。
例えば「アルバイトで社会経験を積んでいた」「資格取得の勉強をしていた」など、前向きな理由で伝える工夫が必要です。
企業は「空白期間に何をしていたのか」「働く意欲があるのか」を重視するため、具体的に話すと好印象につながります。
逆に「何となく働いていなかった」「特に理由はない」などの曖昧な説明ではマイナス評価になりやすいでしょう。
自己分析を通じて、ブランクの期間をどう過ごしたのかを整理しておくと、履歴書や面接での受け答えに活かせます。
職務経歴書の提出を求められる場合もある
既卒者として応募する場合、企業から職務経歴書の提出を求められる場合があります。
アルバイトや短期の就職であっても、自分がどのような仕事に取り組み、どのような成果や学びがあったのかを具体的に記載しましょう。
職務経歴書は、履歴書では伝えきれない実務能力や経験をアピールする資料のため、内容次第で評価が大きく変わる可能性があります。
「責任を持って働いた経験」「接客で得たコミュニケーション能力」など、自分の成長につながった経験を前向きに表現しましょう。
不安な場合は、ハローワークや就職支援施設、転職エージェントで添削を受けるのもおすすめです。
求人によっては学歴や年齢の制限がある
高卒で就職活動をする際は、求人ごとに「高卒以上」「新卒3年以内」などの応募条件が設定されている場合があります。
特に、若年層を対象とした求人には年齢制限がある場合が多く「30歳以下」「既卒3年以内」など、法律で許容されている範囲で年齢を制限しているケースが見られます。
希望する求人に応募できるかどうか、募集要項を必ず確認しましょう。
また、学歴によって応募できる職種や昇進のチャンスに差が出る場合もあるため、自分に合った求人を見極める力も求められます。
条件に合わない場合でも、職業訓練や資格取得を経て再挑戦できる場合もあります。
短期的な視点だけでなく、中長期的なキャリアプランも意識して動くことが大切です。
まとめ
高校在学中と卒業後で、それぞれの就活をスタートする時期や進め方、注意すべきポイントなどについて解説しました。
在学中の場合は、7月1日の採用活動解禁を目安にスケジュールを組むのが理想です。
学校の先生や保護者と連携しながら進めましょう。
既に卒業している場合はいつでも就活できますが、自己分析や求人情報の収集、書類作成など、基本のステップを押さえると着実に前へ進めます。
それぞれのタイミングに合わせて計画的に行動し、確実な一歩を踏み出しましょう。