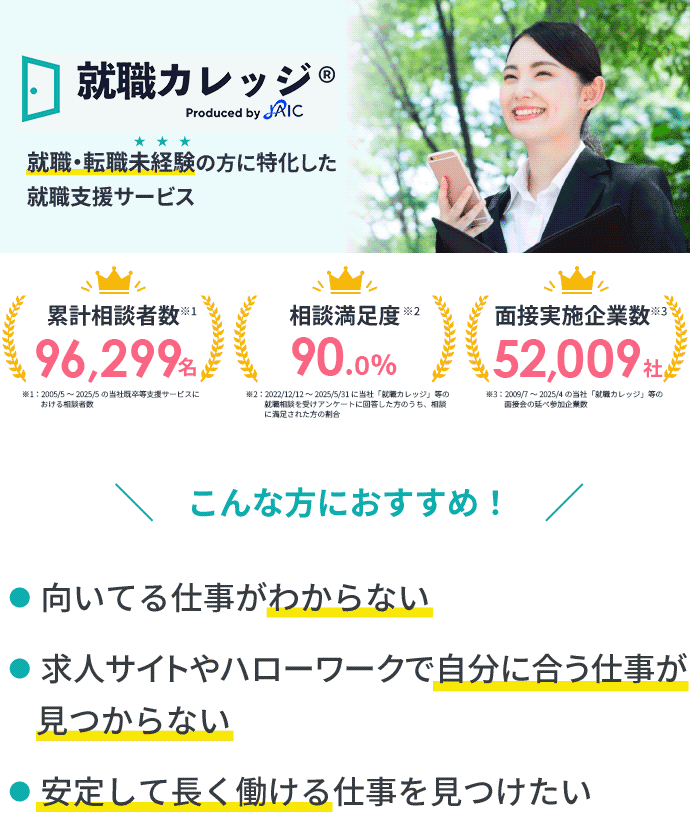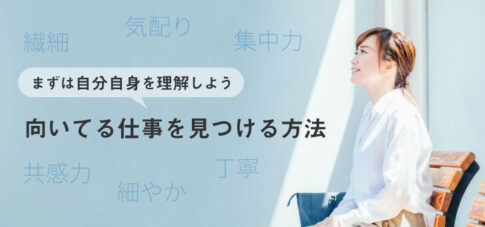HSPだと思っている人が続いた仕事は、WebデザイナーやWebライター、プログラマーなどは一人で黙々と作業しやすい仕事があげられます。
HSPの人は刺激や人間関係に敏感なため、職場でのストレスがたまりやすく、過去に仕事を何度も辞めた経験がある方も多いでしょう。
この記事ではHSPの人が「続いた仕事」を9つ紹介していますので、「他のHSPの人はどんな仕事をしているんだろう?」と気になっている方はぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
HSPの人が続いた仕事9選
HSPの人が続いた仕事としては、WebデザイナーやWebライターなど、IT・Web系の仕事が多く挙げられます。植物工場の栽培管理やペットシッターなど、植物・動物を相手にする仕事も長く続きやすい仕事の代表例です。
宅配便配達員や工場作業員のように、業務時間中は一人で黙々と作業に集中できる仕事もHSPの人から人気を集めています。
ここでは「HSPの人が続いた仕事」を9つ紹介しますので、長く安心して働ける仕事を探すヒントにしてみてください。
1. Webデザイナー
Webデザイナーは自分のペースで創造性を発揮できるため、HSPの人に向いています。
Webサイトのデザインやレイアウト、色使いを考え、訪問者が使いやすいサイトを作るのが主な仕事です。クライアントの要望をヒアリングする過程で人との関わりが生じますが、それ以外は一人で集中して作業を進められることがほとんどです。
細部への気配りや色彩感覚の鋭さ、ユーザーの心理を読み取る力など、HSPならではの特性を活かせることもメリットといえるでしょう。
| 平均年収 | 509.3万円 |
| 役に立つ資格 | ・ウェブデザイン技能検定 ・CGクリエイター検定・色彩検定 |
| 必要なスキル | ・HTML/CSSのコーディングスキル ・PhotoshopやIllustratorの操作スキル ・UI/UX設計の基礎知識 ・レスポンシブデザインの設計スキル ・Webアクセシビリティに関する知識 |
出典:厚生労働省「Webデザイナー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
2. Webライター
Webライターは自分のペースで作業をしやすいため、HSPの人に向いています。
インターネット上の記事や商品説明文などの文章を作成する仕事で、執筆作業の多くは在宅でも行えます。
取材や打ち合わせもオンラインで完結することが増えており、対面のやりとりが少ない点も安心材料です。人との関わりを最小限に抑えられるため、精神的な負担を減らせる点は大きなメリットといえるでしょう。
表現に対する感受性の強さや、読者の心情を想像できる、というHSPの強みを活かせる点もWebライターをおすすめできる理由の一つです。
| 平均年収 | 351万円 |
| 役に立つ資格 | ・WEBライティング技能検定 ・日本語検定 ・SEO検定 |
| 必要なスキル | ・SEOライティングの知識 ・構成案の作成スキル ・読者ニーズを分析する力 ・CMSの操作スキル(WordPressなど) ・リサーチ力 |
出典:求人ボックス 給料ナビ「ライターの仕事の年収・時給・給料」
3. プログラマー
プログラマーは「注意力」を活かせる仕事のため、HSPの人に向いています。
プログラマーは、コンピュータプログラムや、システムの設計・開発などを行う仕事です。
HSPの方は細部への注意力が高いため、細かな作業が続く「コーディング作業」で特に力を発揮しやすいでしょう。
在宅勤務やリモートワークができる会社も増えており、人間関係のストレスを抑えやすいため、「続いた仕事」としてプログラマーを挙げるHSPの人は少なくありません。
| 平均年収 | 557.6万円 |
| 役に立つ資格 | ・基本情報技術者試験 ・応用情報技術者試験 ・情報セキュリティマネジメント試験 |
| 必要なスキル | ・JavaやPythonなどのプログラミング言語の習得 ・アルゴリズムとデータ構造の理解 ・デバッグとテストの実施スキル ・バージョン管理(Gitなど)の知識 ・開発環境の構築スキル |
出典:厚生労働省「プログラマー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
4. インフラエンジニア
インフラエンジニアは変化に敏感な特性を活かせるため、HSPの人に向いています。
インフラエンジニアは、サーバーやネットワーク機器などの構築や保守などを行う仕事です。
HSPの方は細かな変化に気づけるため、システムの不具合を早期に発見する場面において、その“感度の高さ”が大きな強みになるでしょう。
定型化されている業務が多く、突発的な対応以外は精神的な負担が少ないため、HSPの方でも安心して働きやすい仕事といわれています。
| 平均年収 | 684.9万円 |
| 役に立つ資格 | ・ネットワークスペシャリスト ・データベーススペシャリスト ・Linux技術者認定資格 |
| 必要なスキル | ・サーバー構築のスキル(Linux/Windows) ・ネットワーク構成とルーティングの理解 ・監視ツールの運用知識 ・仮想化技術の操作スキル ・シェルスクリプトや自動化ツールの活用スキル |
出典:厚生労働省「システムエンジニア(基盤システム) – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
5. 植物工場の栽培管理
植物工場の栽培管理は「繊細さ」を活かせる仕事のため、HSPの人に向いています。
温度や湿度、光量などを管理し、野菜や果物を最適な環境で育てる仕事で、生育状況の観察や収穫、データ分析なども行います。
HSPの方は植物の微細な変化に気づきやすく、「栽培環境の微調整」といった作業が得意な傾向があります。
人との関わりが比較的少なく、植物を育てる喜びを感じられる点も精神的な安定につながるでしょう。マニュアル作業が多いので業務の流れをあらかじめ把握しやすく、落ち着いて働ける点も魅力の一つです。
| 平均年収 | 374.4万円 |
| 役に立つ資格 | ・園芸装飾技能士 ・植生管理士 ・水耕栽培士 |
| 必要なスキル | ・水耕栽培や養液栽培に関する知識 ・植物の生理生態に関する理解 ・栽培環境(温度・湿度・CO₂)の制御技術 ・異常個体の発見と対処能力 ・栽培データの記録 ・分析スキル |
出典:厚生労働省「植物工場の栽培管理 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
6. ペットシッター
ペットシッターは対人ストレスを減らせるため、HSPの人に向いています。
留守中の飼い主に代わってペットの世話をする仕事で、餌やりや散歩、トイレの清掃などの基本的なケアを行います。
人間相手のコミュニケーションに比べ、動物との関わりはストレスが少ないので、心地よさを感じながら働ける方は多いでしょう。
「続いた仕事」として動物と関わる仕事を挙げるHSPの方は多いため、長く働ける仕事を探している方はペットシッターも選択肢に加えてみてください。
| 平均年収 | 200〜300万円 |
| 役に立つ資格 | ・認定ペットシッター ・ペットシッター士 ・愛玩動物飼養管理士 |
| 必要なスキル | ・動物の健康状態に気づく観察力 ・犬や猫などの基本的な世話に関する知識 ・動物の種類や性格に応じた対応スキル ・散歩や給餌、トイレ処理などの実務スキル ・飼い主からの依頼内容を正確に把握する力 |
出典:動物資格ナビ「ペットシッターの給料っていくら?相場などをご紹介」
7. 経理
経理は「正確さ」を活かせる仕事のため、HSPの人に向いています。
会社の財務状況を記録・管理し、帳簿をつけたり、決算書を作成したりする仕事です。
HSPの方は細部に気を配れるため、数字の間違いに気づきやすく、正確な処理が求められる経理の仕事でその強みを発揮できます。
他部署との関わりはありますが、基本的には社内で業務が完結するため、対人ストレスを抑えられる点も特徴です。
定型業務が中心のため、イレギュラー対応が苦手なHSPの方でも安心して働ける仕事といえるでしょう。
| 平均年収 | 484.6万円 |
| 役に立つ資格 | ・日商簿記検定(1級・2級) ・税理士試験科目(簿記論など) ・MOS |
| 必要なスキル | ・仕訳 ・伝票処理の実務能力 ・月次・年次決算業務の知識 ・会計ソフトの操作スキル ・税務申告に関する基礎知識 ・予算管理 ・資金繰り表作成スキル |
出典:厚生労働省「経理事務 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
8. 宅配便配達員
宅配便配達員は一人で行動する時間が長いため、HSPの人に向いています。
各家庭や事業所に荷物を届ける仕事で、配達ルートを効率よく回り、受取人に確実に荷物を手渡すことが求められます。
配達作業中は、車内やバイクで一人で過ごす時間がほとんどです。そのため、人との関わりでストレスを抱えがちなHSPの方でも落ち着いて取り組みやすい仕事といえるでしょう。
体力は必要ですが、自分のペースで動ける場面が多いため、仕事に慣れて体力がついてくれば無理なく働き続けられるはずです。
| 平均年収 | 393.6万円 |
| 役に立つ資格 | ・準中型自動車免許 ・運行管理者(貨物) ・フォークリフト運転技能講習修了証 |
| 必要なスキル | ・配送ルートの最適化スキル ・荷物の積載 ・積み下ろしの効率的な技術 ・伝票の照合作業の正確性 ・ハンディ端末の操作スキル ・天候や交通状況に応じた判断力 |
出典:厚生労働省「宅配便配達員 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
9. 工場作業員
工場作業員は決められた手順をもとに黙々と働ける仕事のため、HSPの人に向いています。
製品の組み立てや検品、梱包などを工場内で行う仕事で、担当する工程によっては部品の取り付けや機械の操作、品質チェックなどを任されることもあります。
決まった時間に同じ作業を繰り返す仕事のため、業務の流れが大きく乱れることがなく、落ち着いて働ける点が魅力といえるでしょう。
業務中はコミュニケーションが最小限で済むため、「続いた仕事」として工場作業員を挙げるHSPの方も少なくありません。
| 平均年収 | 340.1万円 |
| 役に立つ資格 | ・フォークリフト運転技能免許 ・危険物取扱者 ・電気工事士 |
| 必要なスキル | ・製造工程の手順の理解 ・機械や設備の基本操作技術 ・品質チェック ・検査の知識 ・マニュアルに基づく正確な作業遂行能力 ・異常発見時の初期対応スキル |
出典:厚生労働省「工場労務作業員 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
HSPの人が続く傾向がある3つの業界
HSPの人は、クリエイティブ業界のように「感性」を活かせる業界が向いています。
Web・IT業界や、自然・動物と関わる業界など、他の人とのコミュニケーションが比較的少ない環境で働くのもおすすめです。
実際、これらの業界の仕事をすることでいきいきと働けるようになり、「続いた仕事ができた」と話すHSPの人は少なくありません。
それぞれの業界の特徴を紹介しますので、長く続く業界を探しているHSPの人は参考にしてみてください。
1. クリエイティブ業界
クリエイティブ業界は繊細な感性を活かせるため、HSPの人に向いています。
HSPの人は、色の微妙な差や音の変化、人の気持ちなどに敏感で、こうした感受性は創作現場で大きな力を発揮します。
たとえばWebデザイナーやライターなどの仕事では、見る人や読む人の心に自然と響く表現が求められます。その点、HSPの人は「言葉にしづらい感情を形にしてくれる」「他にはない温かみや深みを感じる」といった評価を受けることも多いでしょう。
このように自分の感性を仕事に活かしやすいため、クリエイティブ業界はHSPの人が長く働きやすい業界といえるのです。
2. Web・IT業界
Web・IT業界は一人で集中して作業する時間が長いため、HSPの人に向いています。
HSPの人は刺激に敏感で、人との関わりが多い環境では疲れやすい傾向があります。その点、Web・IT業界では、プログラミングやコーディング、デザイン制作など、静かな環境で自分のペースで取り組める業務が多く、HSPの人にとって心地よい働き方が可能です。
Web・IT業界を中心にリモートワークが広がっている点も、安心材料といえるでしょう。
このようにWeb・IT業界は一人の作業時間が比較的多いため、HSPの人でも無理なく仕事を続けられる可能性があるのです。
3. 自然・動物と関わる業界
自然や動物と関わる業界は人間関係による消耗が少ないため、HSPの人に向いています。
HSPの人は、人の感情や周囲の雰囲気に敏感で、複雑な人間関係に強いストレスを感じやすい傾向があります。
その点、自然や動物と接する仕事ではそうした負担が軽減されやすく、自分らしく働ける可能性があるでしょう。
たとえばペットシッターとして働くと、業務中は動物と過ごす時間が中心で、飼い主とのコミュニケーションも必要最低限で済みます。
以上の理由から、「続いた仕事」として自然・動物と関わる業界の職種を挙げるHSPの人は多いのです。
HSPの人が避けたい仕事の特徴
HSPの人が続いた仕事や業界を紹介してきましたが、反対に「避けたほうが良い仕事」としてはノルマや売上目標がある仕事が挙げられます。
初対面の人と常に関わる仕事や、マルチタスクが求められる仕事も長く続かない可能性があるので、できる限り避けたほうが良いでしょう。
ここでは、HSPの人が避けたい仕事の特徴を3つ紹介します。転職を繰り返したくない方や、ストレスなく働き続けられる仕事を探しているHSPの方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. ノルマや売上目標がある仕事
数字による評価やプレッシャーが常にかかる仕事は精神的な負担が大きいため、HSPの人には向いていません。
HSPの人は目標達成への不安や焦りを強く感じやすいため、数字に追われる職場は心の負担が蓄積しやすく、ストレスにつながりやすいのです。
たとえば営業職では「今月中にあと3件契約を取らないと目標未達になる」といった状況が日常的にあり、特にHSPの人は「達成できなかったらどうしよう…」という不安から眠れなくなる可能性もあるでしょう。
ノルマや売上目標がある仕事は心労が増えやすいため、HSPの人はできる限り避けることをおすすめします。
2. 初対面の人と常に関わる仕事
初対面の人と関わる仕事はストレスを感じやすいため、HSPの人にはあまり向いていません。
HSPの人は相手の気持ちを敏感に察知するため、初めて会う人とのやりとりでは「相手が何を考えているか」と神経を使いすぎてしまい、心身ともに疲れやすくなります。
たとえば販売員として働くと、「お客さんに不快な思いをさせていないか」「もっと親切にできたのでは」と考え続けてしまい、常に緊張状態が続いてしまうこともあるでしょう。
HSPの人は新しい人間関係を築き続ける仕事に強い疲労を感じやすいため、初対面の人と関わり続ける職種もおすすめできません。
3. マルチタスクが求められる仕事
一度に処理する情報が多すぎて疲れやすいため、HSPの人はマルチタスクが求められる仕事にも向いていません。
HSPの人は周囲の刺激や細かな変化に敏感なため、同時に複数の業務に対応する環境だと“過負荷”になりがちです。
たとえば飲食店のホールスタッフは、お客様の注文を取りながら他のテーブルの状況を把握し、厨房との連携も行う必要があります。このように常に異なる情報が飛び交う環境で働くとHSPの人は混乱しやすく、精神的に消耗してしまいます。
そのため「長く続いた仕事」として、このようなマルチタスクが必要な仕事を挙げるHSPの人は多くないのです。
HSPの人が仕事を続けにくい3つの理由
HSPの人が仕事を続けにくい理由としては、多くの刺激で疲れてしまうことが挙げられます。
人間関係のストレスをためやすいことや、完璧志向が強すぎることも長続きしない要因といえるでしょう。
HSPでも続いた仕事を知りたい方の中には、「どうして自分だけいつもうまくいかないのか…」と悩んでいる人も多いかもしれません。
こうした方は、これから紹介する3つの理由を知ることで、自分に合わない働き方を見直すヒントを手にしてみてください。
1. 多くの刺激によって疲れてしまうから
HSPの人はエネルギーの消耗が激しいため、仕事を長く続けにくい傾向が見られます。
たとえばオフィスで働く場合、電話の着信音やキーボードの打鍵音が気になったり、上司や同僚のピリついた空気を察知したりして疲労感を強く覚えてしまう方は多いでしょう。
特に転職して間もない時期は新しい環境に慣れず、常に神経を張りつめた状態になりがちです。その結果、必要以上に気疲れし、「自分にはこの職場は合っていないのでは…」と悩んでしまうこともあります。
このようにHSPの人は刺激に人一倍敏感で、心が疲れやすいため、一つの仕事を長く続けにくいのです。
2. 人間関係のストレスをためやすいから
HSPの人は他の人の些細な言動に敏感に反応し、人間関係のストレスをためやすいため、仕事を続けにくい傾向が見られます。
たとえば、上司に声をかけたときに「あとにして」と冷たく返されたことで、「怒らせてしまったのでは…」と気に病み、出社するのが怖くなってしまうケースも珍しくありません。
HSPの人は“言葉の裏側”を自然と読んでしまうので、たとえ相手に悪気がなくても深く傷ついてしまうことがあります。
このように人間関係が原因で精神的な負担が蓄積しやすく、結果として「この環境で長く続けるのは厳しいかもしれない」と感じてしまう人が多いのです。
3. 完璧志向が強すぎるから
HSPの人は完璧志向ゆえに自分を追い込みすぎてしまう人も多く、仕事を続けにくい傾向が見られます。
たとえば明らかにキャパオーバーの仕事を前にしても、「自分が頑張ればなんとかなる」「ここで手を抜いたら迷惑をかける」と考え、深夜まで残ってでも仕上げようとすることがあるでしょう。
誰かに頼るのが苦手な人も多く、真面目に仕事をこなす傾向がありますが、こうした姿勢が行きすぎると自分でも気づかぬうちに精神的・体力的に大きく消耗してしまいます。
その結果として、「続いた仕事がない」という状態に陥ってしまうHSPの人は多いのです。
HSPの人が仕事を長く続ける5つのポイント
「HSPの人が続いた仕事」に就けたとしてもストレスの感じ方は人それぞれのため、仕事を長く続けたい方は自分にとってのストレス要因を把握することが大切です。
疲れたときのリフレッシュ法を用意しておく、「100点ではなく60点を目指す」といった心構えを持っておくことも有効でしょう。
ここでは上記のポイントを含め、HSPの人が仕事を長く続けるためのコツを5つ紹介します。
少しでも長く働き続けたい方は、ご自身の日々の仕事や転職活動にぜひ取り入れてみてください。
1. 自分の「ストレス要因」を把握する
自分に合った環境が選びやすくなるため、仕事を長く続けたいHSPの人は自分の「ストレス要因」を把握しておきましょう。
たとえばオフィスで左右と前に同僚がいて、常に視線や気配を感じる環境だと緊張が続いて疲れてしまう方は多いはずです。
このとき「自分は近くに人がいるときに疲れが特にたまる」と気づけていると、フリーアドレスをオフィスに導入している会社など、物理的な距離を保てる職場を意識的に選ぶ、といった選択をとれるようになります。
無理なく仕事を続けるためにも、自分にとって何が負担になるのか?をまずは把握しておきましょう。
2. 疲れたときのリフレッシュ法を考えておく
心と身体が限界に達することを防げるため、仕事を長く続けたいHSPの人は自分なりのリフレッシュ法を考えておくことも大切です。
HSPの人は他の人以上に刺激に敏感で疲れやすいため、「こうすれば少し楽になれる」と思える習慣を事前に持っておくことが日々の負担を減らすうえで欠かせません。
たとえば、仕事終わりに静かなカフェで一人の時間を過ごすことで頭がリセットされ、モヤモヤとした気持ちを翌日に持ち越さずに済む人は多くいます。
ストレスをため込みすぎずに長く働くためにも、自分に合ったリフレッシュ法をぜひ見つけておきましょう。
3. 100点ではなく60点を目標にする
心にゆとりが生まれるため、仕事を長く続けたいHSPの人は「100点ではなく60点」を目標にしてみましょう。
HSPの人は真面目で責任感が強い傾向があるため、ほんの少しのミスでも自分を責めてしまい、精神的に追い込まれてしまうケースが見られます。
一方で「完璧じゃなくて大丈夫」と考えるようになってから心に余裕ができ、「初めて続いた仕事になった」と話すHSPの人は少なくありません。
完璧主義は悪いことではありませんが、HSPの人の場合は心身の負担が大きくなりやすいため、まずは60点くらいを目標に仕事に取り組むことをおすすめします。
4. 自分のペースで取り組める仕事を選ぶ
周囲に振り回されずに働けると力を発揮しやすくなるため、仕事を長く続けたいHSPの人は自分のペースで取り組める仕事を選びましょう。
HSPの人は「急な変化」が苦手な傾向があり、予期せぬ出来事が頻繁に起こる職場で働くと心身に不調をきたしてしまうことがあります。
一方で、Webライターや経理のように、与えられたタスクを期日までにこなすことが求められる仕事は自分のペースで作業をしやすく、変化によるストレスを強く感じずに済みます。
安心して長く働き続けるためにも、HSPの人はマイペースに取り組みやすい仕事を意識的に選ぶようにしましょう。
5. 静かな職場環境や在宅OKの仕事を選ぶ
HSPの人は「音」による疲労も感じやすいため、騒音が少ない環境を選ぶことも重要です。
オフィスでは、キーボード音や電話応対の声など様々な音が飛び交うため、HSPの人の中には仕事に集中できない方も多いはずです。
こうしたストレスを減らすには、たとえばフレックスタイム制を導入している会社に転職し、同僚や上司がまだ出社していない早朝から仕事を始めるといった工夫が有効です。在宅勤務ができる職場を選ぶのも手といえるでしょう。
HSPの人にとって騒音は大きなストレス要因のため、静かな職場環境や在宅OKの仕事を積極的に探してみてください。
まとめ
この記事では、HSPの人が続いた仕事を紹介しました。
たとえばWebデザイナーやWebライターのように、自分の感性を活かしやすく、一人の作業時間が多い仕事はストレスが少ないため多くのHSPの人が活躍しています。
「今度こそ長く続く仕事をしたい」と思っている方は、上記のような仕事をぜひチェックしてみてください。