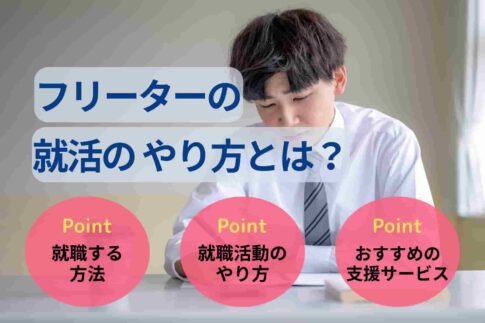既卒1年目の就活は、新卒枠で挑戦できる貴重なタイミングであり、行動次第で有利に進められる期間です。
本記事では、自己分析から企業研究、面接対策までの8つのステップを整理し、失敗を防ぐための注意点も解説します。空白期間の説明や求人の選び方を工夫することで、既卒でも着実に内定獲得を目指せます。
この記事の目次
既卒の定義とは
既卒とは「大学・短大・専門学校・高校を卒業後、一度も就職したことのない人」を指します。
学校を卒業してから1〜3年の若い人の呼称として使われることが多いようです。
既卒の状態になる人の理由には、主に以下のような事情があります。
- 在学中の就職活動が上手くいかなかった
- 資格試験に合格できなかった
- 企業からの採用内定を辞退した
ちなみに、卒業後にアルバイトで働いている人も「既卒」という扱いになります。
一方、企業が既卒者を採用する場合には、以下のような理由や方針があるようです。
- 新卒採用だけでは、十分な人員を確保できなかった
- 若く活躍が期待できる人材なら、新卒でなくても採用したい
既卒とよく混同されるのは「第二新卒」です。「学校を卒業してから就職し、1〜3年位で転職する人」を指します。「学校を卒業してから1〜3年たっている」という点では既卒と同じですが、第二新卒には『就業経験』があります。
既卒と第二新卒との違いを明確にするため、それぞれのメリット・デメリットを下表にまとめました。ご参照ください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 既卒 | ・学校卒業後3年以内なら「新卒枠」でエントリー可能な求人がある ・比較的に好きなタイミングで就活できる | ・大企業に就職しづらい(大企業には「既卒枠」がない場合が多いため) ・「第二新卒枠」の求人に応募できない ・「なぜ就職しなかったのか」と疑問を持たれやすい |
| 第二新卒 | ・基本的なビジネスマナーが身に付いていると考えられている ・転職先によっては、前職の経験やスキルが活かせる ・社会人経験があり、新卒や既卒より早く職場環境になじみやすい印象がある | ・「新卒枠」の求人にエントリーできない ・入社しても、またすぐに辞めるのではないかと不安視されやすい |
既卒1年目の就職活動の進め方
既卒1年目の就職活動の進め方には、大きく8つのステップがあります。
- 求人を探す
- エントリーをしながら企業研究を行う
- 面接対策を行う
- 求人を探す
- エントリーをしながら企業研究を行う
- 面接対策を行う
- 企業と面接を実施する
- 雇用条件や入社日を実施する
以下、それぞれのステップに関する詳細を解説しています。
1. 自己分析をする
既卒1年目の就活は基本に沿って進めることが重要なため、まずは自分の強みや弱み、やりたい仕事を明確にするために自己分析を行います。
自己分析をすることで、企業選びの軸と面接時のアピールポイントに一貫性が持てるようになるため、採用担当者からの見え方がポジティブになります。
自己分析としては、学生時代に力を入れたことや、アルバイト経験から得たスキルや感じたことを言語化し、自身がどういった環境で最大限の力を発揮できるのか整理することに取り組みます。
特に既卒者の場合は、なぜ学校を卒業してから就職をするまでに遅れてしまったのかというポイントを、明確に説明できる状態にしておくのが重要になってきます。
言語化した事はノートにまとめたり、他人と壁打ちをしてみることにも取り組んでみましょう。
2. 履歴書を作成する
履歴書を作成する上では、性格かつ読みやすい記載を心がけるとともに、学校を卒業してから就活をするまでの空白期間について、ポジティブな表現で言い換えることが大切になってきます。
履歴書の学歴や職歴欄を見れば、採用担当者に空白期間があることが分かってしまいますので、空白期間については「自己分析に時間をかけていた」「長期的に働ける職場を見定めていた」など、将来に向けた準備期間であったことを前向きに表現しましょう。
また、履歴書に記載する志望動機や自己PRは、応募先の企業ごとに調整することがポイントです。自己分析で整理した過去の経験を踏まえつつ、具体的にどういったスキルを活かせるのか記載することで、既卒でも書類選考に通過しやすくなるでしょう。
3. 就職サービスに登録する
既卒が就職活動を進めていく場合は、就職サービスに登録することが必須とも言えます。既卒者向けのサービスとしては、以下の3つが挙げられます。
- 就職エージェント
- 求人サイト
- ハローワーク
それぞれ特徴が異なりますので、自分の状況や考えている就活の進め方にマッチした方法を選ぶことが大切です。
ここではそれぞれの就職サービスについて、もう少し詳しく深掘りして解説します。
就職エージェント
就職エージェントは、登録した後に自分専任のアドバイザーが担当につき、応募書類の添削や模擬面接を始め、幅広いサポートを受けながら就活を進めていく方法です。
既卒者専用のサポートを提供していることも多く、企業とのマッチングを重視した就活を進められるため、自分1人では見つけられなかったような求人を見つけやすいといった特徴があります。
また、プロの視点からキャリアの棚卸しや志望動機の整理をしてもらうこともできますので、自信を持って就活に臨めるだけでなく、書類選考や面接の通過率を引き上げることも期待できます。
幅広いサポートを受けられる就職エージェントですが、登録や利用にお金がかかる事はありませんので、気になる既卒者向けの就職エージェントを見つけたら、積極的に登録していくことをおすすめします。
求人サイト
求人サイトは、登録後に自分で求人を検索して応募先を見つけていくことで、就活を進めるような方法となっています。スマホアプリの展開を行っている求人サイトも多く、時間や場所を選ばずに、自分のペースで就活を進められるといった特徴があります。
加えて、求人サイトでは一度にたくさんの求人を検索しながら比較検討できるため、幅広い選択肢から自分に合った求人を見つけやすいというのもメリットと言えるでしょう。
ただし、求人サイトの場合は書類作成から求人の選定、企業の採用担当者との連絡などを全て1人で進めなければならないため、既卒1年目の就活という観点だとやや難易度が高い方法と言えるかもしれません。
したがって、求人サイトを使う際は、並行して就職エージェントも活用することがおすすめです。
ハローワーク
ハローワークは国が運営する公共職業安定所であり、最寄りのハローワークに行くことで既卒者でも就活を進めることができます。
ハローワークに掲載されている求人の検索や、職員に対する職業相談も行えるため、既卒1年目で就活が初めてという人でも安心して利用できます。
掲載されている求人としては地元密着型の企業が多く、現在住んでいる場所で腰を据えて長く働きたいと考えている人に特におすすめできます。
ただし、ハローワークでの職業相談は毎回担当してくれる職員が異なりますので、自分の状況を相談の都度1から話さなければなりません。
専任の担当者に就活の全てをサポートしてもらいたい場合は、ハローワークではなく専任担当制の就職エージェントの方が向いていると言えるでしょう。
4. 求人を探す
まずは、応募したい求人を探しましょう。既卒の人が応募する求人は、大きく2パターンに分かれます。
- 既卒向け、通年採用の求人
- 新卒向け、就活解禁後の求人
この2つの求人はエントリーするタイミングが異なるので、自分の応募したい求人はどちらのタイプなのか確認しておきましょう。それぞれのメリットとデメリットは、以下の通りです。
| 求人対象 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 既卒向けの求人 | 比較的に好きなタイミングで応募できる | 求人数が少ない |
| 新卒向けの求人 | 求人数が多い | エントリーできる時期が就活解禁後なので、それまで待たないと応募できない |
業種・職種に特にこだわりがなければ、まずは既卒向けの求人を探してみて、気に入った求人がなければ新卒向けの求人も視野に入れる手順がおすすめです。
これは既卒・新卒という括りよりも「就職したいと思える企業で働くこと」が第一であり、応募したい求人が見つかったら、すぐに行動する方が得策といえるからです。
5. エントリーをしながら企業研究を行う
エントリーする企業が決まったら、次はエントリー手続きと企業研究を同時に進めます。
企業研究は、以下の6ステップで進めるのがおすすめです。
- 自分の考える「最低限の希望条件」をクリアしているか
- これまでの業績に問題がないか
- 競合他社との違いを文章にまとめる
- 企業の担当者に聞きたい質問内容をまとめる
- 選考情報を整理する
- 履歴書・職務経歴書などの書類対策をする
企業分析を丁寧に行うことで、より自分に合った企業かどうかが判断しやすくなります。入社後の満足度に大きく関わるので、企業研究はしっかりやっておきましょう。
またこの時、面接に備えて以下の内容を速やかに答えられるよう、準備しておくのも大切です。
- その業界を選んだ理由
- その職種を選んだ理由
- 企業理念に共感できるか
- なぜ競合他社でなく、その会社で働きたいのか
- その会社の、どの事業に携わりたいか
逆に、これらの質問に答えられないと、採用担当者から「企業研究が不十分」とみなされてしまいます。
特に、日本の就活においては、既卒よりも新卒が有利です。「既卒が新卒に勝てるポイントは、企業研究の質にある」といっても過言ではありません。企業研究をしっかり行い、新卒に差をつけましょう。
6. 面接対策を行う
企業研究が一通り済んだら、早めに面接対策もしておきましょう。
面接で最も重要なのは「自分の魅力を面接官に伝えること」です。しかし、多くの人が「面接で評価されるには、話が上手くなければならない」と勘違いをしています。雑談がおもしろくても、その人の人柄や魅力が伝わらなければ意味がありません。逆に、流ちょうに話せなくても、コツさえ掴めば「自分はどんな人間か」をしっかり伝えられるようになります。
- 自分の強みと弱み
- 周りからどのような人だと言われるか
- 組織や集団でどういった役割を務めることが多いか
- 大切にしている価値観
- これまでの挫折体験
- どういった時にやる気が出るか
多少の表現は違えど、上記のような質問をされることが多いので、短めに分かりやすく伝えられるよう準備しておきましょう。
また、既卒になった理由は、なるべくポジティブに伝えることが大切です。
例えば「就活が上手くいかなかったから」だけでは、面接官から「準備不足で計画性のない人」と思われてしまいます。実際に就活が上手くいかなかった場合でも、以下のような説明を加えましょう。
- 大手企業を中心に応募していたが、途中から目指す方向性が変わり、一度じっくり自己分析する時間を取った
- 希望条件を多く設定しすぎていたが、本当に自分が求める働き方が分かった
- アルバイトに熱中しすぎていたことを反省し、今は就活に力を入れている
「失敗から学びを得て、それを今後に活かそうとしている姿勢」が伝われば、前向きでポジティブな印象を与えられるでしょう。
7. 企業と面接を実施する
就職サービスに登録し、面接の機会を得ることができたら企業と面接を実施します。
面接は企業と応募者の相互理解の場となりますので、聞かれた質問に答える事はもちろん、自分から企業を見定めていくといった意識がポイントです。
また、既卒者の場合は面接において就活が遅れた理由を聞かれることが多いため、緊張をすることなく前向きな理由で回答することを心がけましょう。
既卒で空白期間があることを、どのように前向きに伝えればいいのか悩んでしまう場合は、就職エージェントやハローワークで模擬面接を経験しておくことが大切です。
8. 雇用条件や入社日を決めて入社
内定を獲得できた後は、雇用条件や入社日について確認し、納得できれば内定承諾となります。特に給料や勤務地、働き方については応募時の求人票の内容と雇用条件が同じものであるかを念入りに確認しておいてください。
内定獲得後から入社までの期間は規則正しい生活を心がけ、入社日以降、
は社会人として問題なく働けるコンディションを作っておきましょう。
既卒1年目の就活で知っておくべきこと
既卒1年目の就活を進める際には、以下のようなポイントを知っておくことで、効率的に内定を目指せるようになります。
- 既卒1年目は新卒枠で応募できる可能性がある
- 就活は早めの方が有利
- 求人はできる限り広く見る
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
既卒1年目は新卒枠で応募できる可能性がある
企業によっては、既卒1年目であれば新卒枠で就活を進められるケースがあります。
厚生労働省は卒業してから3年以内の既卒者は、新卒枠で応募受付をするように企業に声掛けをしているため、厚生労働省の方針に従っている会社であれば、既卒1年目の就活を募集定員の多い新卒枠を応募することが可能です。
新卒枠であれば既卒枠よりも募集が多いため、競争倍率が低くなりやすかったり、コミュニケーション能力やポテンシャルだけで内定を目指せるといった様々なメリットがあります。
就活は早めの方が有利
既卒1年目の就活だと、何からすればいいのか分からず、行動を先延ばしにしてしまいがちですが、空白期間が長引けば長引くほど正社員になれる可能性が低くなっていってしまいますので、就活はなるべく早めに取り組むことが大切です。
空白期間が長引くと、企業側は「既卒になってから就職をせず何をしていたのか」と疑問を持ってしまい、ネガティブな印象に繋がることもあります。既卒1年目はとにかく早めに就活を進めることで、企業側に真剣に就職を考えている熱度を伝えることを意識してみてください。
就活を何から進めていけばいいか分からずに最初の1歩が踏み出せていない場合は、就活の基本的な流れに沿ってサポートを進めてくれるような、既卒に強い就活エージェントに登録してみることがおすすめです。
求人はできる限り広く見る
既卒1年目の就活では、自分がイメージできる業界や職種にばかり偏って求人を比較検討してしまう傾向にありますが、出来る限り広く様々な求人を比較検討することによって、自分が気づいていなかった思わぬ好条件の企業に出会える可能性が高まります。
特に既卒1年目の場合は、未経験者歓迎の求人や研修制度が整っている求人に絞って検索することで、自分にとって働きやすい環境を見つけやすくなります。
また、条件を絞りすぎてしまうと応募できる求人を大きく狭めてしまい、就活を前に進められないといった事態にもなりかねませんので、どうしても譲れない条件を1つに絞り、残りの条件は優先順位をつけて柔軟に求人を見定めるといった考え方も重要です。
求人を探す際は、就職エージェントや求人サイトの検索機能を柔軟に活用し、様々な切り口から求人を探すことが就活の成功に繋がります。
既卒1年目の就活のコツ
既卒1年目の就活を成功させるためには、基本的な就活の流れをインプットしておくだけでなく、選考の通過率を引き上げるためのコツを身に付けておくことが大切です。
既卒1年目の就活のコツとしては以下の4点が挙げられます。
- 既卒になった理由を言語化する
- 気になる会社に積極的に応募する
- ゴールを決めた上で就活をスタートする
- 就職エージェントを活用する
それぞれのコツについて詳しく解説しますので、既卒1年目の就活に役立ててみてください。
1. 既卒になった理由を言語化する
既卒1年目の面接では、面接官からなぜすぐに就職をしなかったのかについて高い確率で問われます。
この時、既卒になった理由がネガティブに伝わってしまうと、それだけで落ちてしまう原因になりかねませんので、あらかじめ既卒になった理由を言語化して整理しておくことがコツになってきます。
なんとなく既卒になった人であっても、就活に向けて努力をしている人であれば「後悔をしない就活をするために自己分析に時間をかけていた」という理由が伝えられますし、他にも「資格取得のために勉強していた」という理由であれば、知的好奇心や行動力の高さのアピールに繋げられます。
既卒になった事実は後から変えられるものではありませんので、これからどうなっていきたいかを前向きに伝えることを意識してみてください。
2. 気になる会社に積極的に応募する
既卒だからといって応募を控えるのではなく、気になる企業があれば積極的に応募するといった意識を持っておくことが、就活を成功させるポイントと言えます。
既卒枠にしろ新卒枠にしろ、就活はタイミングによって大きく左右されるもののため、求人に応募できるというチャンスを逃さないことが重要です。
また、応募する際はとにかく数多く応募するといった意識だけを持つのではなく、履歴書や志望動機を応募先の企業ごとにカスタマイズすることで、採用担当者に熱意を伝えることも意識しましょう。
なお、求人サイトでも就職エージェントでも応募すること自体にデメリットはありませんので、少しでも興味を持ったら応募した方が損をしないとも言えます。
3. ゴールを決めた上で就活をスタートする
既卒1年目の就活は新卒と異なり、明確なスケジュールやデッドラインが存在しないため、よくも悪くも自分のペースで就活を進められるといった特徴があります。
ただし、ダラダラと就活を進めてしまうと書類選考や面接で落ち続けることに繋がり、結果的に就活を長期化させてしまう原因にも何か出ません。
既卒が就活を進める際は、あらかじめいつまでに就活を成功させるといったゴールを決めておくことが大切です。どうしても長期的な計画設計に苦手意識を持っている場合は、週ごとに細かく行動目標を持っておくのも良いでしょう。
また、自分でゴールを決めて行動をしていくことそのものに苦手意識がある場合は、就職エージェントを活用して、自分のやるべきことを管理してもらうというのもおすすめです。
4. 就職エージェントを活用する
既卒1年目の就活において、就職エージェントは幅広いサポートをしてくれるだけでなく、非公開求人の紹介や企業との面接日時の調整代行なども行ってくれるため、非常に心強い存在となるでしょう。
既卒1年目で初めて正社員を目指して就活を進めたい場合は、就活でやるべきタスクやスケジュール感をあらかじめ教えてもらうことで、安心した気持ちで内定を目指せるようになります。
就職エージェントには様々なサービスがありますが、特に既卒者向けの就職エージェントであれば、他のサービスよりも丁寧なサポートを受けられますので、既卒の就職支援実績が豊富なジェイックの利用も検討してみてください。
既卒1年目で押さえておくべき、就活での注意点
既卒1年目の人が押さえておきたい就活の注意点は、以下の2つです。
- 口コミを調べる
- 周りの人と自分を比較しない
それぞれの詳細を、解説していきます。
既卒向け求人は口コミを調べる
既卒者向けの求人では、必ずその企業の口コミ情報を確認しましょう。
新卒が予定よりも採用できずに既卒を募集しているケースも多く、つまりは「新卒の就活生から人気がなかった企業」という可能性があるからです。
特に、低評価の口コミがあまりにも多い場合は要注意です。人手不足で長時間労働を強いられたり、求人に書かれている採用条件と実態が違うなど、ブラック企業でないかは必ずチェックしましょう。
周りの人と自分を比較しない
既卒の人は、周りの人と自分を比較しないことも大切です。
同級生はすでに社会で活躍していることも多く、つい「自分だけがまだ就職できていない」と置いて行かれたような気になってしまうものです。特に近年は、SNSでお互いの近況を簡単にチェックできるので、知らず知らずのうちに周囲と自分を比較して、落ち込んでしまうことも少なくありません。
しかし既卒であっても、自分に合った企業に正社員での就職ができれば、新卒と同じ仕事ができます。新卒・第二新卒・既卒というのは、あくまでも「入社する際の状況」の違いであり、大事なのは「入社後に仕事でどれだけ活躍できるか」です。やりがいや楽しさを感じながら働くことができれば当然スキルアップも加速し、最初の1〜2年の差は大したものではなくなります。
周りと比較せず、自分の就活に集中しましょう。
- 同級生とは会わない
- SNSは開かない
就活期間中は上記のような工夫をし、周りと比較してしまう原因そのものを遠ざけるのがおすすめです。
既卒1年目の就活でよくある質問
最後に、既卒1年目の就活でよくある質問をいくつか取り上げて解説します。
既卒者の内定率は?
既卒者の内定率は、新卒に比べるとやや低い傾向が見られるものの、1年目であれば一定の高い水準を維持していると言われています。マイナビの調査によれば、既卒者の内定率は34.8%という結果となっているため、既卒者が正社員就職をすることが不可能ではないことが分かります。
業界や職種にかかわらず、日本では多くの企業で人手不足が続いています。
既卒であっても自己分析や企業研究をした上で入念な面接対策を行えば、正社員就職しやすい状況となっているため、内定率はあくまでも参考として捉えながら、就職エージェントと二人三脚で就活対策を進めていくことをおすすめします。
既卒でもガクチカは聞かれる?
既卒者であっても、面接で学生時代に力を入れたことを聞かれることがあります。
ガクチカを聞かれる理由は、既卒1年目だと実務経験がないため、それに準ずる学生時代の経験を具体的なエピソードとともに知るためだと言われています。したがって、新卒時のガクチカと同じように作り込むことが大切です。
また、学生時代に力を入れたことを説明するだけでなく、力を入れたことから何を学んだのかを自分の言葉で伝えることが最も重要です。もしガクチカが弱いと感じた時は、就職エージェントのアドバイザーに相談してみてください。
既卒で大企業に就職するのは無理ですか?
既卒だからといって、大企業へ就職することが無理ということはありません。
ただし、大企業は中小企業よりも求人に応募が集まりやすく、競争率が高まる事は避けられません。これによって、既卒者が書類選考で落ちてしまうことも考えられますので、しっかりと対策をしないと大企業に就職する事は難しいでしょう。
昨今では少子高齢化の影響もあり、大企業でも若手の募集が集まらないことに悩むケースが少なくありません。したがって、どうしても大企業に就職したいのであれば、日ごろから就職サービスにログインし、募集のタイミングを見逃さないことがポイントです。
また、既卒からいきなり大企業に就職するのではなく、まずは中小企業で経験を積んだ後に大企業へ転職するといったキャリアパスも考えられますので、中長期的な視点でキャリアを考える意識を持っておいてください。
既卒でも有利になる資格は?
基本的に就活において必須となる資格はありませんが、以下のような資格を持っておけると、書類選考や面接でプラスに働く可能性があります。
- 日商簿記検定
- ファイナンシャルプランナー
- 秘書検定
- マイクロソフトオフィススペシャリスト
- ITパスポート
- 基本情報技術者
- 宅地建物取引士
- 中小企業診断士
- 普通自動車免許
- TOEIC
既卒が就活のために資格を目指す際は、将来的に応募を考えている業種や職種に関連する資格を選ぶことがポイントです。
加えて、資格取得に時間をかけすぎてしまうと、空白期間が長引いて正社員になりづらくなることもあるため、状況によっては資格取得を諦めるといった判断も大切になってきます。
まとめ
ここまで、既卒1年目の人に向けて、就職活動の進め方を解説してきました。
既卒者の就活は、新卒や第二新卒よりも若干ハードルが上がりますが、攻略法を知ってしっかり対策しておけば、決して困難ではありません。
私たちジェイックも、あなたに適した企業さがしをサポートします。既卒1年目の就活攻略法をお伝えし、就活中はもちろん入社後のサポート体制もありますので、お気軽にご相談ください。