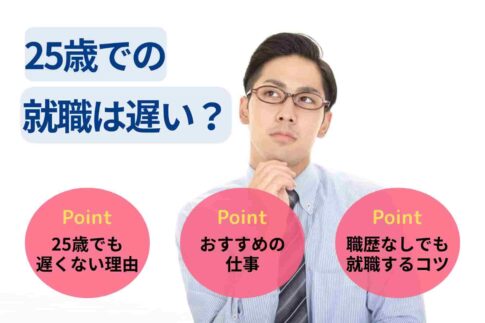既卒だから就職できない…と考えている人は多いかもしれませんが、新卒と同じ選考ルートで応募できる場合があり、既卒の採用に積極的な業界も多いため、就職を諦める必要はありません。
この記事では、既卒でも就職できる理由を詳しく解説しつつ、早めに就活を始める、「既卒歓迎」の求人を探すなど、正社員就職を成功させるコツも紹介します。
新卒と比べて既卒の就活は難しいのかな…と不安に感じている人は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
既卒でも就職できないわけではない
既卒でも就職できる理由としては、新卒枠で応募できる企業や、「戦力になれば新卒も既卒も関係ない」と考える企業が多いことが挙げられます。人手不足に悩んでいる企業が多いことも、既卒が就職できないわけではない理由の一つです。
約半数の企業が既卒者を「新卒として受け入れる予定」としており、「戦力になるのであれば新卒も既卒も関係ない」と答えた企業も9割近くにのぼっています(※)。
どの業界でも人手不足が深刻なため、特に20代の既卒者は「若さ」や「体力」などが評価され、社会人経験がなくても採用されるケースも増えています。
※ 出典:マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について」p.126
1. 53.2%の企業が既卒を新卒枠で受け入れているから
半数以上の企業が既卒を新卒枠で受け入れているため、既卒でも十分に就職のチャンスがあります。
マイナビの調査では、53.2%の企業が既卒者を「新卒として受け入れる予定」と答えています。つまり卒業後すぐに就職が決まらなくても、新卒と同じ条件で応募できる会社が多いということです。
新卒枠で応募するメリットとしては、「仕事経験がなくても内定をもらいやすい」「手厚い研修を受けられる可能性が高い」といったことが挙げられます。
なお、上場企業の6割以上が既卒者を新卒として採用する予定があるため、既卒であっても大手企業に入社できる可能性もあるのです。
▼既卒者採用の予定
| 26年卒 | 上場企業 | |
| 新卒として受け入れる(予定) | 53.2% | 65.1% |
| 中途として受け入れる(予定) | 19.5% | 11.3% |
| 受け入れない予定 | 8.6% | 9.0% |
| 未定 | 18.7% | 14.6% |
出典:マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について」p.126
2. 「戦力になれば新卒も既卒も関係ない」と考える企業が多いから
企業はあくまでも「自社で活躍できる人材」を求めているため、新卒か既卒かをそれほど重視しない企業も多くあります。
マイナビの調査を見ても、既卒者を受け入れる理由で最も多かったのは「戦力になるのであれば新卒も既卒も関係ない」で、全体の87.6%を占めます。
特に製造業は、既卒者を積極的に採用する企業が多いことが特徴です。事実、製造業の9割以上が「戦力になるのであれば新卒も既卒も関係ない」と答えています。
以上のことから、既卒でも自分の強みをしっかりアピールできれば就職のチャンスを十分につかめるのです。
▼既卒者を受け入れる理由(複数回答/「全体」の上位3つ)
| 理由 | 全体 | 製造業 |
|---|---|---|
| 戦力になるのであれば新卒も既卒も関係ない | 87.6% | 90.9% |
| 母集団の確保のため | 37.4% | 36.1% |
| すぐに入社できるので、来春まで待つ必要がない | 25.4% | 23.5% |
出典:マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について」p.126
3. およそ半数の会社が人手不足に悩んでいるから
多くの企業が深刻な人手不足に悩んでいるため、既卒者にも積極的に採用の門戸を開いています。
帝国データバンクの2025年4月の調査によると、「正社員が不足している」と感じている企業は51.4%で、半数以上の企業が人手不足に直面しています。
こうした企業では、新卒採用や中途採用だけでは人材が集まらず、既卒者も貴重な戦力として採用を検討するケースが増えています。特に若い世代は体力があり、会社の成長を長く支えてくれることへの期待も大きいため、20代の既卒の採用に積極的な企業も少なくありません。
このように、人手不足という社会情勢が既卒者には“追い風”になっているため、既卒でも就職できないわけではないのです。
出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」
既卒が「就職できない」と言われる理由
既卒が「就職できない」と言われるのは、現役学生に比べて内定率が低く、フリーター期間が長くなるほど正社員就職率が下がるからです。中途枠で応募する場合のハードルが高いことも理由の一つです。
9月時点のデータを見ると、新卒の内定率は約9割ですが、既卒は5割弱と大きな差があります(※)。
アルバイト期間が長くなると「就職への意欲が低いのでは?」と不安視する企業が増えるため、就職に苦労する既卒者は少なくありません。
また、中途枠では実務経験が豊富な求職者と競うことになるため、社会人経験がない既卒者はどうしても不利になりやすいのです。
出典:株式会社マイナビ「2024年度既卒者の就職活動に関する調査(12)現在内定を保有していますか。<既卒者の現在の内定率>」p.12
1. 新卒者と内定率の差が40ポイント近くあるから
新卒者と既卒者の内定率には大きな開きがあるため、これが「既卒は就職できない」というイメージの大きな原因になっています。
マイナビの調査によると、2025年卒の現役学生(新卒者)の内定率は9月時点で89.8%ですが、既卒者の内定率は49.3%にとどまっています。
このように内定率に40ポイント以上の差があるため、新卒と比べると、既卒の就職は難しいと言われることが多いのです。
▼現役学生と既卒者の内定率
| 現役学生(※1) | 既卒者(※2) | |
| 内定を保有している | 89.8% | 49.3% |
| 内定を保有していない | 10.2% | 50.7% |
出典:株式会社マイナビ「2024年度既卒者の就職活動に関する調査(12)現在内定を保有していますか。<既卒者の現在の内定率>」p.12
※1 「2025年卒大学生活動実態調査 (9月)」のデータ|調査期間:2024年9月25日~9月30日
※2 「24年度既卒者調査」のデータ
2. フリーター期間が長引くと正社員就職が難しくなるから
フリーター期間が長くなると「就職への意欲」を疑われやすく、企業からの評価が下がる傾向があるため、こうした点も「既卒は就職できない」と言われる理由の一つです。
労働政策研究・研修機構の調査によると、フリーター期間が1年以内の人は「正社員になれた割合」が7割ほどですが、2〜3年になると約5割まで下がり、5年以上続くと3割ほどにまで落ち込みます。
このようにアルバイト生活が長引くほど正社員就職の可能性が低くなるため、既卒の就職は厳しいと言われるのです。
| フリーター継続期間 | 正社員になれた割合(男女計) |
|---|---|
| 1年以内 | 68.6% |
| 1~2年 | 61.2% |
| 2~3年 | 56.6% |
| 3~4年 | 61.1% |
| 4~5年 | 37.9% |
| 5年以上 | 32.3% |
出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No. 213 2022 大都市の若者の就業行動と意識の変容-「第5回 若者のワークスタイル調査」から-」p.128
3. 中途採用枠の応募だと経験者がライバルになるから
中途採用枠では即戦力が求められるため、社会人経験が少ない既卒者は不利になりがちです。
既卒者が正社員を目指す場合、応募枠としては「新卒採用」と「中途採用」の2つがあります。
新卒採用では社会人経験がなくても採用されるケースが多いですが、中途採用では“すぐに活躍できる人”を求める企業が多いため、業務経験やスキルがある人が優先されます。その点、正社員経験がない既卒者は経験者と比べるとどうしても不利になってしまうのです。
このように中途採用枠のハードルが高いことも、「既卒は就職できない」と言われる理由といえるでしょう。
【就職活動の進め方】既卒が就職を成功させるポイント
既卒が内定を手にするには、できるだけ早く就職活動を始めることが大切です。既卒就職に強いサービスを利用したり、職業訓練に参加してスキルを手にしたりするのも効果的です。
年齢が上がるほど実務スキルを求められる場面が増えるため、就活を後回しにすると就職の難易度が高くなってしまいます。
わかものハローワークやジョブカフェ、就職エージェントなど、正社員経験がない若者のサポートに強いサービスの利用も就職成功のカギといえるでしょう。
ほぼ無料で受講できる職業訓練を通して、選考でアピールできるスキルを身につけるのもおすすめです。
1. なるべく早く就活を始める
年齢が上がるほど就職が難しくなるため、既卒者はできるだけ早く就職活動を始めることが大切です。
同じスキルを持つ人であれば、年齢が若い人を採用する企業が多い傾向があります。年齢が若いほうが体力や柔軟性があり、長期的な活躍も期待できるからです。
また、既卒者は新卒枠で応募できる場合がありますが、多くの企業では「卒業後3年以内」という条件を設けています。3年を過ぎると中途採用枠での応募が一般的となり、この場合は実務経験者と内定を争わなければなりません。
こうした理由から、既卒者は就職に向けて早めに動き出すことをおすすめします。
2. 既卒に強い就職支援サービスを使う
就職成功の可能性が高まるので、既卒に強い就職支援サービスの利用も考えてみましょう。
▼既卒就職に強いサービス
| サービス名 | 主な特徴 |
|---|---|
| わかものハローワーク | 34歳以下の正社員就職をサポート |
| ジョブカフェ | 地元企業の合同説明会などを開催 |
| 就職エージェント | 専任の担当者が内定獲得まで伴走 |
上記は全て無料で利用でき、既卒の悩みや不安を深く理解してくれるキャリアアドバイザーが手厚くサポートしてくれます。
“就職のプロ”の視点から、履歴書やESの添削、面接のアドバイスも受けられるため、既卒の就職に不安を感じている方は積極的に活用してみましょう。
3. 職業訓練などでスキルを獲得する
実務に役立つスキルがほぼ無料で身につくので、「スキルがないから就職できないかも…」と不安な既卒の方は、職業訓練の受講も検討してみてください。
職業訓練とは、テキスト代など一部の費用を除き、パソコンスキルや簿記、プログラミングなどの講座を無料で受けられる公的サービスで、ハローワークが窓口となって実施しています。
中途採用枠で応募する場合でも、実践的なスキルがあると選考を有利に進められるため、既卒者は職業訓練の活用も検討してみましょう。
職業訓練について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
【求人の選び方】既卒が就職を成功させるポイント
求人の選び方としては、まずは「既卒歓迎」と記載がある求人を探すことが第一歩です。希望条件は狭め過ぎず、採用数が多い業種の求人をチェックすることも意識しましょう。
企業によっては既卒の応募を受け付けていないため、書類選考の通過率を高めるためにも「既卒歓迎」や「既卒OK」と書かれた求人への応募がおすすめです。
勤務地や給与、残業時間などの条件を絞り込み過ぎると求人が限られてしまうので、条件は広く設定することも大切です。
介護やIT、営業や接客など、採用数が多く、正社員経験がない既卒でも始めやすい求人への応募も検討してみましょう。
1. 既卒歓迎の求人を探す
内定獲得の可能性が高まるため、まずは「既卒歓迎(既卒OK)」と記載がある求人を探しましょう。
たとえば新卒向けの求人サイトでは、検索条件で「既卒歓迎」に絞って求人を探せる場合があります。ハローワークの求人票には「既卒者の応募」という欄があり、応募の可否や、卒業後おおむね何年まで応募できるか記されています。
「既卒歓迎」と記載がない求人の場合、企業によっては既卒者の応募をそもそも受け付けていないかもしれません。その点、「既卒歓迎」の求人に絞って応募すると書類選考や面接の通過率が上がり、就職に大きく近づけるでしょう。
2. 希望条件を狭め過ぎない
選択肢が限られてしまうため、希望条件を狭め過ぎないことも大切です。
新卒や転職者に比べ、既卒者は応募できる求人が多くありません。そのため理想の条件にこだわり過ぎると応募できる求人が少なくなり、就職先がなかなか決まらない可能性があるのです。
たとえば希望勤務地を「東京都内」から「関東圏内」に広げるだけでも、応募できる企業は大きく増えます。給与面も希望年収だけで絞るのではなく、住宅手当や資格手当の有無、昇給制度なども含めて柔軟に検討することが大切です。
応募できる企業を増やすためにも、はじめは条件を広く設定して求人を探しましょう。
3. 採用数が多い業種を検討する
内定を獲得できる可能性が高いため、採用数が多い業界や職種への就職も狙ってみましょう。
たとえば介護業界は全国的に人手不足が続いており、未経験の20代の採用が特に活発です。IT業界ではエンジニア不足が深刻で、未経験者向けの研修プログラムを用意する企業が増えています。
営業職はどの業界・会社でも求人が多く、社会人経験がない既卒者でも挑戦しやすいでしょう。接客や販売などのサービス系職種も需要が高く、未経験からスタートできる求人が豊富です。
こうした業種は採用数も多いため、「就職できないかも…」と不安な方は応募をぜひ検討してみてください。
既卒の履歴書の書き方
既卒が履歴書を書くときは、「学歴欄」は卒業した学校の一つ前の学歴から記載し、「職歴欄」ではアルバイト経験、「自己PR欄」などでは就職に向けて取り組んでいることを記入してもOKです。
大卒の場合は高校卒業から書き始めるなど、「学歴欄」は最終学歴の一つ前の学歴から記載しましょう。
アルバイト経験がある場合は、「職歴欄」に簡単な業務内容を添えて記入しても問題ありません。
就職意欲をアピールできるため、スキル習得に向けた取り組みや資格勉強をしている場合は、「自己PR欄」や「志望動機欄」に記載することをおすすめします。
最終学歴の一つ前から記載する
卒業した学校の一つ前の卒業校さえ分かればOKとする企業が多いため、履歴書の「学歴欄」は最終学歴の一つ前から書き始めれば特に問題はありません。
大卒の場合は高校卒業から、高卒の場合は中学卒業から書き始めましょう。
▼記載例(大卒の場合)
| 学歴 | ||
| 2021 | 3 | 東京都立△△高等学校 卒業 |
| 2021 | 4 | ◯◯大学 心理学部 社会心理学科 入学 |
| 2025 | 3 | ◯◯大学 心理学部 社会心理学科 入学 |
▼記載例(高卒の場合)
| 学歴 | ||
| 2022 | 3 | ◯◯市立◯◯中学校 卒業 |
| 2022 | 4 | 東京都立△△高等学校 入学 |
| 2025 | 3 | 東京都立△△高等学校 卒業 |
職歴欄にはアルバイトも記載する
仕事経験のアピールになるため、アルバイト経験がある場合は「職歴欄」に記載しましょう。
「職歴欄」は正社員などの社会人経験を記載する欄ですが、既卒の場合はアピールできる職歴が少ないケースが多いため、アルバイト経験を記載しても構いません。
記載する際は、アルバイトであることをカッコ書きで明記したうえで、主な業務を一行ほどで記入しても良いでしょう。
▼記載例(アルバイト経験がある場合)
| 職歴 | ||
| 2025 | 2 | ◯◯株式会社 入社(アルバイト) |
| 大阪市内の大手カフェチェーンにて、接客・後輩指導などを担当しています | ||
| 現在に至る | ||
| 以上 |
就職に向けて取り組んでいることも記載する
就職への意欲をアピールできるため、自己啓発や資格取得などの取り組みがあれば履歴書に記載しましょう。
企業は既卒の採用にあたり、就職できない期間を何となく過ごしている人よりも、この期間に自分自身を成長させようと取り組んでいる人を高く評価します。
履歴書では「自己PR欄」または「志望動機欄」、職務経歴書では「自己PR」の項目に記載するのがおすすめです。
▼記載例(自己PR欄)
| 強みは「向上心」です。 現在、独学でPythonを使ったWebアプリケーション開発に取り組んでいます。当初はエラーにつまずくことも多々ありましたが、オンライン学習サイトや技術コミュニティを活用して解決策を探し、簡易的な在庫管理ツールを実装できるようになりました。 貴社のプログラマーとして働く際も向上心を活かし、お客様に喜んでいただけるサービスを開発していきます。 |
既卒の面接対策
面接では既卒になった理由を素直に伝え、空白期間の過ごし方はポジティブに説明しましょう。自己PRは応募企業で活かせる強みを示し、志望動機では「接点」を明確にすることが重要です。
就職せずに卒業(中退)した理由については、嘘をつかず正直に答えましょう。
空白期間については、就職に向けた“準備期間”として伝えるのがおすすめです。
自己PRは強みを漠然とアピールするのではなく、応募先での活かし方も伝えるようにしてください。
「企業をしっかりと選んでいる」という姿勢が伝わるので、志望動機では自分と企業の「接点」を示しながら話すことも大切です。
既卒になってしまった理由は素直に答える
誠実な人柄は高く評価されるため、既卒になった理由は正直に話すことが重要です。
企業は既卒であることを咎(とが)めたいわけではなく、「なぜ卒業後すぐに働かなかったのか」という理由をただ単に知りたいために質問しています。
嘘をつくと信頼を失ってしまうため、まずは素直に理由を伝えましょう。また、以下の例のように「今は就職に前向きに取り組んでいる」という気持ちも伝えることで、企業からの評価がさらに高まります。
| 公務員試験に不合格となり、そのまま卒業いたしました。現在は「地域社会に貢献したい」という思いは民間企業のほうが実現しやすいのではと考え、特に貴社のような環境関連の事業を展開する企業への入社を目指して就職活動をしております。 |
空白期間の過ごし方をポジティブに伝える
就職できない期間を単なる“休息期間”ではなく、将来に向けた“準備期間”として過ごしている人は成長意欲を高く評価されるため、既卒の期間について話す際はポジティブな姿勢を示すことが大切です。
具体的には、以下のステップで整理して伝えましょう。
- 空白期間に何をしていたかを簡潔に述べる
- その活動・経験から何を学び、どのように成長したかを説明する
- 学びが応募企業でどう活かせるかを説明する
▼「空白期間の過ごし方」の回答例
| 在学中は、自分自身が本当にやりたいことが明確ではありませんでした。そこで卒業後は一度立ち止まり、自己分析や業界・企業研究に時間を費やしました。 情報収集や就職セミナーへの参加を重ねる中で、私の強みである「傾聴力」が介護業界で活かせるのではと考えるようになり、現在は介護職員初任者研修を受講しています。 介護の現場で働く際は、傾聴力を活かし、利用者一人ひとりに寄り添った丁寧な対応ができる介護職員を目指していきたいです。 |
自己PRは仕事に活かせる強みをアピールする
企業からの評価が高まるため、自己PRでは「仕事に直結する強み」をアピールしましょう。
どんなに優れた強みでも、応募企業や希望する職種にとって必要性の低い強みだと評価につながりません。
そのため、まずは応募先で求められている能力や人物像を理解しましょう。そのうえで、自身の経験と照らし合わせながら、強みをどのように発揮してきたか、入社後どのように活かしたいかを具体的に伝えるようにしてください。
▼「自己PR」の回答例
| 強みは、相手の立場に立って考えられることです。 カフェのアルバイトでは、来店されたお客様の表情や会話の雰囲気から要望をくみ取り、好みに合ったメニューを提案することを意識して接客を行ってきました。その結果、担当したお客様の多くがリピーターとして継続的に来店してくださるようになりました。 このような「相手の視点で考える力」は、お客様の潜在的なニーズを把握し、営業職として的確な提案につなげる場面で活かせると考えています。 |
志望動機は自分と企業の「接点」を示す
「自社とマッチしている人材」として好意的な評価を受けられるため、志望動機を話す際は、自分の価値観や経験と企業の特徴を結びつけて説明することが大切です。
たとえば「業界No.1のシェアを目指している姿勢」に惹かれたのであれば、自身のこれまでの経験の中で「トップを目指して努力したこと」を伝えるのが効果的でしょう。
志望動機を話すときは、“共通点”を示すことを意識してみてください。
▼「志望動機」の回答例
| 御社を志望する理由は、業界No.1の製品開発を目指す姿勢に強く共感したからです。 大学時代はバドミントン部の副主将として、全国大会出場という目標に向かってチームをまとめてきました。困難や葛藤もありましたが、「その先にしか見えない景色がある」と信じ、努力を重ねる日々に大きなやりがいも感じていました。 御社が掲げる「圧倒的な品質で業界をリードする」という姿勢は、まさに私自身の価値観と重なるものがあり、志望させていただいております。 |
既卒が就職活動に抱くよくある質問
既卒として見なされるのは卒業後何年目まで?
新規大卒者の採用を実施している企業のうち、53.9%(※1)が「卒業後おおむね3年までを新卒として扱う」と回答しているため、既卒と見なされるのは「学校卒業後3年以内」といえます。
既卒に明確な定義はありませんが、厚生労働省は「卒業後3年以内の既卒者は新卒枠で応募を受け付けるように」という方針(※2)も企業に示しています。
「5年前後まで」とする会社もありますが少数のため、基本的には「卒業後3年まで」と理解しておくと良いでしょう。
※1 出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業の多様な採用に関する調査|図表2-43 新規大卒採用において何年前までの既卒者を対象とするか(非該当を除く、企業規模別)」p.34
※2 出典:厚生労働省「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!」
既卒でも就活で大手企業に行ける?
上場企業の6割以上が既卒者を新卒枠で受け入れているため、既卒でも大手企業から内定をもらえる可能性は十分にあります。
マイナビの調査によると、「既卒者を新卒として受け入れる予定がある」と回答した上場企業は65.1%にのぼります。つまり約3社に2社が、学校を卒業している既卒者を、在学中の学生と同じ選考ルートで採用すると答えているのです。
なお、同項目の非上場企業の回答率は52.3%となっており、既卒者を新卒枠で受け入れる割合は上場企業のほうが高いことも分かります。
以上のことから、既卒でも大企業への就職を実現できる可能性があるのです。
出典:マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について」p.126
まとめ
既卒は就職できないのかな…と不安な方に向けて、既卒でも就職できる理由を解説しました。
多くの企業が既卒を新卒枠で受け入れており、「戦力になるのであれば新卒も既卒も関係ない」と考える企業も多いため、既卒でも就職できる可能性は十分にあります。
この記事で紹介した就活のポイントも参考にしながら、一歩ずつ就職成功を目指しましょう。