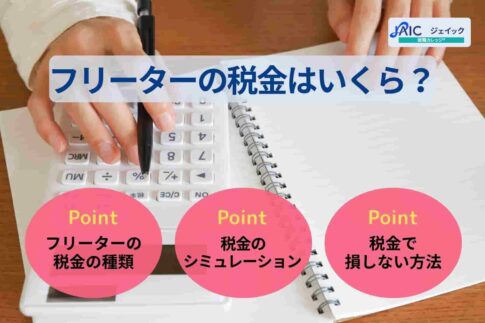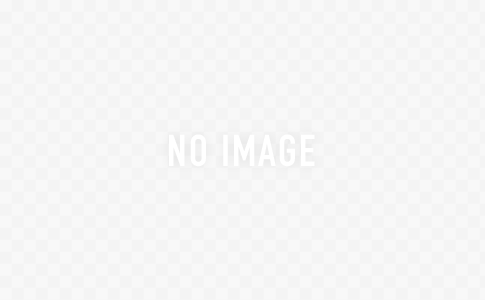介護士は学歴に関係なく採用が活発なため、高卒でも十分に活躍できます。
資格なしでもできる仕事も多く、介護未経験者の採用に積極的な事業所も少なくありません。また、高卒であっても、国家資格の「介護福祉士」を目指すことも可能です。
この記事では、高卒・資格なしでも介護士として働ける理由や、高卒が介護福祉士の資格を取得する方法を具体的に解説します。
年収事情も紹介しますので、収入面の不安を感じている方もぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
高卒・資格なしでも介護士として働くことは可能
高卒・無資格でも働ける環境が整っているため、介護士は未経験からでも挑戦しやすい仕事です。
介護士の業務には、食事の配膳や車椅子での移動補助、着替えの手伝い、施設内の清掃、レクリエーションの準備など、資格がなくてもできる仕事が多くあります。
介護事業所の6割強(※)が人手不足を感じているというデータもあり、「未経験歓迎」や「学歴不問」といった求人も多く見られます。
面接では「やる気」や「人柄」が重視されることが多く、入社後は研修やOJTを通じて実務を学べる職場も少なくありません。
また、高卒・資格なしの状態から介護施設で働き始め、「初任者研修」などの資格を取得し、将来的には「介護福祉士」の取得を目指すことも可能です。
※出典:公益財団法人介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査 結果報告書 2024年7月」p.34
介護初心者でもできる業務が多いから
介護士は資格がなくてもできる業務が多いため、介護経験がない人でも働けます。
たとえば、居室の清掃や洗濯など、「生活援助」と呼ばれる業務は無資格でも対応できる職場が多いでしょう。
その他、介護初心者が任されることが多い業務は以下の通りです。
- レクリエーションの補助
- 事務作業
- 利用者の送迎
相談対応などの専門的な支援や、利用者の身体に直接触れる「身体介護」は、介護福祉士などの有資格者が担うことが一般的です。
とはいえ、こうした専門業務以外は初心者でも対応できるため、介護士は高卒・無資格でもスタートできる仕事といえるでしょう。
介護士の人手不足が深刻だから
介護事業所の64.7%(※)が人手不足を感じており、多くの施設で学歴や経験を問わず働き手を求めているため、高卒・資格なしでも介護士として積極的に採用されています。
たとえば「未経験歓迎」「学歴不問」といった記載のある求人は多く、介護施設の面接では、経験や資格よりも「やる気」や「人柄」を重視する傾向があります。
入社後の研修制度が充実している職場も多く、先輩職員がマンツーマンで丁寧に指導してくれる施設も少なくありません。
このように介護業界は人材確保が大きな課題のため、介護系の資格がない高卒の方でも就職先が見つかりやすいのです。
※出典:公益財団法人介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査 結果報告書 2024年7月」p.34
高卒が介護士になるには?
高卒者が介護士として働くには、「学歴不問」「未経験OK」と記載のある求人を探すことが第一歩です。また、介護系の資格取得も採用で有利になります。
たとえば国家資格の「介護福祉士」を取得すれば、無資格の応募者よりもかなり高く評価されるでしょう。
高卒の場合は「実務経験ルート」や「養成施設ルート」を経て、介護福祉士国家試験の受験資格を得ることが一般的です。
介護福祉士を取得するには最低でも2年以上かかるため、介護系の資格を早く取得したい方は「介護職員初任者研修」や、介護福祉士国家試験の受験要件でもある「実務者研修」もおすすめです。
1. 高卒でも応募しやすい介護士求人に応募する
介護業界は人手不足の影響もあり、学歴や経験を重視しない求人が多いため、高卒の方はまずはこうした求人を探してみましょう。
たとえば、求人サイトで「学歴不問」「未経験OK」「高卒歓迎」といったキーワードで検索すると、多くの介護施設の募集が見つかります。なかでも、規模の大きな特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護事業所では、学歴や資格の有無を問わず採用が活発です。
未経験でも採用される可能性を高められるため、介護士として働きたい高卒の方は、上記のような求人や事業所の募集に積極的に応募してみましょう。
2. 介護福祉士の資格を取得する
就職時に高く評価され、高卒・未経験でも介護士として採用される確率が大きく高まるため、介護福祉士の資格取得を目指すのも一つの手です。
介護福祉士とは、介護に関する専門的な知識と技術を持っていることを証明する国家資格です。
資格取得者は介護の現場で非常に重宝され、無資格の介護職員と比べて月給が2〜3万円高い職場も少なくありません。リーダーや管理職への昇進の可能性が高まることも、介護福祉士の資格を取得するメリットです。
介護福祉士国家試験の受験資格を得るルートは4つありますが、高卒者が主に利用するルートは次の2つです。
- 実務経験ルート(介護現場で3年以上働き、実務者研修を修了する)
- 養成施設ルート(介護福祉士養成校で2年以上学ぶ)
働きながら経験を積み、給料をもらいながら資格取得を目指せる「実務経験ルート」は、多くの高卒者にとって現実的な方法といえるでしょう。
一方で、介護福祉士資格を早く取得したい方は「養成施設ルート」がおすすめです。
※2025年6月時点の試験情報をもとに解説しています。最新の受験要件や日程などは、試験機関(厚生労働省および指定試験実施機関)の公表情報をご確認ください
実務経験ルート
実務経験ルートとは、「実務経験」と「研修の修了」によって介護福祉士国家試験の受験資格を得る方法です。
具体的には、パターン1または2の要件を満たす場合に受験が可能です。
| パターン1 | ・就業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上 ・実務者研修 |
| パターン2 | ・就業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上 ・介護職員基礎研修 ・喀痰吸引等研修 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験|受験資格(実務経験+実務者研修)」
就業期間中の「実務経験」として認められる業務は細かく定められているため、詳しく知りたい方は「実務経験の範囲」のページをご確認ください。
実務経験ルートでは、指定された研修の修了も必要です。
たとえば「実務者研修」では、介護の基本技術に加え、医療的ケアなども含めた幅広い知識を学べます。
養成施設ルート(専門学校など)
養成施設ルートとは、介護福祉士養成施設に通い、必要な知識・技術を修得することで、介護福祉士国家試験の受験資格を得る方法です(※)。
養成施設とは、介護福祉士を養成するためのカリキュラムを備え、厚生労働大臣に指定された大学・短大・専門学校などの教育機関を指します。
具体的には、次の4種類に分かれます。
- 4年制養成施設(大学など)
- 3年制養成施設(専門学校など)
- 2年制養成施設(専門学校・短期大学など)
- 1年制養成施設(短期大学など)
1年制の養成施設は福祉系大学などの卒業者が対象のため、高卒の方は基本的には対象外です。
そのため、高卒の方が養成施設ルートで受験資格を目指す場合は、2年制または3年制の専門学校・短期大学などへの進学が現実的な進路といえるでしょう。
全国の養成施設は、以下のサイトで検索できます。
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験|受験資格(養成施設ルート図)」
※令和8年度までに養成施設を卒業した場合、一定期間、国家試験を受験せずに介護福祉士として登録・就業できる経過措置が設けられています
福祉系高校ルート
福祉系高校ルートとは、福祉系の専門教育を受けられる高校に通い、所定のカリキュラムと介護実習を修了することで介護福祉士国家試験の受験資格を得る方法です。
入学年度や高校の種類によって、以下3つの受験区分に分けられています。
- 平成20年度以前入学者
- 平成21年度以降入学者
- 特例高校など(卒業後に9ヶ月以上の実務経験が必須)
すでに高校を卒業している方が福祉系高校に入り直すのは、年齢や時間などの面から見て現実的とはいえません。
介護の知識や技術を学校で学びたい方は、福祉系の専門学校などに通う「養成施設ルート」を選ぶことをおすすめします。
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験|受験資格(福祉系高校)」
経済連携協定(EPA)ルート
経済連携協定(EPA)ルートとは、インドネシア・フィリピン・ベトナム国籍の「EPA介護福祉士候補者」が、介護福祉士国家試験の受験資格を得るための制度です。
候補者は、それぞれの母国で一定の看護課程や介護課程を修了し、日本語能力試験(N4以上)などの要件を満たすことが求められます。
また、日本の介護施設などで3年以上の就労・研修を行うことも義務づけられており、こうした条件をクリアすることで介護福祉士国家試験の受験資格が与えられます。なお、この制度は外国人向けの特別枠のため、日本国籍の高卒者は利用できません。
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験|受験資格(EPA(経済連携協定))」
参考:公益財団法人 国際厚生事業団「EPA介護福祉士候補者受入れとは」
3. その他の介護系資格を取得する
「介護職員初任者研修」や「実務者研修」を修了すると採用時に高く評価されるため、高卒・未経験から介護士として働きたい方は受講を検討してみましょう。
介護職員初任者研修:介護職の入門的な研修
実務者研修:介護職の中級~上級レベルの研修
どちらも「研修」のため、講義や演習に参加する必要がありますが、全課程を修了すると“公的資格”として認められます。
介護系の資格の中では「介護福祉士」が上位に位置づけられますが、高卒から取得するには最短でも2年以上かかります。
その点、たとえば介護職員初任者研修は最短1ヶ月ほどで取得できるため、「未経験だから資格がほしいけど、できるだけ早く取得したい」と思っている方にぴったりです。
「介護の基礎を理解している人材」として高く評価されるので、介護職への就職を少しでも有利に進めたい方は取得を目指しましょう。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、基本的な介護業務を学べる公的な研修制度(資格)です。
130時間の講義と演習を受け、必須科目を修了することで資格を取得できます。
修了後は、食事・入浴・排せつなどの「身体介護」を行えるようになるなど、無資格では原則できない業務に対応できるようになります。就職時の評価が高まるため、無資格者に比べると採用で有利になるケースも多いでしょう。
研修は、民間のスクールやハローワークで受講できます。受講費用は4〜8万円ほどですが、ハローワークの「職業訓練」を利用すれば、教科書代などを除き、実質無料で受講できる場合もあります。
受講期間は1〜4ヶ月が目安ですが、土日開催のスクールも多いため、働きながら取得を目指すことも可能です。
介護職の“入門資格”としても知られている資格なので、介護未経験の高卒の方は取得を検討してみましょう。
実務者研修
実務者研修は、高度な介護知識・技術を学べる公的な研修制度(資格)です。
介護職員初任者研修よりも内容が専門的で、たんの吸引や経管栄養(※1)といった「医療的ケア」に関する知識と実技も含まれています。
修了すると、訪問介護で「サービス提供責任者(※2)」として働けるようになるなど、業務の幅が広がるため、採用時にかなり高く評価されるでしょう。
受講費用は10〜15万円程度が一般的ですが、ハローワークの「職業訓練」を利用すれば自己負担を大きく抑えて受講可能です。
受講期間は、無資格の場合は6ヶ月ほどです。介護職員初任者研修を保有している場合は、4ヶ月ほどで修了できます。
なお、先ほど紹介した「実務経験ルート」で介護福祉士の資格取得を目指す場合、実務者研修の修了がほぼ必須です。
将来的に介護福祉士として働くことを目指す方も、受講をぜひ検討してみてください。
※1 経管栄養:口から食事や水分を摂ることが難しい方や、誤嚥(ごえん)のリスクが高い方に対し、チューブを使って胃や腸に栄養剤を直接注入する方法
※2 サービス提供責任者 :主に訪問介護事業所において、利用者の支援計画の作成や、訪問介護員の指導・監督、事業所の運営管理などを担う役職(「サ責」と呼ばれることもある)
介護士の平均年収
介護士の平均年収は、施設介護員が376万円(※1)、訪問介護員(ホームヘルパー)が381.2万円(※2)です。
一方で、高卒全体の平均年収は460万円(※3)となっており、介護士の年収はやや低めといえます。
介護士の年収が低い理由としては、人件費の高さやパート職員の多さが挙げられます。「介護報酬制度」によって事業所が受け取れる報酬額に上限があることも、給与が上がりにくい要因の一つです。
「社会保険・社会福祉・介護事業」に従事している人の平均年収を見ると、大卒が約434万円、高卒が約351万円と、学歴によって約80万円の差があります(※4)。
高卒の介護職員の初任給は、訪問介護員で月20万円前後、施設介護員で18万円前後と推定されます(※5)。
また、「高卒・資格なし」の介護士の月給は23万円前後が目安といえそうです(※6)。
※1 出典:厚生労働省「施設介護員 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
※2 出典:厚生労働省「訪問介護員/ホームヘルパー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
※3 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
※4 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|P 医療,福祉(P83~P85)第2表 年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 p85 社会保険・社会福祉・介護事業(規模計)」
※5 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|職種(小分類)、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
※6 出典:厚生労働省老健局老人保健課「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果|第89表 介護職員の平均給与額等(月給・常勤の者)、サービス種類別、保有資格別(介護職員等処遇改善加算を取得している事業所)|施設全体の平均」p.161
高卒と大卒の介護士の年収
令和6年の賃金構造基本統計調査によると、「社会保険・社会福祉・介護事業」に従事している労働者については、大卒の平均年収は434万円、高卒は351万円となっています。
その差はおよそ83万円です。
社会保険料や税金などを差し引いた「手取り額(概算で年収の8割で計算)」で見ると、大卒が約347万円、高卒が280万円となります。
施設の種類や職種、資格の有無、夜勤の有無などによって年収は大きく異なるため、あくまでも目安ではありますが、高卒のほうが大卒よりも年収が低い傾向が見て取れます。
▼社会保険・社会福祉・介護事業の平均年収
| 額面金額 | 手取り(概算 ※額面の8割) | |
|---|---|---|
| 大卒 | 434万円 | 347万円 |
| 高卒 | 351万円 | 280万円 |
出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|P 医療,福祉(P83~P85)第2表 年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 p85 社会保険・社会福祉・介護事業(規模計)」
平均年収=「所定内給与額×12」+年間賞与その他特別給与額(従業員数10人以上/勤続年数計)
高卒の介護職の初任給
高卒の介護職の初任給は、訪問介護員で月20万円前後、施設介護員で18万円前後と推定されます。
これは「経験年数0年」の平均月収のため、厳密には初任給そのものではありませんが、おおよその目安として参考にしてみてください。
具体的には、訪問介護従事者の平均月収は241,100円、介護職員(医療・福祉施設など)が218,800円です。
介護職は高卒の年収が低い傾向があるため、高卒者の初任給は、上記の月収よりもやや低めと見積もっておくと良いでしょう。
▼「経験年数0年」の平均月収の比較
| 職種 | 平均月収 | 高卒の想定初任給※平均月収の8割で計算 |
|---|---|---|
| 訪問介護従事者 | 241,100円 | 192,880円 |
| 介護職員(医療・福祉施設など) | 218,800円 | 175,040円 |
出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|職種(小分類)、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
平均年収=「所定内給与額×12」+年間賞与その他特別給与額(従業員数10人以上/勤続年数0年)
高卒・資格なしの介護士の給料
高卒・資格なしの介護士の給料は、月23万円前後と推定されます。
学歴別の公的なデータは見当たりませんが、「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果」によると、「資格なし」の介護従事者の平均月収は290,620円です。
高卒の月収は全体平均よりやや低い傾向があるため、ここでは目安として8割にあたる約23万円と見積もっています。
なお、保有資格ごとの平均月収では「社会福祉士」が最も高く、次いで「介護支援専門員」が続いています。
▼保有資格ごとの平均月収の比較
| 資格種別 | 平均月収 | 高卒の想定月収※平均月収の8割で計算 |
|---|---|---|
| 資格なし | 290,620円 | 約23万円 |
| 社会福祉士 | 397,620円 | 約31万円 |
| 介護支援専門員 | 388,080円 | 約31万円 |
| 介護福祉士 | 350,050円 | 約28万円 |
| 実務者研修 | 327,260円 | 約26万円 |
| 介護職員初任者 | 324,830円 | 約25万円 |
出典:厚生労働省老健局老人保健課「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果|第89表 介護職員の平均給与額等(月給・常勤の者)、サービス種類別、保有資格別(介護職員等処遇改善加算を取得している事業所)|施設全体の平均」p.161
介護士の主な仕事内容
介護士の仕事は、大きく「身体介護」と「生活援助」に分かれます。
身体介護は、入浴・排せつ・食事・移動・着替えなど、利用者の身体に直接触れて支援する仕事です。
利用者が自立した生活を送れるようにサポートすることを目的に行われ、介護福祉士や実務者研修などの有資格者が担当するケースが多い傾向にあります。
生活援助は、掃除・洗濯・調理・買い物など、利用者の日常生活を間接的に支える仕事です。身体に直接触れる支援は行わないため、介護の中では比較的取り組みやすい仕事とされています。
実際、生活援助に関しては未経験の高卒者が任されることも多いので、介護職としての第一歩を踏み出しやすい仕事といえるでしょう。
詳しい仕事内容は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
介護士の仕事とは?仕事内容から求められるスキルまで網羅して解説
高卒が介護職を辞めたいと思う理由
高卒で介護職に就いた人の中には、給料の低さから「辞めたい」と感じる人が多くいます。
また、精神的なストレスや業務量の多さ、体力的な負担の重さも相まって、介護士として長く働き続けることに不安を抱える方も少なくありません。
さらに、人間関係の悩みや、利用者の生活を支える責任の重さを日々感じ続けることで心身の不調を感じ、介護以外の仕事へと転職を考える人が多いのも現状です。
介護職の厳しい現状について気になる方は、次の記事も参考にしてみてください。
1. 高卒介護士の給料が安い
高卒で介護職に就いた人の多くは、他の仕事と比べて給料が低いことに対して経済的な不安を感じています。
高卒全体の平均年収は460万円(※1)ですが、施設介護員の平均年収は376万円(※2)に留まっており、両者には大きな差があります。
なお、施設介護員の平均年収には大卒や大学院卒なども含まれているため、一般的に年収が低くなりがちな高卒者に関しては、実際に受け取る金額はさらに少ないかもしれません。
特に20代のうちは昇給額も少なく、十分に貯金できるほどの余裕が生まれにくいため、給料の低さに悩み、転職を検討する高卒介護士も少なくないのです。
※1 出典:厚生労働省「施設介護員 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
※2 出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査|学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」
2. 精神的なストレスがたまりやすい
介護士は人間関係の面の精神的な負担が大きいため、「辞めたい」と考える人が多くいます。
事業所の種類や利用者の状態にもよりますが、場合によっては食事介助中に物を投げつけられたり、突然怒鳴られたりすることもあります。利用者の家族から無理な要望やクレームを受ける場面も珍しくありません。
体調の急変に迅速に対応することや、転倒などの事故を未然に防ぐ責任の重さに、大きなプレッシャーを感じることもあるでしょう。
こうした精神的な負荷が続くと「心の病気」につながる可能性もあるため、自身の健康を守るために退職を真剣に考える介護士も多いのです。
3. 業務量が多くて体力的にきつい
介護士は慢性的な人手不足によって一人あたりの業務量が非常に多く、体力的な負担も大きいため、「辞めたい」と感じる人も少なくありません。
入浴介助などの身体介助では腰や膝に負担がかかりますし、夜勤を担当する場合は仮眠が十分に取れず、疲労をなかなか回復できないこともあります。
日々の記録業務やスタッフ間のミーティングなど、介護以外の業務にも多くの時間を取られがちです。
事業所側も改善を試みていますが、深刻な人手不足の中では十分な対応が難しいのが現状です。結果として、自身の体力の限界を感じ、他の仕事への転職を考える介護士も多いのです。
高卒が介護士として働くメリット
高卒で介護士として働き始めると、「介護福祉士」の受験に必要な3年間の実務経験を20代前半で満たせる可能性があり、大卒よりも早く資格を取得できます。
資格手当による収入アップも期待でき、キャリアのスタートが早いぶん、昇進のチャンスにも恵まれます。介護業界では学歴よりも現場での経験やスキルが重視されるため、高卒でもリーダーや主任などの管理職に早期に就けるケースも珍しくありません。
高齢化が進む日本において、介護の仕事は今後も安定した需要が見込まれるため、職を失う不安が少ない点も大きな安心材料といえるでしょう。
1. 介護福祉士に必要な実務経験を早く積める
高卒で介護士になると早く働き始められるため、介護福祉士の資格取得に必要な実務経験を早めに満たすことができます。
介護福祉士国家試験の受験資格を得るには、「実務経験ルート」の場合、3年間の実務経験が必要です。
高校卒業後すぐに働き始めれば21歳頃に受験資格が手に入りますが、大卒の場合は最短でも25歳頃になってしまうでしょう。
介護福祉士の資格を取得すると、資格手当によって毎月の給与が上がる可能性もあります。
以上のことから、介護福祉士として早く活躍したい方にとって、高校卒業後すぐに働き始めることは大きなメリットがあるのです。
2. 大卒より早く管理職に就ける可能性がある
高卒で介護職に就くと実務経験を早く積めるため、大卒者よりも早い段階で主任やリーダーなどの管理職に昇進できる可能性もあります。
介護業界は学歴よりも実務経験が重視される傾向があり、現場での経験年数やスキルが高い人には、その実力に見合ったポジションが与えられることが一般的です。
管理職に昇進すると基本給が上がるだけでなく、管理職手当が支給されるケースもあり、結果として大幅な収入アップも期待できるでしょう。
このように介護士に関しては、経験が少ない新卒の大卒者よりも、4年ほど早く現場で経験を積んでいる高卒者のほうが管理職に登用されやすいのです。
3. 安定した仕事なので経済的な安心感がある
介護職は「高齢化社会」によって需要が安定しているため、働き口が非常に多く、将来的にも経済的な安心感を得やすい仕事といえます。
日本の高齢者人口は今後も増え続けることが見込まれており、介護サービスの需要が減る兆しはありません。
他の業界では景気の影響で人員削減が行われることもありますが、介護業界では慢性的な人手不足が続いていることもあり、むしろ求人は増加傾向にあります。
このように介護士は将来性があり、「長く安定した収入を手にできる」という点において、特に大きなメリットを感じられる職業といえるでしょう。
まとめ
介護士は学歴や資格の有無に関係なく採用が活発なため、高卒・未経験から働き始める人も多くいます。
実務経験を早く積むことで「介護福祉士」の受験資格を大卒よりも早く満たせるなど、高校卒業後すぐに介護士として働き始めることには大きなメリットがあります。
介護士の仕事に興味を持った方は、将来に向けて一歩ずつ準備を始めていきましょう。