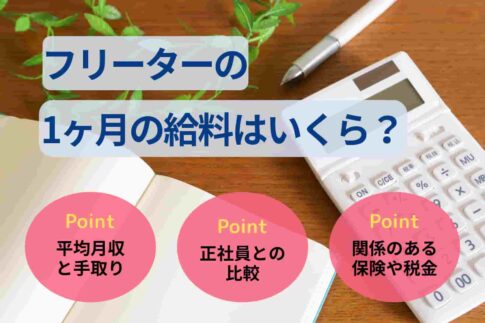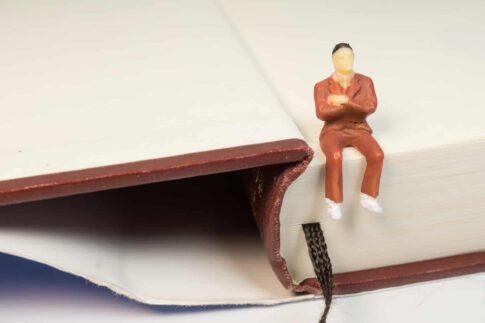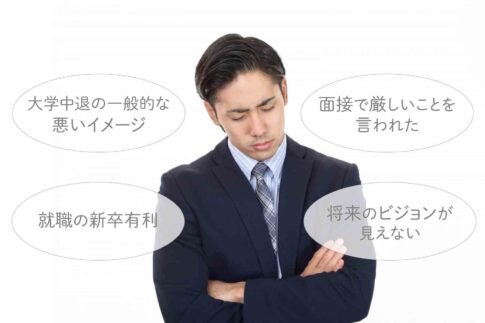「高卒で就職すれば良かった」と感じる人がいます。
「大学なんて行っても意味がない」「高卒で働いていれば、奨学金を返済しなくてもよかったのに」と後悔しているかもしれません。
本記事では、高卒で就職するメリットとデメリットや「高卒で就職すれば良かった」と後悔する原因、後悔した際の対処法、後悔しない進路選びのために知っておきたいことについて解説します。
大卒が基本条件とされる主な仕事も紹介しているため、大学に進学する意味を再確認できるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
高卒で就職するメリット
高卒で就職するメリットは多くあります。
以下の内容について、それぞれ解説します。
- 早い段階から収入を得られる
- 若いうちから社会人経験が積める
- 学費や奨学金の負担がない
- 高校新卒の場合、職場で手厚い新人研修を受けられる
- キャリアチェンジの選択肢が増える
- 手に職を付けやすい専門職や技能職がある
早い段階から収入を得られる
高卒で就職すると18歳から安定した収入を得られるため、短大卒や大卒よりも経済的に早く自立できます。
また、大学に進学した際の学費や奨学金、一人暮らしの生活費に悩むことなく、家計を支えたり、将来の貯蓄や自己投資にも使えたりするのがメリットです。
社会保険にも加入でき、年金の支払いや福利厚生も受けられるため、金銭面でも安心感があるでしょう。
実家暮らしの場合は支出も抑えやすく、計画的な資産形成も可能です。
若いうちから社会人経験が積める
高卒で働き始めると、挨拶やマナー、ビジネスメールの書き方や時間管理の大切さなどを早い段階で身につけられます。
また、年齢に関係なく実力を評価してもらえる職場であれば、若いうちから責任のある業務にチャレンジでき、達成感や成長を実感しやすいでしょう。
実務を通じて人間関係の築き方や「報告・連絡・相談」の重要性も学べるため、社会性が養われると同時に視野も広がります。
人間関係を築きながら、実践的なスキルを身につけると、将来的な転職やキャリアチェンジにも有利です。
若いうちに社会経験を積めば、自信や社会的スキルが自然と磨かれていきます。
学費や奨学金の負担がない
高卒で就職するメリットの1つは、大学の学費や奨学金返済の負担が発生しない点です。
大学の一般的な学費の総額は次のとおりです。
| 種類 | 学費の総額 |
|---|---|
| 国立大学(標準額) | 2,425,200円 |
| 公立大学(平均額) | 2,519,135円 |
| 私立大学(平均額・文科系学部) | 4,431,392円 |
| 私立大学(平均額・理科系学部) | 5,730,033円 |
| 私立大学(平均額・医歯系) | 32,323,540円 |
参考:大学進学 学費ナビ
学費は親が払う場合もありますが、奨学金制度を使用する学生もいます。
奨学金の場合は、卒業後に本人が数百万円の返済義務を負うケースが多くあります。
奨学金の一般的な返還については以下のとおりです。(自宅から通学した場合)
| 種類 | 貸与総額 | 返還月額 | 返還回数(年数) |
|---|---|---|---|
| 国立・公立 | 2,160,000円 | 12,857円 | 168回(14年) |
| 私立 | 2,592,000円 | 14,400円 | 180回(15年) |
参考:独立行政法人 日本学生支援機構 第一種奨学金【4年制】
奨学金の返還が終わるまで10年以上かかることが分かります。
一方で、高校卒業後すぐに働けば学費の負担がなく、収入を得ながら将来に向けて貯蓄や投資ができます。
また、親への経済的負担を軽減できる点も、家庭環境によっては大きな安心材料になるでしょう。
借金を抱えることなく社会に出て自立を目指せるため、経済的な安定を早く手に入れたい人にとっては大きなアドバンテージといえます。
高校新卒の場合、職場で手厚い新人研修を受けられる
高校新卒で就職する場合、多くの企業が新人育成に力を入れており、手厚い研修制度が用意されています。
社会経験がほとんどない高卒社員に対しては、社会人としての基本的なマナーや「報告・連絡・相談」や時間管理など、基礎から丁寧に指導されるのが一般的です。
また、先輩社員がマンツーマンでサポートする「OJT制度」や上司との定期的な面談、フォローアップ研修がある職場も多く、着実に成長できます。
段階的にスキルアップできる環境が整っている点は、高校新卒ならではの強みです。
そのため、社会に出る不安を感じている高卒でも、安心して一歩を踏み出せるでしょう。
キャリアチェンジの選択肢が増える
高卒で社会に出て働くと若いうちから実務経験が積み上がるため、キャリアチェンジの選択肢が早くから広がります。
例えば、20代前半で数年の職歴を持っていれば、転職市場でも「即戦力」として見られるケースが多くなります。
また、働く中で自分の興味や得意分野に気づき、資格取得や専門分野への転向を目指すことも可能です。
最近ではリスキリングやキャリアアップ支援を行う企業も増えており、学歴ではなく実力や経験が評価される場面も多くなっています。
さらに、社会に出てから通信制大学や専門学校で学び直す方法もあるため、将来的に大卒と同様のキャリアパスを目指すことも可能です。
早くから動き出せば、戦略的なキャリア形成が期待できるでしょう。
手に職を付けやすい専門職や技能職がある
高卒で就職する際は、現場での実践経験が重視される専門職や技能職に就きやすい傾向があります。
製造業や建設、整備、電気工事、介護、美容、調理などの分野では、学歴よりも技術力や実務経験が評価されやすく、若いうちから手に職をつけて安定した生活を築けます。
これらの職種は景気に左右されにくいものも多く、資格取得や経験を重ねることで将来的には独立や起業も視野に入れられるでしょう。
また、企業によっては技術習得のための研修や資格取得支援制度が用意されている場合もあり、働きながらスキルを磨ける環境が整っています。
手に職をつける仕事にやりがいを感じる人には、非常に適した進路といえるでしょう。
高卒で就職するデメリット
高卒で就職するメリットは多くありますが、一方でデメリットもあります。
以下の内容について、それぞれ解説します。
- 賃金が大卒より低い傾向がある
- 応募できる職種や企業が限られる場合がある
- 昇進時に学歴要件が設けられる場合がある
- 大学で得られる専門知識に触れにくい
- 自分に合わない職業を選ぶリスクがある
- 大卒でないと受験できない資格がある
賃金が大卒より低い傾向がある
統計的に見て、高卒の初任給や賃金は大卒に比べて低い傾向があります。
これは、求人側が学歴によって職務内容や役職の期待値を変えていることが主な理由です。
高卒と大卒の賃金を以下の表で比較しました。
【新規学卒者の学歴別にみた賃金】
| 最終学歴 | 賃金 |
|---|---|
| 高卒 | 197.5千円 |
| 大卒 | 248.3千円 |
| 差額(高校-大学) | ▲50.8千円 |
参考:厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況
参考:新規学卒者(10)新規学卒者の学歴別にみた賃金
【学歴別にみた賃金】
| 最終学歴 | 賃金 |
|---|---|
| 高卒 | 288.9千円 |
| 大卒 | 385.8千円 |
| 差額(高校-大学) | ▲96.9千円 |
参考:厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況
参考:学歴別(3)学歴別にみた賃金
高卒の社員は現場作業や補助業務など、ルーチンワークが比較的多い職種に配属されやすく、昇給スピードも緩やかになりがちです。
能力や成果に応じて昇格や昇給がある企業もありますが、初任給の段階で数万円の差があるケースも多くあり、長い目で見れば大きな差になる可能性もあります。
そのため、収入の面で不利にならないよう、資格取得や実績作りによって補う工夫が求められます。
応募できる職種や企業が限られる場合がある
高卒の場合、応募できる職種や企業が限られるケースがあります。
総合職や研究開発職、コンサルティングなどの職種は、応募資格に「大卒以上」と明記されていることが多く、高卒ではエントリーすらできない場合もあるのです。
また、国や自治体が実施する公務員試験の中にも、受験資格に学歴条件があるケースが存在します。
高卒だと希望する業界や企業に進めなかったり、スタート時点で選択肢が限られたりするため、思ったようなキャリアを築けないリスクがあるかもしれません。
そのため、高卒で就職する際は興味のある分野で活躍できるかどうか、慎重に見極める必要があります。
昇進時に学歴要件が設けられる場合がある
企業によっては、昇進や管理職への登用にあたって「大卒以上」と学歴要件を設けている場合があります。
その場合、実績や勤続年数が十分あっても、学歴の壁が昇進の妨げになるケースは珍しくありません。
特に大企業や官公庁などでは、一定のポストに就くために学歴が重視される傾向があります。
そのような環境では、高卒社員が一定以上の役職に就けず、モチベーションの低下につながる場合もあるのです。
ただし、企業によっては社内試験や論文で昇格が決まるケースもあり、努力次第で道が開ける可能性もあります。昇進を目指すなら、制度や社風を確認しましょう。
大学で得られる専門知識に触れにくい
高卒の場合、大学で学べる専門的な知識や理論的思考力に触れにくい点もデメリットです。
大学では法律や経済、心理学などの高度な知識を体系的に学べ、資格取得や研究活動を通じて深い理解を養う環境が整っています。
一方で高卒の場合、実務を通してスキルを身につける形が多いため、理論や背景知識に基づいた判断力や応用力が弱くなりがちです。
そのため、将来的に専門性の高い職種へキャリアアップを目指す場合は通信教育などで学ぶ必要があります。
このように、知識の深さが求められる場面では、学歴の差が影響するケースもあるのです。
自分に合わない職業を選ぶリスクがある
高卒で就職する場合、進路選択のタイミングが大卒よりも早いため、自己理解や職業に関する知識が十分でないまま企業を選んでしまう場合があります。
その結果「思っていた仕事と違う」「自分には合わなかった」と感じて、早期離職につながるケースが多くあるのです。
高卒は大卒よりも社会経験が限られているため、業務内容や職場の雰囲気を具体的にイメージするのが難しく、情報が足りないまま就職を決断してしまうこともあるでしょう。
そのようなリスクを軽減するため、可能な場合はインターンシップや職業体験の機会を積極的に活用し、実際の現場を体感しながら自分に合った職場を選ぶことが大切です。
大卒でないと受験できない資格がある
一部の国家資格や専門資格には「大卒以上」の受験資格が設けられているものがあります。
例えば、医師や弁護士、公認会計士、薬剤師、看護師、臨床心理士などの専門職は、大学や大学院での履修が必須条件のため、高卒では受験そのものができません。
将来的にそれらの職種への転向を考えた場合、高卒からの道のりは遠回りになるか、不可能な場合もあります。
また、企業によっては資格取得支援制度を用意していても、その前提条件として大卒であることが求められるケースもあります。
資格を活かしたキャリアを考えている場合は、志望職種の要件を事前に調べておきましょう。
高卒で就職すれば良かったと後悔する原因
大学に進学したものの「高卒で就職すれば良かった」と感じる人は多くいます。
主な理由7点について、それぞれ解説します。
- 奨学金の返済負担が重い
- 高校新卒は学校が就職のサポートをしてくれる
- 大卒でも希望する仕事に就けない場合がある
- 高卒で就職した友人がすでにキャリアを積んでいる
- 大学で学んだ内容が就職に直結していない
- 大学生活はお金がかかる
- 大学生活に価値を見出せない
1. 奨学金の返済負担が重い
大学進学時に奨学金を借りた場合、卒業後に長期的な返済義務を抱えることになります。
労働者福祉中央協議会のアンケートによると、奨学金の返済について約70%が不安を感じており、さらに約40%は返済が苦しいと感じている事実があります。
参考:労働者福祉中央協議会「高等教育費や奨学金負担に関するアンケート」の調査結果(2024年6月調査)
参考:高等教育費や奨学金負担に関するアンケート調査(2024年6月調査)調査結果のポイント 奨学金返済による[結婚][出産]への影響を返済者の4割前後が実感
毎月の返済額が生活費を圧迫し、自由に使えるお金が減ったり、結婚や出産に影響したりする場合も多いのです。
就職先の初任給が期待よりも低かった場合や思うように昇給しない場合、経済的な負担感はさらに大きくなります。
そのような状況の中で、高卒で働き始めた同級生が収入を得て貯金や自己投資をしている姿を見ると「高卒で就職すれば良かった」と後悔するかもしれません。
奨学金の返済が終わるまでに10年以上かかるケースも多く、精神的なプレッシャーも伴うため、大学の入学を後悔する人がいると言われています。
2. 高校新卒は学校が就職のサポートをしてくれる
高校新卒で就職する場合、学校が企業との窓口となり、求人紹介や面接対策、履歴書の添削などを手厚くサポートしてくれます。
自分で就職先を探す必要がないうえ、高校で紹介された良い企業へ内定が決まる場合も多いのです。
一方で大学生の場合、就職活動は基本的に自己責任で進める必要があり、学業と並行しながらの情報収集や複数社の企業研究、エントリー、試験、面接に追われる日々が続きます。
その苦労を経験すると「高卒で就職すれば良かった」と思う場合があるでしょう。
大卒では高校のように学校のサポートが受けられない場合が多く、進学後の後悔につながるケースもあります。
3. 大卒でも希望する仕事に就けない場合がある
大学を卒業しても、必ずしも希望どおりの仕事に就けるとは限りません。
学歴があっても人気の業界や大手企業は競争が激しく、内定を得られないケースは多くあります。
その場合は希望と異なる業種や職種に就くことになり「大卒でも希望する企業に就職できなかった」と思う人もいます。
一方で高卒で入社し、早くからキャリアを築いた人が、自分の希望する分野で活躍している姿を見ると、遠回りをしたように感じて後悔するかもしれません。
大学を卒業しても夢が叶わない現実を知ったとき「高卒で就職すれば良かった」と多くの人が感じます。
4. 高卒で就職した友人がすでにキャリアを積んでいる
自身が大学生のときに、高卒で就職した同級生が職場で経験を積み、昇進したり資格を取得して活躍している姿を見ると、焦りを感じるケースがあります。
「高卒で働き始めていれば、自分も社会で活躍できたのでは」と思うかもしれません。
また、高卒で社会に出た人の方が職場での人間関係やビジネスマナーに慣れており、実践的な力を身につけている様子に感心させられる場面も多いでしょう。
このような友人との差を感じたとき「高卒で就職すれば良かった」と後悔するかもしれません。
5. 大学で学んだ内容が就職に直結していない
大学で専攻した内容が就職後の仕事に直接活かせないケースは多くあります。
例えば文学や哲学、歴史などは教養としての価値は高いものの、企業の実務に直結しない場合が多く、就職活動では学科と関係ない業界を選ぶことになります。
そのため「大学での4年間は本当に必要なのか」「やはり高卒で就職すれば良かった」と感じるかもしれません。
大学で学んだ内容と社会との接点を見いだせなかったとき、進学に対する後悔が生まれやすくなります。
6. 大学生活はお金がかかる
大学生活には授業料の他に教科書代や交通費、サークル活動費、家賃、生活費など多くの費用がかかります。
特に1人暮らしをしている場合は月々の支出が膨らみやすく、仕送りとアルバイトに頼る生活を続ける人も多いのです。
このような経済的負担を考えると「高卒で就職すれば良かったのでは」と感じる瞬間があるでしょう。
将来のために大学へ進学したはずだったのに、現実には金銭的なストレスを抱える結果となり、後悔につながる場合があります。
7. 大学生活に価値を見出せない
大学生活の中で、学びや人間関係に楽しみを感じられない場合「自分は何のために大学に入学したのか」と疑問を抱く場合があります。
興味のない講義が続いたり、大学に入学しても就職に役立つ実感が持てなかったりすると、時間とお金を費やす意味が見えにくくなるでしょう。
周囲に流されて何となく大学へ進学した場合は、特にこの傾向が強くなります。
高卒で就職した友人がやりがいや収入を得ているのを見ると、羨ましさや焦りが生じるため「高卒で就職すれば良かった」と後悔の気持ちが芽生えることもあります。
高卒で就職すれば良かったと後悔したときの対処法
「高卒で就職すれば良かった」と感じた場合、その気持ちを放置せず冷静に考えましょう。
主な対処法をそれぞれ解説します。
- 高卒で働く人のリアルな意見を聞く
- 休学して人生の方向を見直してみる
- 中退して就職する
- 今ある経験を強みに変える
- 他人と比較しない
- キャリアカウンセリングを受ける
1. 高卒で働く人のリアルな意見を聞く
「高卒で就職すれば良かった」と感じたときは、実際に高卒で働いている人の話を聞くのがおすすめです。
仕事のやりがいやキャリア形成の現実、高卒で就労したことのメリットとデメリットを知れば、自分の気持ちが整理できるでしょう。
ネットやSNS、OB訪問などで意見を集めると、理想と現実のギャップが見えてきます。
話を聞くと「自分の場合は大学に行って良かった」と認識できる場合もあり、進路に対する後悔や迷いが少なくなります。
多角的な視点を持つと、気持ちが前向きに変わるでしょう。
2. 休学して人生の方向を見直してみる
大学へ行ったことに関して後悔の気持ちが強く、自分の進路に疑問を感じているなら、一度休学して立ち止まる選択肢もあります。
大学生活に違和感を持ちながら続けるよりも、思いきって時間を確保し、自分の将来像を見直してみましょう。
休学中にアルバイトやインターン、ボランティアなどを通じて社会経験を積むと、自分の適性や興味を再確認できます。
学び直しや進路変更を考えるきっかけにもなり、復学後のモチベーション向上にもつながるかもしれません。
焦って結論を出さず、一時的に大学と距離を置くと進むべき道が見えてくるでしょう。
3. 中退して就職する
「大学は自分に合わない」と強く感じた場合、中退して社会に出るという方法もあります。
大学中退はマイナスに捉えられがちですが、目的を持って就職するのであれば、行動力や判断力の証として評価される場合もあります。
20歳前後なら、若さを武器に未経験からの採用も十分可能です。
ただし、大学を中退すると高卒の扱いになり、学歴による求人の選択肢が限られる可能性があるため、業界研究や企業選びは慎重に行いましょう。
自己分析を深めつつ、自分の適性に合った道を探す姿勢が求められます。
中退をゴールではなく、新たなスタートと捉えると、前向きな歩みにつながります。
4. 今ある経験を強みに変える
「高卒で就職すれば良かった」と感じても、今までの経験が無駄になるわけではありません。
大学で学んだ専門知識や友人とのつながり、アルバイトやサークル活動を通じて得たものは、すべてかけがえのない財産になるからです。
過去の選択を悔やむよりも、その経験をどのように活かしていけるかに意識を向けてみましょう。
自分の強みや価値観に気づき、それを言語化すれば、より自分らしい働き方や生き方を見つけるヒントが得られます。
これまでの経験を振り返りつつ、後悔を原動力に変えて、前向きなキャリア形成を目指しましょう。
5. 他人と比較しない
後悔の多くは、周囲と自分を比較することで生まれると言われています。
「高卒の友人はすでに働いているのに、自分はまだ学生のまま…」と感じると、焦りや劣等感につながるでしょう。
しかし、人生のタイミングは人それぞれで、正解は1つではありません。
他人のペースではなく、自分の価値観や目標に基づいて進むことが大切です。
また、SNSなどで見える「成功の表面」に惑わされず、自分の歩みを丁寧に振り返ってみましょう。
他人との比較をやめて、自分の強みや魅力を冷静に見つめ直すと、自信を取り戻すきっかけになります。
6. キャリアカウンセリングを受ける
進路や将来に迷いを感じたら、キャリアカウンセリングを受けるのも有効です。
大学のキャリアセンターや自治体の就業支援窓口、民間のキャリア相談サービスなどを活用すれば、専門家から客観的なアドバイスが得られます。
自己分析や適職診断を通じて、自分の適性や興味に合った職種を見つけやすくなり、後悔の気持ちが和らぐでしょう。
また、履歴書の添削や面接対策など、具体的なサポートを受けられる点もメリットです。
1人で悩まずプロの力を借りると、新しい選択肢が見えてくる可能性があります。
後悔しない進路選びのために知っておきたいこと
進路を選ぶうえで大切なのは「どの道を選ぶか」だけでなく「選んだ道をどう歩むか」という視点です。
後悔しない進路選びのために知っておきたいことを3点、それぞれ見ていきましょう。
- 大学生活は「何を学ぶか」「どう過ごすか」で変わる
- 一度立ち止まって目的を見直す
- 一度の進路選択で人生は決まらないと考える
1. 大学生活は「何を学ぶか」「どう過ごすか」で変わる
大学生活の価値は「何を学ぶか」「どう過ごすか」によって大きく左右されます。
漠然と通うだけでは得られるものが少なく、時間や費用が無駄になったと感じるかもしれません。
自分の関心に基づいて学問を深めたり、ゼミやインターン、留学などに積極的に取り組めば、知識だけでなく実践的な力や人脈も手に入ります。
大学は自由度が高い分、自分次第で可能性が大きく広がる場所です。
目的意識を持って過ごすと進学を後悔することなく、将来に役立つ力を身につけられます。
2. 一度立ち止まって目的を見直す
進路に迷いや後悔を感じたときは、一度立ち止まって「自分は何のために進学したのか」「どんな将来を目指したいのか」と目的を見直しましょう。
周囲に流されて選んだ進路であっても自分で納得すれば、新たな意味を見出せるかもしれません。
目的が明確になると学びの意欲も高まり、日々の行動に納得感が生まれます。
目的が見つからない場合は、インターンやボランティア、専門家との対話などを通じて新しい知識を身につけると、自分の価値観や適性を探るヒントが得られるでしょう。
迷ったら焦らず、立ち止まる勇気も時には必要です。
3. 一度の進路選択で人生は決まらないと考える
進路選びは重要ですが、それが今後の人生をすべて決めてしまうわけではありません。
近年では転職や学び直しが一般的で、社会に出てからやりたいことが見つかる人も多いため、途中から方向転換すれば満足度の高いキャリアを築ける場合もあります。
進路選びに過度なプレッシャーをかけるよりも、柔軟な視点を持ちつつ自分の変化に合わせて選択肢を広げていく姿勢が求められます。
自分で決めた進路に後悔した場合でも、それを糧にして前向きに行動すれば、いつでも軌道修正できるでしょう。
大卒が基本条件とされる主な仕事
大卒を基本条件とする職種は専門知識や高度な思考力、マネジメント能力が求められるものが中心です。
学歴に加えて、大学で何を学び、どのように過ごしてきたかが評価対象となる場合があります。主な仕事を4つ紹介します。
- 国家公務員(総合職)
- 大企業の総合職
- コンサルティング業界
- 教員
国家公務員(総合職)
国家公務員の総合職は、各省庁の中核を担う幹部候補生として採用されるポジションであり、原則として大卒以上の学歴が必要です。
試験区分も「大卒程度」とされており、大学での専門的な知識や論理的な思考力、政策の立案能力などが求められます。
採用後は、国の政策企画や法令の立案、国際交渉などを担当し、将来的には課長や局長などの高いポストを目指すキャリアパスが用意されています。
高い知的水準と責任感が求められる仕事であるため、学歴や人物評価を重視する傾向が強く、民間企業と比べても安定性や社会的な信頼度が非常に高い職種です。
大企業の総合職
大企業の総合職は将来の幹部候補として採用され、企画や営業、人事、経営戦略など幅広い業務に携わります。
このポジションでは、全国転勤や部門を超えた異動を経験しながらキャリアを積むケースが多いため、論理的思考力や柔軟性、リーダーシップが重視されます。
そのため、基本的に大卒以上が応募条件となっており、大学での学びや社会性、潜在能力が評価されるケースが多いのです。
また、初任給や待遇も高卒に比べて優遇されやすく、長期的に見ると昇進や年収にも大きな差が出るのが一般的です。
大企業の総合職は安定したキャリアを築きたい人に人気の高い職種といえるでしょう。
コンサルティング業界
コンサルティング業界は企業の課題解決をサポートする専門職であり、高度な分析力や課題発見力、提案力が求められます。
そのため、採用の基本条件として大卒以上が必須となっている企業がほとんどです。
大手コンサルファームでは、大学での専攻内容や論理的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション力などが重視され、採用過程も非常に厳しくなっています。
文系と理系問わず採用されますが、MBAや修士号を持つ人材が優遇される場合もあります。
年収が高く、成長環境も整っている反面、成果主義の厳しさもある業界です。
教員
教員として学校で働くためには、基本的に大学を卒業し、教員免許を取得することが前提となります。
小学校、中学校、高校いずれも大学の教職課程を修了して免許状を得る必要があります。
そのため、高卒では教員免許を取得できず、教壇に立てないのが一般的です。
教育実習や学科に関する専門知識、教育心理などの学びを経て、教員採用試験に合格すると初めて教員になれます。
子どもの成長に関わるやりがいのある職業ですが、教務や保護者の対応、部活動の指導など業務量も多く、幅広い能力と責任感が求められます。
まとめ
高卒で就職するメリットとデメリットや「高卒で就職すれば良かった」と後悔する原因、後悔した際の対処法、後悔しない進路選びのために知っておきたいこと、大卒が基本条件とされる主な仕事について解説しました。
「高卒で就職すれば良かった」と感じる人がいる背景には、奨学金の返済や大学生活への疑問、就職活動の苦労などの現実があります。
しかし、高卒と大卒それぞれに異なるメリットやデメリットが存在するため、一概にどちらが正解とは言えません。
本記事を参考にして進路の迷いや不安をなくし、自身の進路やキャリアを見つめ直してみましょう。