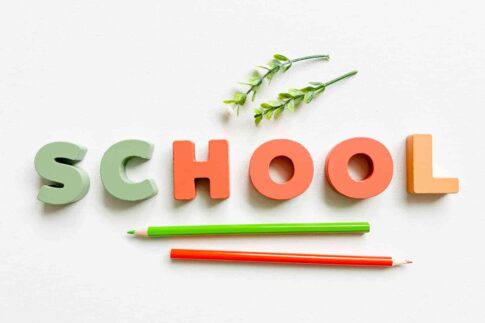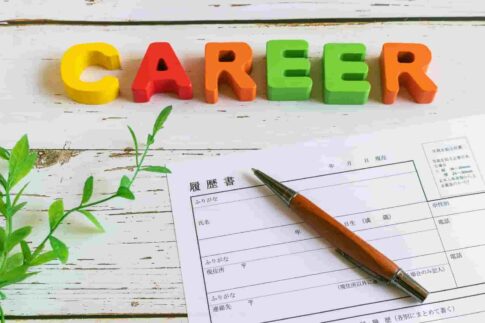大卒と高卒では何が違うのか、就職や転職する時に理解しておくことをおすすめします。この記事では、大卒と高卒で給与や仕事に生じる差について解説します。また高卒の人が効率的に転職活動を行いキャリアアップをねらう方法についても紹介していきます。
高卒と大卒の違い、高卒の現状
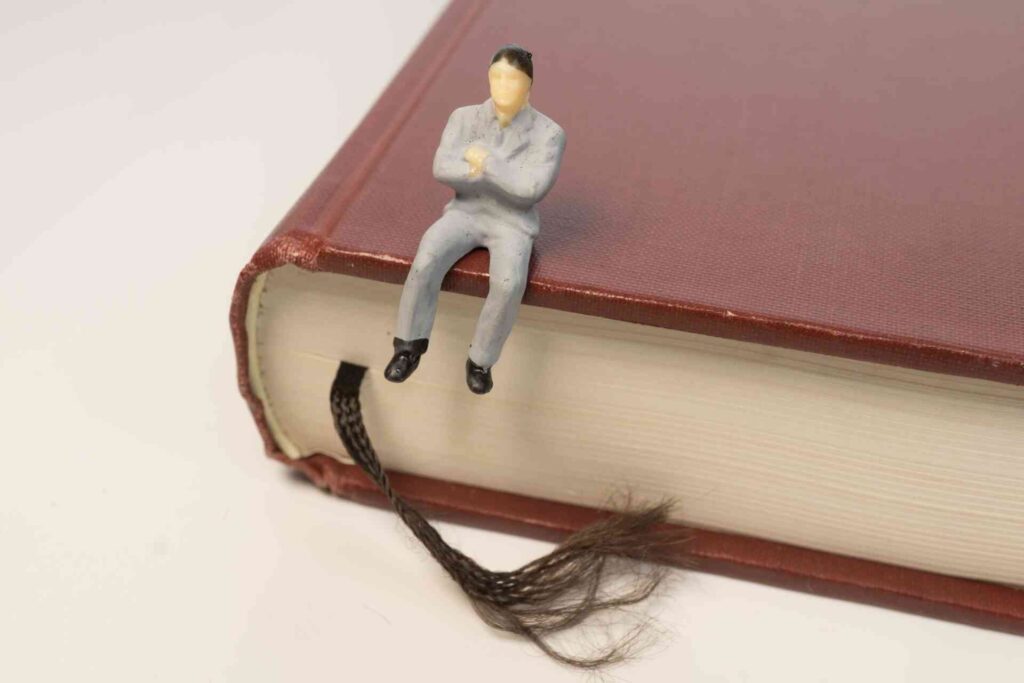
高卒と大卒の違いを5つの観点からまとめました。
高卒と大卒の割合
文部科学省から発表されている「令和元年度学校基本調査」によると、四年制大学への進学率は53.7%です。高等教育機関(四年制大学、短期大学、専門学校など)への進学率は82.6%ですので、高校を卒業した時点の高校卒業者の2割弱が高卒就職者、もしくは高卒求職者であるといえます。
なお、たとえ大学に進学をしても中退をすれば、学歴は高卒になります。文部科学省から発表されている「学生の中途退学や休学等の状況について」によると、学生全体の年間の中退率は約3%(平成26年時点)とあります。
これらの統計から、日本において最終学歴が高卒となる人は少数派であるといえるでしょう。
高卒と大卒は最終学歴が違う
高卒と大卒では履歴書に記載できる最終学歴が違います。最終学歴が大卒以上の求人の場合、基本的には応募もかないません。学歴不問という求人もありますが、大卒以上の募集が多いのが現状です。なお、大学を中退した場合も、最終学歴は高卒になりますので、注意が必要です。
就職・転職状況の違い
高卒と大卒との間には、就職のしやすさや転職のしやすさに違いがあるのでしょうか。
就職状況の違い
厚生労働省によると、2019年3月に卒業した大学生の就職内定率は97.6%。高校生の就職内定率は98.2%で過去最高となりました。この数字を見ると、高卒と大卒の就職率はほとんど変わらない様に見えますし、むしろ高卒の方がやや高いように見えます。
しかし、このデータには少し注意が必要で、実はこの数字は在学中に就職を希望して、内定した高校生の就職率です。高校卒業後に就活や転職活動をする人の就職率はかなり下がることが推測されます。
転職状況の違い
転職サイトにおける大卒以上の求人の割合は44%、学歴不問の求人は40%というデータもでています。この場合、高卒の方は44%の求人には最初から応募できない、ということになってしまいます。
高校在学中の就職活動に比べると、高校卒業後しばらくしてからの就職活動や、高卒という学歴での転職活動は厳しい状況が予想されます。
給与の違い
高卒と大卒ではもらえる給与が違います。
厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」によると、2019年の最終学歴別の初任給において高卒と大卒では約5万円の違いがあることがわかります。
高卒と大卒では、生涯受け取る合計賃金にも差があります。厚生労働省が公表している「学歴別にみた賃金」によると、年齢が25~29歳の場合、大卒・院卒者の月の賃金は261.3千円、高卒は226.5千円という結果になっています。この賃金の開きは年齢が上昇するほど大きくなっていきます。生涯賃金においては、高卒と大卒で6~7千万円ほどの開きがあります。
仕事内容の違い
高卒と大卒の違い仕事内容においてもあります。例えば「大卒でなければいけない仕事」は、高卒の人にはできません。具体的には、研究職や開発職など、専門的な知識と学力が必要な仕事は大卒、もしくは院卒でなければ難しいでしょう。この場合、いくら熱量を持っていても高卒の採用はほぼないと考えられます。こういった専門的な職業でなくとも、大卒はより幅広い職種を経験しやすいでしょう。大卒は将来的に会社の経営幹部にも関わってくる人材です。そのため、総合職に就き、1つの企業内でもさまざまな職業を経験させられるでしょう。
高卒のメリットとデメリット

ここではさらに高卒で就職するメリット・デメリットについて紹介します。
高卒のメリット
たとえばこんなメリットが考えられます。
- 同年齢に比べて早く社会人経験を得られる
- 大学の学費が不要
- 10代のうちに自立できる
- キャリアアップの年齢が早い
高卒のメリットはなんと言っても、大卒より早く社会にでられること。特にじっくり技術を身につけていくような職業では、4年間の差は大きなプラスになるでしょう。また、10代うちから自力でお金を稼ぐことができ、大学の費用もかからないので、経済的な自立が早いことも大きなメリットの一つです。
高卒のデメリット
考えられるデメリットは以下です。
- 社会経験がほとんどないうちに職業選択をしなければいけない
- 大学生活を送ることができない
- 大卒以上の求人に応募できない
- 初任給・生涯賃金の平均が低い
大卒者と比べてスタート時のハンデの多い高卒者ですが、正しい努力を重ねることで立場逆転を狙うことは可能です。大卒でも仕事ができない人はいくらでもいますし、高卒でぐんぐん頭角を表し大出世する人もめずらしくありません。ビジネスに役立つ職業スキル、柔軟さ、素直さ、対人スキルに学歴は関係ありません。高卒だからといって悲観は禁物です。
大卒のメリットとデメリット

次に大卒のメリットとデメリットを見てみましょう。
大卒のメリット
大卒のメリットはこんなところでしょうか。
- 自由な時間が多い
- 書類選考が有利に進みやすい
- 職業の選択肢の幅が広がる
- 初任給・生涯賃金の平均が高卒より高い
大卒のメリットはやはり、高卒より求人が多く、職業の選択肢が広がること。また、初任給や生涯賃金の平均が高いところです。そしてもう一つメリットとして大きいのは、大学生には自由になる時間が圧倒的に多いということです。この時間を使って、将来についてじっくり考えたり、インターンや留学など様々な経験を積むことができます。
大卒のデメリット
大卒にもデメリットがなくはありません。
- 受験や学費に莫大な費用がかかる
- 4年間無駄な時間をすごしてしまう人もいる
- 社会に出るタイミングが高卒に比べて遅くなる
大卒の最大のデメリットは、受験や学費に莫大な費用がかかることです。2019年の日本政策金融公庫から発表された『令和元年度「教育費負担の実態調査結果」』によると、大学の入学費用の平均額は82.8万円。1年間の在学費用は平均151万円とい結果がでています。奨学金を借りて進学した場合は、社会に出ると同時に返済を始めなければいけないので、高卒で社会に出る場合と比べると大きな負担になります。
高卒者は就職支援サービスで転職活動を成功させよう!

大卒にくらべてハンデが多く見える高卒者の転職活動ですが、外部サービスを活用することで効率的に進めることができます。そこでおすすめしたいのが就職支援サービスです。就職支援サービスなら、いわゆる求人サイトとは異なり「転職先を紹介してもらえる」というメリットがあります。就職支援サービスでは実際に面談やヒアリング、カウンセリングを行い、求人紹介だけではなく自分の強みを探したり、自分にぴったりな職種を見つけたりといったことも手伝ってもらえます。無料セミナーを開催している就職支援サービスもありますので、転職に関する情報収集もバッチリ。面接の方法、履歴書の書き方、その他書類の書き方もきちんと教えてもらえます。就職支援サービスに登録したからといって、必ずそこから仕事を見つけなければいけないというわけでもありません。「転職に関する情報を効率的に集めたい」時にも利用可能です。
特に20代での転職を考えている方は、弊社「ジェイック」のご利用を検討してみてください。20代ならではの転職の悩みに寄り添い、よりよい転職のお手伝いをします。
高卒と大卒の違い~まとめ~

高卒と大卒には給与差や待遇差、選べる仕事の違いがるのは事実ですが今から大学に通って卒業し、それから転職というのは現実的ではありませんよね。高卒であっても、自分の能力を最大限に活かせる職場へ転職できればキャリアアップも図れるでしょう。転職活動に行き詰まってしまった、もっと効率よく転職活動をすすめたい。そんな時には弊社「ジェイック」にお問い合わせください。あなたにぴったりな転職先を見つけられるよう、スタッフが全力でサポートいたします。
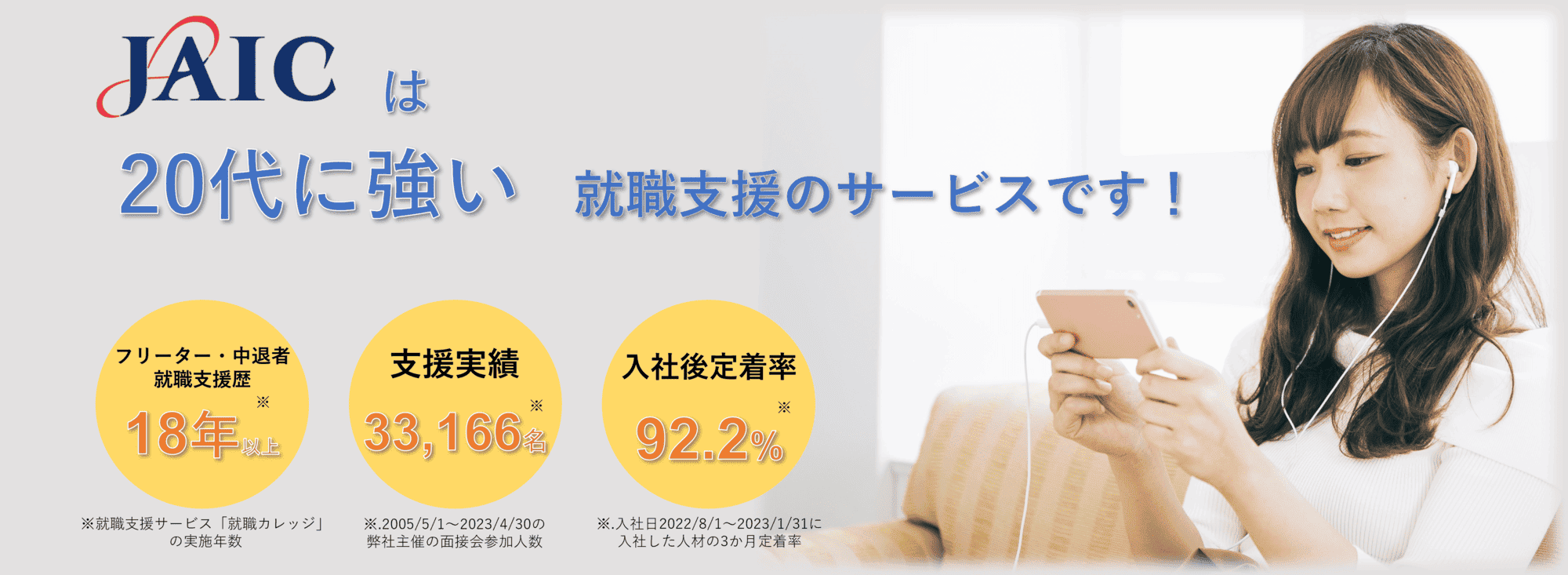
こんな人におすすめ!
- 自分に合った仕事や場所を見つけたい
- ワークライフバランスを重視したい
- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい