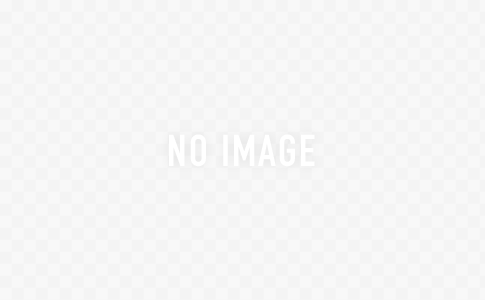ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護が必要な方やその家族の相談に応じ、適切な介護サービスを利用できるように支援する専門職です。
正式には「介護支援専門員」と呼ばれ、要介護・要支援の認定を受けた方に対し、ケアプランの作成をはじめとした様々なサポートを行います。
この記事では、ケアマネジャーの役割や仕事内容、資格の取り方などについて具体的に解説します。
向いている人の特徴も紹介しますので、ケアマネジャーの仕事に興味がある方はぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割は?
ケアマネジャーは、介護が必要な人とその家族を支える「介護サービスのコーディネーター」という役割を担っています。
介護保険制度の中核を担う専門職として、要支援・要介護者一人ひとりに最適なケアプランを作成することが主な仕事です。
ケアマネジャーは国家資格ではなく「公的資格」であり、基本的には保健・医療・福祉分野での実務経験が5年以上ある人が受験できるため、誰でもなれるわけではありません。
専門性と経験が求められるぶん、社会的な信頼が高い職種の一つといえるでしょう。
ケアマネジャーは介護の現場を支えるキーパーソンとして、そして介護領域に関わる高い専門性と判断力をもとに、多くの人の暮らしを支える大切な役割を担っているのです。
ケアマネジャーになるには?資格の取り方を解説
ケアマネジャーになるには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格する必要があります。
誰でも受験できるわけではなく、福祉・保健・医療に関わる資格を持ち、対人援助業務の経験が5年以上あるなどの受験資格が必要です。
合格後は実務研修を受けて「介護支援専門員名簿」に登録し、介護支援専門員証の交付を受けることで業務を開始できます。なお、介護支援専門員証の有効期間は5年間です。継続して業務を行いたい場合は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。
では、試験概要や受験資格、合格率について見ていきましょう。
※令和7年度試験(東京都)の情報をもとに紹介します。
最新情報は、受験地の試験ページや受験要項でご確認ください
ケアマネジャー試験の受験概要
ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)は都道府県ごとに実施され、毎年10月頃に行われます。
試験時間は120分(※)で、出題数は60問です。
試験科目は「介護支援分野」と「保健医療福祉サービス分野」の2つに分かれており、マークシート方式で出題されます。
受験申込は6月頃に開始され、10月の試験を経て、11月末頃に合格発表が行われるのが一般的な流れです。
受験手数料は12,000〜14,000円ほどで、受験地の都道府県によって若干異なります。
※点字受験者の試験時間は180分、弱視等受験者は156分
ケアマネジャー試験の受験資格
ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)は、「A」と「B」のいずれかの条件を満たす人が受験できます(※)。
| A | ・特定の国家資格を保有している ・国家資格に基づく業務の実務経験が通算5年以上かつ、従事日数が900日以上 | 例:国家資格(一部) ・医師 ・薬剤師 ・看護師 ・准看護師 ・理学療法士 ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・あん摩マッサージ指圧師 ・柔道整復師 ・栄養士(管理栄養士含む) ・精神保健福祉士 |
| B | ・相談援助業務に従事している ・規定の相談援助業務の経験が通算5年以上かつ、従事日数が900日以上 | 例:主な役割 ・生活相談員 ・支援相談員 ・相談支援専門員 ・主任相談支援員 |
出典:東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト「令和7年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」
なお、実務経験の年数と従事日数は、AとBそれぞれの期間の合算でもOKです。
実務経験は「直接的な対人援助」が対象のため、事務や営業などの就業期間は対象外になることにも注意が必要です。
※「実務経験」に関しては年数短縮を目指す動きもあり(2024年11月時点)
介護支援専門員実務研修の内容
ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格した方は、各都道府県が実施する「実務研修」を受ける必要があります。
たとえば東京都(第28回 第1期)の研修は、次の3ステップで構成されています。
| 1 | 前期課程 | ケアマネジャーに必要な専門知識などを学ぶ(後期課程と合わせて87時間) |
| 2 | 実習 | 居宅介護支援事業所において、原則3日間の実習を実施 |
| 3 | 後期課程 | グループワークを中心に、知識・技術・倫理観などを深める |
出典:東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト「実務研修|第28回 第1期」
ケアマネジャー試験の合格率
ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の令和6年度の合格率は、32.1%です。
受験者数は全国で53,699名、そのうち17,228名が合格しています。
令和6年度は30%を超える合格率となりましたが、これは比較的高めの水準です。例年10〜20%台の合格率に留まっており、ケアマネジャーは医療・介護福祉系の資格の中でも難関資格の一つとされています。
この先の合格率が30%前後となった場合でも、3人に2人は不合格となるという点で決して簡単な試験とはいえません。そのため、合格を目指すには入念な対策が欠かせないでしょう。
出典:厚生労働省「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」
ケアマネジャー(介護支援専門員)の給料・平均年収
ケアマネジャーの平均年収は、429.6万円です(※1)。日本人全体の平均年収460万円(※2)に比べると、やや低めといえるでしょう。
また、令和4年9月時点のケアマネジャーの平均給与は376,770円(※3)です。この金額から考えると、ケアマネジャーの月収は35〜40万円ほどといえそうです。
ただし勤務先の施設形態や雇用形態などによって収入は異なるため、ここでは以下の3つの観点をもとに、ケアマネジャーの年収について詳しく見ていきます。
- 施設ごとの平均年収
- 常勤・非常勤の平均年収
- 看護師や他職種との年収の比較
※1 出典:厚生労働省「介護支援専門員/ケアマネジャー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
※2 出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
※3 出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果 第102表」p.157
1. 施設ごとの平均年収
ケアマネジャーの平均年収を勤務施設ごとに見ると、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と通所介護事業所(デイサービス)には100万円以上の開きがあります。
こうした差が生まれる一つの理由としては、夜勤手当の有無が考えられます。
ケアマネジャーは基本的に夜勤がない職種ですが、介護職員が不足している施設では夜勤を担当することもあります。
一方、通所介護事業所は夜勤がほぼなく、手当がつかないため年収が低くなりがちです。
| 勤務施設 | 平均年収※ |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 490万円 |
| 介護老人保健施設 | 477万円 |
| 訪問介護事業所 | 437万円 |
| 通所介護事業所 | 376万円 |
出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果 第102表」p.157
※平均年収は、令和4年9月の平均月収を12倍した概算
2. 常勤・非常勤の平均年収
ケアマネジャーの平均年収を雇用形態別に見ると、常勤は約435万円、非常勤は約322万円で、その差は約110万円です。
年収の差には「実労働時間数」の違いが大きく影響していると考えられます。実際、常勤の月間労働時間は約164.9時間、非常勤は約83.3時間と、ほぼ2倍の差があります。
常勤は週5日働くケースが多いため、年収は総じて高めです。一方、パートなどの非常勤のケアマネジャーは週2〜3日勤務などを選ぶ人が多く、労働時間が短くなるぶん、年収が抑えられる傾向にあります。
| 雇用形態 | 平均年収※ |
|---|---|
| 常勤 | 435万円 |
| 非常勤 | 322万円 |
出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果 第117表」p.194
※平均年収は、令和4年12月の平均給与額(基本給(月額)+手当+一時金(1~12月支給金額の1/12))を12倍した概算
3. 看護師や他職種との年収の比較
ケアマネジャーの平均年収は約435万円、看護師は447万円で、看護師のほうがやや高めです。
一方、医療・福祉系の職種で見ると、ケアマネジャーの年収は比較的高い水準にあります。
たとえば理学療法士などは約426万円、生活相談員・支援相談員は約411万円で、いずれもケアマネジャーより低めです。介護職員は約381万円のため、実に50万円以上の差があります。
| 職種 | 常勤の平均年収※ |
|---|---|
| ケアマネジャー(介護支援専門員) | 435万円 |
| 看護職員 | 447万円 |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員 | 426万円 |
| 生活相談員・支援相談員 | 411万円 |
| 介護職員 | 381万円 |
出典:厚生労働省「令和4年介護従事者処遇改善状況等調査結果 第117表」p.194
※平均年収は、令和4年12月の平均給与額(基本給(月額)+手当+一時金(1~12月支給金額の1/12))を12倍した概算
ケアマネージャー(介護支援専門員)の仕事内容
ケアマネジャーの重要な仕事が、ケアプランの作成です。
ケアプランが適切に機能しているか確認するモニタリングや、他の介護サービス事業者との連携・調整も大切な役割の一つです。
要支援・要介護の認定サポートや、給付管理などの事務作業を担う場面も少なくありません。
では、ケアマネジャーの代表的な仕事を5つ紹介します。
1. ケアプランの作成
ケアプランとは、要支援者・要介護者および、その家族の状況に応じて作成される「介護サービスの利用計画」です。
介護保険サービスを利用するには、原則としてケアプランの作成が必要です。
ケアマネジャーは“介護サービスの専門家”として、利用者のADL(日常生活動作)や認知機能の状態、家族の介護負担などを把握し、介護保険の支給限度額内で適切なサービスをバランスよく組み立てることが求められます。
ケアプランは、利用者の介護状況や生活環境に応じて次の3種類に分けられます。
- 居宅サービス計画
- 施設サービス計画
- 介護予防サービス計画
居宅サービス計画
居宅サービス計画とは、自宅での生活を希望する要介護1〜5の認定を受けた方向けのケアプランです。
居宅サービスは、主に4つの種類があります。
- 訪問サービス
- 通所サービス
- 短期入所サービス
- その他のサービス
たとえば足腰が弱くなった高齢者に対し、「週3回のデイサービスで入浴介助を受ける」「歩行器をレンタルする」といった支援内容を、長期・短期の目標と共に計画します。
「自宅で暮らし続けたい」という希望を叶えるための、大切な設計図といえるでしょう。
施設サービス計画
施設サービス計画とは、介護施設を利用する要介護1〜5の認定を受けた方向けのケアプランです。
具体的には、次の3つの施設が対象です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
たとえば「庭の水やりを他の入居者と週3回行う」「座位保持訓練を理学療法士が担当する」といった計画を、他の専門職と連携しながら作成します。
施設という新たな環境の中で要介護者が安心して暮らすうえで、欠かせない計画といえるでしょう。
介護予防サービス計画
介護予防サービス計画とは、要支援1・2の認定を受けた方向けのケアプランです。
介護予防サービスは、要介護状態になるのを防ぐために提供される支援を指します。
たとえば以下のようなサービスが該当し、ケアマネジャーは利用者の状態や希望に応じて内容を計画します。
- 自宅で入浴の介助を受ける
- デイケアで機能訓練を受ける
要支援者が自立した生活を長く続けていくうえで、特に重要な役割を果たしている計画といえるでしょう。
2. モニタリング(定期的な見直し)
モニタリングとは、作成したケアプランが適切に機能しているかを確認する仕事です。
たとえば居宅介護支援を担うケアマネジャーは、要介護者には月1回以上、要支援者には3ヶ月に1回以上のモニタリングが義務付けられています。
具体的には訪問やWeb会議ツールを使い、次の点を確認します。
- 利用者の健康状態や生活状況の変化
- 介護サービスの利用状況や満足度
- 新たなニーズや課題の有無
定期的なモニタリングによって、状態悪化の早期発見や、不要なサービスの見直しが可能です。
より適切で効果的な介護サービスを提供するうえで、欠かせない仕事といえるでしょう。
3. 介護サービス事業者との連絡・調整
介護サービス事業者との連絡・調整とは、介護サービスを提供する様々な事業者と連携を取り、適切なサービス提供が行われるように働きかける仕事です。
「サービス担当者会議」の開催や進行も、ケアマネジャーの大切な役割の一つです。
サービス担当者会議とは、ケアプラン作成時や、要介護認定の更新時などに実施される会議で、利用者の家族や介護スタッフ、医師などに支援方針を共有します。
事業者間の連携が不十分だと、利用者や家族が混乱し、必要な支援が届かない可能性もあります。だからこそ、“調整役”としてのケアマネジャーの存在が欠かせないのです。
4. 要支援・要介護認定に関わる業務
要支援・要介護認定に関わる業務とは、利用者が介護保険サービスを適切に利用できるようにサポートする仕事です。
新規申請や更新申請の際に、次のようなサポートを行います。
- 申請のサポート(申請書類の記入方法の助言、申請の代行など)
- 認定調査の立ち会い(利用者の状態を調査員に正確に伝える役割を担う)
- 情報提供と連携(主治医や関係機関への情報提供、意見書の取得など)
- 認定結果の説明(要支援・要介護の区分や、支給限度額などの説明)
認定結果によって利用できるサービス内容や支給限度額が決まるため、ケアマネジャーにとって特に責任の大きな仕事といえるでしょう。
5. 給付管理に関わる業務
給付管理に関わる業務とは、介護給付費(介護保険からサービス事業者に支払われるお金)が適切に支払われるように管理する事務作業です。
利用者が介護保険サービスを利用すると、そのサービスを提供した事業者は、介護給付費を国民健康保険団体連合会に請求します。
その際、審査のために必要となる「給付管理票」などの書類を作成・提出するのがケアマネジャーの役割です。
書類に誤りがあるとサービス事業者への支払いが遅れてしまうなど、多方面に影響を及ぼしてしまう可能性があります。そのため、正確性が強く求められる仕事といえるでしょう。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の主な勤務先
ケアマネジャーの勤務先としては、自宅で生活している要介護者を支援する「居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)」が代表的です。
長期利用者が暮らす「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、在宅復帰を目指す方が過ごす「介護老人保健施設」で働くケアマネジャーも多くいます。
では、それぞれの勤務先について具体的に紹介します。
1. 居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)
居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)は、自宅で生活している利用者のケアプランを作成する事業所です。
主に要介護1〜5に認定された方を対象に、自宅で適切な介護サービスを利用できるように支援する役割を担っています。
具体的な支援内容は、以下の通りです。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
- モニタリング・評価
- 要介護者・家族からの相談受付
- サービス提供事業者との連絡・調整
- 関係機関との連携
- 給付管理
自宅で暮らし続ける支援に特化しているので、在宅生活を支えるサポートをしたいケアマネジャーは特にやりがいを感じられる勤務先といえるでしょう。
2. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、主に要介護3以上の高齢者が入所する施設です。
日常生活において介護が常に必要で、自宅での介護が困難な高齢者をメインに受け入れています。
具体的な支援内容は、以下の通りです。
- 日常生活の介護(食事、入浴、排泄など)
- 施設サービス計画(ケアプラン)の作成
- 機能訓練
- 健康管理
- 療養上の世話
- レクリエーション
- 送迎サービス
基本的には長期利用を前提とした施設のため、利用者一人ひとりと近い距離で関わりつつ、信頼関係をしっかりと築きながら支援をしたい方におすすめの勤務先といえるでしょう。
3. 介護老人保健施設
介護老人保健施設は、リハビリを中心とした医療ケアや介護が必要な高齢者が、在宅復帰を目指して一時的に入所する施設です。
病状が安定しており、入院治療の必要がない要介護度1以上の方が主な対象です。
具体的な支援内容は、以下の通りです。
- 在宅復帰支援
- 日常生活動作の維持・向上
- 医療ケア
- 日常生活の介護(食事、入浴、排泄など)
利用期間は原則3〜6か月と定められており、限られた時間内で最大限の効果を上げる必要があります。
そのため「在宅復帰」という明確な目標に向け、計画的かつ効率的な支援を行いたいケアマネジャーの方に適した勤務先といえるでしょう。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の一日の仕事の流れ
居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの「一日のスケジュール例」を紹介します。
08:30 出勤
09:15 利用者宅を訪問(1件目:モニタリング)
10:15 利用者宅を訪問(2件目:新規アセスメント)
11:00 利用者宅を訪問(3件目:サービス調整)
12:00 昼食
13:30 サービス担当者会議
15:00 利用者宅へ訪問(4件目:契約更新)
16:00 利用者宅へ訪問(5件目:情報提供・相談)
17:00 ケアプランの作成、給付管理、記録作成など
18:30 退社
月の上旬は給付管理業務に追われるなど、1か月の中でもスケジュールに変動はありますが、基本的には1日あたり4〜6件の訪問が一般的です。
なお、月の中旬はケアプランの作成やサービス担当者会議、月の下旬はサービス利用票作成などの事務処理がメインになる傾向にあります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)に向いている人の特徴
ケアマネジャーは、相手の話にしっかりと耳を傾けられる方に向いています。
細かな事務作業をそこまで苦に感じない方や、感情に流されずに冷静な判断ができる方も適性があるでしょう。
ここでは、ケアマネジャーに向いている人の特徴を3つ紹介します。
自分がケアマネジャーに向いているか気になる方は、ぜひご覧ください。
1. 人の話をじっくり聞ける
ケアマネジャーは傾聴力が必要な仕事のため、人の話をじっくりと聞ける人に向いています。
利用者の中には「家族に迷惑をかけたくないけど、本当は家で過ごしたい」といった複雑な思いを抱える方もいます。
家族からは「仕事と介護の両立がつらい」「どのサービスを選べば良いか分からない」といった相談も寄せられます。
このような状況では、相手の表情や言葉の奥にある気持ちまでくみ取り、焦らず最後まで話を聞く姿勢が大切です。
そのため、話を遮ったり自分の考えを押し付けたりせず、まずは相手の立場に立って理解しようとする人に向いている仕事といえるでしょう。
2. 細かな事務作業が苦ではない
ケアマネジャーは事務作業が業務の多くを占めるため、細かな事務作業がそこまで苦に感じない方に適しています。
具体的には、次のような業務があります。
- ケアプランの作成・修正
- 訪問記録の作成
- 給付管理
- 申請書類の作成
- 契約書関連の事務手続き
利用者やその家族と定期的に会い、困り事を聞き取ることも重要な仕事の一つです。しかし、それ以外の時間は事務作業に追われているケースも珍しくありません。
そのため、パソコンと向き合いながら地道な作業を続けられる方や、一人でコツコツと作業に取り組むことが得意な方はケアマネジャーに向いているでしょう。
3. 感情に流されずに判断できる
ケアマネジャーは“感情的な訴え”に対しても冷静さを失わず、適切なサービスを提案する必要があるため、感情に流されずに判断できる方に向いています。
たとえば、家族から「母親を施設に入れるなんて考えられない」と強く反対されたり、利用者本人から「あなたに言っても無駄でしょ」と投げやりな発言をされたりする可能性もあります。
こうした場面では、相手の気持ちを受け止めつつも冷静に現状を整理し、“介護支援のプロ”として最適な支援方法を見つけ出すことが欠かせません。
そのため、相手の感情に過度に引っぱられない方に適性がある仕事といえるのです。
ケアマネジャー(介護支援専門員)になって良かった人の声
ケアマネジャーの中には、「ありがとう」と感謝される場面が多いことにやりがいを感じている方も少なくありません。
専門職として安定して働ける可能性が高いことや、医療・福祉・法律など幅広い分野にまたがる仕事のため、成長実感を得られることにやりがいを見出す方も多くいます。
では、ケアマネジャーになって良かった人の声を3つ紹介します。
1. 「ありがとう」と感謝される場面が多い
ケアマネジャーは、利用者や家族から感謝の言葉を直接もらえる機会が多いため、「人の役に立っている」というやりがいを感じながら働く方が多くいます。
たとえば利用者の状況に合わせて適切なサービスを提案し、生活の質が向上した際に「家族の負担が軽くなって本当に助かった」と感謝の言葉をかけてもらうことも多いでしょう。
利用者本人との関わりの中でも、「話を聞いてくれてありがとう」といった温かな言葉をいただくこともあります。
自分が力になっている実感を日常的に感じられる仕事のため、ケアマネジャーとして充実した日々を送っている方も多いのです。
2. 専門職として長く働けるので生活が安定する
ケアマネジャーは専門職であり、この先もニーズが高まる仕事のため、年齢を重ねても継続して働ける安定性も評価されています。
ケアマネジャーは公的資格ですが、受験資格として「通算5年以上の実務経験」が求められるため、誰でも簡単になれるわけではありません。
また、高齢化が進む日本では介護サービスの需要が年々増加しており、ケアマネジャーの役割もますます重要になっています。
このように専門性が高く将来性がある職業のため、「安定した収入を得たい」「長く働き続けたい」と考えている方にとって魅力的な仕事といえるのです。
3. 色々な分野に関わるため成長を感じられる
ケアマネジャーは、医療・福祉・法律など幅広い知識が必要な仕事のため、日々学びながら成長を実感できることに喜びを感じる方も少なくありません。
医師との連携によって疾患や薬の知識に関する理解が深まったり、認知症ケア・終末期ケアの最新動向などを追うことで新たな知識を手にできたりすることも多いものです。
介護保険制度や関連法規は頻繁に改正されるため、最新情報を常にキャッチアップすることも業務の一環といえるでしょう。
このように多角的な知識・視点が手に入る仕事のため、学習意欲が高い方の中には大きなやりがいを感じている方も多いのです。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の大変さ
ケアマネジャーとして働くと、事務作業が想像以上に多いことに驚くかもしれません。
多数の関係者との調整が求められるため、精神的な疲労を感じる場面も多いでしょう。
ケアプランが想定通りに進まない場合は、大幅な見直しが必要になることもあります。
では、ケアマネジャーとして働くうえで感じやすい「大変さ」を3つ紹介します。
1. 膨大な事務作業に追われることが多い
ケアマネジャーは書類を作成する業務が多いため、デスクワークに多くの時間を取られてしまいます。
たとえば給付管理業務では、担当している利用者全員分の書類を何枚も作成し、毎月10日までに国保連合会に提出しなければなりません。
居宅介護支援・介護予防支援に関わるケアマネジャー1人あたりの担当件数は平均31.8人(※)となっており、利用者宅への訪問や関係機関との打ち合わせに追われる場面も多いでしょう。
そのため事務作業は夜遅くまで残って行うこともあり、特に仕事に慣れないうちはこうした業務量の多さに悩む可能性があるのです。
※出典:厚生労働省 老健局「居宅介護支援・介護予防支援|ケアマネジャーの1人当たり担当利用者数について」p.36
2. 関係者と調整が難しく、気を遣う場面が多い
ケアマネジャーは、医療機関・介護事業所・利用者の家族など、多くの関係者の間に立って調整を行う仕事のため気を遣う場面が多く発生します。
たとえば利用者の状態変化に伴ってサービス内容を変更する際、家族からは「費用を抑えたい」と希望される一方で、介護事業所からは「安全面を考えるともっとサービスが必要」と提案されることもあります。
「サービス担当者会議」では司会進行の役割を担うため、異なる意見をまとめる調整力も欠かせません。
このように介護には複数の関係者が関わるため、“板挟み”のような状況に置かれてストレスを感じる場面も多いのです。
3. 計画が想定通りに進まず、大幅な見直しが必要なこともある
ケアマネジャーは利用者の状況変化に柔軟に対応する必要があり、一度作成した計画を大きく変更しなければならない場面も出てきます。
時間をかけてケアプランを作成しても、「このままでは目標の達成が難しい」と判断された場合は目標そのものを見直し、再設定しなければなりません。その際は「サービス担当者会議」を再度開く必要があり、関係者への調整や書類の準備といった手間も発生します。
予想外の出来事に対し、冷静かつ迅速に新たな支援体制を整えなければならない仕事のため、柔軟な対応が苦手な方は苦労する可能性があるでしょう。
ケアマネジャー(介護支援専門員)のよくある質問
ケアマネジャーについて「よくある質問」にお答えします。
- ケアマネジャーとは簡単に言うとどんな仕事?
- ケアマネジャーとケアマネージャー、どっちが正しい?
- ケアマネジャーは国家資格?
- ケアマネジャーは誰でもなれる?
- ケアマネジャーの将来性は?
ケアマネジャーとは、簡単に言うと「介護が必要な人をサポートする仕事」です。
本人や家族へのヒアリングをもとに、必要な介護サービスを提案・手配し、ケアプラン(介護サービスの利用計画)を作成します。
介護は専門的な知識が求められる場面も多く、本人や家族だけで判断するのは難しいものです。
その点、ケアマネジャーは“介護支援のプロ”として、介護が必要な人とその家族が安心して生活できるように適切な支援と調整を行っています。
「ケアマネジャー」が一般的な呼び方ですが、「ケアマネージャー」と表記されることもあり、どちらも間違いではありません。
なお、厚生労働省が作成する「居宅介護支援の基本資料」などの公的な文書では「ケアマネジャー」と表記されています。
また、ケアマネジャー(ケアマネージャー)の正式名称は「介護支援専門員」であることも覚えておきましょう。
ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)は都道府県ごとに行われるため、公的資格です。
国家資格の試験は、国の機関が全国一律の基準で実施します。一方、ケアマネジャー試験の実施主体は都道府県のため国家資格ではありません。
とはいえ、ケアマネジャーは介護保険制度の中核を担う重要な資格のため、国家資格にも劣らない社会的信頼性を有していると言えるでしょう。
ケアマネジャーには試験があり、受験資格も厳格に定められているため、誰でもなれるわけではありません。
具体的には、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
| A | ・特定の国家資格を保有している ・国家資格に基づく業務の実務経験が通算5年以上かつ、従事日数が900日以上 | 例:国家資格(一部) ・医師 ・薬剤師 ・看護師 ・准看護師 ・理学療法士 ・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 |
| B | ・相談援助業務に従事している ・規定の相談援助業務の経験が通算5年以上かつ、従事日数が900日以上 | 例:主な役割 ・生活相談員 ・支援相談員 ・相談支援専門員 ・主任相談支援員 |
出典:東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト「令和7年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」
※実務経験の年数と従事日数は、AとBそれぞれの期間の合算でも可
高齢化社会の進展により、今後もケアマネジャーのニーズは高まると予想されています。
2025年には「団塊の世代」の全ての人が75歳以上の後期高齢者となり、日本は本格的な“超高齢社会”に突入します。
実際、すでに多くの地域でケアマネジャー不足が深刻な問題となっており、特に地方では人材確保に苦労している事業所が少なくありません。
介護サービスが必要な人はさらに増えると見込まれているため、それに伴ってケアマネジャーの需要も拡大していくでしょう。
まとめ
この記事では、ケアマネジャーの役割や仕事内容、試験概要などについて紹介しました。
ケアマネジャーは、要支援者・要介護者を支える“介護サービスの調整役”として、非常に重要な役割を担っています。
受験資格に一定の実務経験が求められるため、未経験からすぐに目指せる職業ではありませんが、興味がある方は試験受験に向けてまずは一歩踏み出してみましょう。