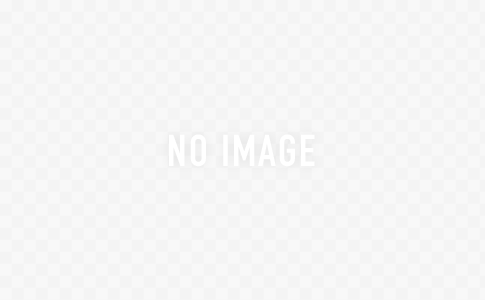就職浪人は既卒扱いが一般的ですが、一部の企業では新卒枠で応募が可能です。
厚生労働省が2010年に発表した指針により、卒業後3年以内の既卒者も新卒枠で応募を受け入れるよう努めることが企業に求められました。
その結果、企業によっては就職浪人も新卒同様に扱うケースが増えています。
本記事では、就職浪人の扱いや割合、就職浪人と新卒の違いとメリット・デメリット、就職浪人中にやっておくべき活動と前向きに伝えるためのポイントについて解説しています。
正しい知識と戦略があれば、就職浪人の内定獲得は十分に可能です。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
就職浪人は新卒の扱い?理由を解説
就職浪人は「新卒扱い」ではなく「既卒扱い」とされるのが一般的ですが、厚生労働省の指針によって、一部の企業では新卒枠で応募できる場合もあります。
厚生労働省は平成22年(2010年)に指針を改正し、企業に対して「学校卒業後3年以内の既卒者については、新卒枠での応募を受け入れるよう努めること」と要請しました。
この改正によって、卒業から3年以内であれば、就職浪人も新卒枠に応募できる可能性があります。
しかし、厚生労働省の要請はあくまでも努力義務であり、すべての企業が一律に受け入れているわけではありません。
就職浪人が求人を選ぶ際は、志望する企業の採用情報を確認し、自分が新卒枠で応募できるのかを見極めましょう。
就職浪人の割合を紹介
文部科学省が公表した「令和6年度(2024年度)大学等卒業者の就職状況調査」によると、
卒業者の就職率は98.0%のため、2.0%に就職浪人が含まれていると考えられます。
2024年度は売り手市場のため、過去と比較しても高い水準で就職率が推移しており、多くの学生が新卒で就職していることが分かります。
一方で、2.0%は就職していないため、この中に就職浪人が含まれると推測されるのです。
就職浪人になる理由はさまざまで、希望する企業から内定を得られなかった人、あえて翌年に挑戦する道を選んだ人などがいます。
統計的には小さな割合に見えても、個々の事情は多様であり、就職浪人として活動する際には情報収集と戦略的な準備が必要です。
就職浪人と新卒の違いを解説
就職浪人は、大学などを卒業した後、就職先が決まらないまま翌年度以降も就職活動を続ける人を指します。
一般的には「既卒」とみなされ、新卒扱いではなく中途や既卒枠に応募するケースが多い点が特徴です。
一方で、新卒は卒業見込みのある学生を対象としており、大学4年生などの最終学年が主な該当者です。
企業は新卒を採用する際にポテンシャルや人柄を重視する傾向があり、応募できる企業の幅が広い点が強みといえます。
就職浪人と新卒は立場や採用の扱いが異なる場合があるため、就職活動の進め方や求められる準備にも違いがある点を理解しておきましょう。
就職浪人と新卒の違いについて、以下のとおり解説します。
- 就職浪人は就職先が決まらないまま学校を卒業した人
- 新卒は卒業見込みのある学生
就職浪人は就職先が決まらないまま学校を卒業した人
就職浪人は、大学や専門学校などを卒業した際に就職先が決まっていない人を指します。
就職活動で希望の企業から内定を得られなかったり、納得のいく企業が見つからなかったりした場合に「卒業後も就職活動を継続する」という選択をする人が多くいます。
就職浪人は一般的には既卒者とみなされ、新卒扱いではなく中途採用や既卒枠での応募となる場合が多くあるのです。
就職浪人が就職活動をする際は、なぜ内定が得られなかったのかを面接で問われるケースもあります。
「内定が取れなかった人」と思われないよう、就職浪人中にどのような取り組みや成長があったかを言語化して面接時に伝えましょう。
新卒は卒業見込みのある学生
新卒は企業が定める「新卒採用」の対象となり、卒業予定の学生を指しています。
大学4年生や専門学校における最終学年の学生が該当し、年度内の卒業を前提として採用活動を行うのが一般的です。
企業は新卒を採用する際、経験やスキルよりもポテンシャルや人柄で採用する傾向にあります。
新卒には「新卒カード」と呼ばれる特権があり、多くの企業に幅広く応募できるだけでなく、未経験でも採用されやすいというメリットがあります。
また、多くの企業が一斉に説明会や選考を行う「就活スケジュール」が整備されており、情報も得やすく、周囲の同級生と支え合いながら進めやすいのも特徴です。
就職浪人のメリット
就職浪人は就職活動の注力やスキルアップ、面接対策の強化やキャリアの追求、実務経験など、新卒とは異なる多くのメリットがあります。
授業や試験に縛られず就活に専念できるため、企業研究や面接準備に十分な時間を割けます。
資格取得やスキルアップにも集中でき、TOEICや簿記、プログラミングなど、将来の仕事に直結する知識を磨ける点も魅力です。
また、面接対策を重ねて自己PRや志望動機を強化し、過去の反省を次に活かすことも可能です。
さらに、自分に合うキャリアを見直す余裕が生まれ、長期的に満足度の高い職業を選べます。
加えて、インターンやアルバイトを通じて実務経験を積めば、履歴書や面接で説得力のあるアピールが可能です。
本章では、就職浪人の主なメリット5点を以下のとおり解説します。
- 就職活動に注力できる
- 資格の取得やスキルアップに集中できる
- 面接対策や自己PRを強化できる
- より適したキャリアを追求できる
- インターンやアルバイトを通じて実務経験を積める
就職活動に注力できる
在学中の就活では、授業やゼミ、試験、サークル活動などの予定が重なりがちですが、卒業後はこれらの制約が少なくなり、企業研究や選考の準備、業界研究などに十分な時間を割けます。
例えば、志望業界の動向や将来性を調べたり、企業の情報を口コミやOB・OG訪問などで集めたりする時間が確保できるのです。
面接で「就職浪人の期間に何をしていたか」「なぜ今、再挑戦するのか」を明確に話せれば、就職浪人の期間を計画的に活用できた点が示せます。
就職浪人の時間は、自分を見つめ直す大切な期間です。焦らず前向きに取り組んでいけば、納得できる就職先に出会えるでしょう。
資格の取得やスキルアップに集中できる
就職浪人をすると学校の拘束がない分、資格の取得やスキルアップに集中できる環境が手に入ります。
企業は即戦力や将来の可能性を見ているため「就職浪人の際に何をしたのか」「何ができるのか」を評価対象にする場合があります。
例えば、TOEICや簿記、プログラミング言語など、業界や職種によって必要な資格をじっくり勉強できるのが強みです。
資格の取得やスキルアップの成果を履歴書や応募書類に記載する場合、例えば「簿記の資格を取って経理のスキルを身につけたため、〇〇の業務に役立てたい」とアピールできます。
採用側に主体性や意欲が伝わりやすく、プラスの評価につながるでしょう。
面接対策や自己PRを強化できる
就職浪人を選ぶと、面接対策や自己PRの準備にじっくり取り組めるうえ、改善するプロセスも可能になるため、実践力がつきます。
過去の選考で落ちた原因を自己分析し、なぜ不採用だったのかを振り返りましょう。主な原因は次のとおりです。
- 回答が抽象的だった
- 志望動機が浅かった
- 企業研究が足りなかった
過去の原因をもとに自己PRや志望動機をブラッシュアップして、エピソードを練り直したり、話し方を練習したりすると効果的です。
在学中は、面接対策のための時間が取りづらい場合がありますが、就職浪人の期間は丁寧に準備できるのがメリットといえます。
「なぜ新卒で就職できなかったのか」についても前向きなストーリーを用意でき、面接官に成長意欲を感じさせられるでしょう。
より適したキャリアを追求できる
就職浪人の期間では、本当にやりたいことや自分に合う働き方を考え直す余裕が生まれるため、より適したキャリアを追求できるメリットがあります。
業界や業種、職種に対する理解を深め、そのうえで「自分がどのような仕事をしたいのか」「どのような働き方を望んでいるのか」「将来どうなりたいか」をじっくり考える時間があります。
過去に妥協して受けた職種を見直したり、仕事の内容や環境(勤務地・労働時間・社風など)を慎重に比較したりすることもできるでしょう。
さらに、5年後や10年後にはどのようなポジションにいたいか、どのようなスキルを持っていたいかを逆算して、今何をすべきかを見定められます。
就職浪人の期間を前向きに活かすと、将来のキャリアをより納得できる形で築いていけます。
インターンやアルバイトを通じて実務経験を積める
浪人期間中は学業に縛られることが少ないため、インターンシップやアルバイトで実務経験を積むチャンスが増える点が特徴です。
業界の業務内容や企業文化、仕事の流れを体感でき、自分の向き不向きが見えてきます。
また、コミュニケーションなど、実務で活用できるスキルを経験から学ぶことも可能です。
さらにアルバイトなどで責任あるポジションを任されれば、マネジメント経験も得られるかもしれません。
インターンやアルバイトの経験は、履歴書だけでなく、面接での自己PRや志望動機にも役立ちます。
例えば「アルバイトで店舗運営を手伝い、業務効率の改善に貢献した」など、具体的に伝えると、評価が高くなります。
就職浪人のデメリット
就職浪人は学生よりも学びや見直しの時間が得られる反面、応募の制限や印象の懸念、サポートや生活の問題、長期化のリスクなど、複数のデメリットが存在します。
就職浪人は既卒扱いとされて新卒枠に応募できない場合があり、採用担当者からも「なぜ学生のときに内定が取れなかったのか」と疑問を持たれ、不利になりやすい点があります。
卒業後は大学のキャリアセンターで支援も受けられず、エージェントやハローワークの活用が必要です。
さらに、収入が限られて就活費用や生活費の負担が増え、精神的なプレッシャーにつながるケースもあります。
就職浪人の主なデメリットについて、以下のとおり解説します。
- 新卒限定の求人に応募できない場合がある
- 採用担当者がネガティブな印象を持つ可能性がある
- 学校のサポートが受けられない
- 経済的な負担が増える場合がある
- 就職浪人の期間が長引くと不利になりやすい
新卒限定の求人に応募できない場合がある
就職浪人は既卒の扱いになる場合があるため、新卒のみを対象とする求人には応募できないケースがあります。
多くの日本企業は依然として「新卒一括採用」を前提に採用活動を行なっており、就職浪人を新卒に含めない企業は一定数存在します。
厚生労働省は、卒業後3年以内の既卒者については新卒枠での応募を受け入れるよう指針を示していますが、あくまで努力義務にとどまるため、すべての企業が一律に適用しているわけではありません。
そのため、志望企業の募集要項や採用情報を事前に確認し、自分がどの枠で応募できるのかを把握しましょう。
採用担当者がネガティブな印象を持つ可能性がある
企業の採用担当者からは「なぜ新卒時に内定が得られなかったのか」と疑問を持たれる場合があります。
この問いに対して前向きかつ納得感のある説明ができないと「計画性や行動力に欠けるのでは」「忍耐力が弱いのでは」と受け止められる恐れがあります。
特に大手企業や人気のある業界では選考基準が高く設定されており、新卒と比較すると就職浪人は不利になりやすい傾向があるのです。
そのため、就職浪人の期間を有意義に活用し、資格の取得やスキルアップ、インターンなどの実務経験を通じて成長を示せば、その努力は大きな評価対象となります。
さらに、自分の将来像や志望動機を具体的に語ると就職浪人の経験がプラスに働き、採用担当者から信頼を得られるでしょう。
学校のサポートが受けられない
就職浪人になるデメリットの1つとして、学校のサポートが受けられない点が挙げられます。
在学中は大学のキャリアセンターなどを活用でき、求人の紹介やエントリーシートの添削、模擬面接などのサポートを受けられますが、就職浪人は学校の支援を受けられないケースが一般的です。
特に推薦枠がもらえない点は大きなデメリットです。
そのため、就職浪人は既卒者向けの就職エージェントや合同説明会、ハローワークなどを活用する必要があります。
環境の違いを理解して就職支援サービスを利用すると、就職浪人を乗り越えるチャンスにつながります。
経済的な負担が増える場合がある
就職浪人は収入がないか、アルバイトの収入に頼るケースが多いため、経済的な負担が大きくなります。
交通費や証明写真代、スーツの購入費など、就活にかかる費用は想像以上にかさみ、予想外の出費が続く場合もあります。
また、学割や学生向けサービスも使えなくなるため、生活コストが上がり、以前よりも出費が増えるかもしれません。
加えて、卒業後に奨学金の返済が始まったり、親からの仕送りが打ち切られたりするケースもあり、金銭的な不安が精神的なプレッシャーにつながる場合もあります。
生活費や就活費用を計画的に見積もり、支出を工夫しながら備えると、経済的な不安を和らげながら前向きに就活を続けられるでしょう。
就職浪人の期間が長引くと不利になりやすい
就職浪人の期間が長引くと、企業の採用担当者は「なぜ内定が長期間取れなかったのか」と疑問を抱く可能性があり、選考で不利になる場合があります。
「積極的に就職活動をしていないのではないか」「適性に問題があるのでは」と企業に判断されるケースがあり、内定の獲得が難しくなるからです。
不採用が続くと、自己肯定感やモチベーションが低下して就活したくないと感じるため、就職浪人の期間がさらに延びるという悪循環に陥る場合もあります。
就職浪人中は不利になりやすい状況だからこそ、過ごした時間をどのように活かしたかを前向きに伝えられるように準備しましょう。
就職浪人中にやっておくべき活動
就職浪人の期間は、自己成長や次の挑戦に向けて準備を進める大切な時期です。
自分の適性や価値観を振り返って自己理解を深め、将来の方向性をより明確にすると、キャリアを選択する際に納得感を持てるようになります。
さらに、社会人として必要な基礎力や実務に直結するスキルを学び直せば、その努力は浪人経験を強みに変えるでしょう。
また、就職エージェントやハローワークなど、外部の支援を積極的に活用しながら行動すると、情報収集や面接対策を効率的に進められ、就職活動をより有利に展開できます。
就職浪人中にやっておくべき主な活動について、それぞれ解説します。
- 自己分析を深めて志望動機やキャリアの軸を明確にする
- ビジネスマナーを習得する
- 就職エージェントを活用する
自己分析を深めて志望動機やキャリアの軸を明確にする
就職浪人中は、今まで以上に自己分析を丁寧に行いましょう。
在学中に行なった自己分析をそのまま使い回すのではなく、これまでの経験や失敗、学びを振り返りながら考えると、より深い自己理解が可能です。
自分がどのような価値観を大切にしているか、どのような働き方をしたいか、将来どのようなキャリアを描きたいかなどを整理しましょう。
これによって、面接での志望動機やキャリアプランの説得力が高まります。
採用担当者は就職浪人の期間に何をしていたかを気にするため、自己分析を通じて「なぜ就職浪人をしたのか」「就職浪人の期間で何を得たか」を具体的に説明できるように準備しておくと、成長の証として伝えられるでしょう。
ビジネスマナーを習得する
就職浪人の期間にビジネスマナーを身につけておくと、社会人としての基礎が備わっていると受け止められるため、就職活動で採用担当者から良い印象を持たれやすくなります。
また、配属後は職場へスムーズになじみやすいと判断される点も大きなメリットです。
正しい言葉遣いや清潔感のある身だしなみ、場面に応じた敬語の使い方、名刺交換のマナー、電話やメールでの適切な対応など、社会人として必要な基本ルールを体系的に学んでおきましょう。
ビジネスマナーの基盤がしっかりしていれば、面接中の立ち居振る舞いや企業訪問の際にも落ち着いた態度を示せるため、面接官に信頼感を与え、高評価につながります。
就職エージェントを活用する
1人で就職活動をするのは限界があるため、就職エージェントを活用してプロの支援を受けつつ効率よく就活を進めましょう。
就職エージェントでは、個別面談によるキャリアの確認や応募先企業の紹介、履歴書やエントリーシートの添削、模擬面接の対策など、豊富なサポートが受けられます。
非公開求人を紹介してもらえるケースもあり、自分だけでは見つけられない企業と出会える可能性もあります。
求人情報の幅を広げるため、複数の就職エージェントに登録し、サポート体制や求人数、キャリアアドバイザーとの相性を見極めながら利用するのが望ましいでしょう。
面接で就職浪人を前向きに伝えるためのポイント
面接で就職浪人を前向きに伝えるためには、明確な意思や目的、具体的な行動や成長、反省と改善意欲を意識して話すと高く評価されます。
企業は「自分で考えて行動できる人材」を求めているケースが多く、就職浪人の期間を戦略的に使った点を具体的に示せば、主体性や努力をアピールできるからです。
また、前回の就活での反省点を正直に伝えつつ、改善に取り組んだ結果を話すと良い印象を持たれるため、採用担当者からプラスの評価を得られるでしょう。
面接で就職浪人を前向きに伝えるためのポイントについて、以下のとおり解説します。
- 明確な目標や目的があった旨を伝える
- 就職浪人中に取り組んだことを具体的に話す
- 就職浪人中に得られた成長を示す
- 反省点や気づきも正直に話す
明確な目標や目的があった旨を伝える
就職浪人を前向きに伝えるため、就職浪人をあえて選んだ理由を明確に話しましょう。
仕方なく就職浪人になったのではなく「自分の意思で就職浪人を選んだ」と伝えると、主体性のある人物として評価される場合があります。
例えば「志望する業界や職種へのこだわりがあった」「納得のいく就職先を選ぶために選択した」など、目的意識を持って就職浪人を選択した旨を説明しましょう。
ポイントは、自分自身で考えて決断したことを伝えることです。企業は「この人が入社後も自分で考え行動できるか」を見ています。
目標に向けて行動した事実が伝われば、就職浪人の経験はプラスに判断されます。
就職浪人中に取り組んだことを具体的に話す
就職浪人の期間をどのように活用したかを面接で具体的に伝えると、前向きに努力できる人だと面接官が感じます。
就職浪人中に取り組む主な例は次のとおりです。
- 志望する企業や業界に直結する資格を取得する
- 就職活動の振り返りと改善を重ねる
- 志望業界や職種に近い現場でアルバイトとして働き、実務の流れを学ぶ
就職浪人中の取り組みが志望企業でどのように活かせるかを面接で話しましょう。具体例は以下のとおりです。
- 接客のアルバイトを続けて、お客様の対応やチームワークを学んだため、店舗運営で活かしたい
- 基本情報技術者試験を取得したため、システム開発業務で役立てたい
志望動機と取り組みを結びつけられると、就職浪人の期間がより戦略的に見えます。
就職浪人中に得られた成長を示す
就職浪人は自分を成長させる貴重な時間になった旨を面接で伝えましょう。
面接官は、就職浪人中に得た変化や気づきを知りたいと思っている場合が多いためです。
どのように変わったかを「ビフォー・アフター」の形で伝えましょう。具体例は次のとおりです。
ビフォー:学生のときは志望動機が漠然としていた
アフター:自己分析を深め、将来のキャリアを明確に語れるようになった
ビフォー:面接で緊張して言いたいことが伝えられなかった
アフター:模擬面接や練習を重ね、自分の強みを論理的に伝えられるようになった
上記のように変化を明確に示すと、面接官に成長が伝わりやすくなります。
また、その成長が今後の仕事へどのように活かせるのかも話すと、企業にとって「採用する価値のある人材」だと感じてもらえるでしょう。
反省点や気づきも正直に話す
面接で就職浪人の話をする際、失敗や反省点をあえて隠さず正直に伝えると、逆に好印象につながる場合があります。
企業側は完璧な人材を求めているわけではなく「失敗から学び、改善できる人」を評価するケースが多くあるからです。
そのため、自分の課題や弱点を冷静に振り返り、それにどう向き合ったかを話しましょう。
例えば「就職活動での情報収集が不十分だった」「自己分析が浅く、志望動機に一貫性がなかった」など、初期の就活でうまくいかなかった理由を具体的に伝えます。
さらに、その反省をもとに「どのように行動を改めたか」「どのように成長につなげたか」まで話すと、説得力が一気に高まります。
失敗を素直に認めると真摯な人柄が伝わり「この人は信頼できる」と感じてもらえるのです。
就職浪人は新卒扱い?に関するよくある質問
「就職浪人は新卒の扱いになるのか?」というのは多くの既卒者が一度は直面し、悩むテーマの1つです。
本章では、就職活動でよく寄せられる疑問を整理し、それぞれ分かりやすく答えていきます。ぜひ参考にしてください。
就職浪人で新卒枠を狙ったら不利になる?
就職浪人で新卒枠を狙う場合、不利になる可能性はありますが、一概に不可能というわけではありません。
厚生労働省は企業に対して「卒業後3年以内の既卒者を新卒枠として扱うよう努めること」と指針を出しています。そのため、就職浪人も新卒枠で応募できるケースがあります。
ただし、企業ごとに対応が異なるため、すべての会社が新卒扱いとして一律に受け入れているわけではありません。
また、採用担当者は「なぜ就職浪人をしたのか」「浪人期間に何をしていたのか」を重視する場合があるため、新卒枠で応募できても、理由を明確に説明できないと不利になる場合があります。
就職浪人と第二新卒の違いは?
就職浪人と第二新卒の違いは社会人経験の有無で、詳細は以下のとおりです。
- 就職浪人:卒業後に正社員としての就職をせず、就活を続ける人
- 第二新卒:一度は正社員として就職したものの、短期間(一般に3年以内)で退職し、転職活動を行う人
上記の違いにより、企業が期待するポイントも異なります。
就職浪人はポテンシャル重視で採用されるケースが多いのに対し、第二新卒は「最低限のビジネスマナーやスキルを持っている」と評価される場合があります。
立場の違いを踏まえて自己PRを工夫すると、より効果的にアピールでき、選考を有利に進められるでしょう。
就職浪人をするときは大学を休学したほうがいい?
大学を休学して新卒扱いを狙う場合はメリットとデメリット両方があるため、ケースバイケースといえます。メリットとデメリットは次のとおりです。
休学のメリット:
- 学籍が残るため、新卒として応募できる可能性がある
- 大学のキャリアセンターを引き続き利用できる
休学のデメリット:
- 休学の費用がかかる場合がある
- 面接で「なぜ休学したのか」と聞かれる可能性がある
- 卒業が遅れる
就職浪人よりも休学して新卒を目指す場合は、メリットとデメリットを理解して判断しましょう。
就職浪人で公務員を目指すのは可能?
公務員試験は新卒を必須条件としていないケースが多いため、就職浪人で公務員を目指すことは十分に可能です。
就職浪人の期間を試験対策に充てられる点は大きなメリットですが、年齢制限がある場合が多い点に注意しましょう。
万が一、公務員試験に失敗した際は、就職浪人の理由を説明して民間企業に応募せざるを得ないケースも考えられるため、リスク管理も必要です。
就職浪人で公務員を目指すときは、試験勉強に力を入れると同時に、年齢制限や民間就職の選択肢も考えて行動しましょう。
まとめ
就職浪人は原則として既卒扱いですが、厚生労働省の指針により、卒業後3年以内であれば新卒枠で応募できる企業があります。
ただし、厚生労働省の指針は努力義務であり、すべての企業に適用されるわけではありません。
就職浪人は在学中と比べて就職活動に専念できる、資格取得やスキルアップに集中できるなど多くのメリットがあります。
一方で、新卒求人に応募できない、学校の支援が受けられない、経済的な負担が増えるなどのデメリットも存在します。
企業は「浪人期間をどのように過ごしたか」を重視するため、明確な目的意識や取り組みを面接でポジティブに伝えると効果的です。
成長や改善を具体的に説明できれば、就職浪人の経験はむしろ強みとなり得ます。前向きな姿勢で努力を積み重ねれば、プラスの評価につながるでしょう。