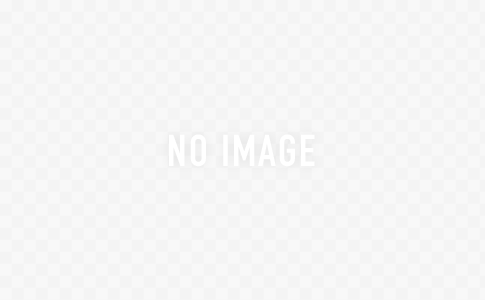売り手市場が続く現在、企業は若手人材を積極的に求めているため、浪人をやめて就職するのは絶好のタイミングといえます。
しかし「浪人をやめて就職するのは本当に大丈夫?」「親にどう説明すればいい?」「将来後悔しない?」と不安を抱える人は少なくありません。
本記事では「浪人をやめて就職する選択肢は有り」の理由やメリットとデメリット、浪人をやめて就職する際の進め方や公的な就職支援サービスについて解説しています。
自分の価値観に照らし合わせて冷静に判断できるようになるため、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
浪人をやめて就職することはできる?
浪人をやめて就職することは可能です。
なぜなら、労働市場が売り手市場の状況にあり、求人の数が求職者を上回っているからです。
厚生労働省の発表によると、2025年7月の有効求人倍率は1.22倍、新規求人倍率は約2.17倍でした。有効求人倍率が1を超える場合は、求職者よりも求人の方が多いため、就職しやすい環境であることを意味しています。
また、新規求人倍率が2倍というのは、2025年7月に新しく求人を出した企業が多く、受け入れ枠が豊富であることを示しています。
有効求人倍率と新規求人倍率の計算方法は次のとおりです。
| 計算方法 | |
|---|---|
| 有効求人倍率 | 月間有効求人数÷月間有効求職者数 |
| 新規求人倍率 | 新規求人数÷新規求職申込件数 |
もちろん、業種や地域、職種によって就職の難易度は変わってきます。
しかし、全体としては求人数が多く、企業が積極的に若手人材を求めているため、浪人経験があっても、また高卒で未経験であっても、就職できるチャンスが十分にあります。
参考:
厚生労働省 一般職業紹介状況(職業安定業務統計):集計結果(用語の解説)
浪人をやめて就職するメリット
浪人をやめて就職すると、時間やお金の節約に加えて、キャリア形成の面でも多くのメリットがあります。
大学進学を目指して浪人すると、入学から卒業までにさらに数年を要しますが、早い段階で就職すれば収入を得ながら社会経験を積めるため、大卒との差を広げやすくなるのです。
また、浪人をやめる選択は「逃げ」ではなく、むしろ戦略的な決断といえます。
自分のキャリアを柔軟に見直し、社会に早く出ることで得られる人脈や経験は、将来の選択肢を広げる大きな財産になります。
大学にこだわらず、自分に合った進路を見極める姿勢は、長期的に見て成功への近道につながるでしょう。
本章では、浪人をやめて就職するメリットを5つの観点から詳しく解説していきます。
- 時間のロスを防げる
- 大卒よりも早く収入を得られる
- 実務経験を早く積める
- 人脈や社会経験を広げやすくなる
- 学費の負担を減らせる
時間のロスを防げる
浪人生活では1年、場合によっては2年以上にも及ぶ長い期間を受験勉強に費やしますが、必ず合格する保証はなく、受かっても希望の大学や学部に入学できるとは限りません。
そのため、浪人をやめて就職した方が時間のロスを防げます。
就職すれば、すぐに社会経験を積めるため、同世代よりも一歩早くキャリアをスタートできます。
近年では学び直しの機会が多く用意されているため、就職後に通信制大学で学んだり、職業訓練を受けながら資格取得を目指したりという方法も可能です。
浪人で時間を失うリスクよりも、早期に社会へ出て得られる経験を重視する選択は、合理的かつ現実的な判断といえます。
大卒よりも早く収入を得られる
浪人をやめてすぐに働くと、大卒よりも早く収入を得られる大きなメリットがあります。
一般的に大学は4年間通う必要があり、その間は学費や生活費など、家計への負担が続きます。
一方で、就職すればすぐに給与が支給されて経済的に自立できるため、将来的な資産形成にも差がつく可能性があるのです。
さらに、早期から収入を得られると、住宅や車の購入など、生活の幅が広がるのも特徴です。
また、親の経済的な負担を減らせるため、家族との関係性にも良い影響をもたらします。
学歴による収入の差は今も存在するものの、収入を得られるタイミングの差は大きなメリットです。
実務経験を早く積める
浪人をやめて就職すると、他の人よりも早く実践的なスキルを磨けます。
学校では学べない現場での対応力や人間関係の築き方、業務の遂行力など、社会人としての基礎を形成する重要なスキルは、仕事を通じて経験できます。
企業が求める人材像として、ポテンシャルだけでなく即戦力が重視される場面も増えており、学歴が高いだけでは通用しない場合もあるのです。
その点、浪人せずに就職した人は早期に現場経験を積めるため、大卒の同世代と比べて圧倒的な力が身につきます。
また、実務経験があれば転職市場でも有利に働きます。
大学卒業後に新卒として就職するよりも、早くから現場に出て経験を重ねると、一歩先を行くキャリア形成が可能です。
人脈や社会経験を広げやすくなる
就職すると年齢や価値観が異なる人と多く関わるため、職場が学びと成長の場になり、人脈や社会経験を広げやすくなります。
大学生活では基本的に同年代との付き合いが中心ですが、職場では10代から60代以上まで、あらゆる世代との接点があります。
そのため、柔軟なコミュニケーション能力やビジネスマナー、交渉力など、実践的な社会人スキルが自然と身につくのです。
また、業務を通じて関わる取引先や外部の関係者とのつながりが、将来的に転職や独立、事業展開などのチャンスに変わるケースもあります。
したがって、若いうちから社会人ネットワークを築けるのは、大きな武器になります。
社会経験を通じて自己成長を促せる点が、浪人をやめて就職する大きな魅力の1つです。
学費の負担を減らせる
浪人や大学進学をせずに就職すると、学費や関連費用の負担を減らせます。
e-Gov法令検索や旺文社のデータによると、国公立大学や私立大学の入学金と授業料は次のとおりです。
| 大学 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 282,000円 | 535,800円 |
| 公立大学(平均額) | 220,661円 | 533,017円 |
| 私立大学(平均額) | 256,116円 | 988,497円 |
参考:
e-Gov法令検索 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令
浪人する場合は、入学金や授業料、夏期講習や冬期講習の費用がかかります。
朝日新聞の調査によると、浪人生の予備校代は年間で120万以上かかる場合もあるのです。
一方で、就職すれば学費がかからないだけでなく、収入が得られるため、経済的な自立が可能です。
費用を抑えながらキャリアを積む選択肢として、浪人せずに就職する道は十分に合理的といえます。
参考:
朝日新聞 Thinkキャンパス【アンケート】子どもが浪人生に…かかる費用はいくら? 「先輩」保護者に聞いた
浪人をやめて就職するデメリット
就職をやめて就職することには多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。
高卒で就職する場合、大卒条件を設けている企業には応募できないため、選択できる就職先が限られてしまいます。
また、大卒と比べると賃金や生涯年収に差が出やすい点も大きなデメリットです。
さらに、専門職や高度な資格を必要とする職種には挑戦しにくく、昇進や管理職への道も狭まりやすい傾向があります。
他には、社会経験が少ないまま働き始めると早期離職につながるケースや、周囲と比較して劣等感や焦りを感じる場合もあります。
これらの点から、浪人をやめて就職する際は収入とキャリア、心理の面でそれぞれに注意が必要です。
浪人をやめて就職するデメリットについて、主な6点をそれぞれ解説します。
- 大卒条件の企業に就職できない
- 高卒よりも大卒の方が賃金が高い
- 専門職への就職が難しい
- 劣等感や焦りを感じる場合がある
- 昇進や管理職への道が難しい場合がある
大卒条件の企業に就職できない
浪人をやめて就職する場合の大きなデメリットの1つは「大卒以上」を条件とする企業に応募できない点です。
日本の就職市場においては、依然として学歴を採用条件に含める企業が少なくありません。
求人票の応募資格に「大学卒業以上」と明記されていると、高卒の場合は応募の機会すら得られないため「希望する業界に挑戦できない」という壁に直面しやすくなります。
そのため、高卒で就職すると、長期的なキャリアの選択肢が狭まる恐れがあります。
浪人をやめて就職する場合は、どの業界や職種なら高卒で挑戦できるのかを冷静に見極めましょう。
高卒よりも大卒の方が賃金が高い
浪人をやめて高卒で就職すると、大卒と比べて賃金や生涯年収で大きな差が生じる可能性があります。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、学歴別の賃金は高卒より大卒の方が高いことが分かります。具体的な金額は次のとおりです。
| 大卒 | 高卒 | 大卒-高卒 |
|---|---|---|
| 385,800円 | 288,900円 | 96,900円 |
参考:厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況→学歴別
さらに、独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「ユースフル労働統計2023」では、学歴別の生涯賃金が示されています。
新卒で60歳まで勤務した場合、大卒と高卒の生涯賃金(退職金を除く)は以下のとおりです。
| 大卒(男性) | 高卒(男性) | 大卒-高卒(男性) |
|---|---|---|
| 247,400,000円 | 203,000,000円 | 43,800,000円 |
| 大卒(女性) | 高卒(女性) | 大卒-高卒(女性) |
|---|---|---|
| 198,000,000円 | 149,200,000円 | 48,800,000円 |
参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 生涯賃金など生涯に関する指標・ユースフル労働統計2023(P300)
男女ともに学歴が高いほど生涯賃金も高く、大卒と高卒では数千万円単位の差が生じます。
もちろん、高卒で起業して成功したり、専門スキルを身につけて高収入を得たりする人もいます。
しかし、統計的に見ると大多数のケースで「大卒>高卒」の賃金格差が存在しており、生涯にわたって続きやすいのが現実です。
専門職への就職が難しい
浪人をやめて就職するケースでは、専門職に就く道が限られてしまう点もデメリットとして挙げられます。
医師や歯科医師、獣医師、薬剤師などの職業は、大学での長期間にわたる専門的な学習と国家資格の取得が必須であり、高卒では挑戦できません。
弁護士や公認会計士などの高度な専門資格については、大学卒業は必須ではありませんが、大学教育を受けた受験生が大半を占めています。
そのため、大学進学を経ずに就職する道を選ぶと、将来的にこれらの専門職を目指すのが難しくなる場合があります。
専門分野に進みたい人にとって、この点は軽視できないデメリットといえるでしょう。
社会経験が少ないため早期離職につながる場合がある
社会経験が少ない状態で就職すると、仕事や人間関係に適応できず早期離職につながる恐れがあります。
厚生労働省の調査によると、新規学卒就職者における就職後3年以内の離職率は高卒で約38.4%、大卒で約34.9%と、高卒の離職率がやや高い傾向にあるのが特徴です。
高卒で社会に出る場合、社会人としての心構えや基本的なスキルが未熟なまま職場に飛び込む点が影響していると考えられます。
仕事のプレッシャーや人間関係のストレスに対応しきれず「思っていたのと違う」と早期に辞めてしまうケースが多いのです。
短期間での離職を繰り返すと、再就職で不利になる可能性もあるため注意が必要です。
参考:厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します
昇進や管理職への道が難しい場合がある
浪人をやめて高卒で就職すると、将来的に昇進や管理職への登用が難しくなる場合があります。
例えば、大卒は入社後すぐに総合職として幅広い業務を経験し、管理職候補としてキャリアが設計されます。
一方、高卒は一般職や技術職に就くケースがあり、同じ会社でも昇進のスピードに差が出ます。そのため、長期的に見ると役職や給与面で大きな格差がつくのです。
浪人をやめて就職すると、社会経験を早期に積める一方で「昇進ルートが制限される」可能性があることを理解しておく必要があります。
しかし近年では、終身雇用や年功序列が崩れつつあり、学歴よりも「成果」や「実力」で評価される企業が増えています。特に中小企業や成長企業では、実績やスキルを重視して管理職に抜擢する例も少なくありません。
そのため、高卒であっても自ら努力して成果を出すことで、キャリアアップの道を切り開くことは十分可能です。
浪人をやめて就職する際の進め方
浪人をやめて就職を選ぶのは、将来を自分で切り拓く勇気ある決断です。
大学進学を断念する理由を整理し、後悔しないと決めたら家族に相談してサポートを得ましょう。
そのうえで、自分が目指す業界や職種を考え、就職支援サービスを利用すると効率的です。
高卒可能・学歴不問などの求人情報を主に集め、履歴書の作成や面接の準備を進めながら、必要に応じて資格の取得も検討すると求人の選択肢が広がります。
内定後は生活リズムを整え、ビジネスマナーの基本を身につけておきましょう。
浪人をやめて就職する際の進め方について、以下のとおり解説します。
- 大学進学を断念する理由を明確にする
- 家族に相談する
- キャリアの方向性を考える
- 就職支援サービスを利用する
- 求人情報を集める
- 応募書類の準備と面接対策を行う
- 必要に応じて資格取得を検討する
- 内定後の準備をする
大学進学を断念する理由を明確にする
大学進学を断念する理由を明確にすると後悔しなくなるため、就職活動のモチベーションを保ちやすくなります。
まずは、なぜ大学進学を辞めたいのかを書き出してみましょう。
「現役で第一志望校に受からなかったから」「浪人を続ける自信がないから」「金銭的な負担が重い」など、具体的な理由があると判断しやすくなります。
また、それぞれの理由がどれほど重要かを順位付けするのも有効です。
例えば、経済的な負担がもっとも重い場合、クリアできるかどうかを家族に相談したり、奨学金の情報を調べたりするなど行動に結びつけられます。
最終的には「大学をあきらめること」が自分にとってどれだけの意味を持ち、どのように将来へ繋げたいのかが見えてくれば、求人を選ぶ際の軸がぶれにくくなります。
家族に相談する
浪人をやめて就職することを決めたら、家族に相談しましょう。
大学進学を断念する場合、金銭面だけではなく、親の希望など複雑な要素が絡む場合があるため、家族との対話は必要です。
「大学は自分にとって必要ではないと感じる」「就職を通じて何を目指したいのか」などを説明できるように準備しておきましょう。
また、家族の経験や知見を活かすのも有効です。
親や兄弟が仕事をしてきた中でのリアルな視点を聞いたり、就職先をどのように選ぶかアドバイスをもらったりすると、自分だけでは気づかなかった部分を補えます。
このプロセスを通じて、なぜ浪人をやめて就職するのかを再確認できるとともに、家族との協力関係を築けると、就職活動中も心の余裕を持って進められるでしょう。
キャリアの方向性を考える
キャリアの方向性を明確にすると、就職活動で自分に合った仕事を見つけられるため、満足度の高い働き方ができるようになります。
方向性が定まっていないと、求人を見てもどれが自分に合っているか分からず、志望動機も曖昧になります。
そのため、まずは自己分析を行いましょう。自分の強みや弱み、興味のある分野、これまでの経験(アルバイト・趣味など)で何が楽しかったか、何が苦手だったかを洗い出します。
次に業界と職種の研究です。高卒や未経験で就ける仕事のうち、自分が興味を持てる業界はどのような特徴があるか、成長性や将来性、職場の働き方の実態を調べます。
最後に、自身の将来像を描きましょう。5年後や10年後にどのような自分でありたいか、実現するためにはどのような職種を経験し、どのようなスキルが必要かを考えると、進むべき道が明確になります。
キャリアプランを持つと就職活動中の選択で迷いが減るだけでなく、面接時にも意欲を伝えやすくなります。
就職支援サービスを利用する
就職支援サービスを利用すると、自分だけでは見つけられない求人情報やノウハウが得られるため、成功率が大きく向上します。
得意分野が異なる場合があるため、複数のサービスに登録して比較するのがおすすめです。
就職支援サービスを利用する際は、勤務地や給料、業界、働き方の中で「妥協できること・できないこと」を整理したうえで、自分の希望や条件を明確に伝えます。
就職支援サービスを使うメリットの1つは、非公開求人にアクセスできる点です。
また、面接対策を実施でき、フィードバックももらえるため、自分のアピールポイントに気づける場合も多くあります。
就職支援サービスをうまく活用すれば、納得のいくキャリアへの第一歩を力強く踏み出せるでしょう。
求人情報を集める
さまざまな情報源から求人を広く集めると、自分に合った職場と出会える可能性が高まります。
求人サイトや転職サイト、ハローワークなど、大手の求人媒体をチェックしながら、既卒・未経験歓迎の求人に絞って探しましょう。
就職支援サービスから紹介された非公開求人やインターネット上の求人だけでなく、企業の採用ページや地元の求人情報誌なども見落とさないようにチェックします。
求人情報を集める際は、勤務地や給与、福利厚生、勤務時間、休み、将来性、職場の雰囲気など、自分にとって譲れないものを明確にし、それを基準に求人を絞ると効率よくチェックできます。
人気のある企業や条件の良い求人は、応募がすぐに締め切られる場合が多いため、定期的に情報をチェックすることも必要です。
応募書類の準備と面接対策を行う
応募書類のブラッシュアップと面接対策をしっかり行えば、浪人をやめて就職する場合でも内定を得る可能性は十分高まります。
志望動機は「〇〇をやりたいから」だけではなく、これまでの経験を通じて何を学び、それを仕事へどのように生かしたいかを具体的に語れるように準備します。
面接対策では、模擬面接の練習を就職支援サービスに依頼し、内容や話し方、表情をチェックしてもらいましょう。
よく聞かれる質問として「なぜ大学に行かないのか」「浪人期間は何をしていたのか」「この会社で何をしたいのか」などがあります。
想定される質問について自分の考えを整理しておき、ネガティブになりがちな部分はポジティブに説明できるようにします。
準備を重ねて自分の思いを丁寧に伝えれば企業に評価され、希望する就職先に出会えるでしょう。
必要に応じて資格取得を検討する
資格の取得はキャリアの選択肢を増やしたり、応募先での差別化を図ったりするための有効な手段ですが、取得までのコストや時間とのバランスを考えて計画的に進めましょう。
まずは、自分が志望する業界や職種で資格がどれほど評価されるかを調査します。
求人情報や企業説明会などで「必要」「歓迎」などの記載を見て有効性を判断しましょう。
次に、現在の学習時間と仕事探しのスケジュールとの兼ね合いを考慮します。参考書や講座などのコストも見積もっておきましょう。
さらに、時間管理や根気など、資格を取得する過程で学んだ点も自己PRの材料になります。
ただし、取得するまでに時間がかかる資格は、就職活動のタイミングを逃すリスクもあるため、優先度を見極めることが大切です。
内定後の準備をする
内定を得た後は、社会人生活をスムーズに始められるように準備しましょう。
雇用形態や勤務地、就業時間、休暇、給与・賞与、昇給制度、福利厚生、交通費支給の有無など、書面で確認できるものは必ずチェックします。
入社日や研修スケジュールなどもあらかじめ把握しておき、スーツや仕事に必要な道具なども準備します。
また、社会人としてのマナーや基本的なスキルの見直しも有用です。
電話対応や敬語、時間管理、報告・連絡・相談など、仕事を始めてからすぐに求められることがあるため、事前に本やセミナーで学んでおくと安心です。
準備を整えておけば、自信を持って社会人生活をスタートできるでしょう。
浪人をやめて就職する際に頼れる公的な就職支援サービス
浪人をやめて就職を目指す際は、キャリアの不安や情報不足に悩む人も多いでしょう。その場合に頼れるのが、公的な就職支援サービスです。
公的な就職支援サービスは年齢や状況に応じて利用でき、就職相談や面接対策、職業訓練、給付金制度など、就活に必要なサポートを無料で受けられるのがメリットです。
「浪人をやめて就職を目指すと不利になるのでは?」と不安を抱きがちですが、公的な支援機関では、そのような状況に理解のあるスタッフが寄り添いながら支援してくれます。
公的な就職支援サービスは利用対象や支援内容が異なる場合があるため、自分に適したサービスを選びましょう。
主な支援機関5つについて、特徴を詳しく解説します。
- 新卒応援ハローワーク
- わかものハローワーク
- 地域若者サポートステーション(サポステ)
- ハローワーク
- 求職者支援制度
新卒応援ハローワーク
新卒応援ハローワークでは、大学などの学生や、卒業後おおむね3年以内の人を対象に就職支援を行なっています。
最大の特徴は、求人紹介から履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接までを一貫して無料でサポートする点です。
担当者制で就職支援ナビゲーターがつくため「何から始めればいいか分からない」という段階でも安心して就職活動をスタートできます。
就職活動に役立つセミナーなども定期的に開催されており、社会人経験のない人でも基礎から学べる環境が整っています。
新卒応援ハローワークは全国に設置されているため、浪人から就職へ進路を変える際の心強い味方となるでしょう。
わかものハローワーク
わかものハローワークは、正社員としての就職を目指すおおむね35歳未満の若者向けに設置された専門窓口です。
個別支援計画に基づき、きめ細かな就職支援を受けられる点が特徴です。
担当者が一人ひとりの経歴や希望に沿って、就職活動を全面的にバックアップしてくれるため「浪人をやめて就職するのは不利になるのでは?」という不安も解消できます。
応募書類の作成指導や面接の練習、就職活動に役立つセミナーなども充実しており、社会経験が少ない人でも安心して就職活動に臨めます。
また、企業説明会や企業面接会を開催しているため、人事担当者と直接話せる機会を持てるのも魅力です。
わかものハローワークは全国に設けられており、どこからでも相談が可能です。利用料は無料のため、迷わず活用することをおすすめします。
地域若者サポートステーション(サポステ)
地域若者サポートステーション(サポステ)は「働くことに不安がある」「社会に出るのが怖い」と感じている15〜49歳の若者を対象に、就職までのステップを無料で支援する公的サービスです。
相談員との個別面談により、心理的なハードルを下げながら就職を目指せます。
職業体験や就労準備セミナー、ビジネスマナー講座など、実践的なプログラムも豊富に用意されており、社会人としての知識を身につけられるのが特徴です。
就職等率は73.7%と高い数字を誇り、就職後の定着支援も行われているため、悩みや不安も解決できます。
サポステは全国各地に設置されていますが、サテライトや出張相談、メールや電話による相談も受け付けているため、直接訪問せずに利用できるのも大きなメリットです。
浪人をやめて就職を検討している人は、サポステの門を叩いてみるのもおすすめです。
ハローワーク
ハローワークは、年齢や経歴を問わず誰でも利用できる就職支援機関です。
浪人をやめて就職したいと考える人にも、頼れる存在といえるでしょう。
ハローワークでは求人情報の提供や職業相談、応募書類の作成支援、模擬面接、職業訓練の案内など、幅広いサポートが無料で受けられます。
雇用保険や失業給付の手続きも行えるため、就職と生活の両面でのサポートが可能です。
全国に500か所以上の拠点があり、どこに住んでいてもアクセスしやすい点も強みです。
ハローワークを積極的に活用すれば、就職活動の不安を減らしつつ、自分に合った新しい一歩を踏み出せるでしょう。
参考:厚生労働省 ハローワーク
求職者支援制度
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者向けに、無料の職業訓練と生活支援給付金を組み合わせた就職支援制度です。
給付金の対象にならない場合でも、職業訓練を無料で受講できるのが特徴です。
浪人をやめて就職を考えているが、スキルや実務経験に不安がある人にとって、非常に効果的なサポートといえます。
求職者支援制度を利用すると、職業訓練コースを無料で受講でき、さらに一定の条件を満たせば、月額10万円の給付金(職業訓練受講給手当)を受け取ることも可能です。
訓練内容は、ITや介護、営業、事務など幅広く用意されており、自分に合ったスキルを身につけられます。
職業訓練中も就職支援が行われ、就職先の斡旋や面接対策もセットで実施できます。
職業訓練受講給付金を受給する際は、収入や資産などの条件がありますが「就職するためにスキルを学びたい」と考えている人にとっては、非常に手厚い制度です。
浪人をやめて就職?に関する主な質問
浪人生活を続けるか、それともやめて就職するか、進路に悩む人にとっては非常に大きな決断です。
「浪人をやめて就職を目指すと不利になるのでは?」という不安の声もありますが、学歴不問で未経験でも可能な職場は多く存在します。
本章では「浪人をやめて就職」にまつわる代表的な質問について解説していきます。
浪人をやめても正社員として就職できる?
学歴や経験よりも本人の意欲やポテンシャルを重視する企業が多数あるため、浪人をやめた後でも正社員としての就職は十分に可能です。
特に若年層の採用では、これからの成長が重視される傾向があり、浪人をやめて就職する理由をどのように説明できるかがポイントになります。
就職支援サービスや支援機関を活用すれば、履歴書や面接でのアピール方法を専門家と一緒に考えながら対策できるため、内定獲得の可能性は十分にあります。
真剣にキャリアを考えて方向転換したという理由が面接担当者に伝われば、企業は前向きに評価してくれるでしょう。
浪人をやめて専門学校に通ってから就職するのは有利になる?
浪人をやめて専門学校でスキルを習得してから就職する場合、状況によっては非常に有利です。
手に職がつく分野(IT・医療・デザイン・調理など)では、専門知識や技術があると即戦力として評価されやすくなるからです。
そのため、業種によっては大卒に負けない強みになる可能性もあります。
ただし、学費や通学が必要になるため、費用対効果を考えた上で専門学校を選択しましょう。
専門学校で学んでからの就職は「何となく」よりも「やりたいことが見つかった」人にとって適した選択肢といえるでしょう。
まとめ
「浪人をやめて就職する選択肢は有り」の理由やメリットとデメリット、浪人をやめて就職する際の進め方や公的な就職支援サービスについて解説しました。
浪人をやめて就職するという選択肢は、売り手市場では現実的かつ有力な進路の1つです。
求人倍率の高さや就職支援制度の充実により、高卒かつ未経験でも正社員として働けるチャンスが広がっています。
浪人をやめて就職する場合はメリットとデメリットがあるため、自分の価値観やキャリアの方向性を明確にしたうえで選択することが重要です。
浪人をやめて就職する決断は、将来を切り開く大切な一歩です。
自分に合った支援をうまく活用しながら、新しいキャリアを前向きに築いていきましょう。