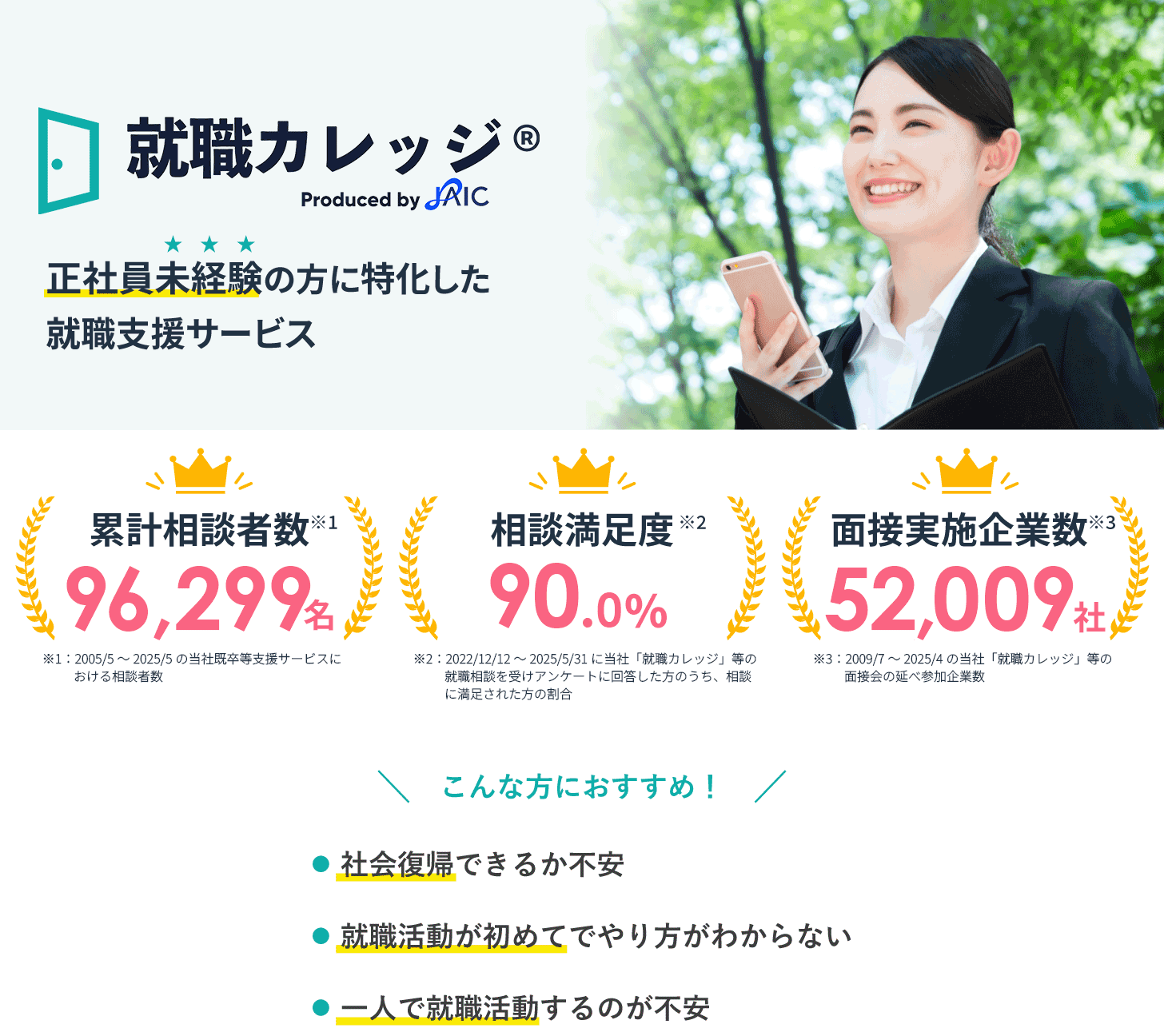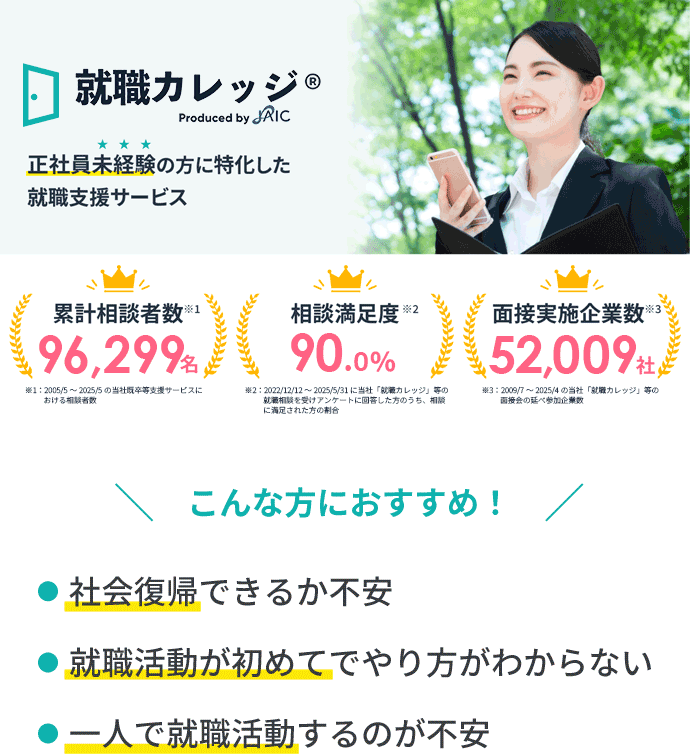ニートを無理に追い出すのは、ほとんどの場合で逆効果になります。
親として「このままではダメだ」「一度外に出して刺激を与えたい」と思うのではないでしょうか。
しかし、準備ができていないまま追い出すと、親子関係の崩壊や社会的な孤立、心身の悪化など、深刻なリスクを招きかねません。
場合によっては、手遅れになる可能性もあるのです。
本記事では、ニートを追い出すのが逆効果である理由を明確にしつつ、親が取るべき具体的な対処法や、頼れる支援機関について解説しています。
今の不安を乗り越え、親子ともに前向きになれる方法が分かるため、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
ニートを追い出すのは逆効果?理由を解説
ニートの子どもを無理に追い出すのは、問題の解決どころか逆効果になるケースが多くあります。
なぜなら、強引に追い出すと親子の信頼関係が壊れたり、子どもが社会から完全に孤立してしまったりなど、深刻な事態を招く場合があるからです。
さらに、取り返しのつかない状況になり、親が罪悪感に苦しむかもしれません。
時間がかかっても、子どもが安心できる環境の中で少しずつ社会とのつながりを取り戻していくことが最善の方法です。
本章では、以下の内容についてそれぞれ解説します。
- 親子の信頼関係が壊れるから
- 社会との接点がないまま追い出すと孤立するから
- 生活力が不十分な場合は自立できないから
- 単に追い出すだけでは問題が解決しないから
- 精神的に不安定な状態を悪化させるから
- 適切な支援機関につながる機会が減るから
- 親が罪悪感に苦しむ可能性があるから
親子の信頼関係が壊れるから
ニートの子どもを追い出すと、親子の信頼関係が壊れ、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。
親が精神的に追い込まれ、子どもに対して「もう出て行って」と言ってしまうケースがあります。
しかし、その言葉で「見捨てられた」と子どもが感じ、親への信頼を一気に失うきっかけになるのです。
また「追い出された」という経験は、強いトラウマとなって子どもの心に深く残る場合もあります。
親が「悪かった」と後から謝っても、関係の修復は簡単ではありません。
一度壊れた関係を取り戻すには、何倍もの時間と努力が必要です。
子どもを変えたいなら、親が「あなたのことを本気で心配している」「味方である」という姿勢を示し、安心できる関係性を築きましょう。
厳しさだけではなく、理解と寄り添いが親子の信頼につながります。
社会との接点がないまま追い出すと孤立するから
社会とのつながりが一切ない状態で家から追い出すと、住まいや仕事、人間関係を最初から自力で築くのは非常に困難なため、子どもが孤立する恐れがあります。
特に、働いた経験がなかったり、外との関係が長く途絶えていたりする場合には、現実の厳しさに直面して心が折れてしまうことも少なくありません。
頼れる相手がいないまま不安や恐怖に押しつぶされれば、行き場を失ってホームレス状態になるリスクも高まります。
社会と再びつながるためには、安心できる居場所と対話できる存在が必要です。
親がその土台を支えると、子どもが一歩を踏み出すきっかけになり、ニートから抜け出す希望が見えてきます。
就職支援サービス「就職カレッジ®」のURLをLINEでシェアしよう
生活力が不十分な場合は自立できないから
生活力がないままでは、自立はおろか、生きていくこと自体が困難になる可能性があります。
ニートの若者は、基本的な生活スキルや社会性が十分に育っていないケースがあります。
そのため、家事や身の周りのことができない、面接の受け方や履歴書の書き方が分からないなど、基本的な部分でつまずいてしまうのです。
その結果、仕事が決まらずお金もなくなって借金を抱えたり、家賃が払えずに住む場所を失ったりするという悪循環に陥るリスクがあります。
自立を促すなら、まずは家庭内で最低限の生活スキルを身につけさせましょう。
例えば、家事の一部を任せたり、買い物や料理を一緒にするなど、小さな成功体験を積ませると効果的です。
小さな積み重ねを大切にすれば、やがては自信となり、安心して社会へ踏み出す力へとつながっていきます。
単に追い出すだけでは問題が解決しないから
「家にいるから甘えている」「外に出れば変わるはず」と思って子どもを追い出しても、多くの場合、それだけでは解決しません。
なぜなら、ニートになる背景には、本人の性格だけでなく過去の挫折体験や発達障害、精神的な傷つきなど、さまざまな要因が複雑に絡んでいるからです。
そのため、本質を見つめ直さずに「とにかく追い出せばいい」と考えるのは逆効果となり、根本的な対応にはなりません。
家を出たとしても就職できず、生活に困窮し、精神的に追い詰められるだけになる可能性があります。
そのため、本人の話に耳を傾けて、何に困っているのか、どうしたいと思っているのかを一緒に考えましょう。
そして、必要に応じて支援機関や専門家の力を借りながら、段階的にサポートしていくことが大切です。
精神的に不安定な状態を悪化させるから
精神的に不安定な状態のまま子どもを追い出すと、心身の病を悪化させるリスクがあります。
ニート状態にある人は、精神的な不調を抱えている場合が多くあります。
そのような状態で無理に追い出すとショックを与えるだけでなく「自分は誰からも必要とされていない」と感じて絶望感や自己否定感を強める原因になり、逆効果になるのです。
心身の病は、ちょっとしたきっかけで一気に悪化する場合があります。そのため、安易な追い出しは非常に危険です。
まずは子どもが安心して過ごせる環境を用意し、少しずつ前を向けるように支援しましょう。
必要であれば医療機関やカウンセリングなど、専門的なサポートにつなぐのも効果的です。
適切な支援機関につながる機会が減るから
子どもを追い出すと、専門的な支援を受けるチャンスが失われるため、逆効果になります。
現在は、ニートや引きこもりの支援を行う機関や団体が数多く存在しますが、それらの支援に子どもが自らアクセスするのは、非常に難しいものです。
多くのニートは人との接触に強いストレスを感じており、自ら動き出すエネルギーがない状態にあります。
そのため、家族のサポートや信頼できる第三者の存在が、支援への重要な橋渡しになるのです。
ところが、家から追い出してしまうと、その橋渡し役すら失われてしまいます。
本人にとって必要なのは「あなたは1人ではない」「サポートしてくれる場所がある」という安心感です。
支えがあると感じられるだけで、子どもは少しずつ心を開き、支援へとつながる道を歩み始められます。
親が罪悪感に苦しむ可能性があるから
子どもを追い出した後に、親が深い後悔や罪悪感に苦しむケースが多くあります。
ニートの子どもと向き合うのは、親にとっても大きなストレスです。
「どうしてこんなふうになったのか」「何が悪かったのか」と自問自答を繰り返し、限界を迎えて「もう無理」と追い出す決断をする親もいます。
しかし、追い出した後に子どもが困窮したり、音信不通になったりした場合には「自分たちのせいで…」と強い罪悪感に苦しむ場合があります。
ニートの子どもを無理やり追い出すのは、問題から一時的に目をそらす方法にすぎず、逆効果です。
親の心が軽くなるのは、子どもが少しずつでも前向きに変わっていく姿を見ることです。
そのためには、怒りではなく理解と対話を選ぶ必要があります。
就職支援サービス「就職カレッジ®」のURLをLINEでシェアしよう
ニートに必要なのは個別に寄り添う支援体制
ニートに必要なのは、画一的なプログラムではなく、一人ひとりの背景に寄り添った個別支援です。
厚生労働省の調査によると、ニートになる若者には不登校やいじめ、中退、家庭内問題、職場での人間関係のトラブル、精神的な不調など、さまざま背景が存在しています。
これらの事情は人によって異なるため「全員に同じ支援をすればよい」という発想では、根本的な解決にはつながりません。
また、ニートの約80%がアルバイト経験を含む就労歴を持っていますが、長期的な職場定着には至っていません。
特に「人と話すのが苦手」など、コミュニケーションへの強い苦手意識があり、これが退職や就労意欲の低下などの問題につながっています。
このような実態から、ニートを支援する際は生活訓練や就労体験、職業訓練を段階的に行うとともに、小さな成功体験を積ませて自信を回復させる方法が効果的であると報告されています。
また、支援終了後のアフターケアや心理的なサポートの継続も、就労の継続につながっているのです。
ニートの状態から脱するためには、若者一人ひとりの状況を丁寧に見極め、無理のないペースで社会との接点を持たせていく点が求められています。
参考:厚生労働省「ニートの状態にある若年者の実態および支援策に関する調査研究報告書(概要)」
ニートの親ができる適切な対処方法
ニートの子どもを持つ親に求められるのは、叱責や強制ではなく、理解と共感、本人のペースを尊重した対話と支援です。
子どもがニートになったとき、多くの親は「甘やかしてはいけない」「自立させなければ」と焦り、つい強く接してしまいがちです。
しかし、そのような対応は子どもの不安や自己否定感を強めてしまい、逆効果になる場合があります。
子どもをニートから脱却させるのに時間がかかるケースもありますが、小さな一歩でも前に進めたときには、親も一緒に喜ぶ姿勢が支えになるでしょう。
ニートの親ができる適切な対処方法8つについて、それぞれ解説します。
- いきなり追い出さずに話をよく聞く
- 親の価値観を押し付けない
- 本人のペースに合わせる
- 日常の挨拶や小さな会話を大切にする
- 過去の出来事を掘り返さず今と未来に目を向ける
- 情報は押し付けずに選択肢として提示する
- 第三者の支援を活用する
- 本人が動き出したときは小さな一歩を喜ぶ
いきなり追い出さずに話をよく聞く
ニートの子どもに対して「もう出て行きなさい」「甘えるな」と感情的に追い詰めるような言葉をかける親もいますが、このような対応は逆効果です。
突然の強制的な追い出しは子どもの心を深く傷つけ、家族との信頼関係を断絶させる可能性があります。
まずは冷静になり、本人がなぜニートになったのか、何に悩んでどのような思いを抱えているのかを聞くことに集中しましょう。
話を聞く際に重要なのは「否定しないこと」「評価しないこと」「途中で遮らずに聞くこと」です。
親が「あなたの話を大切に聞きたい」と思っている姿勢を見せると、子どもの安心感や信頼が少しずつ育っていきます。
無理に解決策を提示する必要はなく「分かろうとしてくれている」という気持ちこそが、再出発への第一歩となります。
親の価値観を押し付けない
ニートの子どもに対して「自分の若い頃はこうだった」「就職するときは正社員になるべき」など、親の価値観をそのまま押し付けると、子どもにとって大きなプレッシャーとなり逆効果です。
近年、社会状況や働き方、生き方は大きく変化しており、今の若者が抱える問題も多様化しています。
親の考えを一方的に押し付けるのではなく、子どもの視点に立って「どう思っているの?」「何に困っているの?」と問いかけてみましょう。
価値観の違いを乗り越えるためには、子どもが望む働き方や生活のあり方に耳を傾けるのも大切です。
押しつけではなく、寄り添いながら一緒に考えると、長期的なサポートにつながります。
本人のペースに合わせる
親が「今の状態をすぐに変えよう」とせず、本人のペースでゆっくり進むのを受け入れましょう。
「いつになったら働くの?」「そろそろ動きなさい」という言葉を子どもにかけてしまいがちですが、本人にとっては重荷に感じます。
自分を責めていたり、何とかしなければという気持ちを持っていたりする場合も多く、外からの急かしやプレッシャーは、さらに心を閉ざす原因となります。
そのため「家族と少し会話できた」「家の外に短時間でも出られるようになった」などの小さな行動を前向きに受け止めましょう。決して焦らず、変化を急がないことが重要です。
ペースを尊重すると、子どもが「自分を受け入れられている」と感じます。
小さな進歩を認めつつ子どもの力を信じると、次のステップへの意欲も高まっていきます。
日常の挨拶や小さな会話を大切にする
子どもに大きな変化がなくても、日常の小さなやり取りを大切にしましょう。
「おはよう」「ご飯できたよ」「寒いね」などのちょっとした挨拶や声かけが、子どもの心に安心感をもたらします。
ニート状態にあると、社会から取り残されたような疎外感や強い孤独を抱えやすくなります。
そのため、日常の中で「自分は大切に思われている」と実感できる小さなつながりがとても重要です。
子どもから返事がなかったとしても、毎日少しずつ声をかけ続けましょう。無理に深い話をしようとせず、自然な会話を繰り返すうちに、少しずつ心の距離が縮まっていきます。
また、笑顔や穏やかな声のトーンを親が意識すると、家庭内の雰囲気が柔らかくなります。さりげない日常の声かけが、子どもの心を支える確かな力になるでしょう。
過去の出来事を掘り返さず今と未来に目を向ける
「どうして仕事を辞めたの?」「あのときもっと頑張っていれば…」など、過去の出来事を責めたり、繰り返し指摘したりすると、本人にとって大きなストレスとなり、自信を奪う原因になります。
ニート状態にある若者の多くは、過去の経験に対してすでに後悔や自責の念を持っており、それを蒸し返されると逆効果になって、心の負担を増すだけです。
そのため「今どうしたいのか」「これからどうなりたいか」という未来志向の姿勢を持つことが大切です。
「これからできることを一緒に考えよう」「手伝えることがあれば言ってね」などの前向きな言葉をかけると、本人の気持ちを尊重しながら支えられます。
過去の失敗や選択を何度も責めるのではなく「今ここから始めよう」という意識で関われば、本人の自立を後押しできます。
情報は押し付けずに選択肢として提示する
親が支援機関や就労支援サービス、地域の相談窓口などの情報を調べたり訪問したりしても「ここに行きなさい」「これを使いなさい」と一方的に押し付けるのは避けるべきです。
本人の立場からすれば「また命令された」と感じ、反発心や無力感につながる可能性があるため逆効果です。
「こういう支援機関があるみたいだけど、興味ある?」「資料だけ置いておくね」など、強制ではなく選択肢として提示しましょう。
情報を渡すこと自体は良い方法ですが、判断は本人に委ねることが重要です。
親は「きっかけの提供者」に徹して、本人の主体性を尊重する姿勢を示しましょう。
就職支援サービス「就職カレッジ®」のURLをLINEでシェアしよう
第三者の支援を活用する
親子だけでニートの問題を解決しようとすると、どうしても感情がぶつかり合って逆効果になったり、行き詰まりを感じたりするケースがあります。
その場合は、第三者の支援を取り入れるのが望ましい選択です。
例えば、地域にあるハローワークや若者サポートステーションなど、専門的な知識と経験を持つ支援機関に相談すると、悩みを抱え込まずに済みます。
また、第三者が関わると、本人が素直に耳を傾けられたり、今後のヒントにつながる気づきが得られたりする場合があります。
家族だけで抱え込まずに信頼できる専門家の力を借りながら、無理なく一歩ずつ前進できる環境を整えていきましょう。
本人が動き出したときは小さな一歩を喜ぶ
ニートの子どもが何かしらの行動を起こしたときは、その一歩を心から喜んで受け止めましょう。
例えば、家族とのちょっとした会話や近所への買い物、求人情報を少し見てみるなどの行動は大切な前進です。
そのときに「たったそれだけ?」と否定的に捉えるのではなく「よくやったね」「すごいね」「嬉しいよ」と肯定的な言葉をかけると、本人の自己肯定感が高まります。
小さな成功体験の積み重ねは、やがて大きな変化へとつながっていきます。
ニートを脱する過程では、目に見える進歩がゆっくりな場合があるため、親は焦らずに本人の歩調に合わせて見守る姿勢が大切です。
子どもの小さな一歩を大切に受け止め、温かく認め続けると、前へ進む力につながります。
ニートの親が頼れる公的な支援機関5選
ニートの子どもを持つ場合、親子だけで抱え込まずに公的な支援機関を活用すると専門的なサポートを受けられます。
子どもがニートになったとき、親だけで解決しようとすると心身の負担が大きくなるうえ、親子関係が悪化して逆効果になるケースも少なくありません。
そのようなときに頼れるのが、公的に整備された支援機関です。
専門的な知識を持つ職員が相談に応じてくれるため、親も安心して対応でき、子どもにとっても客観的で受け入れやすい環境が整います。
本章では、代表的な5つの公的な支援機関について、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。
- 地域若者サポートステーション(サポステ)
- ハローワーク
- ジョブカフェ
- ひきこもり地域支援センター
- 生活困窮者自立支援制度
地域若者サポートステーション(サポステ)
地域若者サポートステーション(サポステ)は、働くことに悩みを抱える15歳から49歳の方を対象とした就労支援機関です。
全国各地に設置されており、職業相談や職場体験、職業訓練の紹介、コミュニケーション能力を高める講座など、多彩なプログラムを提供しています。
大きな特徴は、保護者が同伴して相談できる点です。本人が支援機関へ行くのに抵抗を感じる場合でも、親が一緒に同行すると安心感を得やすくなるでしょう。
サポステでは、キャリアコンサルタントや臨床心理士などの専門的なスタッフが在籍しており、一人ひとりの課題に応じた支援を行います。
例えば「人と話すのが苦手」「どの職場でも長続きしなかった」などの悩みを共有し、解決の糸口を探す場としても有効です。
親にとっても、子どもをどのように支えたらよいかを学べる貴重な機関といえるでしょう。
ハローワーク
ハローワークは、誰もが知る公共職業安定所です。求人紹介や雇用保険の手続きだけでなく、キャリア相談や職業訓練の案内など、幅広いサービスを提供しているのが特徴です。
ニートの若者にとって、社会とつながるための最初の窓口として重要な役割を果たしています。
求職活動を始めたいが、何から取り組めばいいか分からない方に対して、専門の相談員がマンツーマンでサポートしてくれる点が心強いといえるでしょう。
履歴書や職務経歴書の添削や、模擬面接などの実践的なプログラムも充実しており、初めて就職活動に挑戦する方でも安心して利用できます。
親が同行するのも可能なため、本人の不安を和らげると同時に親が現状を理解しやすくなります。
ニートからの脱却に向けた最初の一歩として、ハローワークは欠かせない存在です。
参考:厚生労働省 ハローワーク
ジョブカフェ
ジョブカフェは、都道府県ごとに設置された若者向けの就職支援施設です。就職活動に必要なスキルから、企業紹介まで幅広い支援を行なっています。
キャリアカウンセリングや応募書類のアドバイス、面接練習などの実践的なサポートが受けられるのが魅力です。
また、保護者向けのセミナーも実施されているため「自分だけが苦しんでいるのではない」という安心感を得られます。
ジョブカフェでは職場体験もあり、実際の就業体験を通じて自信を取り戻せます。
「就職したいが、何から始めたらいいか分からない」と悩む若者にとって、ジョブカフェは最初の一歩を踏み出すための実践的なサポートを提供してくれる場所です。
ひきこもり地域支援センター
ひきこもり地域支援センターは、すべての都道府県や指定都市に設置されている行政運営の専門相談窓口です。
社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ支援コーディネーターが対応します。
本人だけでなく親やきょうだいなど、家族からの相談も受け付けており、最初は家族からの相談が入り、その後に本人への支援につながるケースも多くあるのです。
主な支援内容には、電話や来所による相談、居場所の提供、病院・福祉・教育・就労関連機関との連携によるソーシャルサポートが含まれます。
さらに、厚生労働省が運営する「ひきこもりVOICE STATION」というポータルサイトでは、全国の支援機関や相談窓口だけでなく、当事者や家族の声、体験談、イベント情報などが公開されており、情報収集や安心感の醸成に役立ちます。
参考:
厚生労働省 ひきこもり支援センター「全国の相談窓口はこちら」
生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困難な方を対象に、生活と就労の両面から包括的に支援する制度です。
就労準備支援事業では、すぐに働くのが難しい人に対し、個別の就労支援プログラムに基づいて、基礎的な能力の向上をサポートします。
また、住居確保給付金によって、一定期間の家賃相当分を支給してもらえる仕組みもあり、経済的に追い詰められた家庭にとって大きな支援となります。
生活困窮者自立支援制度を利用して生活基盤を守りつつ、就労に向けたステップを踏むことが可能です。
区町村の窓口で相談できるため、親が主体となって申請すると家族全体の安定が図れます。
生活困窮者自立支援制度は、生活の再建と自立を目指す包括的な制度として、知っておく価値がある支援策です。
「ニートを追い出すと逆効果?」に関するよくある質問
「ニートを追い出すと逆効果?」に関するよくある質問をまとめました。
ニートの子どもを抱える家庭では「思い切って追い出すべきか」と悩む親は少なくありません。
本章では、親が取るべき現実的な対応策を解説しているため、ぜひ参考にしてください。
ニートを追い出して成功した家庭もあると聞いたが?
「ニートの子どもを追い出したら就職した」「自立した」という成功体験を耳にする場合もありますが、それはあくまで一部のケースに過ぎません。
追い出すという行為は、本人にとっては「強制」や「見放し」と受け止められるリスクが高く、むしろ心を閉ざしてしまうケースが多いのです。
特にメンタルに不安を抱えているケースや、人間関係にトラウマを持つ場合には、逆効果になる可能性があります。
ニートを追い出して成功したのは、本人がある程度自立の準備をしていたり、支援機関や親のサポートが整っていたりする場合がほとんどです。
したがって、単純に「ニートを追い出せば解決する」と考えるのは危険です。むしろ「支援をどのように活用して、一緒にステップを踏めるか」が成功につながる方法です。
子どもがニートになったのは親のせい?
子どもがニートになると「自分たちの育て方が悪かったのでは」と悩む親は多くいます。
しかし、ニートになる原因は家庭環境だけではなく、学校でのいじめや職場での挫折、社会構造や雇用環境の変化など、複数の要因が絡み合っています。
そのため、親だけに責任を押し付けるのは適切ではありません。
むしろ大切なのは「今、どのように対応するか」です。親が罪悪感を抱いて過度に干渉したり、逆に突き放したりすると逆効果になり、本人の回復を妨げる場合があります。
親ができることは「あなたを理解したい」という姿勢を持ち、支援機関と連携しながら本人が安心して動き出せる環境を整えることです。
親が責任を感じすぎるのではなく、現実的な対応を選ぶと解決につながります。
何歳まで親が面倒を見るべき?
「何歳まで親が支えるべきか」という問いには明確な答えはありませんが、経済的かつ精神的にも無期限に支え続けるのは、親子双方にとって負担になります。
30代や40代になってもニート状態が続くと、親の高齢化や介護問題が重なり、家庭全体が破綻しかねません。
そのため、重要なのは「期限を決めて準備を進めること」です。
例えば「1年後までに支援機関へ相談する」「半年以内にアルバイトを探す」など、現実的な目標を設定しましょう。
親が一方的に面倒を見続けるのではなく、第三者の支援を活用しながら徐々に自立を促すのが理想です。
親が無期限に面倒を見るのは本人のためにもならないため、早めに外部の力を借りて負担を分散するのがおすすめです。
ニートを追い出す「準備期間」を設けるのは有効?
追い出すことを考える際に、いきなりではなく準備期間を設けるのは有効な方法です。
本人に対して「◯ヶ月後には自立を目指そう」と伝え、その間に必要な支援や情報を提供していくと、無理のない形で自立への道が整います。
準備期間中に支援機関へ相談したり、生活リズムを整えたりなどのステップを踏むと、大きな負担を感じさせずにニートから抜け出せます。
重要なのは、親が一方的に期限を押し付けるのではなく、本人と話し合って決定することです。
このプロセスがあると「親から追い出された」という感情が減り「自分で決めた」という主体的な気持ちにつながります。
「支援機関に相談する」と言っても本人が拒否する場合は?
ニートの本人が「支援機関へ行きたくない」「関わりたくない」と拒否するのはよくあることです。その場合、子どもを無理に連れて行くのは逆効果です。
まずは親だけで相談に行き、情報収集から始めましょう。支援機関の担当者とつながりを持ちつつ、本人に合った支援の形を探していくのが大切です。
支援機関によっては家庭訪問や電話相談など、本人が出向かなくても関われる方法を提供している場合があります。
親が「こんな所があるみたい」「無理に行かなくてもいいけど、話だけ聞いてみる?」と選択肢を示すと、本人の抵抗感が和らぐかもしれません。
最初は拒否しても、時間をかけて少しずつ関心を持ち始めるケースも多いため、焦らず継続することが重要です。
ニートになって10年以上経つけど、まだ間に合う?
「子どもがニートになって10年以上経つので、今さら遅いのでは」と不安を抱く親は少なくありません。
しかし、ニートの状態が10年以上続いていても、支援を受けて社会復帰した事例はあります。
確かに、年齢を重ねるほど難しさは増しますが、決して手遅れではありません。
地域若者サポートステーション(サポステ)では「通学や就業していない期間が10年以上ですが、大丈夫ですか」という問いに対して「ご安心ください!」と回答しています。
サポステ利用者の約半数はブランク期間が2年以上あり、多くの方が新しい道を歩み始めているのです。
「遅すぎる」という思い込みを手放し、公的な支援を取り入れると、本人の可能性を広げるきっかけになるでしょう。
家族が暴言や暴力を受けるようになった場合は?
子どものニート状態が続く中で、家族に暴言や暴力が向けられるケースもあります。
この場合、家庭内だけで解決しようとせず、速やかに外部の支援を求めましょう。
暴言や暴力が続く環境では、家族や本人の安全が守られず、解決につながりません。
まずは地域の相談窓口や警察などに連絡し、安全を確保することが最優先です。
その上で、精神科や心療内科などの専門医療を頼るのも効果的です。
親だけで抱え込まず、第三者を介して問題に対処すれば、家族の安全と本人の回復の両方を目指せます。
暴言や暴力は甘えではなく深刻なサインであるため、早めの介入が必要です。
まとめ
ニートを無理に追い出すのは多くの場合で逆効果となり、状況をさらに悪化させる原因になり得ます。
本記事では、ニートの子どもを追い出すリスクとして「親子の信頼関係の崩壊」「社会的な孤立」「生活力の不足による困窮」「精神状態の悪化」「支援機関との接点の喪失」「親自身の後悔」などを詳しく解説しました。
ニートを根本的に解決するためには子どもの背景を理解し、安心できる関係を築きましょう。
そのため、強制ではなく寄り添いや対話を通じた段階的なサポートが効果的です。
また、サポステやハローワークなどの支援機関を活用すれば、本人の自立を無理なく促せます。
「追い出す」という短絡的な行動よりも、信頼と支援を軸にしながら関わると、子どもが前向きに社会と関わる第一歩につながるでしょう。