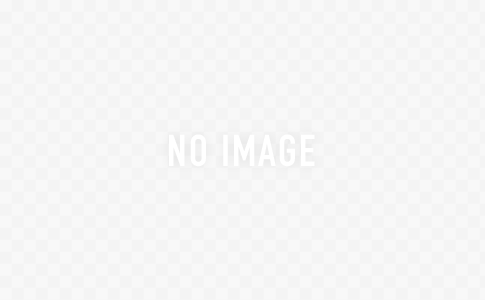第二新卒は社会人経験がある一方、既卒は正社員経験がない人を指すことが一般的なため、両者の大きな違いは「就職経験の有無」といえます。
第二新卒は「即戦力の若手を求める会社」への就職で、既卒は「長期的に人材を育てたい会社」への就職で有利になるケースが多いでしょう。
この記事では、第二新卒と既卒の違いを解説するとともに、それぞれのメリット・デメリットも紹介します。
第二新卒と既卒の違いを詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
第二新卒と既卒の違い
第二新卒と既卒の大きな違いは「就職経験があるかどうか」です。
第二新卒は、新卒で入社した会社を3年以内で辞めて、または辞めることを考えていて転職活動をしている人を指すことが一般的です。つまり第二新卒の場合、会社などで働いた経験があります。
既卒は、学校を卒業後、一度も正社員として働いたことがない人を指すことが一般的です。
違いをまとめると、以下の通りです。
| 第二新卒 | 既卒 | |
| 社会人経験 | あり(就職後3年以内) | なし |
| 正社員経験 | 正社員経験がない人もいる(派遣や契約社員でも第二新卒とされる) | なし |
| 主な特徴 | 新卒で入社した会社を短期間で辞めて転職活動中(または在職中に転職活動をしている) | 学校を卒業後、一度も正社員として働いたことがない |
第二新卒とは
一般に「第二新卒」とは、卒業後に入社した会社を3年以内に辞めて転職を考えている人を指す言葉です。
社会人として数年働いた経験があるため、基本的なビジネスマナーが身についている点に良い印象を持たれる傾向があります。一方で、継続性や忍耐力の面で不安視されることも少なくありません。
厚生労働省の調査を踏まえると、第二新卒の割合は約30%と考えられます(※1)。
5割以上の企業が第二新卒採用を実施しており、8割以上の企業が今後の採用に前向きというデータもあるため、多くの企業が第二新卒を好意的に受け止めていることも分かります(※2)。
※1 出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
※2 出典:マイナビ キャリアリサーチLab「企業人材ニーズ調査2024年版」
企業が第二新卒に抱く印象
第二新卒は「社会人経験はあるものの、定着性には不安がある人材」として見られることが多いため、ある程度の基礎力があることを評価される一方、すぐに辞めるのでは?という印象を持たれがちです。
第二新卒は、電話や来客の対応など、基本的なビジネスマナーを身につけています。そのため、既卒との違いとして「教育コストがかからない」という点をメリットと考える企業が多いのです。
ただし会社を短期間で辞めていることから、「またすぐ辞めてしまうのでは?」という不安を持たれることもあります。
このように第二新卒は、社会人の基礎力がある点でプラスに評価される反面、定着性への不安という点でマイナスの印象を持たれることがあるのです。
第二新卒の割合
新卒で入社した人のうち、およそ3分の1が3年以内に会社を辞めているため、第二新卒の割合は3割ほどと考えられます。
厚生労働省の調査によると、令和3年3月に卒業した新卒者の「就職後3年以内の離職率」は以下の通りです。
新規大卒就職者:34.9%
新規高卒就職者:38.4%
つまり、大卒では3割強、高卒では4割弱の人が、最初に入った会社を3年以内に辞めていることになります。
なお、第二新卒は「転職を考えている人」を指す言葉ですが、会社を退職した人全員が転職活動をしているわけではありません。そのため、上記の離職率のデータからは割合が少しだけ下がることが予想されるため、第二新卒の割合は30%程度といえそうです。
出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
第二新卒を採用する企業の割合
マイナビ キャリアリサーチLabの「企業人材ニーズ調査2024年版」によると、第二新卒採用を実施している企業は52.6%のため、2社に1社以上が第二新卒の採用に積極的であることが分かります。
また、同調査によると「第二新卒採用を予定している」と答えた企業が8割以上にのぼるため、多くの企業が第二新卒の採用に前向きであることが伺えます。
なお、第二新卒に対して“よいイメージ”を持っていると答えた企業は74.7%で、「やる気がある」「適応しやすい」といった点を評価しているようです。
このように5〜8割もの企業が第二新卒に注目しているため、転職を検討している若手社会人にとってはプラスの状況といえるでしょう。
出典:マイナビ キャリアリサーチLab「企業人材ニーズ調査2024年版」
既卒とは
一般に「既卒」とは、学校を卒業後に正社員として就職した経験がない人を指す言葉です。
社会に染まっていないため柔軟性が評価される一方で、「就職していないのは本人に何か問題があるからでは?」と思われることもあります。特にこの点は、社会人経験がある第二新卒との違いといえるでしょう。
既卒の内定率(就職率)はおよそ5割ですが、新卒の約9割と比べると大きな差があることも特徴です(※1)。
なお既卒者が「新卒枠」で応募できる企業も多く、実際のところ、およそ2社に1社が既卒者を「新卒枠」で受け入れる予定があるというデータもあります(※2)。
※1 出典:株式会社マイナビ「2024年度既卒者の就職活動に関する調査(12)現在内定を保有していますか。<既卒者の現在の内定率>2024年9月時点」p.12
※2 出典:株式会社マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について」p.126
企業が既卒に抱く印象
既卒は正社員として働いたことがないため、社会に染まっていない点を評価される一方で、アルバイト生活などが続いていることを不安に思う企業もあります。
社会人経験があると転職先の文化やルールの違いに馴染めず、早期退職してしまう人もいます。こうした短期離職者に苦労している企業も多いため、正社員経験のない既卒は「自社の文化を柔軟に吸収してくれそう」と期待されやすいのです。
ただし、正社員として就職していないことを「何か問題があるのでは」と不安に思われることもあり、この点では仕事経験がある第二新卒のほうが有利ともいえます。
このように既卒は、柔軟性や素直さをプラスに評価される一方で、就職していないことをマイナスに捉えられることもあるのです。
既卒の就職率
既卒の内定率は49.3%のため、就職率はおよそ5割と考えられます。
マイナビの調査によると、2024年に大学・大学院を卒業した既卒者の内定率は、2024年9月時点で49.3%でした。
約2人に1人が内定を手にしているという状況は、一見するとそれほど悪くないように思えるかもしれません。しかし、同時期の2025年卒予定の新卒学生の内定率は89.8%のため、既卒と新卒の内定率にはおよそ40ポイントもの差があります。
このことから、既卒の就職活動は新卒よりも厳しい状況であることが分かります。実際、新卒に比べて既卒は選考で不利になりやすいため、既卒者が内定を獲得するには新卒以上の選考対策が必要といえるでしょう。
出典:株式会社マイナビ「2024年度既卒者の就職活動に関する調査(12)現在内定を保有していますか。<既卒者の現在の内定率>」p.12
既卒を「新卒」として採用する企業の割合
マイナビの「2026年卒 企業新卒採用予定調査」によると、5割以上の企業が既卒者を「新卒枠」で受け入れる予定があるとしています。
具体的には、2025年卒で53.4%、2026年卒で53.2%となっており、特に上場企業のほうが非上場企業よりも既卒の採用に積極的な傾向が見られます。
既卒と新卒は厳密には異なりますが、「社会人経験がない」「年齢が若い」という点では共通しています。そのため、本来は“学校卒業予定の在学者”を対象とする新卒採用において、既卒者も同じ枠で受け入れる企業が多いのです。
実際、上記のデータからも分かる通り、およそ2社に1社が既卒者を新卒として採用する体制をとっていることが分かります。
出典:株式会社マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について」p.126
第二新卒と既卒はどちらが有利?
第二新卒と既卒のどちらが有利かは状況によりますが、第二新卒は「即戦力の若手を求める会社」、既卒は「長期的に人材を育てたい会社」への就職で有利になることが多い、という点に違いは見られます。
第二新卒は社会人経験があり、入社後すぐに仕事を任せられるため、教育に時間やコストをかけられないベンチャーや中小企業では第二新卒の採用が活発です。
既卒は正社員経験がないぶん、どの会社の色にも染まっていません。そのため年功序列の風土が残る大手製造業や、老舗の小売業など、社員を一から育てて自社のやり方を浸透させたい会社では既卒の採用が活発です。
第二新卒が就職に有利なケース
第二新卒は「社会人の基礎を身につけた10代後半〜20代前半」として評価されることが多いため、即戦力の若手を求める会社への就職では特に有利になります。
たとえば急成長中のベンチャー企業では、多くの場合、新卒社員を一から教育する時間やコストをかけられません。人手不足に悩む多くの優良中小企業も、「若手社員に現場ですぐに活躍してほしい」と考えています。
そのためこうした企業では、電話応対や名刺交換などの基本マナーや、営業・事務などの業務経験を多少積んでおり、仕事の進め方を理解している第二新卒は“理想的な人材”として評価されるのです。
既卒が就職に有利なケース
既卒は柔軟性を評価されることが多いため、長期的な視点で人材を育てたい会社への就職で有利になります。
大手の製造業は年功序列の風土が残っていることが多く、「会社独自のやり方を一から丁寧に教えたい」という理由から、社会人経験がない既卒を採用する傾向が見られます。
老舗の小売業でも、「お客様第一の接客スタイルを基礎から身につけてもらいたい」という考えから、前職の習慣に縛られない既卒者を歓迎するケースが少なくありません。
このように、即戦力として働ける点が重視される第二新卒とは違い、既卒は長期的な育成を考えている企業から評価されやすいのです。
第二新卒のメリット・デメリット
第二新卒は社会人経験があるため企業から評価されやすく、新卒で落ちた会社にもう一度挑戦できる点もメリットです。一方で短期離職という事実を不安視され、研修を手厚く受けられない可能性がある点はデメリットといえます。
第二新卒は仕事経験を積んでいるため、教育コストを抑えられます。「実務経験」を武器に、新卒時には手が届かなかった会社に入社できる可能性もあるでしょう。
ただし「また辞めるのでは?」と思われ、継続性の面で不安を持たれるケースも少なくありません。十分な研修を受けられず、すぐに現場で働く可能性がある点も理解しておく必要があります。
メリット1. 社会人の基礎スキルが身についている
第二新卒は社会人経験があるため、基本的なビジネスマナーを身につけている点が既卒との違いであり、大きなメリットといえます。
電話応対で適切な敬語を使えたり、来客時に正しく名刺交換ができたりする人も多いでしょう。ExcelやWordの基本操作、請求書の処理、報告書の書き方などもある程度理解していることも多く、知らないうちに多くの知識やスキルが身についているものです。
こうしたことを一から教えるには時間と労力が必要ですが、第二新卒はすでに基礎ができているため、「教育コストを大幅に削減できる」という点で魅力に感じる企業が多いのです。
メリット2. 就活で落ちた会社に再挑戦できる場合がある
第二新卒は仕事経験を積んでいるため、新卒採用で不合格だった会社にもう一度挑戦できる可能性もあります。
たとえば新卒時は大手金融機関の選考に落ちた場合でも、営業として働いた経験があれば「営業の中途採用枠」で採用してもらえるケースも考えられます。
新卒時には仕事のイメージが湧かず、志望動機が曖昧になってしまった大手IT企業でも、別のIT会社で働いた経験があれば、その経験をもとに具体的な志望動機を話せるでしょう。
このように第二新卒は「実務経験」という武器を活かし、学生時代には届かなかった理想の会社に再び挑戦できることもあるのです。
デメリット1. すぐに辞めるのでは?と不安視される
第二新卒は短期間で会社を辞めた経歴があるため、「うちの会社でも長続きしないのでは?」という不安を持たれがちです。
企業は従業員1人を採用するにあたり、数十万円以上の費用をかけることが一般的です。そしてその費用を“先行投資”と考え、長く働いてもらうことで売上や業績に還元してくれることを期待しています。
その点、入社後すぐに会社を辞めた第二新卒は「採用にかけたコストが無駄になるのでは?」という不安を持たれることが少なくありません。
このように「すぐ辞めるのでは?」と思われ、評価が下がる恐れがあることは第二新卒のデメリットといえるのです。
デメリット2. 研修を手厚く受けられない可能性がある
第二新卒は「社会人の基礎知識がある」と判断されるため、新卒枠に応募できる既卒と違い、研修プログラムを手厚く受けられない場合がある点はデメリットといえます。
新卒であれば、ビジネスマナー研修や、職場や工場での仕事体験など、1ヶ月以上かけて研修を行うケースが一般的です。
一方、第二新卒は会社説明だけを簡単に済まされ、配属部署での業務がすぐに始まることも珍しくありません。
本人としては「ビジネスマナーに自信がない…」と感じていても、その気持ちとは裏腹に十分な教育機会が用意されない可能性がある点はデメリットといえるでしょう。
既卒のメリット・デメリット
企業によっては新卒枠に応募でき、ポテンシャルを評価されやすいことが既卒のメリットです。一方で空白期間の長さを不安視され、中途枠でしか応募できない場合があることはデメリットといえます。
卒業後3年以内であれば、多くの企業が新卒と同じ選考ルートで既卒を受け入れています。成長性などが評価されれば、専門スキルがなくても採用されやすい点も既卒の強みです。
ただし「就職意欲が低いのでは?」とマイナス評価を受ける可能性がある点には注意が必要です。中途枠でしか応募できない企業では、実務経験が豊富な求職者がライバルとなることも理解しておきましょう。
メリット1. 企業によっては新卒枠で応募できる
企業は「卒業後少なくとも3年以内の人」を新卒として扱うよう求められているため、新卒採用枠で応募できる可能性があるのは既卒のメリットです(※1)。
実際、53.2%の企業が既卒者を新卒として採用すると回答しています(※2)。
新卒枠で応募できる主な利点は、以下の通りです。
- 仕事経験がなくても採用される
- 入社後に手厚い研修を受けられる場合がある
- 将来の「幹部候補」として育成を受けられる可能性がある
基本的には中途枠での応募となる第二新卒とは違い、企業によっては新卒枠で選考に臨めることは既卒のメリットといえるでしょう。
※1 出典:厚生労働省「3年以内既卒者は 新卒枠で応募受付を!!」
※2 出典:株式会社マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について(26年卒)」p.126
メリット2. ポテンシャルを評価されやすい
既卒は特定の企業文化や働き方に染まっておらず、企業の教育方針や風土を素直に吸収してくれるはずという期待も大きいため、ポテンシャルを重視して採用している会社では高く評価される傾向があります。
特に、自社の文化や業務の進め方を一から覚えてほしいと考えている企業では、現時点での完成度よりも「素直に学ぶ姿勢」や「成長意欲」といったポテンシャルを重視する傾向にあります。
そしてこうしたポテンシャルは、学生時代のサークルや学業、アルバイト経験などでもアピールできるため、正社員経験がなくても採用される可能性が十分にあるのです。
デメリット1. 空白期間がマイナス評価を受けることがある
既卒は卒業後に正社員として働いていない期間があるため、採用担当者から「本人に何か問題があるのでは?」と疑われることがあります。
たとえば卒業後に1年間フリーター生活を送っていた場合、「働く意欲が低いのでは」という印象を持たれる可能性もあるでしょう。
就職活動が長引いている場合は、「コミュニケーション力などに問題があるのでは」と思われてしまうこともあるかもしれません。
このように空白期間がマイナス評価を受けることがあり、特に半年~1年以上など、正社員として働いていない期間が長くなるほど就活で不利な立場になることは理解しておきましょう。
デメリット2. 中途枠でしか応募できない場合がある
企業によっては既卒を新卒として扱っていないため、たとえ学校を卒業してすぐのタイミングでも、社会人経験が豊富な求職者と同じ土俵で内定を目指さなくてはならない場面もあります。
先ほど「53.2%の企業が既卒者を新卒として採用する」というデータを紹介しましたが、同調査では19.5%の企業が中途枠で既卒を受け入れる予定と回答しており、全ての企業が新卒枠で受け入れているわけではありません(※)。
中途採用では実務経験や専門スキルが重視されるため、正社員経験がないと選考で不利になる可能性が高いことも既卒のデメリットといえるでしょう。
※出典:株式会社マイナビ「2026年卒企業新卒採用予定調査|既卒者採用について(26年卒)」p.126
第二新卒の転職のポイント
第二新卒が転職を成功させるには、これまでの仕事経験を振り返ること、そして退職理由を前向きに伝える準備をしておくことが欠かせません。
たとえ半年間であっても、実際には自分が思う以上に多くの経験を積んでいるものです。営業で顧客対応に苦労した経験や、事務職で新しい業務を覚えるために工夫を重ねた経験などは、転職活動でアピールできる立派な強みになります。
「職場に嫌気が差した」「仕事がつまらなかった」といったネガティブな退職理由を伝えると評価が下がる恐れがあるので、ポジティブな表現に変換して伝えることも意識しましょう。
仕事で得た経験・スキルを棚卸しする
自分としては大したことがないように思えても、既卒とは違い、第二新卒はアピールできる実務経験が意外に多いため、まずは自分が身につけたスキルや成果を整理しておきましょう。
たとえば営業職の場合、自分なりに顧客情報を収集したり、クロージングにつなげる話し方を工夫したりした経験があるかもしれません。
事務職であれば、「Excelの関数を覚えてデータ集計を効率化した」といった経験も立派なアピール材料になります。
転職活動で効果的な自己PRを行うためにも、仕事を通じて得た経験やスキルはしっかりと棚卸ししておきましょう。
退職理由を前向きに伝える準備をする
第二新卒は「短期間で会社を辞めた理由」を面接で聞かれるため、たとえネガティブな退職理由であっても“前向きな理由”として伝える準備をしておくことが大切です。
たとえば「興味がない営業職に配属されて不満だった」という理由が本心の場合、これをそのまま面接で伝えると「わがままな人」という印象を持たれる可能性があります。
しかし、以下のように伝えることでネガティブな印象を与えず、むしろ成長意欲が高い人として評価されるでしょう。
| 短い期間ながら、前職の営業職では顧客ニーズを理解する重要性を学びました。その中で、顧客理解が特に求められる企画職に興味を持つようになりましたが、前職では異動に3年程度かかることが分かったため、転職を決意いたしました。 |
このように、退職理由は前向きな表現で話すことを意識してみてください。
既卒の就活のポイント
既卒が就活を成功させるには、「就職しなかった理由」や「空白期間の過ごし方」を説明できるように準備しておくことが大切です。
「就職しなかった理由」は嘘をつかずに正直に話し、反省点などを踏まえて前向きな姿勢を示しましょう。
「空白期間の過ごし方」を伝える際は、成長や学びにつながった期間であることが伝わる表現を心がけることが重要です。
既卒は第二新卒とは違い、仕事のスキルは十分にアピールできません。一方で、素直さや成長意欲などは既卒の武器ともいえるので、まずはこれらの強みをしっかりとアピールできるように準備しておきましょう。
就職しなかった理由を説明できるようにする
既卒は「就職しなかった理由」を面接で聞かれることが多いため、正直かつ前向きな姿勢が伝わる説明を用意しておきましょう。
たとえば内定が取れずに卒業した場合は、「就活がうまくいかなかった」と素直に伝えつつ、次のような前向きな言葉で補足するのも一つの手です。
| なんとなく大手企業だけを受けており、就活の軸がぶれていたことを反省しています。卒業後は自己分析を徹底的に行い、「協調性を活かせる仕事に就く」という軸のもと就職活動をしております。 |
正直かつ前向きな姿勢は高く評価されるので、「就職しなかった理由」を聞かれた際はぜひ意識してみてください。
空白期間をポジティブに伝える準備をする
「何もしていなかった」という印象を面接官に与えると評価が下がるため、既卒の空白期間(正社員として働いていない期間)は“成長や学びの期間”として伝えるのがおすすめです。
たとえばアルバイトを掛け持ちしていた場合、「とりあえずお金を手にする必要があったのでアルバイトをしていました」とだけ伝えると、就職への意欲などはそこまで感じられません。
一方で、以下のように伝えるとポジティブな印象を与えられるでしょう。
| 大学卒業から現在までの1年間、飲食店とコンビニ、イベントスタッフのアルバイトを掛け持ちしています。自分が休むと周囲に迷惑がかかるため、スケジュール管理を徹底したことで一度も欠勤がなく、計画性も身につけることができました。 |
空白期間は決して無駄な時間ではなく、「自分を成長させる時間だった」と伝えられるように準備しておきましょう。
まとめ
第二新卒と既卒はどちらも10代後半〜20代の若手人材を指す言葉ですが、厳密には以下の点に違いがあります。
第二新卒:卒業後に入社した会社を3年以内に辞めて転職を考えている人
既卒:学校を卒業後に正社員として就職した経験がない人
今回の記事を参考に、自分自身が社会からどう評価されているかを正確に理解しておきましょう。