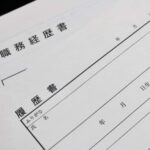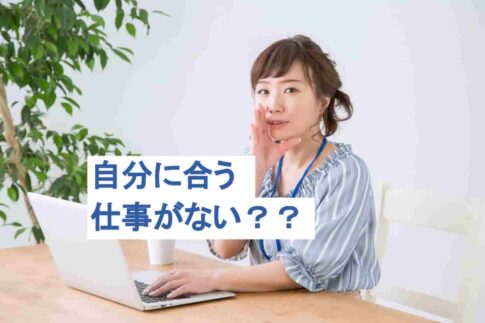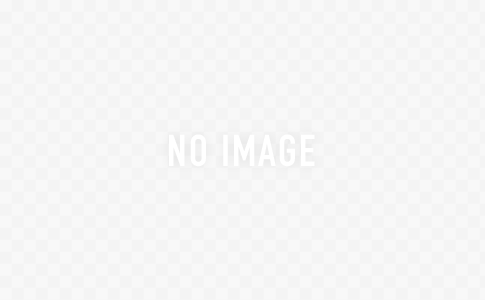「既卒者が仕事を見つける方法が知りたい」
「既卒者から正社員になるのは難しそう」
「既卒者でも応募できる求人の見つける方法が知りたい」
上記のように既卒者から求人を探しているものの、うまく見つけられない人は多いでしょう。
既卒者であっても適切に行動すれば、就職は可能です。正しい手順かつ、周囲の力を借りることで、スムーズに就活が進められます。
この記事では、既卒者向けに求人の探し方や応募できる企業の特徴について、詳しく解説していきます。
最後まで読めば、既卒者なりの就活の進め方がわかり、納得のいく就活になるでしょう。
この記事の目次
既卒者向けの求人の探し方は?
既卒者向けの求人の探し方は、以下の7つです。
- 既卒者向けの求人サイトで探す
- 新卒向け求人サイトで「既卒応募可」の求人を探す
- 中途向けの求人サイトで「未経験歓迎」の求人を探す
- ハローワークを利用する
- 直接企業のHPから応募する
- 就職課を利用する
- 既卒の就職支援に強いエージェントを利用する
既卒者であっても応募できる求人は存在します。
既卒者=就活に不利と考える人が多いかもしれません。しかし、既卒者向けの求人サイトや就職を支援してくれる仕組み、企業があるので安心してください。
既卒者でも応募できる求人を探し、エントリーすることで内定を獲得できるチャンスはあります。
本章では、既卒者向けの求人の探し方を詳しく解説していくので、参考にしてください。
1. 既卒者向けの求人サイトで探す
既卒者の人は、既卒者向けの求人サイトで探しましょう。
自分の状況に合った求人サイトであり、適切なサービスが受けられるからです。適切なサービスとは、既卒者やフリーターに特化した求人やサポートなどが挙げられます。
さらに、新卒者向け就活サイトとは異なり、年齢や時間のハンデを感じずに就活することが可能です。
また、既卒者向けの求人サイトは、自分のペースで求人検索ができます。アルバイトや趣味など、自分の都合に合わせた就活が可能です。
今すぐ就職したい人は積極的に利用し、長期目線で考えている人は週末だけ利用するなど、使い分けができます。
ただし、企業説明会や面接といったスケジュールは、自分で調整・管理する必要があるので注意してください。
2. 新卒向け求人サイトで「既卒応募可」の求人を探す
新卒向け求人サイトで「既卒応募可」の求人を探すことも有効です。
大手企業や人気企業の新卒採用枠を狙える可能性があります。現在の新卒採用は、新卒に加えて、第二新卒や既卒者を含める傾向にあります。
そのため、新卒向け求人サイトであっても、応募できる企業を見つけることが可能です。
具体的には「既卒」「第二新卒」「卒業後〇年以内」などのキーワードで検索してみましょう。
ただし、既卒応募可の求人数は、新卒求人と比較して少ない傾向にあります。
さらに、新卒向け求人では新卒者がライバルになるため、既卒者は不利になりやすいでしょう。しかし、履歴書・ES作成や面接などは、自分で対策する必要ががあるため、他の方法と併用するのがおすすめです。
3. 中途向けの求人サイトで「未経験歓迎」の求人を探す
中途向けの求人サイトで「未経験歓迎」の求人を探す方法もあります。
中途向けの求人サイトでは、比較的条件が緩く設定されている求人があるからです。たとえば、未経験OKや学歴不問、ポテンシャル採用などです。
「新卒と違って職歴がない」と不安に感じている人でも、問題なくエントリーできます。
他にも、勤務地や休日などの条件に合わせて、自由に求人が探せます。働くにあたって譲れない条件がある人は、積極的に活用しましょう。
中途向けの求人サイトは、既卒者専用ではないためライバルも多く存在します。しかし、既卒者向けの求人サイトと同様に、自分のペースで求人を探したい人には適しています。
4. ハローワークを利用する
ハローワークの利用も視野に入れてください。
ハローワークでは、既卒者向けの求人を無料で探しながら、職業相談や面接対策の支援も受けられるからです。
専門の相談員に履歴書を添削してもらったり、面接指導を受けたりすることで、既卒者であることをカバーできます。
また、ハローワークには地元密着型の求人が多いといった特徴があります。地元から離れたくない人や地元に貢献したい人にとっては、魅力的な企業が見つかるでしょう。
ただし、ハローワークの求人には、離職率が高い求人があります。ハローワーク=自分に合った求人が必ず見つかるわけではありません。
事前に企業の口コミや評判を見たり、相談員からアドバイスをもらったりして、求人情報を見極めましょう。
5. 直接企業のHPから応募する
直接企業のHPから応募することも、既卒求人を探す方法の一つです。
興味のある職種や企業がある人は、自分から問い合わせることで、就職のチャンスが獲得できます。
近年、自社サイトの運営に力を入れている企業が増加しているからです。背景には、応募経路の拡大が考えられます。
そこで、志望職種が明確な人は、企業のHPから応募してみましょう。企業のHPを閲覧することで、企業の経営理念や事業内容を知るきっかけになり、業界研究も兼ねられます。
ただし、企業によっては応募できる求人が少ない可能性があります。さらに、就活サイトと違うため、応募に手間がかかるでしょう。
就活に時間がない人や希望職種が決まっていない人には合わないため、注意してください。
6. 就職課を利用する
既卒であっても就職課を利用することが可能です。
大学によっては、卒業後も就職課の利用を許可している場合があります。OB・OG訪問の紹介や、既卒向けの求人情報が提供されることもあります。
たとえば、東京大学では未就労に限られますが、卒業から1年以内であればキャリア相談を受けることが可能です。他にも、早稲田大学はいくつかの条件を満たすことで、卒業から3年以内の人でも就活支援が受けられます。
大学ごとに受けられるサポート内容に違いがあるため、一度確認してみることをおすすめします。
一方で、大学の就職課は新卒向けの求人が中心です。既卒者向けの求人は少ない可能性があります。他の就職支援サービスと併用しながら、就職に向けて活動していきましょう。
参考:東京大学キャリアサポート室「キャリア相談」
参考:早稲田大学キャリアセンター「卒業生・保護者の方へ」
7. 既卒の就職支援に強いエージェントを利用する
既卒者の方は、既卒の就職支援に強いエージェントを利用することもおすすめです。
既卒者専門あるいは、既卒者への支援実績が豊富な就職エージェントは、個別のカウンセリングを通じて、自分の強みや希望に合った求人を紹介してくれます。
他にも、履歴書・ESの添削や面接対策、企業ごとの情報提供など、手厚いサポートを受けることが可能です。
ただし、エージェントによっては紹介してくれる求人数が少なかったり、相性に問題があったりなどのデメリットもあるでしょう。
ジェイックでは、20代・第二新卒・既卒といった若者向けに就職をサポートしています。また、ジェイックには上記のサポートに加えて、独自の研修が受けられるメリットがあります。
就活で欠かせないビジネスマナーや、コミュニケーション能力を身に付けた状態で選考に挑むことが可能です。
相談は無料なので、興味のある方は一度ジェイックにご相談ください。
既卒から正社員になることは可能
既卒から正社員になることは可能です。
厚生労働省が令和6年の9月に発表した「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」によると、令和5年度に正社員を募集した企業のうち「既卒者は応募可能だった」と回答する割合は72%でした。
さらに「既卒者は応募可能だった」と回答した企業のうち、既卒者の採用にいたった企業は40%です。
上記の調査結果から、既卒者であっても正社員になれる可能性は大いにあるでしょう。
さらに、今後の方針として既卒者からの「応募を可能としたい」と回答する企業は32%、「年齢によっては応募としたい」は13%でした。合計約45%の企業が既卒を受け入れるつもりがあります。一方で「応募不可としたい」と回答した割合は3%です。
とくに医療や建築業界では、既卒や新卒にこだわらない傾向があります。正社員を目指している方は、業界の傾向や事情を把握しておくことで、就活が有利に進められるでしょう。
既卒の求人が多い時期はいつ頃?
既卒の求人が多い時期は、1〜4月と10〜11月頃です。
この時期に多い理由は、春採用や年度末、新年に向けて、採用を活発化させる企業が増加するためです。
一方で、既卒者は中途の扱いになります。新卒一括採用とは異なり、通年採用を実施している企業もあります。
既卒者は、求人数が多くなる時期を待つ必要はなく、就職したいと考えた瞬間から行動し始めることが重要です。
時間が経つと既卒者には空白期間が生まれます。就職において、空白期間が長くなるほど面接官にネガティブな印象を与え、選考が不利です。
求人数が増える時期は参考程度に理解し、自分の置かれている状況を考えて就活しましょう。
既卒でも応募できる企業の特徴
既卒でも応募できる企業の特徴は、以下の3つです。
- 教育制度が整備されている企業
- 人柄やコミュニケーション力が活かせる企業
- ポテンシャルで見てくれる企業
既卒者の採用は、新卒ほど丁寧な研修やサポートが受けられない可能性があります。既卒者は中途扱いとなり、即戦力としてカウントされるからです。
既卒から就職を目指すのであれば、既卒者への支援体制が整っている企業や理解のある企業を選択しましょう。
近年では、既卒者を新卒者と同じように扱う企業が増加しています。厚生労働省が3年以内の既卒者を新卒枠で受け付けるように要請しているからです。
既卒を気にすることなく応募することで、自分の魅力や強みをきちんと評価してくれる企業に出会えるでしょう。
既卒を気にすることなく応募することで、自分の魅力や強みをきちんと評価してくれる企業に出会えるでしょう。
1. 教育制度が整備されている企業
教育制度が整備されている企業は、既卒でも応募できます。
社員を育てる環境と意識があり、既卒者のポテンシャルに期待しているからです。
教育制度とは、ビジネスマナー講座やOJT、メンター制度などです。既卒者を新卒者と同様に考え、最初から育てる仕組みがあるため、既卒者でも活躍できるでしょう。
ただし、研修期間や内容は企業によって異なります。エントリー前もしくは、選考を通じて確認しておきましょう。
もし、教育制度がない企業に就職してしまうと、即戦力としての扱いを受けます。その結果、思うような成果が出せず、仕事のやりがいが感じにくくなる可能性があるため、注意してください。
2. 人柄やコミュニケーション力が活かせる企業
人柄やコミュニケーション力が活かせる企業も、既卒者に向いています。
業界特有の知識や専門スキルが必要なく、早期に活躍できるチャンスがあるからです。
具体的な業界を挙げるなら福祉や人材、教育などです。もちろん、専門資格や知識があれば、活躍の幅は広げられますが、未経験からでも挑戦しやすい業界です。
他にも、職種であれば、営業職や販売職、事務職などが該当します。とくに営業職や販売職は、お客様と直接会話する仕事です。
選考段階ではスキルよりも、人柄やコミュニケーション力が重要視されます。性格や会話スキルに自信がある人は、挑戦してみましょう。
3. ポテンシャルで見てくれる企業
ポテンシャルで見てくれる企業も、既卒者におすすめです。
既卒者をネガティブに捉えておらず、将来への期待度で合否を決めてくれるからです。
既卒になるとポテンシャル採用されないと考える人もいるかもしれません。しかし、既卒でもポテンシャルを重要視する企業はあります。
求人サイトを見ただけでは、ポテンシャル採用かどうかわからない場合は、エージェントを利用してみましょう。エージェントは採用方法や採用基準に詳しいため、貴重な情報が得られます。
ただし、ポテンシャル採用=採用ハードルが低いとは限らないので注意してください。
既卒求人の選び方のポイント
既卒求人を選ぶ際のポイントは、以下の3つです。
- 既卒が応募しやすい業界・職種を選ぶ
- 経験不問・未経験歓迎な企業に応募する
- 大手企業ばかりにこだわない
既卒OKや未経験歓迎の企業に応募することは大切です。
しかし、適当に応募すると就職に失敗する原因につながります。
本章では、既卒求人の選び方のポイントを解説するので参考にしてください。
1. 既卒が応募しやすい業界・職種を選ぶ
まずは、既卒が応募しやすい業界・職種を選びましょう。
育成前提で採用しており、教育制度が整っている可能性が高いからです。
たとえば、飲食業界やサービス業、製造業などが挙げられます。人手不足が深刻化しているため、採用を積極的に進めています。
また、どの企業も独自のノウハウやシステムがあるため、未経験からでも問題なく始めることが可能です。
他にも、営業職や事務職などもおすすめです。ポテンシャルやコミュニケーション力が重要視されるため、既卒でも挑戦しやすい環境になっています。
2. 経験不問・未経験歓迎な企業に応募する
経験不問・未経験歓迎の企業に応募するのも有効です。
選考の段階では、高度な専門スキルや知識が求められていないからです。既卒者のなかには、仕事にはスキルが欠かせないと考えている人もいるでしょう。
しかし、企業の価値観や方針によっては、入社後にスキルを身に付ける前提で採用している場合があります。今までの経験が問われないため、既卒者でも就職できるでしょう。
また、中途採用の求人であっても新卒のように扱う企業もあります。20代のような若者が対象になりますが、応募してみる価値はあるでしょう。
3. 大手企業ばかりにこだわない
既卒求人を選ぶ際に、大手企業ばかりにこだわらないようにしましょう。
大手企業に絞ると、エントリーできる企業数が少なくなり、採用ハードルが高くなるからです。中小企業庁が発表した「中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します」によると、大手企業は全体の0.3%しかありません。
中小企業も視野に入れることで、エントリーできる数が増えます。その結果、大手企業と比較して、低いハードルになる傾向にあり、内定が取りやすくなるでしょう。
知名度は低くても優良な中小企業はあります。自分が認知していないだけの可能性があるため、幅広い企業に目を向けてみましょう。
既卒が内定を取るためのコツ
既卒が内定を取るためのコツは、以下の6つです。
- なるべく早く行動に移す
- 行動量を増やす
- 自分の軸を定める
- 入念に面接対策を行う
- 応募職種と関連のある資格を取る
- 企業が既卒に求めていることを理解する
効率良く内定を取るにはコツが存在します。就活は、全力で行動したからといって最善の結果が得られるとは限りません。
かえって時間と体力、お金を消耗して終わる可能性があります。そこで、本章では既卒者が内定を獲得するためのコツを紹介します。
1. なるべく早く行動に移す
既卒が就職したいとなった場合、なるべく早く行動に移しましょう。
とくに既卒から正社員になりたい人は、少しでも早い時期から就活することが大切です。空白期間が長引くほど、書類選考で落ちたり、面接で深掘り質問されたりするからです。
たとえば、大学を卒業してから2年間のブランクがある場合、企業はきちんと働く意思があるのか不安になります。そこで、新卒と比較して落とされることもあるでしょう。
また、企業によっては、既卒OKと求人に記載があっても期間制限を設けている場合があります。「いつか応募しよう」と考えていると応募対象から外れるかもしれません。
就職を志した既卒者は、できる限り早く就活しましょう。
2. 行動量を増やす
既卒者が内定を獲得するには、行動量を増やすことも大切です。
行動を続けることで、志望企業から内定がもらえる可能性が高くなるからです。
もし、気になる求人を見つけたら積極的に応募しましょう。また、書類選考や面接に落ちてもあきらめず行動し続けてください。
不採用の連絡を受けると落ち込む気持ちは理解できますが、内定を獲得するには応募が欠かせません。
応募以外の行動なら、就活セミナーや企業説明会などがおすすめです。就活のほとんどは一人で行うため、モチベーションを維持・管理するのが大変です。
しかし、自分と同じように活動している人の姿を見ることで、就活のやる気につながります。体調管理にも注意しつつ、積極的に行動しましょう。
3. 自分の軸を定める
就活を始めたら、自分の軸を定めましょう。
軸がないまま就活すると、入社後に後悔するからです。内定の獲得を優先してしまうと、働き始めてから「思っていた業務内容と違う」となりミスマッチが発生します。
また就活は、自分が大切にしている価値観「就活の軸」を明確にすることが重要です。もし、軸がないと入社意欲や仕事への熱意が低く見られます。
そこで、将来のキャリアプランや身に付けたいスキル、挑戦したい業務などを想定しておきましょう。さらに、上記を選択した理由を言語化できていると、自分の発言に説得力が生まれます。
就活の軸がない既卒者の方は、自己分析を徹底しましょう。自分について深く分析することで、譲れない条件や価値観が明らかになります。
4. 入念に面接対策を行う
既卒者は入念に面接対策しましょう。
既卒者は空白期間があるため、面接官に対してポジティブな印象を与える必要があるからです。
既卒者の面接では「なぜ就職しなかったのか」「卒業後は何をしていたか」といった質問がよく聞かれます。面接官が求職者の労働意欲を確認したいからです。
そこで、念入りに面接対策し、面接官に前向きな印象を持ってもらえるようにしましょう。
たとえば、アルバイト経験がある人は、勤務経験が仕事にどう役立つかを説明してください。さらに、正社員を目指す理由や入社後の目標なども伝えられると、面接官にポジティブな印象を持たせることが可能です。
面接が不安な人は、就職エージェントに面接対策を依頼し、何度も練習しておきましょう。
5. 応募職種と関連のある資格を取る
就活は、応募職種と関連のある資格を取ることも有効です。
面接官に対して、入社意欲と即戦力としてのアピールができるからです。
もし、海外企業と取引がある企業に応募した場合、TOEICを勉強しましょう。仕事に英語が必要になるため、自分のスキルを客観的に伝えられます。
他にも経理職なら簿記がおすすめです。経理業務に必要な知識が学べるため、入社後も早期に活躍できます。
また、企業によっては資格を取得することで、選考が有利になる場合があります。
しかし、資格取得には時間が必要です。資格よりも就活を優先するべき場合もあるので、資格を取得する際は、費用対効果を意識しましょう。
6. 企業が既卒に求めていることを理解する
就活では、企業が既卒に求めていることを理解してください。
企業が求める人物像に自分を近づけることで、内定を獲得しやすくなるからです。
とくに既卒は、新卒よりもビジネスマナーやコミュニケーション力があると思われています。その分、新卒よりも評価基準が厳しくなる企業もあるでしょう。
そこで、就活では社会人として最低限のスキルを身に付けていることをアピールしてください。新卒にはない魅力を伝えることで、新卒との差別化になります。
既卒が就活をするうえでの注意点
既卒が就活するうえでの注意点は、以下の2つです。
- 一人で既卒求人を見つけるのは難しい
- 嘘をついたり誤魔化したりしない
就活を始めると思うような結果が得られず、苦戦する場合があります。
本章では、自分が納得いく就活にするためにも気を付けるべき点を解説します。
1. 一人で既卒求人を見つけるのは難しい
既卒の就活の場合、一人で既卒求人を見つけるのが困難です。
日本ではまだ新卒一括採用の文化があるため、新卒向けの求人やサイト、サポートが充実しています。
しかし、既卒は新卒と中途採用のどちらにも当てはまりません。その結果、求人数が少ない傾向にあります。
自分一人の力で調査し、行動するのには限界があります。そこで、大学の就職課や就職エージェントをうまく活用しましょう。
既卒=不利とならないためのアドバイスがもらえたり、求人探しを手伝ってくれたりするからです。プロの力を借りつつ、自己分析や志望動機など、自分にしかできない作業に集中しましょう。
2. 嘘をついたり誤魔化したりしない
就活では嘘をついたり、誤魔化したりするのはやめましょう。内定を獲得できたとしても、最悪の場合、内定取り消しになる可能性があるからです。
たとえば、経歴詐称や成果の捏造などが挙げられます。面接官の評価が大きく下がり、信頼関係の構築が難しくなるでしょう。
既卒であることを素直に認め、質問には正直に答えてください。真摯に対応し、入社意欲を伝えることで、面接官の印象を良くすることが可能です。
確かに、自分を魅力的に見せたくなる気持ちは理解できます。しかし、就活ではありのままを話し、評価してもらいましょう。
自分の状況を冷静に分析し求人探しをしよう!
この記事では、既卒者が求人を見つけるための方法やポイントについて解説してきました。
就職は自分一人ではなく、周囲の力を借りることが重要です。大学の就職課や就職エージェントに相談することで、幅広い求人が見つけられるでしょう。
求人以外にも履歴書の添削や面接対策なども可能です。自分一人ではできない対策にも力を貸してくれます。
就活のパートナーとして、ジェイックの利用がおすすめです。豊富な求人数と充実した研修があるため、既卒でも内定を獲得できます。
既卒の方で、正社員に就職したい人は、一度ジェイックにご相談ください。