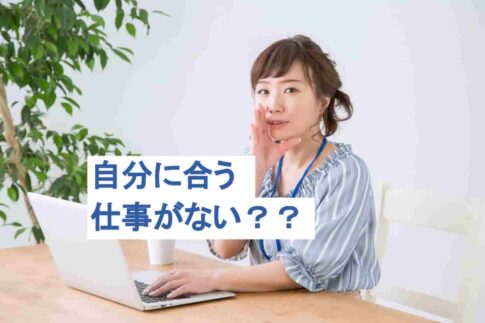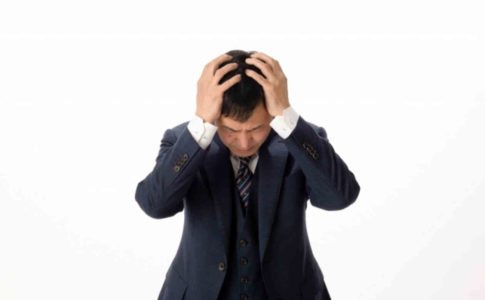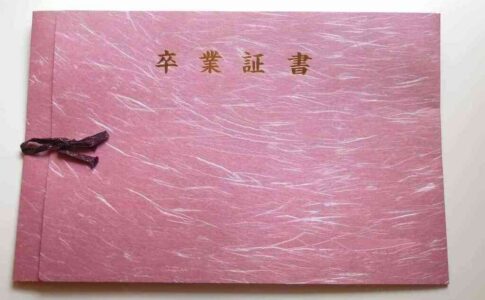警察官は、社会の安全を守る重要な役割を担っています。しかし、「警察官になるためにはどうしたらいいのだろう」と悩む人もいることでしょう。
どのような採用試験を受ける必要があり、具体的な仕事は何なのか、年収はどのくらいなのか、気になる点がたくさんありますよね。
この記事では、警察官になるためのステップや具体的な採用試験の内容、試験のスケジュールを紹介します。
また、仕事内容や気になる年収についても詳しく解説。これから警察官を目指す人にとって、第一歩となる情報をお届けします。
この記事の目次
警察官とは?
警察官は、社会の安全と秩序を守る公務員で、犯罪の防止や捜査、交通の取り締まり、事件・事故の対応などを行い、市民の安全を確保する大切な仕事です。また、地域住民との交流を通じて、防犯活動や相談対応も行っています。
警察官には、交番勤務の地域警察官、事件を捜査する刑事、交通違反を取り締まる交通警察官など、さまざまな役割があります。
警察官は「正義感」「体力」「判断力」が求められる一方で、人々の役に立てるやりがいのある仕事でもあります。社会の信頼を得ながら、地域の安全を守る欠かせない存在です。
警察官になるまでの流れ
国家公務員である警視庁所属の警察官、地方公務員として各都道府県警察に所属する警察官の2つのタイプがあります。
国家公務員と地方公務員では採用プロセスが異なります。ここからは、採用までの流れを詳しく解説していきます。
1. 地方公務員として働く場合
全国の警察官のうち、9割以上は都道府県警察で働く地方公務員です。
彼らは交番勤務やパトロールを通じて、地域の安全を守っています。
地方公務員の警察官になるには、各自治体の警察官採用試験を受験し、合格後「巡査」として採用される必要があります。
警察官登用後は、まずは警察学校に入校し、警察官としての必要なスキルや基礎知識を身に着けるための研修を受けます。
警察学校は全寮制で、大学卒は6ヵ月、それ以外は10ヵ月のカリキュラムが組まれています。
警察学校を修了したあとは、地域の交番からキャリアをスタートします。以降は、勤務年数や実績、評価、実績などに応じて、着実にキャリアアップしていく仕組みになっています。
地方公務員の採用試験は、実施する自治体によって募集要項や試験内容、採用人数に違いがあります。志望する自治体の警察官採用ページやホームページを確認しましょう。
2. 国家公務員として目指す場合
警察庁で働く警察官は国家公務員であり、警察官僚やキャリアと呼びます。現場勤務はほとんどなく、警察組織全体の政策立案や調整を担当しています。
警察庁と警視庁は異なり、警視庁は東京都の警察機関で、そこで働く警察官は地方公務員です。警視庁で働くためには、国家公務員採用試験(国家一般職または国家総合職)に合格し、官庁訪問を経て内定を取る必要があります。
警察庁の採用試験は、例年合格者は30名程度と非常に少なく、全国的にもトップレベルの難易度を誇ります。
狭き門を突破するためには、早めに対策を練り、計画的に学習を進めることが不可欠です。
出題傾向の把握や過去問演習など、しっかりした準備が合格のカギとなります。
警察官の採用試験の区分と受験資格
警察官として採用されるためには採用試験に合格する必要があるため、採用試験の区分や受験資格を正しく理解することが重要です。試験は学歴によって区分され、さらに年齢や身体要項などの条件が存在します。
ここでは、警察官採用試験の区分と受験資格について詳しく解説します。
区分
令和6年度警視庁採用サイトによると、警察官採用試験は応募者の学歴に応じて区分されています。
一般的に大学卒業程度はI類、短大卒業程度はⅡ類、高校卒業程度はⅢ類に分類されます。自治体によっては、大学をA区分、それ以外をB区分とする場合もあります。
詳しくは、自分が受験する地域の警察官採用情報をホームページなどで確認してみてください。
受験資格
警察官採用試験の受験資格には、学歴・年齢の要件と身体的な要件の2つがあります。
これらの条件は自治体によって異なるため、必ず受験前に最新の情報をチェックしましょう。
学歴・年齢の要件
令和6年度警視庁採用サイトの「採用案内(警察官)」によると、警視庁の警察官採用にあたって求められる学歴と年齢の基準は、以下を参照ください。
| Ⅰ類 (大学卒業程度) | ・平成2年4月2日以降に生まれた人で大学(学校教育法による大学(短期大学を除く。))を卒業又は令和8年3月までに卒業見込みの人 ・平成2年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で大学卒業程度の学力を有する人 | |
|---|---|---|
| Ⅲ類 (高校卒業程度) | ・平成元年4月2日以降に生まれた人で高校(学校教育法による高等学校)を卒業又は令和7年3月までに卒業見込みの人 ・平成元年4月2日以降に生まれた人で高校(学校教育法による高等学校)を卒業又は令和7年3月までに卒業見込みの人 平成元年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人で高校卒業程度の学力を有する人 |
出典:令和6年度警視庁採用サイト「採用案内(警察官)」
※下記のいずれかに該当する場合は、注意が必要です。
- 日本国籍を有しない人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
- 東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
出典:令和6年度警視庁採用サイト「採用案内(警察官)」
身体的な要因
令和6年度警視庁採用サイトの「採用案内(警察官)第2次試験」によると、警視庁の警察官採用にあたって求められる身体機能の基準は、以下を参照ください。
| 試験科目 | 内容 | |||||
| 面接試験 | 人物についての面接試験を行います。 | |||||
| 身体検査 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患の有無等についての検査を行います。 | |||||
| 検査内容 | 視力検査、色覚検査、聴力検査、運動機能の検査、医師の診察、身長測定、体重測定、レントゲン検査、血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質等検査、血糖検査)、尿検査 | |||||
| 次表の全てを満たすことが必要です。 | ||||||
| 視力 | 裸眼視力が両眼とも0.6以上、又は矯正視力が両眼ともに1.0以上であること | |||||
| 色覚/聴力 | 警察官としての職務執行に支障がないこと | |||||
| 疾患 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患がないこと | |||||
| その他身体の運動機能 | 警察官としての職務執行に支障がないこと | |||||
| ※令和5年度から、身長と体重については廃止しました。 | ||||||
| 体力検査 | 職務執行上必要な体力の有無について検査を行います。(種目は変更する場合があります。) | |||||
| 種目 | 腕立て伏せ、バーピーテスト、上体起こし、反復横跳び | |||||
| 適性検査 | 警察官としての適性について、記述式等の方法により検査を行います。 | |||||
出典:令和6年度警視庁採用サイト「採用試験(警察官)第2次試験」
警察官の採用試験のスケジュール
警察官採用試験は年に複数回実施されています。自治体によって回数や時期が異なるため、複数の自治体を併願することができます。ただし、自治体によっては男女で試験日程が異なったり、一部の区分を募集していなかったりするため、事前の確認が必要です。
たとえば、警視庁採用サイトの「採用案内(警察官)試験日程」によると2025年4月13日と9月15日に第1回・第2回の一次試験を実施予定です。また、二次試験は男女別に日程が分かれており、男性は5月10日・17日・18日・31日、女性は5月24日・25日から指定されます。
こうした日程の違いにも注意が必要です。
なお、試験日程は年度ごとに変更されることがあるため、最新情報を必ずチェックしてから準備を進めましょう。
警察官の具体的な試験内容
警察官採用試験は、1次試験と2次試験に分かれています。
試験内容は自治体によって多少の違いはありますが、形式はほぼ同一といえるでしょう。
ここでは、各試験の詳細について紹介しますので、受験を考えている方はぜひ確認してください。
一次試験
一次試験では、筆記試験、身体検査、資格経歴などの評定、適性検査の4つの項目が実施されます。
ここからは、一次試験の内容を詳しく解説します。
筆記試験(教養試験、論作文試験)
教養試験とは、公務員として必要な一般的な知識や判断力、論理的思考力を測るための筆記試験です。
論作文試験は、受験者の考える力や表現力、文章構成力、そして警察官としての適性を評価するための記述式試験です。
教養試験と同日に実施されることが多く、一次試験の重要な評価項目の一つです。
身体検査
身体検査は、各自治体が定めた警察官として勤務するために必要な健康状態や身体的条件を満たしているかを確認するための検査です。
身体検査に不安がある人は、事前に自治体の募集要項で詳細な基準を確認し、医療機関でチェックを受けておくと安心です。
資格経歴などの評定
令和6年度警視庁採用サイトの「資格経歴等の評定(警察官)」によると、治安維持に貢献できる意欲的な人材を採用するために設けられた制度です。
柔道や剣道の段位、スポーツ大会への出場経験、語学資格などは、自治体が定める独自の基準に基づいて評価され、加点の対象となる場合があります。
適性検査
適性検査では、警察官の適性があるかを記述式等の方法で検査を行います。警察官として必要な思考傾向、ストレス耐性、協調性などを確認するための心理検査です。
学力ではなく、人物面や職務適性を客観的に評価することが目的です。
二次試験
二次試験では、面接試験や体力検査などが行われます。
体力検査では、警察官としての基礎的な体力が備わっているかを確認するために実施され、種目の内容は自治体ごとに異なります。
自治体によっては身体検査、適性検査を二次試験で行う場合もあります。
ここからは、二次試験の内容を詳しく解説します。
面接試験
面接試験では、受験者の人物についての評価を行います。
面接では、志望動機を整理して自分の強みや長所をしっかりアピールすることが重要です。
面接試験は、個人面接の場合が多いですが、集団面接やグループディスカッションを実施する自治体もあるようです。
体力試験
令和6年度警視庁採用サイトの「採用案内(警察官)第2次試験」によると、職務執行上必要な体力の有無について検査を行います。
試験の種目は、腕立て伏せ、バーピーテスト、上体起こし、反復横跳びなどで、自治体によって検査項目は異なります。
体力検査では、警察官として実際に必要な体力を測る重要な試験であり、身体的な能力だけではなく、精神的な強さや忍耐力も求められます。
身体検査
身体検査では、各自治体が定めた警察官として勤務するために必要な健康状態や、身体的条件を満たしているかを確認します。
身体検査に不安がある人は、事前に自治体の募集要項で詳細な基準を確認し、医療機関でチェックを受けておくと安心です。
適性検査
適性検査では、警察官の適性があるかを記述式等の方法で検査を行います。警察官として必要な思考傾向、ストレス耐性、協調性などを確認するための心理検査です。
学力ではなく、人物面や職務適性を客観的に評価することが目的です。
警察官採用試験の受験前に確認しておきたいこと
警察官を目指すためには、採用試験を受験する前に十分な準備をしておくことが大切です。
以下の3つのポイントを参考にして、しっかりと準備を進めていきましょう。
- 自治体によって条件が異なる
- 試験のスケジュールを確認する
- 試験に有利になる資格がある
それぞれ解説します。
1. 自治体によって条件が異なる
警察官採用試験は、自治体ごとに受験資格や試験内容が異なるため、事前の情報収集が重要です。とくに「試験日」「受験資格」「試験内容」「募集人数」は、必ず確認しましょう。
受験資格を満たしているかを確認することはもちろんですが、募集人数の増減により合格率の変動も考慮し、過去のデータをチェックすることが大切です。
関心のある自治体があれば、早めに試験情報を整理し、どの自治体をいつ受験するのか、また合格に向けてどのような対策が必要かを、事前に考えておくと良いでしょう。
2. 試験のスケジュールを確認する
警察官採用試験は、多くの自治体で年に複数回実施されています。早い自治体では3月に申し込みが開始され、4月に1次試験が行われるため、早めの情報収集が合格のカギです。
遠方からの受験を考慮し、警視庁は1道18県で試験を実施するなど、複数の自治体が共同で試験を行う場合もあります。
複数の自治体を受験する際は、スケジュール管理を徹底することが重要です。試験の実施日や試験内容は年によって変動することがあるため、最新情報を必ず確認するようにしましょう。
さらに、試験日程に合わせて勉強や体力づくりを行う必要があります。余裕を持ってスケジュールを立て、試験に万全の状態で臨めるように準備しましょう。
3. 試験に有利になる資格がある
警察官採用試験では、自治体が指定する資格や職歴を持っていると試験の点数に加点されることがあります。
指定された資格や職歴は自治体によって異なるため、何の資格が加点対象になるか必ず確認しておきましょう。
主な加点対象には、以下のようなものがあります。
- 剣道や柔道の段位
- スポーツ大会の出場歴
- 英検や中国検定などの語学資格
- ITパスポートなどの情報処理資格
加点対象となる資格を持っていなくても、他の試験の成績が優れていれば合格することは可能ですが、合格の可能性を高めるために、加点資格の取得を検討するのも良いでしょう。
警察官採用試験に有利なスキル
警察官採用試験で有利になるスキルは、いくつかあります。
以下の3つのスキルが自分にあるか確認し、しっかりと準備を進めていきましょう。
- 柔道やスポーツ歴
- 英語や中国語などの語学力
- 情報系の資格
普段からスキルを磨いておくと、試験対策として有利です。新たなスキルの取得を検討しても良いでしょう。
1. 柔道やスポーツ歴
警察官は犯人を捕まえるために、一定の武道のスキルが必要です。たとえば、剣道や柔道の経験があると有利になります。
また、スポーツ歴も全国規模の大会やそれに準ずる大会に出場していたり、結果を残していたりするとアピールにつながります。
とくに体力検査が重要な試験項目であるため、武道やスポーツを通じて得た体力や忍耐力は、大きな強みになります。
普段から積極的にスポーツや武道に取り組むことは、警察官としての適性を高めるだけでなく、試験でも有利に働くでしょう。
2. 英語や中国語などの語学力
語学力が堪能であることも、試験で有利になる要素の一つです。英語や中国語などの語学力を証明するスキルを身に着けておくと良いでしょう。
その背景には、外国人観光客や在住者が増えていることが考えられます。また、国際的な業務や外国との連携を強化するため、警察官としての幅広い業務に貢献する能力を示すものです。
語学力を高めることは、警察官としての仕事の幅を広げ、採用試験でも有利に働くため、積極的に学んでおくことが望ましいです。
3. 情報系の資格
情報系の資格には、ITパスポートや基本情報技術者試験などの資格があると良いです。
情報系の資格を所持していれば、IT関連の業務に強みを持っていることが証明できます。
現代の警察業務では、サイバー犯罪対策やデータ解析が重要な役割を担っており、こうした資格を取得することで、サイバー犯罪への対応能力をアピールできます。
また、交番や生活安全課での市民からの相談対応においても、ITやネットワークに関する知識は有益です。
情報系の資格を取得することで、警察官としての幅広い業務に役立つ知識を習得でき、試験合格のチャンスを高められます。
警察官採用試験の合格ハードルはどれくらい?
警察官採用試験の内容自体は、基礎的な知識や技能が求められる内容が多いため、難易度は高くありません。しかし、倍率が高いことや体力試験があるので、難しく感じる人もいます。
たとえば、警視庁採用試験の過去3年間の採用倍率は、男性が5~10倍、女性が5~7倍であり、年度ごとに大きな差が見られます。
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| Ⅰ類 | 6.0倍 | 5.7倍 | 6.1倍 | 7.4倍 | 5.7倍 | 6.2倍 |
| Ⅲ類 | 8.0倍 | 6.0倍 | 10.3倍 | 6.3倍 | 8.5倍 | 6.5倍 |
出典:警視庁採用サイト「採用案内(警察官)合格倍率」
警察官採用試験は複数の自治体を併願することが可能です。
合格のチャンスを広げるためにも、複数の自治体に挑戦しておくことをおすすめします。
倍率が高いということは、試験に合格するためには十分な準備が必要であることを示しています。
自分の強みを最大限にアピールできるようにしておくことが、合格へのカギとなります。
警察官の種類と主な仕事内容
警察官の種類は、主に「警察官(地方公務員)」「警察庁警察官(国家公務員)」「皇居警察本部」の3つに分類されます。
ここでは、警察官の種類の詳細と主な仕事内容について解説します。自分がどのような警察官になりたいのか明確にしましょう。
1. 警察官(地方公務員)の場合
地方公務員としての警察官は、都道府県警察に勤務し、地域の治安維持を担当します。
警視庁の警察官とは異なり、地方自治体の一員として、地域に密着した業務が求められます。
都道府県警察は、以下のような所属に分かれ業務に従事している状況です。
- 生活安全課警察
- 地域警察
- 刑事警察
- 交通警察
- 警備局
- 総務・警務警察
それぞれの仕事を詳しく見ていきましょう。
生活安全警察
生活安全警察は、日常的に発生する身近な犯罪から市民を守るため、犯罪の取り締まりや防犯活動を早期に実施し、犯罪が起こりづらい環境を整備しています。
主な仕事内容は以下の通りです。
- 防犯対策や防犯教室
- 子供・女性の安全対策(DV、ストーカー被害、性犯罪など)
- サイバー犯罪対策
- 少年犯罪対策、立ち直り支援活動
- 風俗営業、古物営業、鉄砲等の許認可
- 環境犯罪や経済犯罪の取り締まり
生活安全警察は、市民一人ひとりの安心・安全な暮らしを守るため、地域に根ざした活動を通じて、日々さまざまな課題に取り組んでいます。
出典:警察庁「都道府県警察採用案内(職種について)生活安全警察」
地域警察
地域警察は、全国各地に配置されている交番・駐在所を拠点に地域に根ざした活動を行いながら、住民や企業、自治体と連携し、安全で安心な暮らしを守る役割を担っています。
主な仕事内容は以下の通りです。
- 管内のパトロール・巡回連絡
- 遺失届・拾得物対応、地理案内
- 事件・事故発生時の初動対応
- 防犯指導
- 犯罪者の検挙
- 犯罪の未然防止活動
- 交通指導取締り
- 事故防止活動
地域警察は、住民の身近な存在として日々活動を続けています。
地域に密着した細やかな対応と迅速な行動で、誰もが安心して暮らせるまちづくりを支えています。
出典:警察庁「都道府県警察採用案内(職種について)地域警察」
刑事警察
刑事警察は、殺人や強盗といった凶悪犯罪をはじめ、生命・財産・社会の安全を脅かすあらゆる犯罪に対して、毅然とした姿勢で対応します。
主な仕事内容は以下の通りです。
- 事件の捜査、聞き込み等
- 犯人の取り調べ
- 鑑識
- 検視
テレビの刑事ドラマでもよく知られる刑事警察は、凶悪で卑劣な犯罪に立ち向かうため、高度な鑑識技術や最先端の科学捜査を駆使して捜査をしています。
出典:警察庁「都道府県警察採用案内(職種について)刑事警察」
交通警察
交通警察は、市民が安全に生活できる交通社会を築くために、事故の発生しやすい場所での指導や取締りを行っています。また、ひき逃げや交通事故を装った保険金詐欺などの事件の捜査も重要な任務です。
主な仕事内容は以下の通りです。
- 交通指導取締り(白バイ・パトカー)
- 交通事故捜査
- 交通整理・交通規制
- 道路標識の整備、道路使用許可
- 運転免許に関する事務
- 交通安全教育
これらの活動を通じて、すべての人と車が安心して通行できる環境の整備に力を入れています。
出典:警察庁「都道府県警察採用案内(職種について)交通警察」
警備局
警備局では、災害時の救助活動や祭り・イベントでの雑踏警備、空港や港湾など重要施設の警戒・警備を行っています。
また、テロやゲリラ行為の防止・検挙、要人の警護などを通じて、社会の安全を守ることも重要な任務です。
主な仕事内容は以下の通りです。
- 要人警護
- 治安警備
- 国際テロ対策
- 不法滞在者の取締り
- 災害救助(水難救助、山岳救助)
- 爆発物や化学物質の処理
警備局は、その機動力を生かして地域住民の安全な生活と生命を守るために、日々業務に従事しています。
総務・警務警察
総務警察は、広報活動や予算の管理、留置施設の運営などを担当し、警務警察は職員の採用や福利厚生の整備、犯罪被害者支援などを行っています。
それぞれが警察の運営や活動を多方面から支えているのです。
主な仕事内容は以下の通りです。
- 議会や公安委員会との連絡・調整
- 広報活動、音楽隊
- 予算管理
- 装備資機材の整備・開発
- 犯罪被害者支援
- 人材育成
すべての職員が快適に働ける環境を整備し、さらに犯罪の被害に遭われた方々に対して寄り添い、必要な支援を行うことで、安全で安心な街づくりに貢献しています。
出典:「都道府県警察採用案内(職種について)総務・警務警察」
2. 警視庁警察官(国家公務員)の場合
警察庁は警察組織の中核を担っており、警視庁内には刑事局、生活安全局、交通局、警備局、情報通信局などの各内部部局があります。
全国の警察組織の運営や企画、組織間の調整などを行っているのです。
警視庁警察官には、警視庁警察官(国家総合職)と警察庁警察官(国家一般職)の2つの種類があります。
いわゆる「キャリア警察官」とも呼ばれるエリートコースを歩むのが、この警視庁警察官です。
警察庁警察官(国家総合職)
警察庁警察官(国家総合職)は警察庁に所属し、日本の警察行政を担うキャリア官僚のことを指します。
政策立案や警察組織の運営を担当し、都道府県警察を指導・監督を行っています。
現場で直接犯罪捜査を行う警察官とは異なり、主に政策の策定や警察行政の運営に関わります。治安維持や犯罪予防、各種法律の運用、警察組織の改革などを担当し、全国の警察機関を調整・指導することも重要な仕事の一つです。
警視庁警察官(国家一般職)
警察庁警察官(国家一般職)は警察庁に所属し、警察行政の事務や都道府県警察の支援を行う職員です。総合職とは異なり、主に実務や調査・分析、システム管理などを担当しています。
警察官としての基本的な業務(犯罪捜査、事件対応、パトロール、交通取り締まりなど)が含まれます。また、警視庁内の異動や昇進を経て、さまざまな部署で専門的な業務を担当することもあるようです。
3.皇宮警察本部
皇宮警察本部は、皇室の安全を守るための日本の警察組織です。
皇居や御用邸の警備、皇族の護衛を担当しており、警察庁の管轄下にあります。
特殊な訓練を受けた警察官が配置され、儀仗(儀式警護)などの業務も担当します。
主な業務内容は以下の3つです。
- 護衛部門
天皇・皇后両陛下や皇族の護衛、国家の重要人物や外国大使が皇居に訪れる際の身辺警護などを担当 - 警備部門
皇居や御所、御用邸、皇室行事の警備など、天皇の居住地を守るための業務を行う - 警務部門
皇宮警察の活動を円滑に運営するため、勤務体制の管理や採用、人事、教養、予算、福利厚生など、組織全体の環境整備を担当
皇宮警察本部は、国家の象徴である皇室の安全と尊厳を守るという、極めて重要かつ特殊な使命を担っています。
高度な専門性と厳格な規律のもとで活動を続けながら、日本の伝統と信頼を支える役割を果たしています。
警察官の給料・年収はどれくらい?
警察官の給料・年収は、その勤務先や役職、勤務地によって異なりますが、基本的には安定した給与体系が整っています。
日本の警察官は公務員として給与が支払われるため、一般的に民間企業よりも安定性が高いとされています。
職業情報提供サイトjob tagの「警察官(都道府県警察)」によると、全国の平均賃金は21万8,000円です。
厚生労働省が発表した「令和5年賃金構造基本統計調査の概要」によると、2023年の正社員の平均賃金は33万6,300円でした。年収に換算すると、警察官は約220万円、一般的な正社員は約410万円です。これを踏まえると、警察官の平均賃金は一般的な正社員の平均賃金と比較して、やや低いといえるでしょう。
しかし、警察官にはさまざまな手当が支給されます。たとえば、夜勤手当や危険手当、住居手当、扶養手当などが支給される場合があるのです。これらの手当を含めると、実際の年収は基本給の倍以上になることもあります。
警察官を目指して内定を勝ち取ろう!
警察官は国家公務員と地方公務員に分かれ、国家公務員として働くには国家公務員採用試験、地方公務員としては各都道府県警察の採用試験を受ける必要があります。
試験内容や日程、倍率は自治体ごとに異なるため、早めの情報収集と対策が重要です。
ただし、試験の難易度や準備には高いハードルがあるため、警察官を目指すのが難しいと感じた場合、一般企業も選択肢として考えるのも一つの方法です。
自分に合った道を選び、全力で取り組んでいきましょう。