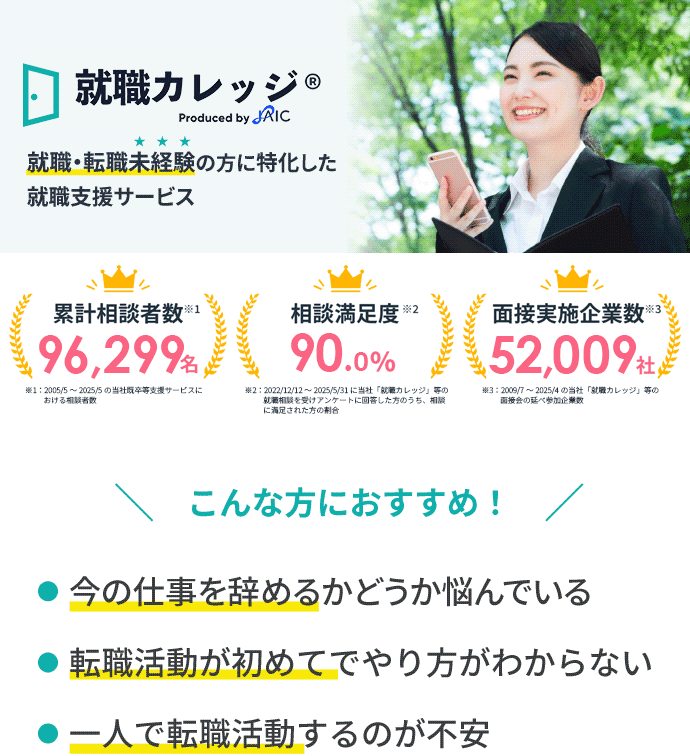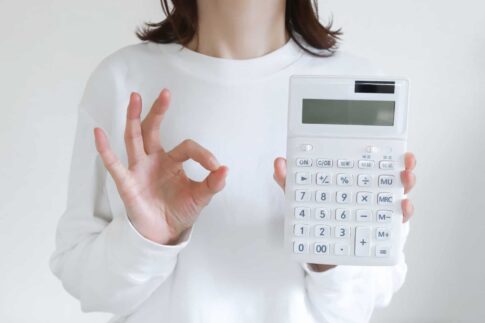「休職期間の満了日が近いけれど、回復しないからこのまま退職になるかもしれない」「自然退職は会社都合退職なのでは?」そんな不安や疑問を抱えていませんか。
自然退職は「自己都合退職」と同じ扱いです。この点を誤解していると、退職後の手続きや今後の生活設計に影響するかもしれません。
本記事では休職期間満了に伴う自然退職の基本的なルールや一般的な流れ、退職後に行う各種手続きや自然退職を避けるための方法について解説しています。
休職期間満了や自然退職のルールを正しく理解すると不安や疑問が解決でき、次のステップに向けて動き出せるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
休職期間満了に伴う自然退職とは?
休職期間満了までに復職できない場合「自然退職」という形で労働契約が終了するケースがあります。本章では、以下の内容についてそれぞれ解説します。
- 休職期間満了に伴う自然退職は労働契約が終了する形の1つ
- 自然退職は「自己都合」と「会社都合」いずれにも分類できない退職
休職期間満了に伴う自然退職は労働契約が終了する形の1つ
休職期間満了に伴う自然退職は、労働契約が終了する退職形態の1つです。就業規則に基づいて特定の条件を満たした場合に、労働契約が自動的に終了する仕組みを指しています。
会社が休職期間満了による自然退職を適用する場合は次のとおりです。
- 労働者が病気やケガで休職し「休職期間中の職場復帰が難しい」と医師が判断した場合
- 労働者が復職の意思を示さない場合
休職期間満了に伴う自然退職は、就業規則で定められたルールに従って手続きを進めるのが一般的です。
自然退職は「自己都合」と「会社都合」いずれにも分類できない退職
自然退職は、労働者から退職を申し出る「自己都合退職」と、会社が労働者に退職を求める「会社都合退職」のいずれにも分類できない退職です。
本章では、以下3種類の退職について、それぞれの特徴を解説します。
- 自然退職のケース
- 自己都合退職のケース
- 会社都合退職のケース
自然退職のケース
自然退職は、休職期間の満了によって自動的に退職となる形態です。適用される主なケースは次のとおりです。
- 休職期間満了までに復職できない場合
- 無断欠勤
- 音信不通
上記のケースでは就業規則や労働契約に基づき、自動的に退職が成立します。休職期間満了日や退職日などの通知が会社から届いたら退職書類を作成します。
会社から貸与された備品の返却や健康保険の切り替え、年金や失業保険の手続きも併せて行いましょう。
自己都合退職のケース
自己都合退職として取り扱われるのは「転職や結婚、健康上の理由など、個人的な理由による退職」の場合です。
会社都合退職と比べて次のデメリットがあることに注意しましょう。
- 失業保険を受け取るまでに約3ヶ月待機する必要がある(特定の条件を除く)
- 退職金の支給額が会社都合退職よりも少ない場合がある
しかし、自己都合退職の場合は、自分の意思やタイミングで新しい道を選べるメリットがあります。
自分の意思を尊重しながら、前向きに次のキャリアやライフプランを考えるとよいでしょう。
会社都合退職のケース
会社都合退職は、企業の経営状況や事業の統合などによって、会社側から労働者に退職を求める形態です。主に以下のケースが該当します。
- 会社の倒産
- 業績悪化による人員削減
- 事業所の統廃合
- 事業の縮小や撤退、組織再編
会社都合退職の場合は、労働者に以下のメリットがあります。
- 自己都合退職よりも退職金が増える可能性が高い
- 失業保険の給付額が手厚いうえ、自己都合退職よりも早く受給できる
- 転職先にネガティブな印象を与えにくい
自己都合退職の場合、失業保険の受給が始まるまでに約3ヶ月の待機期間が必要です。
しかし、会社都合退職の場合は待機期間が免除されるため、すぐに受け取れます。
また、給付額が手厚いのもメリットの1つです。
自然退職は就業規則等に記載されている場合がある
自然退職のルールは、ほとんどの企業で就業規則に明記されています。
ただし、就業規則に記載がない場合は、労働契約書や個別の合意が必要となるケースもあるため、事前にしっかり確認しましょう。
自分の権利や義務を把握しておくと、不安を軽減できます。
休職中は就業規則を確認するのが難しいため、自然退職に関する情報が会社からの通知書に記載されるのが一般的です。
通知書には「自然退職となる日付」や「休職期間の満了日」などが記載されています。
書類が届いたらすぐに内容を確認し、不明な点がある場合は人事部門へ確認しましょう。
通知書を放置すると重要な手続きが遅れるリスクがあるため、早めに目を通すことをおすすめします。
休職期間満了に伴う自然退職は「自己都合退職」と同じ扱い
休職期間満了後の自然退職は「自己都合退職」と同様に扱われるケースが一般的です。
これは、退職理由が「労働者の事情によるもの」とみなされるためです。
本章では、自然退職が自己都合退職と同じ扱いになる理由について、それぞれ解説します。
- 復職できない理由が労働者側にあるから
- 自然退職の退職金は自己都合退職と同じ
- 失業保険も自己都合退職と同じ場合が一般的
復職できない理由が労働者側にあるから
自然退職が「自己都合退職」と同じ扱いになる理由は、復職できない理由が労働者側にあるためです。具体的には次の状況が該当します。
- 復職が難しいと医師が判断した場合
- 個人的な事情で従業員が復職の意思を示せない場合
- 会社からの再三の連絡にも関わらず、欠勤や音信不通が続いている場合
これらの場合、復職できない理由が労働者自身にあるため「会社都合退職」には該当しません。
そのため、自然退職は自己都合退職と同じ扱いになります。
会社への連絡を怠るとトラブルが起きたり、誤解が生じたりする恐れがあります。
不明点がある場合は人事部門へ早めに相談しましょう。
自然退職の退職金は自己都合退職と同じ
自然退職の退職金は、自己都合退職と同じルールが適用されるのが一般的です。
そのため、会社都合退職よりも退職金の額が少なく設定されているケースが多いのです。
退職金の計算方法や金額は、会社のルールに基づいているため、規程を必ず確認しましょう。
不明点がある場合は、人事担当者へ早めに相談するのをおすすめします。
失業保険も自己都合退職と同じ場合が一般的
失業保険についても、自然退職は自己都合退職と同じ条件になるのが一般的です。
そのため、以下の点に注意しましょう。
- 給付までに3か月の待機期間が必要(特定の条件を満たす場合を除く)
- 給付期間が会社都合退職よりも短く設定される場合が多い
しかし、退職理由に特別な事情がある場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合、失業保険の要件が緩和されたり、待機期間が免除されたりなど、自己都合退職よりも有利な条件で受給できるケースがあるのです。
自分が特定理由離職者の条件に当てはまるか知りたい場合は、ハローワークで確認できます。 自分の状況を把握して、必要な手続きを進めましょう。
休職期間満了に伴う自然退職の一般的な流れ
休職期間満了に伴う自然退職は、いくつかのステップを経て進むのが一般的です。
会社と連携しながら手続きを進めていきましょう。
以下は自然退職までの主な流れです。
- 休職期間満了が近づくと会社から通知が届く
- 復職の可能性を主治医と相談
- 人事部門や産業医と面談する
- 休職期間満了日までに復職できない場合は退職手続きを行う
- 保険証や社員証、会社貸与品を返却する
- 本人が出社義務を果たさない場合も自然退職になる
1. 休職期間満了が近づくと会社から通知が届く
休職期間の満了日が近づくと、会社から労働者に通知書を送付します。
この通知書には休職期間の満了日や、その後の対応に関する案内が記載されています。
重要な情報が記載されているため、届いたらすぐに内容を確認しましょう。
例えば「休職期間が〇月〇日で満了になるため、復職の可否を確認したい」と記載された通知書が届く場合があります。
状況によっては自然退職になる可能性が高いため、通知書をしっかりと確認し、不明点があればすぐに会社へ問い合わせましょう。
2. 復職の可能性を主治医と相談
会社より通知書を受け取ったら、復職の可否について主治医に相談します。
医師の診断書が復職の判断に大きく影響するため、現在の健康状態や復職の可能性について確認しましょう。
「まだ一定期間の療養が必要」と医師が診断した場合は復職が難しくなるため、自然退職に進む可能性が高くなります。
「完治したと思っているのに、療養が必要と医師に言われた」「主治医と自分の考えが合わない」と思う場合は、セカンドオピニオンを受けて、別の医師の意見を聞くのも有効です。
3. 人事部門や産業医と面談する
現在の体調や復職の意思を確認するために、診断書を基にして産業医や保健師、人事部門との面談を行います。
この面談では以下の点について主に話し合います。
- 現在の体調
- 復職可能なタイミング
- 復職先部署の検討や業務内容の調整(復職が可能な場合)
- 自然退職の条件確認(休職期間満了日までに復職が難しい場合)
面談では、診断書の内容や会社の判断が復職可否に影響するため、労働者が復職を希望していても認められない場合があります。
この場合は話し合いを通じて、双方が納得できる解決策を見つけることが大切です。
4.休職期間満了日までに復職できない場合は退職手続きを行う
休職期間満了日までの復職が難しい場合、退職手続きを進める必要があります。
人事部門の指示に従って漏れのないように対応しましょう。
- 退職届などの提出
- 退職金や未払い給与の確認
- 離職票の発行依頼(失業手当の申請に必要です)
これらの手続きが完了すると、自然退職が成立します。
退職の際は多くの書類を作成するため、不明な点があれば遠慮せずに人事担当者へ確認しましょう。
手続きがスムーズに進むよう、必要書類を事前に確認すると安心です。
5.保険証や社員証、会社貸与品を返却する
退職する際は、会社から貸与されている物品をすべて返却します。
具体的には次のものが該当します。
- 保険証
- 社員証
- PCやICカード
- スマートフォン
- 制服やユニフォーム
会社貸与品を返却しないと横領罪に問われる恐れがあります。
損害賠償を請求されたり、退職金から差し引かれたりするケースもあるため、必ず返却しましょう。
返却する際は職場に直接持参するか、配達記録が残る方法で郵送するのがおすすめです。
退職後も会社の保険証を使用する「任意継続」の場合は、保険証を返却する必要はありません。退職後も使用する旨、健康保険組合の担当者に伝えましょう。
本人が出社義務を果たさない場合も自然退職になる
本人が出社義務を果たさない場合も、自然退職になるケースがあります。
例えば、休職期間中に連絡が取れなくなったり、復職の意思が確認できなかったりする場合です。
しかし、この場合でも会社は自然退職について従業員に十分な説明を行う必要があるため、何度も連絡して記録を残すのが一般的です。
会社からの連絡に応答しないまま休職期間が満了になると「音信不通」の理由で自然退職となる可能性が高いため注意しましょう。
自然退職後にすぐ転職しない場合は各種手続きが必要
自然退職後、すぐに転職しない場合は多くの手続きが必要です。特に健康保険や年金、失業保険などの手続きを忘れると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
退職後に必ず行う手続きについて、以下のとおり解説します。
- 健康保険を切り替える
- 年金を切り替える
- 失業保険を申請する
- 健康保険の傷病手当金制度は最長1年6ヶ月もらえる
健康保険を切り替える
健康保険を切り替える方法は、大きく分けて次の3種類があります。
あなたの希望や状況に応じて最適な方法を選びましょう。
任意継続被保険者制度:
退職後も最大2年間、前職の健康保険を利用できる制度です。
在籍中は会社が保険料を半額負担しますが、任意継続被保険者制度の場合は保険料が全額自己負担のため、負担に感じるかもしれません。
市区町村で加入手続きを行います。前年の所得に応じて保険料が決まるため、退職した年は高額になる可能性があります。
保険料の支払いが難しい場合は減免措置が適用されるケースもあるため、窓口で相談してみましょう。
家族の被扶養者として加入:
家族が会社の健康保険に加入している場合、収入などの条件を満たせば扶養に入れます。
被扶養者になる場合は保険料の負担が発生しないのがメリットです。
健康保険の手続きは、退職日から14日以内に行う必要があるため速やかに進めましょう。
年金を切り替える
退職後は、厚生年金から国民年金に切り替える手続きが必要です。
退職日から14日以内に手続きする必要があるため、健康保険の切り替えと同時に行うのが一般的です。
切り替えを怠ると未納扱いとなり、将来の年金額に影響するかもしれません。
早めに対応しましょう。以下の書類を持参して、市区町村の窓口で手続きします。
- 退職日を証明する書類(退職証明書や健康保険資格喪失証明書)
- 年金手帳や基礎年金番号が分かるもの
「退職後は働かずに、しばらく治療に専念するので生活費が心配」と感じることはないでしょうか。
収入の減少により年金の支払が難しい場合は、全額免除や一部免除、猶予の申請が可能です。
市区町村の窓口や年金事務所で相談してみましょう。
失業保険を申請する
過去2年間で12か月以上雇用保険に加入しており、自然退職後に再就職の予定がない場合は、失業保険を申請しましょう。手順は次のとおりです。
1.必要な書類を準備する:
離職票(退職後、会社から発行される書類)
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
自分の口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
2.ハローワークで手続きする
自己都合退職の場合は、給付までに約3か月の待機期間があります。
しかし、病気やケガで退職した場合は「特定理由離職者」になり、待機期間が免除される可能性があります。
自身がその条件に当てはまる場合は、窓口で相談しましょう。
参照:雇用保険手続きのご案内 – ハローワークインターネットサービス
3.給付内容を確認する
給付期間は加入期間や年齢などによって異なります。認定日にはハローワークに訪問し、求職活動の実績を報告します。
失業保険は生活の基盤を支える重要な制度です。早めの申請を心がけましょう。
健康保険の傷病手当金制度は最長1年6ヶ月もらえる
前職で健康保険の傷病手当金制度を利用していた場合、退職後も受け取れる可能性があります。条件は次のとおりです。
- 退職前に傷病手当金が支給されていること
- 引き続き療養が必要であり、働けない状態であること
支給内容:
支給額は標準報酬日額の3分の2相当で、最長1年6ヶ月間受給できます。
退職後も継続して受け取るためには、健康保険の任意継続が必要です。
手続き方法:
会社の健康保険組合に医師の診断書や傷病手当金支給申請書を提出しましょう。この制度を利用すると、経済的な負担を軽減しながら療養に専念できます。健康保険組合の担当者に確認しながら手続きを進めましょう。
参照:全国健康保険協会「傷病手当金について | よくあるご質問」
休職期間満了に伴う自然退職を避けるための方法
主治医の指示を守りつつ職場と連携すると、自然退職を回避できるかもしれません。ここでは、自然退職を避けるための具体的な方法を6つ解説します。
- 定期的に主治医の診察を受け、治療に専念する
- 人事部門や産業医と定期的に面談をする
- 体調を見て復職準備やリワークプログラムの参加を検討する
- 復職が見えてきたら復職先の部署を検討する
- 短時間勤務や負担の少ない業務からスタートする
- 復職後も当面は産業医面談を継続する
1. 定期的に主治医の診察を受け、治療に専念する
主治医の診察を定期的に受けながら治療に専念します。医師の指導に従って薬物療法やリハビリなどを継続すると、体調が少しずつ回復していくでしょう。
診察の際は診断書を作成してもらい、会社へ提出します。診断書は復職の可否を判断するだけでなく、会社との面談で現状を説明する際にも使われます。
治療が長期にわたる場合もありますが、無理をせず一歩ずつ進むことが大切です。体調や状況に変化があった際には医師や会社に相談し、適切な対応を取るように心がけましょう。
2. 人事部門や産業医と定期的に面談をする
休職中は人事部門や産業医と定期的に面談を行い、現在の体調や復職の可能性を確認します。面談では現状と今後の見通しについて主に話し合います。
主治医の診断書を基にしながら「療養期間ががもう少し必要」「復職した場合、どの部署でどのような業務なら可能か」などを相談しましょう。
産業医面談では生活リズムの整え方やストレスの軽減方法についてもアドバイスを受けられます。「睡眠の質があまり良くない」「復職に向けた生活リズムの整え方に悩んでいる」といった場合は、面談で気軽に相談してみましょう。
3. 体調を見て復職準備やリワークプログラムの参加を検討する
体調が十分に回復してきたら、可能な範囲で復職準備やリワークプログラムの参加を検討してみましょう。
リワークプログラムはスムーズに復職するためのサポートを受けられる制度です。
多くの自治体などで提供されており、主に以下の内容を行います。
- グループワーク
- ストレス対処法の学習
- 簡単な作業訓練
参加を検討する際は、主治医や産業医に相談しましょう。体調や希望に応じてプログラムの期間や頻度を調節することも可能です。
復職準備は焦らず、体調を考慮しながら自分のペースでゆっくりと取り組むことが大切です。
専門家にサポートを求めながら一歩ずつ進めていきましょう。
4. 復職が見えてきたら復職先の部署を検討する
体調が回復して復帰の見通しが立ってきたら「復職可能」と記載された診断書を主治医に作成してもらいます。
診断書には、業務上の配慮や制限を具体的に記載してもらうと、会社側で職場の配慮がしやすくなります。
例えば、以下のように診断書へ記載してもらうとよいでしょう。
- 復職の際は軽作業から始める
- 部署を変えて復職する
- 短時間勤務から開始する
復職先は休職前と異なる部署でも問題ありません。「休職前の部署の仕事が合わず、メンタル不調になってしまった」「休職前は営業だったが、復職後は過去に経験のある管理部門で働きたい」といった場合は会社に相談し、自身の希望に合った部署を提案してもらいましょう。
あなたが無理なく働ける環境を作るため、復職先の調整は非常に大切です。
1人で悩まず、人事部門や産業医と相談しながら、納得のいく選択をしていきましょう。
5. 短時間勤務や負担の少ない業務からスタートする
復職後は体調を最優先に考慮しつつ、短時間勤務や負担の少ない業務からスタートしましょう。
産業医や保健師、人事部門や復職先の上司と相談して、復職後の働き方を決定します。例えば、1日4〜5時間の短時間勤務や軽作業から始め、少しずつフルタイム勤務に戻していくと、体へ負担をかけずに働けます。無理なく取り組めるペースで、職場のリズムに少しずつ慣れていきましょう。
復職後も主治医や産業医に相談しながら、体調をチェックすることが大切です。復職後に疲れがたまりやすく、ストレスを感じる場合はすぐに相談して調整しましょう。
6. 復職後も当面は産業医面談を継続する
復職後も安心して働けるよう、産業医面談を数ヶ月ほど継続します。産業医面談では体調を確認するだけでなく、業務が適切に配慮されているかもチェックします。
「思ったより業務負担が重くつらい」「当初聞いていた仕事と異なっている」と感じた場合は面談時に伝えましょう。
体調を再度崩すリスクを避けるために、産業医や保健師、人事部門のサポートを継続すると安心です。健康面だけでなく職場環境の改善にもつながるため、関係者との連携を引き続き大切にしましょう。
休職期間満了に伴う自然退職についてよくある質問
休職期間満了に伴う自然退職についてよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
- 休職期間満了までに復職できそうにない場合は、自然退職前に退職した方がよいですか
- 復職の見込みが立たない場合、いつ会社に相談すべきですか
- 休職期間に有給休暇は使用できますか
- 転職先に提出する履歴書には休職期間をどのように書けばいいですか
- 休職期間の延長は可能ですか
- 復職のタイミングを逃すと、自動的に自然退職になりますか
休職期間満了までに復職できそうにない場合は、自然退職前に退職した方がよいですか
自然退職前に退職した方がよいかは、状況によって異なります。
自然退職前に辞める場合と自然退職を待つ場合、それぞれにメリットとデメリットがあるため、あなたの健康状態や今後のキャリアを考慮して慎重に判断しましょう。
自然退職前に退職する場合
| メリット | 次のステージへ進む準備が早く始められるため、キャリアアップや転職成功の可能性が高まります。 |
| デメリット | 自然退職前に辞めると退職金や各種手当、保険の面で不利になる恐れがあります。 |
自然退職の場合
| メリット | 早めに辞める場合と比べて、退職金や保険の面で有利になる可能性があります |
| デメリット | 次の仕事を探すタイミングが遅くなるため、キャリアアップが遅れたり、希望する求人を逃したりするかもしれません。 |
自身の健康状態を最優先に考えつつ、どちらを選ぶか慎重に判断しましょう。
復職の見込みが立たない場合、いつ会社に相談すべきですか
復職が難しいと感じた場合は、早めに会社へ相談しましょう。
主治医の診断書に「自宅療養が必要」と記載されている場合は、その診断書を会社へ提出し、現状を伝えます。
以下の情報を伝えると、会社側も手続きを進めやすくなります。
- 現在の体調や治療の進捗状況
- 治療の見通しや回復までに必要な時間
- 休職期間満了後の手続き
不安な場合は主治医や会社だけでなく、家族や信頼できる人にも相談しながら進めてみてください。
周りのサポートを受けながら、治療に専念するとよいでしょう。
休職期間に有給休暇は使用できますか
原則として、休職中は有給休暇が使用できません。
有給休暇は働ける状態で取得できる休みのため、休職と有給休暇は併用できない場合が一般的です。
有給休暇は休職に入る前か復職後に使用できるため、休職に入る前の休息や復職後の通院などに使用しましょう。
有給休暇の制度は会社によって異なります。
使用する際は就業規則を確認し、不明な場合は人事部門に相談しましょう。
転職先に提出する履歴書には休職期間をどのように書けばいいですか
「〇〇年〇月~〇〇年〇月 病気療養のため休職(現在は回復しており、業務への支障はありません)」などと記載します。
具体的な病名は不要です。
現在は体調が回復しており、業務に影響しない旨を明確にしましょう。
一般的に、休職したことは履歴書に記載しなくてもよいとされています。
そのため、転職活動で不利になると感じる場合は記載しなくても問題ありません。
しかし、1年以内に休職した場合は、転職先に提出した源泉徴収票から発覚する可能性があるため、記載した方がよいでしょう。
休職期間の延長は可能ですか
休職期間の延長が可能かは、会社の就業規則や労働契約書によります。
延長条件が明確に定められている会社が多いため、就業規則を確認しましょう。
主治医の診断書に「さらなる療養が必要」と記載されている場合、会社が休職期間の延長を認めるケースがほとんどです。
しかし、休職期間には限度があり、勤続年数や出勤率などでも変わるため、延長できずに自然退職になる可能性もあります。
休職期間の延長を希望する場合は、診断書を会社に提出した上で、産業医や保健師、人事部門に相談しましょう。
復職のタイミングを逃すと、自動的に自然退職になりますか
休職期間満了時に復職のタイミングを逃すと、自動的に自然退職として扱われるかもしれません。
これは会社の就業規則などで定められているからです。
しかし、やむを得ない事情がある場合や、会社との間で特別な取り決めがあるケースは、例外が認められて自然退職が回避できる可能性があります。
復職のタイミングを逃さないようにするため、会社から送られた書類を必ず確認し、不明点がある場合は早めに会社へ問い合わせましょう。
主治医より「復職可能」と判断された場合は診断書を会社に提出し、復職の準備を始めると自然退職を回避できます。
まとめ
休職期間満了に伴う自然退職は「自己都合退職」と「会社都合退職」のいずれにも分類できない形態です。
しかし、自己都合退職と同じ扱いになるため、退職金や失業保険を受け取る際は注意しましょう。
休職期間満了の前に復職を目指す場合は、治療に専念しながら会社と連携することが大切です。
主治医や産業医のアドバイスを参考にしつつ、無理のない範囲で復職計画を進めましょう。
自然退職となる場合は、失業保険や健康保険などの手続きを適切に進めると、退職後の生活が安定します。
本記事を参考にして、自分の状況にあった方法を検討してみてください。
1人で悩まず、周りのサポートを活用しながら、次のステップを前向きに進めていきましょう。