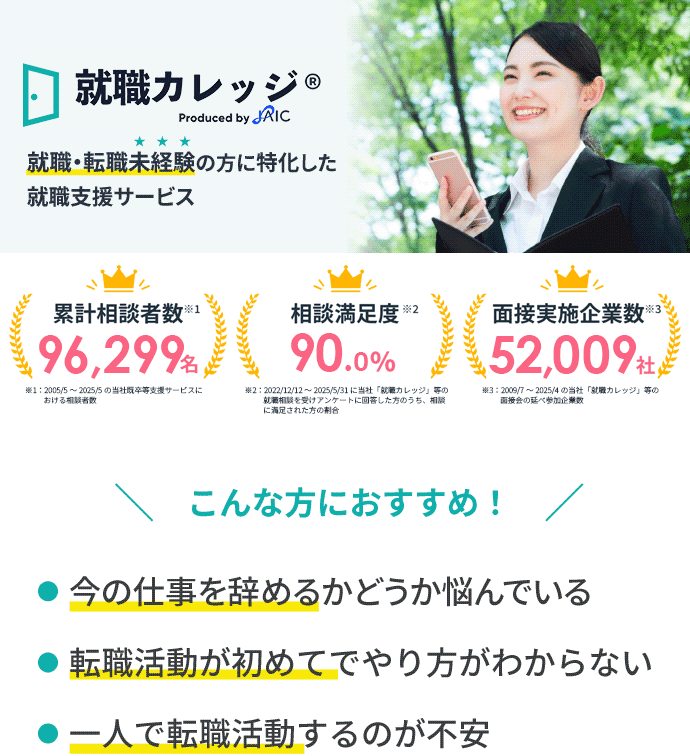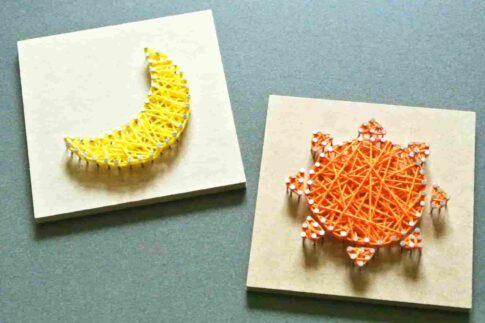「半年で退職するのは気まずい」と悩んでいる方は少なくないでしょう。周囲への申し訳なさや、反応を気にして退職を躊躇しているかもしれません。しかし気まずさを感じるあまり無理に働き続けることは得策ではありません。半年での退職が悪いとは限らないためです。
本記事では、半年での退職で感じる気まずさの理由や上司への伝え方、円満退職のコツまで解説します。半年での退職を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
半年で退職することを気まずいと感じる必要はない
半年で退職することを気まずく感じる人は少なくありません。しかし正社員は民法で定められた規定により、退職の申し出から2週間で退職する権利が保障されています。実際、厚生労働省の令和2年転職者実態調査によると、直前の勤め先での通算勤務期間が「1年未満」の転職者は17.7%を占めています。
半年での退職を考える場合、周りの同僚や上司への申し訳なさや自分自身への後ろめたさを感じるのは自然なことでしょう。しかし自分のキャリアを見つめ直し、より良い職場環境を求める権利は誰にでもあります。
むしろ気まずさを感じるあまり、無理をして働き続けることはおすすめしません。心身の健康を損ねたり、自分の望むキャリアを築く機会を逃したりするためです。自分の将来のために必要な決断であれば、半年での退職を恐れる必要はないでしょう。
参考: e-Gov 法令検索『民法 第六百二十七条』
参考:厚生労働省『令和2年転職者実態調査の概況』
半年で退職するのが気まずいと感じる理由4選
半年で退職するのが気まずいと感じる理由4選は下記のとおりです。
- 周りからどう思われるのか気になるから
- お世話になった人に対して申し訳なく感じるから
- 引き継ぎが終われば手が空いてしまうから
- 仕事へのやる気がなくなり周りとの温度差を感じるから
1つずつ詳しくお伝えします。
周りからどう思われるのか気になるから
半年で退職することを気まずく感じる理由の1つは、周囲からの評価です。自分のキャリアにとっては最善の決断でも、周りからの目を気にしてしまうのは自然な感情です。
特に同僚から同じ志をもった仲間だと思われている場合、絆を断ち切る申し訳なさや辞めると伝えた時の反応が怖くなる人もいます。半年で退職すると同僚との関係性を壊す可能性があるため、大きな心理的抵抗を感じる場合もあります。
周りから「短期間で辞めていく人」というレッテルを貼られることへの懸念から、退職の決断をためらってしまう場合も少なくありません。
お世話になった人に対して申し訳なく感じるから
半年で退職することを気まずく感じる理由として、指導してくれた先輩や上司への負い目を感じる場合があります。多くの時間を割いて丁寧に仕事を教えてもらったにもかかわらず、すぐに辞めてしまうことへの後ろめたさを感じるのはよくある感情です。
特に上司や先輩が自分の業務を後回しにしてまで教育してくれた場合、思いに応えられない申し訳なさは大きいでしょう。教えてもらった技術や知識を会社のために活かせない後悔の念も生まれるかもしれません。
引き継ぎが終われば手が空いてしまうから
退職までの期間は周りよりも仕事量が減少することから、気まずいと感じる場合があります。企業は退職が決まった人に対して「中途半端な仕事を残してほしくない」という考えから、新しい業務を任せない傾向にあります。
そのため、退職までの仕事は引き継ぎ業務がメインになり、引き継ぎが終わると仕事がほとんどない状態が続くでしょう。周りの同僚が繁忙期で忙しく働いているのに対し、自分だけが手持ち無沙汰になってしまうと、居づらさや後ろめたさを感じる人も多いはずです。
仕事へのやる気がなくなり周りとの温度差を感じるから
半年で退職する際に感じる気まずさの要因は、周囲との意識の違いにもあります。自分は転職先が決まり、新天地への期待や今の仕事から解放される一方、同僚は今後も会社に残って働き続けます。
立場の違いは仕事への姿勢や発言内容にも表れ、次第に周囲との価値観の違いを実感するようになるでしょう。退職が決まっていると、通常業務へのモチベーションがいつもよりも高い状態にはならないはずです。
今まで頻繁に交わしていた業務の相談や雑談が少なくなることで周囲との距離感が生まれ、居心地の悪さを感じる人も多いでしょう。
半年で退職すると迷惑になる理由3選
半年で退職すると迷惑になる理由3選は下記のとおりです。
- 採用や研修にかかった費用・時間が無駄になる
- やっていた業務を周りに引き継がなければならない
- 人員配置を見直さなければならない可能性がある
1つずつ詳しくお伝えします。
採用や研修にかかった費用・時間が無駄になる
半年で退職することで企業に迷惑になる理由の1つは、採用や研修にかけた投資が無駄になることです。就職みらい研究所の就職白書2020によると、新卒採用には1人あたり93.6万円、中途採用では103.3万円のコストがかかります。
採用活動は経費だけでなく、面接や入社後の研修をするための時間も必要です。新入社員に対して戦力になる人材だと期待しているからこそ、企業は人材育成に投資しています。半年という短い期間で退職すると、企業は再び採用活動にコストをかけなければいけません。
参考:就職みらい研究所『就職白書2020』
やっていた業務を周りに引き継がなければならない
半年で退職する場合でも、業務は誰かに引き継がなければなりません。引き継ぎ作業は、自身の業務で手一杯の同僚への負担を増やすことになります。
特に退職までの期間が短い場合は、十分な引き継ぎ期間を確保できないため、同僚は通常業務に加えて新たな業務をかかえる必要があります。突然の業務負担はチーム全体の業務効率を低下させる要因ともなり得るでしょう。
人員配置を見直さなければならない可能性がある
半年での退職は企業の人員計画にも影響を与えます。特に半年後の戦力として期待され、重要なプロジェクトのメンバーとして組み込まれている場合、企業は代替要員を確保しなければなりません。
新しい人材を探して育成するまでの間、他のメンバーで業務を補う必要があり、チーム全体の業務バランスを大きく見直す手間が発生します。
半年で退職するデメリット4選
半年で退職するデメリット4選は下記のとおりです。
- 応募書類に半年で退職した経歴を書かなければならない
- 半年で退職した経歴が転職で不利になる可能性がある
- 失業保険を申請できない
- スキルや実務経験が身につかない
1つずつ詳しくお伝えします。
応募書類に半年で退職した経歴を書かなければならない
半年で退職した場合でも経歴は必ず履歴書に書かなければなりません。正社員として働いた経験はたとえ短期間であっても、職歴として記載する必要があるためです。ちなみに3か月以上の空白期間がある場合は、その間の活動内容も記載が必要です。
経歴を履歴書に記載しなかった場合、経歴詐称とみなされる可能性があります。経歴詐称が発覚した場合、下記のような深刻な事態を招く場合があります。
- 内定を取り消される
- 懲戒解雇や損害賠償の対象となる場合がある
- 企業から信頼を失い働きづらくなる
半年という短い期間であっても正直に経歴を記載しましょう。
半年で退職した経歴が転職で不利になる可能性がある
半年で退職した経歴は、転職活動に大きなハンディとなる可能性があります。企業は短期間の退職に対して、働く意欲や継続性の面から不安だと思われる傾向にあるためです。半年で退職した経歴が不利に働く場合、具体的に起こり得る状況は下記をご覧ください。
- 書類選考で通過しづらくなる
- 企業に「すぐ辞めるのではないか」と思われる可能性があり
- 半年の経験はスキルがあるとみなされない場合がある
半年での退職は、その後の転職活動に影響を与える可能性があると言えるでしょう。
失業保険を申請できない
半年で退職する場合、失業保険を受給できないデメリットがあります。失業保険とは失業中も安定した生活を送り、早く再就職をするための支援として給付される制度です。在職中に、加入者が納付した保険料をもとに給付されます。
自己都合で退職する場合、失業保険を受給するためには「離職前2年間に12か月以上の被保険者期間がある」条件を満たす必要があります。そのため半年で退職した場合、受給資格を得ることができません。
失業保険が受給できないと、生活費や次の転職に影響を与える可能性があります。具体的な影響は下記のとおりです。
- 転職先が決まるまで金銭面に余裕がなく、貯金を崩す場合がある
- お金がない焦りから、希望する条件に満たない転職先に応募してしまう
- 税金や年金の負担が重いと感じるようになる
半年での退職を考える際は、転職先の目途や十分な貯蓄があるかを慎重に検討しましょう。
参考:厚生労働省『Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。』
スキルや実務経験が身につかない
半年での退職は、実務経験の面でも大きなデメリットになる可能性があります。実務経験を積んでいるとみなされるためには、一般的に1〜3年以上の業務経験が必要です。
半年の在籍期間では、1つのプロジェクトの立ち上げから完了までを経験することが難しく、実践的なノウハウを積めていないと判断される傾向にあります。次の転職先でアピールできる経験やスキルが乏しいまま、転職活動をスタートさせる状態となるでしょう。
気まずさを感じても半年で退職した方がいいケース4選
気まずさを感じても半年で退職した方がいいケース4選は下記のとおりです。
- 職場でハラスメントが横行している場合
- 入社前に聞いていた条件と明らかに異なる場合
- 働き続けると体や心がボロボロになると思った場合
- 職場の文化や価値観があまりにも合わない場合
1つずつ詳しくお伝えします。
職場でハラスメントが横行している場合
半年で退職することを気まずく感じても、職場でハラスメントを受けている場合は早期の退職を検討しましょう。
ハラスメントの多くは個人の力だけでは解決が難しい問題です。また、ハラスメントを受けている状況下では本来の実力を発揮することもできません。精神的なストレスが蓄積することで、将来的に心身の健康を損なう可能性もあります。
まずは社内の人事部門やハラスメント相談窓口に状況を報告してみましょう。それでも改善が見込めない場合は、自分の健康を守るために転職を視野に入れるべきです。気まずさを感じるよりも、自分の心身の健康を優先しましょう。
入社前に聞いていた条件と明らかに異なる場合
入社前に説明された条件と実態が大きく異なる場合は、たとえ気まずさを感じても半年で退職した方がいいでしょう。具体的には次のような条件の違いが生じた場合は、退職を考えても不自然ではありません。
- 説明された給与や待遇が実際より低い
- 残業が「ほとんどない」と聞いていたが、当たり前のように長時間労働がある
- 配属予定の部署や担当業務が、面接時の説明と異なる
- 転勤なしのと聞いていたが、突然の転勤を命じられる
早期に見切りをつけ新たな環境を探すことも、賢明な選択といえるでしょう。
働き続けると体や心がボロボロになると思った場合
半年間働いたうえで、このまま働き続けると体や心がボロボロになると思った場合は、たとえ気まずくても退職したほうがいいケースです。毎日の業務に強いストレスを感じたり、休日も仕事の不安から解放されなかったりする場合は早めの決断が必要です。
無理に働き続けた場合、下記のような深刻な事態を招く可能性があります。
- 慢性的な睡眠不足や不眠症に陥る
- 食欲不振や胃腸の不調が続く
- 不安障害やうつ病を発症する
気まずさを感じて退職を躊躇するよりも、心身の健康を最優先に考えることが重要です。体調を崩してからでは、次のキャリアへの準備もできません。
職場の文化や価値観があまりにも合わない場合
企業文化があまりにも合わない状況とは、具体的には次のとおりです。
- 仕事に対してネガティブな社員が多い
- スキルアップしようとする風潮がない
- 残業や休日出勤が美徳とされる雰囲気がある
- 飲み会や社内イベントへの参加が暗黙の義務になっている
価値観の違いを感じながら働き続けると、モチベーションが低下するだけでなく、仕事の質が落ちる可能性があります。また心身の不調にも繋がり、キャリア形成の機会損失にもなり得ます。自分の価値観に合った環境を探すことが、賢い選択といえるでしょう。
半年の在籍期間でも円満に退職するポイント4選
半年の在籍期間でも円満に退職するポイント4選は下記のとおりです。
- 退職を切り出すタイミングは就業規則を参考にする
- 退職意思が固まったら早めに上司へ伝える
- スムーズに引き継ぎできるよう対応する
- お世話になった人へ感謝の気持ちを伝える
1つずつ詳しくお伝えします。
退職を切り出すタイミングは就業規則を参考にする
円満な退職のためには就業規則に定められた期間を守ることが大切です。就業規則で定められた期間よりも遅く退職の意思を伝えると、引き継ぎや後任の採用など会社側の負担が大きくなります。
特に長期プロジェクトへの参加が予定されている場合や繁忙期が近づいている場合は、就業規則の定めよりも早めに退職の意思を伝えましょう。少しでも早く伝えることで会社側は十分な準備期間を確保でき、後任の人員を手配できるためです。
自分の都合だけでなく会社の状況も考慮に入れたうえで、退職のタイミングを決めることが大切です。今の会社と円満に退職することは、将来のキャリアにもプラスになるでしょう。
退職意思が固まったら早めに上司へ伝える
退職を決意したら、最初に直属の上司に伝えることが基本です。退職の意思は会社の正式なルートを通じて伝えることで、引き継ぎもスムーズに進めやすくなります。
ただし、上司とのトラブルが原因で退職する場合は、人事部門に相談することをおすすめします。人事部門は中立的な立場から状況を判断し、適切なアドバイスをくれるでしょう。
注意点は、退職の相談を同僚や取引先にはしないことです。たとえ親しい間柄でも噂という形で上司の耳に入ると信頼関係が損なわれ、気まずい雰囲気になる可能性があります。退職の意思は、最初に上司か人事部に伝えることが円満に退職するポイントです。
スムーズに引き継ぎできるよう対応する
半年で退職する場合でもスムーズに引き継ぎをすることで円満退職が可能です。退職を伝えた直後から、マニュアル作成に取り掛かりましょう。スムーズに引き継ぎをするためには、具体的に下記の点に気を配る必要があります。
- 日常的な業務の手順書
- 取引先との連絡方法や注意点
- トラブル時の対処方法
- 必要なパスワードや各種アカウント情報
引き継ぎの準備が不十分だと退職後も問い合わせが頻繁にある状態が続き、気まずい関係が生まれかねません。しっかりとした準備で、お互いが気持ちよく離れられる環境を整えましょう。
お世話になった人へ感謝の気持ちを伝える
半年の期間で退職することに気まずさを感じても、周囲の人々への感謝の気持ちを丁寧に伝えれば、円満な退職に繋がります。誠実な態度で感謝の気持ちを伝えることが重要です。
同僚への挨拶ももちろん大事ですが、特に時間を割いてまで仕事を積極的に教えてくれた、上司や先輩への感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。短期間でも熱心に指導してくれた時間は、少なくとも次のキャリアの貴重な一歩となったはずです。
誠実な姿勢で感謝を伝えれば、半年の退職であっても互いに気持ちよく次のステップに進めるでしょう。
半年で退職する時の伝え方3パターン【例文付き】
半年で退職する時の伝え方3パターンを例文付きでお伝えします。
- 直接上司と会って退職を伝える時
- 電話で退職を伝える時
- メールで退職を伝える時
ぜひ、参考にしてください。
直接上司と会って退職を伝える時
直接上司と会って退職を伝える時は、次のポイントを押さえましょう。
- 事前にアポイントを取り2人きりで話せる場所を選ぶ
- 感謝の言葉から切り出し終始丁寧な言葉遣いを心がける
- 退職理由は前向きな内容に留め、ネガティブな発言は避ける
- 引き継ぎへの協力姿勢を示し責任感をアピールする
直接上司と合って退職を伝える時の例文は、以下を参考にしてみてください。
「半年間という短い期間ではありましたが、○○部署で多くのことを学ばせていただき、ありがとうございました。この経験を活かしてさらなる成長を目指すため、大変申し訳ありませんが、○月末日をもって退職させていただきたく存じます。残りの期間は、引き継ぎをしっかりと行い、ご迷惑をおかけしないよう努めさせていただきます」
感謝と誠意を伝えたうえで、前向きな姿勢で退職の意思を伝えることが大切です。
電話で退職を伝える時
電話で直接退職の意思を伝える時は次の点に注意しましょう。
- 上司に「相談したいことがある」と電話でアポイントを取る
- 通話環境の良い静かな場所で電話をかける
- 用件は手短にし丁寧に伝える
- 具体的な退職時期と引き継ぎの進め方を明確に説明する
電話で退職を伝える時の例文は、以下をご覧ください。
「突然のお電話で申し訳ありません。入社から半年という短い期間ではございますが、一身上の都合により○月末日をもって退職させていただきたく存じます。本来であれば直接お会いしてご説明すべきところ、電話での報告となり大変申し訳ございません。」
退職の意思は直接会って伝えることが最も望ましい方法です。それでも電話という手段を使う場合は、誠意を持って丁寧に意思を伝えることが重要です。
メールで退職を伝える時
退職の意思は直接会って伝えることが最も望ましい方法です。やむを得ずメールで伝える場合は、次のポイントを意識しましょう。
- 簡潔かつ丁寧な文面を心がける
- 退職時期は明確に記載する
- 引き継ぎへの協力姿勢を示す
- 送信前に誤字脱字をチェックする
メールでの退職連絡の例文は、以下を参考にしてみてください。
○○部長
お疲れ様です。△△課の□□です。
突然のご連絡で大変恐縮ではございますが、一身上の都合により、○月末日をもって退職させていただきたくご相談申し上げます。
本来であれば直接ご説明すべきところ、メールでのご連絡となりましたことを深くお詫び申し上げます。なお、残りの期間につきましては、引き継ぎ業務に全力を尽くす所存でございます。
これまでのご指導に心より感謝申し上げます。
何卒ご理解いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
メールで退職を伝える時は、相手に誤解を与えない文章になっているか慎重に見直すことが大切です。
半年で退職しても転職活動を成功させるポイント4選
半年で退職しても転職活動を成功させるポイント4選は下記のとおりです。
- 在職中に転職活動を始めておく
- 企業が納得できる退職理由を用意する
- 自己分析をして転職活動の方向性を定める
- 転職エージェントに相談する
1つずつ詳しくお伝えします。
在職中に転職活動を始めておく
半年で退職しても転職活動を成功させるためには、早い段階から転職活動を始めることが必要です。転職活動は一般的に2〜3か月程度の期間が必要とされるため、退職後に活動を始めると、長期間の無収入状態に陥る可能性があります。
また、半年未満の退職は有給休暇が使えない場合が多く、失業保険も受給できません。そのため退職後に転職活動を始めると、焦りから希望の条件に満たない仕事を選択せざるを得なくなる場合があります。
在職中に転職活動をスタートさせてキャリアの選択肢を広げておきましょう。
企業が納得できる退職理由を用意する
面接では半年の退職理由について質問される傾向にあります。回答次第で面接の結果に影響するため、説得力のある理由を準備しておきましょう。退職理由を説明する際に気を付けるポイントは、下記のとおりです。
- 前職の会社や上司の悪口は言わない
- 自分にも改善の余地があったと率直に認める
- 半年間の就業では前向きな学びや気づきがあった点を伝える
- 今後のキャリアビジョンと結びつけて説明する
- 次は長期的に働く意思があると伝える
状況別の回答例をぜひ参考にしてください。
【適性の不一致を感じた場合】
「営業職として入社しましたが、自身の適性をじっくり考えた結果、事務職の方が力を発揮できると気づきました。この経験を通じて自己理解が深まったと考えています」
【キャリアアップを目指す場合】
「半年間の経験を通じて、より専門性の高い業務に携わりたいと考えるようになりました。決断すべきタイミングに悩んだ結果、若いうちにキャリアの方向性を見直すべきだと判断しました」
半年での退職を単なる失敗ではなく次のステップに向けた必要な決断として前向きに説明することで、面接官の理解を得やすくなります。
自己分析をして転職活動の方向性を定める
半年で退職を決意した場合、次の転職を成功させるためには徹底的な自己分析が必要です。自己分析をすることで同じ失敗を繰り返さず、自分に合った職場を見つけられるでしょう。自己分析をする際は、下記の項目を明確にしてみてください。
| 退職に至った要因 | ・なぜ今回半年で退職しなければいけなかったのか ・仕事内容は自分の適性に合っていたか ・職場の人間関係に問題なかったか ・会社の価値観や文化は自分に合っていたか |
| 理想の職場を整理 | ・希望する働き方(勤務時間、場所など) ・自分に合っていないと思う職場環境 ・重視する企業文化や雰囲気 ・キャリアアップ機会の有無 |
| 将来のキャリアビジョン | ・身につけたいスキルや資格 ・目指したい役職や立場 ・達成したい具体的な目標 |
自己分析を通じて、次の転職選びの具体的な基準を設定できます。
転職エージェントに相談する
半年で退職する場合、転職エージェントの活用は有効な選択肢の1つです。転職エージェントに相談する主なメリットは下記のとおりです。
- キャリアアドバイザーと一緒に半年での退職理由を整理できる
- 半年の退職でも受け入れてくれる可能性が高い企業を紹介してもらえる
- 転職エージェントからの推薦で面接機会を得られる場合がある
- 面接対策や条件交渉のサポートを受けられる
転職エージェントは企業の内部情報にも詳しいため、選考で採用担当者が重視しているポイントや職場の雰囲気などを共有してくれます。社会人経験の少ない人や業界未経験の転職でも、エージェントのサポートを受けることで希望通りの転職を実現しやすくなるでしょう。
まとめ
半年で退職することを気まずく感じるのは自然な感情です。しかし、無理に我慢し続ける必要はありません。大切なのは経験を次のステップに活かすことです。
しかし、闇雲に転職活動を始めるのではなく次の点に気をつけましょう。
- 退職までの期間は誠実に対応する
- 次の転職を成功させるため早めの準備を始める
- 自己分析を通じて自分に合った職場を知る
転職活動に不安を感じる方は、経験豊富なキャリアアドバイザーに相談することをおすすめします。プロのアドバイスを受けることで、経験やスキルを活かせる新しい職場が見つかるはずです。
半年で退職することに関するよくある質問2選
半年で退職することに関するよくある質問2選は下記のとおりです。
- 半年で退職するのは不利ですか?
- 3月いっぱいで退職する場合はいつ言う?
ぜひ、参考にしてください。
半年で退職するのは不利ですか?
半年で退職するのは転職活動で一定の説明が必要になりますが、必ずしも不利になるとは言い切れません。
「より専門性の高い仕事を目指したい」「自分の適性に合った職種にチャレンジしたい」など、退職理由を前向きに説明することが大切です。前向きな退職理由は、むしろ自己理解の深さとして評価されることもあります。
3月いっぱいで退職する場合はいつ言う?
3月いっぱいで退職する場合は、遅くとも2月上旬までに退職の意思を伝えるのが一般的です。ただし、いつまでに退職意思を伝えたらよいかは会社の就業規則によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
特に3月のような年度末は、人事異動や新年度の体制づくりなど、会社にとって忙しい時期と言えます。少しでも早く退職意思を伝えることで、企業は余裕を持って次の準備に取り掛かれるでしょう。