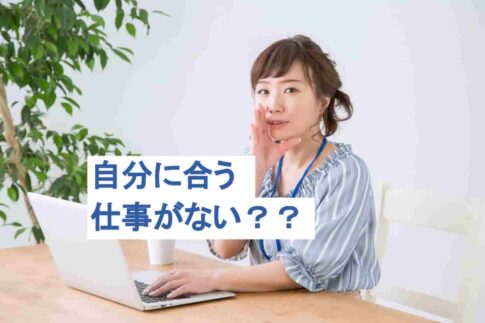キャリアカウンセラーとは、就職や転職、キャリアに関する相談を受け、相談者の希望や状況に応じて適切な助言やサポートを行う仕事です。
この記事では、キャリアカウンセラー(キャリアコンサルタント)の仕事内容や資格の取得方法、主な就職先などについて詳しく解説します。
人の相談に乗る仕事に興味がある方や、自分自身が仕事に悩んだ経験から「今度は誰かを支える側になりたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
キャリアカウンセラーとは?
キャリアカウンセラーは、就職や転職、キャリアアップなどに関する相談に応じ、適切なアドバイスを行う専門家です。
キャリアカウンセラーが提供する主なサポートは、以下の通りです。
- 自己分析の支援
- キャリアプランの策定
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 面接対策
- 情報提供(転職市場・業界動向など)
- 求人紹介(エージェント業務の場合)
なお、キャリアカウンセリング自体は資格がなくても行うことができます。
ただし「キャリアコンサルタント」と名乗るには、キャリアコンサルタント試験に合格し、名簿に登録することが必要です。
キャリアカウンセラーとキャリアコンサルタントの違い
キャリアカウンセラーとキャリアコンサルタントの違いは「国家資格の有無」です。
キャリアカウンセラーとして働いたり、自分を「キャリアカウンセラー」と呼称したりするうえで資格は必要ありませんが、「キャリアコンサルタント」と名乗るには国家資格の取得が必要です。
| キャリアカウンセラー | キャリアコンサルタント | |
|---|---|---|
| 定義 | キャリア支援を行う職業の総称 | 国家資格に基づく正式な職業名称 |
| 資格要件 | 特に法的な資格要件なし | 国家資格の取得が必要 |
| 名称使用 | 「キャリアカウンセラー」と自由に名乗れる | 資格取得者のみ「キャリアコンサルタント」と呼称可能(※) |
| 業務内容 | キャリア相談、就職・転職支援など | キャリア相談、就職・転職支援など(基本的にはキャリアカウンセラーと同じ) |
※紛らわしい名称に関しても資格取得者のみ使用可(例:キャリア・コンサルタント、キャリアコンサルタント専門士など)
キャリアカウンセラーとキャリアアドバイザーの違い
キャリアカウンセラーとキャリアアドバイザーの違いは「支援の方向性」です。
両者に明確な線引きはありませんが、キャリアカウンセラーはどちらかというと、相談者の心理的側面にも配慮しながら中長期的なキャリア支援を行う傾向があります。
一方でキャリアアドバイザーは、就職・転職活動の現場において、求人紹介や面接対策など、より実務的で具体的なアドバイスを行う役割を指すことが一般的です。
| キャリアカウンセラー | キャリアアドバイザー | |
|---|---|---|
| 定義 | キャリア支援を行う職業の総称 | 就職・転職活動をサポートする実務的なアドバイザー |
| 資格要件 | 特に法的な資格要件なし | 特に法的な資格要件なし |
| 名称使用 | 「キャリアカウンセラー」と自由に名乗れる | 「キャリアアドバイザー」と自由に名乗れる |
| 主な役割 | 心理面を含めた深い相談対応・支援 | 就職・転職に関する実務的なアドバイス |
キャリアカウンセラーの平均年収
キャリアカウンセラーの平均年収は、551.4万円です(※1)。
日本人全体の平均年収が460万円(※2)であることから、比較的高めの水準にあるといえるでしょう。
キャリアカウンセラーの収入は、以下のような要素によって構成されます。
- 基本給
- インセンティブ(人材紹介会社の場合)
- 経験や保有資格による昇給
- 勤務先による給与差(企業、教育機関など)
キャリアカウンセラーの給与体系は、所属する機関によって大きく異なります。
たとえば人材紹介会社(エージェント)に勤務する場合、基本給に加えて「インセンティブ」が支給されるケースが多いことが特徴です。
インセンティブとは、担当した求職者の就職や転職が成功した際に支払われる手当を指します。この仕組みにより、実績を多く上げたキャリアカウンセラーは平均を大きく上回る収入を得ることも可能です。
※1 出典:厚生労働省「キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
※2 出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
キャリアカウンセラーの5つの仕事内容
キャリアカウンセラーは、相談者の仕事の悩みや課題に寄り添い、より良い選択ができるようにサポートする仕事です。
具体的には「キャリア相談・カウンセリング」に関わる業務のほか、将来の目標に向けた道筋を一緒に考える「キャリアプランニング」などを行います。
では、キャリアカウンセラーの代表的な仕事を見ていきましょう。
1. キャリア相談・カウンセリング
キャリアカウンセラーの中心的な業務が、相談者とのキャリア相談・カウンセリングです。
具体的には、これまでの職業経験やスキル、価値観、興味・関心などを丁寧に聞き取り、今後の方向性を一緒に整理していきます。
たとえば「今の仕事に不満はあるけれど、何がしたいのか分からない」といった漠然とした悩みに対しては、自己理解を深める問いかけを通じて、本人も気づいていなかった適性や志向を引き出すことが大切です。
答えを一方的に与えるのではなく、あくまでも相談者が自らキャリアについて考えるきっかけを提供することがキャリアカウンセラーに求められます。
2. キャリアプランニング
キャリアプランニングとは、将来的な目標の設定から、そこに至るまでのステップ、必要なスキル・資格の取得などを相談者と一緒に考えていく業務です。
たとえばIT業界への未経験転職を希望する営業職の方がいた場合、まずは現在のスキルを整理し、未経験からでも挑戦しやすいIT系の職種を検討します。
そのうえで、資格の取得やポートフォリオの作成を含め、実行可能なロードマップをライフプランも踏まえて組み立てていきます。
このようにキャリアプランニングは、単なる助言ではなく、相談者が自分らしいキャリアを主体的に歩めるようにサポートする仕事といえるのです。
3. 応募書類・面接対策のサポート
応募書類や面接対策のサポートとは、相談者の強みや経験を引き出し、それを企業に効果的に伝えるための支援をする仕事です。
履歴書や職務経歴書の作成では、応募先が求める人材像に合わせた自己PRの方法などをアドバイスします。
面接対策では、質問に対する答え方の練習だけでなく、話し方や表情といった“非言語面”についても指導します。模擬面接を通じて具体的なフィードバックを行い、相談者が自信を持って本番に臨めるようにサポートすることも大切です。
相談者の魅力を言語化し、未来への一歩を後押しできるという点でやりがいのある仕事といえるでしょう。
4. 求人紹介・マッチング
すべてのキャリアカウンセラーが担当するわけではありませんが、求人紹介やマッチングを仕事の一環として行うこともあります。
たとえば人材紹介会社で働く場合、求職者からの「年収600万円以上」「フレックス制度あり」といった希望に基づき、該当する企業や求人をリストアップします。
そのうえで、相談者の価値観や理想の働き方も踏まえながら、企業側のニーズと照らし合わせて最適な求人を提案することが大切です。
短期的な転職成功だけでなく、求職者が長く満足して働ける職場との出会いを意識した、丁寧で責任感のある対応が求められる仕事といえるでしょう。
5. セミナーや講座の講師
キャリアカウンセラーの中には、セミナーや講座の講師として活動する方も少なくありません。
大学のキャリアセンターや公共職業訓練施設などが実施するセミナー・講座に登壇し、「効果的な自己PRの作り方」や「30代からのキャリアチェンジ成功法」といったテーマで講義を行うケースが多く見られます。
集団向けの支援では、ファシリテーション力(場をまとめ、参加者全体の理解を促す力)に加え、的確な情報提供力や時間管理のスキルも求められます。
キャリアに関わる知識を、幅広い層に向けて伝えることにやりがいを感じる方に向いている仕事といえるでしょう。
キャリアコンサルタントの国家資格を取る方法
「キャリアコンサルタント」と名乗って仕事をするには、国家資格であるキャリアコンサルタント試験に合格し、専用の名簿に登録することが必要です。
また、キャリアコンサルタントの上位資格として「キャリアコンサルティング技能士」があり、こちらの試験に合格すると「◯級 キャリアコンサルティング技能士」と名乗ることができます。
ここでは上記2つの国家資格について、それぞれの受験資格や取得期間などについて解説します。
キャリアコンサルタント
国家資格キャリアコンサルタントは、基本的なキャリア支援に関する知識とスキルを証明する資格です。
キャリア系の国家資格の中では“入門レベル”と位置づけられており、「相談者に安心してキャリアコンサルティングを実施できるレベル」とされています。
試験は年に3回実施されており、学科試験・論述試験・面接試験(ロールプレイ)の3つで構成されています。
すべての試験に合格したあとに資格登録を行うことで、「キャリアコンサルタント」と名乗って仕事をすることが可能です。
受験資格
キャリアコンサルタント試験は、次のいずれかの条件を満たすことで受験できます。
- 厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した方
- 労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力開発および向上のいずれかに関する相談に関し、3年以上の経験を有する方(条件あり)
- 技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験または実技試験に合格した方
キャリア相談の経験が3年未満の方は、基本的には厚生労働大臣が認定する講習(養成講習)の受講が必要です。講習期間は3か月〜6ヶ月ほどで、受講料は30万円ほどです(※)。
※教育訓練給付金の支給を受けることで受講料を減額できる可能性あり
出典:キャリアコンサルティング協議会「国家資格キャリアコンサルタント試験|受験概要」
取得期間
キャリアコンサルタント試験合格までの期間は、養成講習に通う場合は8〜10か月ほどが一般的です。
試験の勉強時間は200時間が目安とされており、1日2時間の勉強時間を確保できれば3〜4か月で合格を目指せます。
たとえば11月の試験を受験する場合、3月〜4月に養成講習を開始し、7月頃に修了して受験資格を得ます。その後は3〜4か月かけて、学科・論述の対策や、面接試験(ロールプレイ)の練習などを通じて本番に向けた準備を進めていく流れが基本です。
なお、実務経験が3年以上ある方の場合、試験機関に認められれば養成講習を受けずに受験できます。
合格率
キャリアコンサルタント試験の合格率(学科・実技同時受験者の合格率)は、約50〜60%です。
試験実施機関が2つあり、それぞれの機関で合格率は微妙に異なりますが、学科試験・実技試験ともに合格率は毎回60〜70%で推移しています。
たとえば、2025年3月に実施された「第28回キャリアコンサルタント試験 試験結果(キャリアコンサルティング協議会)」を見ると、学科・実技同時受験者の合格率は54.8%です。
細かい内訳としては、学科試験の合格率が69.3%、実技試験の合格率が67.2%で、いずれも70%に迫る水準となっています。
キャリアコンサルティング技能士
キャリアコンサルティング技能士は、高度なキャリア支援スキルと実務経験を証明する資格です。
キャリアコンサルタント資格よりも上位に位置づけられており、2級は「熟練レベル」、1級は「指導者レベル」と位置づけられています。
試験は、2級は年に2回、1級は年に1回実施されており、学科試験・論述試験・面接試験(ロールプレイ)の3つで構成されています。
試験に合格すると合格証書が交付され、「◯級 キャリアコンサルティング技能士」と名乗ることが可能です。
受験資格
キャリアコンサルティング技能士試験の受験資格は、次の通りです。
- 1級:10年以上の実務経験を有する者(3年以上9年未満でも条件を満たす場合は受験可)
- 2級:5年以上の実務経験を有する者(3年以上9年未満でも条件を満たす場合は受験可)
どちらの試験も、ある程度の長期にわたってキャリア支援業務に携わってきた実績が求められるため、誰でもすぐに受験できるわけではありません。
ただし実務経験が3年以上ある場合は、一定の条件を満たせば受験できます。詳しくは、こちらの「キャリアコンサルティング協議会」のページ内にある「受検資格」の欄をご確認ください。
出典:キャリアコンサルティング協議会「国家資格キャリアコンサルティング技能検定|受験概要」
取得期間
キャリアコンサルティング技能士試験合格までの期間は、2級の学科試験でいうと、1日2時間の勉強時間を確保できる方は4~5か月で合格を目指せる可能性があります。
1級の学科試験は難易度がやや高くなるため、プラスして1〜2か月程度の学習期間を確保しておくと良いでしょう。
実技試験に関しては1級・2級ともに難易度が高く、経験やスキルによって必要な対策期間が大きく異なるため、一概に「◯か月で取得できる」とは言い切れません。
技能士として活動している現役カウンセラーからフィードバックをもらったり、「ロープレ練習会」に参加したりするなどして、地道に合格レベルを目指していきましょう。
合格率
キャリアコンサルティング技能士の合格率は、学科試験でいうと、1級が20〜60%、2級が50〜70%です。
一方で実技試験の合格率は、1級が10%未満、2級が10〜20%と低い水準となっています。
1級・2級ともに毎回の合格率には変動があるものの、学科試験に関してはキャリアコンサルタント試験よりも「やや難しい」というイメージを持っておくと良いでしょう。
一方で実技試験は、高度な支援能力や口頭試問への対応力が求められるため「難関」とされています。特に1級は年に1回しか実施されないため、十分な準備をして臨む必要があるでしょう。
キャリアカウンセラーの就職先5選
キャリアカウンセラーの就職先としては、ハローワークなどの公的機関や、大学のキャリアセンターが挙げられます。
その他、民間の人材紹介会社や、企業の人事部門、キャリアコーチング事業を行う会社でも活躍の場が数多く用意されています。
では、キャリアカウンセラーの主な就職先について、それぞれの特徴や業務内容を詳しく見ていきましょう。
1. ハローワークや市町村の就労支援窓口
ハローワークや市町村の就労支援窓口では、幅広い年齢層や背景を持つ求職者に対してキャリア支援を行います。
「就職支援ナビゲーター」や「キャリアコンサルティング専門職」として、失業者や若年層、子育て後の復職希望者など、様々なニーズやライフステージに応じた支援に携われる可能性があります。
民間と比べて成果主義の色が薄く、インセンティブ制度がない場合も多いので年収はやや低めです。
その一方で、より求職者に寄り添った長期的な支援ができることや、ワークライフバランスを重視した働き方を実現しやすい点は公的機関で働く魅力といえるでしょう。
2. 大学のキャリアセンター
大学のキャリアセンターは、自己分析や業界研究、エントリーシートの添削、面接対策まで、一貫した就職支援を行えることが特徴です。
キャリアコンサルタントの資格保有者を対象に、就職課の契約職員として採用されるケースが一般的です。
学生との個別面談に加え、就活セミナーの企画・運営を担当することもあります。近年では1年次からのキャリア教育に力を入れる大学が増えており、キャリア関連の授業を任されることも多くなっています。
支援対象者は学生に限られるものの、安定した職場環境で、学生の成長を長期的に支援できる点は大きな魅力といえるでしょう。
3. 転職エージェント(人材紹介会社)
転職エージェント(人材紹介会社)では、求職者と企業をつなぐマッチング業務を行います。
成果報酬型のビジネスモデルのため、転職支援が成功すればインセンティブを得られる可能性があることが特徴です。
ノルマや数字目標が課されるなどプレッシャーもありますが、実力次第で高年収を目指せるのは大きな魅力といえるでしょう。
求職者への支援だけでなく、会社によっては「リクルーティングアドバイザー(RA)」として企業の採用課題に直接関わる機会もあります。
提案力や交渉力といった営業スキルを磨ける点でも、成長機会の多い職場といえるでしょう。
4. 企業の人事部・社内キャリア相談窓口
企業の人事部やキャリア相談窓口では、社員一人ひとりのキャリア形成と人材戦略の両立を担います。
近年は、終身雇用制度の見直しや、ジョブ型雇用の普及といった背景もあり、「社内キャリアカウンセラー」などの専門職を設ける企業が増えています。
具体的には、キャリア研修の企画や、社員との面談などを通じて、仕事への主体性の向上や、適材適所の人材配置を支援しているキャリアカウンセラーは少なくありません。
社員の成長を継続的に支援できるだけでなく、企業戦略と連動しながら個人と組織の両方に貢献できる点において、やりがいが大きいポジションといえるでしょう。
5. キャリアコーチング事業を行う企業
キャリアコーチングとは、個人のキャリア目標達成に向けた、1対1の対話を中心とした支援のことです。
キャリアコーチングを提供する企業は求人紹介を行わず、20〜40代の転職希望者やキャリアに悩む社会人に、理想のキャリア実現に向けた“伴走型支援”を提供することが一般的です。
具体的には、キャリアの棚卸しや強みの言語化、転職活動の方向性の整理、選考対策まで一貫してサポートします。
「コーチング(相談者が自ら答えを見つける支援)」を土台にしているため、カウンセリングスキルや心理学の知識を活かしたい方にとってはやりがいのある仕事といえるでしょう。
キャリアカウンセラーに向いている人の3つの特徴
キャリアカウンセラーは、相談者の話にじっくり耳を傾けることで気持ちの整理や意思決定をサポートする仕事のため、自分が話すよりも聞くほうが好きな人に向いています。
人の成長や変化を応援したい気持ちが強い人や、共感力が高い人も適性があるでしょう。
では、キャリアカウンセラーに向いている人の特徴を具体的に解説します。
1. 自分が話すより聞くほうが好き
キャリアカウンセラーは、「自分が話すより、相手の話をじっくり聞くのが好き」という人に向いています。なぜなら、相談者の話に丁寧に耳を傾け、本人も気づいていない価値観やニーズを引き出す力が求められる仕事だからです。
たとえば「なんとなく今の仕事に不満がある」といった漠然とした悩みに対しては、丁寧に話を聴き、適切な問いかけを通じて、相談者の“本質的な思い”を明らかにしていきます。
このように自分の意見を押し付けず、まずは相手の言葉に真摯に向き合いながら支援できる人は、キャリアカウンセラーとして高い適性があるといえるでしょう。
2. 人の成長や変化を応援したい気持ちが強い
「人の成長や変化を心から応援したい」という気持ちが強い人も、キャリアカウンセラーに向いています。相談者と一緒に不安や困難を乗り越える「強い意志」が求められる仕事だからです。
たとえば、初めての転職が不安な40代の方が「自分の年齢で転職は厳しいかもしれない…」と弱気になっていた場合でも、その不安な気持ちを受け止めたうえで、前向きな姿勢を取り戻せるように支援することが大切です。
相談者以上にその人の可能性を信じ、新たな一歩を踏み出せるように力強く伴走できる人であれば、キャリアカウンセラーとして大きなやりがいを感じられるでしょう。
3. 共感力・思いやりがある
共感力と思いやりに優れた人もキャリアカウンセラーに向いています。相談者の不安や葛藤、喜びといった感情に寄り添い、信頼関係を築くことが支援の土台になるからです。
たとえば、長年勤めた会社を辞めるか迷う相談者が「家族に迷惑をかけるのでは…」と不安を語ったときは、まずはその気持ちに共感を示します。
そのうえで、現状を変えようとする前向きな思いに焦点を当て、その姿勢を丁寧に言語化することで気持ちの整理をサポートします。
悩みや本音を安心して打ち明けられる信頼関係を築くためにも、相手の立場に立ち、感情を理解しようとする姿勢は欠かせないのです。
キャリアカウンセラーになって良かった人の声
キャリアカウンセラーになって良かった人の声としては、「人生の転機に寄り添えることにやりがいを感じる」といった意見が多く見つかります。
「自分自身の挫折経験が役に立った」「人の話を聞くのが好きな自分に合っていた」という声も少なくありません。
ここでは、現役のキャリアカウンセラーが日々の業務の中で感じている喜びや楽しさについて、3つの視点から紹介します。
1. 人生の転機に関われるので「やりがい」が大きい
キャリアカウンセラーとして働く魅力として、相談者の人生における“重要な転機”に寄り添えることを挙げる人は少なくありません。
たとえば、正社員としての働き方に不安を感じていた相談者が、カウンセリングを通じて「本当に実現したいこと」に気づき、派遣社員として働く決断をする場面に立ち会うこともあります。
「人生が変わりました」「今の仕事が楽しいです」といった感謝の言葉を直接もらう機会も多いものです。
このように、誰かのキャリアが大きく変わる瞬間に立ち会い、その一歩を後押しできたときの喜びは何物にも代えがたい魅力といえるでしょう。
2. 自分自身の挫折経験が役に立った
「過去の自分の挫折や悩みが今のサポートに活きている」と語るキャリアカウンセラーも少なくありません。
仕事やキャリアで壁にぶつかり、それを乗り越えた経験があるからこそ、同じように悩む人の不安や焦りに深く共感できるからです。
たとえば「私も同じように悩んだので、◯◯さんの気持ちは本当によく分かります」と心から伝えられる経験は、相談者との信頼構築において大きな強みとなります。
仕事の失敗や人間関係のトラブルといった過去の苦労がマイナスなものではなく、“財産”として活かせる点はキャリアアドバイザーならではの魅力といえるでしょう。
3. 人の話を聞くのが好きな自分に合っていた
「人の話を聞くのが好き」という自分の特性が、キャリアカウンセラーという仕事とぴったり合っていると感じる人も多くいます。
たとえば学生時代から友人や知人の相談を受けることが多く、「◯◯さんには相談しやすいんだよね」と言われてきた経験が相談業に役立っている、と話す方は少なくありません。
ときには、相談者の辛い過去を受け止める場面もあり、大変に感じることもあります。
とはいえ「傾聴力」や「共感力」といった自分の強みをそのまま活かせる仕事のため、むしろ楽しさを感じながら、大きなストレスなく働けているキャリアカウンセラーも多いのです。
キャリアカウンセラーの求人の探し方3選
キャリアカウンセラーの求人の探し方としては、求人サイトの「キーワード検索」を活用する方法が一般的です。
人材業界や人事領域に強い転職エージェントから求人を紹介してもらったり、公的機関や教育機関の採用ページをこまめにチェックしたりするのも有効な手段といえるでしょう。
では、キャリアカウンセラーの求人を探す方法を3つ紹介します。
1. 求人サイトでキーワード検索をする
求人サイトの「キーワード検索」とは、職種名や業務内容などの言葉を任意に入力することで求人情報を絞り込む方法です。
求人検索画面には「キャリアカウンセラー」のような検索条件は用意されていますが、思うような求人がヒットしない場合、次のような“関連ワード”を検索ボックスに入力してみることをおすすめします。
- 就労支援
- 進路指導
- 大学 キャリアセンター
- ハローワーク 相談員
- 人材会社 アドバイザー
希望の求人をピンポイントに探したい方は、複数のワードを組み合わせるなど、検索方法をぜひ工夫してみてください。
2. 人材業界や人事に強い転職エージェントを利用する
人材業界や人事領域に特化した転職エージェントを活用することも、キャリアカウンセラーの求人を効率よく探すうえで有効な方法です。
利用するメリットは、以下の通りです。
- 好条件の「非公開求人(※)」を紹介してもらえる可能性がある
- 就職エージェント、公的機関、教育機関など、幅広い求人を扱っている
- 人材業界の転職ノウハウに詳しいため、具体的な選考アドバイスを受けられる
“転職のプロ”の目線から自分に合った求人を紹介してもらいたい方は、転職エージェントをぜひ利用してみましょう。
※非公開求人:転職エージェントを通じてのみ紹介される求人のこと。人気企業の高年収求人や役職者向けなど、好条件の求人が多い傾向にある
3. 公的機関や教育機関の採用ページをチェックする
安定した職場で長く働きたい方は、公的機関や教育機関の採用ページを定期的にチェックしましょう。
たとえば大学のキャリアセンターでは、4月や10月といった新学期が始まるタイミングにあわせて契約職員や嘱託職員の募集が集中する傾向があります。
ハローワークや自治体の就労支援窓口、NPO法人が運営する就業支援施設などでは、「就労支援員」「就職支援ナビゲーター」といった名称で求人が出ていることが一般的です。
なお、キャリアコンサルタント資格が応募条件になっているケースが多いため、応募要件は事前にしっかりと確認しておきましょう。
まとめ
この記事では、キャリアカウンセラーの仕事内容や、資格の取得方法などについて解説しました。
資格がなくても働ける職場はありますが、より専門性を高めて活躍したい方は「キャリアコンサルタント」の資格取得がおすすめです。
「仕事の面で誰かの成長を支える仕事がしたい」と感じている方は、キャリアカウンセラーへの転職をぜひ目指してみましょう。
キャリアカウンセラーのよくある質問
キャリアカウンセラーの仕事に興味がある方から寄せられる「よくある質問」にお答えします。
- キャリアカウンセラーは「やめとけ」と言われるのはなぜ?
- キャリアカウンセラーとして働くには資格が必要?
- キャリアカウンセラーの資格難易度は高い?
主な理由は、国家資格であるキャリアコンサルタントを取得しても安定収入に結びつくとは限らないからです。
「キャリアコンサルタント」と名乗るには国家資格の取得が必要ですが、名乗れるからといって仕事がすぐに手に入るわけではありません。
特にフリーランスのキャリアカウンセラーとして独立する場合、カウンセリング技術だけでなく、集客やマーケティングの知識・スキルも求められます。
特定分野に強みを持ったり、公的機関などで働いたりすることで安定収入を得ることは可能ですが、「資格さえあればすぐに稼げる」という仕事ではないことは理解しておきましょう。
キャリアカウンセラーとして働くうえで、資格は必須ではありません。
人材紹介会社やキャリアコーチング会社など、こうした民間のフィールドで働く人の中には資格を持っていない人も多くいます。
しかし近年の転職市場では、国家資格「キャリアコンサルタント」の保有者が優遇される傾向が強まっています。たとえば、ハローワークや大学のキャリアセンターなどの公的機関・教育機関では、資格保有者のみを対象とした求人が出されることも少なくありません。
このように資格必須の求人もあるため、まずはキャリアコンサルタントの国家資格取得を検討することをおすすめします。
国家資格キャリアコンサルタントの試験難易度は、そこまで高くありません。
合格率は例年50〜60%程度で、たとえば公認会計士(7〜10%程度)や社会保険労務士(5〜7%程度)と比べると取得しやすい資格といえます。実際、社会人として働きながら合格している人も少なくありません。
とはいえ試験には「実技」も含まれており、相談者との模擬カウンセリング(ロールプレイ)や、それに対する口頭試問も行われます。
知識だけでは太刀打ちできない部分もあるため、養成講座や民間の資格サービスなどを使い、学科・実技両面の対策をしっかり行っておくことが大切です。