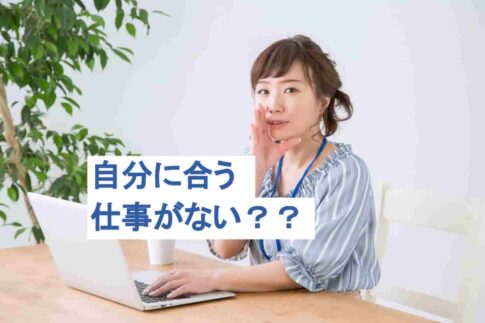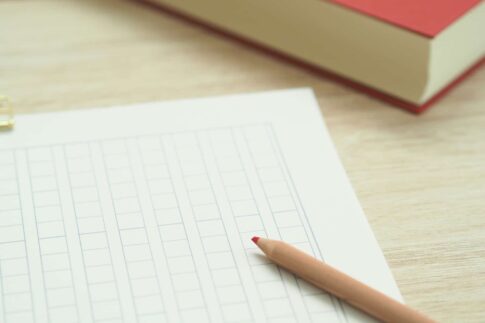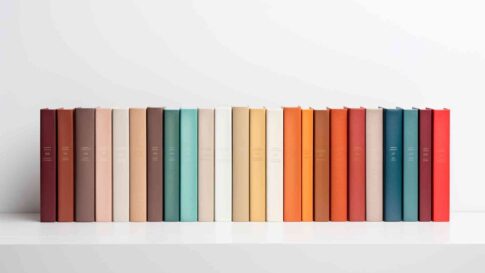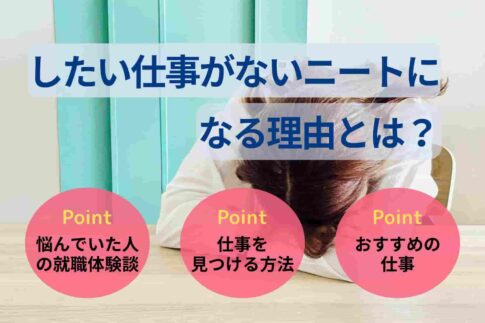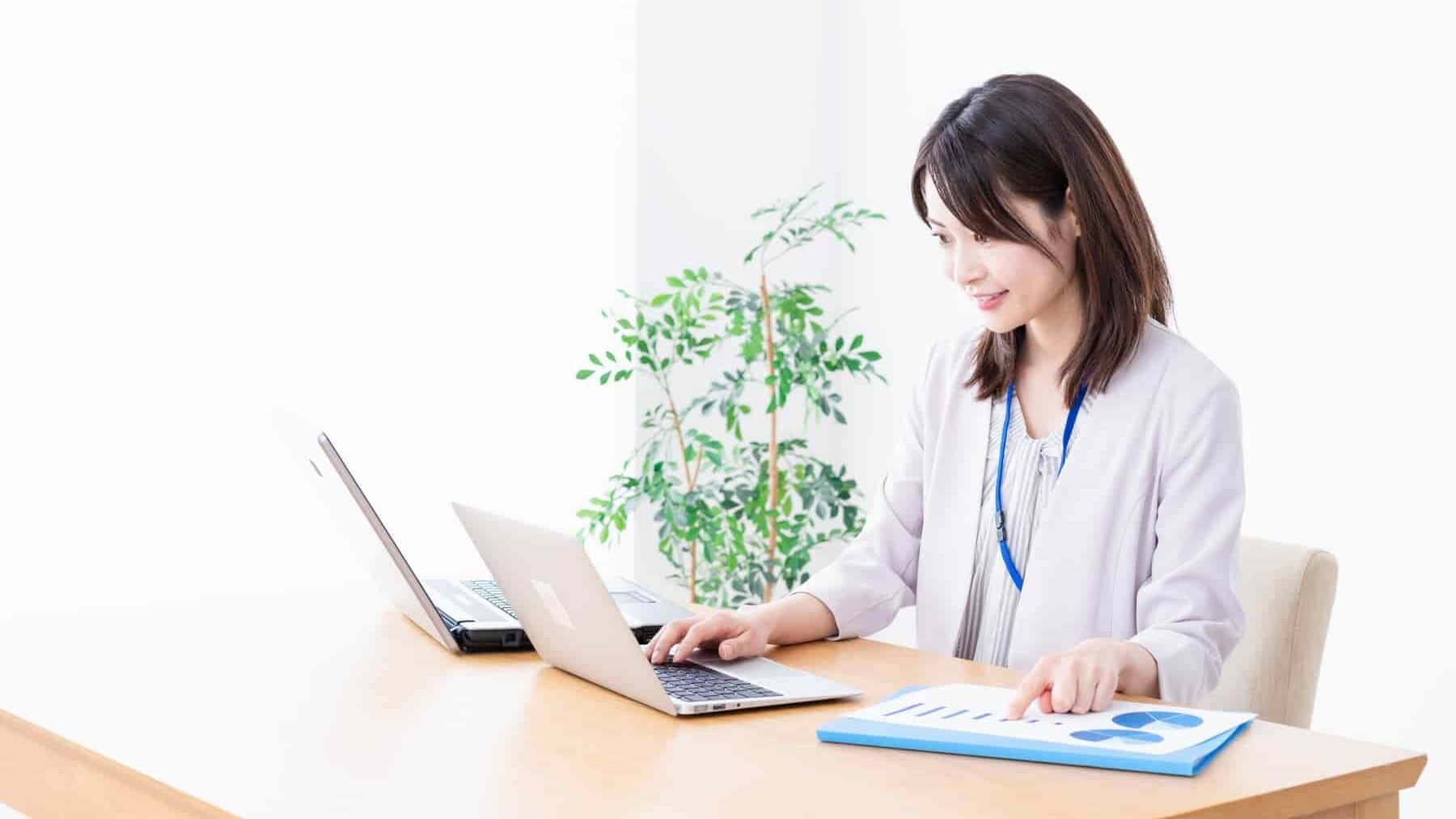
校正・校閲は、どちらも文章を読みやすく整える仕事です。
ただし校正は、誤字脱字や表記のゆれなど「文章の形式面」をチェックする作業が中心です。
一方で校閲は、内容の正確性や論理展開など「文章の中身」をチェックする作業という点に違いがあります。
この記事では、校正・校閲の違いを解説しつつ、必要なスキルや将来性、向いている人の特徴について詳しく紹介します。
落ち着いて働ける仕事を探している方や、文章に関わる仕事に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
校正と校閲の仕事内容の違い
校正は、誤字脱字や文法の誤りなどを直す「形式面」のチェックが中心です。
校閲は、文章の内容の正確性や、論理の整合性などを確認する「内容面」のチェックを主に行います。
つまり校正と校閲は、作業において“注目するポイント”が異なるのです。
どちらも文章の質や読みやすさを高めるうえで欠かせませんが、校正は「文字や表記」に注目し、校閲は「内容や論理」に注目するといった、チェック作業における役割の違いがあります。
校正とは
校正とは、主に「誤字脱字」や「表記ミス」などを見つけて修正する作業です。
読みやすく、正確な文章に仕上げることを目的に、次のような点を確認します。
- 誤字や脱字の有無
- 句読点の使い方が適切かどうか
- 文体や言葉の表記が統一されているか(「です・ます」調になっているか、送り仮名のルールが守られているかなど)
- 段落の分け方や改行の位置が適切か
表記の誤りや文体の乱れがあると、読者が読みづらさを感じたり、文章全体の印象が損なわれたりする原因となります。
そのため校正は、読み手が違和感なく内容を理解するための大切なプロセスといえるのです。
校閲とは
校閲とは、文章の内容面を重点的にチェックする作業です。
内容の正確性や論理展開が適切かどうかを確かめるため、主に以下の点を確認します。
- 事実関係や専門的な知識に誤りがないか
- 文章全体の構成や論理の流れに矛盾がないか
- 法的な問題がないか(著作権や肖像権などに抵触していないか)
校閲者は、必要に応じて取材や調査を行い、記述内容の正しさを確認することもあります。
内容に誤りや矛盾があると、読者の誤解を招いたり、信頼を損ねたりするおそれがあります。そのため読者に正確かつ信頼性のある情報を届けるうえで、校閲も欠かせないステップといえるのです。
校正・校閲の平均年収
校正・校閲の平均年収は、およそ430万円ほどです(※1)。
日本人全体の平均年収が460万円(※2)であることを考えると、やや低めの水準といえるでしょう。
出版社や編集プロダクションに校正・校閲職として正社員で勤務する場合、年収300万円台前半からスタートするケースは少なくありません。
フリーランスの校正者・校閲者として働く場合、3,000字の文章チェックで1,000円(文字単価0.3〜0.5円程度)といった低単価の案件も多く、安定した収入を得るのが難しいこともあります。
ただし、専門分野の知識(医薬・法務・ITなど)を活かし、専門性の高い校正・校閲業務に携わることで年収500万円以上を目指すことも可能です。
はじめは校正・校閲の実務経験を積み、将来的に編集者や制作ディレクターといった職種にステップアップすることで、より高い収入を手にする道もあります。
※1 出典:求人ボックス 給料ナビ「校閲の仕事の年収・時給・給料」
※2 出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
校正・校閲の仕事に必要な3つのスキル
校正・校閲の仕事をするうえで、まず身につけておきたいのが「文法・表記ルールの知識」です。
書き手の意図や文脈を正確に読み取りつつ、読者に適切なかたちで伝える「表現のセンス」や、デジタル環境に対応するための「パソコンスキル」も重要です。
ここでは、校正・校閲に特に必要な3つのスキルについて具体的に解説します。
1. 文法・表記ルールの知識
文法や表記ルールの知識は、校正・校閲に欠かせない基本スキルです。なぜなら、文章の正確さや読みやすさを支える土台となる力だからです。
たとえば「ウェブサイト」「Webサイト」のように表記が混在していると読者が違和感を覚える可能性があるため、適切な表記へと統一する力が求められます。
なお、校正・校閲者は『記者ハンドブック』などの基準に従い、「できる/出来る」や「など/等」の使い分けを判断することが一般的です。
文法や表記ルールの知識は文章を読みやすく整えるうえで欠かせないため、特に校正者として働くうえで必要なスキルといえるでしょう。
2. 表現のセンス
表現のセンスも、校正・校閲の仕事をするうえで重要なスキルです。
書き手の意図や文脈を正しく読み取り、伝わりやすい表現に変える力が求められるからです。
たとえば「35歳までに転職しないとまずい」という記述があった場合、読み手によってはプレッシャーを感じるかもしれません。
この場合、「35歳までに転職を考える人が増えています」といった表現に修正することで、読者の不安感を和らげつつ、「早く転職するように後押ししたい」という書き手のメッセージも伝えられます。
このような「表現のセンス」も、校正者・校閲者として高めていきたい力といえるでしょう。
3. パソコンスキル
出版・編集の現場ではデジタル化が急速に進んでいるため、パソコンスキルも重要なスキルの一つです。
具体的には、以下のようなスキルが求められます。
- オフィスソフトの基本操作(Word、Googleドキュメントなど)
- DTPソフト*の使用スキル(InDesignなど)
- 校正支援ソフトの使用スキル(Just Right!など)
また、デジタル原稿への赤字入力やコメント挿入といった基本的なPC操作ができると、よりスムーズに作業を進められます。
デジタル環境に対応できるスキルも、現代の校正者・校閲者には欠かせない力といえるでしょう。
*印刷物のレイアウトや編集を行うためのソフトウェア
校正・校閲の仕事に役立つ資格3選
校正・校閲の仕事に未経験から携わりたい方や、スキルアップを図りたい方は「校正技能検定」の受検がおすすめです。
日本語力を高めたい方は「日本語検定」、Webメディアの校正・校閲に興味がある方は「Webライティング技能検定」も役に立つでしょう。
ここでは上記3つの検定について、試験内容や特徴を具体的に紹介します。
1. 校正技能検定
校正技能検定は、校正の技能を認定する唯一の検定試験です。
校正のプロフェッショナルとしての知識と技能を証明できるため、出版業界や、印刷・編集の現場で高く評価されています。
検定は初級から上級まで3段階に分かれており、上級と中級は「実技試験」と「学科試験」が実施されます。実技試験では、実際の原稿を用いた実践的な問題が出題されることが特徴です。
初級は「日本エディタースクール」主催の講座を修了し、指定科目を修得することで認定を受けられます。
校正の基本を体系的に学べるため、未経験から校正者を目指す方に特におすすめできる資格といえるでしょう。
出典:日本エディタースクール「校正技能検定試験」
2. 日本語検定
日本語検定は、日本語の総合的な運用能力を客観的に評価する資格です。
校正・校閲の基盤となる日本語力を証明できるため、就職・転職時のアピールにつながる資格として広く知られています。
1級から7級まで分かれていますが、校正者・校閲者として活躍したい方は2級を目指しましょう。なぜなら、書かれている内容の整合性や妥当性を評価する力、書き手の意図を正しく読み取る力など、校正・校閲の現場で必要とされるスキルを身につけられるからです。
“日本語のプロ”として正しい知識と実践力を磨きたい方は、日本語検定にもぜひチャレンジしてみてください。
出典:語検「日本語検定」
3. Webライティング技能検定
Webライティング技能検定は、Webメディア特有の文章作成スキルや基礎知識を証明できる資格です。
デジタルコンテンツの需要が高まる現代において、Webメディア専任の校正者・校閲者として働く人も増えています。
活躍の場が大きく広がるので、雑誌や書籍などの紙媒体だけでなく、Webコンテンツにも関わっていきたい方は取得しておきたい資格といえるでしょう。
なお、誰でも受検できるわけではなく、ヒューマンアカデミー通信講座の「WEBライティング技能検定講座」を購入・受講した方のみが受検できる点には注意が必要です。
出典:一般社団法人 日本クラウドソーシング検定協会「WEBライティング技能検定」
校正・校閲の仕事のやりがい
校正・校閲は、洗練された文章へと整えていく達成感や、知らなかった言葉・知識に出会える喜びを感じられる仕事です。
一般的には「神経質すぎる」と見なされがちな性格や細かなこだわりが、実際の業務の場面では大きな強みに変わることも魅力といえるでしょう。
では、校正・校閲の仕事で感じられる3つのやりがいを紹介します。
1. 文章を整える達成感が手に入る
校正・校閲は、いわゆる「荒削りな原稿」を整えていく過程で大きな達成感を味わえる仕事です。
自分自身の手によって、文章に次のような変化を加えられるからです。
- 曖昧だった表現が明確になり、文意がより伝わりやすくなる
- 論理の飛躍や説明不足が解消され、説得力が増す
- 冗長な部分がすっきりとし、読みやすさが向上する
たとえば、論理展開の矛盾を見つけ出し、筋の通った内容へと整えていく作業は、まるでパズルを解くような満足感をもたらします。
文章が洗練されていく過程に関われることは、校正・校閲ならではの醍醐味といえるでしょう。
2. 知らない言葉や新しい知識に出会える
知的好奇心が満たされることも、 校正・校閲のやりがいの一つです。
多種多様な原稿に触れることで、幅広い分野の専門知識や最新情報を自然と吸収できるからです。
たとえば、料理本の校正では調理工程や食材の特徴に詳しくなり、科学記事の校閲では最先端の研究内容や新技術の概要に触れる機会も多いでしょう。
こうした知識は実生活で役立つこともあり、校正・校閲の仕事を通じて視野が広がっていく実感を持てるのは大きな魅力といえます。
知らなかった言葉や新しい知識に日々出会えるため、まさに「知的好奇心が刺激される仕事」といえるでしょう。
3. 自分の「こだわり」が強みに変わる
校正・校閲の仕事は、「細かすぎる」「神経質すぎる」と見なされがちな性格やこだわりが、むしろ強みとして活かせる場面が多くあります。
たとえば「同じ言葉の表記ゆれがどうしても気になる」という人は、文章中に混在する「ウェブ」と「Web」といった“ゆれ”を瞬時に見つけ出せるでしょう。
「本の背表紙の位置が少しでもズレていると気になる」といった几帳面さは、細部まで目を配り、丁寧な作業が求められる体裁チェックの場面で大いに役立ちます。
このように自分自身の気質・感覚をそのまま活かせることも、校正・校閲のやりがいといえるでしょう。
校正・校閲の仕事に就いて良かった人の声
校正・校閲の仕事に就いて良かった人の声としては、「几帳面な性格が初めて武器になった」「静かに集中できる環境が自分に合っていた」という声が多く見られます。
最新情報に触れる機会もあるため、「知的好奇心が満たされやすい」という点をメリットとして挙げる方もいます。
では、これらの声について具体的に見ていきましょう。
1. 几帳面な性格が初めて武器になった
校正者・校閲者として働く方の中には、「短所だと思っていた几帳面さが大きな武器になった」と感じている方が少なくありません。
というのも、校正・校閲の仕事では、むしろその几帳面さが求められるからです。
几帳面な性格は、次のような場面で活かせます。
- 文脈の矛盾や不自然な論理展開を見逃さない
- 一つひとつの情報に向き合い、粘り強く出典元を確認できる
「神経質すぎる」と言われがちな性格が、校正・校閲の現場では信頼されるスキルとして高く評価されます。
生まれ持った特性をそのまま活かせるため、仕事を通じて自己肯定感が高まったと感じる方も多いのです。
2. 静かに集中できる環境が自分に合っていた
「静かな作業環境が自分に合っていた」と感じている校正者・校閲者も多くいます。
校正・校閲の仕事は一人で黙々と進める作業が多く、在宅で働ける会社も多いからです。
静かな環境で働くことには、次のようなメリットがあります。
- 集中力を保ちながら作業に没頭できる
- 自分のペースで仕事を進められる
- 社交的なやりとりで疲れる心配がない
こうした環境では一つひとつの文章に丁寧に向き合えるため、より質の高いチェックが可能になります。
人との関わりが少ない環境のほうが落ち着ける方にとって、校正・校閲は特に働きやすい仕事といえるでしょう。
3. 知的好奇心が満たされやすい
校正・校閲は様々な文章に触れる機会が多いため、「知的好奇心が刺激されて楽しい」といった声も多く聞かれます。
次のように、知的好奇心がくすぐられる場面は少なくありません。
- 医療や科学など、自分が詳しくない分野の記事の校正を担当する
- 時事ニュースや、最新の業界動向をいち早くチェックできる
- 調査や用語の確認作業を通じて、知識が自然と身についていく
仕事を通じて学び続けられることは、知的好奇心が旺盛な人にとっては大きな魅力といえるでしょう。
実際、「毎日新しい発見がある」「仕事を通じて自分の世界が広がった」と感じている校正者・校閲者は多いのです。
校正・校閲の仕事に向いている人の4つの特徴
校正・校閲の仕事は、言葉や文章に興味がある方に向いています。
細かなことに気づけたり、地道な作業に粘り強く取り組めたりする方も適性があるでしょう。
いわゆる“縁の下の力持ち”として、裏方として働くことにやりがいを感じる方にもおすすめです。
では、校正・校閲の仕事に向いている人の4つの特徴を具体的に解説します。
1. 言葉や文章に興味がある
校正・校閲に向いているのは、言葉や文章に強い関心がある人です。
なぜなら、仕事の中に大きな喜びを感じられる可能性が高いからです。
こうした方は、読書が習慣になっている、辞書や用語集を調べることが苦にならない、といった特徴が見られます。
言葉に対する深い愛情があると、細かい規則や表記ルールを覚えることも苦になりません。むしろ、言葉の正しい使い方を追求する過程そのものに「楽しさ」を感じられるでしょう。
文章の誤りを見つけることが単なる作業ではなく、言葉の正確さや美しさを追求する喜びに代わるため、長くやりがいをもって働いていけるのです。
2. 細かいことに気づける
細部への強いこだわりと集中力があり、ほんの小さな違和感も見逃さない方も校正・校閲の仕事に向いています。
校正・校閲の世界では、一見すると些細なものに思える誤字脱字や表記のゆれを見逃さない“目”が、何よりも重要とされているからです。
実際の業務では、何十ページにもわたる文章を読み進めながら、誤字脱字、句読点の使い方、レイアウトの乱れなど、様々な不備を発見していく必要があります。
「なんとなく変だな」という違和感を見過ごさず、細かな差異を見分けて正すことができる方は、校正・校閲の仕事で活躍できる可能性が高いでしょう。
3. 地道な作業を根気強くやり抜ける
「根気強さ」がある方も、校正・校閲に向いています。
なぜなら、膨大な量の文章を隅々まで精読し、同じ文章を何度も読み返して問題点を洗い出す忍耐力が求められることが多いからです。
たとえば、締切が迫っている状況でも集中力を切らさず、最後まで丁寧に作業を続ける姿勢が必要です。
ときには長時間のデスクワークが続くこともありますが、それでも正確さを保ち続ける安定した精神力も求められます。
地道な作業を「単調」と感じるのではなく、「文章の品質を高めるための大切なプロセス」と捉えられる方は、校正者・校閲者として高い信頼と評価を得やすいでしょう。
4. 裏方として支えることが好き
著者やライターが書いた作品や記事を陰から支える、“縁の下の力持ち”としての役割に誇りを持てる方も校正・校閲の仕事に向いています。
校正者・校閲者はあくまでも裏方のため、自分が表舞台に立つことはほとんどないからです。
たとえば、校正後に文章が読みやすくなったり、誤りのない美しい印刷物を手に取ったりしたときに喜びを感じられる方は、高い満足感を持って仕事を続けられるはずです。
このような理由から、校正・校閲は、自分が目立つことではなく、裏方として支えることにやりがいを感じる方に向いている仕事といえるのです。
校正・校閲の仕事に未経系からなるには?
校正・校閲の仕事が未経験の方は、言葉のチェックに関わる基本知識を学ぶことから始めましょう。
そのうえで、クラウドソーシングサイトなどで簡単な校正・校閲案件に挑戦して実績を積み、出版社などのアルバイト求人や派遣求人を探すのがおすすめです。
ここでは3つのステップに分けて、校正・校閲の仕事に未経験から挑戦する流れを紹介します。
1. 言葉のチェックに関わる基本知識を学ぶ
まずは、言葉のチェックに必要な基本知識を身につけましょう。
正しい日本語の使い方や表記ルールを理解していることは、校正者・校閲者として欠かせない“基礎力”といえるからです。
日本語表記の基本ルールは、次のような参考書を使って学ぶのが効果的です。
- 『記者ハンドブック』
- 『標準校正必携』
修正事項を赤ペンで書き込む「校正記号」の使い方や、送り仮名のルールや外来語の表記といった「用字用語」の知識も大切です。
これらの知識を学べる「校正技能検定」の受検も検討しつつ、まずは基礎をしっかり固めることを意識しましょう。
2. 実践経験を積む
基本知識を身につけたら、次は実践経験を積むことが大切です。
実際に文章をチェックする経験を重ねることで、校正・校閲のスキルがさらに磨かれていくからです。
編集プロダクションなどの案件に応募するのはハードルが高いため、まずは次のような未経験でも始めやすい案件に挑戦してみましょう。
- 副業求人サイトで「校正アシスタント」「文字校正」の仕事を探す
- クラウドソーシングサイトを使い、「初心者OK」と記載された校正案件に応募する
経験を重ねるごとに自信がつき、依頼者からの評価も高まるため、より難易度が高い案件にチャレンジできるようになります。
3. 出版社などのアルバイト・派遣案件を検討する
基礎知識と実践経験を積んだら、出版社や編集プロダクションのアルバイトや、派遣の仕事に応募してみましょう。
たとえば出版業界では、「編集アシスタント」や「校正補助」といった職種で募集されているケースが一般的です。
はじめは給料が低めで、簡単な校正・校閲作業からスタートする可能性が高いですが、信頼を得られると重要な業務を任されるようになります。
校正・校閲の仕事は、経験と実績が重視される世界です。能力が認められれば正社員登用の声がかかることも珍しくないので、まずは現場でプロの技術や姿勢を学びつつ、地道にスキルを高めていきましょう。
校正・校閲の仕事の働き方5選
校正・校閲の働き方としては、正社員・派遣社員といった企業に所属して働くかたちの他に、アルバイトやパート、フリーランスとして個人で働くスタイルもあります。
在宅で副業として取り組む方も増えており、ライフスタイルに合わせて柔軟に働きやすい仕事としても知られています。
では、校正・校閲の働き方について詳しく見ていきましょう。
1. 正社員
校正・校閲の仕事を長く続けたい方は、出版社や編集プロダクション、印刷会社に務める「正社員」という働き方が適しています。
安定した給与や福利厚生を手にすることができ、専門スキルを磨きながら長期的なキャリアを築けるからです。
編集者やディレクターなど、関連職種へのステップアップを目指せる可能性もあるでしょう。
一方で、締切前の残業や、繁忙期の業務量の増加といった業界特有の忙しさもあるため、体力的・精神的な負担には注意が必要です。
とはいえ、安定したキャリアを築きたい方には、正社員は特に魅力的な働き方といえるでしょう。
2. 派遣社員
派遣社員として校正・校閲の仕事をする場合、出版社やWeb制作会社でアシスタントとして働くケースが一般的です。
派遣として働く魅力は、プロの現場でスキルを磨けることです。簡単な文字校正から始まることが多いですが、実務経験を徐々に積んでいきたい方には適しているでしょう。
固定の給与が毎月手にでき、残業代がしっかり支払われることも嬉しいポイントです。「紹介予定派遣*」の場合は正社員登用のチャンスもあります。
高度な業務に挑戦しにくい点はデメリットですが、固定収入を手にしつつ、未経験から実務に関われるという点で魅力的な働き方といえるでしょう。
*一定期間の派遣就業後に、派遣先企業の正社員や契約社員になることを前提とした派遣形態
3. アルバイト・パート
校正・校閲の仕事に気軽に挑戦したい方には、アルバイトやパートという働き方が向いています。
出版社や校正会社のサポート業務の募集が多く、基本的には原稿の整理や簡単なチェック作業、データ入力など、未経験でも取り組める仕事を任されます。
「週2〜3日」「1日4時間」など、自分のライフスタイルに合わせて働ける柔軟さもアルバイト・パートとして働くメリットです。
時給は1,000~1,200円程度と決して高いとはいえませんが、子育て中の主婦(主夫)の方や、学生の方など、隙間時間を有効に使いたい方にはぴったりの働き方といえるでしょう。
4. フリーランス・業務委託
フリーランスや業務委託の校正者・校閲者は、時間や場所にとらわれずに仕事ができることが大きな魅力です。
依頼元は出版社やWeb制作会社が中心で、メールやチャットツールで原稿を受け取り、納期までに修正を済ませて納品する流れが一般的です。
専門ジャンル(医療、法律、ITなど)を持っていると案件の幅が増え、企業や編集プロダクションと継続的に取引できる可能性も高まります。
スケジュールの管理や営業、確定申告などの事務作業を自分で行う必要がある点はデメリットですが、実務経験をもとに在宅で自由に働きたい方には適した働き方といえるでしょう。
5. 在宅の副業
在宅でできる校正・校閲の副業は時間や場所に縛られずに働けるため、柔軟な働き方を求める方にぴったりです。
本業との両立はもちろん、育児や介護の合間に取り組みやすいことも魅力といえるでしょう。
在宅の副業案件を獲得する主な方法は、次の通りです。
- クラウドソーシングサイトで校正・校閲の案件を受注する
- SNSやブログで校正スキルを発信し、個人や企業から依頼を受ける
はじめは簡単な案件から始めて実績を積み、信頼を得ることが継続的な受注につながります。
自分のペースで仕事量を調整できるため、無理せず副収入を得たい方も在宅副業に挑戦してみましょう。
校正・校閲の仕事のつらいところ
校正・校閲はメリットが多い仕事ですが、その一方でミスが許されないプレッシャーや、長時間の作業で目や肩が疲れる、といった点に大変さを感じる可能性もあります。
繁忙期は時間に追われる日々が続くこともあり、体力的・精神的なストレスを強く感じることもあるでしょう。
ここでは、校正・校閲の仕事の「つらさ」を3つ紹介します。
1. ミスが許されないプレッシャーがある
校正・校閲の仕事で特につらいのは、ミスが許されないプレッシャーがあることです。
なぜなら、たった一つの見落としが印刷物や記事全体の価値を下げてしまうからです。
たとえば、次のようなプレッシャーが常につきまといます。
- 印刷後にミスが見つかると刷り直す必要があり、大きな損失につながる
- 見逃したミスは、自分の評価や信頼に直結する
- 数百ページにおよぶ文章から、どんな小さな誤りも見つけなければならない
校正者は“最後の砦”として重要な役割を担っているため、こうした強いプレッシャーと日々向き合わなければならないのです。
2. 長時間の細かい作業で目が疲れる
校正・校閲は長時間にわたって文字を凝視し続ける仕事のため、眼精疲労に悩んでいる校正者・校閲者は少なくありません。
具体的には、次のような症状が現れることがあります。
- 目の乾き、充血、かすみ
- 焦点が合いにくい、物が二重に見える
- 視力の低下、目の疲れによる集中力の減退
- 眼精疲労による肩こり、頭痛の慢性化
また、紙の原稿とモニターを行き来する場合、「ピント調節」の繰り返しによって目の疲れがさらに強まる恐れもあります。
長時間の細かい作業で目が疲れる可能性が高いことも、校正・校閲の大変さとして理解しておきましょう。
3. 時間に追われることがある
校正者・校閲者として働くと、多くの場合、厳しい納期との戦いの日々が待っています。
特に、雑誌や新聞などの定期刊行物は発売日が固定されているため、どんな事情があっても締切を守らなければなりません。この場合、原稿の差し替えや急な追加校正があっても、納期が動くことはまずないでしょう。
アルバイトやフリーランスとして働く場合は、指定された納期に遅れると発注元からの信頼を失い、契約を打ち切られる原因となる可能性もあります。
このように「時間的に厳しい制約の中で、高い品質の作業が求められる」という点も、校正・校閲として働く大変さといえるのです。
校正・校閲の仕事の将来性は?なくなるって本当?
校正・校閲の仕事がすぐになくなることは考えにくいですが、特に校正に関しては、AIツールの発展によって一部の作業が自動化されつつあります。
一方で校閲は、文章の意味や事実関係の整合性を確認する仕事のため、現時点のAIでは正確な作業が難しい領域とされています。
では、校正・校閲のそれぞれの将来性について見ていきましょう。
校正はAIによる自動化が進む可能性がある
校正業務の中には、AIに代替される可能性が高い作業もあります。
AIの「自然言語処理技術」の進化によって、一定のルールに基づいた誤りを高い精度で検出できるようになってきたからです。
以下のような業務では、すでにAIによる自動化が進んでいます。
- 語尾表現の統一(「~です」と「~である」の混在など)
- 送り仮名の誤りの検出(例:「表わす」→「表す」)
- 表記ゆれの判定(「ウェブ/Web」など)
これらの作業はパターンやルールに従って処理でき、AIが得意とする分野です。
そのため将来的には、校正業務の一部がAIに置き換わる可能性はあるでしょう。
校閲は今後も“人間にしかできない仕事”と言われている
校閲は、この先も人の手が必要な仕事と言われています。
文章全体の文脈や作者の意図、さらには社会的な背景や事実関係を踏まえた「高度な判断」が求められる作業だからです。
また、次のような作業は人の目による最終チェックが欠かせません。
- 数字や統計に誤りがないか、元データにさかのぼって確認する
- 信頼性のある出典元・引用元かどうか確認する
- 倫理的に問題がある表現が含まれていないか確認する
このような判断や、読者への影響まで考慮した調整作業はAIでは対応しきれないため、校閲は今後も“人間にしかできない仕事”とされているのです。
まとめ
校正・校閲の仕事について、その違いや仕事内容などを解説しました。
校正・校閲は、文章を整える達成感や、知的な楽しさを感じられる仕事です。
在宅で働ける可能性も高く、ライフスタイルに合わせた働き方を実現しやすい点も魅力の一つです。
「自分でもできそうかも」と感じた方は、校正・校閲の仕事にぜひ挑戦してみましょう。