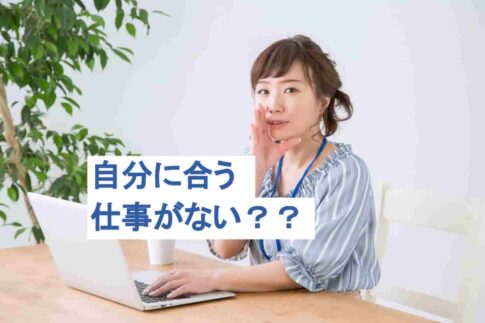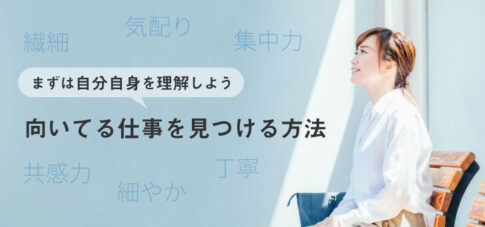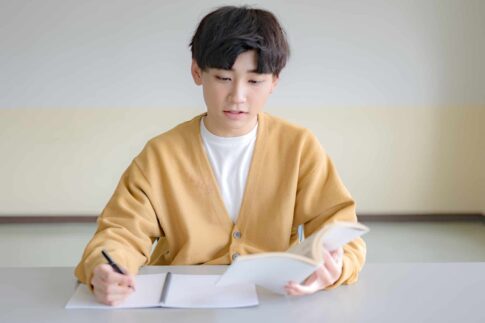この記事の目次
社内SEはどんな職種?
社内SE(社内システムエンジニア)は、企業内の「情報システム部門」などに所属し、自社の情報システム全般に関わる業務を担当する職種です。
社内SEの主な仕事内容は、以下の通りです。
- 社内システムの保守・運用
- システムの予算作成・管理
- 新システムの企画・開発
- PCやネットワーク機器の設定・管理
- 社員からのITに関する問い合わせ対応(ヘルプデスク業務)
- ウイルス対策やアクセス制限などのセキュリティ対策
このように社内SEは、多岐にわたる業務を通して社内のIT環境を円滑に保ち、業務効率化やトラブルを未然に防ぐ役割を担っています。
決して目立つ仕事ではありませんが、企業の成長を陰から支える、非常に重要なポジションといえるでしょう。
社内SEとSEの違い
社内SEは、特定の企業に所属し、その会社のシステム運用を担当する仕事です。
一方でSEは、IT企業やSIerに勤め、複数の企業(クライアント)向けにシステム開発を行うことが一般的です。
つまり、社内SEは「自社の業務を支える役割」、SEは「クライアントの課題を解決する役割」を担っている点に違いがあります。
「誰のために働くか」という点で、大きく異なる仕事といえるでしょう。
| 社内SE | SE | |
|---|---|---|
| 主な勤務先 | 一般企業の情報システム部門 | IT企業、SIer(システムインテグレーター) |
| 対象範囲 | 自社内の業務システム・インフラ | 顧客企業の業務システム |
社内SEと常駐SEの違い
社内SEは「自社内で働く」、常駐SEは「顧客先で働く」という点に違いがあります。
社内SEはその名の通り、自分が所属している会社のオフィスで仕事を行います。
一方で常駐SEは、顧客企業のシステム開発・運用・保守などを、クライアントのオフィスで行う働き方です。
社内SEと常駐SEは、どちらも「ITシステムの安定運用を支える」という点で共通していますが、それぞれが働く場所には大きな違いがあるのです。
| 社内SE | 常駐SE | |
|---|---|---|
| 主な勤務先 | 一般企業の情報システム部門 | SIer、SES |
| 勤務場所 | 自社内のオフィス | 顧客企業のオフィス |
社内SEの平均年収
社内SEの平均年収は、499万円です(※1)。
日本人全体の平均年収が460万円(※2)であることから、平均よりもやや高めといえるでしょう。
社内SEは、スキルアップによって年収アップが見込める職種です。具体的には、セキュリティやクラウド、データ分析などの専門知識や資格を獲得すると市場価値が高まります。
近年は社内の「DX化推進」が重視されており、ビジネスとITの両面の知見を持つ社内SEの価値も上昇中です。
大手企業では年収700万円以上、外資系や金融業界ではさらに高水準の報酬も期待できます。マネージャーやCIO(最高情報責任者)などの役職に就けば、年収1,000万円以上も夢ではありません。
社内SEの平均年収はそこまで高くないものの、スキルや経験次第で大きなキャリアアップ・収入アップが期待できる職種といえるでしょう。
※1 出典:求人ボックス 給料ナビ「社内SEの仕事の年収・時給・給料」
※2 出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
社内SEの仕事内容
社内SEは、自社の業務システムや、ネットワーク環境などのインフラを整備・管理し、社内の業務が円滑に進むように支える仕事です。
また、IT予算の立案や、新システムの企画・開発など、全社戦略に基づいた業務を担当・推進する場面も少なくありません。
PCやネットワークの設定・管理、ヘルプデスク対応、セキュリティ対策といった、運用・保守業務も重要な仕事です。
では、社内SEの6つの業務について具体的に解説します。
1. 社内システムの保守・運用
社内システムの保守・運用は、業務システムやインフラの安定稼働を支える仕事です。
具体的には、サーバーやネットワーク機器、業務アプリケーションを監視し、障害が発生した場合には原因を特定し、迅速に復旧対応を行います。
定期的なメンテナンスやアップデート、バックアップも重要な業務で、パフォーマンス改善や効率化のためのチューニング、利用状況の分析も行います。
システムが止まると業務効率が下がり、顧客へのサービス提供に遅れが出る恐れもあります。そのため社内システムの保守・運用は、ビジネス全体を支える重要な役割も担っているのです。
2. システムの予算作成・管理
システムの予算作成・管理は、自社のIT戦略に基づき、年間のIT予算計画を立案する業務です。
次のような費用を見積もり、配分を検討します。
- 新規システムの導入費
- 既存システムの改修費
- 運用保守費
- ITインフラの維持費
- ソフトウェアライセンスの管理費
- 人材育成費
各部門からの予算要求を集約し、経営方針に沿った予算配分を提案します。予算の執行状況を定期的に確認し、コスト削減の可能性を探ることも大切な仕事です。
システムの予算作成・管理は、効率的なIT投資やコスト削減を通じて、企業の経営目標の達成に貢献している業務といえるでしょう。
3. 新システムの企画・開発
新システムの企画・開発は、業務効率化や競争力強化などを目的に、新たな情報システムを構想し、実現に向けて推進する仕事です。
まずは現場の業務フローや課題を分析し、問題解決のためのシステム要件を定義します。その後は自社開発か外部委託かの判断を行い、プロジェクト計画を立案します。
導入時はユーザー教育やデータ移行、マニュアル作成などを支援し、稼働後は効果測定や改善提案を通じて最適化を図ります。
このように多岐にわたる業務を担いますが、比較的落ち着いた業務が多い社内SEの仕事の中では、創造性とやりがいに満ちた仕事といえるでしょう。
4. PCやネットワークの設定・管理
PCやネットワークの設定・管理は、業務用PCやプリンターなどの端末機器、社内ネットワーク、インターネット接続環境を構築・維持する仕事です。
具体的には、新規PCのセットアップやソフトウェアのインストール、アカウント・セキュリティの管理を行います。
ルーターやスイッチ、ファイアウォールなどのネットワーク機器の設定・監視・トラブル対応も重要な業務です。社内LANやWi-Fi、VPN、インターネット接続などのインフラ整備も担当します。
社員が安心して業務に集中できる環境を整える、縁の下の力持ち的な仕事といえるでしょう。
5. ヘルプデスク対応
ヘルプデスク対応は、社員から寄せられるIT関連の問い合わせやトラブルに対応する仕事です。
具体的には以下のような内容に対し、電話・メール・チャットなどを用いてサポートを行います。
- PCのトラブル
- ソフトウェアの使い方
- ネットワークの不具合
よくある質問やマニュアルの整備、社員向けのIT研修を通じて、社内のITリテラシー向上を図ることも重要な役割です。
近年は在宅勤務が増えており、リモート対応やオンラインツールに関わるサポートの重要性も高まっています。
社内SEの業務の中でも、特にコミュニケーション力が求められる仕事といえるでしょう。
6. セキュリティ対策
セキュリティ対策は、社内の情報資産(顧客データや機密情報など)をサイバー攻撃や不正アクセス、情報漏洩などから守る業務です。
具体的には、セキュリティポリシーの策定、ファイアウォールやアンチウイルスなどのツールの導入・運用、アクセス権限の管理などを行います。
脆弱性対策や侵入検知、インシデント発生時の対応計画策定・実施も重要な業務です。
セキュリティ意識向上のための社員研修や啓発活動を行い、人的なセキュリティリスクを低減することも求められます。
外部の脅威から会社を守る、重要な役割を担っている仕事といえるでしょう。
社内SEに求められる3つのスキル
社内SEとして働くうえで、「業務系システムの運用・保守スキル」や「サーバー・クラウドの運用スキル」は欠かせません。
社内からの相談やトラブル対応を行う中で、状況に応じた柔軟な提案力が求められる場面も多いため、「課題解決力」も重要なスキルといえるでしょう。
では、社内SEに求められる3つのスキルについて具体的に解説します。
1. 業務系システムの運用・保守スキル
業務系システムの運用・保守スキルとは、会計・人事・販売管理など、自社内で使用される業務アプリケーションを安定的に運用・改善していくための知識と実務能力のことです。
具体的には、設定変更やマスタ管理、バッチ処理の監視などを担当します。
障害発生時には、迅速な原因特定と復旧対応が求められるため、ログ解析やトラブル対応のスキルも不可欠です。ベンダーとの契約管理や改修のための折衝力、社員に分かりやすく説明する力も必要でしょう。
業務系システムは日々の業務を支える重要な基盤のため、運用・保守スキルは社内SEにとって欠かせない力といえるのです。
2. サーバー・クラウドの運用スキル
企業のITインフラを安定して支えるうえで、サーバーやクラウドの運用スキルも社内SEには必要です。
具体的には、Windows ServerやLinuxの管理、Active Directoryによるアカウント管理、グループポリシーの設定などで必要となります。
近年はクラウド環境への移行が進んでおり、AWSやMicrosoft Azureなどのクラウドサービスに関する設計・運用スキルの重要性も高まっています。
このように社内SEは、自社のIT環境を安定して管理・改善する役割を担うため、サーバー・クラウド運用の知識は欠かせません。
3. 課題解決力
課題解決力も、社内SEにとって重要なスキルの一つです。現場の業務課題を正しく理解し、ITツールや技術を活用してどのように解決するかを考える視点が求められるからです。
たとえば「手作業の業務に時間がかかる」といった課題に対しては、単にツールを導入するだけでなく、業務フロー全体の見直しが必要になることもあります。
このような場面では、ユーザー部門との対話を通じて課題を正確に把握し、適切な解決策を考えていきます。
このように社内SEは、本質的な課題解決に主体的に取り組む姿勢が必要な仕事であることも理解しておきましょう。
社内SEになって良かった人の声
社内SEになって良かった人の声としては、「安定した働き方を実現できた」「人と関わるのが苦手でも活躍できた」といった声が多く見られます。
「裏方のプロとして評価されるのが嬉しい」といったように、目立たないながらも感謝される場面にやりがいを感じている方も少なくありません。
では、それぞれの声をもとに、社内SEならではのメリットを紹介します。
1. 安定した働き方を実現できた
社内SEとして働くことで「生活が安定した」と感じる方は少なくありません。
主な理由は、土日祝が休みの会社が多く、残業時間も比較的少ないため予定を立てやすいからです。
客先常駐や突然の出張がなく、社内で腰を据えて働ける安心感がある点も魅力です。業務内容も日々大きく変わることが少なく、ルーティンを中心とした管理・改善業務が多いため、自分の働くペースを保ちやすいこともメリットといえるでしょう。
このように社内SEは落ち着いた環境で働ける仕事のため、「安定した働き方を実現できた」と実感している方が多いのです。
2. 人と関わるのが苦手でも活躍できた
社内SEは、人との会話が得意ではない人でも働きやすい仕事です。社内の人とだけやり取りすることが多く、お客様対応に比べて緊張やストレスが少ないからです。
なかでもシステムの開発や運用保守といった仕事は、パソコンに向かって黙々と作業する時間が多く、仕事に没頭できる可能性もあります。
社外からの電話対応や営業的なやり取りもほとんどなく、社内だけでコミュニケーションが完結する点も安心材料といえるでしょう。
このように社内SEは自ら人と関わる場面が多くないため、「人と関わるのが苦手でも活躍できた」と感じる方が多いのです。
3. 裏方のプロとして評価されるのが嬉しい
社内SEは、いざというときに頼りにされる“縁の下の力持ち”的な役割を担っています。
たとえばシステムの不具合にすぐ対応したり、社員の困りごとに的確なサポートを行ったりすることで感謝の言葉を直接もらえる場面も少なくありません。
業務改善や効率化につながる提案が採用されることで、「ITの専門知識を持った、社内に欠かせない存在」として信頼されることも多々あります。
このように社内SEは「人の役に立っている」と実感しやすく、“裏方のプロ”として頼りにされる存在のため、「地道な努力を評価されることにやりがいを感じる」と話す方も多いのです。
社内SEの大変さ
社内SEの大変さとしては、「様々な仕事を任されやすい」といった業務の広さや、「急ぎの対応が多い」といった突発的な仕事の多さが挙げられます。
日々のトラブル対応や改善業務など、目立つ仕事が多くないため、「成果が評価されにくい」と感じることも少なくありません。
では、それぞれの大変さについて詳しく見ていきましょう。
1. 様々な仕事を任されやすい
社内SEは、社内のITに関する様々な業務を任されることが多いため、担当範囲がどうしても広くなりがちです。
システムの保守・運用だけでなく、PCの初期設定や社内ネットワークの整備、さらには機器の不調や、ちょっとした操作の質問対応まで、社内から日々多くの依頼が寄せられます。
「ITに詳しいからちょっと話を聞かせて」「会議に参加して」と他部門からの相談が舞い込むことも多く、自分自身の仕事に集中できない場面も少なくありません。
このように“便利屋”のような役割になってしまい、業務量が増えてしまうケースも多いのです。
2. 急ぎの対応が多い
社内SEの仕事は、「今すぐ対応してほしい」といった緊急の依頼が発生することがあります。
たとえば、業務に大きな支障をきたすシステム障害やネットワークトラブル、パソコンの不具合などが起きた際は、社内の業務を止めないために迅速かつ的確な対応が求められます。
こうした緊急の対応にあたると、予定していた作業や資料作成などを中断せざるを得ず、作業の優先順位を見直さなければならない場面も少なくありません。
普段は比較的落ち着いて働けますが、突発的なトラブルが起きたときは急ぎの対応に追われることは理解しておきましょう。
3. 成果が評価されにくい
社内SEの仕事は、目に見える成果として評価されにくいという難しさもあります。トラブルを未然に防ぐための管理や改善といった“予防的な業務”が中心だからです。
「何も問題が起きていない」という状態を保つのは簡単ではありませんが、それが「当たり前」と受け取られてしまうことも少なくありません。
実際には、システムの安定稼働や業務効率化の裏側には、社内SEの地道な努力や工夫があります。しかし、それが注目されることはあまりなく、自分のがんばりが評価されにくい仕事のため、人によっては達成感や自己肯定感を得にくいと感じることもあるでしょう。
社内SEになって後悔している人の声
社内SEとして働き始めて後悔している人の声としては、「最新技術に触れる機会が少ない」という声が多く見られます。
「想像以上に地味な仕事が多い」と感じる方や、「相談相手がいないので孤独を感じやすい」といった声も少なくありません。
では、どのような点にギャップを感じやすいかについて具体的に見ていきましょう。
1. 最新技術に触れる機会が少ない
社内SEは、既存システムの保守や運用が業務の中心となるケースが多いため、最先端の技術やトレンドに触れる機会は多くありません。
特に中小企業では、コストなどの面から古いシステムを使い続けているケースも多く、最新のクラウドサービスやAI技術に関われない可能性もあります。
そのため「常に新しい知識を学び、技術者として成長したい」と考えている人ほど、日々の業務に物足りなさを感じてしまうでしょう。
結果として「このままでは市場価値が上がらないのでは…」という不安を抱き、将来を見据えて転職を考える方も少なくありません。
2. 想像以上に地味な仕事が多い
「システムを作る華やかな仕事を想像していたけど、実際は地味な作業が多かった」という声も社内SEからよく聞かれます。
社内SEの業務は、新しいシステムを開発するというより、日常的なエラー対応やマニュアルの作成、PCの初期設定、社内からの問い合わせ対応などが中心です。
こうした仕事は成果が見えにくく、同じような作業の繰り返しになりがちなため、モチベーションの維持が難しく感じられる場面も少なくありません。
特に「ITの仕事=専門技術で新しいものを創り出す」というイメージを持っていた方ほど、現実とのギャップに戸惑いやすいようです。
3. 相談相手がいないので孤独
社内SEは、企業によっては数人、あるいは一人で担当しているケースも多く、相談や情報を共有できる相手がいないことに孤独を感じる方もいます。
少人数の職場では、トラブルが発生したときに自分ひとりで判断を下す場面もあり、プレッシャーが大きくなりがちです。
また、ITに詳しい社員が限られていることから、自分の業務内容が十分に理解されず、「何をしているのか分かりにくい」といった印象を持たれて孤立感を抱くこともあります。
このように社内SEとして働く社員の数は少ないため、精神的な負担を感じてしまう方も意外に多いのです。
社内SEになるには?未経験転職のポイントを解説
未経験から社内SEを目指す場合、まずは社内SEに求められる「基本スキル」を把握することが大切です。
ITパスポートや基本情報技術者といった資格の取得を目指したり、自分の過去の経験を整理して「キャリアの棚卸し」に取り組んだりするのもおすすめです。
では、未経験から社内SEになるために転職で意識したいポイントを5つ解説します。
1. 求められる基本スキルを把握する
社内SEは幅広い業務を担当するため、まずは仕事に必要なスキルを理解しておくことが大切です。
たとえば、OSやネットワークの基礎知識、Excelや社内ツールの操作方法などの知識が主に求められます。社内からの問い合わせ対応や、マニュアル作成といった事務作業も日常的な業務の一つです。
こうした基本スキルを理解しておくと、企業にアピールする自分の強みや経験も整理しやすくなります。
「ITに詳しい人」として社内から頼られる存在となるためにも、まずはどのようなスキルが社内SEに求められているか把握することから始めましょう。
2. IT系の資格を取得する
未経験から社内SEを目指す場合、ITに関する資格の取得も大きなアピールになります。「学ぶ姿勢がある」「基本的な理解がある」として、採用担当者から評価されやすくなるからです。
特に「ITパスポート」や「基本情報技術者試験」は、ITの基礎知識を客観的に証明できる資格のためおすすめです。
また、社内SEはネットワークやクラウドなど幅広い知識が求められるため、分野別に資格取得を目指すのも効果的でしょう。
たとえば、ネットワーク系であれば「CCNA」や「CompTIA A+」、クラウド系であれば「AWS認定クラウドプラクティショナー」などの取得を検討してみてください。
たとえ未経験であっても、資格を取得することで一定の知識があることを証明できるため、実務経験がない方でも選考時にプラスの評価を受けやすくなります。
3. キャリアの棚卸しをする
社内SEとして働きたい方は「キャリアの棚卸し」にも取り組みましょう。
異業種・未経験からの転職であっても、これまでの経験が社内SEの仕事に活かせる場面は多いからです。
たとえば、以下のような経験は社内SEの実務で活かせます。
- 前職でPCの初期設定を任されていた
- Excelでマクロを組んで業務を改善した
まずは自分のこれまでの業務を振り返り、「どのようなスキルを身につけたか」を洗い出してみましょう。
そのうえで、それらの経験が社内SEの業務にどう結びつくかを言語化しておくことで、履歴書や面接で自信を持ってアピールできるようになります。
4.「中小企業」や「内製化を進める企業」への応募を検討する
未経験から社内SEを目指す場合は、中小企業や、システムを外注せずに自社で管理する「内製化」を進めている企業を狙うのもおすすめです。
中小企業は大企業に比べて採用のハードルが低く、ポテンシャル重視で未経験者を受け入れてくれることが多いからです。
内製化を進めている企業は社内SEの募集が活発なケースが多く、採用される可能性を高めやすいでしょう。
特に大企業の社内SEは人気が高く、実務経験のある人が優遇されがちです。まずは、中小企業や内製化を進めている企業など、未経験者を受け入れている環境にも目を向けてみてください。
5. 面接では「人の役に立ちたい」という思いを伝える
社内SEの面接では、「誰かの役に立ちたい」「快適な職場環境を整えたい」といった思いを明確に伝えましょう。
社内SEは困りごとを解決する場面が多いため、こうしたホスピタリティや貢献意識が高く評価されるからです。
たとえば「社員にわかりやすく説明することを意識したい」「社内の各部署・社員と円滑な人間関係を築きたい」といった意欲は、採用担当者に好印象を与えるでしょう。
社内SEの採用では「人のために行動できる人物かどうか」が重視されるため、面接では協力的で前向きな姿勢をしっかりとアピールすることが大切です。
社内SEの求人の探し方
社内SEの求人を探す際は、求人サイトで「社内SE」「情報システム」といったキーワードを使って検索するのがおすすめです。
IT特化型の転職エージェントを活用したり、企業の「自社採用ページ」を直接確認したりすることで、一般には出回っていない求人情報を見つけられる可能性もあります。
では、社内SEの求人の探し方を3つ紹介します。
1. 求人サイトでキーワード検索をする
社内SEの求人は、求人サイトで「社内SE」「情報システム」「社内インフラ」などのキーワードで検索すると見つかります。
または、以下のようなワードをもとに検索するのも効果的です。
- 社内SE 未経験
- 社内SE 情報システム部
- 社内SE ヘルプデスク
- インフラ 内製
- 情シス(※情報システム部門の略)
その他、「ITサポート」「社内IT」「テクニカルサポート」といった関連職種は社内SEと似た業務が多いため、あわせてチェックしてみると良いでしょう。
未経験の場合は、「未経験歓迎」や「教育制度あり」といった記載がある求人を優先的に確認するのがおすすめです。
2. IT特化型の転職エージェントを活用する
IT特化型の転職エージェントは社内SEの求人を多く扱っているため、確認できる求人数を増やしたい方におすすめです。
こうしたIT専門エージェントでは、IT業界に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、あなたのスキルや経験を的確に評価したうえで希望にマッチする求人を紹介してくれます。
非公開求人も多数取り扱っているため、自分では見つけにくい好条件の案件に出会える可能性も高いでしょう。
一般の転職サイトでは掲載されていない社内SEの案件が多いので、IT特化型の転職エージェントの利用もぜひ検討してみてください。
3. 企業の「自社採用ページ」をチェックする
社内SEの求人を探している方は、企業の公式サイトにある「採用情報ページ」も確認してみましょう。“独自募集”を行っている会社は意外に多く、こうした求人は競争率が低い傾向もあるからです。
特に中小企業やベンチャー企業は、採用コストを抑えるために自社サイトのみで社内SEを募集しているケースも少なくありません。
企業の採用ページを直接チェックすることで、求人サイトや転職エージェントでは確認できなかった社内SEの求人を発見できる可能性があります。
より多くの求人と出会いたい方は、企業のホームページもこまめにチェックしてみましょう。
社内SEのよくある質問
社内SEへの就職・転職を検討している方に向けて、「よくある質問」に3つお答えします。
- 社内SEが勝ち組と言われるのはなぜ?
- 社内SEは「楽すぎ」と聞いたけど、本当?
- 社内SEは「やめとけ」と言われるのはなぜ?
社内SEが“勝ち組”と言われるのは、IT系の仕事の中で「働きやすさ」が特に優れている職種だからです。
社内SEはオフィス勤務や在宅勤務が中心で、客先常駐がなく、過度な残業に悩まされることも少ないためワークライフバランスを保ちやすいのが特徴です。
社内の業務効率化やIT化を担う重要なポジションでもあるため、専門性を活かしながら安定的にキャリアを築けることも魅力といえるでしょう。
このように、安定した働き方と将来性のあるスキルを両立できる職種であることから、社内SEは“勝ち組”と表現されることが多いのです。
実際の働き方は会社の規模や体制、業務範囲によって大きく左右されるため、社内SEの仕事は一概に「楽」とは言えません。
たしかに、社外対応が少なく、残業が比較的少ない仕事ですが、トラブル発生時の緊急対応に追われたり、他部署以上に幅広い業務をこなしていたりする社内SEは多いものです。
特に少人数体制の企業では、ネットワーク管理やPCの初期設定、業務改善まで、様々な領域の仕事を一人でカバーしなければならないケースもあります。
安定感のある職種ではありますが、決して“気楽な仕事”ではないということは理解しておきましょう。
社内SEは“なんでも屋”になりやすく、市場価値も思うように高まらないことから「やめとけ」と言われることがあります。
たとえば、開発業務を期待して入社したのに、実際は保守や設定作業が中心だったというケースは少なくありません。成果が目に見えにくい仕事のため評価されづらく、やりがいを感じにくいと悩む方もいます。
社内SEは、精神的・体力的な負担がそこまで大きくないなど、様々なメリットがあります。とはいえ、技術の最前線で活躍したい方や、成長意欲が高い方にとっては物足りなさを感じてしまう可能性があるでしょう。
まとめ
この記事では、社内SEの仕事内容や、平均年収、メリット・デメリットなどについて解説しました。
社内SEは、社内のIT環境を支えつつ、業務効率化を推進する重要な役割を担う仕事です。
幅広い業務を任される可能性があるなど大変な面もありますが、自社内で腰を据えて働けるという点で安定性の高い職種といえるでしょう。
落ち着いた働き方を実現したい方や、裏方として社内の業務を支えることにやりがいを感じる方は、社内SEへの転職を前向きに検討してみてください。