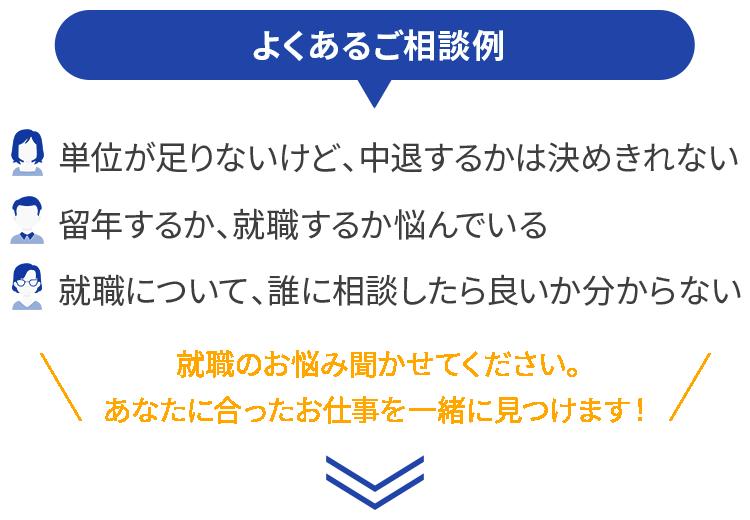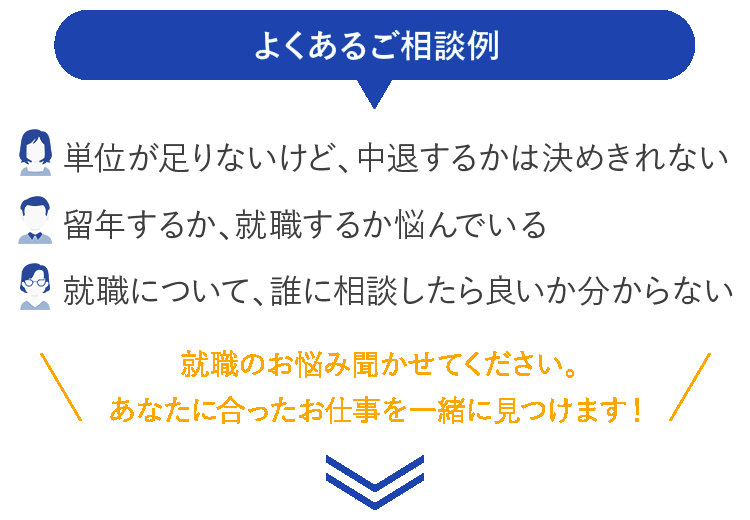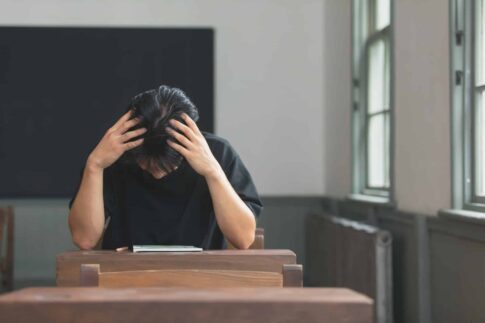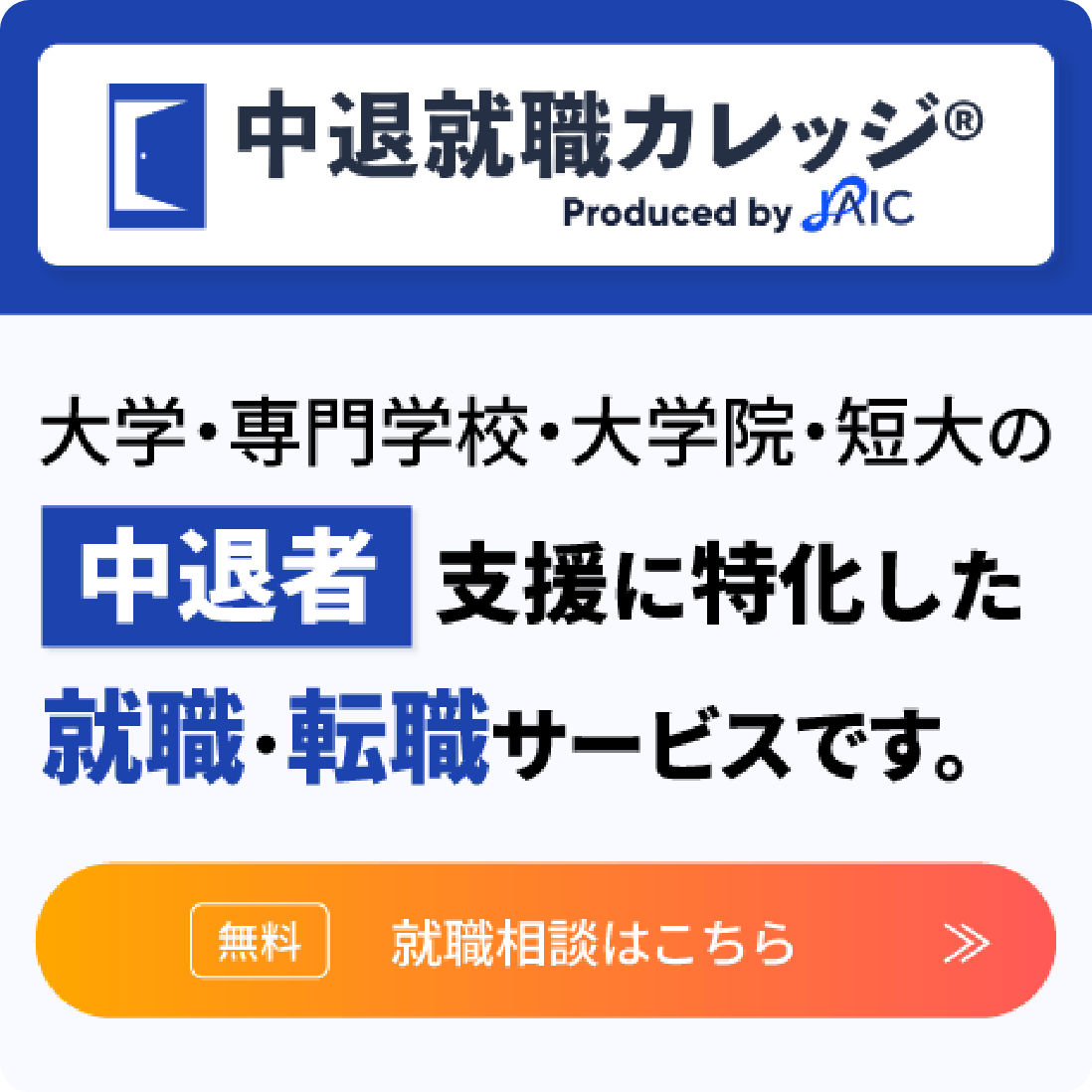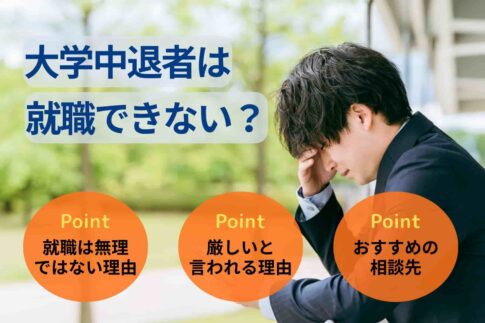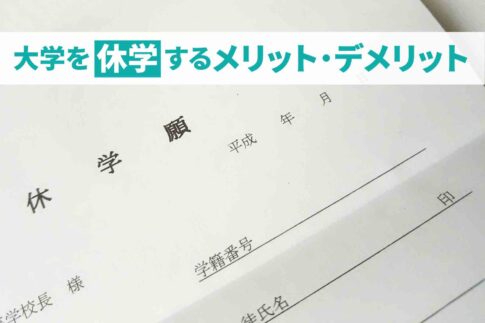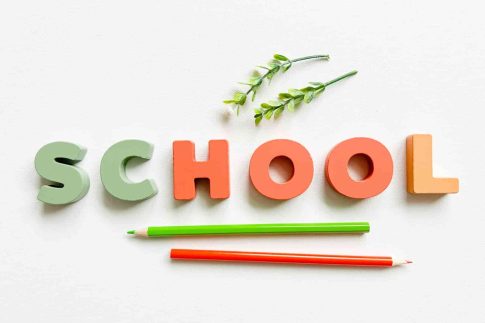大学中退率はどれくらい?辞める人の特徴やその後の進路も解説

令和5年度の大学中退率は2.04%で、およそ50人に1人が中退を選択しています。
数でいうと53,470人が1年間に大学を中退しており、大学に限って見ると中退率・中退者数ともに令和3年度から増加傾向にあります。
この記事では、大学中退率について詳しく解説すると共に、大学を辞める人の特徴や、中退後の進路についても紹介します。
中退するか迷っている方や、中退後の生活に不安を抱いている方は最後までご覧ください。
出典:文部科学省「令和5年度 学生の中途退学者・休学者数の調査結果について」
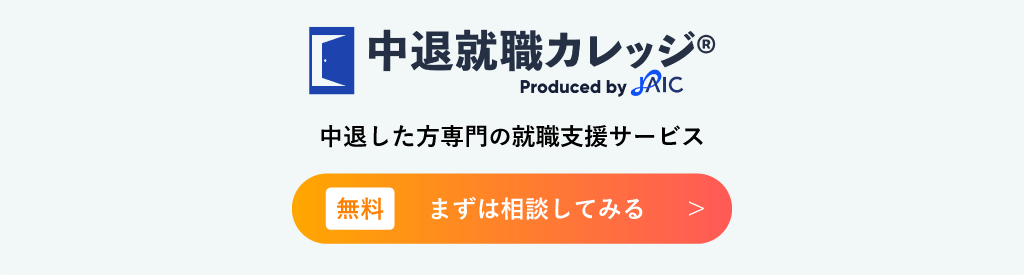
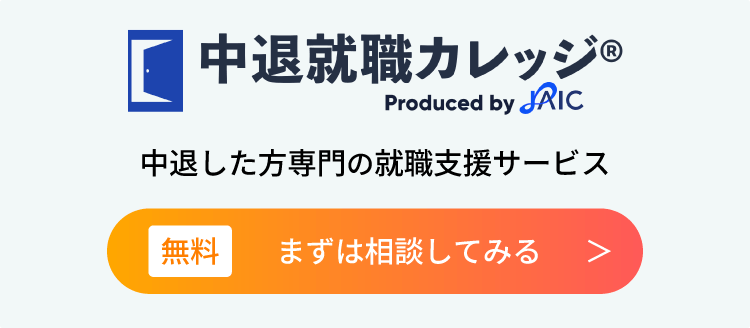
この記事の目次
大学中退率は約2%
令和5年度時点の大学中退率は2.04%です。短大生の中退率は3.95%、大学・短期大学全体では2.10%となっており、およそ50人に1人以上が中退しています。
文部科学省の令和5年度の調査によると、全国の大学に在籍する学部生のうち、中途退学者は約5万3,000人で、学部生全体の約2%にあたります。
割合だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、実際には1年間で5万人以上が中退していることを考えると、大学中退は決して珍しい出来事ではないことが分かるでしょう。
| 学校種別 | 中退者数(令和5年度) | 学生数に占める中退者数の割合 |
|---|---|---|
| 大学 | 53,470人 | 2.04% |
| 短期大学 | 3,240人 | 3.95% |
| 大学・短期大学全体 | 56,710人 | 2.10% |
出典:文部科学省「令和5年度 学生の中途退学者・休学者数の調査結果について」
1. 大学中退率の推移
大学中退率は年々上昇しています。令和3年度時点では大学・短期大学の中退率は1.79%でしたが、令和4年度は1.94%、令和5年度は2.10%と増加傾向にあることが特徴です。
わずかな差に感じるかもしれませんが、人数にすると毎年およそ4,000人ずつ増えており、大学・短期大学の中退を検討する学生が増えていることが見て取れます。
なお、大学院生の中退率は令和3年度から令和5年度までに0.71ポイント下がっています。このことから、中退率の一貫した増加は大学特有の傾向ともいえるでしょう。
| 学校種別 | 大学・短期大学 中退者数 | 学生数に占める中退者数の割合 |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 48,694人 | 1.79% |
| 令和4年度 | 52,459人 | 1.94% |
| 令和5年度 | 56,710人 | 2.10% |
出典:文部科学省「令和5年度 学生の中途退学者・休学者数の調査結果について」
出典:文部科学省「令和4年度 学生の修学状況(中退者・休学者)等に関する調査 結果」する調査及び学生の修学状況(中退・休学)等に関する調査の結果について」
2. 大学別の中退率
続いて、大学の区分や大学院の修士課程・博士課程といった観点で中退率を見てみましょう。
先ほどと同じく文部科学省が調査した中退率のデータをまとめると以下の通りです。
| 区分 | 国立 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|---|
| 学部(大学)中退率 | 1.2% | 1.23% | 2.88% |
| 修士課程中退率 | 3.09% | 4.38% | 6.02% |
| 博士課程中退率 | 7.33% | 8.75% | 9.46% |
| 短大中退率 | ※国立無し | 1.88% | 3.86% |
この調査結果からは、以下の2つの事実が分かります。
- 短大、大学、大学院における中退率は私立>公立>国立の順で下がっていく
- 大学以上の中退率は学部>修士>博士の順で下がっていく
逆に言えば、私立大学の学生の方が国立大学の学生よりも大学中退率が高いということです。
これは、国立大学の方が入学難易度が高い傾向にあり、私立大学よりも苦労して入学している人が多い傾向から来ているとも考えられます。
また、修士課程、博士課程とより上級の学問を学ぶにつれて中退率が上がっていってしまうのは、年齢が高まるにつれて学問ではなく就職する人が増えていくことに起因していると考えられます。
3. 学歴別の中退率
令和5年度の学歴別中退率を比べると、短大が3.95%となっており、大学院(2.85%)、高等専門学校(2.09%)、大学(2.04%)が続きます。
| 学校種別 | 中退率(令和5年度) |
|---|---|
| 短期大学 | 3.95% |
| 大学院 | 2.85% |
| 高等専門学校 | 2.09% |
| 大学 | 2.04% |
出典:文部科学省「令和5年度 学生の中途退学者・休学者数の調査結果について」
なお、JAICが中退者・中退予定者314人に実施したアンケートでは、「4年制大学に在籍していた(在籍している)」と答えた人が8割弱を占めています。
このことから、中退率で見ると短大が高いものの、中退者の人数でいうと4年制大学が大きな割合を占めていることが伺えます。
| 学校種別 | 中退者・中退予定者の割合 |
|---|---|
| 4年制大学 | 78.3% |
| 専門大学 | 12.4% |
| 専門学校 | 4.1% |
| 短期大学 | 2.2% |
| 大学院 | 1.6% |
| 6年制大学 | 1.3% |
出典:JAIC「2023年度中退データ集|Q2.中退した(予定の)学校の種類」
中退経験者3000人以上に就職支援!
未経験からの就職をサポート!
※2018/2~2024/4の当社「中退就職カレッジ」主催の面接会参加人数
学年別の大学中退率
続いて、学年別に大学中退率を見ていきましょう。
| 大学中退時の学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 18.1% | 31.5% | 22.7% | 27.7% |
| 女性 | 38% | 39% | 12.2% | 10.7% |
| 合計 | 25.7% | 34.4% | 18.7% | 21.2% |
この調査結果から分かることとして以下が挙げられます。
- 大学2年生で最も大学中退率が高まる
- 大学4年生でもう一度中退の波が来る
大学に入学したての1年生時点では、大学に対する期待や夢を抱いていることもあり、比較的大学中退率は男性を中心に低めとなっています。しかし、2年生に進級すると大学に対するモチベーションが維持できない人が一気に中退します。
その波に耐えた人は3年生になっても大学に通い続けることができますが、最後4年生になって単位が足りなかったりなどの理由でもう一度中退の波が来る。というのが大まかな大学中退の外観と言えます。
もちろん大学を中退する理由というのは、学業不振やモチベーション低下といった項目以外もありますが、学年別に大学中退率が違うという事実は知っておいて損はないでしょう。
参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「大学等中退者の就労と意識に関する研究」
偏差値別の大学中退率
最後に、偏差値別の大学中退率についても解説します。独立行政法人 労働政策研究・研修機構「大学等中退者の就労と意識に関する研究」の結果をまとめると以下の通りです。
| 偏差値 | 国公立 | 私立 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 39以下 | ※該当無し | 17.2% | 17.2% |
| 40-44 | ※該当無し | 16.9% | 16.9% |
| 45-49 | 6.7% | 11.6% | 11.5% |
| 50-54 | 3.8% | 8% | 6.8% |
| 55-59 | 3.6% | 6% | 5% |
| 60-64 | 1.6% | 3.4% | 2.9% |
| 65-69 | 2.4% | 3.2% | 3% |
| 70以上 | 1.5% | 3% | 2.2% |
この調査結果から分かることは単純に大学の偏差値が上がるにつれて大学中退率は下がっていく傾向にあるということです。これは国公立でも私立でも同じ傾向となっています。
偏差値は50が平均値となりますが、それよりも低い49以下の偏差値の大学に関しては、中退率が10%を超えてくるのが特徴的です。
未経験割合96.8%
中退しても未経験から就職できる!
※2024/2~2025/3の中退就職カレッジ参加者のうち、当社が把握している正社員未経験者の割合
大学を中退する人は何年生が多い?
「2023年度中退データ集」によると、大学を中退する人は、2年生が多いことが分かります。また、文系では入学3年目と4年目、理系では2年目と3年目で多くなる傾向が見られます。
| 入学後何年目に中退したか(中退予定か) | 文系 |
|---|---|
| 1年目 | 15.6% |
| 2年目 | 24.3% |
| 3年目 | 23.1% |
| 4年目 | 20.9% |
| 5年目 | 10.9% |
| 6年目 | 3.4% |
| 7年目 | 1.6% |
| 8年目 | 0.3% |
| 入学後何年目に中退したか(中退予定か) | 文系 | 理系 |
|---|---|---|
| 1年目 | 14.1% | 13.2% |
| 2年目 | 22.8% | 23.2% |
| 3年目 | 24.8% | 23.2% |
| 4年目 | 24.8% | 19.2% |
| 5年目 | 9.4% | 13.9% |
| 6年目 | 2.0% | 5.3% |
| 7年目 | 2.0% | 1.3% |
| 8年目 | - | 0.7% |
出典:JAIC「2023年度中退データ集|Q10.実際に中退をしたのは(する予定なのは)入学後何年目か(文系理系別)」
文系・理系ともに入学1年目の中退は15%未満に留まっており、2年目以降に増える点は共通です。
一方で、文系は3年目と4年目が24.8%で最多、理系では2年目と3年目が23.2%で最多となっており、理系のほうが早い段階で中退を選ぶ人が多い傾向が見て取れます。
なお、この調査には様々な学歴が含まれていますが、回答者の約8割が「4年制大学」のため、ここで示した結果は大学中退率の傾向として一定の参考になるでしょう。
中退を考え始めた学年
中退を考え始めた学年としては、文系・理系ともに入学後2年目が特に多くなっています。
文系では28.8%、理系では32.5%が2年目に中退を考え始めており、約3割の学生が2年目で退学を意識し始めていることが分かります。
| 中退を考え始めたのは入学後何年目か | 文系 | 理系 |
|---|---|---|
| 1年目 | 25.5% | 19.2% |
| 2年目 | 28.8% | 32.5% |
| 3年目 | 22.9% | 23.8% |
| 4年目 | 17.6% | 17.9% |
| 5年目 | 3.9% | 4.0% |
| 6年目 | 1.3% | 2.0% |
| 7年目 | - | 0.7% |
文系・理系どちらも、入学後3年目までに8割ほどの学生が中退を検討していることは共通です。
一方、文系は1年目に中退を考え始める割合が25.5%で、理系の19.2%より6.3ポイント高くなっています。このことから、文系学生のほうが入学直後に中退を迷い始める人が多い傾向にあることが伺えます。
大学中退率に影響!大学を中退をする理由6選
文部科学省の調査によると、大学の中退理由としては「転学・進路変更等」が最も多く、次に「学生生活不適応・修学意欲低下」が続きます。
「就職・起業等」や「経済的困窮」を理由とする中退も多く、「学力不振」「精神疾患」による中退者も少なくありません。
専門的に学びたい分野が見つかって別の学校へ転学したり、学内の雰囲気や人間関係に馴染めずに大学を離れたりするケースはよく見られます。
大学で学ぶよりも「働くこと」にやりがいを感じ、就職や起業を選ぶ人もいます。このように中退の背景には様々な事情があり、必ずしもネガティブな理由による中退とは限りません。
出典:文部科学省「令和5年度 学生の中途退学者・休学者数の調査結果について」
1. 転学した
大学在学中に転学するケースとしては、次のようなものが考えられます。
- 専門的に学びたいことができ、専門学校に転学した
- 受験生時代に第一志望だった大学に仮面浪人して受験。合格できたため転学した
- 大学のカリキュラムが自分に合わずに転学した
- 何らかの理由で引っ越しをしなければならずに転学した
転学による大学中退は、ポジティブな理由とネガティブな理由に分けられます。
いずれにせよ転学は自分の環境を大きく変えるだけでなく、周囲の人間関係も大きく変わることになりますので、慎重に検討する必要があるでしょう。
また、転学に当たっては転学先に入学するための受験が必要になることがほとんどですので、大学に通いながら受験勉強をしなければならないという点も知っておいてください。
2. 大学に馴染めなかった
大学に入学し、自分の学びたい学部に通えるようになったのは良いものの、人間関係や大学そのものの雰囲気に馴染むことができずに中退する人は少なくありません。
特にサークルやゼミなど、少数で活動するような場面において、人間関係にトラブルを抱えてしまったような人は、フェードアウトするように大学を中退してしまう傾向にあります。
大学は高校までとは異なり、キャンパスの面積が広いだけでなく様々な学生が通っています。そのため、自分から働きかければいくらでも人間関係を築いていくことが可能です。
ただ、コミュニケーション能力に自信がなかったり、特定の学生や教授との相性が極端に悪かったりする場合、大学に馴染めず中退する選択を取る人がいるのも仕方ないことなのかもしれません。
3.中退して就職した
大学に進学する多くの人は、大学を卒業してそのまま新卒として会社に就職し、社会人になっていきます。しかし、中には大学在学中に就職する道を選び、就職するために中退する選択をする人がいます。その理由は2つ考えられます。
1つは大学に通い続けるモチベーションが低下してしまったという理由です。
単位不足や留年を何度もしてしまうと、次第に大学に通う意義が分からなくなり、「このまま大学に通い続けているよりも、就職した方が良いのではないか」と考えるようになります。
このような考え方の変化によって、大学中退から就職への道を選ぶ人が一定います。
2つ目は、大学在学中に起業してビジネスに専念するパターンです。
在学中での起業はそこまで珍しいものではありませんが、ビジネスが軌道に乗ってきたり、本格的にビジネスに集中したいといった思考になった人は、大学に通う時間が勿体無いと感じて中退します。
いずれの理由であっても、中退後のステップが明確となっているため、そこまで悪い中退理由とは言えないでしょう。
4. 経済的に厳しくなった
JAICの調査によると、「経済的事情・家庭問題」によって中退する学生は、文系では22.4%、理系では14.5%を占めています(※1)。
大学に通うには授業料や施設費に加えて、理系では実験費用が数十万円かかることもあります。大学によっては留学が必須の場合もあり、経済的な負担は決して小さくありません。
たとえば私立大学の平均授業料は95万円(※2)で、施設費などを含めると年間100万円を超えるケースが一般的です。
家族に頼らず、アルバイトを増やしたり、奨学金を利用したりして学費を工面する学生もいますが、それでも支払いが難しい場合があります。結果として経済的に追い込まれ、中退を選ばざるを得ない状況になる学生は多いのです。
※1 出典:JAIC「2023年度中退データ集|Q8.中退理由(文系理系別)」
※2 出典:文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
5. 学業不振
試験やレポートで単位を落とし続けたことで、卒業に必要な単位の取得が難しくなり、自ら中退を選ぶ学生も少なくありません。
「授業内容に興味が持てなかったから」という理由も多く、JAICの調査では文系が29.1%で最多、理系は25.4%で2位となっています。
たとえば理系の学生であれば、実験や専門科目の難易度が上がるにつれて授業についていけなくなり、次第に意欲を失っていく人もいます。
サークルやアルバイト、長期インターンシップなどに熱中し過ぎた結果、学業への関心が薄れ、勉強に身が入らなくなるケースも見られます。
こうして学業不振が続くと大学に通う意義が見い出せなくなり、最終的に中退を選ぶ学生が多いのです。
6. 精神的な不調
学業・アルバイト・人間関係など、複数の心理的な負担が重なることで心身のバランスを崩し、中退を決断する学生もいます。
JAICの調査でも、「体調不良」を理由に中退した学生は文系で7.5%、理系で7.2%にのぼります。
たとえば上京して一人暮らしを始めた学生の場合、周りに頼れる人がいないことで孤立感を抱えがちです。そこに慣れないアルバイトやレポート提出が重なると、気持ちに余裕がなくなり、生活全体が不安定になりやすいのです。
気分の落ち込みが原因で授業に出られなくなり、単位を落として不安をまた抱く…といった悪循環に陥るケースも珍しくありません。
結果として「今の辛い状況からとにかく離れたい」という思いから、大学中退を選ぶ学生も多いのです。
大学中退率から見る大学を辞める人の特徴
大学を辞める人の特徴として代表的なのは「目的があいまいなまま進学してしまった人」です。実際に調査では約4割が「なんとなく」や「親や先生に言われて」と回答しており、目標を持てずに学ぶ意味を見失いやすい傾向があります。
ほかにも、在学中に新たな夢や挑戦したいことを見つけて大学以外の道を選ぶ人や、学部内容や環境とのミスマッチから通えなくなる人も少なくありません。また、人間関係を築けず孤独感を抱えたまま相談できずに辞めるケースもあり、中退には学業面だけでなく心理的な要因も関わっています。
それぞれの特徴について詳しく解説していきます。
1. 大学に通う目的が明確になっていない
大学を中退する人の中には、入学時点で「なぜ大学に進学するのか」という目的が十分に定まっていなかったケースがあります。周囲の流れや親の期待から進学したものの、具体的な目標がないまま講義を受けると、学ぶ意味を見失いやすくなります。その結果、モチベーションが続かず出席や単位取得が難しくなり、中退という選択に至ることがあります。
大学中退者・予定者322人に「大学や専門学校への進学理由」を調査したデータを見ると、約4割が「なんとなく・親や先生に言われて・進学が当たり前だと思った」と回答しています(※)。
目的が曖昧だと、自分に合った学びや進路を見つけにくい点が特徴です。
※出典:JAIC「2023年度中退データ集|Q4.大学や専門学校への進学理由」
2. 大学以外でやりたいことが見つかった
在学中に新たな夢ややりたいことが明確になり、それを優先するために中退を選ぶ人もいます。例えば、起業に挑戦したい、専門学校で技術を学びたい、芸術やスポーツなどの分野で実績を積みたいと考える場合です。
大学に在籍し続けるよりも、自分の時間を投資して早く行動した方が良いと判断し、中退を前向きな選択肢とするケースです。このような人は、自己決断力や主体性が強いという特徴も見られます。
3. 入学後のミスマッチを感じた人
進学した学部や学科が、自分の興味や適性と合わなかったことが理由で中退する人も少なくありません。入学前に想像していた内容と実際の授業が大きく異なり、「思っていた勉強ではない」と感じることがあります。
また、大学の雰囲気や人間関係、生活スタイルが合わず、居心地の悪さから通学を続けられなくなる場合もあります。こうしたミスマッチを放置すると学業が続かず、最終的に中退という選択に至ることが特徴です。
4. コミュニケーションが苦手
大学生活では友人や教授とのつながりが「心の支え」になりますが、コミュニケーションに苦手意識がある人は人間関係をうまく築けず、悩みを抱え込みやすくなります。
たとえば、勉強やアルバイト、恋愛の悩みを気軽に相談できる友人がいなかったり、授業で疑問があっても教授に質問できなかったりすると、だんだんと孤独感が強まっていくでしょう。
ちなみに「中退を誰にも相談していない」と答えた学生は2割弱にのぼり、誰にも助けを求められないまま自ら中退を選択してしまうケースも少なくありません(※)。
人との関わりを避け続けると「大学に居場所がない」と感じやすくなるため、こうした孤立感も大学中退率が高まる要因となっているのです。
大学中退前にほしかったサポート
大学中退者の多くは、適切な支援があれば辞めずに続けられたと考えています。特に、教員や職員からの「学習支援」と「心理的な支援」がほしかったと考える人は少なくありません。
学習面では、レポートや研究の進め方を丁寧に指導してもらえれば中退を避けられたと感じる人もいるようです。実際、JAICの調査でも「学習支援があれば中退しなかった」と答えた人が37.8%と最も多い結果が出ています。
心理面では、不安や悩みを相談できる場があれば良かったと考える学生が多く、同調査でも29.9%が「心理相談の場があれば中退しなかった」と答えています。
出典:JAIC「Q12.中退(中退検討)前に得られていれば、中退しなかったと思うサポート」
1. 教員や職員などからの学習支援
レポートの書き方や研究の進め方など、学習面で教授から丁寧な指導を受けられていれば中退を思い留まったかもしれない、と考える人は少なくありません。
実際にJAICが中退者・中退予定者に行ったアンケートでは、「中退(中退検討)前に得られていれば、中退しなかったと思うサポート」という質問に対し、37.8%が「教員や職員からの学習支援」と回答しています(※)。
先ほど「大学を中退する理由」でも触れたように、学業への意欲が低下して辞めてしまう学生は少なくありません。こうした点からも、大学側の学習支援は、中退を防ぐための大きな支えになるといえるでしょう。
2. 教員や職員などとの心理相談
教授や職員と気軽に話せる「心理相談」の場があれば、不安やストレスとうまく付き合うことができ、中退を考えずに済んだと答える学生もいます。
JAICの調査でも、「中退前に得られていれば、中退しなかったと思うサポート」として、29.9%が「教員や職員との心理相談」と回答しています(※)。
大学生活は、学業の悩みや将来の進路、恋愛や人間関係など、一度に多くの悩みが重なり、心の負担が増えがちです。その点、不安や悩みを相談できる場があれば「心理的な支え」ができ、中退を思い留まったかもしれないと考える人も多いのです。
大学中退率から考える中退後の進路
大学を中退した後の進路は、大きく5つに分けられます。具体的には、民間企業への就職、フリーターとしてアルバイト生活をする、起業、別の大学や専門学校への編入、そして結婚や家事手伝いです。
10代・20代の中退者・高卒者を正社員として採用する企業は多いため、中退の前後に就職活動を行い、そのまま正社員として働き始める人は少なくありません。
一方で、アルバイト生活を続けながら、自分の将来についてじっくり考える人もいます。数は多くありませんが、自ら会社を立ち上げる人もいるなど、大学中退後の進路は人によって様々です。
民間企業に就職する
自分自身の生活を支えるために、中退後に社会人として就職する道を選択する人は多くいます。
JAICが中退者317人に「就職しようと思った理由・きっかけ」を質問したところ、「自立したい」と「親孝行・親を安心させたい」という回答が7割弱を占めました。この結果からは、親に頼り続けるのではなく、「自分の力で生きていきたい」という意志も見えてきます。
実際、中退者の多くは大卒者よりも早く社会へ出て働き始めるため、実務経験を通じて専門的なスキルを身につけ、経済的に自立した生活を送れている人も少なくないのです。
▼中退者が就職しようと思った理由・きっかけ
| 自立したい | 42.3% |
| 親孝行・親を安心させたい | 26.2% |
| 年齢的な焦りや漠然とした将来への不安 | 15.1% |
| 安定的な収入が欲しくなった・必要になった | 10.7% |
| 同期や友人など周囲の人が就職や卒業をしたから | 5.7% |
出典:JAIC「Q13.就職しようと思った理由・きっかけ」
フリーターとして働く
大学中退後の進路に真剣に向き合うことができなかったり、就職活動に失敗し続けていたりすると、お金だけがどんどん減っていく状態になります。生活していくためにも、フリーターとして生活していくといった進路を選ぶ人も少なくありません。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構「大学等中退者の就労と意識に関する研究」によれば、大学中退直後にフリーターとして働きたいと思っていたような人は11.1%程度しかいませんでしたが、中退後に実際にフリーターになっていたという人は27.3%となっています。
つまり、フリーターになりたくてなったのではなく、「なってしまった」という人が大学中退者には多いということです。フリーターは将来的に見て非常に不安定な働き方ですので、特別な理由や思いがないのであれば、早々に民間企業へ就職できるようアクションするのがおすすめです。
起業する
大学中退理由のところでも触れましたが、中退後に起業をする人も少なくありません。今ではパソコン一台さえあれば誰でもビジネスができる時代となっていますので、ビジネスとしてやりたいことが明確にある場合は、中退後に起業するのも良いでしょう。
ただ、起業をすることが目的となってしまい、肝心の「起業をして何をするか」が固まっていない場合、結局具体的な行動に落とし込むことができずにフリーターになるというケースも考えられます。
大きな目標を掲げることは重要ですが、起業をするのであれば「具体的に何をいつまでにするのか」というプランニングをしっかり行うようにしてください。
別の大学や専門学校に編入する
大学中退後に別の大学や専門学校に編入するという進路も考えられます。特に専門学校であれば、随時入学受付をしているケースも多く、思い立ったらすぐに学び始められるのが特徴です。
ただ、この場合も大学や専門学校に目的意識を持って編入するのがポイントです。社会に出たくないからなどの理由で別の学校に逃げるように進学しても意味がありません。何を学び、どういう働き方をしていきたいのか、今一度言語化していきましょう。
結婚や家業を手伝うケースも
割合としては少ないですが、大学中退を機に結婚をする人もいます。ライフステージが大きく変わることになりますので、結婚をする場合はパートナーとしっかりと話し合い、仕事や家計をどうしていくかの目線合わせを行うのがおすすめです。
また、実家が自営業をしているのであれば、家業を手伝うという進路を選択するケースもあります。家業である程度経験を積み、そのままその世界で自分も自営業として働いていくこともあれば、民間企業への就職にシフトすることも考えられます。
いずれにせよ、自分の人生をどうしていきたいかから逆算し、後悔しない選択をするのがポイントとなります。
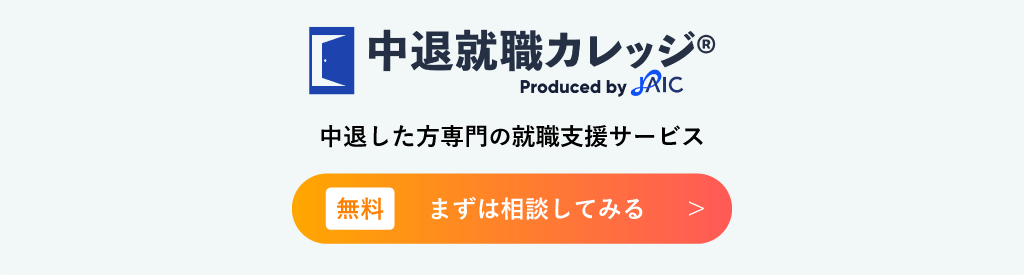
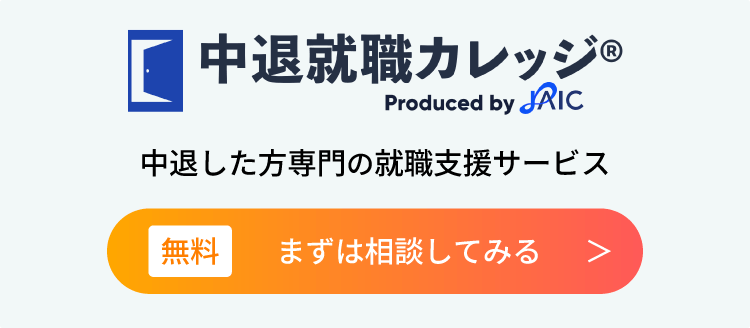
大学中退者の就職率から考える就職への影響
大学中退者の就職率は34%となっており、大卒の就職率が69%、高卒の就職率が68%であることから考えても、明らかに大学中退は就職率に悪影響をもたらすと言えます。
ここでは、具体的に大学中退が就職活動にどのような影響を与えるのかについて解説していきます。
大学中退者の就職率はなぜ低い?就職成功率を上げるやり方も解説
学歴が高卒になるため不利
大学を中退することにより、最終学歴は高卒になります。高卒だと、大卒を応募条件とする求人に応募できなくなってしまいますので、応募先が狭まるという観点で大きく不利になります。
また、募集条件に学歴の制限が無かったとしても、大卒と高卒から応募が同時にきた場合、多くの企業は大卒の人を採用したいと考える傾向にあります。これは、大学を卒業するだけの地頭と継続力があると思われやすいからです。
このように、大学中退は高卒になるというだけでも就職活動に大きく響いてくることが分かります。
面接官の心象的に不利
大学中退率は先ほど解説した通り2%です。大学生が100人いれば、そのうち2人しか中退者がいないということですので、それだけで以下のようなネガティブなイメージを面接官は感じることになります。
- 大学を卒業できない人が、会社で長く働けるだろうか?
- 採用しても、すぐに嫌になって退職してしまうのではないか?
- 人柄的に問題があるのではないか?
大学中退の事実は応募時点で基本的に面接官に伝わっていますので、面接がスタートする段階からネガティブなイメージを持たれるのは明確なデメリットと言えます。
面接対策が不十分だと、面接官が感じているネガティブイメージを払しょくできず、そのまま見送りになることが考えられます。事実として、大学中退者が大卒や高卒よりも就職率が非常に低いのは、この観点が大きいと考えられるでしょう。
空白期間があるとさらに不利
求人募集企業は、就職していない空白期間が長い人を採用することは避けがちです。その理由は、ひとえに「採用しても会社で上手くやっていけなさそう」と思われやすいことにあります。
なお、フリーターとして働いていた期間も、就職活動においては空白期間とみなされます。そのため、フリーターの期間が長くなればなるほど就職も難しくなりやすいため、合わせて認識しておくようにしてください。
大学中退から就職する時のコツ
大学中退者の就職率は低いという事実はあるものの、一方で正社員として就職できている人がい社会人経験がなくても正社員として採用される可能性があるので、まずは「学歴不問」や「未経験歓迎」と記載された求人を探しましょう。特に建築系の技術職や営業職など、採用倍率が低い仕事は“狙い目”といえます。
面接では「中退理由」を前向きに伝えることが大切です。学習意欲の低下などネガティブに受け取られやすい理由は、「この経験をどう生かすか」という形に言い換えて伝えることがポイントです。
就活が初めてで不安な人や、中退者向けの正社員求人を効率的に探したい人は、内定獲得に向けて無料でサポートしてくれる就職エージェントの利用も検討しましょう。
学歴不問・未経験歓迎求人を探す
大学中退者が就職活動をするのであれば、学歴不問で募集している求人を中心に応募するのがコツです。
学歴不問の求人であれば、高卒となる大学中退者でも内定を獲得できる可能性があります。加えて、学歴不問の求人には中卒や大学に進学したことのない高卒も応募してきますが、一度でも大学に進学できた能力があるという点が評価され、選考で有利になることも期待できるでしょう。
また、学歴不問に合わせて未経験歓迎の求人に応募するのもポイントです。未経験歓迎の求人であれば、社会人経験がない人でも内定をもらいやすく、加えて入社後の研修制度が整っていることが多いため、社会人デビューを円滑に進められるでしょう。
特に求人サイトを使って就職活動を進めていきたいと思っている場合、これら2つの条件を必ずチェックした上で求人を検索するようにしてください。
倍率の低い仕事を選ぶ
やりたい仕事が特別無いのであれば、就職倍率が低い仕事から検索していくというのもコツになります。
求人サイトdodaの調べによれば、以下の仕事は比較的求人倍率も低いため、大学中退者であっても内定を獲得しやすいと考えられます。
- 建設系技術職
- 事務・管理系
- 営業職
- 機電系エンジニア
特に営業職については、業績さえ出せれば大学中退者でも大卒以上に稼ぐことができますし、求人数が非常に多いためおすすめです。
なお、事務職は求人数に対して就職希望者が非常に多い人気の仕事となりますので、大学中退者が就職を希望する場合は、厳しい選考が待ち受けている可能性があるため注意してください。
資格を取得する
ほとんどの仕事において、資格が必須となるケースはありません。ただ、資格を持っておくことで選考で有利になることは考えられるため、時間的余裕があるならば資格取得も検討してみると良いでしょう。
大学中退者でも勉強に取り組みやすく、幅広い業界・仕事でアピールできる資格としては、以下のようなものが挙げられます。
- TOEIC
- 日商簿記検定
- ファイナンシャルプランナー
- 秘書検定
- ビジネスマナー検定
- マイクロソフトオフィススペシャリスト
就職活動における資格の有用性については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせて参考にしてみてください。
大学中退理由をポジティブに話す
大学を中退していると、高い確率で面接官に大学中退理由を聞かれます。この時、ネガティブに中退理由を伝えてしまうと、面接官に対してマイナスイメージを植え付けてしまうことになり、選考に通過しにくくなります。
上手く大学中退理由をポジティブに話すことができれば、面接官に魅力的な人材というアピールにも繋げられることができるため、大学中退理由については必ず言語化し、面接で語れるようにしてください。
大学中退理由の伝え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
応募する企業のことをしっかり調べる
応募する企業については、面接までに必ず徹底的に調べるようにしましょう。企業調査の上で確認すべきものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 求人票
- 求人広告
- 企業ホームページ
- 就職口コミサイトでの口コミ
- 決算説明会資料(上場企業の場合)
企業のことを調べることは、そのまま面接での熱意をアピールすることに繋がりますし、入社後の悪いギャップを感じにくくなるという点でも有効です。
企業研究の詳しいやり方については、以下の記事を参考にしてみてください。
就職エージェントを活用する
何から就職活動を始めればいいのか分からないという大学中退者には、就職エージェントの利用がおすすめです。
就職エージェントを利用することで、就職活動に必要な知識を直接アドバイザーが教わることができるだけでなく、履歴書の添削や模擬面接の実施をしてもらえるため、就職成功率を引き上げることができます。
また、キャリアカウンセリングを経て、自分の希望する仕事の求人の紹介を受けられるようになるため、就職活動全般にかかる期間を大幅に短縮する期待も持てます。
就職エージェントの利用は無料となっていますので、気になるサービスを見つけたらまずは登録してみることから始めると良いでしょう。
大学中退率に関する注意点
大学生活が精神的にキツイ場合、そのまま通い続けると状態がさらに悪化してしまうリスクがあるため、大学中退を検討しても良いでしょう。
ただし「なんとなく合わない」など、中退後に明確な目標やビジョンがないまま大学を辞めるのはおすすめできません。高卒になるので就職で不利になる場合があるなど、大卒と比べて何かとデメリットを感じるケースが多いからです。
また、奨学金を借りている人は、中退後に返済が待っていることにも注意が必要です。たとえば日本学生支援機構の「貸与型奨学金」の場合、貸与終了月の翌月から数えて7ヶ月目から返済が始まります。
本当にキツいなら中退してもいい
大学中退率は2%と極めて低く、中退により自分が少数派になることは避けられません。しかし、真剣に検討してもなお「どうしても自分は大学に通い続けられない」と感じるのであれば、大学を中退してもいいでしょう。
精神的にキツい中で大学に通い続けていれば、精神病を患ってしまうリスクもあります。人生において、心身ともに健康な生活を送るのが最も大切と言っても過言ではありませんし、そのためであれば大学を中退するという選択肢は持っておいてもいいと考えられます。
明確な意思がないなら大学を卒業した方が有利
大学中退後に明確なビジョンや進路を持っておらず、ただなんとなく合わないという理由だけで大学を中退するのはおすすめできません。明確な意思がないのであれば、大学を卒業して就職活動をした方が後々あらゆる面において有利になります。
大学へのモチベーションがどうしても湧かないのであれば、中退ではなく休学という選択肢も検討してみてください。
奨学金の返済が待っていることにも注意
日本学生支援機構の「貸与型奨学金」を利用していた場合、中退後(貸与終了月)の翌月から数えて7か月目に返済が始まる点に注意が必要です。
貸与終了後に「返還確認票」「返還のてびき」「口座振替(リレー口座)加入申込書」が届き、指定された期限までに金融機関で口座加入手続きを済ませる必要があります。
JAICの調査では、中退者の約37%が奨学金を受給していたと回答しています。返済が滞ると延滞金が加算されたりするため、安定的に返し続けるだけの収入や貯蓄が欠かせません。
そのため奨学金を利用している人は、返済開始の時期や毎月の支払い額をしっかりと確認し、中退後に本当に返し続けられるかを冷静に考えるようにしましょう。
出典:日本学生支援機構「よくあるご質問|貸与中~貸与終了までの手続き」
出典:JAIC「2023年度中退データ集|Q5.奨学金の受給状況」
まとめ
大学中退率は2%と極めて低いです。また、大学の区分や偏差値によっても大学中退率は大きく変わるというデータもありますので、この記事の内容を参考にしつつ、本当に大学を中退していいのかどうかの検討を進めてみてください。
なお、大学を中退するとどうしても就職成功率は下がりやすいため、もし正社員就職を目指して中退するのであれば、記事で解説した就職活動のコツを意識していきましょう。

こんな方におすすめ!
- 学歴に自信がないから就職できるか不安
- 就職について、誰に相談したら良いか分からない
- 中退しようかどうかを迷っている
- 学歴に自信がないから就職できるか不安
- 就職について、誰に相談したら良いか分からない
- 中退しようかどうかを迷っている
当社の就職に関するコンテンツの中から、大学中退後の就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- 大学中退者が就職するには?就活のやり方のコツを徹底解説!
- 大学中退者の就職先におすすめの仕事15選!選び方のポイントも解説
- 大学中退後の就職は厳しい?中退して良かった声や就職成功法を解説
- 履歴書に中退を書かないのはNG?大学中退の書き方を見本付きで解説!
- 大学中退理由は武器になる!履歴書/面接での効果的な伝え方
- 大学中退者の就職体験談総まとめ!11人の成功談を徹底分析
- 大学中退者は就職できない?厳しい理由と行った方いい相談先を解説
- 大学中退者向け就職サイト5選!選び方や活用法を解説!
- 大学中退してよかった理由と後悔した理由を実際の声から解説
- 大学中退は人生終了?就職を成功させる方法や注意点を解説!
- 大学中退したその後の進路7選!将来どうなるか選択肢を解説