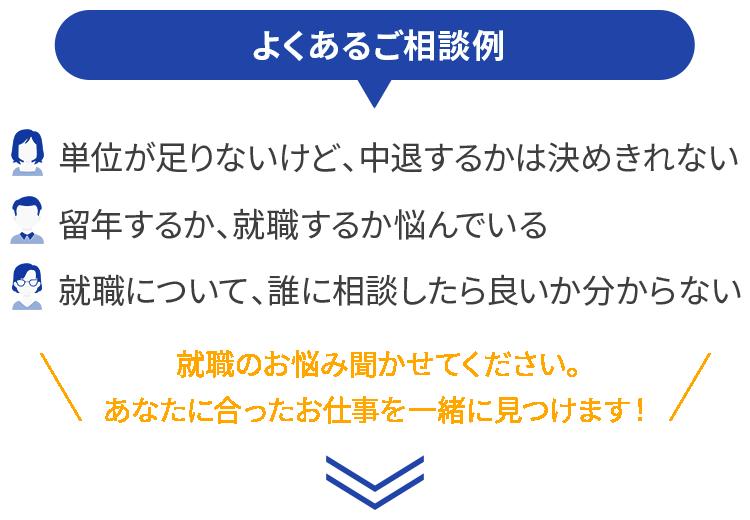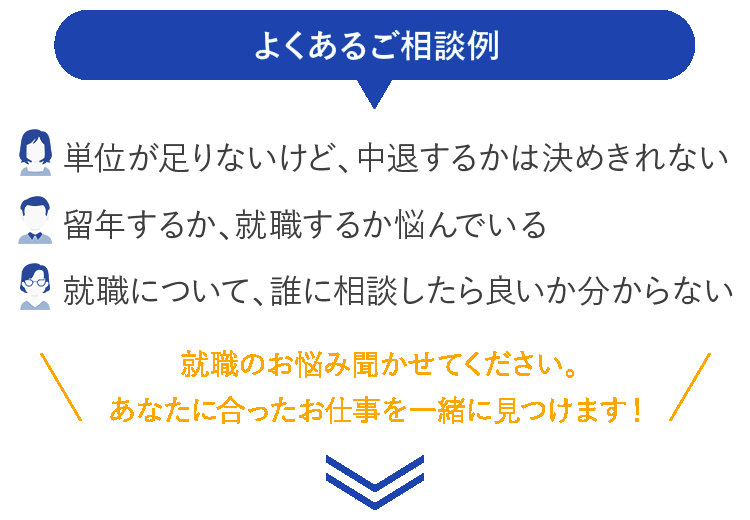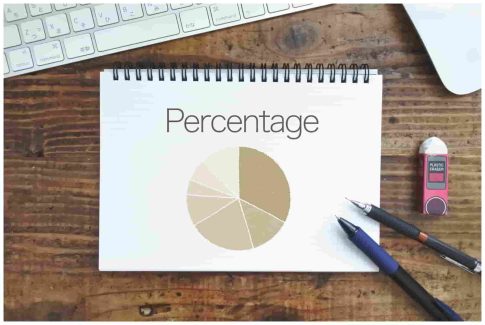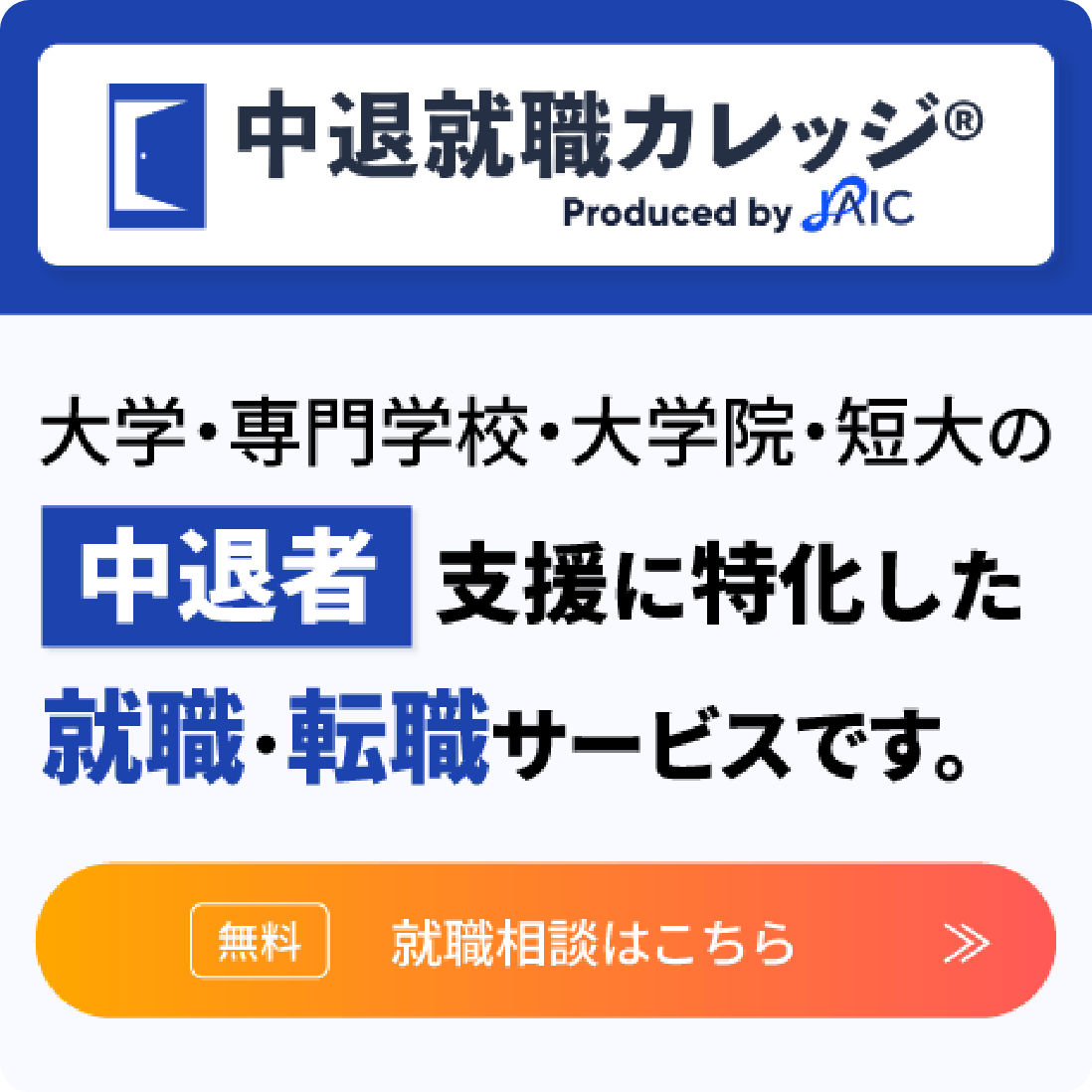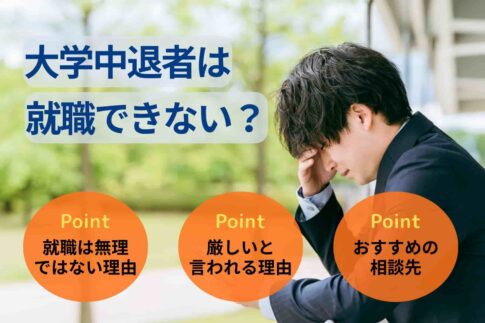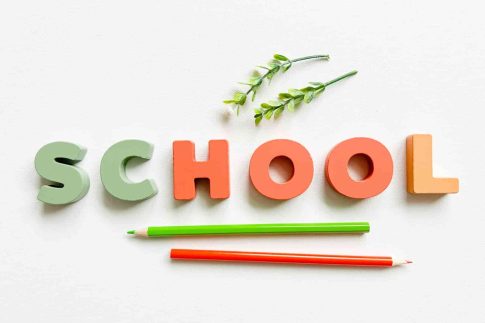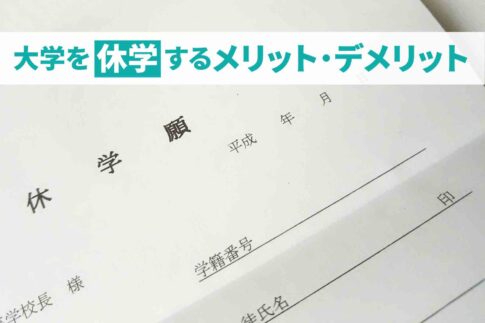大学院を中退して公務員を目指す方!就職成功のポイントを解説

大学院を中退していたとしても公務員になることは可能です。
公務員試験は学歴にかかわらず受験できるため、大学院を中退した後に公務員試験対策に取り組み合格することができれば、中退という経歴があっても問題なく公務員として活躍できます。
ただし、大学院を中退すると修士号や博士号が取得できないだけでなく、公務員試験そのものに時間やお金がかかるなど、公務員を目指す上で認識しておくべき注意点があります。
この記事では、大学院を中退して公務員を目指したいと考えている人が知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。大学院中退後に公務員になることを考えている方はぜひ読んでみてください。
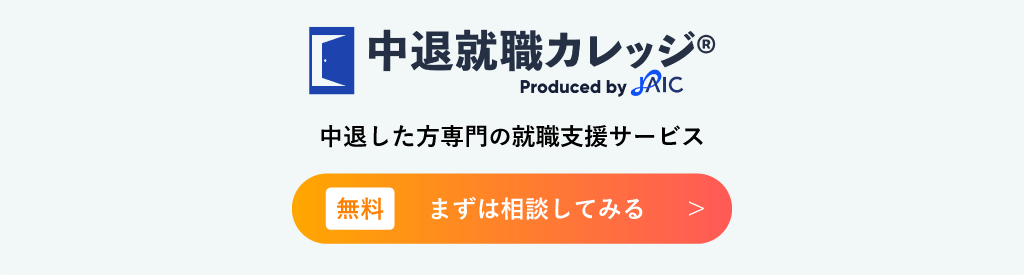
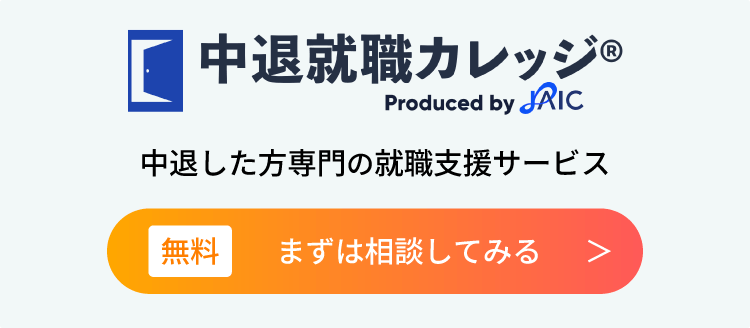
この記事の目次
大学院を中退すると公務員になれないの?
大学院を中退しても、試験に合格すれば公務員になれます。なぜなら、公務員試験は高等学校を卒業していれば、学歴にかかわらず受験できるからです。
また、公務員試験に学歴フィルターは存在しておらず、良い大学を出ていても選考時に有利なわけでもありません。
例えば、高校を卒業後に一般企業へ就職した場合や大学院を中退して1年間フリーターとして活動していても、公務員試験を受けることが可能です。
また、公務員試験では基本的に学力を測るペーパーテストと面接が実施されます。ペーパーテストでは専門的な知識は必要なく、中学・高校で学ぶような一般常識問題になります。
面接では一般企業のように社会経験や実績が問われることが少なく、人間性を重視する傾向にあります。
そのため、大学院を中退しても、試験に合格すれば公務員になることができます。
大学中退者でも受験できる国家公務員試験
公務員は3種類存在しており、国家公務員と地方国民は大学を中退している場合でも、問題なく受験できます。
しかし、国際公務員に関しては、大学もしくは大学院を卒業する必要があります。国際公務員を目指す場合は、大学院を中退する前に確認する必要があるでしょう。
また、国家公務員と地方公務員は「すべての国民は平等である」・「職員の採用および昇任は、競争試験によるものとする」と定められています。
そのため、学歴や経歴を元に公務員試験を受けられなくする、落とす行為は禁止されているのです。
それぞれの公務員の詳しい情報については、後述しますので合わせて確認してみてください。
引用:公務員試験総合ガイド
大学院を中退した公務員の給与
公務員の給与は学歴ではなく、役職と勤続年数によって異なります。
同じ役職でも、勤続年数が違えば年収も変動します。下記は、国家公務員の平均給与・年収です。
| 種類 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 国家公務員(一般行政職) | 41万984円 | 667万4,380円 |
| 地方公務員(一般行政職) | 36万5,549円 | 592万1,893円 |
基本的に地方公務員よりも、国家公務員の方が月収・年収はともに高めに設定されています。
初任給は国家公務員・地方国民ともに20万円前後になりますが、勤続歴が長くなれば高めることが可能です。
大学院を中退したとしても、それぞれの年収は変わらないため、高年収を狙うのであれば国家公務員が良いと言えるでしょう。
引用:国家公務員の給与
大学院を中退して公務員を目指すメリット
大学院を中退したとしても、大学院に進学できるだけの学力があると言えるためますので、筆記試験が中心となる公務員試験においては、体感的に難易度が優しいと感じられるようなメリットが挙げられます。
また、大学院中退によって時間に余裕ができるため、公務員試験と並行して民間企業への就職活動も並行できる点もメリットです。
新卒で公務員を目指す場合は、公務員試験対策と就活を並行するといったハードなスケジュールになるため、どちらもおろそかになってしまう可能性があり、大学院中退者ならではのメリットと言えるでしょう。
ここからは、大学院を中退して公務員を目指すメリットについて詳しく解説していきます。
試験の難易度が低い
公務員試験には、年齢以外の制限が存在しないため、試験の難易度が非常に低いです。
例えば、大手企業に就職したい場合、履歴書を送付したとしても学歴で落とされてしまい二次試験に進めないケースが存在します。
公務員試験では、高卒程度の試験の場合は20代前後、大卒程度の試験は25歳〜30歳前後の年齢制限しかないため、条件を満たしていれば誰でも受けることが可能です。
受験する公務員試験によって難易度は異なりますが、市役所や教員採用試験などの公務員試験では、一般的な高校・大学レベルの問題が提出されます。
ペーパー試験の対策問題も販売されているため、試験までにコツコツ勉強すれば、大学院を中退したとしても合格できる可能性が高いです。
また、大学院を中退した場合でも、受験資格に影響を及ぼすことはないため、公務員を目指すメリットと言えるでしょう。
ただし、受験資格の年齢以上の場合は、公務員試験を受験できないことがあるため、あらかじめ注意が必要です。
就職活動に時間を割ける
公務員試験は地方・国家公務員ともに年に一度受験が可能です。
大学院を中退して学校に通うことが無くなった時間を利用することで、就職活動に時間を割けるでしょう。
また、中退する時期によっては希望する公務員試験の日程に余裕があることも多いです。
公務員試験の内容は、基本的にペーパーテストと面接練習の2種類となるため、時間をかければかけるほど、精度が高くなります。
さらに、面接対策は公務員試験だけではなく、一般企業の就職活動にも活用可能です。時間をかけて面接に強くなれれば、万が一公務員試験に落ちたとしても、一般企業への就職活動をスムーズに進められます。
企業の中には大学卒業後3年間は新卒もしくは第二新卒として扱ってくれるため、通常よりも有利に進められる可能性があります。
そのため、大学院を中退した場合、試験までの時間を有効活用することで、他よりも有利に活動できるでしょう。
強みを活かした活動ができる
大学院を中退して公務員を目指す場合、これまでの学生生活で得た強みを活かして活動が可能です。
中退したとしても大学院まで進学できた学力は事実であるため、ある程度試験に対応する力を備えています。
高卒と大学院中退では、経験している試験の回数・学習時間に大きな差が存在します。
高校を卒業してすぐ働いた実務・社会経験があったとしても、公務員試験ではアドバンテージにはなりません。
公務員試験に合格するためには、試験に合格するための学力と経験が必要になります。
その点、大学院まで進学している場合、一定回数の試験経験と継続的な学習スキルが備わっているため、大きな強みと言えるでしょう。
また、ペーパー試験だけではなく、面接時に培った経験を面接時に生かすこともできます。
大学院を中退した場合でも、強みを活かした活動ができるのはメリットです。
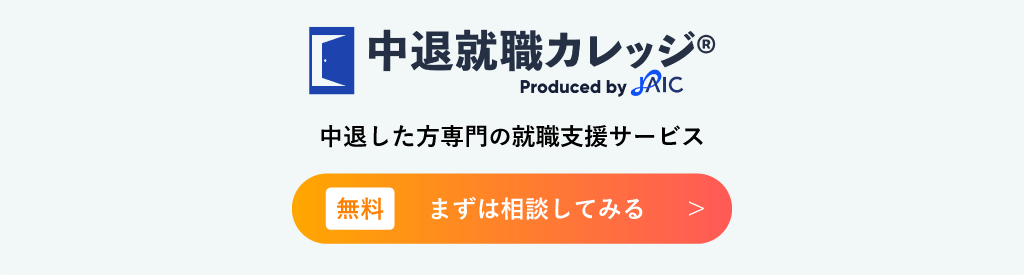
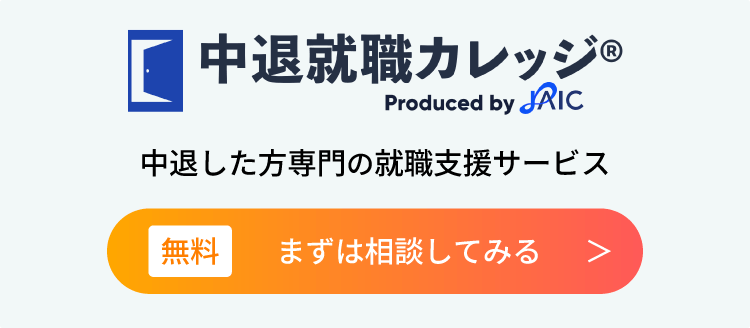
大学院を中退して公務員を目指すデメリット
大学院を中退することによって、学歴上は大卒になってしまいます。
せっかく大学院に進学するためのお金や時間といったコストが全て無駄になってしまう点は、今後の人生においても大きなデメリットと言えるでしょう。
また、公務員は民間企業と異なり副業が禁止されているため、様々な働き方を通じてスキルと収入を高めていきたいと考えている人にとっては、働き方が自分に合わないと感じてしまう可能性も考えられます。
他にも、公務員になった後に民間企業への転職が難しくなる傾向が見られたり、学歴社会の中で公務員として働くことになるといったデメリットが考えられます。
大学院を中退して公務員を目指す上ではメリットだけでなく、デメリットについてもしっかりと理解しておきましょう。
学位は取得できない
一般的に大学院を卒業した場合、修士号や博士号などの学位を取得可能です。
一方、大学院を中退する場合、当然ですが学位の取得はできません。
つまり、履歴書では学歴を「〇〇大学大学院〇〇研究科博士課程単位取得満期退学」と記載することになります。
学位は履歴書などに学歴として記載できるため、一般企業で少しでも多く給与が欲しい場合は注意が必要です。
大学院に進むためには時間と費用がかかるため、中退してしまうのはデメリットと言えるでしょう。
ただし、大学院を卒業するためのストレスで頭を抱えている場合、中退して希望する公務員に就職した方が、精神的に良い場合があります。
副業ができない
一般企業の場合は、本業に勤める傍ら、副業で収入を得ることができます。
一方、国家公務員をはじめとする、全ての公務員は副業を禁止されています。
本業だけではなく副業をしながら、スキルと収入を高めたいと考えている場合は、デメリットと言えるでしょう。
しかし、公務員でも副業自体に収入が発生しなければ、スキルアップを目指すことができます。例えば、公務員として働きながらプログラミングスキルを身につけたい場合、自身で教材を購入して勉強する分には問題はありません。
身につけたスキルをもとにプログラマーとして転職することは禁止されていないため、身につけたいスキルがある場合は、収益を発生させることなく身につけると良いでしょう。
一部企業に就職しづらくなる
大学院を中退した後、必ず公務員を目指す必要はありません。
公務員の仕事が自分に合わないと考えた場合、一般企業に就職する道も存在します。
ただし、大学院を中退した場合、学歴として内容が明記されるため、一般企業への就職が難しくなるケースがあります。
公務員試験には大学院を中退した影響はありませんが、一般企業の中には学歴を重視するケースも少なくありません。
どれだけ企業に入る熱量があったとしても、中退を理由に入社を断られる可能性があります。
また、基本的に大学院を中退した場合、新卒ではなく既卒として扱われます。
つまり、就職活動は新卒ではなく、中途採用枠に当てはまるため、実務経験がなければ採用される可能性が低いです。
大学院を中退した後、公務員だけではなく一般企業への就職を考えている場合はデメリットと言えるでしょう。
公務員は学歴社会
公務員試験にこれまでの学歴は関係ありませんが、実際の現場は基本的に学歴社会です。
高卒の公務員と大学院卒の公務員では、その後のキャリアに違いが出てくるケースも少なくありません。
例えば、先に大学院を中退し公務員になったとしても、後に公務員となった大学院卒の人材の方がすぐに出世する可能性があります。
また、国家公務員と地方国民は大学院を中退したとしても試験の受講が可能ですが、国際公務員は大学卒業以上の学歴が必要です。
公務員試験では学歴の有無は関係ありませんが、出世を考えている場合はデメリットと言えるでしょう。
大学院を中退して公務員を目指す際のポイント
大学院を中退して公務員を目指す場合は、スケジュールをしっかり立てて自分自身でタスク管理を行いながら試験対策を進めていくことがポイントです。
特に中退によって自由に使える時間が多くなるため、スケジュールを区切っておかないとダラダラと公務員を目指すことになりかねません。
また、公務員を目指す上では、どの種類の公務員を目指すかによっても試験対策の内容が変わるためってきますので、あらかじめ公務員の種類を認識しておくことも重要です。
合わせて、公務員試験では面接も行われますので、大学院を中退した理由を言語化しておくなど面接対策にも取り組みましょう。
ここからは、大学院を中退して公務員を目指す際のポイントを4つにまとめて解説します。
スケジュールをしっかり立てる
大学院を中退して公務員を目指す場合、事前にスケジュールをしっかり立てておきましょう。
公務員試験はいつでも受けられるわけではありません。
公務員の種類ごとに日程が定められており、申し込み可能日も存在します。特に地方公務員は地位によって試験日程が異なるため、中退する前に確認が必要です。
例えば、公務員試験の準備を6ヶ月間で完了させたい場合は、期間内にどの公務員試験を受けたいのか、試験までに何ができるようなっておくべきなのか、などを把握しておきましょう。
公務員試験までにしっかりとスケジュールを立てておくことで、大学院を中退してもダラダラと就職活動をすることなく、必要なことに集中して取り組めます。
どの公務員を目指すか決める
大学院を中退して公務員を目指す場合、どの公務員になりたいのか決めておきましょう。
公務員は、大きく分けて以下3つの種類が存在します。
- 国際公務員
- 国家公務員
- 地方国務院
それぞれ試験難易度や業務内容が異なるため、詳しく解説していきます。
国際公務員
国際公務員とは、国連や世界保健機関など国際機関に勤務する公務員です。各国の政府にとらわれることなく、中立な立場で世界的な利益のために活動します。
国際公務員の応募資格は非常に厳しく、原則として大学以上の学歴と修士号以上の学位が必要となります。学歴だけではなく、英語やフランス語が堪能でなければなりません。
つまり、大学や大学院を卒業が前提となり、学位を取得しておく必要があるのです。
国際公務員の主な勤務先は、以下の通りです。
- 国連事務局
- 国連開発企画(UNDP)
- 国連児童基金(UNICEF)
- 世界保健機関(WHO)
- 国際通貨基金(IMF)
また、職種は「一般職」と「専門職」の2つに分かれています。
世界各国の事務所で専門職のサポートを行う一般職か、専門知識と技術を活かして業務を進める専門職のいずれかを選ぶことになります。
専門職の方が就職難易度が高く、様々な知識とスキルが必要とされます。
国家公務員
国家公務員とは、省庁や関連する国の機関に勤務する公務員です。
国内の事業を中心に運営・サポートがメインの業務となります。
毎年行われる各業種の国家公務員試験を受験し、合格することで就職が可能です。
高卒程度の学歴が必要で、業種によって年齢制限が設けられています。
また、国家公務員の主な勤務先は、以下の通りです。
- 自衛隊
- 検察官
- 刑務官
- 裁判官
- 海上保安官
- 参議院・衆議院事務局員
- 労働基準監督官
さらに、国家公務員には以下4つの職種が存在します。
- 総合職
- 一般職
- 専門職
- 特別職
基本的には、数年間一般職や総合職として勤務し、専門的な知識・スキルなどキャリアを積んだ後に専門職や特別職に就くことになります。
特別職に関しては、選挙や議会で決議・任命など、特別な手続きで選ばれる必要があります。
そのため、特別職だけは国家公務員試験に合格しただけでは就くことができないため、あらかじめ注意しましょう。
地方公務員
地方公務員とは、地方自治体に勤務する公務員のことを指します。地域に密着したサービスや事業を行います。
地方公務員の主な勤務先は、以下の通りです。
- 市役所、区役所の職員
- 消防官
- 警察官
- 看護師
- 栄養士
- 学校教員
- 保育士
また、地方公務員には以下5つの種類が存在します。
- 一般行政職
- 技術職
- 公安職
- 資格・免許職
- 特別職
市役所職員や学校教員など、地域に根付いた勤務先が多いため、公務員の中でもイメージしやすい種類と言えるでしょう。
一般行政職や技術職に関しては、大学院を中退して試験に合格さえすればすぐに慣れます。
ただし、公安職や資格・免許職に関しては、特定学校の卒業や資格を取得しなければ、就職することはできません。
例えば、学校教員の場合は年齢・種類別の教員免許を取得する必要があります。
そのため、大学院を中退して地方国民を目指す場合は、一般行政職技術職の試験日程を確認すると良いでしょう。
大学院中退の理由をまとめる
大学院を中退して公務員を目指す場合「なぜ中退したのか」をあらかじめまとめておきましょう。
公務員試験の面接時に中退した理由を求められる可能性が高いです。
下記にて、大学中退の理由をまとめるべきなのかを解説します。
面接時に必ず聞かれる
前述の通り、大学院を中退した後に公務員試験を受験する場合、下記のように必ず中退した理由を問われます。
- なぜ大学院を中退しようと思ったのですか?
- 大学院を中退して公務員を目指した理由は何ですか?
上記のような質問は必ずされるため、面接前に自分の中で中退した理由をまとめておきましょう。
また、大学院中退の理由を整理しておくことで、理由を聞かれた際にネガティブな印象を持たれる可能性が低くなります。
大学院を中退したことを引きずって面接を受ける場合、自分の中で整理がついておらず、面接官にネガティブな印象を与えてしまうでしょう。
そのため、大学院中退の理由を言語化し、問われてもスムーズに答えられるようにしておくことで、ポジティブな印象を与えられます。
試験勉強をしておく
大学院を中退して公務員試験を受験する場合、必ず試験勉強をしておきましょう。
大学院まで進学している場合、試験に慣れているケースが多いため、試験勉強を怠る可能性があります。
公務員試験は一般教養と中学〜大学レベルの問題が出題されるため、難易度は低いと言えるでしょう。しかし、公務員試験の内容は受験する種類によって異なるため、全く勉強していない状態だと落ちる可能性が高いです。
公務員試験に特化した教材や予備校が存在するため、自身のやり方に適した勉強方法を実施しましょう。
民間企業に就職する方法もある
大学院を中退して公務員を目指す場合、民間企業に就職する方法もあることを把握しておきましょう。
国際公務員以外の公務員は学歴に左右されることなく、試験に合格すれば就職が可能です。
しかし、就職してからの数年間は給与が少なく、副業を始めることもできません。
必ずしも公務員として働くことが最適ではない可能性があります。
そのため、公務員が自分に合わないと感じた場合は、民間企業に就職しても問題ないでしょう。民間企業は大学院を中退していることをネガティブなイメージで捉えがちですが、自分の中で理由を整理できていれば、面接時にポジティブイメージで捉えてもらえます。
民間企業の中には、学歴を重視しないところもあります。
大学院を中退したからといって、公務員だけを目指すのではなく、同時に民間企業への就職も考えてみましょう。
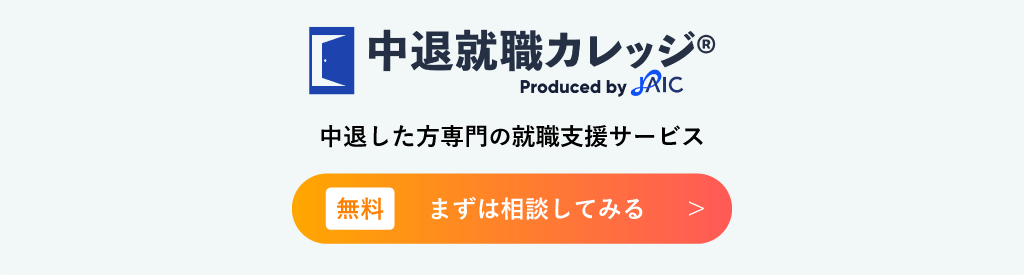
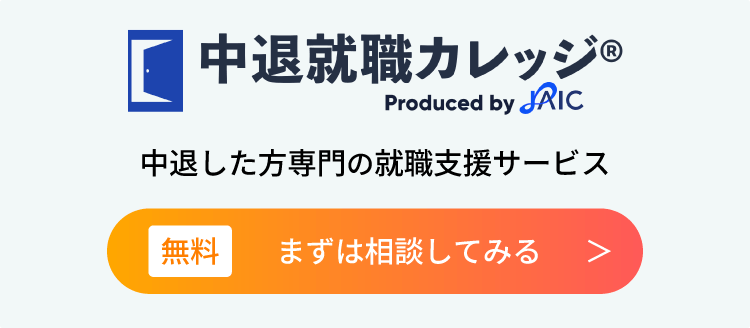
大学院中退で公務員へ就職する流れ
大学院を中退した後に公務員を目指す場合は、まずは公務員試験に申し込みます。
例年2月から5月にかけて各自治体や省庁のホームページで募集要項が公開されるため、ますので、申し込み期限に間に合うようにインターネット経由で出願しましょう。す。
公務員試験に申し込むことができたら入念に試験対策を進めていき、一次試験として筆記試験と小論文試験を受験します。
無事に一次試験に突破できた場合は二次試験として面接が行われ、面接でも合格となると無事に公務員として就職することができます。
大学院を中退して公務員を目指す際は、大まかな流れを理解しておくことが重要です。それぞれのポイントについて詳しく解説します。
公務員試験に申し込む
公務員試験を受験するためには、自分が希望する内容に申し込みを行いましょう。
その年の2〜5月ごろに自治体のHPで公表されます。
公務員試験の申し込みは、3〜4月から開始するケースが多く「現地申し込み」と「インターネット申し込み」の2種類が用意されています。
現地申し込みの場合、事務所で書類手続きをする必要があるため、近年は混雑回避のためインターネット申し込みが主流です。
1次試験:筆記試験と小論文
公務員試験の申し込みが完了した後、試験対策を行い1次試験に望みます。
多くの公務員試験は、1次試験で筆記と小論文が出題される傾向にあります。
小論文は受験する公務員の種類によって異なりますが、筆記試験は必ず出題されるため、必ず事前に学習を進めておきましょう。
2次試験:面接
1次試験を無事通過した後は、2次試験の面接を行います。
面接方式は「個別面接」と「集団面接」の2種類が存在しており、受験する公務員の種類によって異なります。
地方公務員の場合は前述した面接のみですが、国家総合職や国家一般職は、各府省に『官庁訪問』を実施します。
官庁訪問で面接及び自己PRを実施し、そこで合格しなければ就職することはできません。
2次試験までが終了した後は、公務員試験の合格者に内定が発表されます。一般的に内定の発表は8〜10月に行われます。
大学院を中退したら公務員就職に不利?
大学院を中退した場合、受験資格や筆記試験において不利になる事はありませんが、面接で中退理由を聞かれる可能性が高くなるため、面接対策が充分でないと公務員就職に不利になってしまうことがあります。
ただし、無事に公務員試験を突破することができれば、就職後には大学院中退の経歴は関係なくなります。仕事での経験や活躍が評価に直結するため不利になることは無いでしょう。
ここからは、大学院を中退したら公務員就職に不利になるのかどうかについて詳しく解説します。
学歴的には不利にならない
公務員試験の受験資格には主に年齢制限が設けられており、学歴は関係ありません。
したがって、大学院を中退した場合でも学歴的に不利になる事は無いと言えます。
公務員試験は高卒程度と大卒程度の2つの受験種別が用意されていますが、それらは学歴に応じて受験科目を分けられているのではなく、あくまでも出題される筆記試験の難易度を示しているものになります。
大学院中退者でも高卒程度の試験を受けることも可能であり、筆記試験に限って言えば、幅広い知識を有しているという点で大学院中退者の方が高卒や大卒よりも有利とも言えます。
面接で中退理由を聞かれる可能性はある
公務員試験では筆記試験だけでなく、面接を通じて人物面が望ましい人材であるかを判断されます。
面接においては大学院を中退した理由を聞かれる可能性が高いです。
中退理由でネガティブな印象を与えてしまうと公務員にふさわしい人物像ではないと判断されることがあり、準備次第では中退の経歴が不利になることも考えられます。
大学院を中退している人が公務員試験の面接を受ける際は、相手にネガティブな印象を与えないようポジティブに中退理由を伝えることがポイントです。
例えば「研究を進めていく中で実務に関心を持ち、公務員として地域に貢献したいと考えるようになった」など、進路変更の理由を客観的にも納得できる形で説明することが大切です。
就職後は大学院中退の経歴が関係なくなる
公務員として採用された後は、大学院を中退した経歴が業務の評価や昇進に影響する事は基本的にありません。
実務での活躍や年齢となってきますので、就職後に中退の事実が不利になるような事は無いと言えます。
また、多くの公務員は数年おきに異動を通じて幅広いキャリアを身に付けていくというキャリアパスになっています。そのため、柔軟な姿勢で学び続ける意欲があれば、中退をしていない大卒や大学院卒よりも高い評価を受けられるでしょう。
大学院中退者が知っておくべき公務員の注意点
大学院を中退して公務員を目指す際は、いくつか注意しておくべきポイントがあります。
例えば公務員には安定して収入を上げていけるといったイメージがありますが、必ずしも安定して働けるわけではなく、民間企業よりも収入が低いことがあるなどの注意点があります。
また、働き方として異動が多く専門的なスキルが身につきづらいことから、将来的に民間企業への転職を目指す際に苦戦してしまうことも考えられます。
ここからは、大学院中退者が知っておくべき公務員という仕事の注意点について、3つのポイントを解説します。
民間企業より稼げない可能性がある
公務員は年功序列で収入が上がっていくことが基本です。例えば2025年の時点で公務員の平均年収は684万円であり、国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査結果による民間企業の平均年収は460万円であることから、平均年収という観点では公務員に分があると言えます。
ただし、民間企業の場合は実績に応じて若くしても役職と年収を上げていける一方で、公務員は年齢が上がるにつれて緩やかに年週が上がっていくことから、特に20代や30代のうちは民間企業よりも稼げない可能性があると言われています。
実力を身に付けて若いうちから高い年収を目指していきたい人の場合は、公務員の給与形態が合わないと感じることもあるでしょう。
公務員だから必ず安定しているわけではない
公務員と聞くと安定した職業というイメージが強いでしょう。
確かに公務員は国や地方自治体に雇用される形で働くため、民間企業のようなリストラは基本的にはありません。
ただし、自治体の財政状況や配属先によっては業務内容が大きく変わったり、頻繁に配置転換が行われることがあります。
良くも悪くも国や自治体によって目の前の仕事内容が大きく左右されてしまうことから、精神的な意味で不安定さを感じてしまうことが考えられます。
雇用が安定しているから精神的にも安定して働けるというわけではない点に注意が必要です。
異動が多く専門的なスキルが身につきづらい
公務員では数年ごとに部署異動があるケースが多く、特定の領域や分野における専門性を高めるのが難しいといった注意点も挙げられます。
部署異動によって、まるで転職したかのように仕事内容が変わってしまうため、幅広いスキルは身に付くものの専門的なスキルは身に付きづらいのが実情です。
民間企業のように、特定の領域で自分の強みを活かしてキャリアを積み上げたい人にとっては、公務員の働き方がミスマッチになるかもしれません。
加えて、専門性が身に付きづらいことで、民間企業への転職を目指す際にアピールポイントになるスキルがないという問題にもつながります。
公務員を目指す場合は、将来的にどういったキャリアを歩んでいきたいのかを明らかにしておくことが大切だと言えるでしょう。
大学院中退で公務員への就職がおすすめな人・おすすめではない人
大学院を中退して公務員に就職することがおすすめできる人としては、公務員としての社会貢献性や、公務員そのものに対する憧れや魅力を感じている人が挙げられます。
また、公務員は土日祝日が休みであることや安定した給料が稼げることから、ルーティーンのように働きたい人にもおすすめできるでしょう。
一方、働きながら副業をしたり、実務経験を通じてスペシャリストを目指していきたい人には公務員への就職がおすすめできません。
加えて、将来具体的にやりたい仕事があるような人だと、公務員の業務内容に物足りなさを感じてしまうことがあります。
大学院を中退して公務員を目指す上では、自分がそもそも公務員に適したマインドを持っているのか、あらかじめ認識しておくことが大切です。
おすすめな人
大学院を中退して公務員への就職がおすすめな人は、以下の通りです。
- 安定した給与、環境で働きたい人
- 公務員の中にやりたい仕事がある人
- 公務員としての社会的信頼が欲しい人
- 社会貢献をメインとした仕事に就きたい人
上記のいずれかに当てはまる場合は、大学院を中退して公務員への就職がおすすめです。公務員は時代に左右されることなく、基本的に土日・祝日は休みで、平日のみ勤務となるため、安定した給与・労働環境が特徴です。
また、公務員の仕事は社会貢献や地域に密着した住民のサポートとなるため、仕事を通して社会貢献がしたい場合には、おすすめの就職先と言えるでしょう。
おすすめではない人
大学院を中退して公務員への就職がおすすめではない人は、以下の通りです。
- 将来やりたい仕事がある人
- 働きながら副業したい人
- 実務経験やスキルを身につけたい人
- 積極的な昇給を希望する人
上記のいずれかに当てはまる場合は、大学院を中退して民間企業への就職がおすすめです。
公務員は安定した給与や環境、社会的な信頼を得られる仕事です。しかし、副業は禁止されており、実務経験やスキルを身に着けることはできません。
また、昇給は決められた年度だけで、インセンティブが発生することもないため、給与を積極的に高めていきたい場合は、おすすめできない仕事と言えるでしょう。
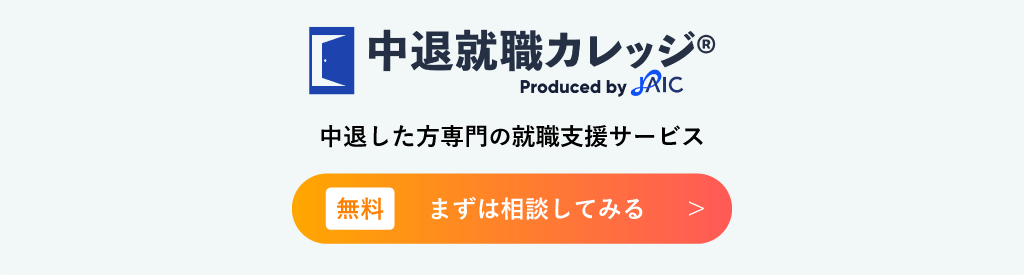
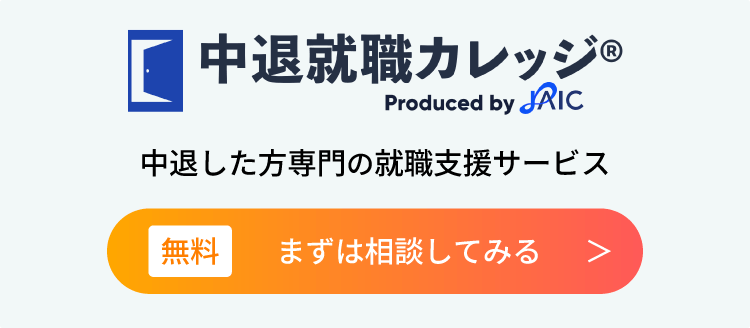
大学院を中退して公務員ではなく民間企業を目指す理由
大学院中退後の進路としては、公務員だけでなく民間企業への就職もメジャーです。
民間企業に就職することで、それぞれの業界や職種に特化したスキルを身に付けることができるため、転職市場における市場価値を高めることが期待できます。
また、専門的なスキルや副業経験を通じ、将来的に転職や独立を目指せる点も、公務員ではなく民間企業を目指す理由として挙げられます。
ここからは、大学院中退後の進路として公務員だけでなく、民間企業も選択肢として考えたい人が検討しておくべきポイントについて詳しく解説します。
業種に特化したスキルが身につく
大学院を中退して民間企業に就職することで、業種に特化したスキルを身につけられます。
公務員は事務処理に関するスキルを身につけられますが、専門的なスキルを使用するシーンがありません。
一方、民間企業では営業やマーケティング・プログラミングなど、専門性の高いスキルを身に付けられます。
専門的なスキルを伸ばすことで、実績を積み高収入・高待遇で働くことが可能です。
転職・独立も目指せる
民間企業に就職した場合、身につけたスキルや実績をもとに転職・独立を目指せます。
公務員の場合は、実務経験を積めないため、転職や独立を目指しづらいと言えるでしょう。
しかし、民間企業では日々の業務でスキルやキャリアを積めるため、積極的に転職や独立を目指せます。
在籍企業で専門スキルや良い実績を積むことで、有利に転職を進めることも可能です。
そのため、優良企業への転職や独立を考えている場合は、民間企業に就職がおすすめです。
副業ができる
近年、多くの民間企業が副業を解禁しています。しかし、公務員は完全に副業が禁止されています。
民間企業全体で副業を推進する流れが出てきており、積極的に取り組むことで、給与以外の収入を得られます。
また、副業で獲得したスキルを活用して、転職活動や独立を目指すことも可能です。
本業の給与を得ながら、副業で収入とスキルを獲得できるのは、民間企業に就職するメリットと言えるでしょう。
大学院中退者に公務員以外でおすすめできる職種
大学院を中退した後には、公務員だけでなく営業職やプログラマーなど、汎用的かつ専門的なスキルが身に付く仕事がおすすめです。また、公務員のように安定的な働き方を民間企業で実現したい場合は、事務職などもおすすめです。
大学院中退者であれば大卒扱いとなりますので、民間企業への就活において学歴上不利になる事は基本的にありません。
ここからは、大学院中退者におすすめできる民間企業での職種について詳しく解説します。
営業職
営業職として就職すると、どんな仕事でも求められるコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力、交渉術などを身に付けられるため、市場価値を高める意味でも大学院中退者におすすめですきます。
また、営業職は業態や企業規模など幅広い求人が募集されているだけでなく、大学院中退者でも就職を成功させている事例が多いため、選べる求人の幅が広いという点もポイントです。
中退のタイミングによらず就職活動を進めていけるため、ブランク期間を長引かせないで済む点もメリットの一つです。
事務職
事務職は基本的にマニュアルに従ってルーティンワークのように業務をこなしていく働き方になるため、公務員と似たような働き方を民間企業で実現できる点がおすすめです。
特に事務職については、大学院まで進学したという経歴がポジティブに捉えられることが多く、大学院中退が無理になりづらい点もポイントとして挙げられます。
ただし、事務職は人気な仕事の1つであるため、面接対策や自己分析をしっかりとしておかないと就活に苦戦してしまう可能性がある点には注意が必要です。
プログラマー
プログラマーは今後も需要が高く、スキル次第で将来的に独立も目指せるため、専門性を高めていきたいと考える人に向いています。
昨今ではプログラマーの人材不足も相まって、未経験者を積極的に募集している企業も多く見られますので、大学院中退からでもプログラマーのキャリアを歩むことが可能です。
プログラマーとして働くためには、知識のインプットが非常に重要になります。大学院まで進学できているだけの地頭の良さを仕事でも発揮することができるため、素質としても噛み合っている点がポイントです。
就職カレッジを利用して公務員にチャレンジ
大学院中退から公務員を目指す上では、公務員試験対策スクールを利用するのが一般的ですが、安くない費用がかかるのでお金に不安が残る人だと躊躇するでしょう。
公務員試験における筆記試験は過去問や問題集が販売されているため、独学で対策をすることは可能です。しかし、中退者の場合は特に面接対策が必要になっていますので、民間の就職エージェントの模擬面接を活用するのがおすすめです。
ここからは、大学や大学院中退者の面接対策やキャリアの相談実績が豊富な就職カレッジのご紹介をしますので、公務員試験の面接対策に不安を感じている人は相談も検討してみてください。
一般的な就活方法よりも就職しやすい
一般的なフリーターや既卒の就職成功率は30%前後ですが、就職カレッジでは、内定に直結する就活スキルを得られるため、通常よりも効率的に就職活動が可能です。
また、自分のやりたい仕事がわかった上で就職活動を始められるため、自分の強みを把握して充実した就職活動を行えます。
大学院を中退した場合でも、公務員を目指すべきなのか、民間企業を目指すべきなのか、自分に合った判断ができるでしょう。
最短2週間で内定を得られる
就職カレッジでは、専任アドバイザーがビジネスマナーから履歴書・面接対策まで実施しています。
また、就職カレッジでは、就職未経験者を採用した優良企業を数十社集めた集団面接会を開催しています。
集団面接会では、書類選考なしで企業担当者と直接会話でき、そのまま面接まで→ことが可能です。そのため、面接対応がうまくいけば最短2週間で内定を得られます。
大学院を中退して公務員試験に落ちた場合でも、面接対策を実施していれば、すぐに一般企業へ就職できるでしょう。
就職後の1年間サポートあり
就職カレッジは、就職が完了してから1年間サポートしてくれるため、安心して社会人生活を過ごすことが可能です。
専任アドバイザーにいつでも悩み相談ができ、新入社員向け講座を受講できます。職場に関する悩みをいつでも解決できるため、安心して就職活動を実施できるでしょう。
また、公務員のように民間企業と異なる職場でも、豊富な経験を持った専任アドバイザーがサポートするため、どのような職場でも問題ありません。
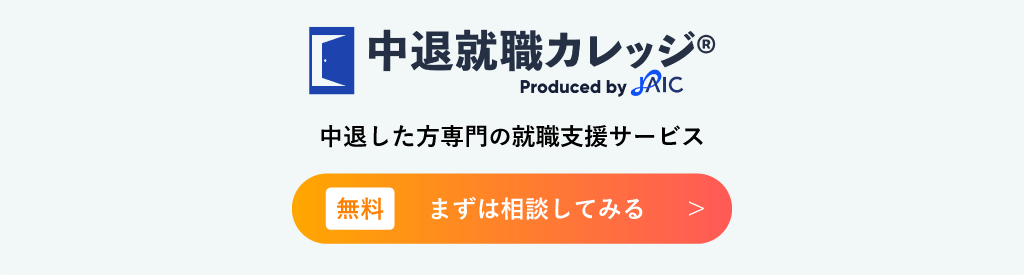
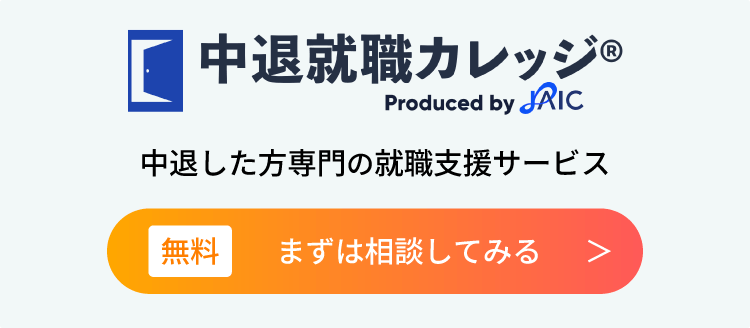
よくある質問
公務員試験合格後に大学院を中退したら内定取り消しになる?
公務員試験合格後に大学院を中退したとしても、基本的に内定が取り消される事はありません。ただし、試験区分や面接での受け答えの内容によっては、大学院を修了することを見込んで合格が出されていることもありますので、その場合は内定取り消しになるリスクがあります。
特に大学院修了見込みで受験をしている場合には注意が必要なため、もし不安な場合は中退する前に公務員試験事務局の担当者に相談してください。
大学院中退でも公務員に合格できますか?
大学院を中退していたとしても、公務員に合格することは可能です。公務員試験の受験資格には学歴が関係なく、筆記試験と面接による人物評価によって選考されるため、大学院を中退していることが大きなハンデになるわけではありません。
ただし、面接においては中退理由を問われることが大半のため、前向きに説明できるように準備しておくなど、中退者向けの公務員試験対策のポイントを意識しておくことが大切です。
まとめ
以上、大学院を中退して公務員になれるのか、公務員を目指すメリットやデメリット・ポイントについて解説しました。
大学院を中退したとしても、国家公務員と地方公務員を目指すことができます。学歴に関係なく、年に1度行われる公務員試験に合格すれば、公務員に就職できます。
しかし、大学院を中退して本当に公務員を目指すべきか不安な方も多いでしょう。このような場合は、就職カレッジがおすすめです。
就職カレッジは専任のアドバイザーが自身の強み・本当にやりたいことを明確化してくれます。
この記事で、公務員を目指すメリット・デメリットを把握し、就職カレッジを利用して仕事にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
大学院を中退すると就職できなくなるのか知りたい方は、ぜひ以下の記事を参考にしてください。

こんな方におすすめ!
- 学歴に自信がないから就職できるか不安
- 就職について、誰に相談したら良いか分からない
- 中退しようかどうかを迷っている
- 学歴に自信がないから就職できるか不安
- 就職について、誰に相談したら良いか分からない
- 中退しようかどうかを迷っている
当社の就職に関するコンテンツの中から、大学院の中退を検討している方、中退後の就職に悩んでいる方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。