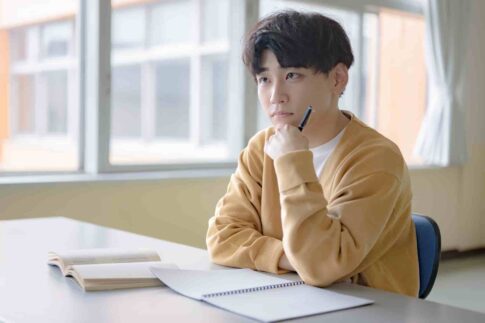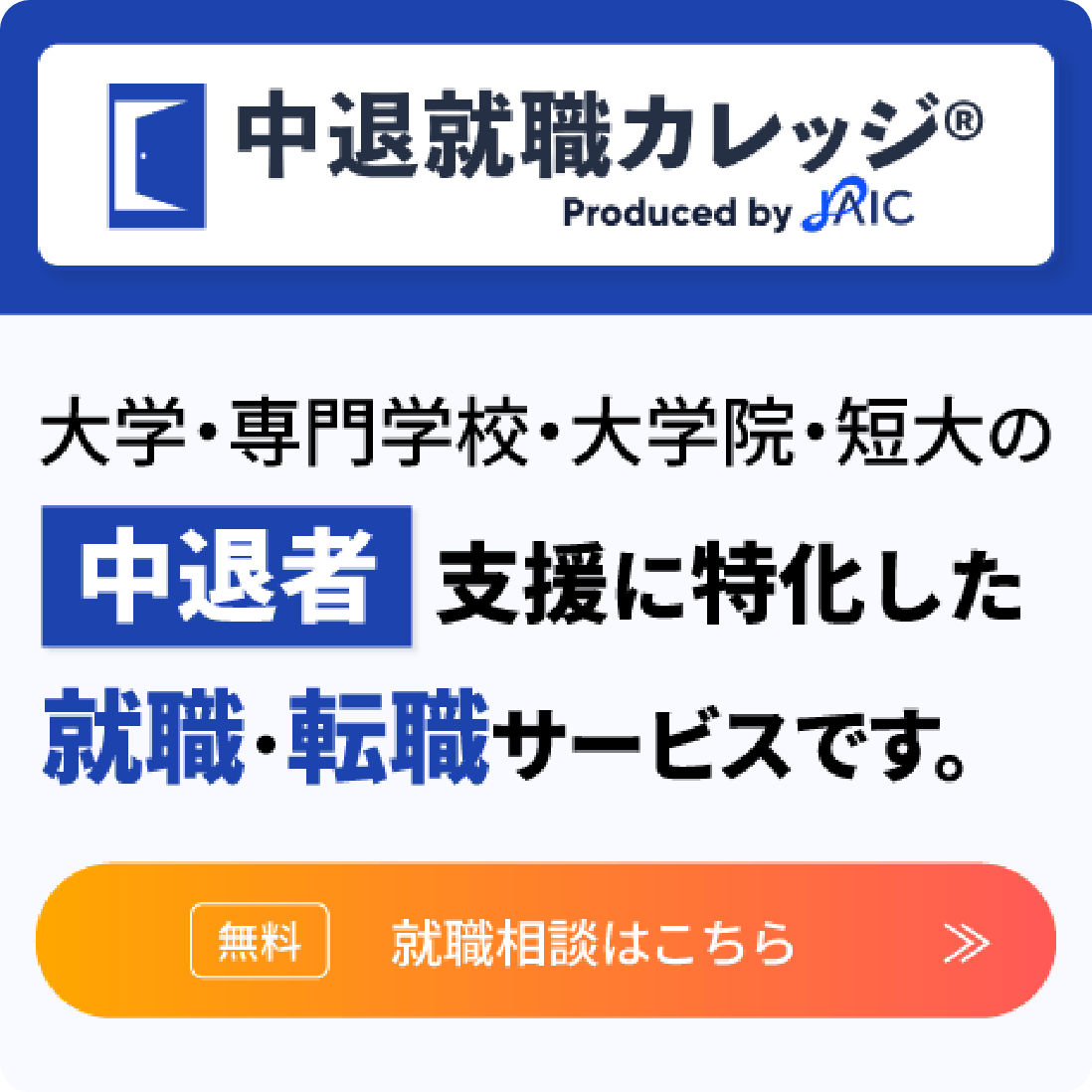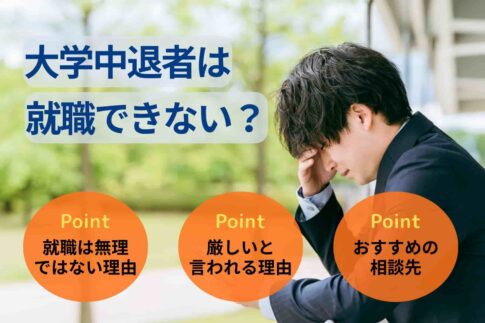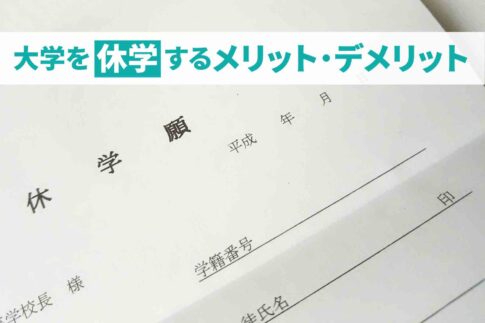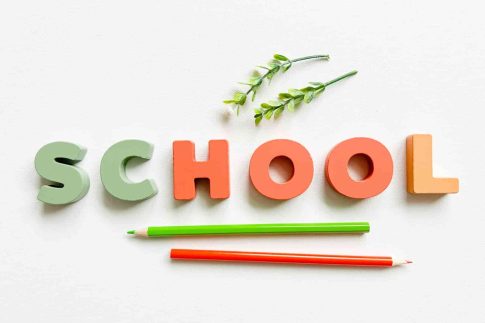専門学校を辞めてよかったと思う場面は?辞めた後のメリットも紹介
専門学校を辞めてよかったと思う場面は、やりたかった仕事に取り組めている時です。なぜなら、辞めたことで学校生活のストレスから解放され、やりたかった仕事に挑戦できるからです。
とはいえ、専門学校を辞めたいと思っても、将来への不安が大きければ、なかなか決断できない場合もあるでしょう。専門学校を辞めた後のメリットとデメリットを知れば、辞めた後の生活がイメージしやすくなるため、自信を持って次の行動を選択できるはずです。
この記事では、専門学校を辞めてよかったと感じる瞬間や辞めて後悔しないためのポイントを紹介します。
専門学校を中退しようか悩んでいる方や、辞めた後の選択肢を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
専門学校を辞めてよかったと思う場面は?
専門学校を辞めてよかったと思う場面は、やりたかった仕事に取り組めている時です。授業や実習に時間をかけるよりも、早く社会に出てやりたかった仕事の経験を積めると実感する人が多いからです。
また、学校に通うストレスから解放されたり、学費や生活費の負担が軽くなったりすることで精神的に余裕が生まれることもあります。
これらの理由を見て分かるように、中退は必ずしもマイナスではなく、自分に合った環境を選び直す大切な選択肢でもあります。
ここで紹介する専門学校を辞めてよかった思う場面を理解したうえで、あなた自身が納得できる進路を考えてみてください。
1.やりたかった仕事に取り組めている時
専門学校を辞めてよかったと思う場面は、中退後にやりたかった仕事に取り組めている時です。
実際に、専門学校を辞めてよかったと思う人たちの体験談を以下にまとめました。
専門学校をやめても私は全然後悔していません。今は自分の好きな仕事がやれているんで幸せです。
(引用:Yahoo!知恵袋)
「辞めた人はイラストレーターになれなかった」って言われたから「あーなってやるよ」と負けず嫌いが働いて、今はありがたくイラストレーターとして生活してます💪
(引用:X)
どの体験談にも共通しているのは、辞める前からどうしてもやりたい仕事があったという点です。親に反対されても、周りの人に止められても自分の気持ちにしたがって行動しています。
それだけ強い気持ちでやりたい仕事に取り組めていると、辞めてよかったと思いやすいでしょう。
2.学校に通うストレスがなくなった時
専門学校を辞めてよかったと思う場面は、学校に通うストレスがなくなった時です。
実際に、学校に通うストレスがなくなったと思う人たちの体験談を以下にまとめました。
もー4月まで学校行かなくていいって最高すぎる。
(引用:X)
関西の専門学校(専門実践教育訓練校)を辞めてよかった。もうなじめない。若い子達とはうまあってない。自分が一番上なのに無能だった。
(引用:X)
レポート再提出多かったみたいだから、本当辞めてよかった。
(引用:X)
共通しているのは、日々の学校生活が大きなストレスになっていたことです。こうした状況から離れられたことで、気持ちが軽くなり、新たな挑戦をしようと考える人もいます。
また、体験談から単純に学業を放棄したのではなく、自分を追い詰める環境や人間環境から距離をとったことがわかります。学校に通うストレスを本気でなくしたい場合は、どこかで区切りをつけて休学や中退を選択する必要があるでしょう。
専門学校を辞めた後のメリット3選
専門学校を辞めた後のメリットは他の進路を選択できることです。学校を辞めれば、実習や課題にかけていた時間を、自分がほんとうにやりたいことに使えるようになります。
また、中退することで学費や生活費などの経済的な負担を減らせるでしょう。
さらに、学校生活から離れることで精神的に余裕が生まれる場合もあります。こうしたメリットは専門学校を続けることだけに縛られず、自分の将来を見直すきっかけになります。
大切なのは、辞めることで生まれた余裕を次にどう活かすかです。ここで紹介するメリットを理解したうえで、これからどう動くのかを考えてみてください。
1.学費や生活費の負担を減らせる
専門学校を辞めると、学費や生活費の負担を減らせるのがメリットです。
独立行政法人日本学生支援機構の調査によると、年間の学生生活費の内訳は以下の表のとおりです。
| 費用 | 区分 | 金額 |
| 学費 | 授業料 | 764,300円 |
| その他の学校納付金 | 185,900円 | |
| 修学費 | 96,000円 | |
| 課外活動費 | 4,100円 | |
| 小計 | 1,050,300円 | |
| 生活費 | 食費 | 124,600円 |
| 住居・光熱費 | 120,300円 | |
| 保健衛生費 | 42,600円 | |
| 娯楽・し好費 | 106,800円 | |
| その他の日常費 | 159,300円 | |
| 小計 | 553,600円 | |
| 計 | 1,603,900円 |
参考:独立行政法人日本学生支援機構「令和2年度 専修学校生生活調査結果」
上記の表をみると、学費は生活費の約2倍の金額がかかっていることがわかります。仕送りが少なく、アルバイトと勉強の両立が難しい学生であれば、専門学校に通うのが大変だと思うようになるのも無理はありません。
2.精神的に余裕が生まれる
専門学校を辞めると精神的に余裕が生まれるのがメリットです。専門学校は実技・実習が多いからこそ、課題や練習量に追われやすくなります。
また、授業は少人数制が多いため、人間関係がうまくいかないとつらくなりやすいです。
実際に文部科学省の調査によると、専門学校を中退した理由として「心神耗弱・衰退」をあげた人の割合が2番目に多いことがわかっています。
| 中退理由 | 割合 |
| 学生生活不適応・修学意欲低下 | 25.0% |
| 心神耗弱・疾患 | 12.6% |
| 就業・起業等 | 12.5% |
| 学力不振 | 11.7% |
| 転学等 | 8.6% |
参考:文部科学省「令和6年度 専門学校生の中途退学者・休学者数等の調査結果」
心神耗弱とは、精神が弱っていて、正しい判断や行動が難しい状態のことを指します。
専門学校が原因で心神耗弱の状態が続いている場合は、辞めた方が気持ちが楽になるはずです。しかし、専門学校を中退した事実は今後の将来に影響しやすいからこそ、まずは休学やクリニックの受診で様子を見るのをおすすめします。
3.他の進路を選択できる
他の進路を選択できることは、専門学校を辞めた後のメリットの一つです。専門学校に残らず、他の進路を選択することで、自分に合った進路に時間とお金をかけられるからです。
他の進路を選びたいと感じる理由は、実習や課題を進めるうちに長く続けたい仕事だと思えなくなったり、自分のやりたいこととミスマッチがあったりしたからだと考えられます。
次の進路が明確に決まっていて、専門学校ではその道に進めないとはっきりしているのであれば、他の進路を選択するのも一つの手段です。
他の進路:就職する
他の進路として就職する道があります。「学費の負担が重くてこれ以上の在学が難しい」と感じる場合は就職しようと思いやすいです。
以下の表に専門学校を辞めて就職するメリットとデメリットを表にまとめました。
| メリット | デメリット |
| ・卒業を待たず働ける・お金を稼げるので経済的に豊かになる・早めにキャリアを積める | ・専門学校で身につけたスキルを活かせない・最終学歴が高卒になる・専門学校の就職サポートが受けられない |
就職する場合は、早めに働けるので経済的な負担が軽くなりますが、最終学歴が高卒になります。メリット・デメリットを天秤にかけて考える必要があるでしょう。
他の進路:大学・短大・別の専門学校に進学する
専門学校を辞めて他の学校に進学するのも一つの選択肢です。やりたいと思ったことが、他の専門学校や大学でしか学べない場合、この進路を選びやすいでしょう。
別の専門学校へ入学する場合のメリットとデメリットを整理すると、以下のようになります。
| メリット | デメリット |
| ・自分に合った専門分野を学べる・必要な資格を取得できる・新しい環境で再スタートできる | ・同年代の人よりも卒業や就職が遅れやすい・学費や生活費の負担が多くかかる・新しく人間関係を築いていく必要がある |
このように、やりたいことができる一方で、経済的な負担が増えるリスクが伴います。自分がやりたいことと、現実的な面を考慮して冷静に判断する必要があるでしょう。
他の進路:フリーターになる
専門学校を辞めてフリーターになる進路もあります。学歴やスキル不足に不安を覚えて正社員になる自信がなかったり、何の仕事をしたいかが明確ではなかったりすると、フリーターになろうと思いやすいです。
実際、中退前は別のことをやろうと思っていても、結局フリーターになる人は多くいます。
労働政策研究・研修機構の調査によると、中退前の希望と中退後に実際にしていたことの割合は以下の表のとおりです。
| 活動項目 | 中退した直後にしたいと思ったこと | 中退した直後に実際にしていたこと |
| アルバイトをしたい/アルバイトを探した | 21.4% | 31.8% |
| 在学中から行っていたアルバイトを継続/アルバイトを継続した | 11.1% | 27.3% |
参考:労働政策研究・研修機構「第3章 ハローワークに来所した中途退学者の実態②:中退後の就職活動」
アルバイトは正社員よりも気楽に働けるからこそ「生活費を稼ぐためにとりあえずアルバイトをしよう」と思う人が多いのではないかと考えられます。
また、専門学校を辞めてフリーターになるメリットとデメリットが知りたい方は、以下をご覧ください。
| メリット | デメリット |
| ・プライベートを優先しながら働ける・興味のある仕事を複数経験できる | ・収入が安定しづらい・勤務時間が少ないと社会保険に加入できない |
フリーターは自由な時間がある一方で、収入などが不安定になるリスクがあるでしょう。
他の進路:公務員試験を受ける
専門学校を中退した人でも、公務員試験には「高卒程度」の枠があるためチャレンジできます。安定した働き方や長く安心して働ける環境を望んでいる人は公務員を目指しやすい傾向があるでしょう。
公務員になるメリットとデメリットを以下の表にまとめました。
| メリット | デメリット |
| ・社会的に信頼されやすくなる・雇用や給与が安定している | ・合格までに時間がかかる可能性がある・3~4年で異動が行われる |
公務員の魅力は安定性と社会的信頼の高さです。長期的に働きやすい環境が整っており、将来設計も立てやすいでしょう。
一方で、公務員試験に合格するには数ヶ月から1年以上の勉強が必要になる場合もあります。公務員を目指すなら、計画的な勉強が必要になるでしょう。
他の進路:留学する
専門学校を辞めた後の進路に、留学する道があります。海外の生活や文化に憧れがある人は、留学を選びやすいでしょう。
留学するメリットとデメリットを整理して以下の表にまとめました。
| メリット | デメリット |
| ・語学力アップを目指せる・異文化を体験し視野が広がる | ・留学費用がかかる・現地生活に馴染めない場合がある |
留学や語学力アップや異文化体験ができ、その後の人生に役立つ経験が得られる可能性があります。一方で、金銭面の負担が大きいので、慎重な判断が必要です。
留学したい場合は何を学び帰国後にどう活かすのかを明確にし、金銭面も考えながら検討していきましょう。
専門学校を辞めた後のデメリット4選
専門学校を辞めた後のデメリットは、最終学歴が高卒となり、就職活動で不利になる可能性があることです。中退という経歴はネガティブなイメージを持たれやすい傾向にあるため、就職活動を行う際は十分な対策が必要と言えます。
そのほかにも希望していた専門職に就きにくくなったり、学校で受けられる就職支援を利用できなかったりするデメリットがあります。
このように中退は自由度が広がる一方で、将来のキャリアにおいて制約を受けるリスクもあることを理解しておいてください。
ここで紹介する デメリットを理解したうえで、それを補うにはどうしたらいいか考えてみましょう。
1.元々希望していた専門職を目指すのが難しくなる
専門学校を辞めると、看護師や保育士、美容師などの元々希望していた専門職を目指すのが難しくなります。上記の仕事は専門学校の卒業や国家資格の取得が必須であり、中退するとこれらの受験要件を満たせなくなるからです。
このデメリットを解消するための対処法を、中退後の希望ごとに以下の表にまとめました。
| 希望 | 対処法 |
| 別の仕事につきたい | ・就職活動を行う・やりたい仕事で必要な資格を得る |
| 専門学校を辞めても学んだ知識を活かしたい | ・看護助手など資格なしでもできる同業界の仕事を探す |
| 希望していた専門職がしたい | ・別の専門学校に入学する |
専門学校を中退しても、上記のような工夫をすれば道はあります。紹介した対処法を参考に最適な方法を選んでみてください。
2.最終学歴が高卒になる
専門学校を中退すると、最終学歴が高卒扱いになります。高卒になると応募できる求人の数が少なくなる傾向があります。
東京労働局の調査によると、高卒者(専門学校中退者)と専門学校卒業者の求人数は以下の表のとおりです。
| 学歴 | 求人数 |
| 高卒者(専門学校中退者) | 50,504件 |
| 専門学校卒業者 | 63,787件 |
上記の表から、高卒枠の求人は約5万件あるものの、専門学校卒業者と比較すると約1万3,000件も応募求人の数が少ないとわかります。
ただ、求人の数が少なくても未経験歓迎求人に応募すれば、通過しやすくなります。面接や応募書類で学歴以外の強みをアピールできれば、十分にチャンスはあるでしょう。
3.中退が原因で就職活動が不利になりやすい
専門学校を中退すると、就職活動が不利になりやすいです。企業は中退者に対して以下のような印象をもつからです。
- 就職してもすぐに辞めてしまうのではないか?
- 計画性が足りないのではないか?
- 責任感が足りないのではないか?
企業側は仕事を続けてもらえる人材を探しているので、中退者に対して「すぐ辞めてしまわないか」と心配する傾向にあります。ただし、以下の表のように書類や面接で中退理由をポジティブに伝えることで、上記の印象を変えることが可能です。
| 中退理由 | ポジティブに変換した伝え方 |
| 学費が払えなかった | 経済的に厳しい状況だったが、働いて自立したい気持ちが強まり就職を決意した |
| 授業が合わなかった | 学ぶ中で自分の適性を再確認し、より力を発揮できる分野に挑戦する決断をした |
このように中退理由をポジティブに伝えることで、逃げたのではなく、前向きな姿勢を持っていると受け取ってもらいやすくなるでしょう。
4.専門学校での就職支援が受けられない
専門学校を中退すると、学校の就職支援が受けられなくなります。その結果、就職活動の仕方がわからない状態に陥りやすいでしょう。
対処法として、就職支援サービスを使うのがおすすめです。代表的なサービスとして、ハローワークと就職エージェントの特徴を以下の表にまとめました。
| サービス | 特徴 |
| ハローワーク | ・厚生労働省が運営している・地元企業の求人数が多い |
| 就職エージェント | ・民間の人材紹介サービスである・専任のキャリアアドバイザーに相談できる |
ハローワークは安心して相談できる公的サービスを利用したい人におすすめです。また就職エージェントは専任のキャリアアドバイザーに相談しながら進めたい人に向いています。
専門学校を辞めたい時に親を説得する5つのコツ
専門学校を辞めたい時に親を説得するコツは、辞めた後の行動を明確にして伝えることです。「辞めたい」とだけ伝えると、親は将来を心配して反対しやすくなるからです。
一緒に次の進路を具体的に話せば、ちゃんと考えているんだとわかり、親も安心しやすくなります。
また、落ち着いて話せるタイミングを選んだり、感謝や謝罪の気持ちを伝えたりすることも大切です。これらを実践することで、親の理解を得やすくなります。
ここで紹介する 説得のコツを理解したうえで、自分の考えを冷静に整理し、親に安心してもらえるように伝えてみてください。
1.落ち着いて話せるタイミングを選ぶ
専門学校を辞めたい時に親を説得するコツは、落ち着いて話せるタイミングを選ぶことです。相手が忙しいタイミングやイライラしている時に話を切り出すと場が混乱し、説得が難しくなるからです。
落ち着いて話せるタイミングがわかっているならその時間を狙って話を切り出すといいでしょう。わかっていない場合は、話をしたいと事前に相談するのがおすすめです。
2.なぜ専門学校を辞めたいのかを整理する
親を説得したいときは、なぜ専門学校を辞めたいのかを整理しておくのがコツです。辞めたい理由が曖昧だと反対された時に親を説得できないからです。
すぐ気が変わる・本気ではないと思われて、真剣に話を聞いてもらえない可能性もあります。
専門学校を辞めたい理由を整理する時は「なぜ辞めたいか」だけでなく「辞めない選択肢はないか」という視点でも考えるようにしてみてください。
親を説得する時に「辞めない選択肢も考えた」と伝えると、一時の感情に流されたわけではなく、真剣に考えた話だと認識してもらいやすくなります。
3.専門学校を辞めた後の行動を決める
専門学校を辞めたい時に親を説得するコツは、辞めた後の行動を明確に決めておくことです。親は専門学校を中退した後の進路が決まっていないと不安になるはずです。次の行動が何も決まっていないとわかれば、親が反対するのも無理はないでしょう。
専門学校を辞める前から今後の行動を細かく決めておき、詳細を親に伝えれば安心してもらいやすくなります。
また、労働政策研究・研修機構の調査では、中退前に正社員になろうと思っていた人でも、中退後に心がわりする人もいるとわかりました。具体的な割合は以下のとおりです。
- 正社員として就職したいと思っていた割合 46.6%
- 正社員として就職するための準備をした割合 32.1%
参考:労働政策研究・研修機構「第3章 ハローワークに来所した中途退学者の実態②:中退後の就職活動」
このように、中退前はやる気があっても、中退後の行動が曖昧であれば行動に移せない可能性があります。しっかりと中退後の行動を決めておきましょう。
4.感情的に話さないようにする
専門学校を辞めたいと親を説得する時は、感情的に話さないことがコツです。親に専門学校を辞めると伝えると、反対される可能性が高いです。
その時に、感情的になってしまうと、親も自分も冷静になれず話を前に進められなくなってしまいます。
話すことをメモにまとめて読んだり、手紙にして読んでもらったりすると感情的にならずに気持ちを伝えられます。
また、第三者に親へ話す内容を聞いてもらうのもおすすめです。客観的なアドバイスをもらえば、落ち着いて話せる場合もあるでしょう。
5.感謝と謝罪の気持ちを伝える
最後に、専門学校を辞めたいと親を説得する時は感謝と謝罪の気持ちを伝えることが大切です。
親は専門学校へ行くことを応援しているからこそ、学費を出して通わせてくれています。専門学校を辞めると親の期待を裏切ってしまうことにもつながるため、ショックを受けるのは当然と言えます。
進学させてくれたことへの感謝と謝罪の言葉があれば、真剣に考えたのだと受け止めてもらいやすいでしょう。
専門学校を辞めて後悔しないための3つのポイント
専門学校を辞めて後悔しないためには、辞める前に信頼できる人へ相談することが大切です。
自分一人で考えていると視野が狭くなりがちですが、第三者の意見を取り入れることで冷静な判断ができるようになります。
さらに辞める以外に選択肢がないかを探したり、辞めた後にだらだら過ごさず、次の行動につなげたりする努力も必要でしょう。
ここで紹介するポイントを理解して行動に移せば、辞めてから後悔するのを防ぐことが可能です。専門学校を辞めてから「間違った選択をした」と悩みたくない方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.辞める前は信頼できる人に相談する
専門学校を辞める前は、信頼できる人に相談するのがおすすめです。一人で考えて専門学校を辞めるかどうか判断すると、あとで「別に辞めなくてもよかった」と思うようなことが起こる可能性があるからです。
専門学校の教員やキャリアセンターの職員、信頼できる友人などに相談すれば、自分では気づかなかったような考えを発見しやすいでしょう。
2.専門学校を辞める以外の選択肢がないか探す
専門学校を辞めて後悔しないためには、辞める以外の選択肢がないか探すことがポイントです。
他の選択肢を探し尽くした上で、辞める以外にないとわかれば後悔せずにいられるでしょう。以下のようなケースであれば専門学校を辞めずにすむ場合があります。
- 学費を工面できない→奨学金制度を利用する
- 心身に不調をきたしている→休学して体調を回復させる
- 授業内容が合わない→学科変更や履修を見直す
このように、辞めなくても問題が解決できる場合があります。一度立ち止まって自分が辞めたい理由を整理し、その他の選択肢がないか冷静に考えてみてください。
3.専門学校を辞めた後はだらだらする時間を減らす
専門学校を辞めて後悔しないためには、だらだらする時間を減らすことがポイントです。専門学校を辞めて時間があるからといって休んでばかりいると、当初決めていた予定も後回しになりやすいでしょう。
専門学校ではスケジュールが決まっていますが、何の縛りもない状態だと行動するのがおっくうになる可能性があります。
また、何もしていない期間が長くなると、就職活動を行う際に「何をしていたか」と聞かれやすいです。うまく答えられないと「就業意欲が低い」と思われ、印象が下がりやすくなってしまいます。
だらだらしやすいタイプの方こそ、生活リズムが崩れないよう起きる時間を決めたり「〇日までに10件応募する」など短期的な目標を決めたりするのがおすすめです。
専門学校を辞めることに関するよくある質問3選
ここからは専門学校を辞めることに関するよくある質問を紹介します。疑問点を解消し、辞めるかどうかの判断材料としてぜひご覧ください。
1.「専門学校辞めたい」と親に言えない時は?
「専門学校辞めたい」と親に言えない時は、辞めたい理由を冷静に整理し、親への感謝と共に今後の具体的な計画を伝えることが大切です。
学校を辞めるためには親の同意や印鑑が必要な場合もあるため、内緒で辞めるのは難しいです。あとで専門学校を辞めたと知った親から怒られる可能性もあるので、事前に相談しておいた方が良好な関係を築けるでしょう。
親に辞めたい気持ちを伝えるのは勇気がいることではありますが、誠実かつ正直に気持ちを伝えれば、状況を理解してもらいやすくなります。
2.専門学校を辞めたあとに後悔する時は?
専門学校を辞めたあとに後悔する時は、進路を決めずに辞めた時です。辞めた後、目標もなく時間だけが過ぎていくと、周りの友人と比べて後悔する場合が多いです。
専門学校を辞めたあとに後悔するケースは以下のように他にもあります。
- 専門学校を卒業した仲間との間に差が生まれたと感じた時
- 大学卒業した友人から比較された時
- 就職がうまくいかない時
周りと比較して自分が劣っていると感じたり、辞めた後の生活がうまくいかなかったりすると後悔するケースが多いです。
後悔しないためには、辞めたあとの進路を決めておくこと、周りと比較しないことが大切です。自分がどうしたいのかをしっかり整理しておきましょう。
3.専門学校を辞める人は多い?
専門学校を辞める人は、文部科学省の調査によると約6.05%で、全体からみると多くはありません。(参考:文部科学省「令和6年度 専門学校生の中途退学者・休学者数等の調査結果」)
割合だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、全国で28,450人が専門学校を中退しています。「自分だけが専門学校を辞めた」のではと孤独に感じる必要はありません。
専門学校を辞めたことについてマイナスにとらえるよりも、辞めた後はどのように行動したかで状況を変えられます。
まとめ
専門学校を辞めてよかったと思えるのは、やりたかった仕事に挑戦できたり、学校生活のストレスから解放されたりするなど、自分に合った環境を見つけられた時です。
専門学校を中退する人は多くはありませんが、一定数の人が別の進路を選択しています。最終学歴が高卒になったり、中退が原因で就職活動が不利になったりすることもありますが、前向きに行動している人もいるので悲観的になる必要はありません。
大切なのは、専門学校を中退した後の時間をどう使い、どんな進路を選ぶかです。選んだ道を正解にすることこそが、新しい可能性を開いてくれるでしょう。